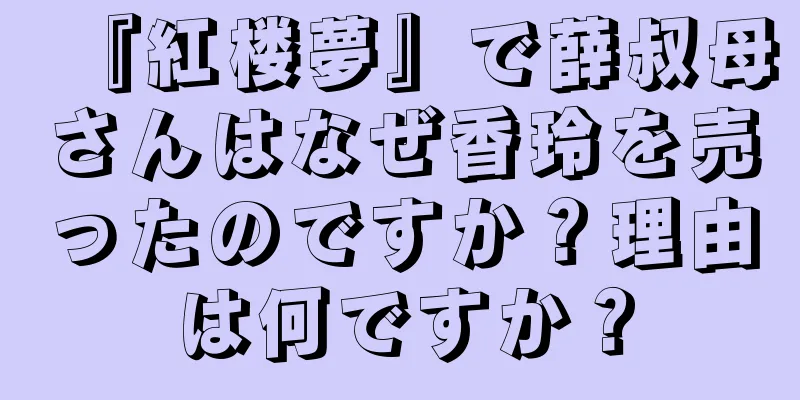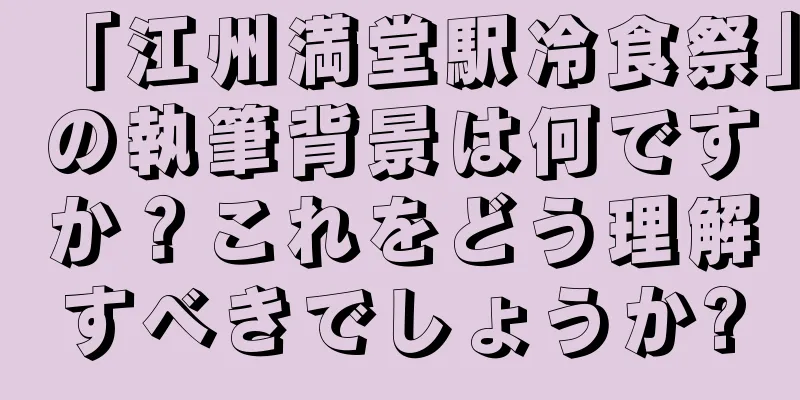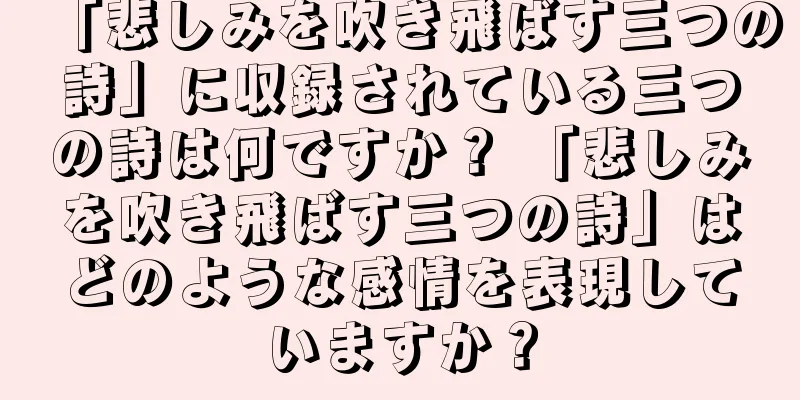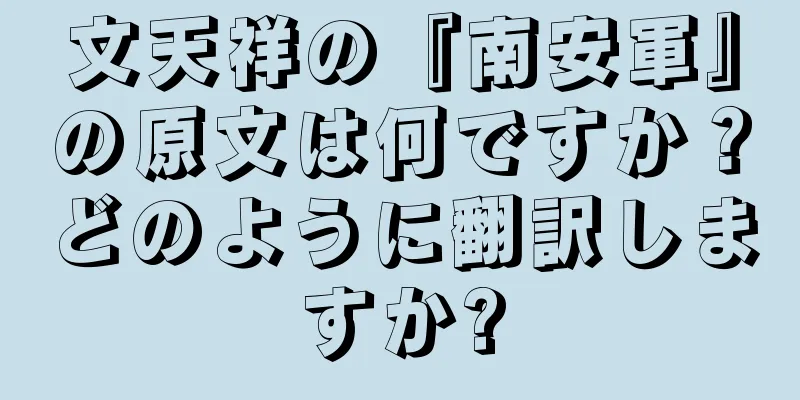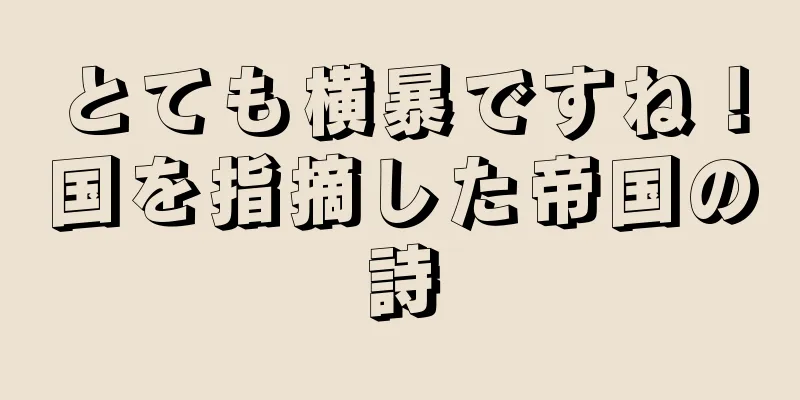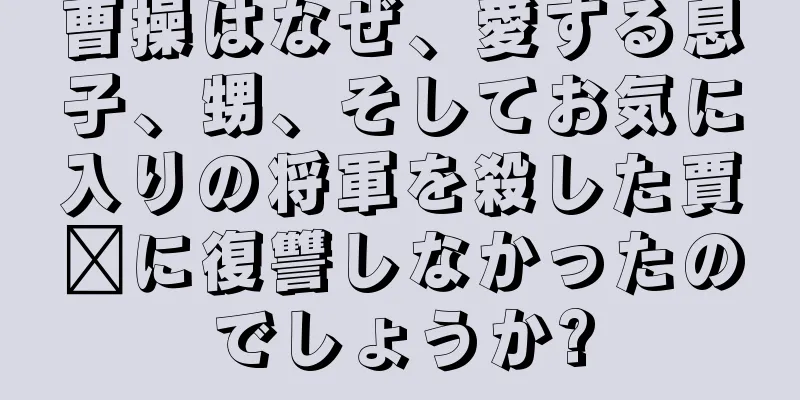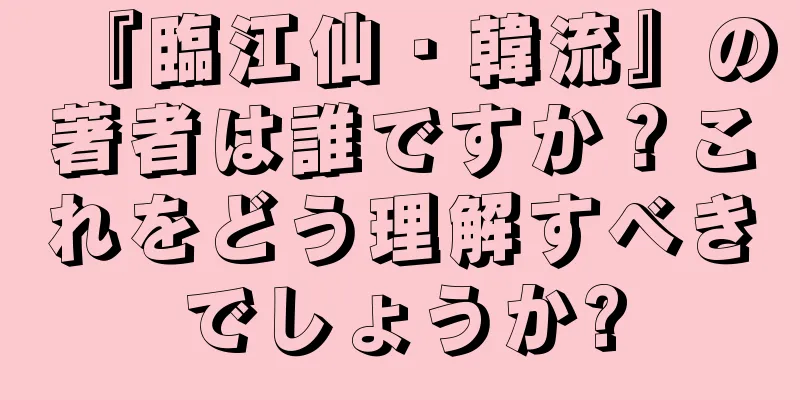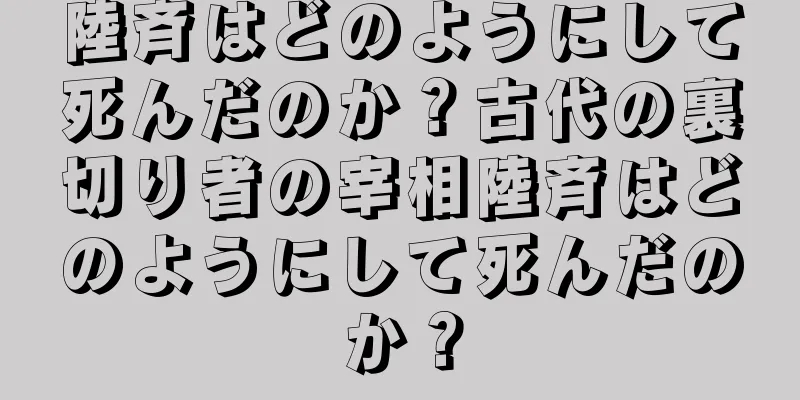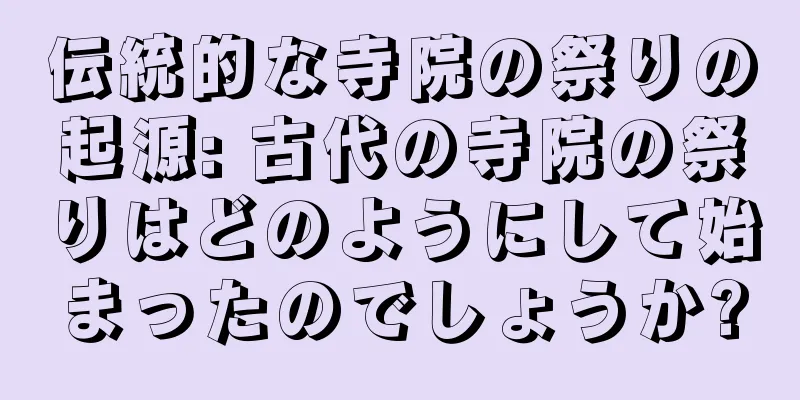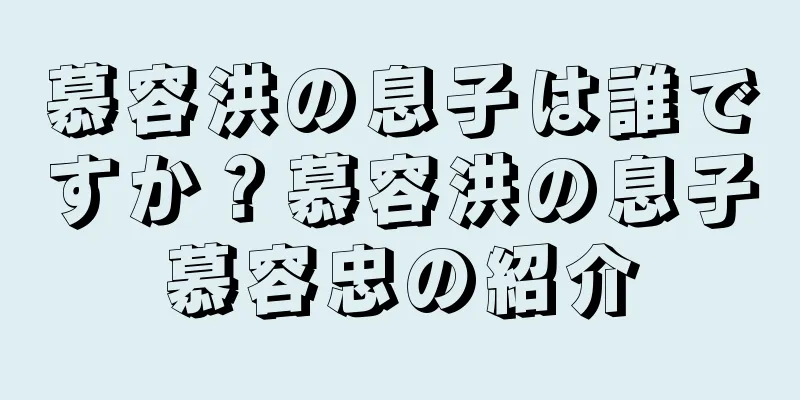明治維新と百日天下の改革の10大相違点を読み解く
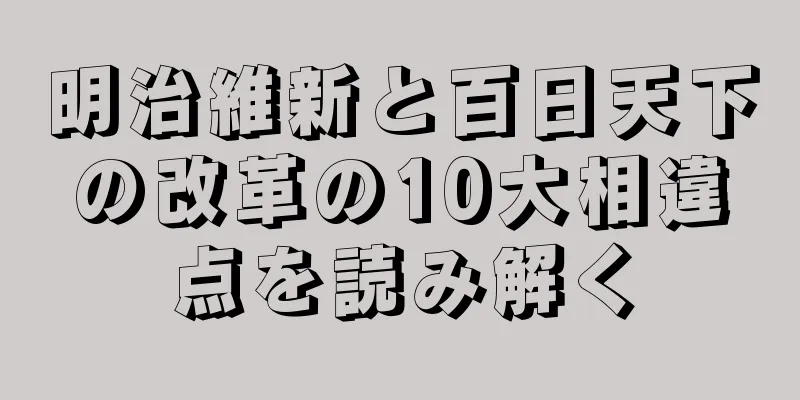
|
1868 年の明治維新により、封建的で後進的で分裂していた日本は、急速に文明的で科学的な、発展した統一された日本へと変貌しました。1898 年の百日天下の改革は、中国の悪化する状況を効果的に逆転させることに失敗しただけでなく、改革者自身の命さえも危険にさらしました。なぜ日本の明治維新は成功体験に学ぶべきものがないのに成功したのか? なぜ中国の百日天下は日本の明治維新という成功体験に学ぶべきものがあったのに失敗したのか? 長い間、教科書の答えはこうだった。1898年の改革運動の失敗は「主観的には、中国のブルジョアジーが十分に発達しておらず、弱く、妥協的だった。客観的には、中国の封建的反動勢力が強すぎて、改革を深刻に妨げた」というものだった。一部の専門家は、ソ連の急進的改革がソ連の崩壊を招いたのと同じように、1898年の改革運動の失敗の主な原因は急進的改革によるものだという新たな見解も提示している。同時に、明治維新の成功は西洋列強の日本への支援によるものであり、百日天下の改革の失敗は西洋列強の中国に対する反対によるものと考えられています。私個人としては、上記の見解はすべて間違っていると思います。これらの誤った見解が形成され、広まったのは、思想的要因に加えて、明治維新の真実に対する十分な理解が欠如していることが主な原因であると思います。中国で日本の明治維新を紹介する資料のほとんどには、明治維新の成功に絶対的な役割を果たした中心人物である坂本龍馬の名前がないことに気がつきました。このことから、ほとんどの中国人が明治維新についていかに理解が乏しいかがわかります。 最近、日本で最も有名な歴史小説家、司馬遼太郎が書いた全8巻のオリジナル歴史小説『龍馬の足跡』(日本語タイトルは『龍馬が玉』)を読みました。そこから、ほとんどの中国人にとってまだあまり馴染みのない明治維新に関する多くの歴史的情報を学びました。そして、それを1898年の維新運動に関する歴史的情報と比較し、明治維新の成功と1898年の維新運動の失敗の10の理由、あるいは10の違いをまとめました。これに興味がある皆さんとこれについて議論したいと思います。 まず、改革の条件は国によって異なる 1185年から徳川幕府の統治を経て1868年の明治維新まで、日本の実際の統治はさまざまな将軍によって行われ、天皇は名目上の統治者に過ぎませんでした。明治維新以前、日本には大小さまざまな約300の武将が存在し、その中で最大のものは徳川幕府でした。徳川幕府は、天皇から将軍の称号を授けられた将軍を正式な地位として利用し、天皇を利用して他の属国を統制しました。したがって、明治維新の第一段階は、この軍閥分離主義の状態を終わらせ、日本全国に統一された中央集権的な政府を確立することでした。 紀元前221年に秦の始皇帝が全国に統一的な中央集権体制を確立してから、1898年の百日天下改革前の清朝まで、短い分裂期間を除いて、国はほとんどの期間統一されていました。しかし、1898年の改革運動の第一段階は、中央集権体制を内部から分裂させることであり、もともと統一されていた国家統治集団を「天皇党」と「天皇派」という2大政治集団に分裂させ、最終的には武力クーデターで相互排除するまでに発展した。 分裂から統一への移行は正義の期待と歴史の流れに沿ったものであるが、統一から分裂への移行は失敗する運命にある。 第二に、改革前の準備は異なっていた 幕末には、下級武士や地方領主を中心に天皇の実質的な統治権の回復を主眼とした尊皇攘夷運動が数十年にわたって盛り上がり、思想や軍事面だけでなく人材や経済力の面でも明治維新に向けた万全の準備が整った。 1898年の改革運動はゴンチェの皇帝への嘆願から始まった。 1895年4月、日本が下関条約の締結を強行したとの知らせが北京に伝わり、康有為は北京で科挙を受ける1,300名以上の受験生を動員し、光緒帝に宛てた手紙を共同で書き送らせ、1898年の改革運動の始まりとなった。 1898年6月、光緒帝は「国事清澄の勅」を発布し、改革を宣言した。全部で3年しかなく、全国各地で強学協会を組織し、改革を宣伝するための新聞をいくつか発行した以外、軍事的、経済的準備も、思想的、人材的準備も行われなかった。特に改革の推進役である康有為は、改革に対する成熟した考えや能力を持っておらず、その場の勢いに任せて憤慨し、皇帝に改革を進言する手紙を突然書いただけであり、改革の進め方については全く準備が出来ていなかったと言える。 改革の準備が十分に整えば整うほど、成功する可能性は高くなります。一方、必要な準備が欠けている改革は必ず失敗します。 3. 改革のリーダーは異なる 明治維新の指導者たちは、一人や二人ではなく、幕末の数十年間続いた血と火の革命で鍛えられ成長した多数の人々でした。その中には、職業革命家、職業軍人、諸大名の官僚、国際貿易に従事した実業家などが含まれていました。例えば、坂本龍馬は侍として生まれました。彼は、幕府を倒そうとする多くの侍が虐殺され、地方領主の反乱が鎮圧されるのを目撃しました。彼自身も絶えず追い詰められ、盲目的な暗殺だけでは幕府を倒すことはできないと悟りました。彼は海運の知識と西洋の社会、政治、経済問題を長期にわたって研究し、徐々にプロの革命家へと成長していった。彼は国際貿易を行う「開元会」を設立した。幕府を倒すための海軍の人材を育成しただけでなく、幕府を倒すための資金を蓄え、幕府に反対する諸侯が密かに海外から大量の先進兵器を購入するのを助けた。さらに重要なのは、さまざまな諸侯が「開元会」に投資できるようにすることで、もともとさまざまな陣営に分かれていた現地の諸侯を団結させたことである。 1898年の改革運動の指導者たちは、脆弱で無能な皇帝と、政治経験のない熱心な数人の知識人だけでした。彼らは十分な準備も実現可能な改革計画もなく、国家運営の基本的な常識さえ理解していませんでした。 成熟した指導者のいない暴徒集団が、何億人もの人々の運命を左右する大国の改革に成功することは不可能だ。 第四に、異なる改革戦略 幕府を倒すには常に二つの方法がありました。一つは違法な武力攻撃や暗殺を行うことであり、もう一つは合法的な武力攻撃を行うことです。いわゆる合法的な聖戦には天皇の許可が必要であるが、天皇は常に徳川幕府の監視下にあり、公的に聖戦命令を出すことは不可能であった。当時の日本の天皇は曹操に支配されていた漢の献帝のような存在でした。そのため、幕府を倒す革命は常に違法であり、何度も血なまぐさい失敗に終わってきた。坂本龍馬はこれらの教訓を吸収して「王政復古」の戦略を提唱した。つまり、武力による血なまぐさい闘争によって徳川幕府の統治を打倒するのではなく、徳川幕府が自発的に統治権を天皇に譲り渡し、日本全体の新しい真の統一政府が結成され、徳川幕府も他の君主と同様に新しい政府の運営に平等に参加するというものでした。 こうして、天下統一の目標は達成され、徳川幕府は滅亡の運命を免れた。まさにウィンウィンの結果であった。諸大名たちは徳川幕府に統治権を明け渡すよう強制するため、軍備を強化し、武力で和平を強要した。坂本龍馬が提唱した「王政復古」の方針は、諸侯の賛同を得て、彼の調整のもとにロビー活動が進められ、ついに1867年、徳川幕府最後の将軍・徳川慶喜が天皇に自主退位させられ、「王政復古」は理論から現実のものとなった。 基本的に、1898年の改革運動には戦略がありませんでした。その代わりに、当初からまだ権力を握っていた「侯党」と権力争いをしました。最後には、「侯党」の兵士に賄賂を渡してクーデターを起こし、「侯党」を飲み込もうとさえしました。本当に愚かでした! 正しい戦略があれば、改革は必ず成功します。正しく実行可能な戦略がなければ、改革が失敗に終わらなくても、回り道をしたり、道を誤ってしまうことがよくあります。 5. さまざまな改革案 明治維新は、「大政奉還」という素晴らしい戦略だけではなく、具体的で実現可能かつ簡潔な計画を持っていました。それが坂本龍馬が提唱した「船中八策」です。その内容は以下のとおりです。 1. 天下の政治権力は朝廷に返還され、すべての政令は朝廷から発せられるべきである。 2. 朝廷は上院と下院を設け、議員を任命して国政を討議し決定しなければならない。国政を決定する基礎は正義でなければならない。 3. 全国から有能な大臣、君主、庶民を召集し、顧問として雇い、相応の官位を与え、官位はあるが能力のない朝廷の役人を解任する。 4. 新たな条約を締結する前に、外交は広範な国民的議論に基づいて行われなければならない。 5. 元の古い法律に基づいて新しい法律を制定する。 6. 海軍は積極的に拡大されなければならない。 7. 天皇と日本に属する新しい軍隊を設立する必要があります。 8. 法律に従い、海外の他の国々と対等に金、銀、その他の物品を取引する。 1868年に明治天皇が発布した「船中八策」から「五箇条の御誓文」に至るまで、主要な内容は基本的に同じであり、数十年間一貫しています。 1898年の改革運動には、明確で大きな改革計画が欠けていた。わずか103日間で、180以上の新しい政策に関する勅令が出された。それらは、重要なことと緊急なことの区別がつかなかっただけでなく、地方の役人を困惑させ、疲弊させた。 具体的かつ実行可能な改革計画の実施と継続が、改革の成功を確実にする鍵となります。 6. 改革の焦点は異なる 明治維新の主な課題は、近代的な民主主義制度による審議制度の確立、近代的な国防の確立、西洋の技術を導入するための開国、近代教育の開始など、それまで存在しなかったものを確立することに重点を置き、無から有を生み出すことでした。そうすると抵抗が少なくなります。 1898 年の改革運動は、古いものから新しいものへというものでした。その焦点は、まず元のものを否定し、次に新しいものを作り出すことであり、それが大きな抵抗を生み出しました。 いかなる社会改革も抵抗に遭遇する。鍵となるのは、いかにして状況を利用し、改革の突破口となる重要な分野に焦点を絞り、特定の分野での突破口を通じて全体の状況に変化をもたらすかである。 7. 改革によってさまざまな人々が恩恵を受ける 明治維新の恩恵を受けたのは全員日本国民であった。司馬遼太郎が著書に書いたように、明治維新以前の日本人には「日本」という概念はなく、封建領主と天皇という概念しかありませんでした。明治維新後、国民の階級制度は崩れ、国民皆平等の「日本」と「日本人」という概念が生まれました。 「五箇条の御誓文」の教育に関する内容についてですが、当時の日本は近代的な義務教育を開始し、全国を8つの大学区に分け、各大学に1つの大学、32の中学区に1つの中学校、各中学区に210の小学校区、各小学校区に8つの小学校を設置しました。全国に合計8つの公立大学、245の中学校、53,760の小学校があります。 これに対し、1898年の維新運動では科挙制度の廃止が提唱されたものの、義務教育は全国的に一斉に実施されず、中国のような大国に北京帝国大学が一つだけ設立されただけであった。残念なことに、中国では今日に至るまで、すべての人に対する無償の義務教育が完全に実現されていません。 1898 年の改革運動の恩恵を受けたのはごく少数だったが、それは大多数の人々の既得権益を剥奪するという前提に基づいていた。一般市民の大多数にとって、基本的に言うほどの利益はなかった。 大多数の国民に利益をもたらさない改革は、大多数の国民に支持されず、長続きせず、成功もしないであろう。 8. 改革に対する人々の態度は異なる 明治維新は、徳川幕府のごく一部の既得権益層の反対を除けば、国民の大多数から支持され、承認されました。特に、徳川幕府の頑迷な勢力の反乱が終結した後は、国民のほぼ全員の支持を得ました。このような改革により、国は急速に強くなり、国民も急速に豊かになり、まさに富民強国を実現しました。 1898年の改革運動は、多数の新政策を公布したものの実施が間に合わず、学者が政治を議論するための新聞や雑誌を多数創刊した以外、国民に実質的な利益をもたらさなかったため、改革は基本的に国民に認められなかった。 国民の大多数の承認を得られない改革は成功しない。 9. 外国軍に対する異なる態度 明治維新以前、日本は西洋列強による侵略と屈辱に苦しみ、国にとって屈辱的で不利益な不平等条約に署名することを余儀なくされました。西洋諸国も日本の軍事闘争に介入した。例えば、当時フランスは徳川幕府を支援していましたが、長州藩はイギリスから支援を受けていました。坂本龍馬のような洞察力のある人々は、外国勢力の日本への介入を見て、地方の大名たちが外国政府の支援を受けて幕府を倒す戦争を開始すれば、日本人同士が大規模な虐殺を行うだけでなく、虐殺の後、日本の大名たちは西洋列強からさらに厳しく統制され、日本はより分裂状態に陥るだろうと懸念しました。したがって、外国勢力の介入を避けるためには、平和的な手段で徳川幕府に「政権の返還」を強いることが最善の方法です。この歴史的事実は、明治維新が西洋列強の支援によってのみ成功したとする国内の一部学者の見解とは全く逆である。 1898 年の改革運動は、最終的に「侯党」による虐殺を引き起こしました。これには 2 つの主な理由がありました。1 つ目は、光緒帝が袁世凱を味方につけ、軍事力を使ってクーデターを起こそうとしたことです。2 つ目は、光緒帝が 8 月 5 日に元日本首相の伊藤博文を召喚し、新しい政策の顧問として雇う計画を立てたことです。この二つの出来事は西太后のグループに大きな疑念を抱かせた。彼らは皇帝派が軍隊を掌握することを恐れ、改革派が外国勢力と手を組み、帝国主義が光緒帝を支援して西太后から権力を奪取することを最も懸念した。そこで西太后は光緒帝が伊藤帝に会う前にクーデターを起こすことを決意した。 このことから、外国勢力からの援助を真に得ようとしたのは、明治維新ではなく、百日天下の改革であったことが分かる。明治維新が成功したのは、西洋列強の介入を排除したからである。残念なことに、百日改革から今日まで100年以上が経過した現在でも、中国のさまざまな政治グループが自らの利益を維持し、競争するために外国勢力の介入に頼るという悲劇は終わっていません。 外国勢力の介入に頼った改革は成功する可能性は低い。たとえ一時的な勝利を収めたとしても、それを持続させることは難しく、後遺症がいつまでも残ることになるだろう。 10. 改革の期間はさまざま 明治維新がどのくらい続いたかについては、統一された見解はないようです。日本の明治維新は20年続いたとする記事もあれば、西洋の資本主義国が200年かけて完成させた産業化の過程を明治維新が完成させるのに50年かかったとする記事もあります。外交の観点から、外国から押し付けられた不平等条約を完全に廃止することが、その国が本当に強いかどうかの証しとみなせるならば、日本は1854年に米国との最初の不平等条約の締結を余儀なくされ、1868年に明治維新を迎え、その後も継続的な改革を経て、1911年に欧米列強から押し付けられた不平等条約をすべて廃止した。1868年から1911年まで43年かかったことになる。 1898 年の改革運動は改革前には極めて短期間しか続かなかっただけでなく、改革後もわずか 103 日間しか続かなかった。 1898 年の改革運動は明らかに「持続不可能」であったため、失敗に終わった。このことから、1898 年の改革運動の実際の価値は中国人によって誇張されていたことがわかります。その真の価値は、その象徴的な意義が実際的な意義よりも大きいということだけを私は言えます。 まとめると、明治維新の成功と百日天下の改革の失敗は偶然ではなく必然だった。これら二つの社会変化が歴史となった今日、私たちはその長所と短所を分析し比較しますが、それは誰かを賞賛したり批判したりするためではなく、今日の私たちの改革の参考となるためです。私個人としては、中国において日本の明治維新に真に匹敵する改革は、百日改革ではなく、1978年に始まった鄧小平の改革開放であると考えています。日本の明治維新は、西洋資本主義国が200年かけて完成させた工業化の過程を50年かけて完成させた。では、中国の現在の改革開放は、西洋資本主義国が200年かけて完成させた工業化の過程を何年かけて完成させるのだろうか。これが注目すべき重要な点である。 中国の人口と国土面積はともに日本の10倍以上です。ですから、中国の改革開放が日本の明治維新の2倍のスピードで明治維新の課題を成し遂げることができれば、それは誇るべきことだと思います。今日の中国を見てみると、経済、交通、国防、都市建設、科学技術などの面で日本の明治維新が成し遂げた課題をはるかに上回っています。しかし、政治体制の改革と国民の福祉の面では、日本の明治維新が成し遂げた課題の達成にはまだまだ程遠いです。特に、国民の社会福祉保障の向上という明治維新の課題を日本が未だに達成していないことは、非常に残念で恥ずべきことだと思います。私たちも警戒すべきです。いかなる歴史の時代であっても、国民の社会福祉が根本的に保障されなければ、いかなる改革も大きな危機に直面することになります。したがって、私個人としては、今日の中国の改革の第一の課題は、中国国民が直面している「就学困難、医療困難、就職困難」という3つの大きな問題をできるだけ早く解消することだと考えています。 注: 司馬遼太郎の本名は福田貞一であり、その雅号は「司馬遷の太郎よりはるかに劣る」という意味から取られた。彼は日本と中国に関する歴史小説を数多く執筆しており、彼の最高傑作は日本の明治時代を扱った歴史小説である。 「日本の歴史上、坂本龍馬は最も魅力的な人物だ」と司馬氏は信じている。司馬遼太郎氏は生涯を通じて数え切れないほどの作品を生み出し、1960年(37歳)以降、ほぼ毎年賞を受賞してきた。1993年(70歳)には日本人最高の栄誉である文化勲章を受章し、1996年に亡くなった。 |
<<: 1898 年の改革運動の意義と影響は何ですか? 1898年の改革運動を正しく評価する方法
>>: 明治維新が成功し、百日天下の改革が失敗した本当の理由は何でしょうか?
推薦する
諸葛亮はなぜ馬蘇の処刑を主張したのでしょうか?そして彼は本当に斬首されたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝で趙蓋が死後宋江に見た夢の内容は何でしたか?
水滸伝に詳しい人なら、趙蓋が史文公の手で殺されたことはご存じでしょう。Interesting His...
白族の松明祭りと白姫の伝説とは?
白族の松明祭りは「松明塔を焼く」という伝説に由来しています。伝説によると、唐の時代に、大理の六趙の一...
董卓は呂布と父子になることを誓った。呂布が董卓を殺そうとした理由は何でしょうか?
董卓は呂布と「父と子」になることを誓った。呂布が董卓を殺そうとした理由は何だったのか?『Intere...
袁浩文の「未開花のベゴニアと子供たちの詩」鑑賞
同じ世代の子供たちは、未開封のサンザシについて詩を書いた。王朝:晋 著者:袁浩文オリジナル:枝には新...
『江南の夢 蘭灰散る』の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
江南の夢:青い灰の落下皇甫宋(唐代)蘭の灰が落ちて、画面には濃い赤色のバナナの葉だけが残っています。...
「十一月十九日梅摘み」は南宋時代の楊万里が書いたもので、彼の内なる愛情を表現しています。
楊万里は、字を廷秀、号を成斎といい、南宋時代の詩人、作家である。陸游、幽當、樊成大とともに「南宋四大...
『紅楼夢』で王夫人が初めて賈邸に入ったとき、林黛玉をどのように試しましたか?
林黛玉が賈邸に入ったことは多くの人が聞いたことがあると思いますし、彼女もそれをよく知っています。本日...
詩「白髪の少女の歌」をどう鑑賞するか?この詩の作者は誰ですか?
白頭隠【漢代】卓文君、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!山の上の雪のよう...
「卜算子·凉挂晓云轻」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ブ・スアンジ・リャン・グア・シャオ・ユン・チン呉文英(宋代)涼しい朝の雲は軽く、西風の音は穏やかです...
明代の有名な宦官であり摂政であった馮宝は、なぜこのような悲劇的な結末を迎えたのでしょうか?
明代の宦官といえば、九千歳の魏忠賢、大嘘つきの王震、皇帝の劉瑾など、多くの人が名前を口にできるのでは...
孟浩然の詩「北京から帰った張維(または王維)に贈る」の本来の意味を理解する
古代詩「北京から帰国した張維(または王維)に贈ったもの」時代: 唐代著者: 孟浩然南の山でぐっすり眠...
曹植の『良夫行』:詩全体は肯定的な描写と間接的な対比の技法を用いている
曹植は三国時代の著名な文人であり、建安文学の代表者および巨匠の一人として、晋や南北朝時代の文芸の模範...
双鳳伝説第48章:芙蓉嶺の王龍と新詩:太行山脈の地、巨大な昆虫を追う
清代の小説『双鳳凰伝』は、夢によって元帝の側室に選ばれた王昭君が、毛延寿の憎しみと嫉妬によって冷たい...
「金木犀の歌」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
聖聖曼:キンモクセイへの頌歌呉文英(宋代)青い雲が朝を覆い、ヒスイの木が秋に垂れ下がり、金色のブレス...