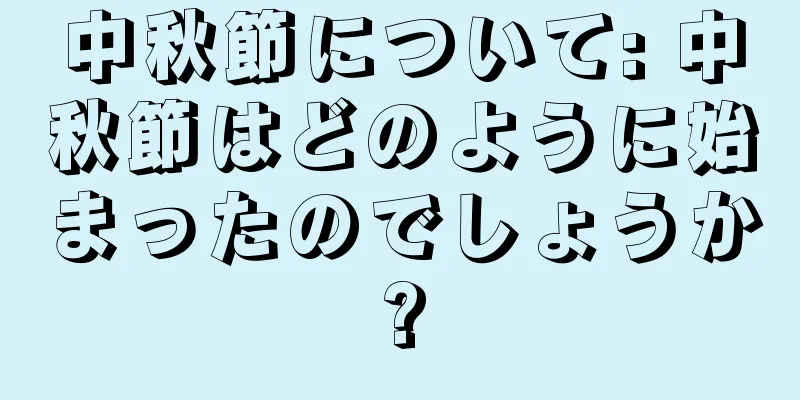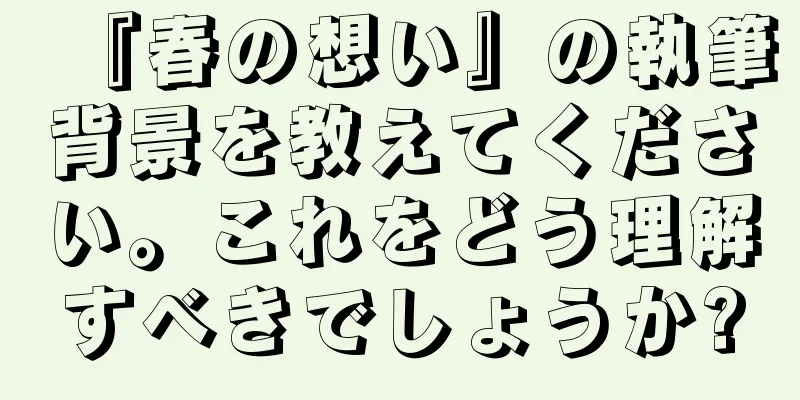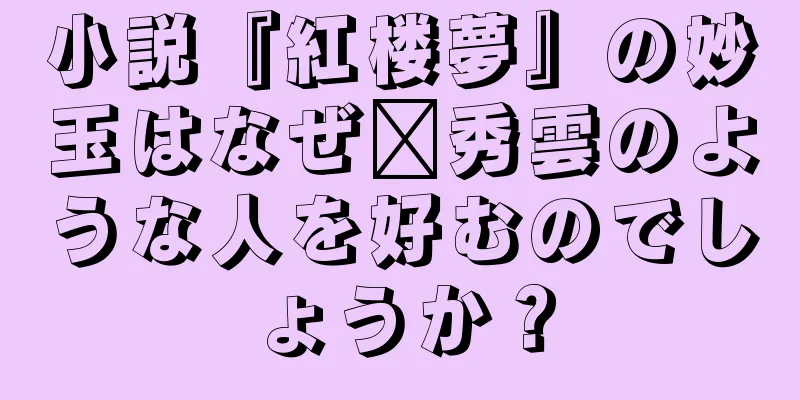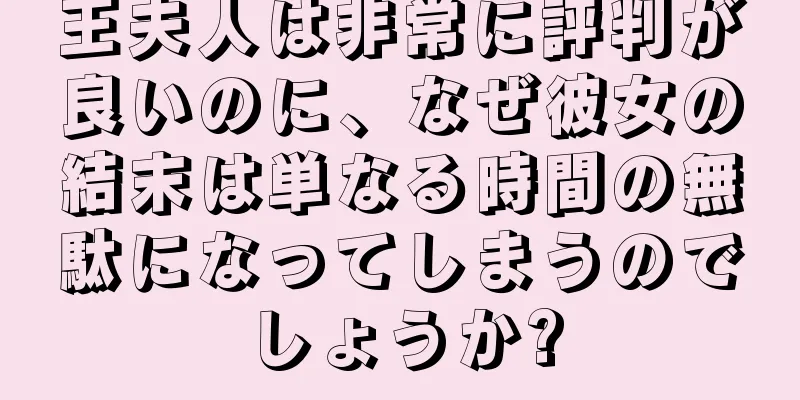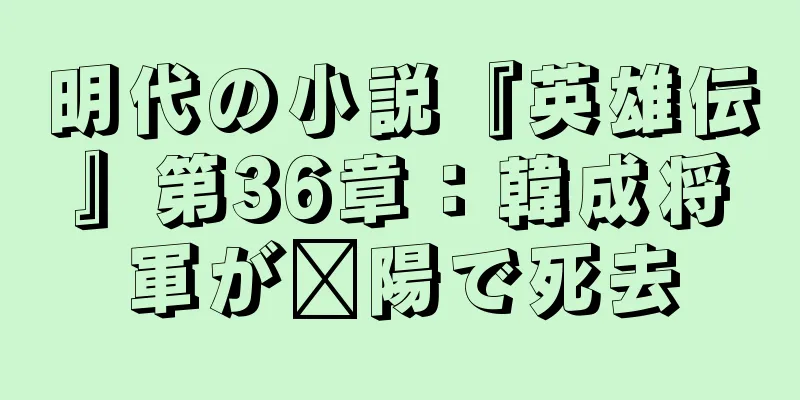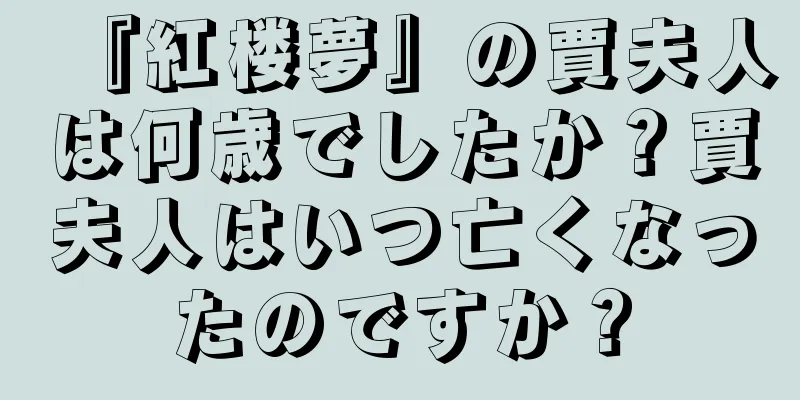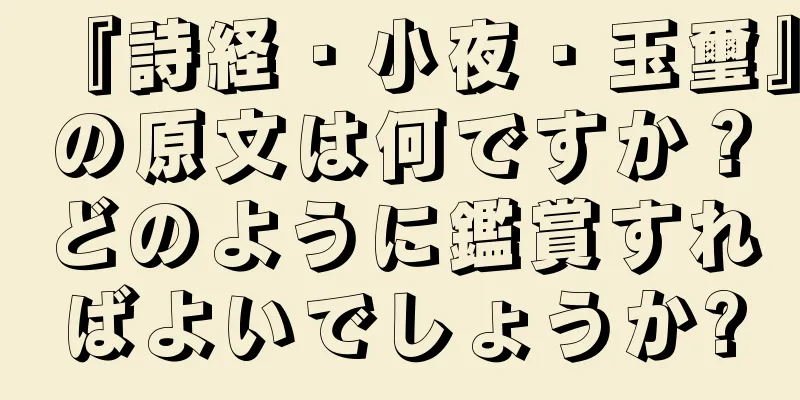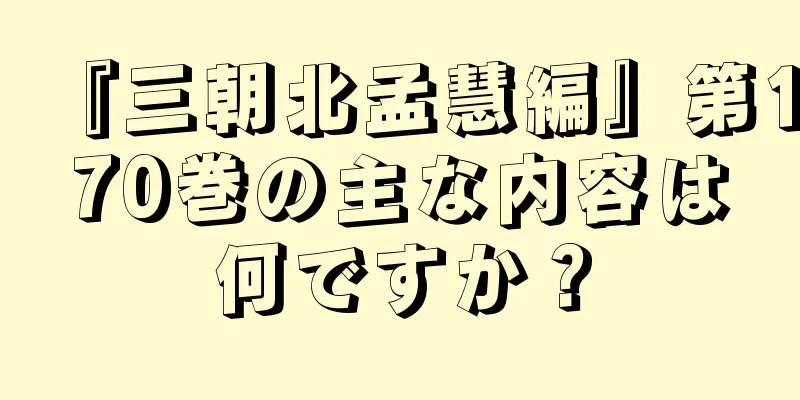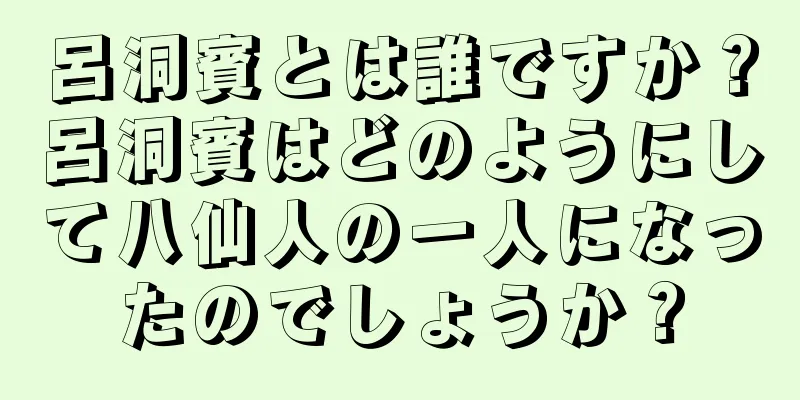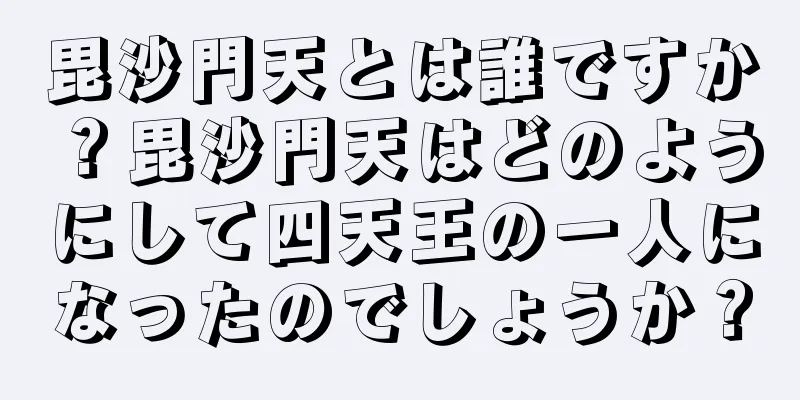日本の明治維新の時代背景は何でしたか?明治維新入門
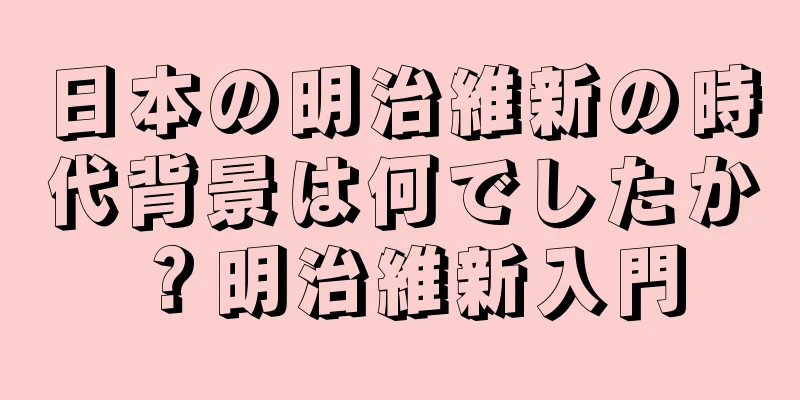
|
明治維新とは、1860年代に日本が西洋資本主義産業文明の影響を背景に、トップダウン型、資本主義型の包括的な西洋化・近代化改革運動を行ったことを指します。 この改革は1868年に明治天皇が新政府を樹立したときに始まりました。日本政府は近代的な政治改革を実行し、立憲君主制を確立しました。経済面では「工業と商業」を奨励し、欧米の技術を学び、産業化の波を起こし、「文明開化」を唱え、社会生活の欧米化を主張し、教育を盛んに発展させた。この改革により、日本はアジアで初めて工業化の道を歩み、世界の列強の仲間入りを果たしました。これは日本の近代化の始まりを示しました。 背景 海外:経済:第一次産業革命が完了し、資本主義の世界市場が初めて形成されました。 (1840年) 政治:資本主義システムの改善と発展。 イデオロギーと文化: 自由資本主義の活発な発展とマルクス主義の誕生と発展。 国際労働運動の継続的な発展。 西洋列強は植民地拡大のペースを加速させ、植民地や半植民地における民族解放運動の発展を促した(例:1851年から1864年までの太平天国の乱など)。 国内においては、幕府の専制政治(幕藩体制、身分制度)、鎖国政策、農業重視と商業抑圧が日本における資本主義の発展を妨げ、幕府体制は危機をはらんでいた。 農民の抵抗闘争は続く(主導:下級武士) 1853年、ペリーの来航により日本の鎖国政策は終わり、日本は半植民地危機に陥った。 討幕運動の展開と勝利(明治天皇の支援による)。 明治維新の内容 天皇を首班とする新政府は、1868年4月6日に政治綱領である五箇条の御誓文を発布し、6月11日に憲法書を公布した。 9月3日、天皇は江戸を東京と改めるという勅令を発布した。 10月23日、元号が明治に改められました。 1869年5月9日に首都が東京に移されました。一連の改革措置が公布された。 1869年6月、明治政府は「版籍奉還」「廃藩置県」の政策を強行し、日本を3府72郡に分割し、天皇が無制限の権力を持つ中央集権的な政治体制を確立した。 社会制度面では、従来の「士農工商」という身分制度を廃止し、公卿や公子などの旧貴族を「公家」、大名以下の武士を「武家」、その他の農工商従事者や不可触民を総じて「平民」と呼称し、「版籍奉還」による財政負担を軽減するため、公債補填により貴族や武士の封建給与を徐々に回収し、さらに武士に対する「廃刀令」や戸籍制度の基礎となる「戸籍法」を公布した。 社会文化の面では、西洋の社会文化や習慣を学び、西洋の作品を翻訳することを推奨しています。太陰暦は廃止され、太陽暦に置き換えられました(在位称号を除く)。 西洋近代工業技術を導入し、土地制度を改革し、従来の土地政策を廃止して土地取引を許可し、新しい地租政策を実施し、諸藩が設置した関所を廃止し、通貨を統一し、1882年に日本銀行(国の中央銀行)を設立し、工商界のギルド制度と独占組織を廃止し、工業と商業の発展を促進しました(工業と商業の発展)。 教育面では近代ブルジョア義務教育が整備され、日本全国が8つの大学区に分かれて各大学が1校、中学校区が32区に分かれて各中学校が1校、中学校区ごとに小学校区が210、小学校区ごとに小学校が1校設置され、合計で全国に公立大学が8校、中学校が245校、小学校が53,760校あった。教育機関は「考試教育勅語」を公布し、道教、皇帝への忠誠、愛国心などの思想を植え付けた(この動きは、最高権力を集中させた社会システムを強化し、将来の対外拡大への道を開くことを意図していたと考える者もいる)。さらに、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツなどの先進国への留学も選抜しています。 軍事面では、陸軍の組織が改革され、陸軍の訓練はドイツを、海軍はイギリス海軍の組織を基準とした。1872年には、20歳以上の成人男子全員に兵役を義務付ける徴兵令が発布された。一般兵役は3年、予備兵役は2年。その後、一般兵役と予備兵役はそれぞれ3年と9年に延長され、合計12年となった。 1873年までに、動員された戦闘部隊の数は40万人に達した。また、明治政府は国営の軍需産業も育成し、明治中期から後期にかけて軍事費は飛躍的に増加し、政府資金の約30%から45%を占め、軍国主義と武士道精神を実践しました。 交通面では、各地の交通の整備や新たな鉄道や高速道路の建設を進めていきます。 1872年に、東京(新橋)から横浜(桜木町)までの初の鉄道が開通し、1914年までに日本の鉄道総距離は7,000キロメートルを超えました。 司法制度に関しては、西洋の制度を模倣し、1882年に立法刑法典、1898年に立法民法典とドイツ民法典、1899年にアメリカの商法典を制定した。 宗教に関しては、政府は政治的な理由から、天皇への忠誠の思想を促進し、それが天皇の国政運営に役立つことから、神道を強く奨励しています。同時に、他の宗教の存在も認められました。1873年、日本はキリスト教の布教活動の禁止を解除しました。 結果 明治維新後、日本は20年以上の発展を経てますます強大になり、幕藩体制時代に西洋諸国と結んだ一連の不平等条約を廃止し、国家主権を取り戻し、ついに近代化へと突入しました。明治維新は日本の歴史における転換点であったと言えるでしょう。それ以来、日本は自立した発展の道を歩み始め、アジア、さらには世界でも有数の大国へと急速に成長しました。 日本は強国への道、そして拡大への道を歩み始めました。 |
<<: カトリック、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の関係と相違点
>>: 日本の明治維新の意義と影響は何でしょうか?明治維新を客観的に評価するにはどうすればよいでしょうか?
推薦する
水滸伝で宋江が陸智深を叱ったのはなぜですか?なぜ武松は敵対しなかったのか?
『水滸伝』では、宋江の涼山における威信が認められている。 Interesting History の...
杜甫は放浪と苦難の人生を送ったが、幸せな詩も書いた。
長い歴史の流れの中で、杜甫は非常に有名であると言えますが、彼の物語をご存知ですか?次に、Intere...
嘉慶帝はなぜ即位後に和申を殺害したのですか?神聖な王位に脅威を与えたからです。
現在、嘉慶が和神を排除したことについて人々が話すとき、彼らはいつも和神がどれだけの金を横領したかにつ...
趙崇志の『辞』:「臨江仙・西池の酒を思い出す」の鑑賞
以下に、興史編集長が趙崇志の『臨江仙・西池飲想記』の原文と評価をお届けします。ご興味のある読者と興史...
シェイクスピアの『リア王』のテーマは何ですか?リア王のテーマの簡単な分析
『リア王』はシェイクスピアによって書かれた戯曲であり、彼の四大悲劇の一つです。この物語は、8 世紀頃...
李白の有名な詩句を鑑賞する:婺源の秋草は青く、胡馬は傲慢だ
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
劉宗元の「衰退からの覚醒」:これは作者の詩集の中では珍しい「速詩」です。
劉宗元(773年 - 819年11月28日)は、字を子侯といい、河東(現在の山西省運城市永済)出身の...
『太平広記』第283巻の「呉」の原文は何ですか?
魔法使い シュウリ 魔女 秦世陽 リン ライ・ジュンチェン 唐の武后 阿来容 文志 鵬俊青 何坡 ラ...
『続・英雄物語』が制作された背景は何でしょうか?主人公は誰ですか?
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
「彭公事件」第97話:英雄の一団が花春園を探索し、捕らわれた人物を救出する
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『紅楼夢』では薛宝琴というキャラクターをどのように描いていますか?彼女はなんて完璧なんだ
薛宝琴は『紅楼夢』の登場人物で、四大家の一つ薛家の娘です。今日は、Interesting Histo...
『紅楼夢』で王希峰が病気になったとき、なぜ誰にも言わなかったのですか?
『紅楼夢』の登場人物、王希峰は金陵十二美女の一人です。これは今日、Interesting Histo...
『射雁英雄の帰還』では、武三通と李莫愁のどちらがより強いのでしょうか?
『射雁英雄の帰還』では、呉三通と李莫愁はともに同じ苦しみと敵を共有する人物である。物語が進むにつれて...
もし劉鋒が主力を率いて関羽を支援したのなら、なぜ関羽を救うことができなかったのだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
歴史上、揚子江南部の夏を描写した詩は何ですか?詩人たちが描いた長江南岸の夏とはどのようなものでしょうか?
歴史上、揚子江南部の夏を描いた詩は数多くあります。興味のある読者は、Interesting Hist...