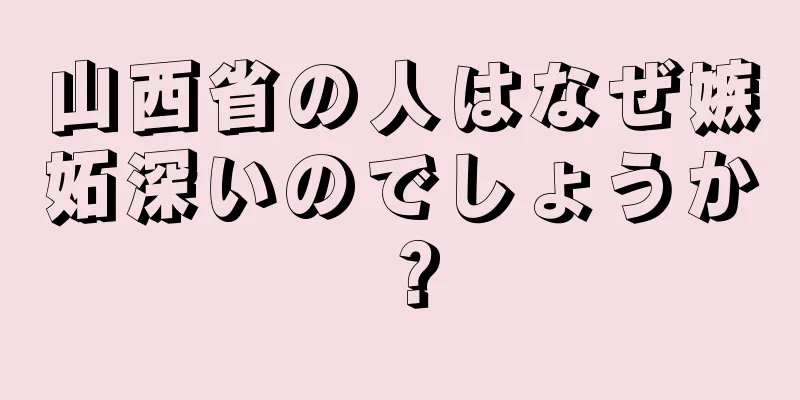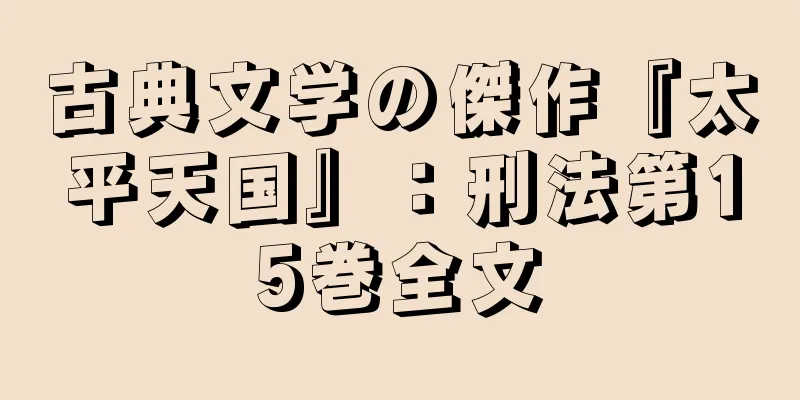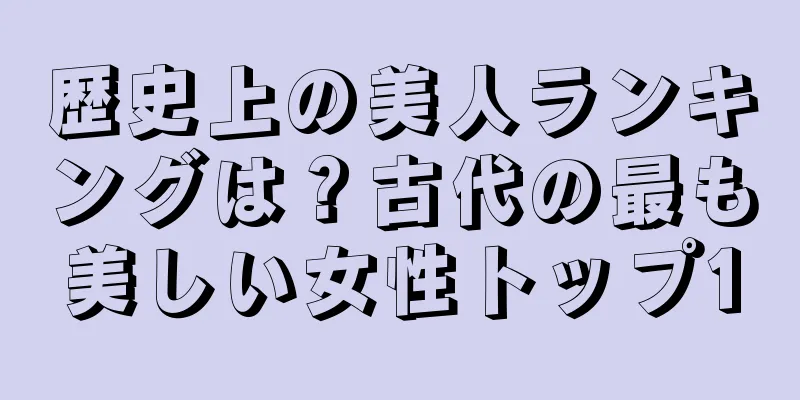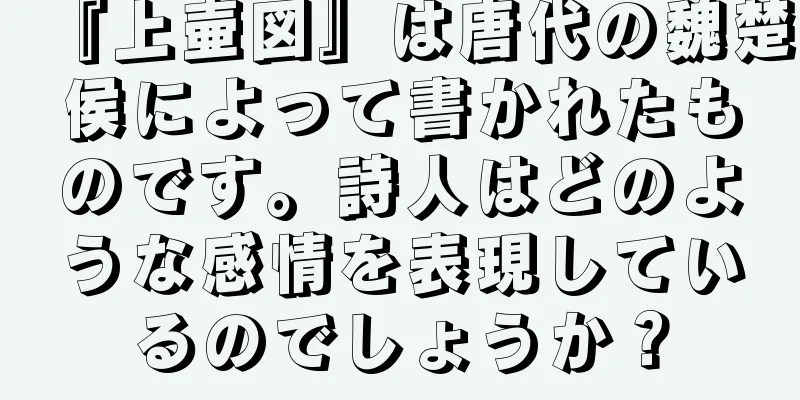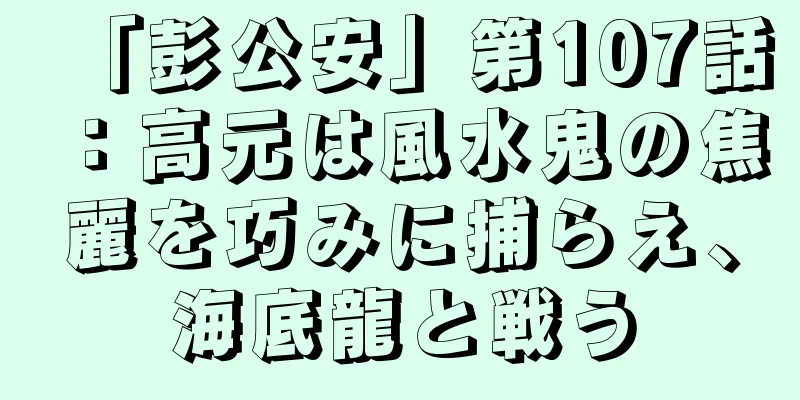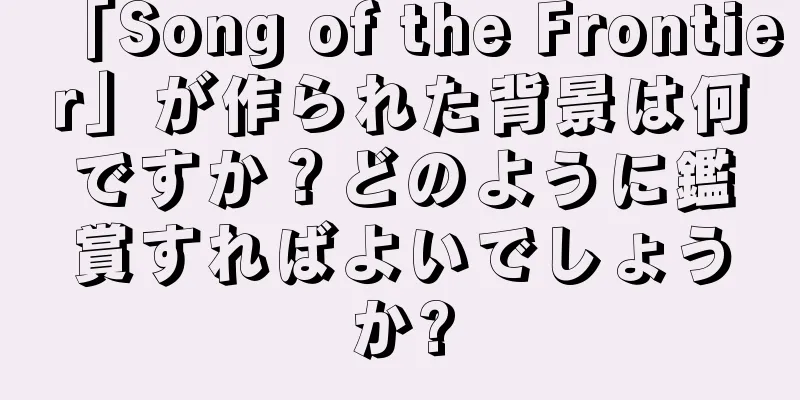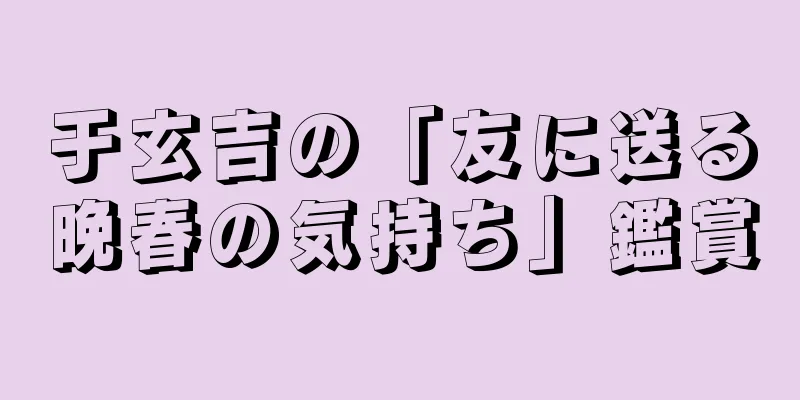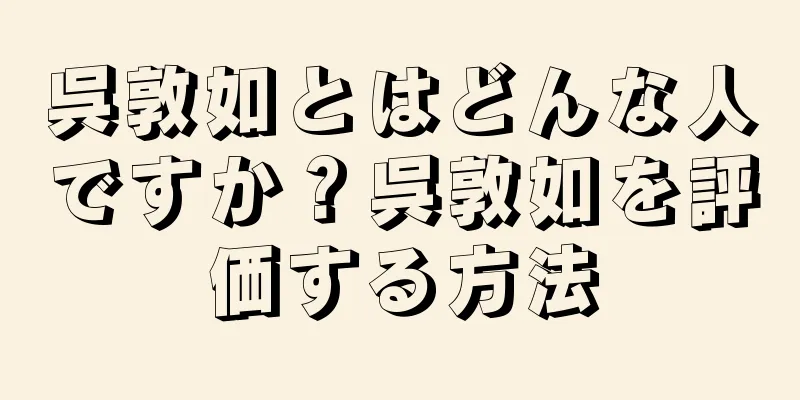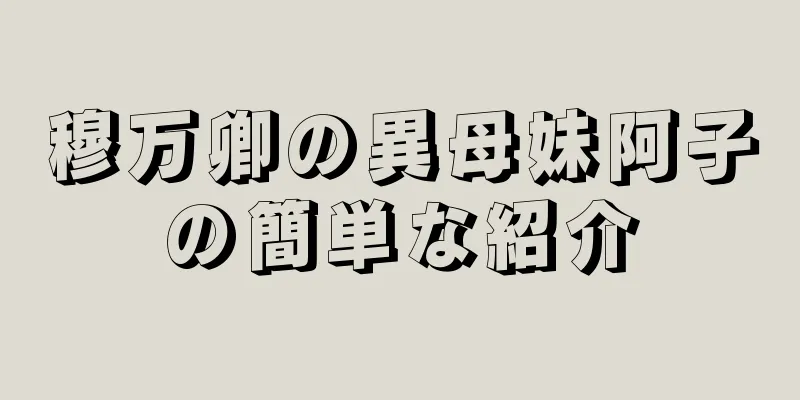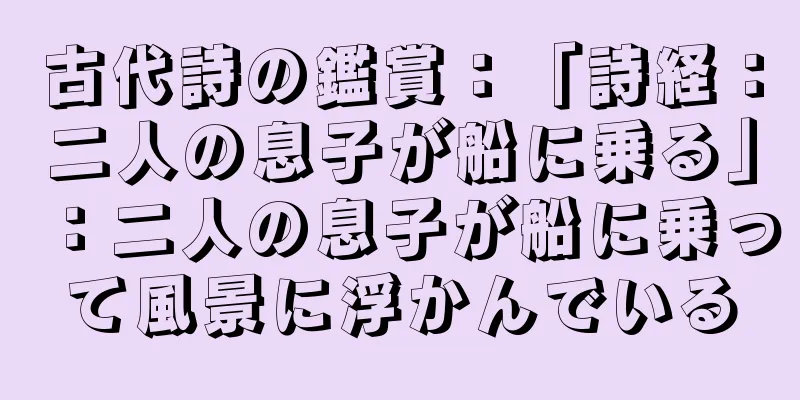「泰尚黄」と「泰尚黄帝」は実際には2つの異なる概念である
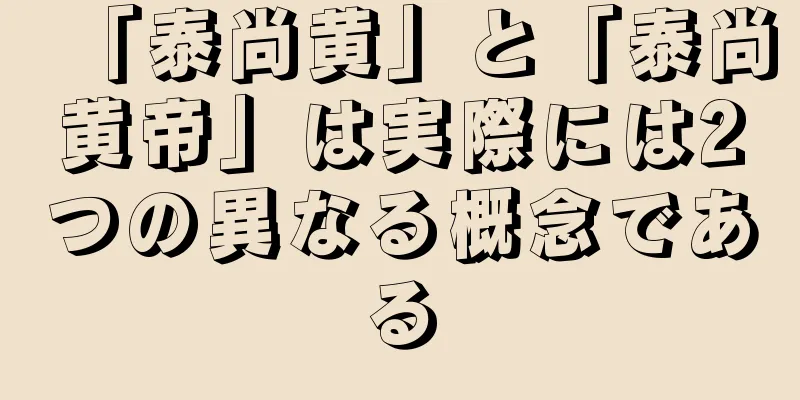
|
「泰尚皇」と「泰尚皇帝」は歴史資料に頻繁に登場する二つの用語です。文字の違いが 1 つしかないため、混同されやすく、互換的に使用されることもあります。実は、「泰上黄」と「泰上黄帝」はもともと2つの異なる概念でした。 「泰尚皇」という用語は『史記』に初めて登場します。秦の始皇帝は天下を平定した後、最高統治者は「皇帝」であると規定したほか、特に「荘襄王を死後に最高皇帝として尊崇した」。こうして、秦の始皇帝の息子である荘襄王(英一仁とも呼ばれる)は、中国史上初めて「太帝」の称号を持つ人物となった。 「太上」は最高かつ至高を意味し、非常に高貴なものを表します。しかし、当時、英一仁はすでに亡くなって何年も経っていました。 歴史上、存命中の最初の退位した皇帝は劉邦の父、劉太公であった。劉邦が皇帝になった後、彼が父の劉太公を訪ねるたびに、劉太公は臣下のような礼儀をもって彼を迎えた。劉太公の考えでは、「皇帝は息子であるが、国の君主でもある。太公は父であるが、国の大臣でもある」。君主と大臣の間の秩序は乱されてはならない。劉邦は非常に不満でした。息子が竜になったのだから、父親として相応の称号を持つべきだと考え、勅令を発しました。「王、侯、将軍、大臣、官吏は私を皇帝として敬っていますが、太公には称号がありません。今、私は太公を最高皇帝として敬います」(『漢書』)。 秦漢時代の「太尚皇」は称号であり名誉であり、皇帝ではなく政治には関与していなかった。これについて、後漢の蔡邕は「太尚皇は皇帝ではない、天子ではない」と述べている。また、唐初期の顔世孤は「彼は天子の父であるので皇と呼ばれ、政治に参加しないので皇帝とは呼ばれない」と評している。「太尚皇」は、現王朝の皇帝が人間関係から父に与えた敬称であり、実際の政治的権力はないことがわかる。 漢代以降、皇帝の上位の皇帝を意味する「泰尚帝」という称号が登場するようになった。例えば、十六国時代の後梁王呂光、北魏の献文帝拓跋洪、北斉の武成帝高占、唐の睿宗帝李旦などは、いずれも生前に退位した後は「太帝」を名乗った。時代的な隔たりから判断すると、「泰上黄帝」は「泰上黄」に由来しますが、両者の間には本質的な違いがあります。呂光は権力の円滑な移行を確実にするために「上皇」として務めるために早期に退位した。拓跋洪が退位した後、「すべての重要な国事は彼に報告された」(『魏書』)。高占が退位した後、「すべての重要な軍事と国家の事柄は彼に報告された」(『北斉書』)。李丹が退位した後、「彼は5日に1回太極堂で朝廷に出席し、自分を「私」と呼ぶ。彼は三位以上の官吏のすべての任命と重大な処罰を決定し、彼の決定は勅令と布告と呼ばれる」(『旧唐書』)と規定された。 「泰尚帝」は退位後も国政を執り行うことができ、現皇帝よりも優れた皇帝であることが分かる。 古代においては、「皇帝」の重みは「天皇」の重みよりもはるかに大きかった。両者を比較すると、「皇帝」は幻想的であるのに対し、「皇帝」は実権を握っているため、単に「皇帝」と呼ぶこともできます。 「泰尚皇」の「皇」という言葉は、もともとは単なる象徴的かつ名誉的な称号でした。 おそらく『泰上皇帝』は『泰上皇』に由来するため、後世の歴史資料では『泰上皇』と『泰上皇帝』が互換的に使用されるという混乱した現象が見られ、その中でも『宋史』が最も顕著であった。退位した同じ皇帝を指す場合、歴史家は「泰尚皇」と「泰尚皇帝」を使うこともあった。例えば、『高宗皇志』には宋の高宗趙狗が退位した際、「私は泰尚皇帝と称する」と述べたと記されているが、『孝宗皇志』には「泰尚皇帝は直ちに徳寿宮へ向かい、…泰尚皇を追って天竺寺へ向かった」と記されている。1つの年代記では両方の用語が使われている。例えば、『光宗皇紀』には、宋光宗の趙盾が退位した後、「太上帝」と尊崇されたとあるが、「太上帝は病気で赦免された。新茂で太上帝は崩御した」とある。この2つの年代記は異なる。 「泰尚皇」と「泰尚皇帝」の本来の意味によれば、「泰尚皇」は皇帝の父に過ぎず、実権を握っていません。一方、「泰尚皇帝」は父であるだけでなく、皇帝でもあり、実権を握っています。そのため、乾隆帝は退位後にどのような尊称を受けるかについて非常に心配していました。退位する前に、乾隆帝は「復位後、すべての追悼文は上皇に宛てて書き、追悼文も上皇に言及する」と具体的に規定しました。これは、公式文書では「上皇」と呼ばなければならないが、口頭では「上皇」と呼んでもよいことを意味します。この文は、乾隆帝が死ぬまで権力を放棄することを拒否したことを示しています(『清史草稿』)。 南北朝時代以降、「泰尚皇」や「泰尚皇帝」といった用語も登場した。例えば、北斉の最後の皇帝である高渭は「太帝」と称えられ(『北斉書』)、北周の宣帝である宇文雲は「天元帝」と称えられ(『周書』)、唐の玄宗皇帝である李隆基は「天帝」と称えられ、また「天聖帝」とも称えられた(『新唐書』)、唐の順宗皇帝である李宋は「応前聖寿太帝」と称えられ(『新唐書』)、宋の徽宗皇帝である趙季は「道君太帝」と称えられ(『宋史』)、西夏の神宗皇帝である李尊旭は「太帝」と称えられた(『宋史』)、などである。筆者の研究によれば、称号に「黄」のみが含まれる者は権力を握っておらず、「泰尚黄」の範疇に属するが、「黄」と「帝」の両方が含まれる者は依然として権力に関与することができ、「泰尚黄帝」とみなされるべきである。 中国の歴史上に登場する20人以上の「上皇」あるいは「退位した皇帝」の中で、晋の司馬忠、宋の趙狗、清の洪礼の3人は比較的特別である。 司馬忠は最も位の低い皇帝でした。太上皇とは通常、皇帝の父または祖父を指しますが、司馬忠は大叔父によって太上皇にされました。西晋永康元年(300年)、司馬懿の9番目の息子で司馬忠の大叔父である司馬倫が「八王の乱」で帝位を簒奪し、金の恵帝司馬忠を退位させ、金雍城に幽閉した。司馬倫は簒奪行為を隠蔽し、民衆を黙らせるために、孫の司馬忠に不適切な方法で「太帝」の冠を与え、それが歴史の笑いものとなった。しかし、幸福な時代は長くは続かず、司馬忠は復位し、司馬倫は殺害された。 趙狗は最長の在位期間を送った皇帝であった。紹興32年(1162年)、56歳で壮年だった宋高宗は、「高齢で病気のため、長い間引退を望んでいた」(『宋書』)という理由で、皇太子趙申に帝位を譲る旨の勅を出し、自らを「退帝」と宣言した。その後、趙狗は81歳で亡くなるまでさらに25年間「太帝」として君臨した。実際、趙狗が壮年に自ら退位したのは、「高齢で病気だった」からではなく、趙申への好意、死への恐怖、そして対金戦略の変更などの要因によるものであった。 洪礼は最も独裁的な皇帝だった。乾隆洪禧帝は皇帝の座に60年就いた後、大きな葛藤を抱えていました。彼は引き続き天下を治めたいと思っていましたが、61年間皇帝の座にあった祖父の康熙帝と争う勇気はありませんでした。そのため、皇太子の永厳に帝位を譲りました。実際、乾隆帝が退位した後も、「軍事や国の重要な事柄は依然彼に報告され、決定は彼の指示に従って行われ、主要な出来事は依然皇帝の勅令によって発せられ、宮廷暦は乾隆の年号を使用していた」。嘉慶永延帝は「高宗皇帝を最高皇帝として尊敬した」だけでなく、「最高皇帝が崩御し、皇帝が自ら国を治め始めるまで」昼夜を問わず「彼の政務を聞かなければならなかった」 (『清朝史草稿』)。 封建社会における終身帝位の補足として、古代中国の「上皇」と「上皇」の退位制度は長期間続き、同時に近隣諸国にも程度の差はあれ影響を与えたが、その中で最も顕著だったのがベトナムの陳王朝である。陳朝の成立後、帝位をめぐる内紛を避けるため、皇帝と上皇による「二君共同統治」の制度が実施され、これが陳朝全体の慣例となった。古代ベトナムの歴史家、呉世廉は次のように述べている。「陳家の掟によれば、…息子が成長すると、その子が王位を継承し、父親は最高皇帝と呼ばれる神聖で慈悲深い地位に退き、政務に参加する。実際、最高皇帝は将来の政務を決定し、緊急事態に備えるための優れた才能を継承するだけである。すべての事柄は最高皇帝によって決定され、後継者は皇太子と何ら変わらない」(『大越史』)。 「優れた才能のみが継承され、すべての事柄は最高皇帝によって決定される」という記述は、まさに中国の「上皇」制度と同じである。ベトナムのチャン朝の皇帝が退位した後、彼らのほとんどは「太帝」ではなく「大帝」として崇敬されましたが、これは「太帝」と「太上帝」が異なる概念であることを示しています。 (劉秉光) |
<<: 後漢末期の大臣、王允についての簡単な紹介。王允はどのようにして亡くなったのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』で賈邸が襲撃された後、賈廉はどこへ行きましたか?結末は?
賈廉は栄果邸の長男で、一流将軍賈奢の息子。「二代目賈」と呼ばれている。多くの読者が気になる問題です。...
楊仔の『都へ』:元代の「宗堂」の潮流における成功作
楊在(1271年 - 1323年9月15日)、字は中洪、普城(現在の福建省普城県)の人。元代中期の著...
「秦歌」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
秦 宋李斉(唐代)今夜は主人が祝杯を挙げてお酒を飲んでいますので、広陵からの客人のために琴を弾いてあ...
『半神半魔』における武夜子の武術はどれほど優れているのでしょうか?武耶子はどんな武術を知っていますか?
北明神術(ベイミンチー) 【荘子の『小瑶有』には「極毛の北には暗い海があり、それは天池である。そこに...
明代『志農(抜粋)』:言語と知恵の章・蘇哲全文と翻訳注釈
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
李公の事件第29章:パイプを返した貧しい女性はトランプゲームの正義を知っていた、夜警は客に遅れていた
『李公安』は『李公安奇談』とも呼ばれ、清代の西洪居士が書いた中編小説で、全34章から構成されています...
玄奘三蔵と同じくらい有名な僧侶、鑑真和上人の東方への旅の途中で、どんな興味深い出来事が起こったのでしょうか。
唐の時代には、仏典を求めて西へ旅した玄奘三蔵法師だけでなく、説法と問答のために東へ日本へ旅した鑑真和...
唐代の伝奇小説の特徴は何ですか?
Tang Dynastyには多くのメモ小説があります。 UanとTianbao Yishi、Li D...
キッチンの神様を送るって何?春節前の旧暦12月23日に厨房神を送り出す歴史
はじめに:厨子神送りは小正月を祝うとも呼ばれ、長い歴史を持つ漢民族の民間行事です。旧暦12月23日に...
「牡丹頌歌」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
牡丹への頌歌陳毓宜(宋代)胡塵が漢関に入って以来、易と洛への道は10年も長いものであった。老人が青墩...
『紅楼夢』で、犯罪者の娘である喬潔の運命はどうなったのでしょうか?
本日は、Interesting Historyの編集者が、皆様のお役に立てればと願って、喬潔について...
済公第233章:皇帝は金山に初めて到着した悪魔に称号を与えた
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
辛其記の『清平月:博山王寺独居』はどのような背景で制作されたのでしょうか?どのように鑑賞しますか?
辛其記の『清平月:博山王寺に一人で泊まる』に興味がある読者は、Interesting History...
古代中国の軍事戦略である三十六計の正しい順序は何ですか?
三十六の戦略:第一の戦略:戦争の勝利36の戦略の第一は真実を隠すことである十分に準備すれば怠け者にな...
楊季の「天平山にて」:多角的な描写で構成された素晴らしい山の風景
楊季(1326-1378)は、元代末期から明代初期の詩人であった。名は孟仔、号は梅安。彼はもともと嘉...