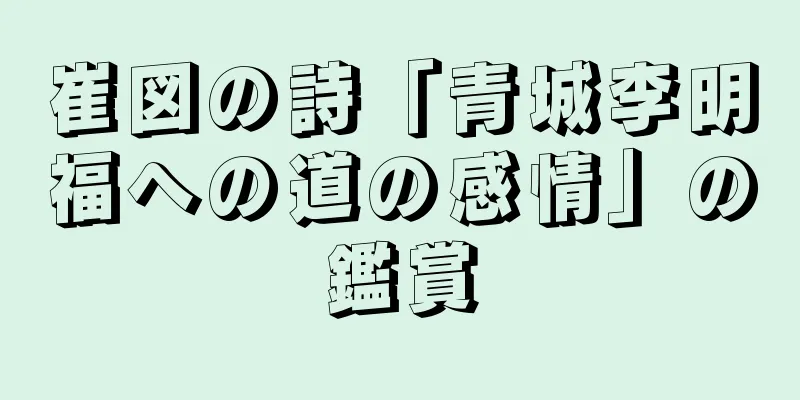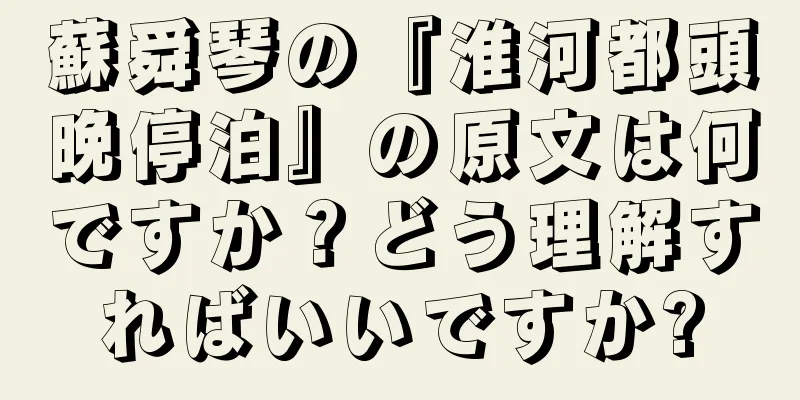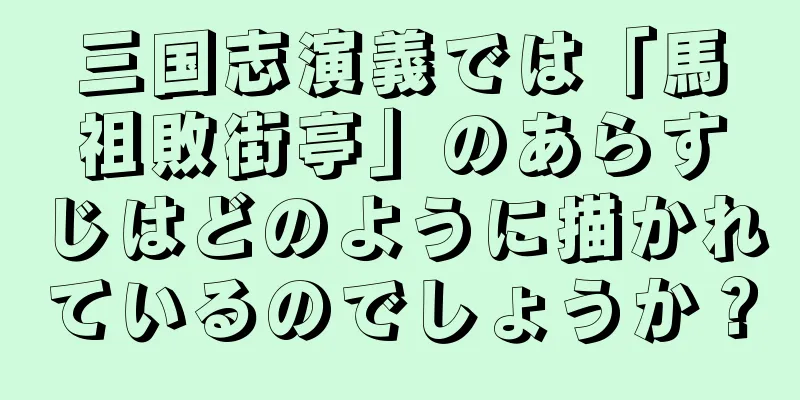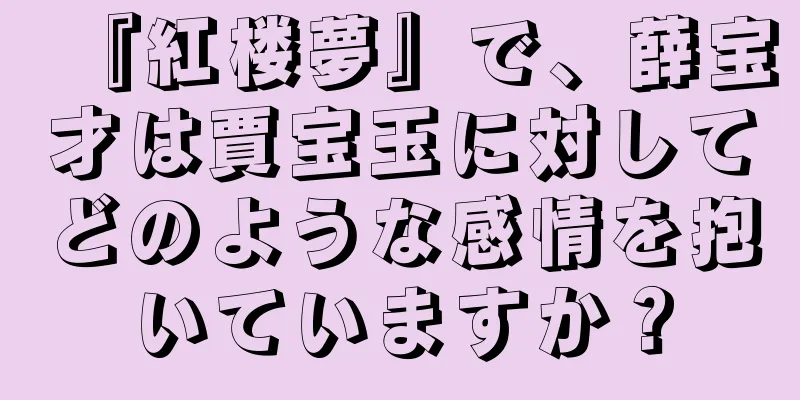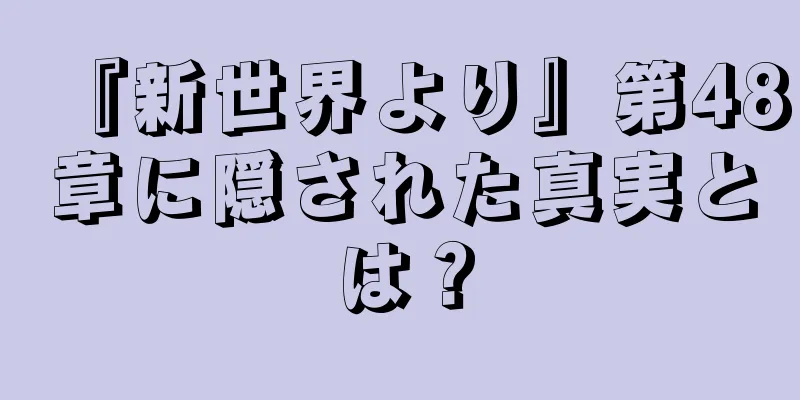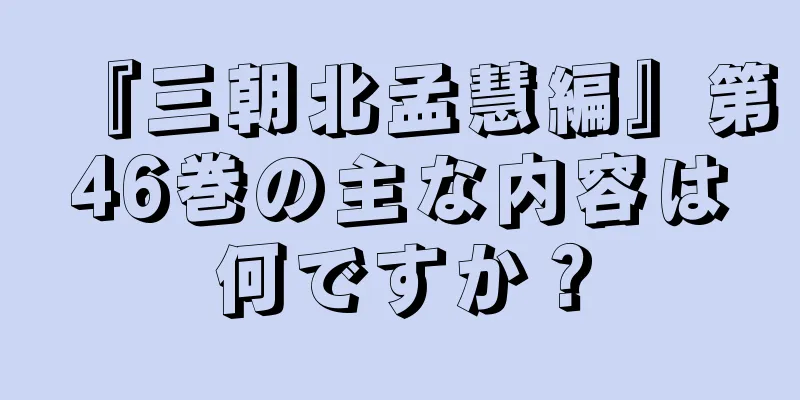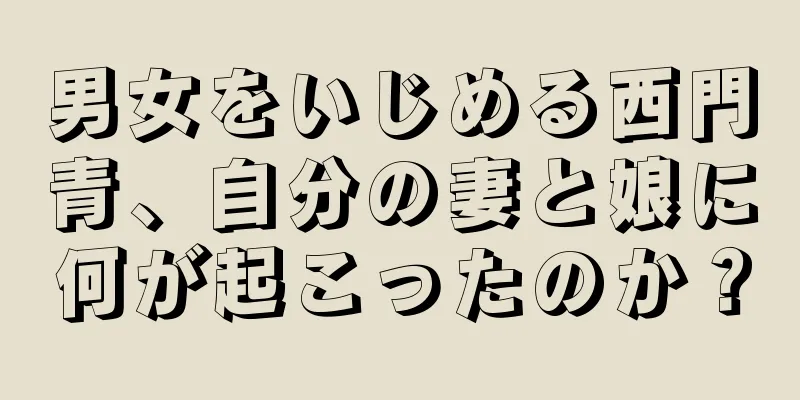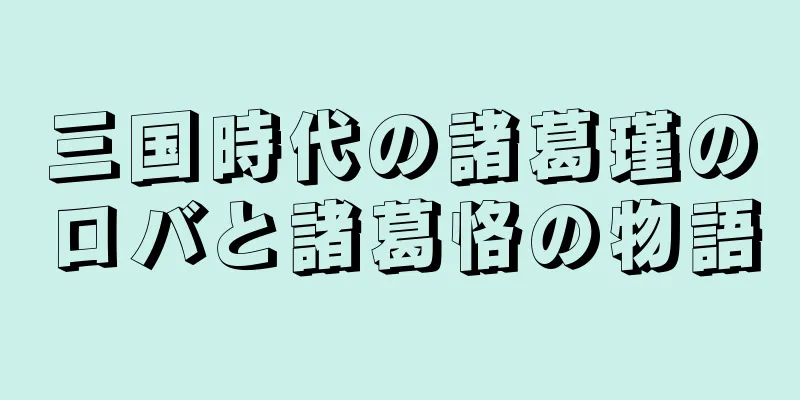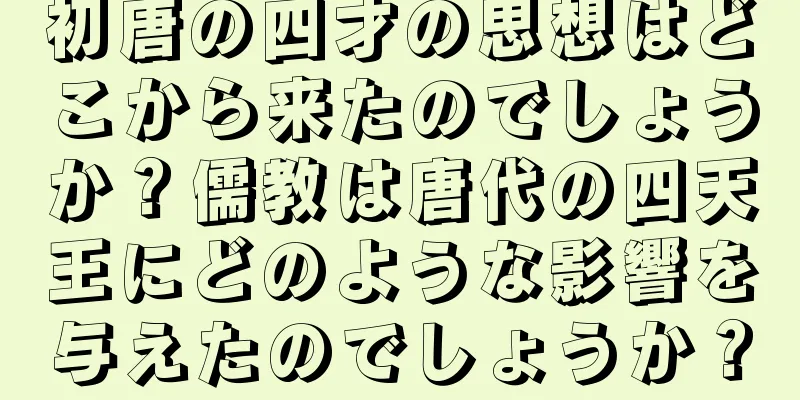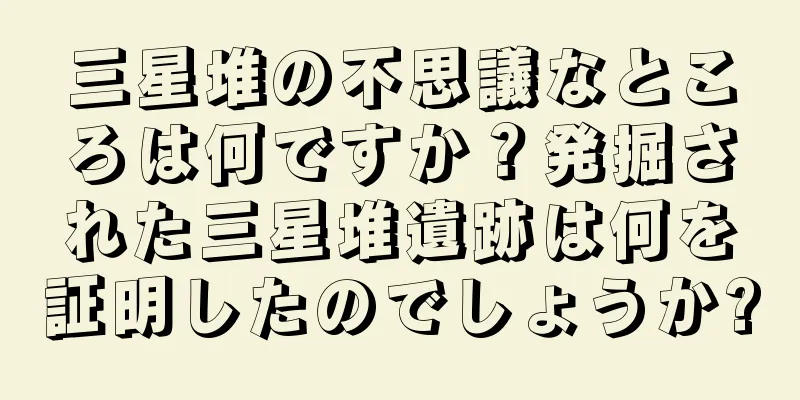琉球と沖縄は同じ場所ですか?沖縄と琉球の関係は?
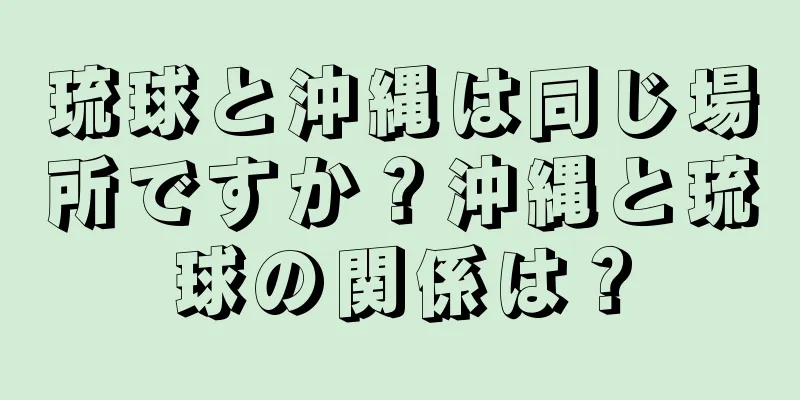
|
現在の日本の沖縄県は、沖縄島、宮古島、八重山島の3つの島を中心に、大小140以上の島々で構成されています。現在、人が住んでいるのは 40 の島のみで、総人口は約 120 万人です。もともとの「琉球王国」、あるいは「琉球弧」や「琉球文化圏」という地理的概念は、現在の沖縄よりもはるかに広大でした。さらに、「琉球諸島」は南北1,000キロメートルの海域に点在しており、面積は日本の本州よりも広い。沖縄本島最西端の与那国島からは、晴れた日には台湾が見えます。最南端の島、波照間島は台北よりもさらに南に位置しています。 沖縄は日本本土から遠く離れているだけでなく、歴史、文化、習慣も日本本土とは大きく異なります。最大の理由は、琉球がもともと独立国だったことです。地理的な位置から、海を挟んだ二大隣国、すなわち文化大国である中国と、武家政治を実践する封建国家である日本と頻繁に交渉しなければなりませんでした。 中国の影響を強く受けている 琉球の歴代国王は、当時の中国との「朝貢」や「冊封」の関係を通じて、密接な外交・貿易関係を築き、頻繁な貿易交流を通じて、中国文化、特に福州人の風俗習慣の影響を強く受けました。初期の日本が琉球に与えた主な影響は、第一に海賊「倭寇」による嫌がらせ、第二に強力な隣国「薩摩」による軍事的支配でした。このような歴史的背景により、琉球人は今でも日本人本来の気質とは異なっており、相容れないところさえある。 沖縄を旅して一番印象に残るのは、中国の食文化をはじめ、古代琉球の伝統と中国文化の痕跡がいたるところに見られ、自然と懐かしさを感じることです。 琉球が統一される以前は三国分立の時代があり、沖縄島を中心に、北から北山、中山、南山の3つの国に分かれていました。三山の「天下の君主」は皆、自発的に中国の明朝皇帝に「貢物」を納め、明朝はそれをすべて受け入れ、一つ一つ「授与」することで承認した。 琉球王国の始まり 1429年、中山王尚橋本が琉球を統一し、首里城を首都として「琉球王国」が誕生しました。しかし、首里城の建設は1930年代に始まりました。現在再建された那覇市の首里城公園は、かつて琉球王朝の宮殿があった場所です。 首里城は第二次世界大戦中に大きな被害を受けました。修復は1992年に始まりました。復元された首里城は、今も壮麗です。正殿のドーム型のデザインは典型的な唐風の門で、金色の屋根、朱色の柱、金色の龍の彫刻が施された梁、朱色の獅子が描かれた建物など、とても華やかです。 史料によれば、琉球が日本に併合される前、正殿二階には中国皇帝から琉球国王に下賜された勅額九枚が掲げられていたという。数回の戦争を経て、現在では所在が分かっていない。現在、正殿に掲げられている「中山寺図」の額は、康熙帝22年(1683年)尚禎王が列聖された際に贈られたもので、これも複製である。皇帝の椅子の所在は不明で、現在展示されているのは台湾の現代巨匠が作った傑作のレプリカだ。薩摩人を接待するために使われた南風殿を除いて、すべての建物は中国風で、特に本殿に続く北殿は、遠方からの使節を迎えて爵位を授与するために特別に建てられたもので、言うまでもなくすべて中国の宮殿を再現したものです。 沖縄国宝「守礼門」 沖縄の「国宝」であり、沖縄を象徴する建物が「守礼門」と呼ばれる「守礼の国」と書かれた記念碑のある記念碑です。宮殿の入り口である首里城公園の門のすぐ外側に立っています。首里城公園を訪れた日は、門が改修工事中だったため、有名な「礼を守る国」の4文字をじっくり見ることができませんでした。その後、ガイドの比嘉さんが私たちに「日本で一番有名な観光名所だが、行ってみてがっかりした場所はどこ?」と尋ねました。答えは那覇の守礼門でした。 守礼門の原型は中国の慰霊の門であり、門に掲げられた「守礼門の国」の扁額はまさに琉球を象徴するものである。唯一の欠点は、龍を1インチに縮小するという日本の習慣に染まっており、そのせいで威厳が薄れてしまっていることです。 「百聞は一見にしかず」と言う人がいるのも不思議ではありません。ツアーガイドは、見逃したことを悲しく思わないように、私たちを慰めるためになぞなぞを出してくれました。実際、多くの物事は、たとえ実際に会ったことがなくても、心の中に美しいイメージを留めておくことができるというのは本当です。 首里城の規模、特にその中国色の強い雰囲気から、当時の琉球王国と明清国との関係がいかに特別なものであったかが容易に想像できる。歴史の記録によれば、琉球王国は明・清との貿易を通じて大量の物資報酬を受け取っており、その一部は薩摩商人に転売され、後に日本が琉球を渇望するようになったという。同時に、琉球はより高度に発達した中国の製品と引き換えに、日本からの銅やその他の商品を琉球製品として中国に貢物を納めていた。琉球の王はどの王朝でも中国に貢物を納めていました。特に新しい王が即位したときは、必ず中国に使者を派遣して新王に「貢物を贈呈する」儀式を執り行うよう依頼しました。遣唐使の豪華な陣容と荘厳な情景を描いた「遣唐使行列図巻」は、現在、那覇市の沖縄県立博物館に所蔵されている。 琉球はかつて海洋貿易王国だった 琉球王国は何度か王朝が変わったが、中国に「朝貢」し、中国はそれを「贈与」した。この関係は、琉球が日本に完全に併合されるまで500年間続いた。 この関係を通じて、琉球は中国から大量の物資供給を受けるだけでなく、当時鎖国状態にあった中国の海上貿易の「総代理店」として発展していった。琉球船は那覇と福州の間を行き来しただけでなく、北は日本や朝鮮、南は安南(ベトナム)、ルソン(フィリピン)、シャム(タイ)、アチェ、ジャワ(インドネシア)、マラッカなど南洋各地へ航行しました。 |
<<: 貧しく弱体だった清朝末期がなぜ繰り返し他国を支援したのか?
推薦する
明代の暗殺事件は鄭妃が実行したのか、それとも皇太子朱昌洛が演出したものなのか?
棍棒暗殺事件は、明代末期の三大謎の一つで、万暦帝の長男朱昌洛と愛妾馮馮の鄭貴妃が主人公であった。そこ...
『江城子:金陵岸の草は夕暮れに平らかになる』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
江城子:夕暮れの金陵河畔の草欧陽瓊(五代)夕方になると、金陵のほとりの草は平らになり、沈む太陽は明る...
東晋の葛洪著『包朴子』外篇:良則、全文と翻訳と注釈
『包朴子』は晋の葛洪によって書かれた。包埔([bào pǔ])は道教の用語です。その由来は『老子』の...
ファン・リーに関する逸話や物語は何ですか?ファン・リーは息子にどんな教訓を教えたのでしょうか?
范蠡が軍を率いて呉国を破り、越国滅亡の恥辱を洗い流した後、范蠡は苦難は共有できても喜びや悲しみを分か...
宜禄:唐代に楊貴妃が新鮮なライチを食べることができた理由の一つ
「ポストロード」とは、大都市を結ぶ道路のことです。古代では交通は不便でした。古代には道路建設に使用で...
プミの結婚式で面白い「ロッキング仲人」とは何ですか?
プミ族の結婚式には、仲人をロックするという興味深い手順があります。花嫁の弟または兄が花嫁を寝室から運...
シナンは本当に存在するのか?歴史資料にはどのように記録されているのでしょうか?
シナンといえば、何を思い浮かべますか?次にInteresting Historyの編集者が、関連する...
段遂の生涯の簡単な紹介 段遂はどのように亡くなったのか? 段遂をどのように評価するのか?
段遂(?-386年)は、十六国時代後期の西燕の君主。もともと西燕の右将軍であった。段遂の伝記太元11...
「紅楼夢」のヨウシの人生には、決して許されないことが2つある。
『紅楼夢』の幽士の人生には許せないことが二つあります。それが何なのか知っていますか?次の興味深い歴史...
ユグ族の日常の礼儀作法とタブー。外出する前や商売をする前に暦を確認します。
エチケットユグル族は寛大で心が広く、親切で、友人を作るときや客をもてなすときには礼儀作法に細心の注意...
古代の人々が入浴に使っていた木製の桶はなぜ漏れ防止だったのでしょうか?秘密は何ですか?
古代人が入浴に使った木製の樽はなぜ漏れなかったのでしょうか?その秘密は何でしょうか?次の興味深い歴史...
劉克荘は梅谷を使って自分の気持ちを表現し、「曼江紅 - 斗凡為梅谷」を書いた。
劉克荘(1187年9月3日 - 1269年3月3日)は、原名は卓、字は千福、号は后村で、福建省莆田県...
『新説・讃美物語』第136条に記されているのは誰の言葉と行為でしょうか?
『十朔新于』は魏晋の逸話の集大成です。では、『十朔新于・讃・136』には誰の言葉や行いが記録されてい...
『環西沙:漂流することが哀れではないと誰が言った』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
環希沙:一人でいることが哀れではないと誰が言った?那蘭興徳(清朝)一人でいるのは哀れではないと誰が言...
『晋書』第109巻第9章の原文は何ですか?
◎慕容黄慕容皇は、号を元鎮といい、魏の三男であった。彼は龍の顔と皿のような歯を持ち、身長は7フィート...