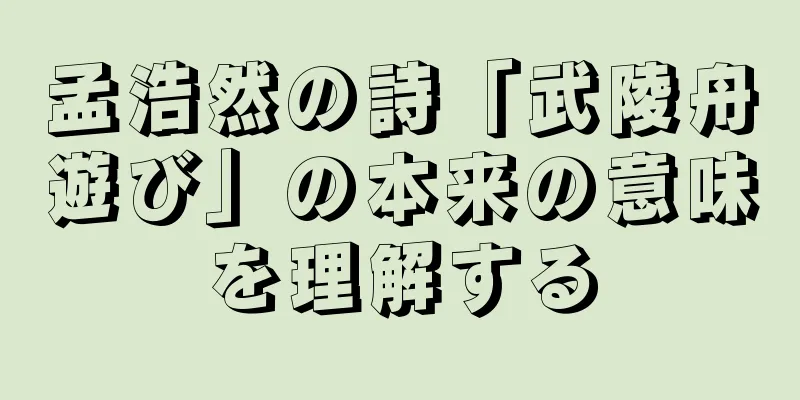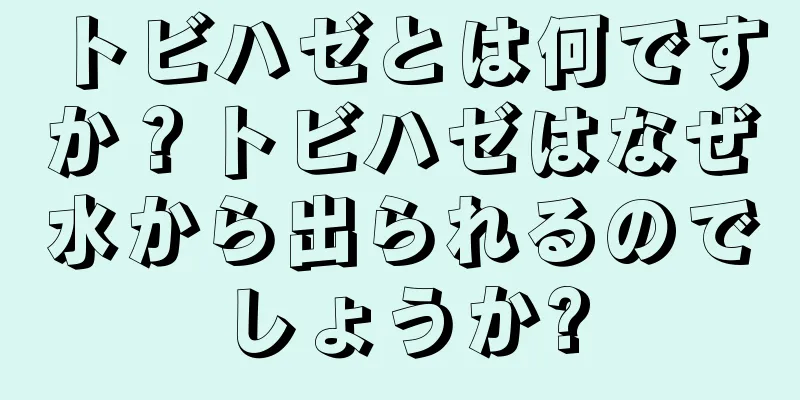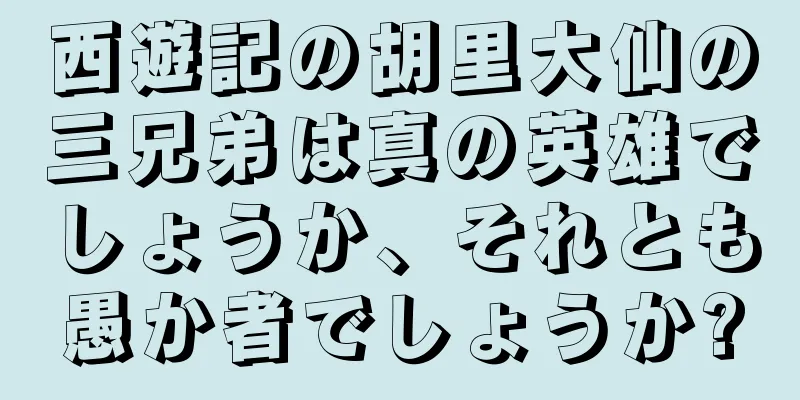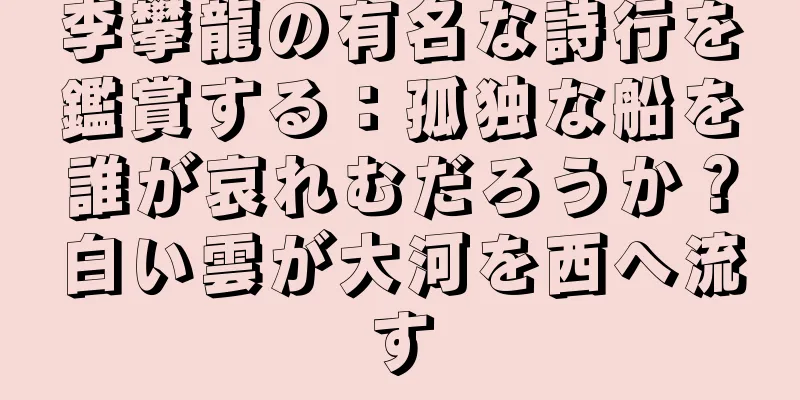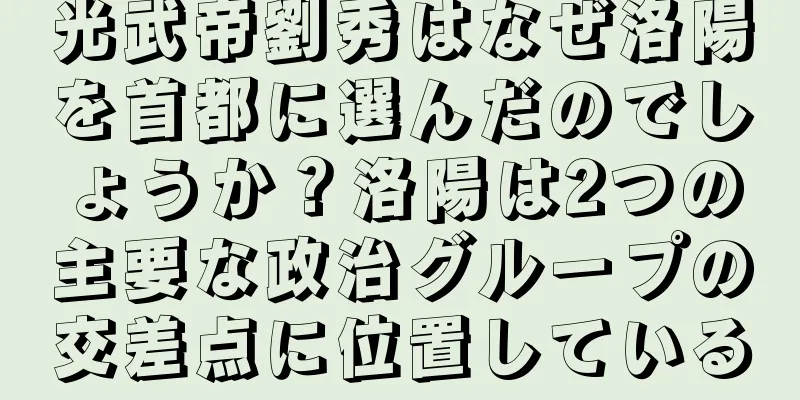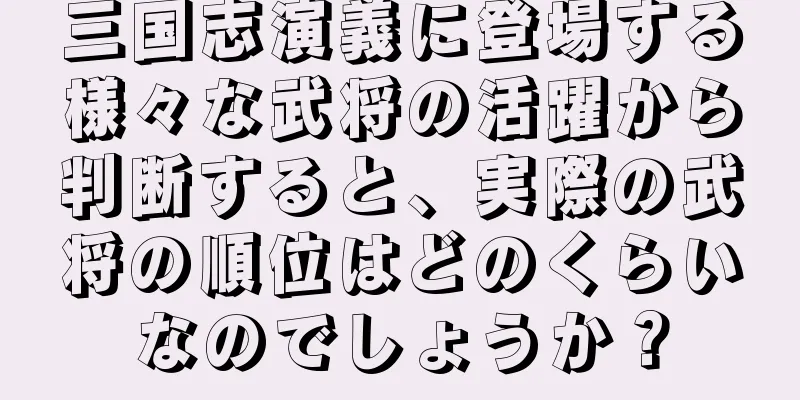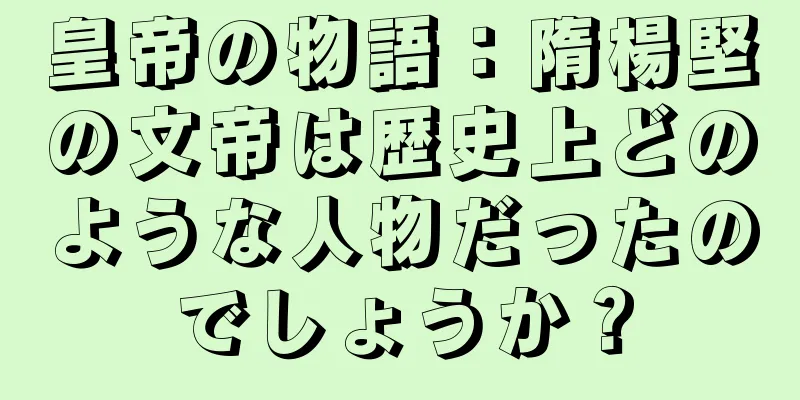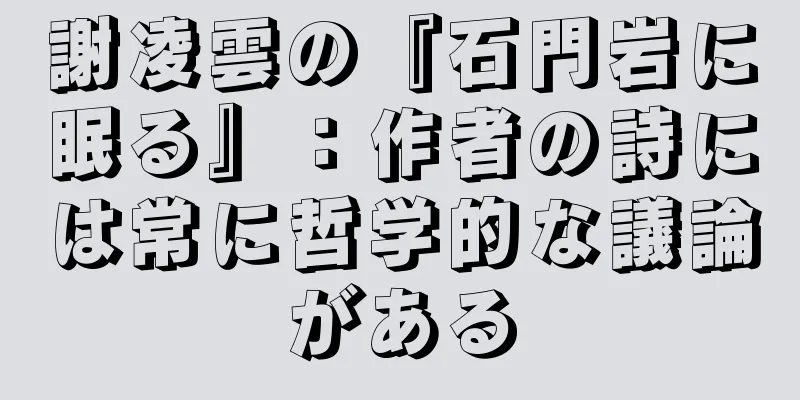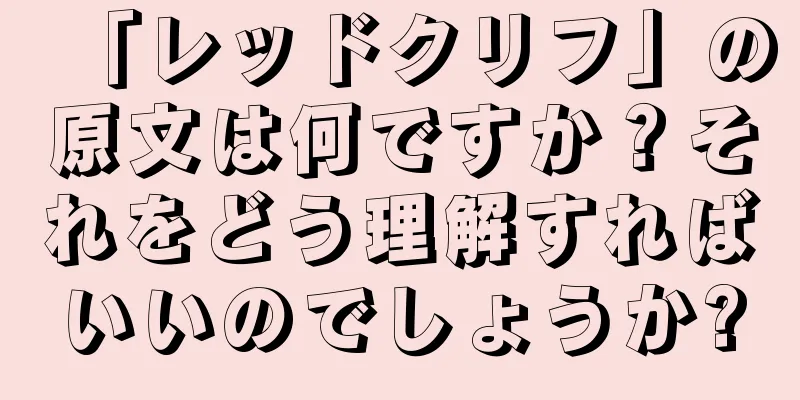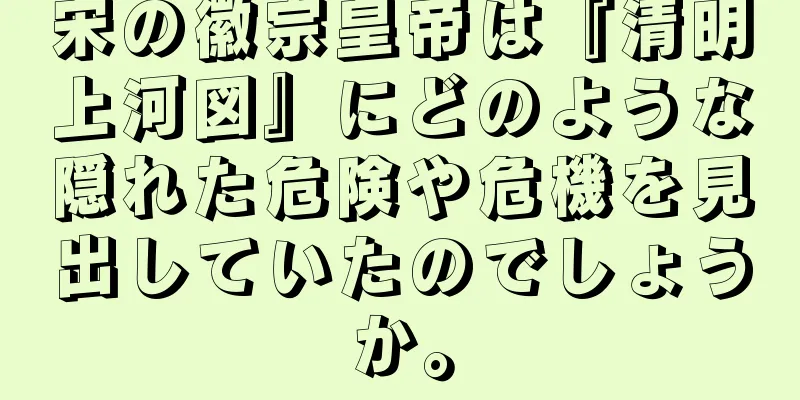大学入試でトップスコアを獲得した古代人15人
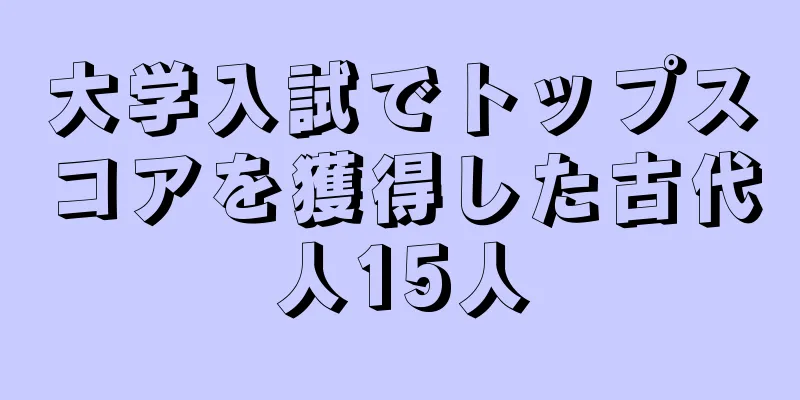
|
大学入試でトップスコアを獲得した古代人15人 今日、2015年度の大学入試の得点ラインが全国各地で発表されました。ほとんどの省や都市の受験生は自分の得点を確認しました。結婚初夜に合格者リストに自分の名前が載り、希望の大学に入学できたことは、ほとんどの学生にとって人生最高の思い出です。もちろん、試験でトップの得点を取れれば、それは幸せの極みです。 古代中国の大学入学試験である科挙は、隋代から清代までの1300年以上の期間に700人以上の成績優秀者を輩出しました。この700人の学生は皆、優れた才能を持ち、学問の達人と呼ぶにふさわしい人々でした。 しかし、科挙で首席になることよりもさらにすごいのは、科挙に3回合格することです。 三元科挙:科挙における地方科挙、都科挙、宮廷科挙で一位を取ること。 地方の試験は地方朝貢とも呼ばれ、各州と県によって主催されました。試験に合格した候補者は中居と呼ばれ、試験に合格した人だけが首都に行き、都の試験に参加する資格がありました。地方の試験で1位になった人は結院と呼ばれました。 合同試験は3年ごとに北京で開催され、省試験に合格した受験者が参加しました。試験会場は通常科挙会場に設置されたため、合同試験に合格した者は公師または中師進師と呼ばれ、合同試験の1位は慧遠と呼ばれました。 内科試験は、その名の通り、皇帝自らが主宰し、合科試験に合格した者が参加する試験です。内科試験に合格した者は進士と呼ばれ、内科試験の1位は荘園と呼ばれました。 一つの科挙において、地方の科挙、都の科挙、宮中の科挙で第一位となることは、三つの科挙で第一位となることであり、すなわち、三つの科挙で第一位となり、三つの科挙で第一位となることである。 考えてみれば本当に恐ろしいことです。科挙制度の1300年の歴史の中で、このような偉業を成し遂げたトップ学生はわずか15人です。彼がどんな人か見てみましょう。 唐代には3人の人物がいました。 1. 崔元漢は唐の徳宗皇帝の辛佑の年(781年)に科挙で一位を獲得し、三傑にも選ばれました。彼は史上初めて三傑を獲得した学生でした。当時、科挙は180年以上続いていましたが、崔にとって容易なことではありませんでした。彼が一位を獲得したのは52歳の時でした(崔三元、何回科挙を受けたのですか?)。三傑を獲得したことに加えて、崔元漢は2人の弟とともに進士になる栄誉も得ました。同じ家に3人の進士がいることはもう一つの名誉でした。 張有鑫の「お茶の淹れ方ノート」 2. 張有鑫は唐の献宗元和9年(814年)に科挙で首席となり、当時は張三頭と呼ばれていました。張三頭は試験に非常に優秀で、趣味はお茶の味見でした。彼の『茶水注』は陸羽の『茶経』と並んで重要なお茶の歴史書です。 3. 呉易煌は唐の献宗元和元年(806年)の科挙で首席成績を収めた。呉三元は宰相呉元衡の息子で、科挙に優勝した後、家庭内暴力で弾劾された。 宋代の6人: 4. 孫和は宋の太宗の春化3年(992年)、科挙で首席になった。孫和は後に宰相となった丁維と同じくらい有名で、孫丁と呼ばれた。二人は一緒に科挙を受けた。孫和は1位、丁維は4位だった。丁維はこれに非常に不満だった。太宗はそれを聞いて、「A、B、C、Dの中で、丁維が4位になるのは当然だ」と言った。 クラスメイトの丁偉が不満を抱く理由はないはずだ。なぜなら孫何は孫三元だからだ。 5. 王増は、宋の真宗5年(1002年)の科挙で首席となった学者であり、北宋の第25代首席学者であり、副宰相を務めた。 6. 宋陽は、仁宗皇帝の天勝2年(1024年)に科挙で首席を獲得しました。当時、宋陽と弟の宋啓は一緒に科挙を受けました。当初、宋啓は1位、宋陽は3位でした。劉郁皇太后は、弟が兄より上位にランクされるべきではないと考え、2人の順位を入れ替えました。こうして、宋陽は科挙の成績上位3名となりました。 7. 楊志は、仁宗皇帝の清暦2年(1042年)に科挙で首席になった。楊三元は不運に見舞われた。科挙で首席になった後、母が亡くなった。楊三元は喪に服すために帰省したが、喪が明ける前に病死した。科挙で首席になったことは楊三元にとって幸運をもたらさなかった。また、この年の2位から4位は、後に帝国の有名な宰相となった王桂、韓江、王安石であったことも特筆に値します。この3人は合計200年間生きました。 8. 宋代仁宗元年(1049年)、馮三元は科挙の成績で首位に立った。容姿端麗で、未婚の青年であったため、帝国の奪取商品となった。二人の王族の張という名の女房が、娘を彼に嫁がせようと競い合い、かつては城中に知られるほどの大喧嘩をした。最後に、宰相の傅弼が彼女を奪い取った。傅弼の娘が亡くなった後、傅弼は末娘を彼に嫁がせた。科挙の成績で首位に立った馮三元は、「宰相の娘と二度結婚し、科挙で三度首位を獲得する」という永遠の伝説を達成した。 写真:ダイヤモンド5の馮静を獲得しようと争う東京住民 9. 王延蘇は宋の仁宗の治世、嘉祐六年(1061年)に科挙で三位を獲得した。彼は北宋で科挙で三位を獲得した最後の人物である。また、仁宗の治世には科挙で三位を獲得した人が4人いたことも特筆に値する。なぜ欧陽秀、范仲厳、蘇三兄弟、王安石、司馬光、鮑正など多くの一流の文人が仁宗の治世に現れたのかは、理解に難くない。 写真:北宋時代の知識人は厚遇されていたため、優れた学問の達人がたくさんいた。 晋 10. 孟宗憲は、金の世宗大徳3年(1163年)の科挙で最高得点を取った人物である。金の科挙は他の王朝の科挙とは少し異なっていたことは特筆に値する。科挙は、省試、県試、省試、朝試に分かれていた。孟宗憲は、4つの科挙すべてで最高得点を取った人物である。 孟嗣源は道教を崇拝し、有名な道士である王重陽を師としました。王重陽の葬儀を執り行ったのも彼でした(全真七子??) 元朝 11. 王宗哲は、元代の智正8年(1348年)の左記の筆頭学者であり、科挙の筆頭三学者である。生没年は不明である(元代では知識人は重視されず、元代末期には世が混乱していたため、王三元の栄光はその時代に影を潜めてしまった)。 明代 12. 洪武23年(1390年)の科挙首席の黄冠は、科挙の最高位の3人の学者の一人でした。後に彼は建文帝の侍医になりました。燕王朱棣が帝位を奪取したとき、黄冠は忠誠を示すために川に飛び込んで自殺しました。朱棣が権力を握った後、彼は科挙首席の称号を取り消しました。ここで、黄冠にそれを補いたいと思います。 13. 正統10年(1445年)の科挙で首席となった尚魯。尚三元は後に内閣の宰相に任命され、名宰相となった。科挙の首席3人の中で、彼の政治経歴は最も輝かしいものであった。 清朝 14. 乾隆46年の第1学者、千琦。明清時代に科挙制度がさらに細かくなり、郡試、県試、学試に分かれ、さらに省試、都試、宮試に分かれたため、千三元は実は千柳元であった。前述の黄冠という学生もこのレベルです。 15. 嘉慶26年(1820年)の最高学者、陳紀昌。陳三元は中国史上最後の最高学者であった。85年後、1300年以上続いた科挙制度は終焉を迎えた。 上記の15人の文民トップスコアラーの他に、軍事試験では4人の軍事トップスコアラーもいた。明代の殷鋒と王世明、清代の王毓弼と古林である。 |
推薦する
『宋書』巻五、歴代五◎文帝原文
太祖文帝の本名は宜龍、あだ名は車児。武帝の三男。彼は晋の安帝の義熙三年に京口で生まれた。 4年前、陸...
『荀孟評論』第六巻「魚」原文の鑑賞と注釈
司守謙作「子供のための片居」、明代美しい顔が現れ、柳の眉毛が緩んでいます。雁文字が2行と魚文字が書か...
目録: 古代中国の 4 つの主要な民間伝説は何ですか?
古代中国の四大民間伝説は、「牛飼いと織女」、「蝶の恋人」、「孟姜女の万里の長城での泣き声」、「白蛇伝...
李白は女性を一緒に旅に誘うためにあらゆる努力をし、彼女の心を勝ち取るためにEQの高い詩を書いた。
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が李白につい...
中国における宮廷クーデターのトップ10は何ですか?なぜ宮廷クーデターが起こったのか?
中国の封建時代の歴史では、文官や将軍によるもの、あるいは王族内部によるものなど、宮廷内でのクーデター...
薛涛の「友よ別れよ」は、曲がりくねっていて、暗黙のものである。
薛涛は、字を洪都といい、唐代の音楽家、遊女、女教師、詩人であった。卓文君、花瑞夫人、黄鄂とともに蜀の...
『後漢書 梁洪伝』の原文と翻訳、『梁洪伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
諸葛亮はなぜ大きな権力を握り、それを劉禅に返還することを拒否したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』の賈家の女性のうち、二番目の妻だったのは誰ですか?子どもを持たない理由は何ですか?
小説『紅楼夢』の最大の特徴はその巧みな構成にあります。これについて言及されるたびに、詳しくお話ししな...
陸倫の詩集「辺境の歌」の一つ:「張普社に応えて辺境の歌、第二部」
陸倫(739-799)、号は雲岩、河中普県(現在の山西省普県)の人。祖先は樊陽涛県(現在の河北省涛州...
マラソンの起源。マラソンの歴史を簡単に紹介します。
マラソンの起源:世界最長の陸上競技 - マラソン。マラソンは、42.195キロメートルの距離を走る長...
黄色いローブは誰と関係があるのでしょうか?黄色いローブはどうやって生まれたのですか?
黄色いローブを着た主人公が誰か知っていますか? 知らなくても大丈夫です。Interesting Hi...
『紅楼夢』の中で、薛宝才は、本を読んだ後に悪くなる人もいると言っています。この文章はどういう意味ですか?
薛宝柴は『紅楼夢』のヒロインで、林黛玉と並ぶ存在です。これについて言及するたびに、詳細をお話ししなけ...
飛竜伝説第33章:李太后が皇太子を探し、郭元帥が王位に就く
『飛龍全篇』は清代の呉玄が書いた小説で、全編にわたって趙匡胤が暴君に抵抗する物語を語っています。物語...
清朝の康熙年間、「人口増加に伴う税金を決して増やさない」という政策にはどのような改革が行われましたか?
鼎税地割制度は、鼎税地割、鼎税地租合一とも呼ばれ、中国後期封建社会における重要な税制改革である。清朝...