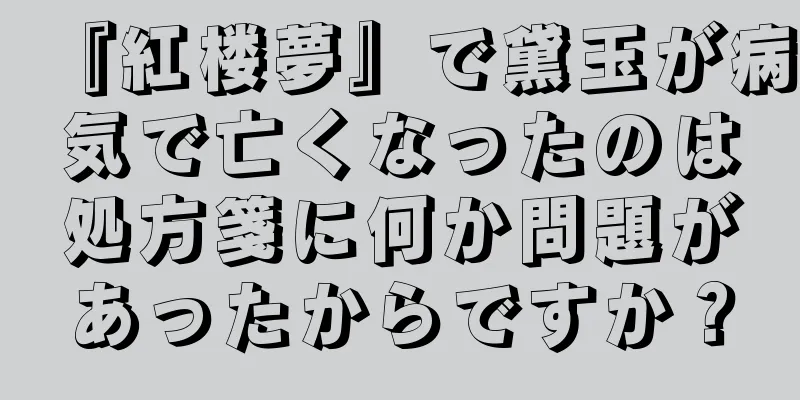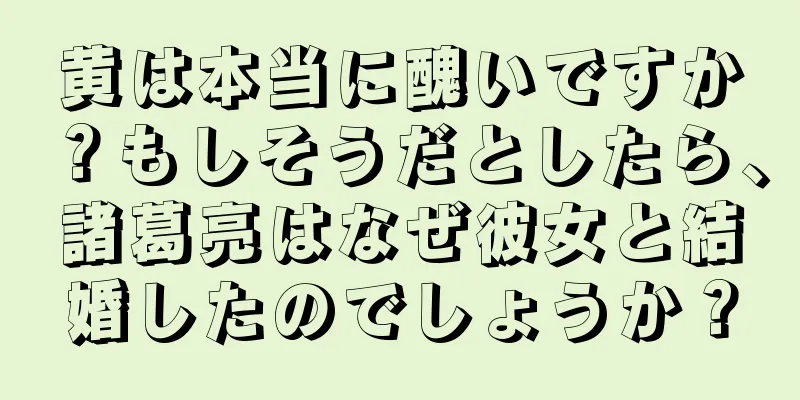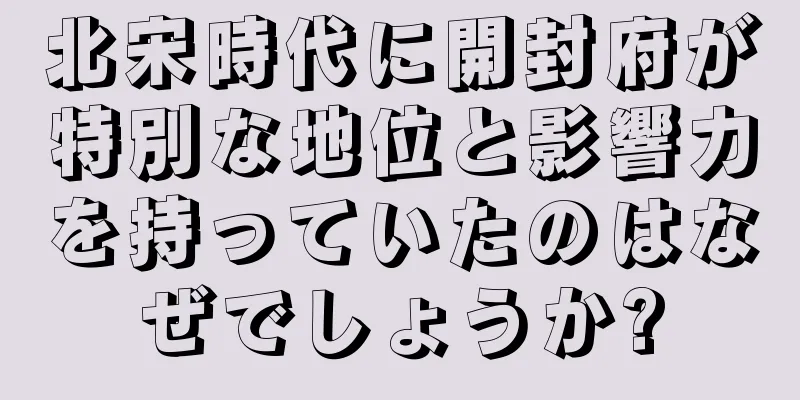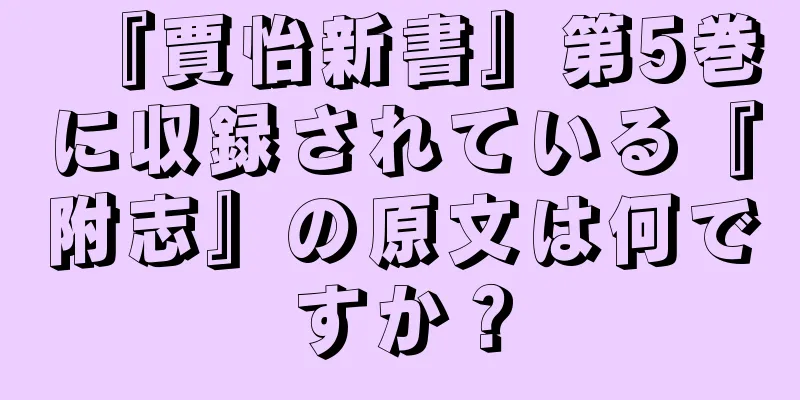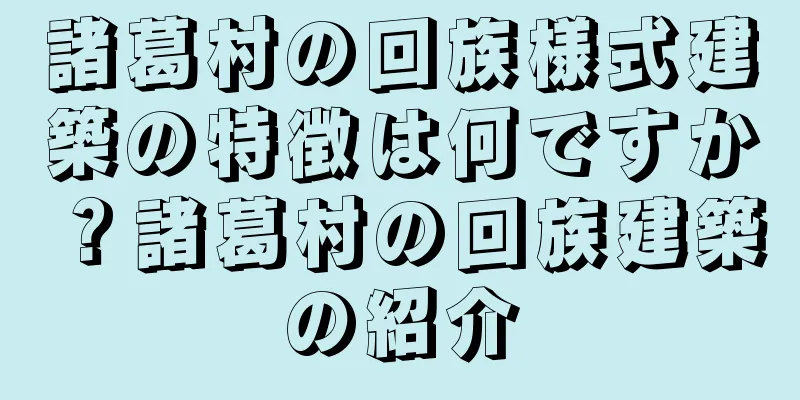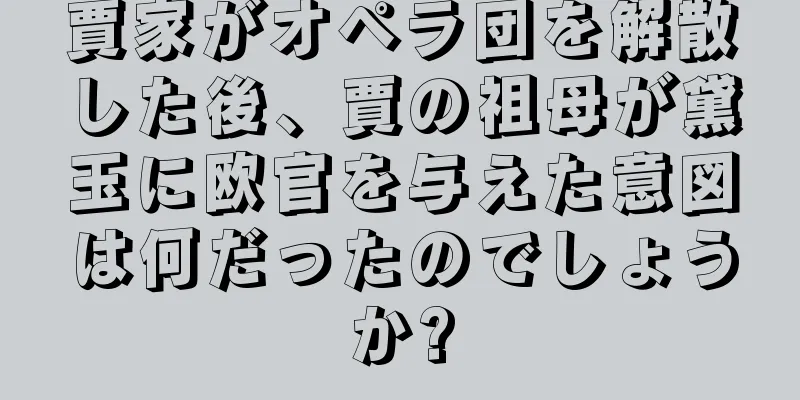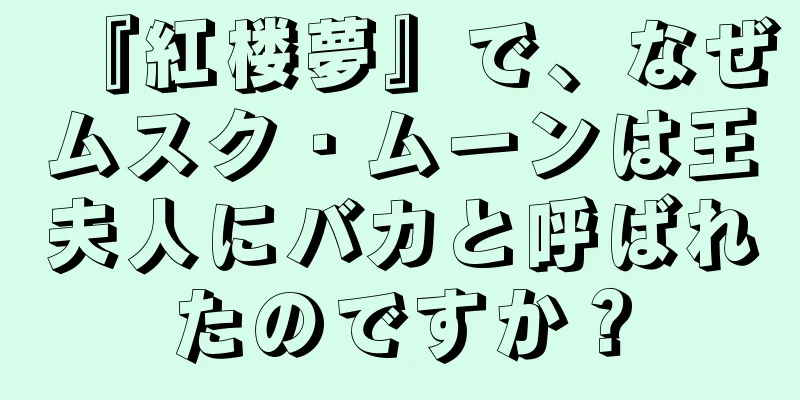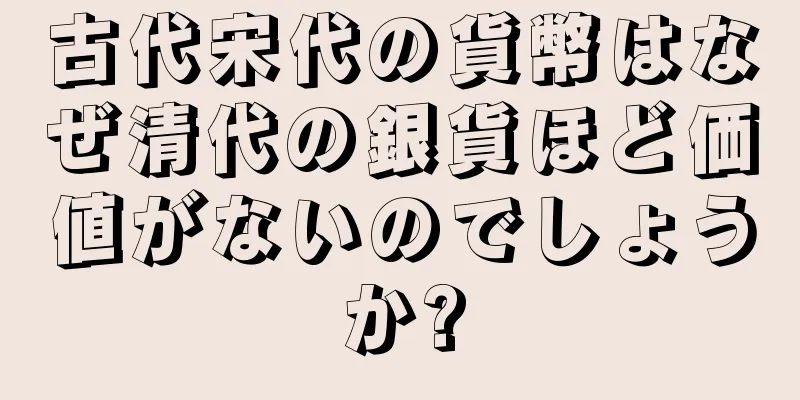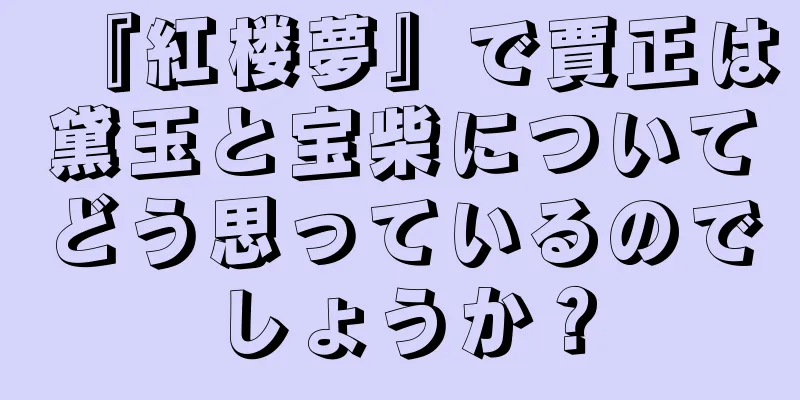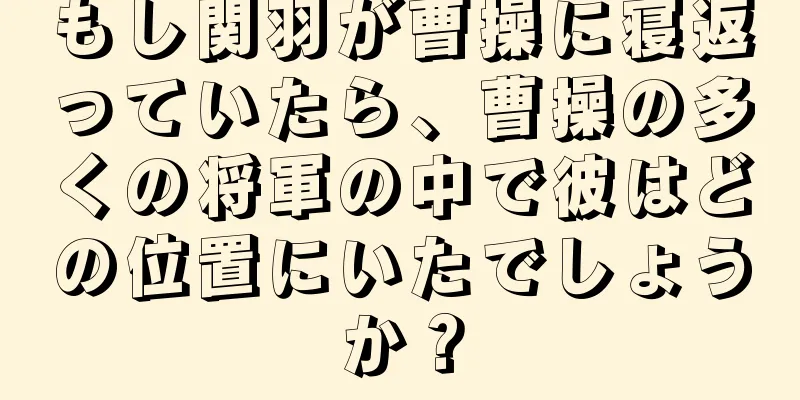古代中国でそろばんを発明したのは誰ですか?そろばんの起源
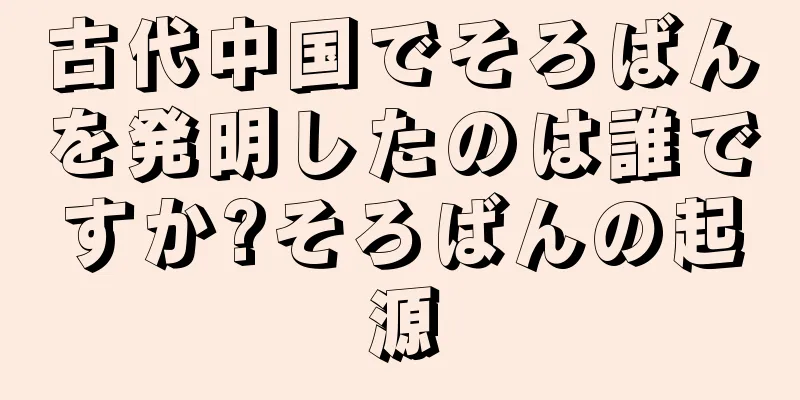
|
そろばんは中国の伝統的な計算道具です。これは中国人が長年使用してきた数え棒に基づいて発明したものです。古代中国の偉大で重要な発明であり、アラビア数字が登場する前は世界中で広く使用されていた計算ツールでした。 そろばんという用語は、特に中国のそろばんを指すわけではないことに注意する価値があります。現存する文献から判断すると、多くの古代文明にはそろばんに似た独自の計算ツールがありました。中国や海外の古代から現代に至るまで、そろばんにはさまざまな種類がありますが、大きく分けて砂盤、数え盤、珠算盤の3つに分類できます。 そろばんの起源について。 一説によると、漢末期の三国時代にまで遡り、関羽が発明したと言われています。その頃、我が国にはすでに「そろばん」があったと言われています。古代人は、10 個のそろばん玉をグループにつなぎ、グループを並べて枠の中に入れ、素早く玉を動かして計算をしていました。 しかし、公開されている情報によると、「そろばん」という用語が初めて登場したのは、東漢の徐岳が著した『算数集意』で、「そろばんは四季と三才の経度と緯度を司る」と述べられている。北周の甄鸞はこれについて注釈を残しており、大まかに言えば、木の板を3つの部分に彫り、上部と下部は珠を留めるために使い、中央の部分は位置決めに使うという意味である。一人当たり5個のビーズを持ち、一番上のビーズと一番下の4個のビーズは色で区別されており、これは後に「レベル」と呼ばれるようになります。一番上のビーズは 5 個として数え、一番下の 4 つのビーズはそれぞれ 1 個として数えます。今日の説明は、そろばんは長方形で、木枠に細い棒が埋め込まれており、その棒にそろばん玉が張られています。そろばん玉は細い棒に沿って上下に動かすことができ、そろばん玉を手で動かすことで算数が完成します。 古代の人々は、計算をするために小さな木の棒を使っていました。これらの小さな木の棒は「数え棒」と呼ばれていました。数え棒を使った計算は「数え棒」と呼ばれていました。その後、生産技術の発達により、小さな木の棒を使った計算には限界が生じたため、人々はより高度な計算ツールであるそろばんを発明しました。 明朝の時代になると、そろばんは足し算、引き算、掛け算の計算ができるようになっただけでなく、土地の面積やさまざまな形状の物体の大きさも計算できるようになりました。 そろばんは作りやすく、安価で、そろばんの公式も覚えやすく、計算も簡単なので、中国で広く使われており、日本、北朝鮮、アメリカ、東南アジアなどの国や地域にも徐々に広まってきています。現代は電子計算機の時代になりましたが、古代のそろばんは今でも一定の役割を果たしています。 |
推薦する
伝説の九龍の母、婁昭君:婁昭君の息子は誰ですか?
古代の歴史は、男性が競い合う舞台であると同時に、女性の輝かしい色彩に満ちている。編集者によれば、中国...
『三朝北孟慧編』第46巻の主な内容は何ですか?
静康巻。それは、景康元年4月16日に始まり、易愁の29日に終わりました。蔡靖は潼管を衡州に移し、蔡有...
安史の乱の当時の唐王朝は何世紀でしたか?この期間にどのような歴史的出来事が起こりましたか?
8 世紀は西暦 701 年から 800 年までの期間を指します。この世紀は唐代中期で、李唐の復興から...
『射雁英雄の帰還』では夜露厳のキャラクターはどのように描かれていますか?
夜鹿炎は夜鹿斉の妹です。夜鹿斉は全真宗の「悪童」周伯同から真の教えを受け、高い武術の腕を持っています...
関羽は西遊記に出てきますか?西遊記の関羽とはどんな神様ですか?
西遊記に関羽は登場しますか? 西遊記の関羽とはどんな神様ですか? 興味のある読者は編集者をフォローし...
「彭公事件」第31章:黄三台は法務省に連行され、裁判にかけられ、皇帝から杯を探す許可を得た。
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『破陣詩 家族と国家の四十年』の執筆背景を教えてください。どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】 40年間、私の祖国と私の家族、3000マイルの山々と川。鳳凰楼と龍の塔は天に届き、玉...
「長湘思雲易沃」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
愛への憧れ·ユン・イーウォ李嶽(五代)雲のようなリボン、翡翠のようなシャトル、薄いシルクで作られた軽...
春秋時代の五大覇者とは誰ですか?
春秋時代の五覇とは、斉の桓公、宋の襄公、晋の文公、秦の穆公、楚の荘王を指します。斉の桓公斉の桓公は、...
『紅楼夢』の「少女」という言葉にはどのような意味がありますか?
皆さんご存知の通り、『紅楼夢』には娘が最も多く登場し、「少女」という名前が最も多いです。では、「少女...
羅斌王の生涯における最高傑作は何ですか?千年にわたる驚異
今日は、Interesting Historyの編集者が羅斌王に関する記事をお届けします。ぜひお読み...
辛其の最も古典的な詩は、人々に突然気づかせる
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が辛其記につい...
諸葛亮の死後、平民に降格された李厳はなぜ怒りで死んだのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
馮延舒の『菩薩男:深紅の扉と横金の錠』はどのような感情を表現しているのでしょうか?
以下に、Interesting History の編集者が、Feng Yansi の「菩薩人・陳陳珠...
『新世界物語・方正篇』第43話の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの有名な学者の言葉、行為、逸話を記録していま...