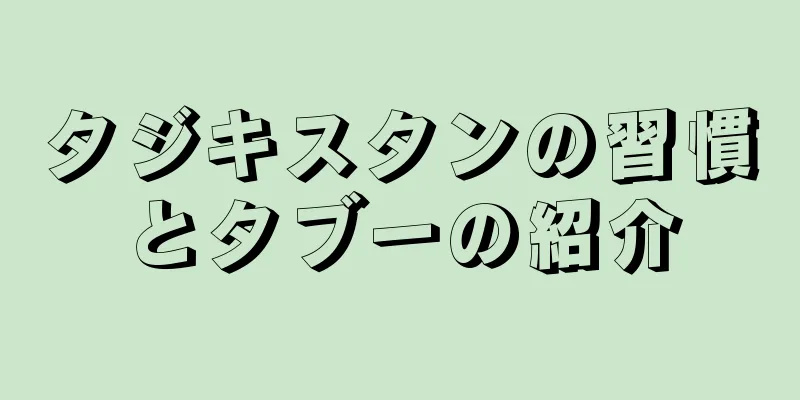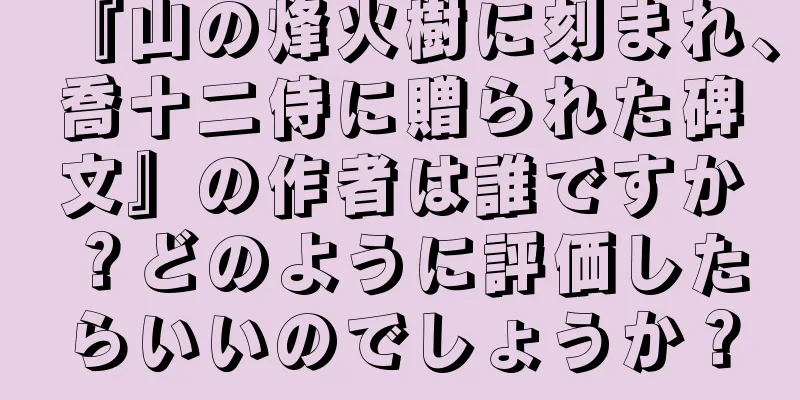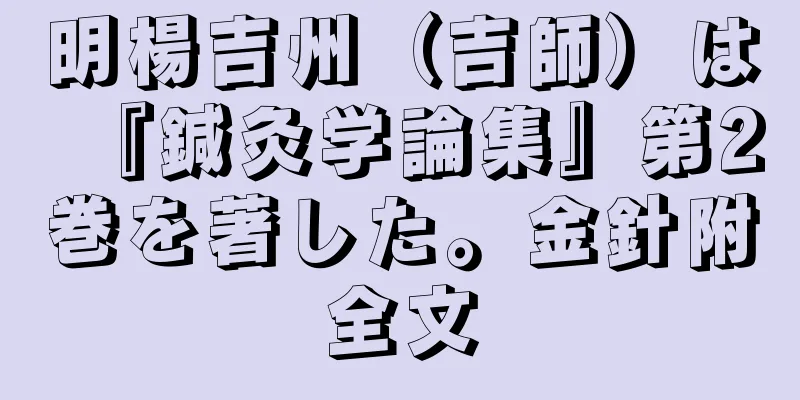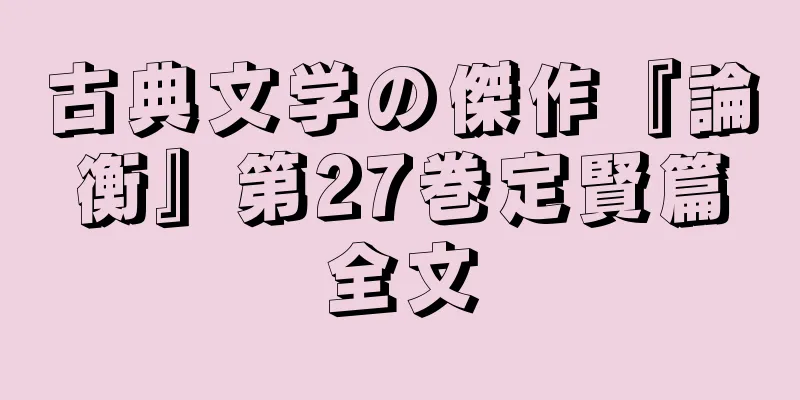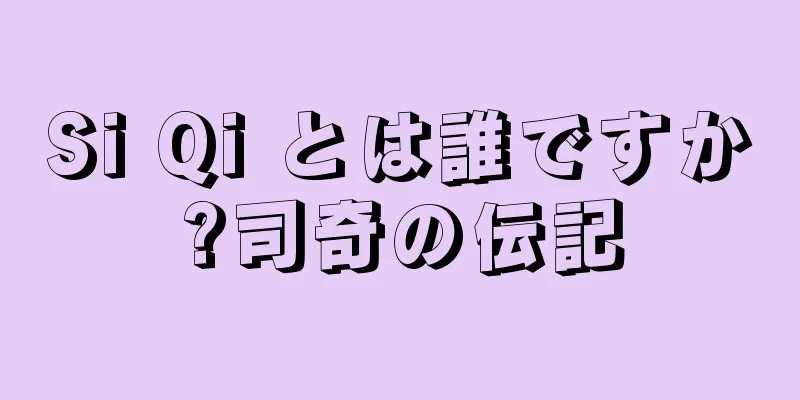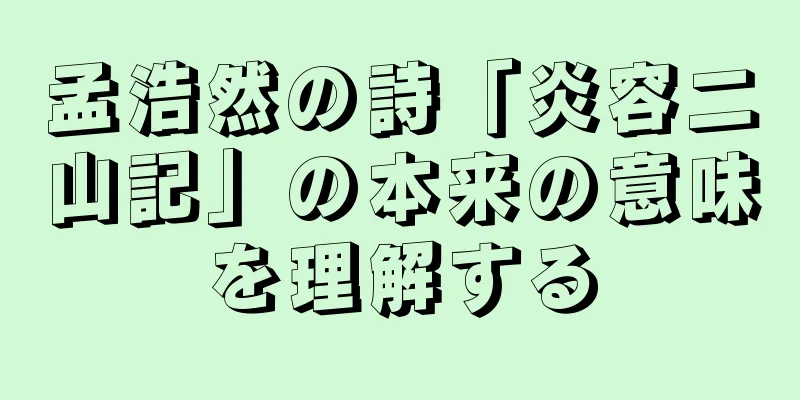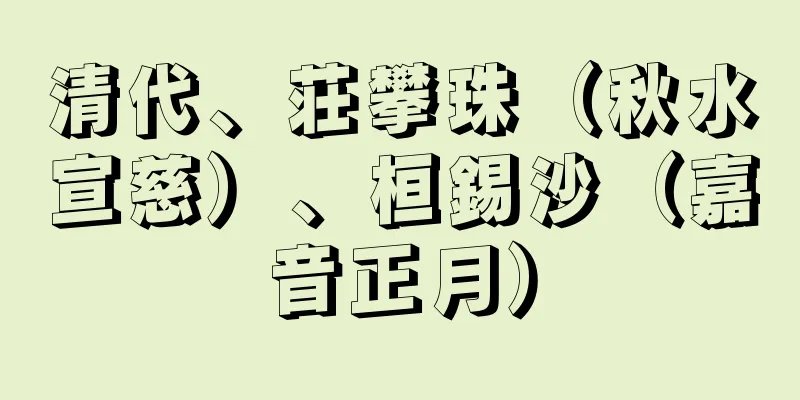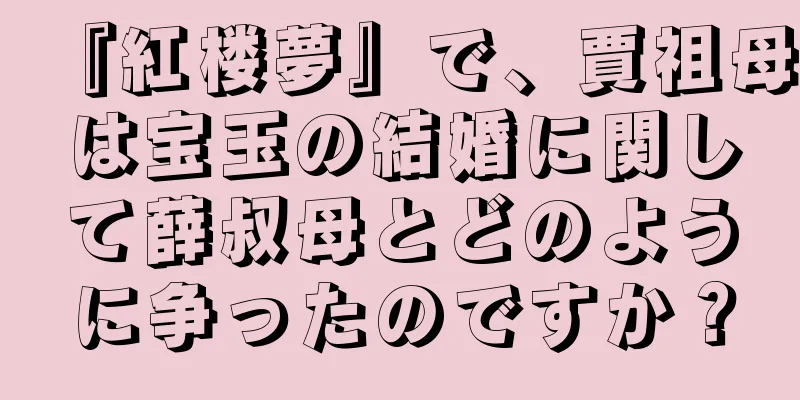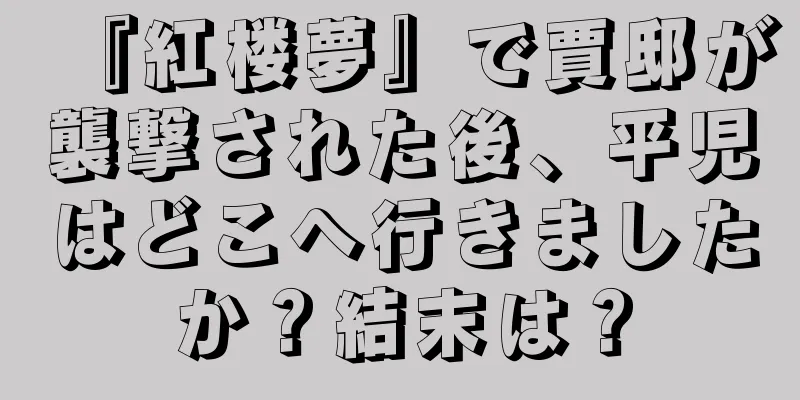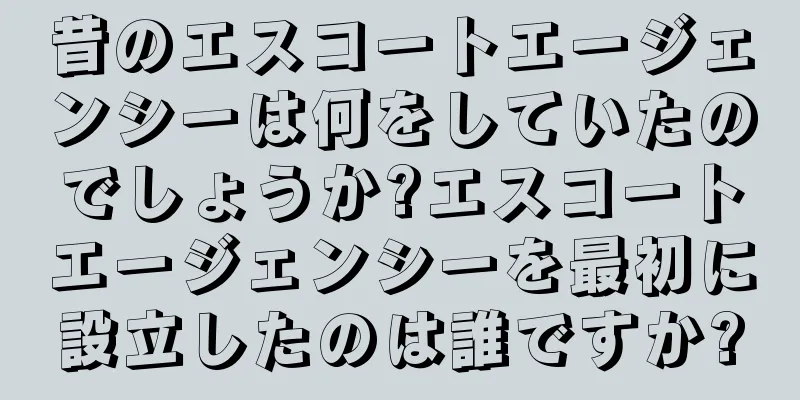なぜ宋代は近代化の入り口に入ったと言えるのでしょうか?
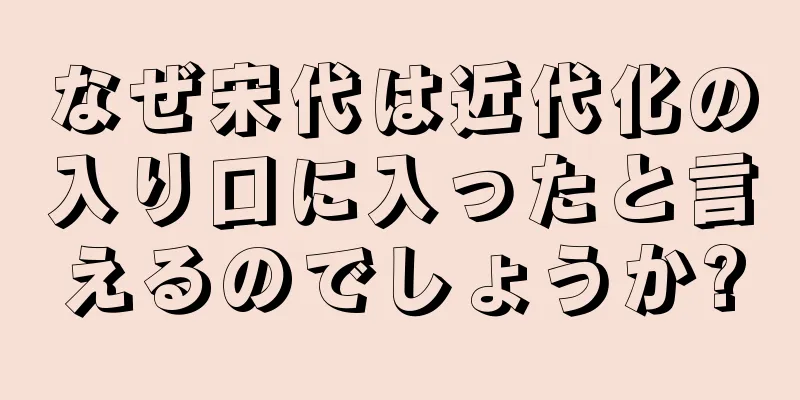
|
はじめに:宋代の国家は「スーパービジネスマン」の役割を果たしたと言える。リベラル派はこれを嘲笑するかもしれないが、歴史的に言えば、現代の商業エンジンは国家の力なしには始動できない。朱元璋が樹立した明の政府のような、商業の発展に無関心で何もしない政府は、本当に近代化の拡大に資するのでしょうか? 1つ もちろん、宋王朝が近代の始まりであると主張する海外の中国学者に盲目的に同意することはできません。宋代は本当に近代化の入り口に立ったのだろうか。近代化の基準を列挙し、宋代社会と比較してみるのも一案だろう。 社会が中世から近代に移行すると、必ず共通の傾向や特徴が現れます。以下にそれらを列挙してみます。 商品化。ビジネスは次第に繁栄し、商品経済が徐々に自然経済に取って代わりました。 市場化。商品経済の発展に伴い、市場は行政命令に取って代わり、資源を配分するための重要なメカニズムとなりました。 収益化。市場経済の発展により、通貨は市場取引の決済手段となっただけでなく、国民の税金や労働、さらには国の行政動員も通貨で決済できるようになり、黄仁宇氏が言うところの「デジタル管理」が実現した。 都市化。ますます多くの人々が田舎や土地を離れ、生計を立てるために都市に移り住み、都市住民になっています。総人口に占める都市人口の割合が増加しています。 工業化。手工芸産業が発達し、市場取引を生産目的とし、手工芸工房を生産形態とする手工芸品が出現した。 契約化。英国の歴史家メイン氏は「これまでのところ、すべての進歩的な社会の動きは『地位から契約へ』の動きである」と述べた。中世から近代化への移行の中心的な兆候の1つは、「個人的な依存」から「契約関係」への変化である。 動員。個人の依存が弱まるか、あるいは消滅するにつれて、近代化された社会では、地域間や階級間の移動を含め、移動がますます顕著になるのは必然です。 普及。特権階級としての世襲貴族は徐々に衰退し、庶民の影響力は増大し、世俗的な市民文化が栄え、最終的に民間社会が形成されました。 均等化。貴族階級の衰退と庶民階級の台頭の結果、異なる背景に基づく人々の間の地位の格差はなくなり、階級間の厳格な壁は打ち破られました。 実用的。商品経済の浸透と社会慣習の世俗的な進化により、近代化された社会では常に明白な功利主義的思想が生み出されることになります。 福祉。現代ヨーロッパの経験は、社会が商業化、都市化、流動化へと変化し始めると、必然的に大きな貧困層が出現することを示している。宗教団体がもともと提供していた救済制度はもはや社会のニーズを満たすことができず、救済の責任は強力な国家財政によって担われなければならない。 拡大。ここでの拡大とは、国の経済機能の拡大を指します。一部のリベラル派は、自由放任主義の市場経済メカニズムが自発的に近代的な経済システムの構築を促進できると信じている。しかし、これは単なる仮定であり、事実ではありません。事実、近代化の開始には常に国の重商主義が先行しており、政府によって確立された経済部門は大幅に拡大し、市場拡大の基礎を築いてきました。 集中化。国の権力構造は貴族封建制から君主制へと変化した。 「遅かれ早かれ、ほとんどすべての国は近代世界への扉を開く前に、専制君主制の段階を経なければならない。封建国家から専制体制への転換を完了できないということは、近代政治の出発点に入ることができないことを意味し、したがって、その国は近代化の第一段階で完全に失敗したことを意味する」と指摘する学者もいる。ここでの「専制」という言葉は「君主制」に置き換えたほうが正確だろう。 民生化(合理化)。王政の確立とともに、貴族の政治権力は徐々に官僚的な公務員制度に取って代わられていった。ウェーバーの見解では、公務員制度と合理化はほぼ同義語である。公務員制度の確立は国家統治の合理化を告げるものである。政治権力の分配と行使は明確な手順とシステムによって規制され、個人の意志や感情の干渉が排除される。 合法化。近代化が徐々に進むにつれて、異質な人々で構成される複雑な社会と複雑な統治システムが形成されました。知り合いの関係、慣習、道徳観だけでは、この複雑さに対処するのに十分ではなくなりました。そのため、国家は時代の変化に適応するために、より複雑な法律を作成する必要があります。 そこで疑問になるのが、経済の変化、社会の変革、政治の構築を伴うこれらの近代化の指標は宋代に同時に現れたのか、ということです。はい、同時に現れました。 二 宋代は、漢代初期に続く商業繁栄の時代であった。商業化の波は宋代全土に広がり、「商業はより緊迫し、商人の商売はより重要になった」。宋代の人はこう言いました。「お金を持っている人のほとんどは、そのお金で家を建てたり、家を質に入れたり、船で商売をしたりします。どうしてそのお金を遊ばせておいて、金を買って家に保管しておくことができるでしょうか。」宋代の人々は、余剰金が手に入るとすぐにそれを投資に回しました。一部の中国学者は、「宋王朝時代に真の商業革命が起こった」とさえ主張している。 「ビジネス革命」と呼ばれる以上、確かに革命的な経済パフォーマンスが求められます。宋代には経済に革命的な変化が起こりました。 ——「土地制度が確立されていない」、つまり国家が完全な私有財産権を認めている(中唐以前は均田制が実施され、財産権の自由取引が制限されていた)。 ——農業生産性は革命的な向上を遂げ、特に早生米品種の導入や耕作地再開発技術の推進により、同じ面積の土地でより多くの人々を養えるようになり、より多くの余剰人口と農産物を土地から抽出し、都市や産業、商業に流入させることが可能になった。 ——もともと商業の自由を制限していた市場制度は宋代に完全に崩壊し、街頭市場制度が形成され始めました。「大通りから小さな路地まで、大小さまざまな店が戸口に並び、空き家はありませんでした。毎朝、通りや路地の戸口に何百もの市場が開かれ、商売は賑わっていました。」宋代以前には、これは考えられないことでした。 ——海外貿易が非常に盛んで、当時、宋代の海岸線は、北は膠州湾から、中央は杭州湾、福州、漳州、泉州の黄金三角地帯、南は広州湾、そして瓊州海峡まで、すべて外界に開かれており、西洋や東南アジア諸国との貿易が発展していました。シボシ(税関)は海上貿易から毎年200万連近くの銭を税金として徴収し(明代の「龍清開港」以降、税関は毎年数万両の銀しか徴収しなかった)、輸出入貿易総額は2000万連を超えた。 ——商業信用が非常に発達し、北宋から南宋にかけて、便宜貨幣(銀行手形に類似)、現金受取証(現金小切手に類似)、茶証、塩証、香薬証、明礬証(証券に類似)、餃子、会子(法定通貨)などの商業信用が次々と登場しました。商業信用が発達しなければ、大規模な市場取引や地域間市場取引は不可能となるでしょう。 ——商業化の深化は国の財政・税制構造に反映され、農業税の割合が減少し、商業税の割合が増加した。南宋の春熙・紹熙期には、非農業税による財政収入が85%近くに達し、農業税は微々たるものになった。これは中国史上前例のないことだ。清朝末期の19世紀、文明開化運動を経て、ようやく清朝政府の地租の割合は48%にまで下がった。 宋代における商業化の発展は、市場化が継続的に深まる過程でもあった。市場化とは、人々の衣食住や交通が市場を通じて解決されるということだけを意味するのではない。宋代には江南地域の多くの農民が基本的に農業をやめ、「商人に頼って生計を立てる」ようになった。さらに、国は行政命令方式を放棄し、市場メカニズムを採用して政府の消費財を入手し、公共物資を分配し、さらには経済制裁の脅しを使って近隣諸国との平和を維持した。 宋代には貨幣化の傾向も顕著であった。宋政府は民間の取引に応じるために毎年膨大な量の貨幣を鋳造しなければならなかった。北宋時代の年間最高鋳造量は570万連銭で、平年は100万~300万連銭の間で維持されていた。明朝の約300年間に鋳造された貨幣の総量は、宋の人々がわずか2年で鋳造した量である。 宋代の人々はなぜ大量の貨幣を鋳造しなければならなかったのでしょうか? それは貨幣化の時代のニーズを満たす必要があったからです。市場取引が通貨で決済されるだけでなく(自然経済の時代には物々交換も可能だった)、役人や従業員の報酬も通貨で支払われなければならなかった。宋代以前は、賃金は主に現物で、通貨はわずかな割合を占めるに過ぎなかった。宋代の国家税も、主に現物から主に通貨に移行した。北宋治平2年(1065年)、宋政府の通貨収入の割合は50%を超えた。王安石の改革では、強制労働も通貨決済に変更され、通貨化が一般的な傾向になったことが示された。 宋代の都市化にも革命的な特徴があり、都市人口の割合はすべての王朝の中で最高レベルに達した。北宋時代には都市人口が全体の20.1%を占め、南宋時代には22.4%に達した。佐々木吉信氏によれば、南宋時代の最盛期には都市化率が30%に達した可能性があるという。清朝中期(嘉慶年間)の都市化率は約7%で、中華民国時代には約10%に上昇しました。1957年までに都市化率はわずか15.4%でした。そのため、一部の研究者は宋代に「都市革命」が起こったと主張している。 一部の歴史家は、「原始的な工業化」は宋代に出現したと考えています。宋代の「原始的工業化」の最も優れた例の一つは鉄の生産である。大規模な炭鉱の採掘と鉄の製錬への応用により、北宋代の鉄の生産は飛躍的な発展の勢いを見せたが、イギリスでは16世紀の初期の工業化まで同様の「石炭と鉄の革命」は経験されなかった。大量の科学技術が手工芸品の生産にも応用された。英国ケンブリッジ大学のジョセフ・ニーダム博士は「中国の科学技術は宋代までに頂点に達し、多くの面で18世紀半ばの産業革命以前の英国やヨーロッパのレベルを実際に上回っていた」と述べている。 三つ ここまでは、宋代の近代化を経済変革の観点から説明してきました。次に、宋代を社会変革の観点から見てみましょう。 唐代と宋代には、中国社会に非常に大きな変化が起こった。唐代には、貴族の家に代々土地を耕作し、独立した戸籍を持たない農奴がいた。唐代の奴隷は独立した法人格を持たず、独立した戸籍を持たず、主人に依存する賤民であった。宋代以降、貴族の家の解体に伴い、農奴も賤民も自由民となった。宋代には、借地人と地主の間にはもはや人間的な依存関係はなく、両者の自発的な結びつきに基づき、契約によって証明される経済的な借地関係のみが存在した。宋代における奴隷と主人の関係は個人的な依存関係ではなく、経済的な意味での雇用関係であり、両者間の自発的な契約に基づいていました。このような社会構造の変化の核となる意味は「契約化」、つまり「個人的な依存」から「契約関係」への変化です。 この契約プロセスは平等化のプロセスでもあります。宋代以前は、戦士であろうと奴隷であろうと、彼らは皆不可触民であった。しかし、宋代にはこれらの不可触民は基本的に姿を消した。つまり、かつての不可触民は自由民の地位を獲得し、平等な法的地位を持つ国の「登録公民」となった。「平等とは平等である。貴族と賤民の区別はなく、彼らは皆平等な公民と呼ばれる。」 貴族社会の終焉は民間社会の到来を告げるものである。宋代以前は、政治は貴族によってほぼ独占されていました。唐代には科挙制度がありましたが、科挙を通過した平民官僚はほんの一握りでした。宋代になると状況は一変した。学者は家柄に関係なく選ばれるようになった。「政治の上層部に昇進したのは、すべて平民の出身で、どこからともなく出世した学者だった。古代の封建貴族や家系の伝統は残っていなかった」(銭牧の言葉)。南宋の保有4年(1256年)の『科挙録』の学者の統計によると、宋代の進士601人のうち、417人が平民の出身で、184人が官吏の子息であり、進士の大半は賤民の出身であった。 宋代には民間社会の代表として、教育、文化、芸術の分野にも明確な民衆色が見られました。宋代以前は貴族が独自の教育資源を持っていたが、宋代の学校は一般大衆に開放されており、「商人や雑多な人々」の子供たちも郡立学校に通うことができた。宋代以前は、文学、音楽、美術はすべて上流階級の趣味でした。宋代になって初めて、俗語小説や喜劇など、完全に庶民(市民)に属する文学や音楽の形式が登場しました。宋代以前の芸術作品には、庶民の痕跡はほとんど見当たりません。『踏歌』や『清明上河図』などの宋代の絵画を広げて初めて、庶民と市場の雰囲気を感じることができます。 同時に、個人の依存がなくなったことで、宋代社会では流動性が広範かつ持続的に高まった。この流動性には、地理的な意味での水平的流動性(つまり、人々は自由にある場所から別の場所へ移動できる)と、階級的な意味での垂直的流動性(つまり、硬直した階層構造が崩れ、誰もが自分の努力で昇進する機会を得られる)の両方が含まれていた。 宋代の人々は、「昔は、人々は故郷で同じ田畑や井戸を共有し、土地に愛着を持って移動を嫌がりました。遠くに追放されれば、生活の糧がなく、一生屈辱と苦難に耐えなければなりません。現代では、人々が故郷を離れて四方八方に移住することは少なくなり、もはや問題ではありません」ということを発見しました。ここでの「現代」とは、もちろん宋代のことです。現代の言葉で言えば、宋代の人々は「自由な移住」の権利を持っていた。 宋代の人々はまた、「先王の制度によれば、貴族は最初に富み、賤民は富まなかった。富める者と貧しい者、貴族と賤民は4つの区分に分けられ、それは後の世代に生じた」ということを発見した。ここでの「後の世代」も宋代を指している。 「貧富貴卑が四分する」とは、宋代からこの四つが自由に組み合わさるようになったこと、すなわち、貧者は富めることも高貴になることもでき、卑者は高貴にも富むこともでき、富者は高貴にも卑しむこともでき、高貴な者は富むことも貧しむこともでき、富者、貧者、高貴、卑しいは変化し続ける状態にあることを意味する。現代社会学の観点から言えば、社会階級は「固定化」されていません。だからこそ社会は活性化するのです。 社会全体の構造転換と商品経済の徹底的な発展は、宋代の社会雰囲気にも大きな変化をもたらした。人々はもはや利益について語ることを恐れなくなった。「誰もが金持ちになりたい。農民、商人、職人は皆、利益を求めて昼夜を問わず働く」。富の追求は当然のこととなった。物質主義、消費主義、享楽主義が蔓延しています。この功利主義的な世界観は、宋代、明代後期、あるいは現代の西ヨーロッパの都市など、資本主義時代の初めに一般的に見られた社会現象です。 4つ さて、国家統治機能の構築の観点から宋代の近代化の成果を見てみましょう。 研究者たちは、16世紀のヨーロッパで経済構造が封建主義から資本主義に移行した際に、経済の不均衡により都市部に貧困層が大量に発生するという特徴が生まれたことを発見しました。近代ヨーロッパ諸国が徐々に展開した福祉政策は、この経済構造の変化に対処することを意図したものでした。英国も近代化が始まった16世紀後半に一連の「救貧法」を制定し、政府が貧困者救済の責任を引き受けた。中国の国家福祉制度も宋代に頂点に達した。この「福祉」という国家機能の出現は偶然ではなく、近代化によって生じた圧力の結果であった。 宋代の貧困救済は主に二つの制度から成っていた。一つは宋の神宗皇帝の治世中の熙寧十年(1077年)に施行された「乞食扶助法」である。毎年10月の立冬後、各州政府は「役人を派遣して国内外の老人、病人、貧乏人、自立できない人を検査し」、一人当たり「一日に米と豆一升、子供にはその半分」を与えた。宋人の「乞食」の定義は現代とは違っていた。乞食の範囲にはすべての貧困者が含まれた。その一つは宋哲宗の元福元年(1098年)に公布された「養老法」である。各州に養老院が設けられ、「寡婦、孤児、孤独な人、貧乏人、自活できない人は官舎に住み、毎月米と豆を与え、病人には薬を与える」とされていた。簡単に言えば、「乞食扶助法」は政府が貧困者に米とお金を配ることを指し、「養老法」は国の福祉機関が住む場所のない貧困者を受け入れることを指す。 近代化の課題に対応するために、国家は福祉機能を発展させるだけでなく、課税、借入、投資、市場開発、市場規制、ビジネスルールの策定、市場秩序の維持など、経済活動に深く介入する必要があります。これは、重商主義の下での国家の経済機能の拡大です。宋代は歴史上最も重商主義的な王朝であったことは疑いようがない。政府は市場経済に参加するために、海関、塩井監督、娑甸局(不動産会社)、九屋(醸造所)、曲院(麹を作る工房)、造船局、紡績局、染色局、製粉所(穀物加工工場)、茶墨(茶加工工場)など、多数の経済部門を設置した。金融機能を持つ経済部門には、専売局、便利貨幣局、餃子局、市場交換局、清廟法、建秀財務局、質屋などがあった。 宋代の国家は「スーパービジネスマン」の役割を果たしたと言える。リベラル派はこれを嘲笑するかもしれないが、歴史的に言えば、近代商業のエンジンは国家の力なしに始動することはできない。朱元璋が樹立した明の政府のような、商業の発展に無関心で何もしない政府は、本当に近代化の拡大に資するのでしょうか? おそらく、資本主義の台頭における国家の重商主義政策の重要性を示す例がある。宋代は河北路と京東路で塩の自由貿易制度を実施し、他の地域では塩の許可制度(間接的な国家独占)を実施した。論理的に言えば、塩の禁止は民間商品経済の発展を妨げ、資本主義の出現を遅らせるはずだった。しかし、学者の研究によると、宋代の塩自由貿易区では「生産技術の進歩や革新はなく、生産規模は拡大せず、塩商人の資本成長率は速くなく、特に裕福な塩商人はいなかった」という。対照的に、塩導入制度が実施された制限地域では、「生産技術と工程に明らかな改善と革新が見られ、井戸塩生産において新しい生産関係の芽が生まれつつあるようだった。紙幣導入制度が実施された南東部の塩地域では、大手塩商人が富を得るのが見られた。」 近代化の発動と発展は国家権力の支えと切り離せないからこそ、中央集権化を完成して初めて国家は近代化を成功させることができるのである。これは、先に近代化したヨーロッパ大陸やイギリスと、後から近代化した日本が示している。対照的に、中国の中央集権化は非常に早く完了しました。秦王朝は郡制を確立し、君主制の到来を告げました。早すぎる中央集権化は必ずしも歴史の流れに沿うものではなく、魏晋の時代には貴族制が復活し、南北朝、隋唐の時代には貴族階級が形成された。唐・宋の時代以降、「君主独裁」の政治体制が完全に確立されました。 ここで言う「君主独裁制」とは、貴族制とは対極にある政治体制、つまり政府機関が皇帝の直接指揮下に置かれることだけを指し、君主が何の制約もなく独断で決定を下せるという意味ではないことに注意する必要がある。逆に、宋代は「名目上の君主との共同統治」制度を形成し、君主は「命令を発する」が「すべては宰相の慎重な審議に委ねられる」、つまり宰相が国家統治の具体的な権限を握っていた。政府の命令が「不適切」であれば「検閲官が弾劾する」、つまり検閲官は宰相の統治権を牽制し均衡させるための監督・審査権を握っていた。与党、検閲官、君主の3つの権力は比較的独立しており、「それぞれが自分の専門を持ち、互いに侵害することはできなかった」。 中国の官僚制度も郡制の確立と同時期に早くから確立されていたが、官僚制度が十分に合理的に発達したのは宋代になってからであった。合理化は公務員制度の核心的な意味であり、公務員の分類、職能、試験と採用、評価、賞罰、訓練、昇進、異動、解雇、権力命令の発動、伝達、審査、執行、フィードバック、説明責任など、すべてに完全なシステムと手順があり、それによって私的要因の影響を可能な限り隔離します。束縛を嫌う皇帝は、官僚制度を打破したいという衝動に駆られる。例えば、前漢の武帝は、宦官、侍従、親族、尚書(皇帝の個人秘書)などの側近や大臣で構成される「内廷」を使用し、三官が率いる「外廷」を脇に置いた。明朝は単に宰相を廃止し、「内閣」を設置したが、これは実際には皇帝の秘書チームであった。 300年以上続いた宋代に限って、官吏制度を破壊する「内廷」は存在せず、官吏制度の運用は非常に安定していた。 現代の統治秩序には、法の支配というもう一つの特徴があります。今日のほとんどの人は、「法治」は西洋の産物であり、中国の統治の伝統は「人治」であると信じているが、宋代の人々はそうは考えていなかった。彼らは自らを「法を遵守する人々」と称した。南宋の思想家である陳良と葉舒は次のように要約している。「漢は人を頼りにする王朝であり、唐は人と法を頼りにする王朝であり、わが王朝は法を頼りにする」「祖先が天下を治めるとき、物事の大小に関わらず、すべて法に従った」。いわゆる「法を頼りにする」「法に従う」とは、現代の用語で言えば「法によって国を治める」という意味である。 宋代の法制度の複雑さは、多くの人の想像を超えているかもしれない。宋代の学者、葉石はこう述べている。「現在、国内外を問わず、どんなに小さな事でも、どんなに軽い罪でも、それに対処する法律があらかじめ用意されている。人々は一生の知恵を尽くして一つの知恵を出し、それがとても斬新だと思うが、法律はすでに用意されている。これが法律の秘密である。」賢い人は一生の知恵を尽くして一つの法律を出し、それが斬新だと思うが、法律集を調べてみると、同じような法律がすでに制定されていることに気づく。 これらの複雑な法律には、民事法と商事法が含まれます。宋代の民事法と商事法は非常に完全でした。これらの複雑な法律には、民事法と商事法が含まれます。宋代の民事法と商事法は非常に完全でした。私的賃貸、抵当、質入れ、売却、融資、財産相続はすべて包括的な法律によって規制されていました。宋代の人々は「官規の中で、取引に関する規定が最も詳細である。おそらく争いを防ぐためだろう」と語っている。民事法と商事法が発達していたことから、宋代にはすでに「法の近代化」の兆しが見られたと考える研究者もいる。 近代化の特徴に関する上記の要約と宋代の近代化の実績の説明に同意するならば、宋代の中国は確かに近代化の境界に足を踏み入れていたことを認めるべきである。 (ウー・ゴウ) (この記事は著者の新著『宋代:近代の夜明け』の序文からの抜粋です。『宋代:近代の夜明け』は2015年9月に広西師範大学出版局から出版されました) |
>>: 楊寛の紹介:南梁の有名な将軍、楊寛はどのように亡くなったのでしょうか?
推薦する
孫悟空はどれくらい大きいですか?西遊記で釈迦が仏陀になった後の実際の年齢
孫悟空は仏典を求める旅の途中で怪物に遭遇するたびに、「私は500年前に空で大騒ぎをした天に等しい大聖...
『観瓦宮の追憶』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
観和宮の郷愁皮日秀(唐代)美しい骨組みは塵と化したが、宮殿の壁は崖と同じくらい厚いまま残っている。金...
平原趙勝の家臣、毛遂とは誰ですか? 戦国時代の毛遂はどこの出身ですか?
茅遂は戦国時代の趙の人です。遅咲きの人物だったと言えます。趙の趙王の家臣として3年間仕えましたが、重...
『紅楼夢』では、希仁が母親を喪っている間に、青文はどのようにして権力を握ったのですか?
『紅楼夢』の青文は宝玉の側室の地位をめぐって争う気がないように見えたが、本当に誘惑されることはなかっ...
成功か失敗かに関わらず、トルイがカーンになるべきかどうかを議論しましょう。
中国の歴史には優れた軍事戦略家が数多くいる。彼らを年功順に並べると、チンギス・ハーンは間違いなくトッ...
鍾馗の神格化三部作:植物から神へ
はじめに:鬼節は、一般的に鬼節として知られ、グレゴリオ暦では 8 月 10 日、太陰暦では 7 月 ...
第55章:華元はベッドに登って息子を奪い、老人はカン・ドゥ・フイに草の結び目を結びました
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
明らかに:孔嘉とは誰ですか?孔嘉の夏に対する反乱はどうなりましたか?
孔嘉は布江の息子で、夏王朝の第14代君主であった。彼は在位31年の後に亡くなり、北京市延慶県の北東に...
黄庭堅の『王崇道が五十本の水仙を贈った』:作者の自由で気楽な詩が表現されている
黄庭堅(1045年6月12日 - 1105年9月30日)、字は盧直、幼名は聖泉、別名は清風歌、善宇道...
西遊記で孫悟空を捕まえるために白黒無常が派遣されなかったのはなぜですか?
中国の神話では、地獄の王が遣わした2人の幽霊の使者(1人は太っていて1人は痩せていて、1人は白くて1...
『文心语龍』第16章の原文は何ですか?
元朝初期は年月が長く、歴史は果てしなく続いていました。私たちは今を生きながら、過去を知ることができる...
古代人は、「三度の犬の日」は悪霊によって引き起こされると信じていました。つまり、彼らは犠牲として犬を殺し、その食べ物を分け合ったのです。
「最初の土用の丑の日に餃子を食べ、2番目の土用の丑の日に麺を食べ、3番目の土用の丑の日に卵でパンケー...
「竹枝二歌第一番」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
竹の枝の詩二首黄庭堅(宋代)浮雲は百八回循環し、夕日は四十八回輝きます。地獄の門は遠いなどと言わない...
清朝において黄色い上着は何を表しているのでしょうか?それは、この人物が皇帝に非常に寵愛されていることを意味します。
馬褂はもともと満州族特有の民族衣装で、ゆったりとしたデザインは乗馬や狩猟に適しており、日常生活でも着...
詩人李清昭の深い愛への憧れを描いた「切り梅の花:秋の紅蓮の葉と玉マットの香り」鑑賞
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...