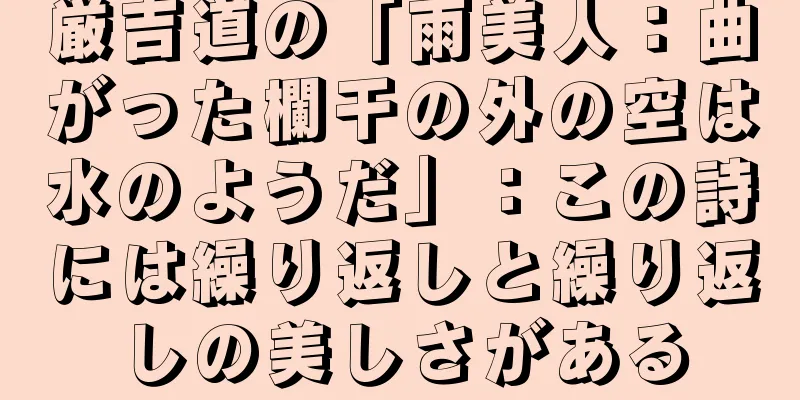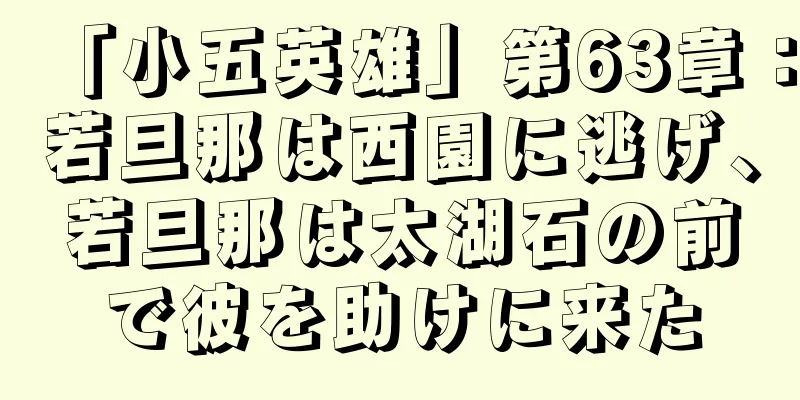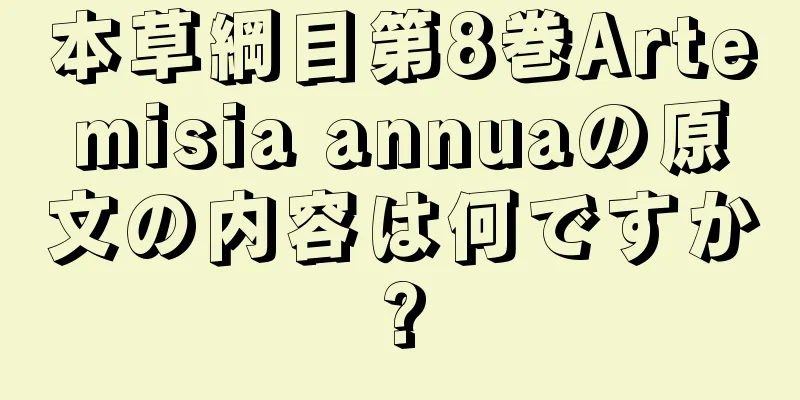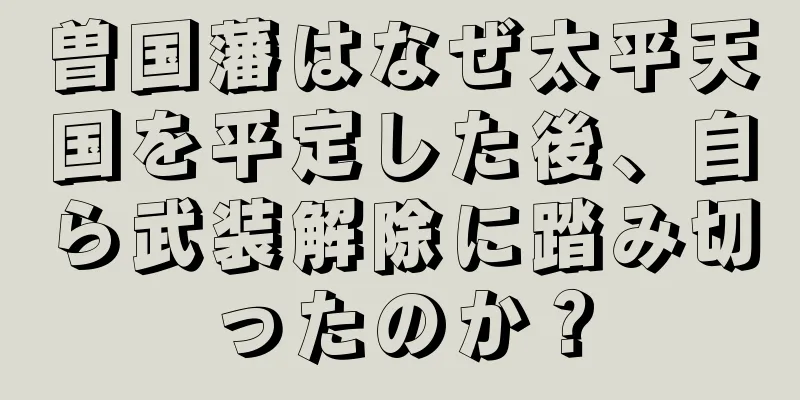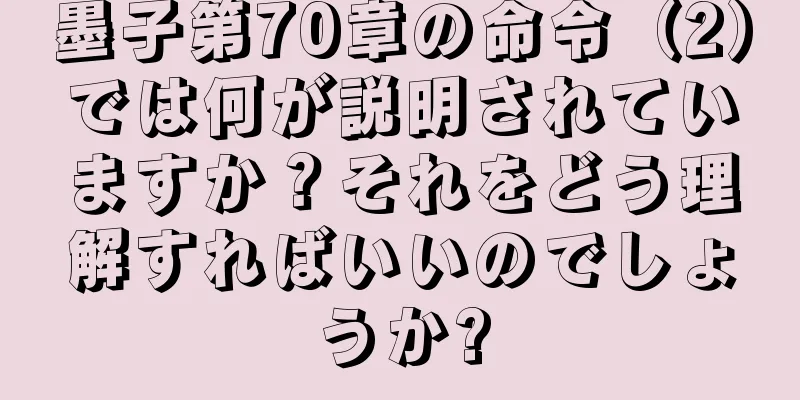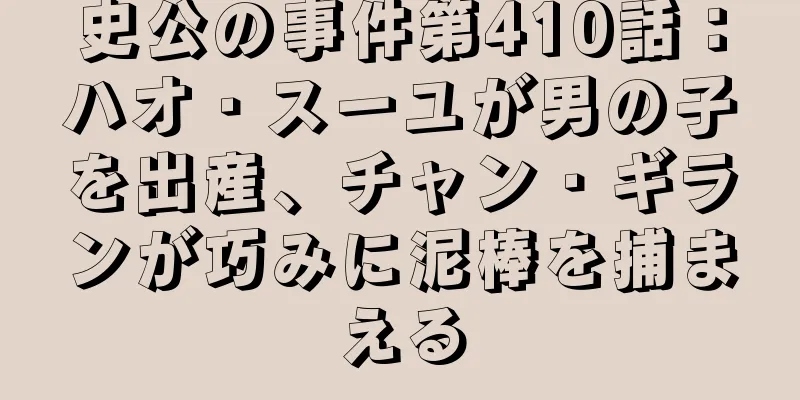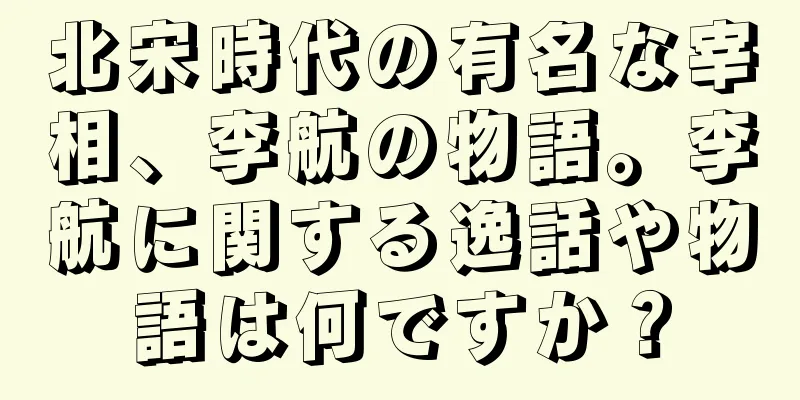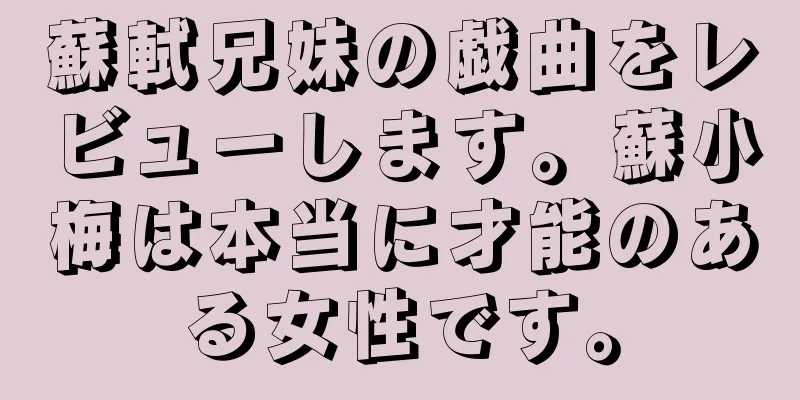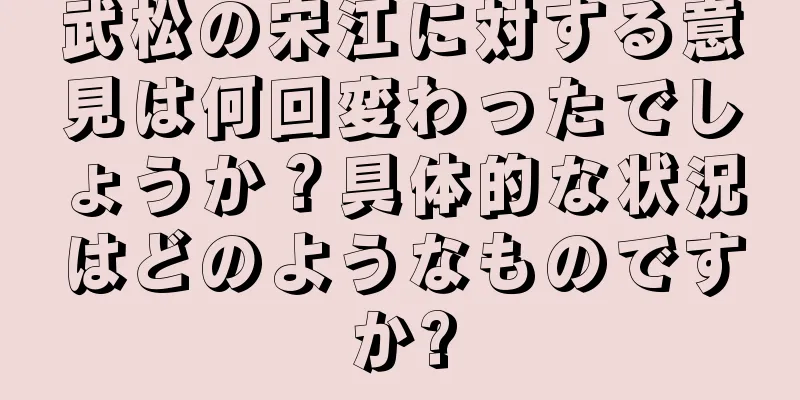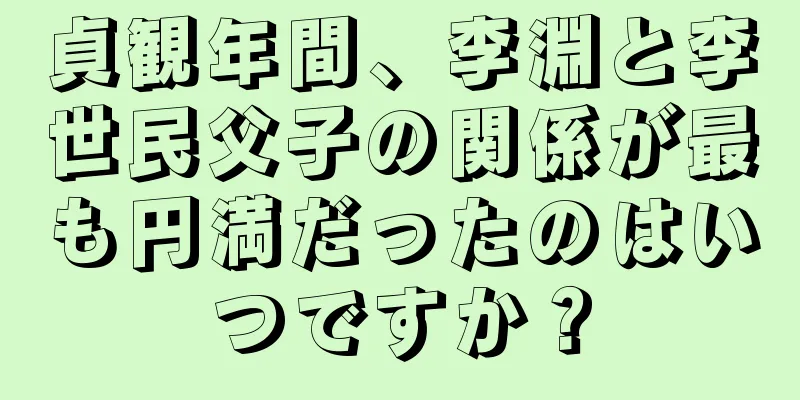遣唐使は中国から何を学んだのでしょうか?
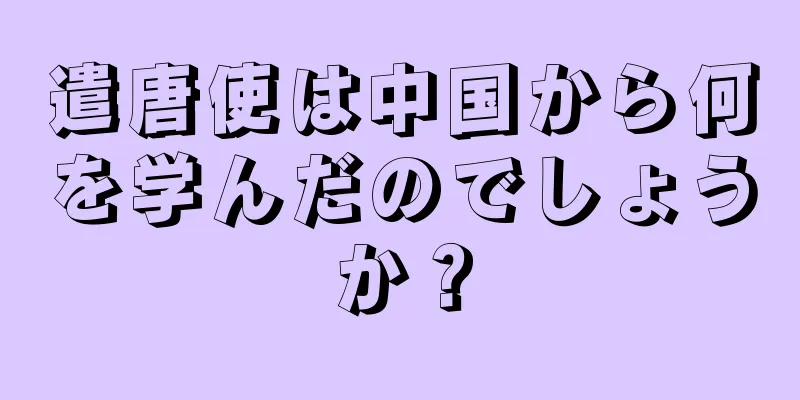
|
唐代は日中関係史上最も友好的で緊密な時代の一つであった。両国は正式な外交関係を結び、両国政府は互いに使節を派遣した。日本の学者の中にはこの時代を「遣唐使時代」と呼ぶ者もいた。 日本の推古25年(西暦617年)、中国の隋王朝は滅ぼされ、唐王朝が建国されました。これまで、福田氏のような日本から隋に派遣された留学生は次々と帰国し、自らの目で見たものをもとに、「大唐」の文化やその豊かな社会、そして法の完成などを精力的に推進した。これにより「遣唐使」が派遣されることになった。日本の遣唐使派遣の主な目的の一つは、中国に留学生を派遣して文化、宗教、法律、教育などを学ぶことであった。簡単に言えば、中国の生活で使われる食べ物や飲み物を含め、中国の良いものをすべて日本にコピーすることを意味します。 遣唐使は、日本が中国の唐王朝に派遣した使節です。日本は630年の最初の派遣から894年の派遣中止まで、約270年間にわたり計19回の遣唐使を派遣した。しかし、さまざまな理由により、実際に遣唐使が唐に来た回数は合計13回だったと言われています。日本が派遣した外交使節団には、大使、公使、留学生、海外僧侶、随行員などが含まれており、その数は一回につき数百人に達することも多かった。 唐の使節が乗った大型船は「船」と呼ばれていました。遣唐使派遣には膨大な準備と費用がかかったが、日本にとって最も頭を悩ませたのは海上での事故の多発で、多数の死者と物的損失をもたらした。唐に遣わされた使節は40人以上にのぼり、そのうち少なくとも12人が海の底に沈んだと言われている。幸い沈まなかった使節も風や波による被害や死傷者は含まれていない。 唐の日本への影響は政治法、宗教文化、生産技術、社会習慣など広範囲に及んだ。かつて誰かがとても簡単にこう言いました。「日本の中世の制度は常に日本独自のものだと考えられてきましたが、唐代の歴史を見ると、その多くが唐の制度を模倣したものであることがわかります。」これは誇張ではありません。日本には今でも、名前の先頭に唐文字が付いていて中国から来たものであることを示すものが数多くあります。例:唐辛子、唐料理、唐語、唐服など。 唐は主に唐王朝を指し、唐王朝が日本に与えた影響がいかに深かったかを示しています。当時、影響力を広める手段はいくつかあったが、この任務における主な役割と専門家は、唐の使節とともに唐に留学した留学生と僧侶たちであった。中国と日本の間の文化交流における彼らの役割は極めて重要です。 交通が困難で海を渡ることが極めて危険であった時代に、日本は中国から学ぶために何度も使節を中国に派遣し、特に唐の使節を中国に渡らせることは多大な犠牲と極めて高い費用を伴いました。しかし、遣唐使によって持ち帰られた唐の文明は、日本の社会の発展に大きく貢献しました。日本の「大化の改新」は、中国の影響を受けて、唐代に留学した初期の留学生や僧侶(隋の時代に日本に派遣され、唐代初期に日本に帰国した)が直接企画し実行した大改革でした。日本におけるその重要性は、19 世紀の明治維新に匹敵するほどです。確立された天皇を中心とした中央集権的な制度、いわゆる律令制は、ほぼすべての面で唐の制度をモデルにしていました。 隋唐文化、特に唐代の文化は、学僧や留学生の流入を通じて日本に継続的にもたらされ、中国の文学、天文学や暦学、医学、儒教、中国化した仏教などが日本に大きな影響を与えました。日本は中国から多大な恩恵を受けてきた。 中国の唐の時代は繁栄と寛大さにあふれた時代でした。当時、日本の使節が中国の領土に足を踏み入れた限り、中国政府はすべての結果を負うことになったのです。唐の使節は中国と日本の間の文化交流、そして中国人と日本人の間の交流と友好を促進しました。危険を冒して何千マイルも離れた中国まで渡航した留学生の中には、吉備真備、長岡大和、大岡禅、粟田札麻呂、藤原正雄などがおり、彼らは皆、日本でその世代の有名人となった。阿倍仲麻呂(漢名:趙衡)は、李白や王維などの詩人たちと広く交流し、中国で生涯を過ごし、多くの優れた詩を残しました。 |
<<: Zang Ba はどうやって死んだのですか?歴史上、Zang Ba はいつ亡くなったのでしょうか?
>>: 太史慈の武器は何ですか?太史慈は普段どんな武器を使っていますか?
推薦する
台北の国立故宮博物院のトップ10の宝物は何ですか?富春山の住居の順位は?
台北国立故宮博物院のトップ10の宝物は何ですか?「富春山居」は何位にランクされていますか?興味深い歴...
『詩経』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
『詩経』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?これは多くの読者が気になる質問です。次に、Inte...
唐の粛宗皇帝の娘である和政公主の実の母親は誰ですか?
和政公主(729年 - 764年)は唐の粛宗皇帝李衡の三女(墓誌では次女とされているが、墓誌では和政...
カラハン朝:我が国の極西にある分離主義政権
カラ・ハン朝(カラ・ハン朝)は、古代イランの最西部に存在した地方の分離主義政権であった。全盛期には、...
盧兆林は、波乱に満ちた公務と障害を抱えながら、読むと胸が張り裂けるような絶望的な作品を執筆しました。
みなさんこんにちは。私は『Interesting History』の編集者です。陸兆麟といえば、みな...
石公の事件第318章:偽の水の怪物は敵に抵抗して捕らえられ、本物の悪魔は誰かが待っているときにのみ現れた
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
世の中に幽霊はいると思いますか?真昼間に幽霊が見えて、それで有名になった男がいました!
世の中に幽霊がいると思いますか?昼間に幽霊が見えると主張する青い目の男がいました。幽霊は賑やかな場所...
唐代全物語第10章:秦叔宝が夜に故郷に戻り、越王の誕生日を祝う
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、全68章から成り、「元湖漁夫編」と題され、略称は『唐物語』。...
劉おばあさんは賈邸に入る前にどんな人たちと会ったのですか?彼女の恩人は二人います。
Interesting History の編集者をフォローして、歴史上の本当の劉おばあちゃんについて...
賈芬の晩年の生活はどのようなものだったのでしょうか?有名な東漢の将軍、賈芬はどのようにして亡くなったのでしょうか?
賈芬(9-55)、号は君文、南陽の関邑(現在の河南省鄧県の北西)出身の漢人。東漢の有名な将軍で、雲台...
英雄物語続編第二章:劉基が人々の盛衰を論じ、太祖が天の意志に従って王位を継承する
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
明清戦争については、その勃発はどのような歴史的必然性があったのでしょうか。
明清戦争(1618年 - 1683年)は、明王朝と後金(清王朝)の間で戦われた戦争で、農民軍政権が第...
チャン族の新年の食習慣は何ですか?
チャン族が住む山間の村々は、異なる部族に属している可能性が高い。したがって、祭りは同じではありません...
孟子:李楼第11章、原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
中国の伝統文化作品の鑑賞:『禹書』易記章の原文は何ですか?
皇帝は言った。「さあ、禹よ! あなたも意見を言うべきだ。」禹は頭を下げて言った。「杜! 皇帝よ、私は...