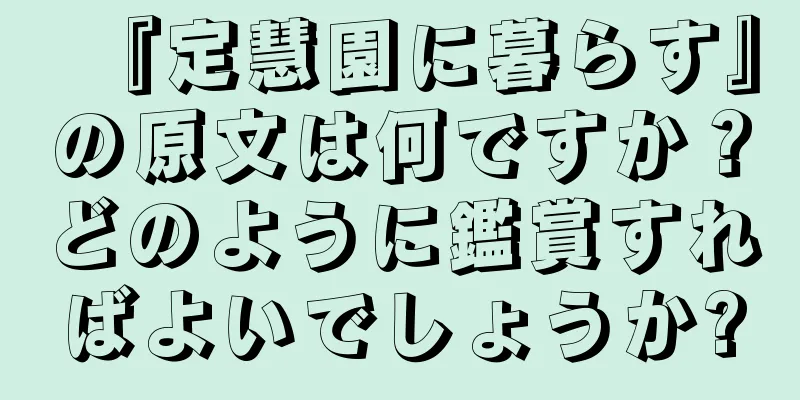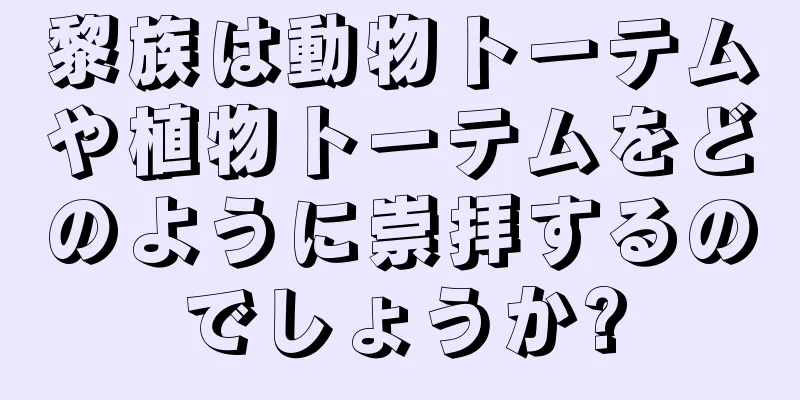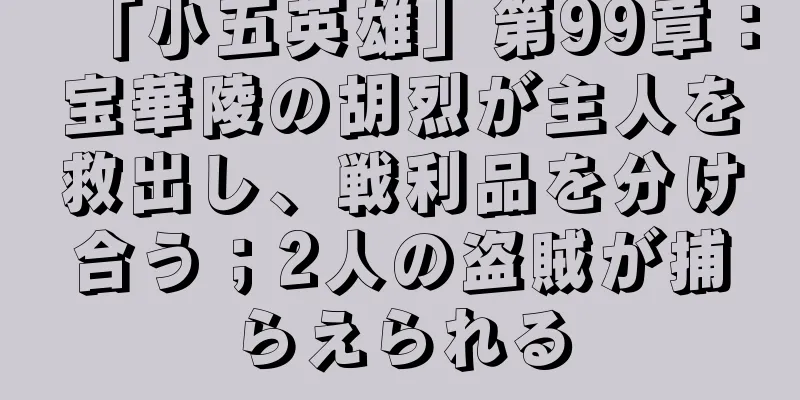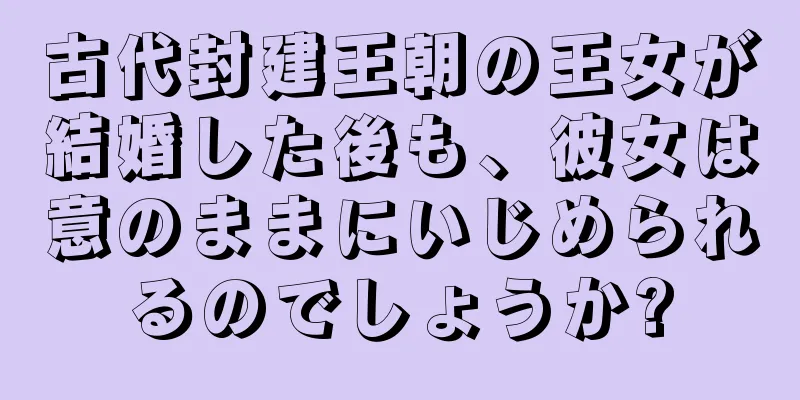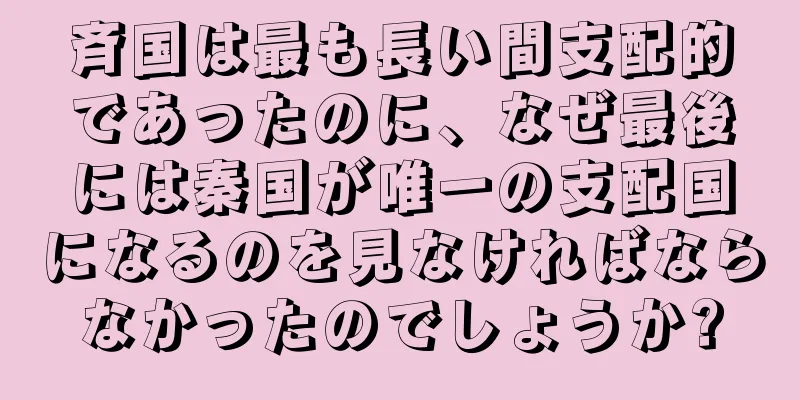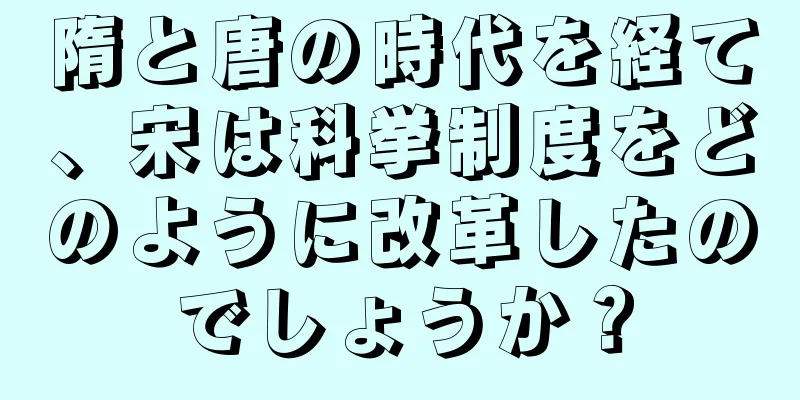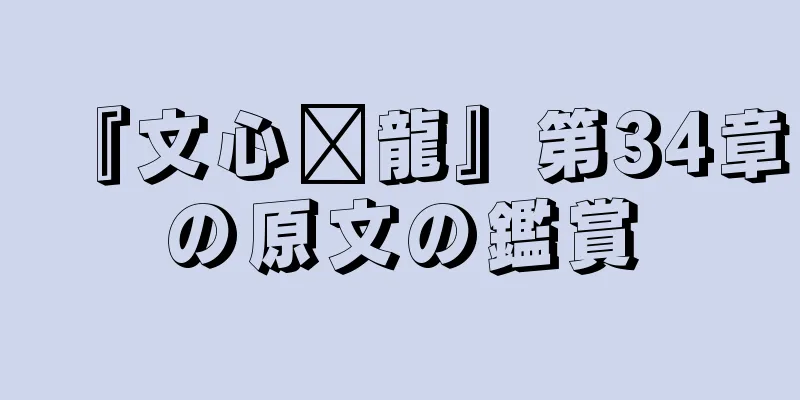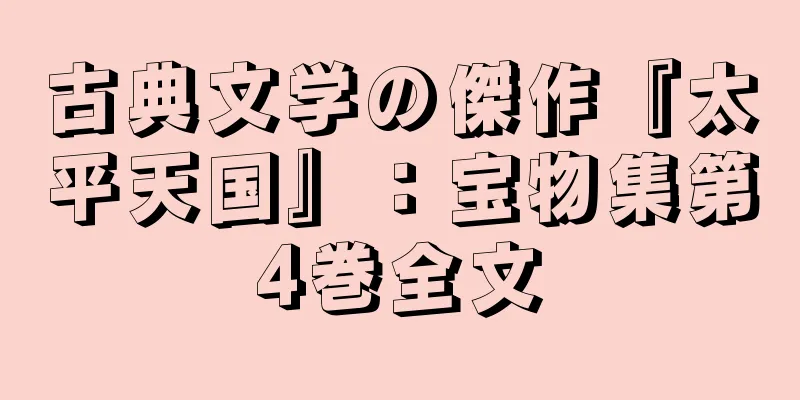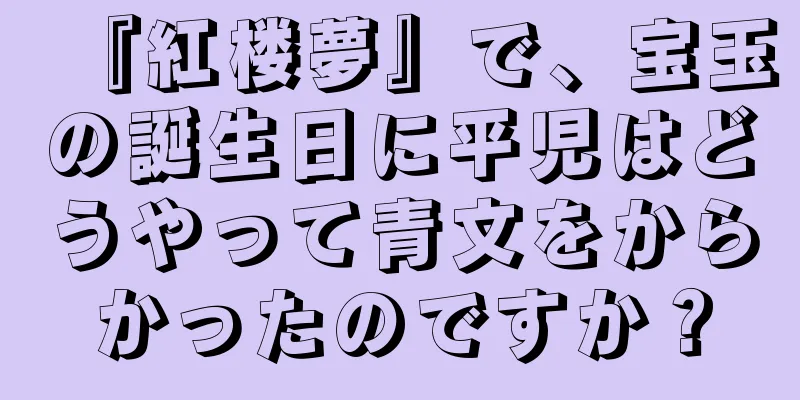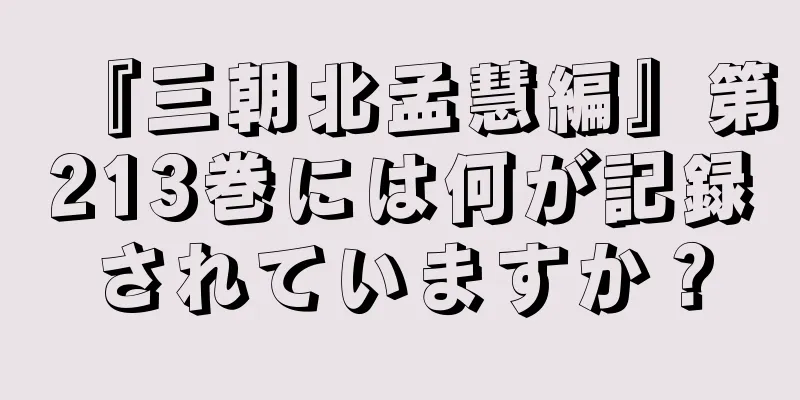古代の役人はいつ引退できたのでしょうか?退職金制度はどのように決まるのですか?
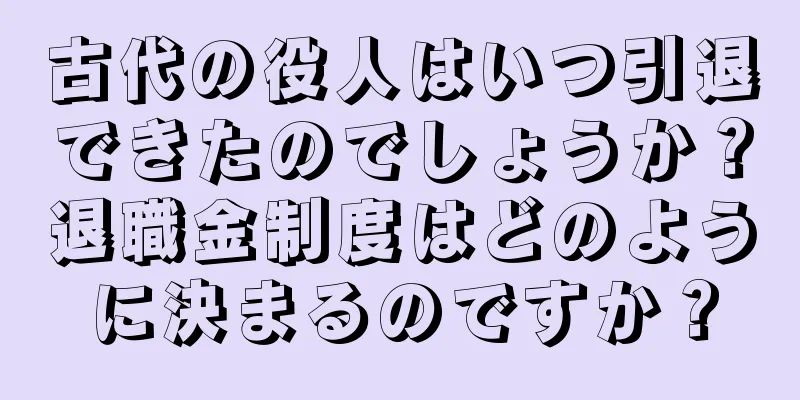
|
古代の役人はいつ退職できたのでしょうか?退職制度はどのように決定されたのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、ぜひ読み続けてください〜 退職制度は、実は一石二鳥の制度で、働く人の老後を保障し、死ぬまで働かなくてもいいようにするだけでなく、年齢による仕事の効率低下の問題を解決できるのです。しかし、退職制度は数千年かけて徐々に導入されてきました。古代人と比較すると、現代人の退職金はすでに非常に充実しています。古代には長い間、引退という概念がありませんでした。消極的に引退し、皇帝に辞職を強制されない限り、残りの人生は働かなければなりませんでした。では、退職金制度はいつから導入されたのでしょうか? 以下で調べてみましょう。 70歳で退職することは古代では珍しいことでした。 実際、退職という概念は、2,500年以上前の春秋時代から存在していました。ただ、当時は「引退」という言葉は使われておらず、「引退」、「仕事からの引退」、「政治からの引退」などと呼ばれていました。『春秋公陽伝』には「引退と隠居」が記録されています。「引退」とはどういう意味ですか?それは「君主に給料と地位を返す」、権力を君主に返すことを意味します。この意味では、官僚だけが「引退」できる。なぜなら、官僚だけが王に権力を返還する資格があるからだ。他の階級にはこれが存在しないので、引退というものは存在しない。 古代では、何歳で退職が許されていたのでしょうか? 『礼記: クリー』には、「高官は 70 歳で退職しなければならない」と規定されています。つまり、公務員は70歳に達したときにのみ退職が認められる。 70 歳という概念とは何でしょうか? 「70 歳まで生きる人は稀である」。古代では、70 歳は「高齢で稀」な年齢であり、この年齢まで生きられる人はほとんどいませんでした。学者の林万暁は論文「わが国各王朝の人の平均寿命と平均寿命」の中で、周秦の時代は約20歳、漢の時代は約22歳、唐の時代は約27歳、宋の時代は約30歳、清の時代は約33歳と推定している。杜甫は詩「羌郷三詩」の中で「老年を生きることを余儀なくされた」と述べているが、この詩を書いた当時は46歳で、すでに「老年」である。また、もう一人の文豪蘇東坡は「私は老人だが、青春の情熱をかき立てたい」と書いたとき、この「老人」は38歳であった。もちろん、乳児死亡率や戦争の要因を考慮に入れなければ、『人口論要綱』の推定によれば、古代人の平均寿命は60歳程度に達する可能性がある。 「60歳は60歳の年齢」という民間伝承によると、60歳になっても死ななければ「生きた墓」に埋葬されるそうです。これは伝説ではあるが、古代の人々が幼少期まで生きていたことを間接的に証明している。 現在の中国人の平均年齢からすると、70歳で退職するのは遅すぎる。楽しめる人は多くなく、楽しめる人も数年程度しかいません。そのため、古代の官僚の多くは「終身在職」となり、この年齢に達する前に亡くなりました。 この規定は『礼記』に定められて以来、漢代から元代にかけて千年以上にわたり朝廷はこれを遵守してきた。明・清の時代、おそらく70歳は高すぎると感じられたため、皇帝は慈悲深く、官吏の定年年齢を引き下げ、「60歳以上の文武官吏は定年退職」を認めた。 60歳で退職するのは現在と同じで、より合理的です。下位の官吏の場合、定年年齢は繰り上げられる。例えば、清朝では「中将の定年年齢は54歳、守備隊長の定年年齢は48歳、千人隊長または大隊長の定年年齢は45歳」と規定されていた。当時の平均寿命からすると、この退職年齢は比較的妥当なものでした。 韓愈が最初に「引退」を提案し、宋代の人々は最高の待遇を受けた 「退職」という言葉は現代人が作ったものではありません。 1300年以上前の唐代、文豪の韓愈は『夫之賦序』の中で「私は家に引きこもって『夫之賦』を書いた」と述べています。これは文学における「隠居」という言葉の最も古い記録です。韓国愈が「隠居」という言葉を「発明」した後、後世の人々に使われ、次第に普及していった。 『宋史記 韓治伝』には「15年間隠遁し、世間を見ることを拒み、読書をしたり詩を書いたりして自分を楽しませていた」という一文があるが、これは韓愈より数百年後のことである。 退職金に関しては、王朝によって大きな違いがあります。例えば、漢代には、70歳で一定の地位(年俸2,000石以上)に達した官吏は、在職中の給与の30%を退職後に年金として受け取ることができました。この条件を下回る場合、退職金は支払われません。年俸2,000段とはどういう意味ですか? 漢代の「大将」の年俸は2,000段で、これは現在の省級や部級の幹部に相当します。古代では70歳というのは珍しい年齢とされ、省や大臣クラスに達すると古代では役人が少なく、退職金を得られる幹部は多くなかった。 唐代は、差別化された退職給与制度と福利厚生制度を実施しました。功績のある官吏が第一級で、皇帝の特別な許可を得て退職した後は、在職中と同じ給与を全額受け取ることができましたが、権力はありませんでした。5位以上の退職官吏には「半額の給与」が与えられ、6位以下の官吏は退職後に年金を受け取れませんでした。「唐代の退職官吏は、特別な命令がなければ給与を与えられなかった」が、生活問題を解決するために、補償として一定量の土地を発行することができました。明朝の初代皇帝、朱元璋は貧しい家庭出身で、官僚に対して特にケチだった。一般的に、彼は引退した官僚に「年金」を支給しなかったが、引退した官僚の税金や強制労働を免除した。調査の結果、退職した公務員の家族が生活費を賄えないほど貧しいことが判明した場合、「公務員は生涯にわたり毎月米二段を支給する」ことになるが、これは年金手当とみなすことができる。清朝は明朝とあまり変わらなかったため、官僚たちは将来の老後のことを考えて、在任中は「貪欲」に「奉行三年で銀貨十万枚」と頑張った。もしあなたが私の退職金を支払ってくれないなら、私は自分で方法を見つけます。もちろん、これには斬首される危険が伴います。 相対的に言えば、宋代は引退した官僚に対する待遇が最もよかった。宋神宗以降、官僚は在職中に引退することが許された。引退は実権を失うことを除けば引退しないのとほとんど同じであり、待遇は同じままであった。定年退職を奨励するため、官吏は定年退職時に一階級昇進し、定年退職後もさらに上の官職に昇進したり、宮廷事務に参加したりする権利が保持される。宋代は文官を武官より重んじ、学者にとって黄金時代だった。経済も高度に発達し、国家が官吏を「支援」していた。この待遇は現代とあまり変わらない。もしタイムトラベルができたら、ほとんどの学者はやはり宋代に戻りたいと願うだろう。 昔は、定年まで待つことができたのは幸運なことでした。 「皇帝に仕えることは虎に仕えるようなものだ」ということわざがある。古代において、官吏であることは、実は命を危険にさらす行為だった。もし、半生の間皇帝に仕え、幸運にも生き延びて引退することができれば、それは人生における祝福であった。大臣にとって、引退は一種の「逃避」のようなものだ。使命を果たしたあと、キャリアのピーク時に引退するのは賢明な選択だ。大臣が引退すべき時に引退せず、皇帝を怒らせたら、それはまずいことであり、死に至る可能性さえある。疑い深い皇帝にとって、大臣は王室の秘密を多く知っており、彼らがいなくなったら、彼らをコントロールすることは難しい。だから、大臣を帰国させて引退させるのは、「虎を山に帰らせる」ようなものだ。この「虎」は年老いていますが、トラブルを防ぐために常に監視する必要があります。 そのため、大臣が退職を申請する際、「骨乞い」と呼ばれる言葉がありました。大臣が官吏になるということは、皇族に体を売るのと同じことだからです。引退するときには権力を返上し、自分の故郷に埋葬したいので、皇帝に自分の老いた骨を返して欲しいと懇願するのです。 大臣は「引退を懇願」することはできるが、最終的に引退できるかどうかは皇帝次第である。皇帝があなたをまだ役に立つと判断すれば、引退は許されず、生きて死ぬまで働くことしかできなくなります。漢代の有名な儒学者である張愈は何度も引退を申請したが、皇帝は拒否した。あなたに引退を許さない唯一の理由は、あなたが病気であり、皇帝の医師があなたを治療しているからです。 宋代には、大臣が引退を申請することが一般的だったが、皇帝はそれを承認しなかった。二代にわたる歴任大臣である項民忠は、法定の定年である70歳に達しても引退を許されず、72歳で在職中に亡くなった。老大臣の孫固は「就任を余儀なくされ」、75歳で在職中に亡くなった。老大臣の孫綿は71歳であったが、依然として「重要な任務」を任され、長い旅の苦難に耐えられず、ついには就任の途中で亡くなった。これは、一方では、これらの大臣が皇帝に頼られていたことを示し、他方では、大臣が官吏になると個人の自由を失ったことも示しています。 退職が認められなかった公務員とは対照的に、裁判所は、評価されていない公務員の一部が早期退職することを期待し、空きを作るために彼らに退職を命じた。明朝の孝宗皇帝は「年齢に関係なく、自発的に辞職する官吏は、退職を命じる」という特別勅令を出した。官吏になりたくない者も、官吏になりたい者も、すぐに認められた。清朝は「老齢で病気で、職を離れることを嫌がり、辞めないことで批判される者は、退職を命じる」と規定した。彼らは「退職」を強制され、年金も支給されなかった。健康上の理由で大臣の早期引退を認めた慈悲深い皇帝もいました。例えば、唐代の大臣である李靖は、健康上の理由で64歳で引退することを認められました。功績をあげた後に朝廷を退くケースは他にもある。越国の大臣、范礼は郭堅の国を復興させた後、将軍の位を授けられたが、高官としての待遇を受けられなかった。その代わりに、彼は「恩給」を受け取らずに朝廷を去り、名前を変えて実業家となり、儒教実業家の祖となった。 昔の人は、引退について「引退は馬車を吊るすようなものだ」ということわざがありました。役人が無事に「引退」して老後を楽しむことができれば、「年金」がいくら多くても、それはその役人にとっては幸運なことでした。古代人は「子供を育てることは老後の備えである」と信じていたため、年老いたときには朝廷からの給与よりも主に子孫に頼っていました。もちろん、功績のある将軍や有名な役人の中には、老後を楽しめるよう賢明な皇帝から特別な褒賞を与えられる者もいました。 |
<<: 高麗王朝は高句麗と関係がありますか?高麗王朝はどのようにして滅亡したのでしょうか?
>>: 「荊州」は歴史上どこにあったのでしょうか?湖光はどうやって分裂したのですか?
推薦する
乾隆帝はなぜ十公主をそんなに好いたのでしょうか?十番目の王女の結末はどうでしたか?
乾隆帝はなぜ第十公主を最も愛したのでしょうか? 結局、第十公主はどうなったのでしょうか? Inter...
山海京にはどんなかわいいエキゾチックな動物がいますか?これらの愛らしい獣はどんな姿をしているのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が山海経の可愛くてエキゾチックな獣たちを紹介し...
『旧二県白花州・荊霞営自筆』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
丁鳳波:旧鎮朗下営百花州の2つの県から、個人的に作られた范仲燕(宋代)春が終わりに近づくにつれ、街は...
『紅楼夢』の石向雲と賈宝玉の関係は?この二人の白髪の双子は実在するのでしょうか?
『紅楼夢』の金陵十二美女の一人、石向雲は中性的な美しさを持つ女性です。多くの人が理解していないので、...
七人の剣士と十三人の英雄 第101話: 三度の計画と傲慢な兵士の敗北、そして一つの命令で戦いに勝つ
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
文学作品に登場する5人の守銭奴:グランデ、シャイロック、顔建生
有名な文学作品における守銭奴のイメージ世界の文学の名作の中で、文豪たちは、バルザックの作品のグランデ...
どのような種類のコレクション用ブレスレットが安価で手頃な価格ですか?人気のないブレスレットトップ10の価格をご紹介!
今日は、Interesting Historyの編集者が人気のないブレスレットの価格についての記事を...
孫権の長女、孫魯班の簡単な紹介
孫魯班(生没年不詳)、号は大湖、武順富春の出身。東呉の皇帝孫権の長女。彼女の実母は武夫人であり、全易...
『紅楼夢』の妙玉の結末は何ですか?ミャオユの経歴
『紅楼夢』の妙玉の結末は何ですか? 『紅楼夢』に登場する金陵十二美人の一人、妙玉は髪を切らずに仏法を...
サラール族の民俗詩にはどのような民俗習慣が表れているのでしょうか?
サラール地方の民俗詩には、民俗叙事詩や民謡が含まれます。 「サラ・ソング」は、サラール語で「ユル」と...
宋代はなぜ皇帝を「関甲」と呼んだのでしょうか?この名前にはどんな意味がありますか?
昔の人が皇帝を呼ぶ方法は、さまざまなテレビドラマでよく見られます。ほとんどの場合、「陛下」という、威...
東呉には有名な将軍がたくさんいたのに、なぜ曹操は蜀漢の将軍だけを優遇したのでしょうか?
この問題に気づいたかどうかはわかりません。三国時代、曹操は才能をとても愛する人物でした。才能のある人...
中国のバレンタインデーの愛の詩「私たちの間の愛が永遠に続くなら」は誰に宛てて書かれたのでしょうか?文人秦貫の恋物語!
中国のバレンタインデーの愛の詩「私たちの間の愛が永遠に続くなら」は誰のために書かれたのでしょうか?学...
諸葛亮の姓は「諸葛」ではないことが判明?
古代の有名人といえば、諸葛亮は誰もが知る名前です。正史、非正史、映画、テレビ、オペラなど、三国志を語...
雍正帝は康熙帝と乾隆帝の後を継ぎました。なぜ彼の統治はわずか13年だったのでしょうか?
康熙帝は合計で約61年間統治しました。乾隆帝は名目上は60年間統治しましたが、実際の統治期間は約63...