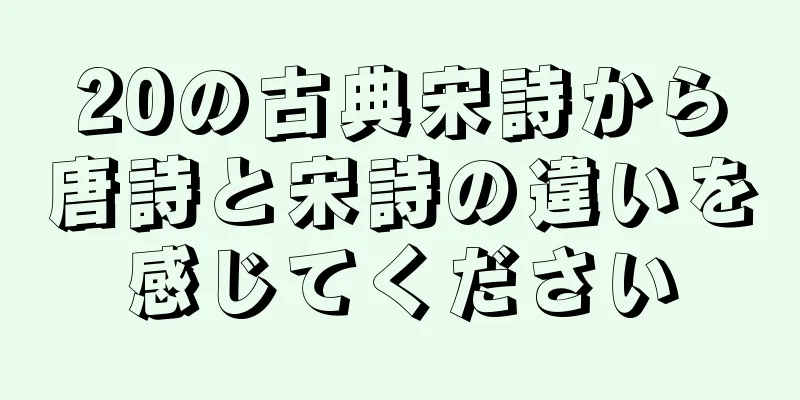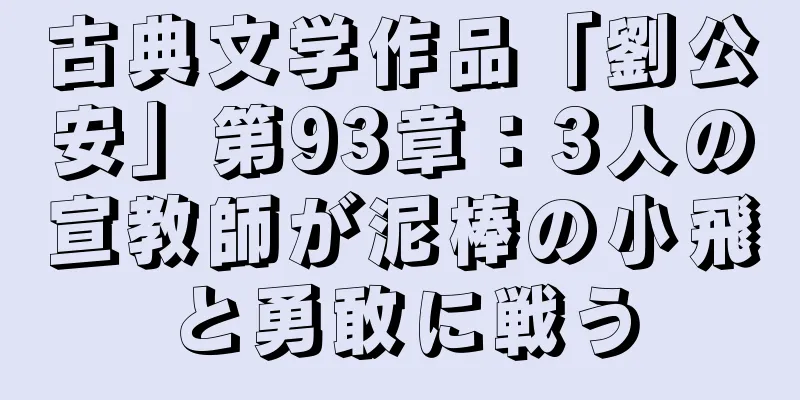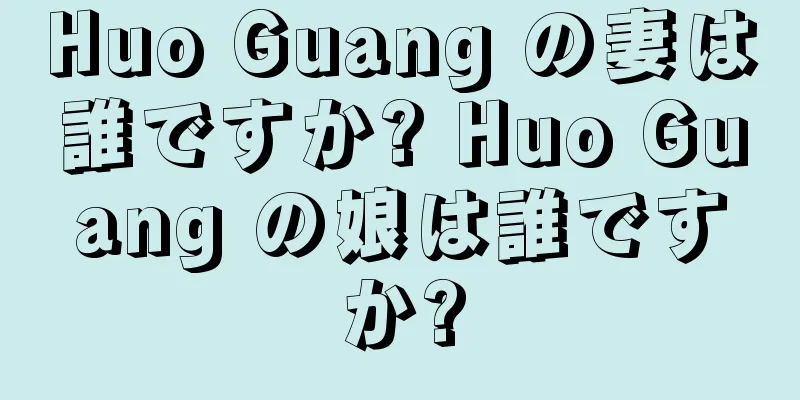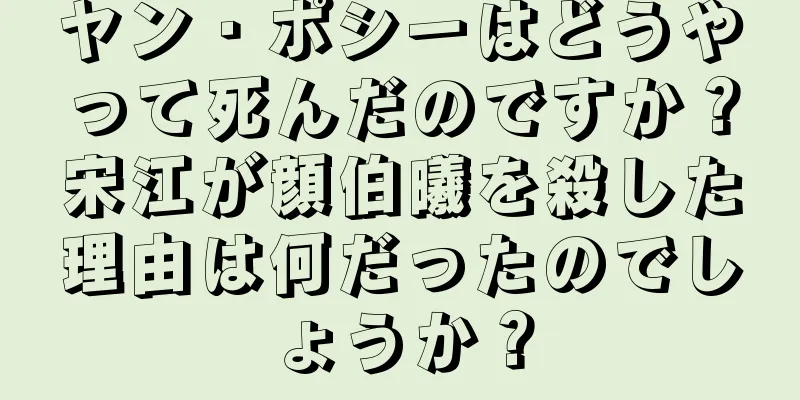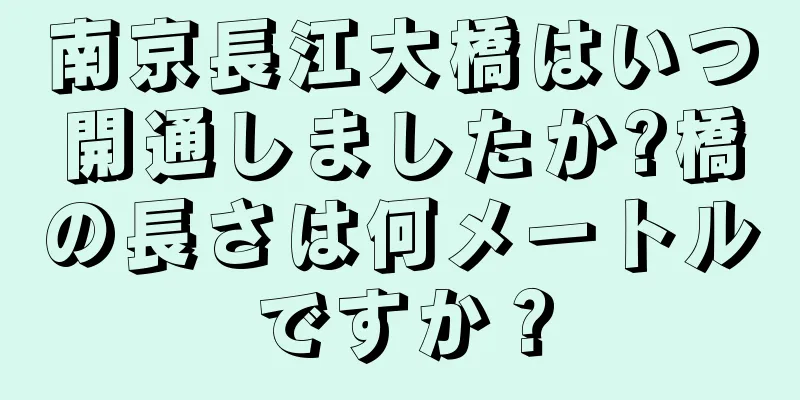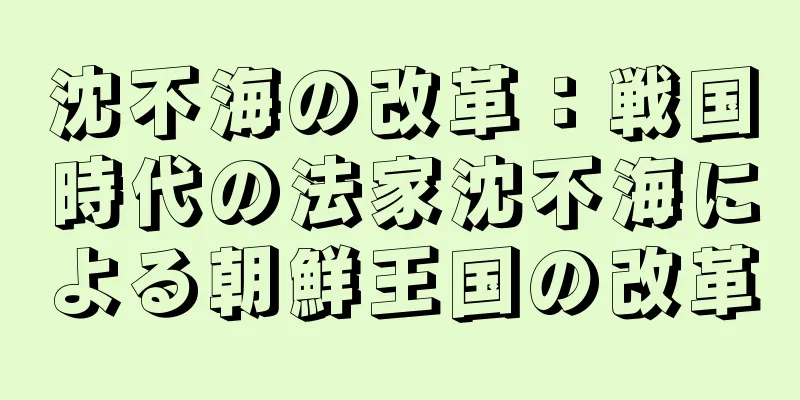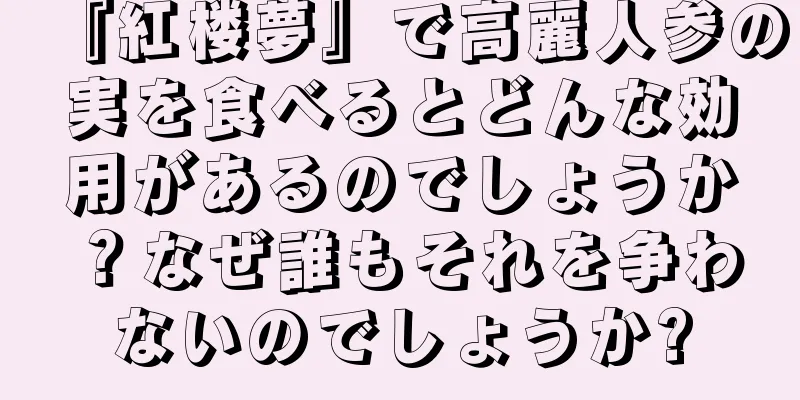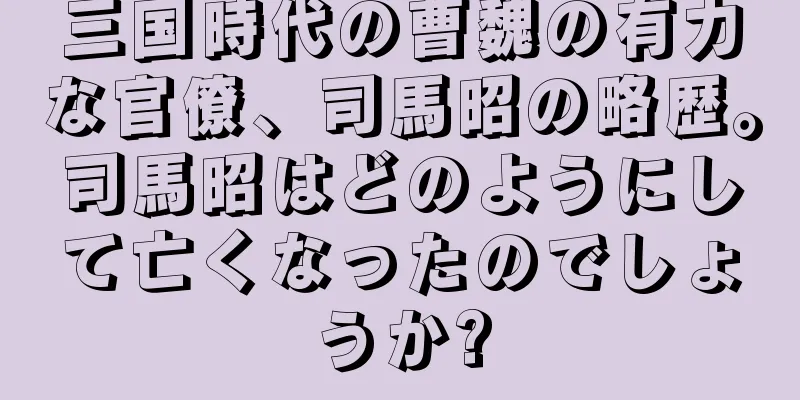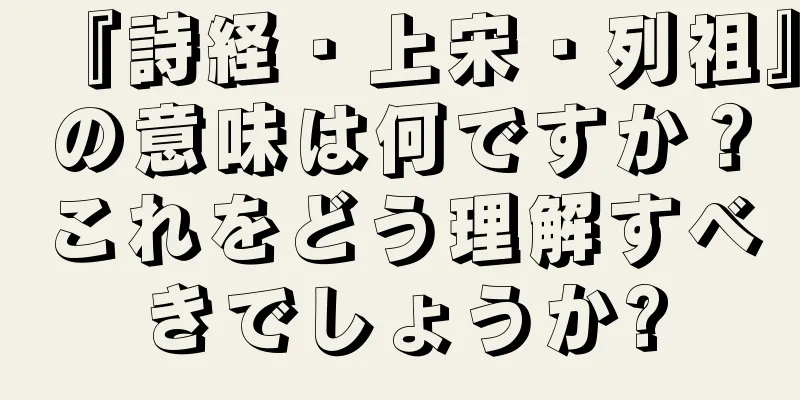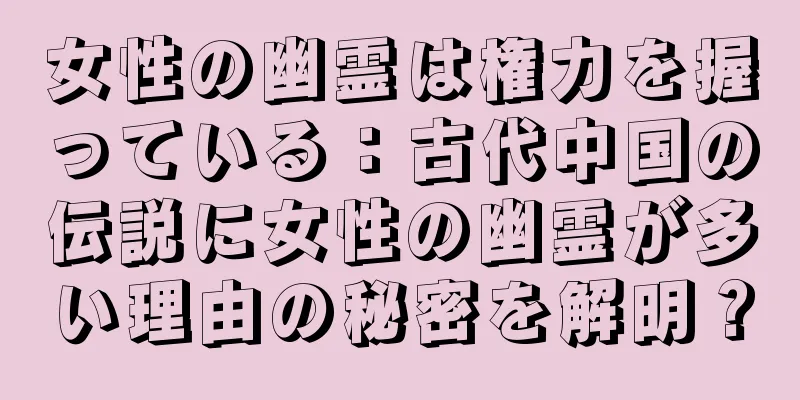乾隆帝は何本の剣を持っていましたか?乾隆帝の剣は今どこにあるのでしょうか?
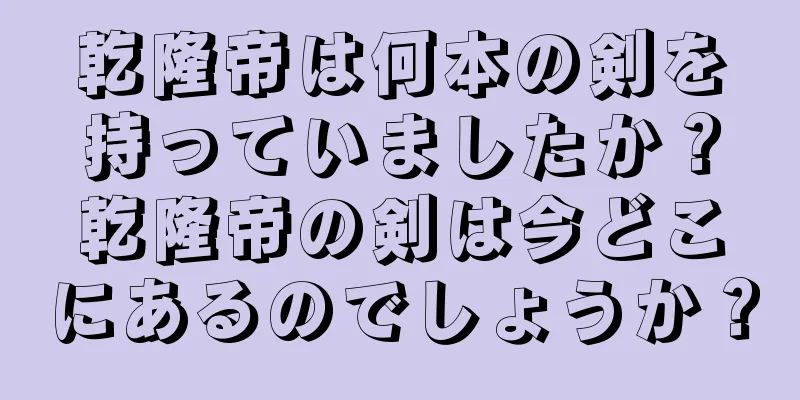
|
乾隆帝は何本の剣を持っていたのか?Fun History編集部と一緒に調べてみよう! 乾隆帝の剣といえば、今でも多くの人が興味を持っています。結局のところ、剣は英雄に付き添うものです。最近、剣で遊んでいたら乾隆帝に勝てないと言う人が多いです。結局のところ、彼は当時の一国の王だったので、手にたくさんの剣を持っていました。最近、誰かが非常に興味深い質問をしました。それは、乾隆帝の剣はどこで見つけられるかということです。この質問は興味深いようですが、その背後には魂があります! 乾隆帝の剣は見つかりません。国宝です。現在市場に流通しているのは1本だけですが、残りの89本がどこにあるかは誰も知りません。どうやって見つけるか?この質問には答えがありません。 乾隆帝と90本の剣 剣が作られた後、乾隆帝は27本を5回に分けて、保管のために盛京宮に送りました。盛京(現在の遼寧省瀋陽市)は清朝建国の「基礎となる場所」であった。 乾隆天子3号「孔春」刀、全長94cm、緑玉柄12.5cm、重さ18両、現在北京故宮博物院所蔵(写真:北京故宮博物院ウェブサイト) 近年、知識を得るためのチャネルが増え続けるにつれ、私たちの心の中の乾隆帝のイメージも静かに変化してきました。私が子供の頃、乾隆帝に対する印象は次のようなものだったことを覚えています。 現在、彼の農家風の美学にさらなる注目が集まっています。 清代乾隆帝のバラ中空回転ハート花瓶(写真:中国国立博物館のウェブサイト) もし乾隆帝がこれを知ったら、間違いなく不当だと叫ぶでしょう。「私はただの平凡な男だ!!! 私が美しい女性や農家の美学を好むのは私のせいではない! 私が剣や棍棒を扱うのも好きだということは、おそらく知らないだろう!!!」 えっ?乾隆帝は実際に剣や棒を使うのが好きだったの?これはロマンチックな皇帝のイメージとはまったく矛盾していますね。しかし、歴史の記録によると、乾隆帝は、現代の言葉で言えば「ある程度の武術を知っていた」そうです。 乾隆帝の治世中、毎年夏になると、皇帝は武官を迎えた後、宮殿の門の外で弓矢の競技会を開き、1回につき3本の矢を3回連続で射ていました。乾隆帝は、どの競技でも、9本の矢のうち6本か7本を的中に当てることができ、その命中率は合格ラインを超えていました。乾隆28年(1763年)の競技では、9本の矢をすべて的中に当てた。多忙な政務や旅行の傍ら、乗馬や弓術の練習も怠らなかったことが伺えます。 郎世寧による『乾隆視察図』は、乾隆帝が29歳の時の軍服を着た肖像画である。 馬上弓術(「騎馬弓術」とも呼ばれる)は、満州族の独特の国民的特徴の 1 つです。しかし、清軍が峠に侵入し国内を統一するにつれて、満州族と漢族の交流はますます頻繁になりました。満州族の全体的な騎馬弓術のレベルは低下傾向にある。乾隆帝はこれを非常に憂慮し、数度の勅令を出し、王族や八旗の諸侯に自らを模範として「毎年の狩猟旅行の際には馬に乗って射撃をすることができるように」し、乗馬と射撃の家族の伝統を「後世まで変わらずに伝える」よう努めるよう要求した。 さらに、清朝の朝廷は、満州族の官吏の選抜、試験、将兵の登録、科挙などの評価基準として、乗馬や弓術の熟練度、満州語の熟練度を採用した。第二世代の官僚、つまり王子や大臣の息子や甥は、官職でさらに昇進したいのであれば、「国語(ここでは満州語を指す)と乗馬と射撃に堪能で」なければならず、満州人の独自性を維持しようと努めた。 乾隆帝が一矢で二頭の鹿を射る 乾隆帝の武術に対する熱意のもう一つの表れは、武器に対する愛情である。内務省の記録によると、乾隆年間、内務省の工房は皇帝の命令に従って、4回に分けて腰刀90本と刀30本を製作した。腰刀は「天」「地」「連」の3種類があり、各30本ずつあります。 それぞれのナイフには番号の他に名前も付いています。例えば、今日紹介する天子の3号包丁は「孔春」と名付けられています。「孔」は古代で「非常に、極めて」を意味し、「孔春」は「非常に純粋」を意味します。他にも、第18天剣の「双明」や第3帝剣の「建水」など、武器の気質に合った良い名前がたくさんあります。 「孔春」刀の一部(写真:劉銀、毛先民、「乾隆帝御用金桃皮鞘『天子17号』『宝騰』腰刀」、『故宮』2007年4月) これら90本の刀は、基本的に形状が同じです。刀全体が細長いS字型をしており、刃先から先端にかけてわずかに上向きになっています。柄と鞘の材質にわずかな違いがあるだけです。天級の剣は玉の柄と金桃皮の鞘(金桃皮は大興安山脈で産出される低木で、表面は赤黒く、内側は金色に輝き、武器の装飾として使用できます)、そして、二級の剣は木製の柄と緑の鮫皮の鞘を備えています。刀のスタイル、質感、仕様はすべて乾隆帝自身によって承認されました。 「孔春」ナイフを例に挙げてみましょう。このナイフの刃は鋼で作られており、刃の上部には銀色の「天子三好」の文字が埋め込まれており、金、銀、銅の線で象嵌された雲、花、鹿の模様や龍の模様も刻まれています。 天子18号「双明」腰刀とその細かい模様(写真:上と同じ) 剣が作られた後、乾隆帝は27本を5回に分けて、保管のために盛京宮に送りました。盛京(現在の遼寧省瀋陽市)は清朝建国の「基礎となる場所」であった。そのため、盛京宮には清代の文化財が大量に保管されており、盛京の地位を高めるだけでなく、東巡の途中で盛京に到着した皇帝の日常生活を便利にするためにも使われました。文化財には刀剣などの軍事装備品だけでなく、磁器、金銀器などの生活必需品、玉書や歴代王朝の皇帝の馬車などの儀式用品も多数含まれています。しかし、清朝末期、清政府の腐敗と無能さにより、二つの清王朝の宮殿にあった多数の文化財が失われました。現在、北京の紫禁城には乾隆帝が作った剣が50本以上あり、瀋陽故宮博物館には2本だけが所蔵されている。残りの刀剣は所在不明のものを除き、各地の収集機関や個人収集家に分散している。 煙台博物館所蔵の乾隆帝の刀剣2本と鞘(写真:李宇、「乾隆帝の刀剣」『世界へ行く』2014年12月) 2004年、ドイツのオークションに「17」の番号が付いた「プロトン」ウエストナイフが登場した。しかし、代々受け継がれてきた乾隆帝の剣は数が少なく、極めて希少であるため、多くの人がこの文化財の真贋を疑い、入札をためらっています。結局、このナイフはドイツ人の買い手によって11万4000ユーロで購入された。 2006年4月10日、この「プロトン」ナイフは、サザビーズ香港オークションハウスで開催された「プロトン龍勝-乾隆宝物と徳安堂白玉特別オークション」に再び登場し、最終的に4,604万香港ドルで落札され、中国皇室工芸品の世界オークション記録を樹立しました。 『故宮』誌もこの腰刀を紹介する特集記事を掲載した。それ以来、誰もその信憑性を疑うことはなくなった。 「陽子」腰刀(一部)(写真:劉隠、毛先民、「乾隆帝作 金桃皮鞘陽子腰刀 17号」、『故宮』、2007年4月) このナイフは2012年に中国嘉徳秋季オークションに再び出品され、再び4830万元という高値で落札された。もし乾隆帝が、自らが監修した刀が数百年後にこれほど高値で売られたと知っていたら、自分の「先見の明」を誇りに思うだろうか? 参考文献: 李玉『乾隆帝の皇剣』Towards the World、2014(52)。 劉隠. 乾隆帝御用金桃皮鞘「天子17号」「包丁」腰刀[J]. 紫禁城, 2007(4):144-147. 呉九. 刀とナイフの交差における民軍功績[J]. 世界知識画報・芸術ビジョン、2014(8)。 張漢傑「瀋陽皇宮の乾隆帝が使用した二本の剣の文献研究について」北方文化財、1995(2):53-56。 孫景. 乾隆帝の「国語、馬、射撃」の維持について[J]. 大連民族大学学報、2006年、8(4):49-53。 |
<<: 「アルバニア」はどこですか? 「アルバニア」はどのようにして誕生したのでしょうか?
>>: 1億年前のトカゲはザリガニを食べるのが好きだったのでしょうか?ザリガニはいつ出現したのでしょうか?
推薦する
古代の大臣たちはなぜ死刑判決を受ける前に皇帝に感謝の意を表したのでしょうか?
時代劇を愛する友人たちは、皇帝が他の誰よりも天子であり、すべての人の命を握っていることを知っています...
西洋物語第56章:守護神ナイエルが力を発揮し、2人の仙子ヘヘが聖人になる
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
派安景奇初版第34巻:翠福寺の戦いを聞き、黄砂の小道の尼僧を見る
『楚科派安経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。この本は、一般大衆に人気のある「疑似...
『呉越春秋』第1巻の呉太伯伝の主人公は誰ですか?
呉の先王太伯は侯季の子孫であった。侯季の母、蒋元は泰の娘で、羌帝の最初の妻であった。彼女がまだ妊娠し...
「涼州三歌」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
涼州慈の詩三篇張季(唐代)国境の町では、夕立の中、雁が低く飛び、新芽のアスパラガスが育ち始めています...
目覚めた結婚物語第58章:疑わしい女性は、青白い口と丸い目をした男性と関係を持っています。
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
周邦彦の「冷たい窓・冷たい食べ物」:詩人は放浪者としてのアイデンティティを決して忘れなかった
周邦厳(1057-1121)、号は梅成、号は清真居士、銭塘(現在の浙江省杭州市)の人。北宋時代の作家...
曹丕はなぜ甄嬛を処刑したのですか?甄嬛の死因は何でしたか?
曹丕はなぜ甄嬛を処刑したのか?今日は、おもしろ歴史編集長が詳しく説明します〜曹丕が26歳のとき、曹丕...
歴史上「晋には王族がいない」と言われているのはなぜか
晋は周成王の弟である叔玉から始まった(詳細は「弟の桐葉封土」を参照)。叔玉の姓は季、雅号は子玉である...
古代の人々は歯ブラシを持っていなかったら何をしていたのでしょうか?歯ブラシはどうやって生まれたのでしょうか?
古代の人々がどのように歯を磨いていたかご存知ですか? Interesting History の編集...
曹操軍による呂布の二度の包囲戦の際、なぜ八将軍は姿を見せなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清朝の老人保健に関する論文「老老衡眼」第4巻。ベッド
『老老衡厳』の著者は清代の学者曹廷東で、老年期の健康維持に関する論文集で全5巻からなる。周作人はこれ...
昌平の戦いの前に各国は何をしていたのでしょうか?歴史上の大きな出来事は何ですか?
本日は、Interesting Historyの編集者が、皆様のお役に立てればと願って、昌平の戦い以...
古典文学の傑作「淘宝夢」第7巻 氷山の記録
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...
蜀漢は魏延の手の中では岩のように強かったのに、なぜ姜維の手の中では負けたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...