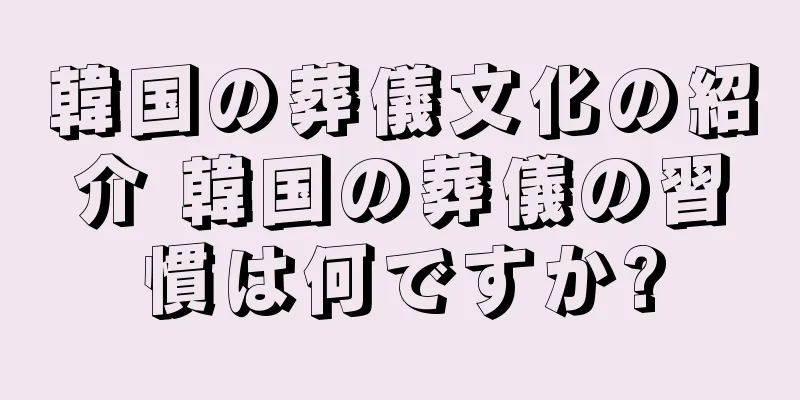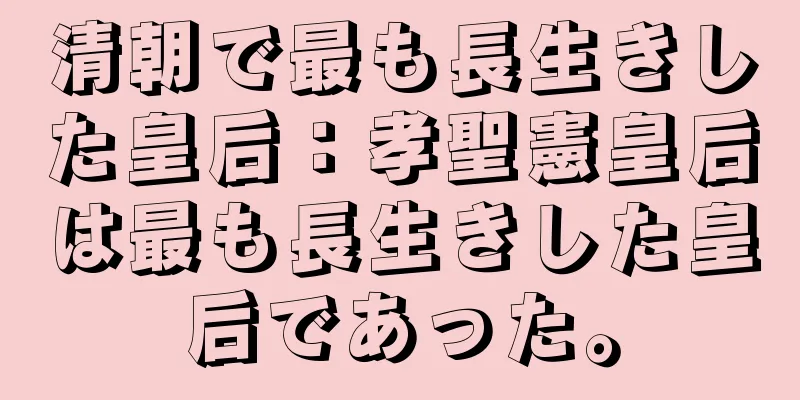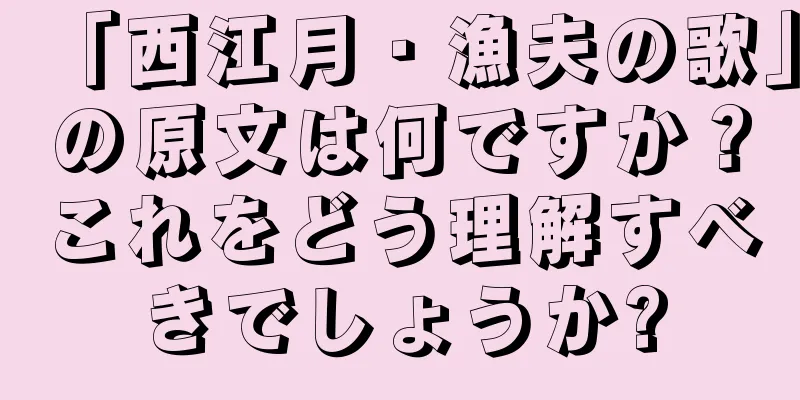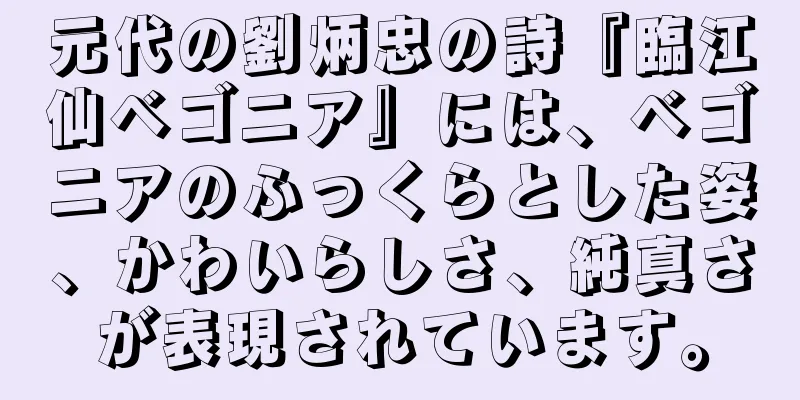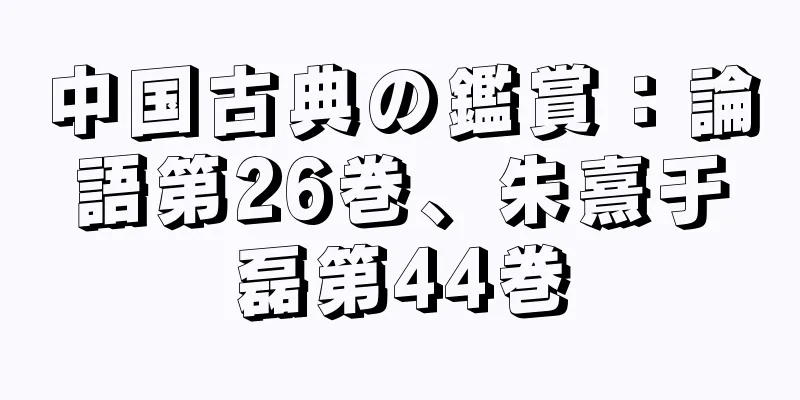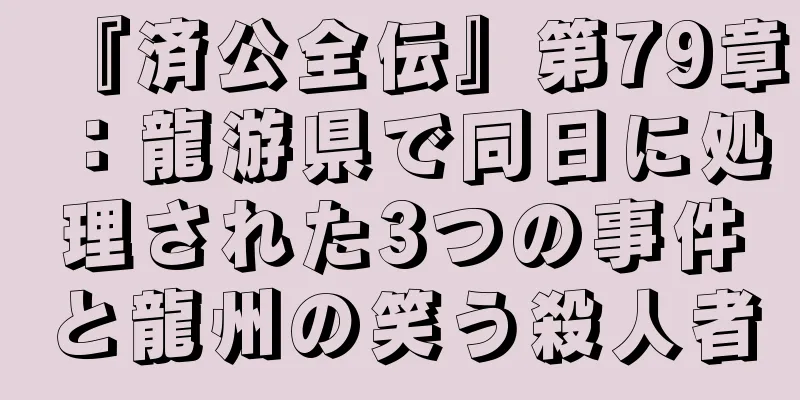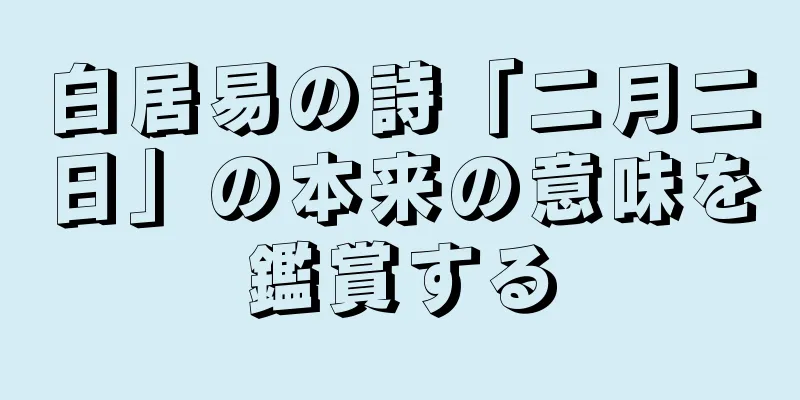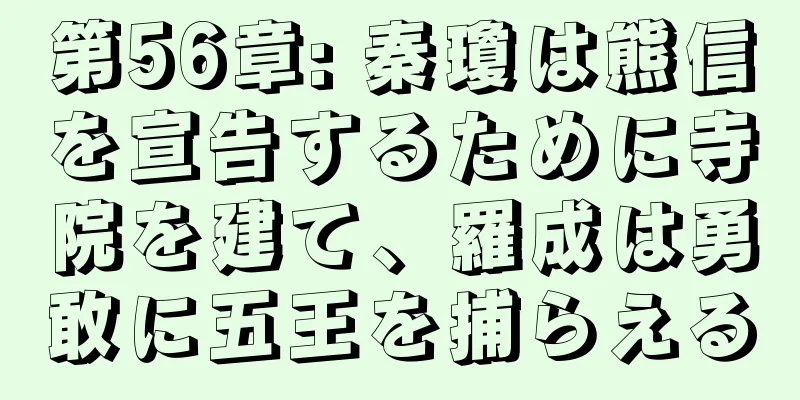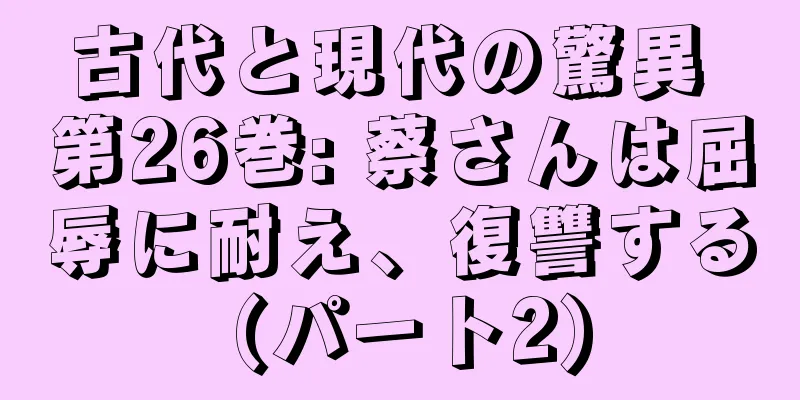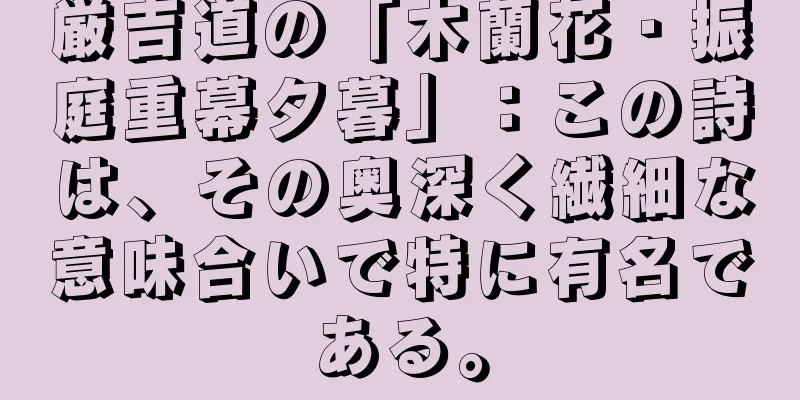清朝時代の退職制度はどのようなものだったのでしょうか?なぜ退職後に呼び戻されなければならない人がいるのでしょうか?
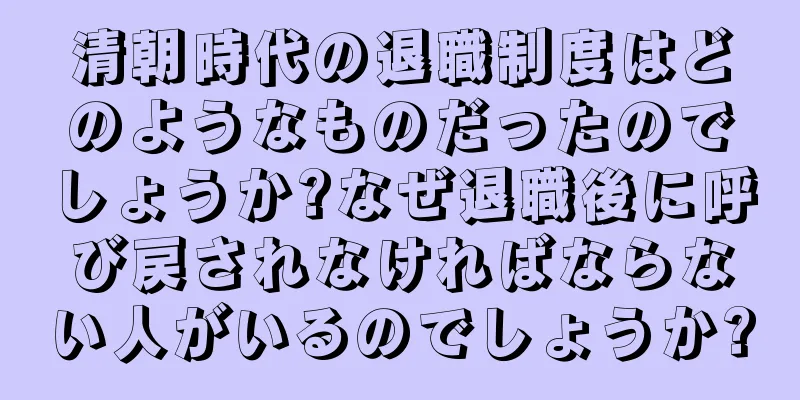
|
今日は、Interesting Historyの編集者が皆さんのために用意しました。清朝時代の退職制度はどのようなものだったのでしょうか?ご興味のある方はぜひご覧ください。 現代社会の重要な制度の一つとして、公務員は一定の年齢に達すると退職し、国からの財政支援を受けることになります。実は、この制度は近代経済社会の産物ではありません。退職制度は中国の周王朝に始まり、徐々に国民的慣習へと発展しました。 「隠居」という言葉は唐代と宋代の文学作品に初めて登場しました。唐代の散文作家、韓愈の『輔志賦』の序文に「家に引きこもって『輔志賦』を書いた」という一文がある。漢代には、官吏の退職は「辞職」と呼ばれていました。清朝時代、官僚の退職は、昇進による退職、失敗して皇帝に処罰されての退職、定年退職など、多くの種類に分かれていました。 今日は清朝時代の官吏の退職制度についてお話しましょう。 官僚の定年については、乾隆時代の制度規定により、尚書、士郎を含む各部署の55歳以上の官僚は全員、本当に定年に達しているかどうかを慎重に確認しなければならないとされた。公務員の定年は70歳までです。70歳までに退職しない場合は、上級官庁から強制的に退職させられます。 しかし、70歳で定年退職するというルールは、高い地位と大きな権力を持つ一部の公務員にとっては、おおよその範囲に過ぎません。多くの場合、官吏が引退すべきかどうかは、官吏の気力、皇帝の官吏に対する態度、そして上官との関係に大きく関係していると言える。 さらに、清朝時代には、官僚が退職したい場合には、一般的には上司に理由を説明し、承認を得た上でのみ退職することができた。三位以上の官吏は皇帝に直接「退官弔辞」を提出することができた。四位以下の官吏は、所属部署の尚書または士郎を通じて皇帝に退官弔辞を提出しなければならなかった。 首都以外の公務員は知事と人事省の承認を受ける必要がある。 一般的に言えば、役人の退職要請が承認された場合、空席を埋めるための費用は直ちに精算され、その後、そのポストに就く別の人物が見つかるまで皇帝の勅令が求められる。 しかし、特別なケースもあり、乾隆帝の時代には、退官を希望する官僚を「太政官の職務は政府を補佐すること」や「勤続年数が長い」などの理由で留任させ、その官職を1か月間留保した例もあった。乾隆帝はこの方法によって、国の老臣に対する配慮を示した。たとえその臣が引退しようとしていたとしても、国は彼に対する配慮を忘れることはなかった。 公務員の退職後の処遇の観点から見ると、公務員の退職は次の2つに分けられます。 一つは定年制度に従って年齢に応じて退職する方法です。 もう一つは、元の官吏の退職です。簡単に言えば、このタイプの退職は、退職した官吏の元の官職と階級の栄誉を保持することを意味します。 本来の官職の給与については別途規定が設けられた。 一般的に、太政官や国務大臣級の官吏が定年退職後も元の官職に留まる場合には、帰郷後も元の官職の給与全額が支給される手当が支給されることが多い。在職中の公務員が審査を受け、元の階級に基づいて退職する場合、元の給与の半額が支給されます。役人が上司から退職を命じられた場合、給与は支払われない。 清朝は、官僚が退職後に給与を受け取るかどうかについてこのような詳細な規定を設けていたが、これは絶対的なものではなかった。皇帝が特別の恩恵を与えれば、役人は無給から有給に、あるいは半給から満額の給与に変わることも可能であった。官僚が官職を退いた後、皇帝は在任中の宮廷への貢献を報いるために、称号や階級などの昇進を与えることを検討しました。 例えば、雍正帝が権力を握っていたとき、太政官の陳元龍は、重要な責任を担うには年を取りすぎていると感じ、引退を申し出ました。雍正帝は陳元龍が勤勉に働き、朝廷に多大な貢献をしたと感じていた。また、陳元龍が康熙帝時代の老臣であったことも考慮した。そのため、雍正帝は陳元龍に太夫王の爵位を死後に授け、元の官職のまま退位することを許可した。これは、公務員が定年後に昇進した例です。 また、引退した官吏に爵位や官位を昇進させる例もあったが、逆に、官吏が傲慢すぎるために故意に引退願いを無視したと皇帝が判断し、懲戒処分や処罰を与える例もあった。例えば、乾隆5年、当時工部大臣であった魏廷鎮は、高齢と虚弱を理由に引退を希望した。しかし、乾隆帝は、自分が長年この地位に就いていたにもかかわらず、目立った政治的功績はなく、朝廷に対して大きな貢献もしていないと考えていた。そのため、彼を公職から解任し、故郷に送還する命令が出された。 皇帝から隠居を命じられることは珍しくなかった。 そして命令するということは他人を罰することを意味します。現時点では、職員の年齢や体調が退職に影響を与える主な理由ではない。こうした退職は、公務員が自ら申告する退職とは根本的に異なる。例えば、雍正帝の時代、雍正帝は自分の部署の一部が私利私欲のために徒党を組んでいることに気づき、一部の官僚にその件を徹底的に調査するよう命じました。そのような現象が見られる官僚は、その職を解かれました。 このうち、解雇された職員は退職を命じられた。このような状況では、役人はミスを犯したため、当然ながら給与やその他の福利厚生を享受することができません。 さらに、別の特別な状況として、ある役人がミスを犯したために他の大臣から弾劾されるという状況があります。このとき、皇帝は役人の面目を保つために、罰を与える代わりに、その役人を引退させます。しかし、退職する職員は承認を得た後すぐに退職するわけではありません。退社前に部下とすべての作業を調整する必要があり、タスクを完了した後にのみ退社できます。 しかし、例外として、引退しても天皇の要請があれば官職に復帰する役人もいます。 簡単に言えば、皇帝が必要としない場合は官吏は引退しなければなりません。また、皇帝が必要とする場合は官吏は宮廷に戻り、引き続き国に奉仕しなければなりません。 |
<<: 「五穀改革の六君子」とは誰ですか?五穀改革の六君子が処刑されたとき、なぜ人々は拍手喝采したのでしょうか?
>>: 「公職や肩書を売る」ことは合法だというのは本当ですか?古代の寄進制度はいつ始まったのでしょうか?
推薦する
ヨン・タオの「孫明福と山を巡る」には強い郷愁が込められている
雍涛、号は郭君、唐代末期の詩人。作詞や賦を得意とした。代表作に『君山碑文』、『城西友山荘訪』などがあ...
『呉中の馮氏を偲んで』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
呉中の馮氏を偲んで杜牧(唐代)常州園の外では草がざわめき、旅は長く感じられます。今思い出すのは、夕霧...
歴史上、蘭を讃えた詩にはどのようなものがありますか?蘭はなぜそんなに人気があるのでしょうか?
歴史上、蘭を讃える詩は数多くあります。Interesting History の次の編集者が、関連す...
『蘇中清・宝月山著』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】青波門の外には薄着の女性がいます。柳の花穂が飛んでいきます。西湖ではまた晩春が訪れ、水...
「目覚めた結婚の物語」第85章:ディ・ジンリは逃げて仕事に行き、シュエ・スージエは騙されて家に留まる
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
太平広記・第85巻・奇人・徐明福の具体的な内容は何ですか?どのように翻訳しますか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
沈朗は実は白菲菲をとても愛している。なぜそう言うのか?
沈朗は古龍の武侠小説『武林外史』の主人公であり、「天下一の英雄」として知られている。彼と白菲菲との関...
『史記』の「秦が鹿を失ったとき、天下はそれを追った」という文章の「鹿」とは何を指しますか?
『史記 淮陰侯伝』には、「秦の支柱が折れ、支えが緩み、山東は大混乱に陥り、様々な姓が立ち上がり、才能...
陳勝の反乱は、時代を超えてさまざまな評価を受けてきました。なぜ司馬遷は陳勝の反乱を高く評価したのでしょうか。
「始皇帝の死後も、彼の威信は依然として各流派を震撼させた。しかし、陳奢は農民、奴隷、移民の息子であり...
『詩経・暁雅・教公』原文、翻訳、鑑賞
角弓(先秦)角弓は、折り返せるほど美しいです。兄弟とその結婚の間に遠い関係などというものは存在しませ...
黄河の「鉄牛」の役割は何ですか?なぜ1,300年経ってもそのまま残っているのでしょうか?
Interesting History の編集者と一緒に、黄河鉄牛の秘密を探りましょう。黄河の「鉄牛...
古典文学の傑作『論衡』第14巻「断罪」
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
五代孫光賢の「桓渓沙:葦原の風が蜜柑とグレープフルーツの香りを運ぶ」原訳と鑑賞
環西沙·葦原の風がミカンとグレープフルーツの香りを運んでくる第五世代:孫光賢葦原に沿った風がオレンジ...
『学者』の紹介 『学者』の著者、呉静子
『学者』の紹介: 『水滸伝』や『三国志演義』などの不朽の名作が出版されて以来、古代中国の長編小説は知...
小説『紅楼夢』の中で、賈玉村が中秋節に書いた連句の意味は何ですか?
賈玉村は小説『紅楼夢』の登場人物であり、全編を支配する重要人物である。 今日は、Interestin...