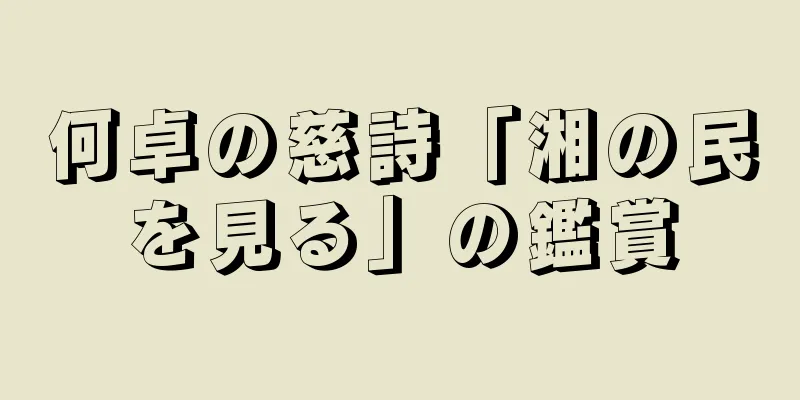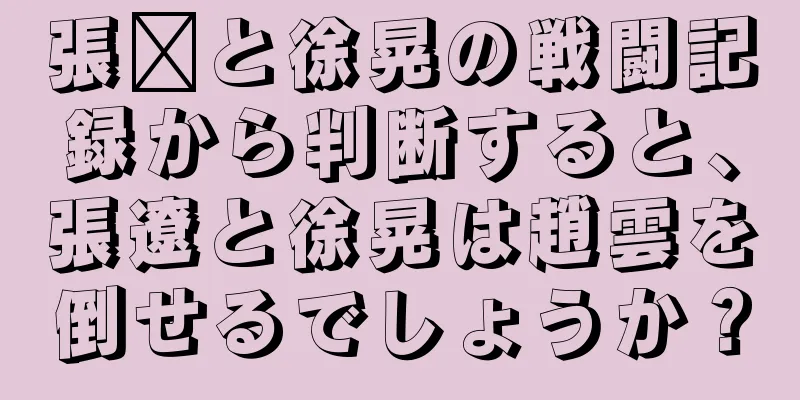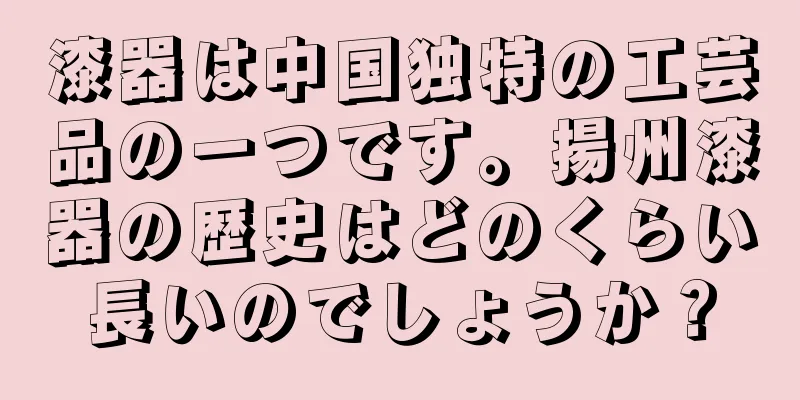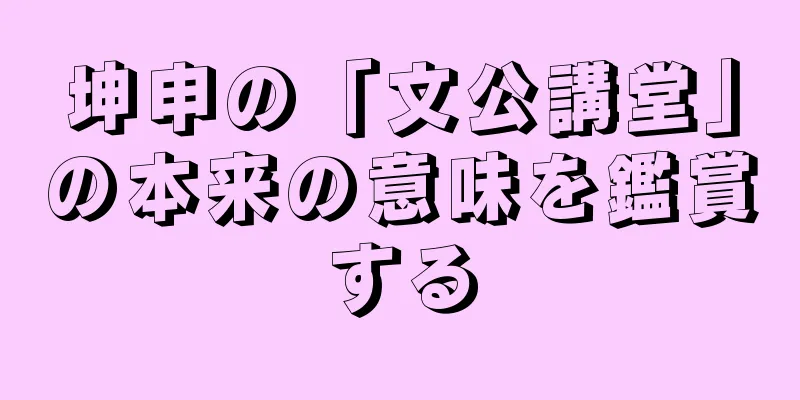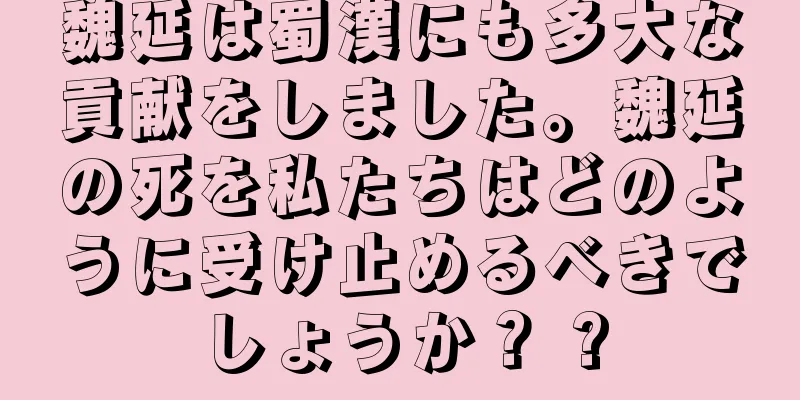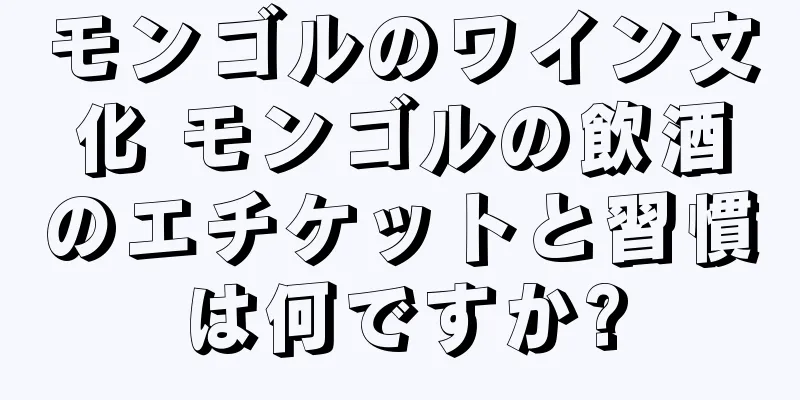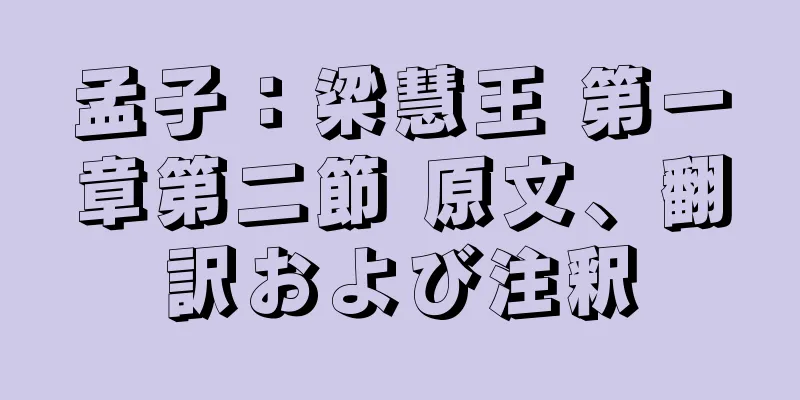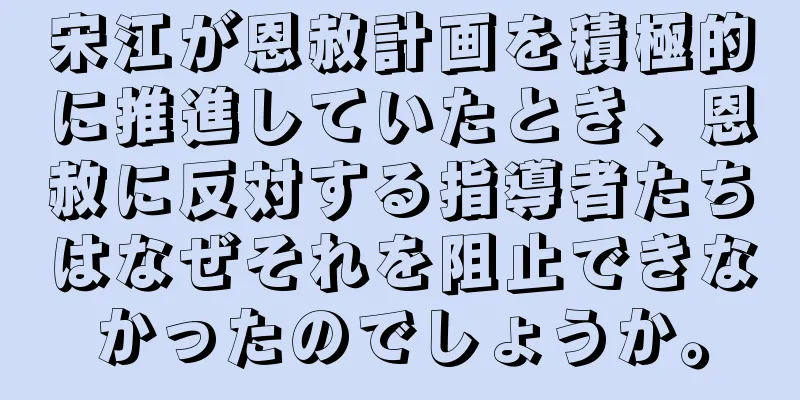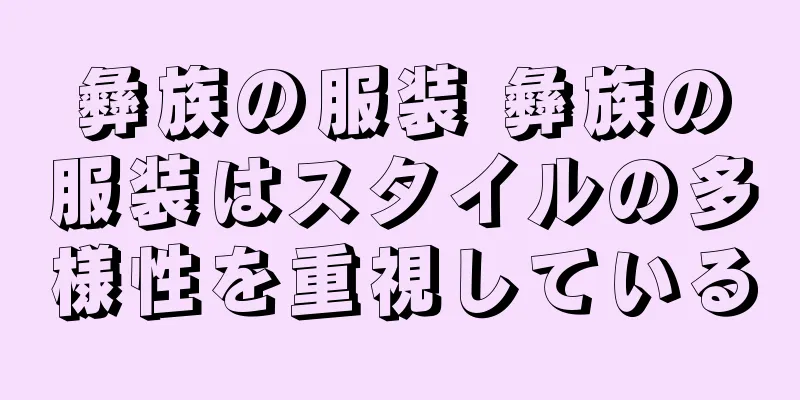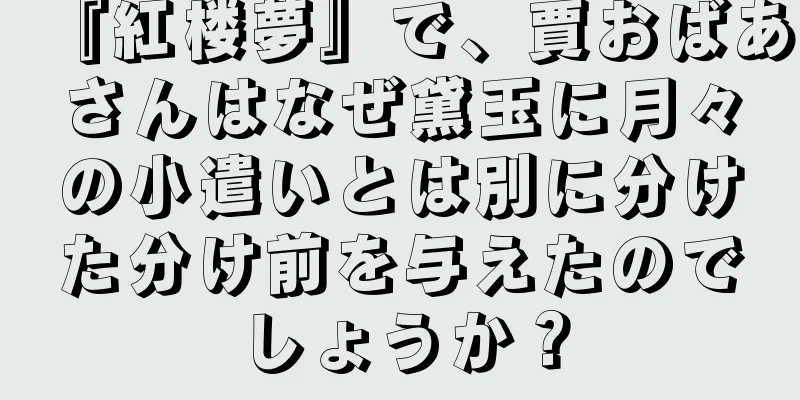「公職や肩書を売る」ことは合法だというのは本当ですか?古代の寄進制度はいつ始まったのでしょうか?
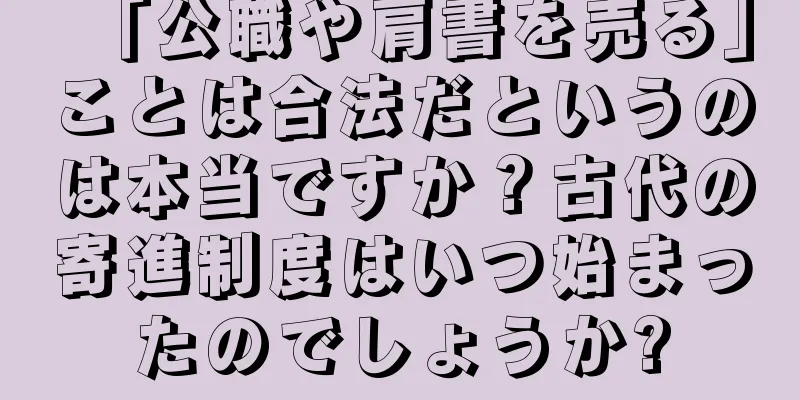
|
今日は、Interesting History の編集者が古代の寄付制度がいつ始まったのかをお話しします。興味のある読者は編集者をフォローしてご覧ください。 公職の売買として一般的に知られている寄付制度は、多くの人から腐敗の一形態であり、容認されるべきではないと考えられています。しかし、この制度は中国の科挙制度よりも長く存在し、良い役割を果たしてきたと言っても、多くの人は信じないでしょう。寄進制度は戦国時代から清朝に至るまで帝国財政の補助手段であり、清朝時代には一時期、税務部の収入の70%を占めていた。しかし、清朝末期になると、朝廷は徐々に寄付金に依存するようになり、これもまた朝廷の信頼性を損ねることとなった。 寄付制度の起源 紀元前242年、秦の国でイナゴの大発生が起こり、広大な農作物が壊滅しました。この甚大な災害に対処するため、秦王朝は「穀物を払って爵位を得る」政策を実施しました。これは、一定量の穀物を払えば爵位が与えられるというものです。しかし、これらの官職の授与は、当初から通常の官僚制度を乱すことなく行われていた。つまり、寄進制度は当初は「家門に栄誉をもたらす」ための手段にすぎず、官僚制度の変更にはならなかったのだ。 また、当時の秦王朝が与えた官位は比較的小規模で、秦王朝には20の位階があり、最下位の8位は、財力と道徳的威信を兼ね備えた庶民のために特別に設けられたものであった。したがって、寄付と引き換えに得られる官職は、一種の社会的名誉、社会的地位に過ぎません。 西漢の時代になると、これらの官職は商品市場で自由に交換できるようになりました。たとえば、東漢の霊帝劉洪は、売りたい官職の価格を明確に表示していました。曹操の父曹宋は太衛の地位を買いましたが、この地位も名目上のものでした。北魏の時代には、8,000 丹の穀物を寄付すると、無力な爵位である侯爵という最高の爵位を得ることができました。 安史の乱の時代には、寄付をすることで知識人の称号である「明静」の地位を得ることができた。宋代には、こうした寄進者たちは実権を持たずに官職に就くことができた。実権を持たないこうした官職でさえも厳しい選抜が必要で、寄進によって誰もがこれらの称号を得られるわけではなかった。 寄付金の選定プロセスを「選定」と呼びます。この選抜プロセスには、経歴の調査、面接、弁論などが含まれていました。明清時代には、選抜プロセスにおける主観的な点数は削減され、明清後期には抽選方式に変更されました。 そのため、秦の時代から始まった寄付制度は、国家がこれらの名誉職を利用して人民と利益を交換するというものでした。明清の時代には制度が調整され、規則はより複雑になりましたが、全体的なプロセスは宋の時代と似ていました。同時に、寄付によってもたらされる利益も増加していました。 明代の寄進制度 明代、朱元璋の時代には寄進制度が一時廃止されました。しかし、「土木事件」の後、軍備を拡張するために、明代の財政赤字は深刻でした。軍備は最も高価であり、朱元璋の時代には税率が厳しく制限されていたため、寄進制度が再開され、一度開かれた赤字はますます大きくなっていました。 1453年、飢饉の救済のため、朝廷は被災地に穀物800石を寄付した者には、帝国大学で学ぶ資格を与えるという進貢学生の令を出した。これらの学生は進貢学生とも呼ばれた。明朝の財政税収は常に比較的低く、農業税に依存していた時代であったため、寄付金は財政収入の重要な源泉となっていた。明代には寄進の範囲が拡大し、正徳時代には、儒学者でなくても寄進によって儒学者の地位を得ることができた。この階級は「礼鑑生」と呼ばれた。さらに、朝貢学生と一般学生の両方に官吏になる資格があり、これは官吏予備軍に相当するものであり、秦以前の時代とは根本的に異なっていた。 なぜ多くの人が寄付で官職を得ようとしたのでしょうか。明代には科挙が3年ごとに行われ、同試、県試、県試、官試、省試、都試、宮試の試験に合格しなければなりませんでした。同試から都試まで順を追うと、20年以上かかることもよくありました。競争の激しい江南地方に生まれた場合は、さらに長くかかることもありました。 明代の有名な学者、文徴明はかつて統計をとったことがある。当時、蘇州には合計1,500人の学生、つまり候補者がいた。3年以内に、そのうち官職に就いたのはわずか3.3%で、これは我が国の公務員の合格率に匹敵する。 梁啓超は「郷は数百人の学生を集め、そのうち数十人を学生に進級させる。省は数万人の学生を集め、そのうち数百人を選抜して准人とする。国全体で数千人の准人を集め、そのうち数百人を選抜して進士とする。そして数百人の進士の中から数十人が翰林学院に入学する」と述べた。科挙の合格率の大きな格差が、寄付制度の長期的な繁栄につながった。 多くの学生は、貢学生になるまで何年も待たなければなりませんでした。当時、学生が貢学生に昇格する過程は「愛公」と呼ばれ、目標を達成するのに何年もかかることを意味していました。寄付金を寄付することで、候補者は同勝から公勝までの長いプロセスを省略し、直接公勝レベルに進むことができました。これは近道と考えられていたため、明代には非常に人気がありました。 寄付は必ずしも試験のためではなく、科挙制度の有機的な一部となり、社会移動の手段となっている。社会移動の主体である者にとって、寄付は科挙と本質的には変わらない。もっと経済力があれば、寄付をすることで郡知事や知事、さらに上の階級の役人になることもできます。これにより、一部の富裕層、特に裕福なビジネスマンが政治活動に参加する資格を得て、政権基盤を拡大できるようになる。 寄付金の多様な使い道 寄付金は軍事ニーズや災害救助のほか、官僚への入職資格や選抜、懲罰の取り消しや軽減、昇進などの社会問題にも関係している。寄付金は社会流動性のツールとして、人材の上向きの流れを促進するだけでなく、予測可能な下向きの流れに対する予防策としても機能する。下向きの流れが発生した場合、寄付金は下向きの流れによって生じる損失を軽減または回避するために使用できる。 寄付は人民自身の利益に基づいて、社会交流の産物となった。清朝では、寄付金は貢学生、皇学生、官職資格、名誉称号、帽子や羽根などの称号に寄付するために使用できました。寄付金は、朗中以下の北京官吏、道夫以下の外官、滄江有基以下の軍官などの昇進に寄付するために使用できました。寄付金は、降格、留任、辞職、元の称号、元の資格、元の羽根の回復に寄付して、降格を維持または防止するために使用できました。寄付金は、省への配属、昇進、記録保管などに寄付するために使用できました。寄付金は、元の欠員の補充、給与の審査免除、実際の推薦、実際の辞職、紹介、告白、検査、回避などに使用できました。名前は多かった。 寄付をすることで、すぐに選抜・採用されるので、就任への良いスタートを切ることができます。選抜された後は、昇進寄付や推薦寄付をすることができ、昇進のスピードを速めることができます。官僚になった後は、試験合格寄付をすることができ、降格を事前に防ぐことができます。何らかの理由で降格・解雇された場合は、復職寄付をすることができ、自己再生の道が広がります。明・清時代には、官職・非官職を問わず多くの役人がこの機能を活用しました。 寄付と科挙はともに社会流動性の重要な手段であり、科挙を相当程度支えている。社会流動性の手段としての寄付には、次のような特徴もある。第一に、長期的な有効性。科挙の役割は出生資格の取得に限定されている。この資格を取得すれば、科挙の社会流動性の手段としての役割は基本的に終了する。社会流動性が生涯に渡って緩和されれば、社会流動性の手段としての寄付は生涯にわたって有効となる。 寄付には下層階級への転落を防ぐ機能がある。科挙同様、寄付は「賤民」を除くすべての社会構成員に開放されている。しかし、寄付は科挙よりはるかに一般的である。科挙に合格するには、完全に科挙に頼って席を確保しなければならない。科挙に合格するには、一定の学力と経済力が必要である。寄付制度では、一定の経済力があれば、寄付して席を確保できる。当面資金を調達できない人も、借金をして寄付することができ、それによって社会的地位を変えることができる。 寄付金の使用の柔軟性。科挙は社会流動性の手段として、厳格な使用条件があります。個人は指定された時間と場所で指定された試験を受けなければなりません。しかし、寄付金は異なります。個人が自分で行うか、他の人が行うかに関係なく、その人は死者か新生児かに関係なく、故郷にいるか外国にいるかに関係なく、社会流動性の手段として、社会のさまざまな構成員のさまざまなニーズを満たすことができます。つまり、庶民は出生や官僚の選抜資格を得るために使用でき、官僚はできるだけ早く昇進したり、地位が低下しないようにするために使用でき、官僚や民間人は先祖に栄誉をもたらすためにも使用できます。 この制度のもう一つの重要な独創性は、寄進制度を科挙制度と併せて考察し、寄進制度と科挙制度の特徴を比較することで、中国の明清社会における寄進制度と科挙制度の機能を生き生きと再現していることである。 寄付は価値があるのでしょうか? 清朝時代には、さまざまな政府機関の規則や規制に精通した銀行の代理店を通じて寄付金を集めることができましたが、代理店手数料を支払う必要がありました。清朝の時代には、浙江省と山西省の代表が主に傅與し、北京の龍福寺と東四牌楼の近くに集まっていた。その中でも、浙江省の代表は、中央政府から地方政府に至るまで江蘇省と浙江省の役人が最も多かったため、最も評判が良かった。 献金した貢物学生は、人事部のポストが空くのを待たなければなりませんでした。清朝では、役人は月に一度解雇されました。喪や病気などで職を離れた役人は、代わりの人を雇う必要がありました。ただし、これらの役職は、正式なルートで称号を取得した進士や柔連が優先され、政府に寄付をした貢物は後回しにされます。 清末期には、多くの白紙寄進許可証が発行された。例えば、光緒20年から同32年にかけて、白紙寄進許可証は合計43万枚発行された。つまり、当時は寄進が過剰に行われていたのだ。寄進許可証の価格は1枚1,000両以上の銀で、乾隆時代の3,000両の銀と比べると大幅に価値が下がっていた。当時、清朝の四等官の年俸は銀105両であり、利益を出すには10年以上かかることになります。合法的な収入であれば、間違いなく赤字事業です。 寄付をする役人が営利を目的として寄付をする場合には、費用を回収するために権力による地代を求めなければならないが、同時に、できるだけ昇進を求めなければならない。なぜなら、官位が高ければ高いほど、収益率も高くなるからである。言い換えれば、寄付制度には腐敗を招く本質的な動機があるのです。 康熙帝の時代、三藩を平定するための軍事資金を集めるため、朝廷は寄付を許可しました。これは歴史上「義茂寄付」として知られています。当時、それは帝室の一部の役職に限定されており、主に国家の犠牲やその他の任務を担当していましたが、実際の権力はあまりありませんでした。さらに、乾隆帝の時代、国が財政黒字になった後、この抜け穴は再び閉じられました。 咸豊年間、清朝は太平天国の乱を解決するために、資金集めを目的とした寄付制度を立ち上げた。首都の六省の郎官以下、地方政府の道台以下の官職はすべてこの制度の対象となり、合計21の役職がこの制度の対象となり、光緒5年まで続いた。 これらの寄付事業は清朝が崩壊寸前だったときに資金援助を提供し、辛うじて乗り切ることができたため、励みとなった。これにより清朝の統治が維持されただけでなく、社会の安定も確保された。 康熙帝の治世中の易茂の寄付は、500人以上の役人が寄付し、合計200万両以上の銀を集め、国庫を実質的に豊かにしました。雍正9年、献銀額は420万両に達し、税務部銀庫収入の42%を占めた。乾隆年間、献銀額は566万両に達し、税務部銀庫収入の39%を占めた。嘉慶9年、献銀額は1083万両に達し、税務部銀庫収入の78%を占めた。献金が次第に清朝にとって欠かせない資金源となっていったことがわかる。 同時に、寄付は社会進出のもう一つの手段でもありました。清朝では、官吏になる手段は世襲、科挙、寄付、推薦の4つしかありませんでした。推薦を受けるには、一般的に地方知事の下で職員として働き、地方知事の昇進を通じて昇進の機会を得る必要がありました。清朝には、雍正年間の李維、田文静、張光嗣、清朝末期の外交官張寅、汚職官僚の処罰で有名になった岑春軒など、寄付によって大きな成功を収めた名官が数多く登場した。彼らは皆、寄付の経験があった。 政府を支えるために寄付金を寄付したこれらの官僚たちは、学者の硬直した考え方から脱却し、実際の政府業務をより柔軟に処理し、間接的に清朝の人材構造を豊かにしました。彼らは新しい知識や新しい考えをより積極的に受け入れ、それが清朝後期の近代化を推進した。 政治的誠実さの観点から見ると、これはほぼ必然的に腐敗につながるため、悪いシステムです。しかし、社会階層の流動性や人材構造の改善の観点から見ると、これは良いシステムでもあります。試験が苦手な有能な人々に才能を発揮する機会を与えることができ、社会全体で人材資源の最適な配分を実現できます。財政援助の観点から見ると、これは良い面と悪い面の両方があるシステムです。さまざまな名義での寄付は本質的には料金であるため、料金を課すことで一時的な問題は確かに解決できますが、それは「料金依存」にもつながります。裁判所は、低い徴収コストですぐにお金を集めることに満足し、適切な金融システムを確立することを求めなくなりました。 |
<<: 清朝時代の退職制度はどのようなものだったのでしょうか?なぜ退職後に呼び戻されなければならない人がいるのでしょうか?
>>: 古代の人々はなぜ死んだ後に物を口に入れたのでしょうか? 「舌を押さえる」という言葉はいつ始まったのでしょうか?
推薦する
岑申の詩「早春に王残夫を西閣に送る使節に随伴」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「早春に使者を西閣に同行させ、王残夫を選挙に送る」時代: 唐代著者: セン・シェン旧友を見送る...
「千の宮殿」と呼ばれる大明宮はいつ建てられたのですか? 「大明宮」という名前はどこから来たのですか?
「千の宮殿」大明宮はいつ建てられたのでしょうか?次のInteresting History編集者が詳...
李白の「清平貂・名花楽美国」:詩全体が巧妙に考え出され、色彩豊かである
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
瑞翁亭の九景とは何ですか? 瑞翁亭は誰にちなんで名付けられたのですか?
瑞翁閣の九景とは何でしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!瑞翁亭は...
スアニ: 古代神話の「竜の9人の息子」の1人。香炉の足元を飾るのによく使われる。
スアンニ(suān ní)は、古代中国の神話に登場する架空の獣です。スアンニはライオンに似ており、動...
胡隠の簡単な紹介 胡隠は古代中国の十大女医の一人である。
胡隠は、建素子、建孫、建孫とも呼ばれ、太白山(陝西省の南部)に住んでいました。胡隠の『五臓六腑補排図...
宋代の詩人辛其基の『醜奴博山路壁記』の原文と鑑賞
辛其記『醜い奴隷 博山の道の壁に書いたもの』次回はInteresting History編集長が関連...
宋の真宗皇帝趙衡には何人の娘がいましたか?実の母親は誰ですか?
宋の真宗趙衡には何人の娘がいましたか?彼女たちの実の母親は誰でしたか?宋真宗趙衡(968年12月23...
康熙帝の第10王子殷娥の実の母親は誰ですか?文熙妃の簡単な紹介
康熙帝の第10王子殷娥の実の母親は誰ですか?愛新覚羅殷娥(1683-1741)は康熙帝の10番目の息...
『新説天下一篇・方正篇』第18条の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの有名な学者の言葉、行為、逸話を記録していま...
七剣十三英雄第3章:呉天宝が宜春の庭で騒ぎを起こし、李文暁が普天鈞を鞭打つ
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
屈原の詩「項夫人九歌」の鑑賞
項夫人の九つの歌時代: 先秦 著者: 屈原皇帝の息子は北岸に降りていったが、その目は暗く、悲しみに満...
『紅楼夢』における幽二潔と賈震とその息子の関係は何ですか?
幽二潔は賈廉の2番目の妻であり、賈震の継母である幽夫人の娘です。 Interesting Histo...
宋代の詩を評価する:昭君元 - 松林の歌。作者はどのような感情を表現しているのでしょうか?
昭君元帥の宋山溝カモメ、宋代の楊万里、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見て...
『紅楼夢』で薛宝琴はなぜ賈屋敷の祭祀に参加したのですか?
薛葆芙芙芙は、曹雪芙が書いた中国の古典『紅楼夢』の登場人物です。以下の記事はInteresting ...