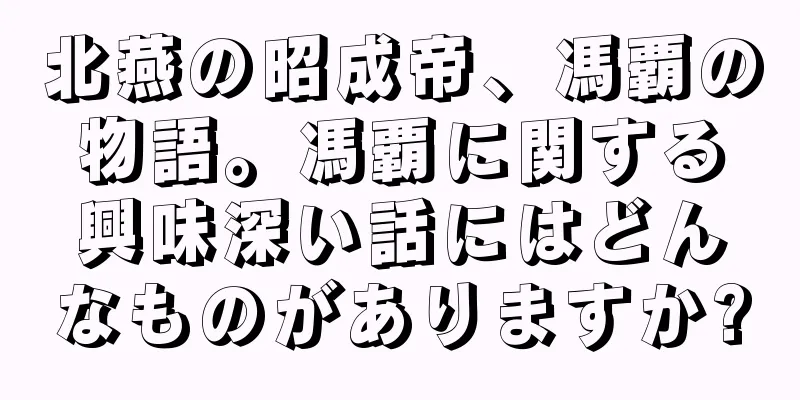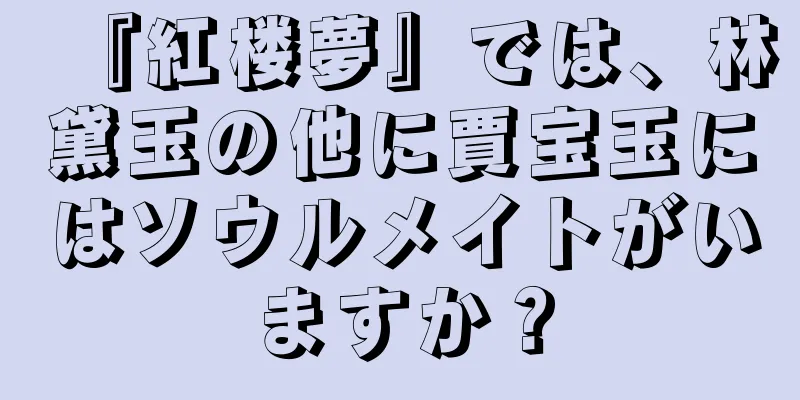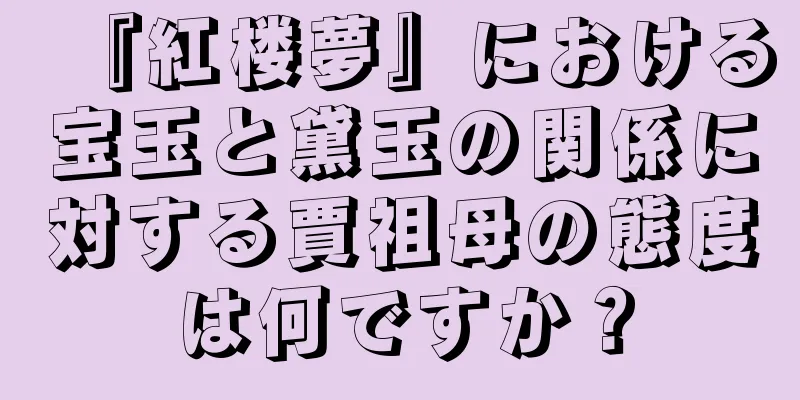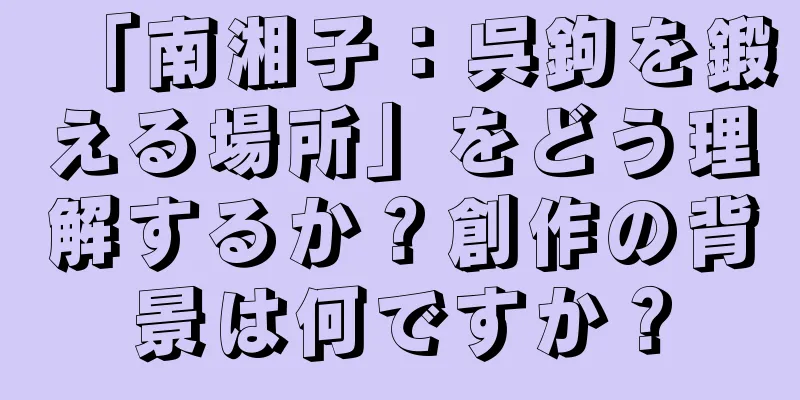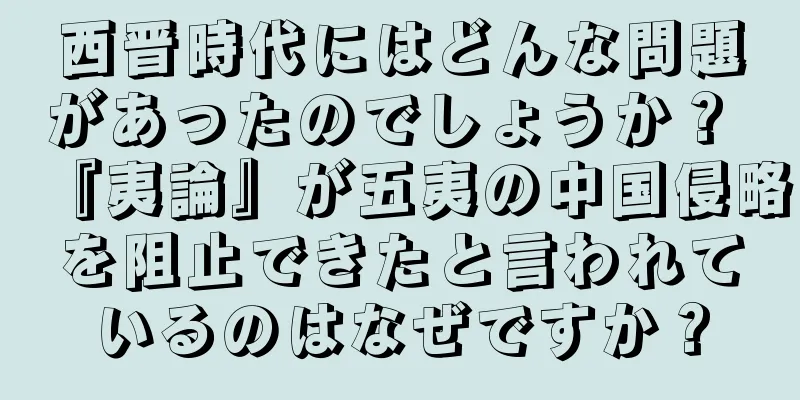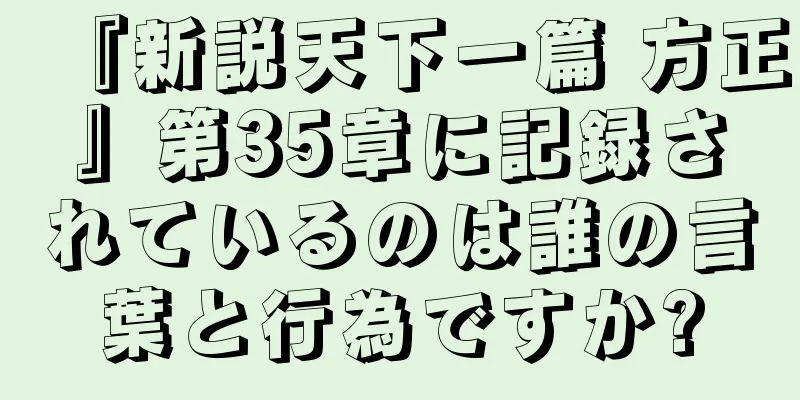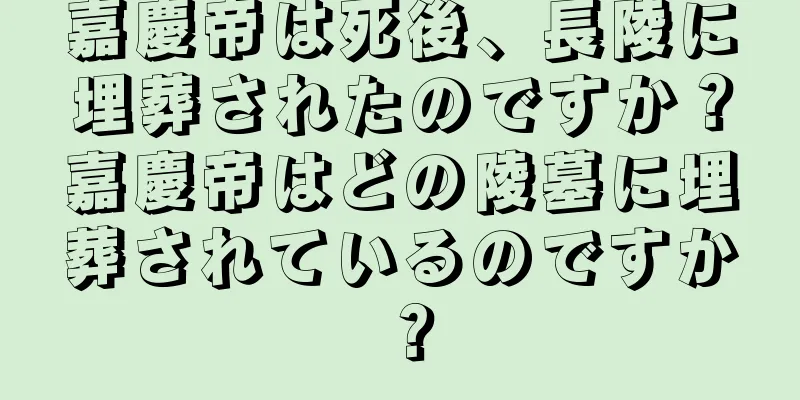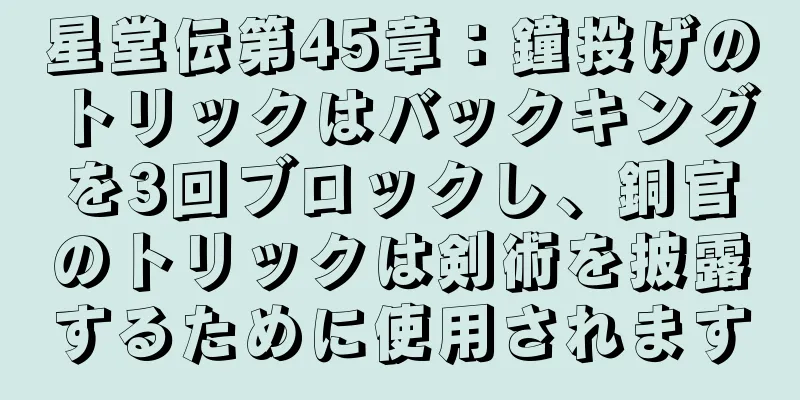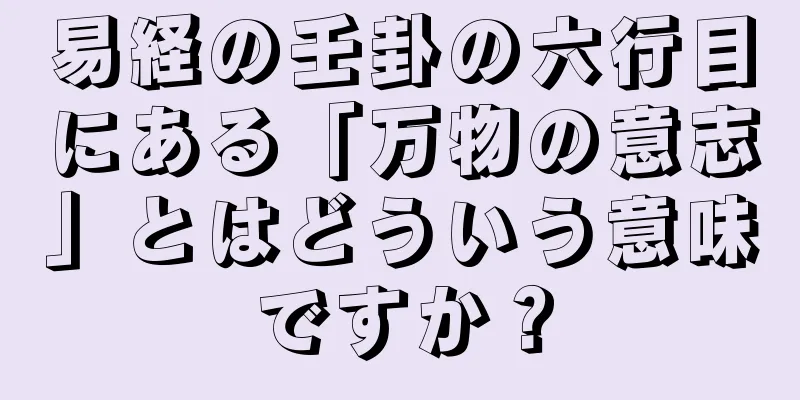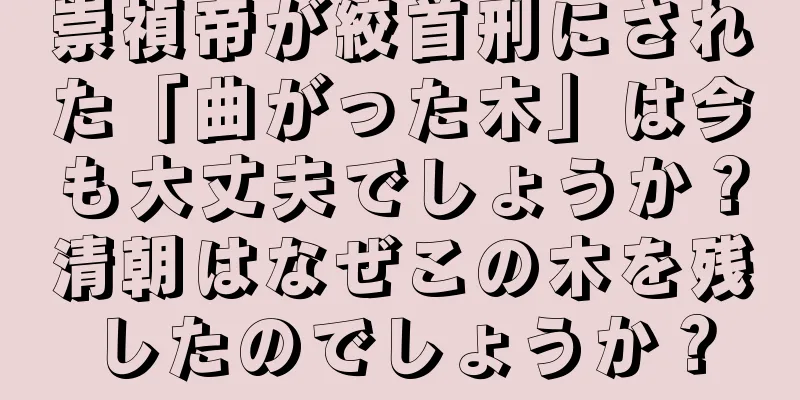さまざまな王朝で官職に就く方法は何ですか?科挙以外に方法はあるのでしょうか?
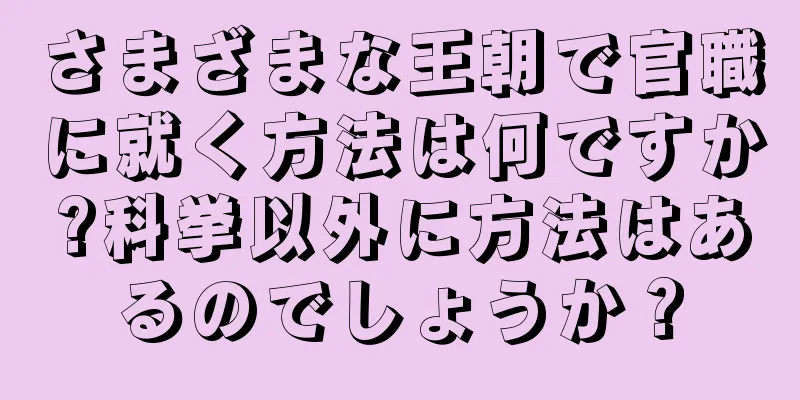
|
各王朝で官職に就くにはどのような方法があるのでしょうか。これは多くの人が知りたい質問です。次の Interesting History 編集者が詳細な回答を提供します。 古代中国では戦国時代以降、君主による文武官の任免制度が実施された。官吏の任命時には印章が発行され、解任時には回収され、同時に官吏への報奨として俸給制度も確立された。 秦の始皇帝は六つの国を併合し、全国に統一された官僚制度を確立した。 「土地を開拓し」、「反乱を鎮圧し」、「農業に励む」ことができれば、誰でも官吏に昇進できる。 『水虎地』雲夢秦簡の「官吏の道」には「人民の能力を審査し、それに応じて官吏に任命する」とあり、秦代における官吏の任命基準を示している。 皇帝が官吏を任命したり解任したりする権限を持つことに加えて、官吏は互いに推薦することもできたが、慎重さを示すために連帯責任を負わなければならなかった。 『史記 范坤・蔡澤伝』には、「秦の法律によれば、任命した人物が優秀でない場合は、その罪に応じて処罰される」と記されている。 漢代には、官吏を任命する方法として推薦と徴兵の二つがあった。試験によって官吏を選抜する制度は漢代に恒久的に存在した制度であり、高祖11年(紀元前196年)の人材を求める勅令から始まった。恵帝と文帝も相次いで「孝行、年長者への敬意、農耕に励むこと」、「高潔で正直な人々」、「率直で率直な人々」を求める勅令を出した。漢の武帝は当初、各郡に「孝行で誠実な」人物を一人選ぶよう命じた。徴兵の習慣は前漢の時代に始まり、後漢の時代には普及しました。皇帝の勅令に加えて、大臣や郡役人も学者を徴兵して官吏として働かせることができましたが、誤った人物を任命した場合は連帯責任を負わされました。 また、試験に合格して官吏となった博士課程の学生は「朗軒」と呼ばれた。 2,000石以上の給与を得ている高官は、3年間勤めた後、息子の1人を郎に推薦することができ、これを「人子」と呼んだ。いわゆる「父親の免職により、息子が郎に任命される」というものだった。漢の武帝の治世中、彼は戦費問題を解決するために「財力に基づいて官吏を選ぶ」政策を実施しましたが、これは実際には官職や称号を売却するものでした。 漢代には、中央官僚と地方官僚の両方が階級に応じて国家から給与を支払われ、さまざまな税金と労働奉仕が免除されていました。前漢の時代には、官吏の選任において出身地の制限はあまりなかった。例えば、会稽出身の朱麦塵は会稽の太守に任命された。しかし、身分に関しては制限があり、商人は役人になることが許されず、王族は高い公職に就くことが許されなかった。漢王朝の役人は皆、長期の任期を重視しており、中には任期無制限の者もいた。例えば、17年間司法大臣を務めた于定国である。 漢代初期には皇帝の中央集権を強化するため、官位が百石程度の下級官吏も皇帝によって任命された。その後、権力関係の進化に伴い、首相は高官の異動権限も持つようになった。漢代の官吏の任命方法には、代理を務めることを意味する「賈」、兼任することを意味する「建」、上書の事務を担当するなど兼任することを意味する「凌」、空席の官吏の地位を引き継ぐことを意味する「行」、1年間の試用期間を経て能力があれば正式に任命されることを意味する「使首」などがある。役人の任命方法は、一方では政府が慎重で適切な人物を任命しようとしたという事実を反映しており、他方では、財政危機や国民への負担を引き起こすような官僚機構の急速な拡大を防いだ。 東漢の時代になると、政治腐敗により、科挙によって官吏を選抜するかつて一般的だった制度は単なる形式的なものになってしまった。葛洪は『包朴子』の「神居」でこう言っている。「選ばれた学者は書物を知らず、選ばれた孝行で誠実な人は父と別居しており、貧しく誠実な人は泥のように濁っており、高位で才能のある将軍は鶏のように臆病である。」 魏、晋、南北朝時代には貴族階級が法的特権を享受し、官吏を選抜する九位制度が生まれた。この制度は、魏の文帝の時代に人事大臣の陳群が確立した九位制度に始まる。つまり、各州に「徳があり知識がある」大中正がおり、各県に中正がいた。彼らは地元の人々を家柄によって評価し、上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下の9つの階級に分類した。最上階級の人は誰でも高い地位に就くことができ、「上階級に庶民なし、下階級に貴族なし」という現象を引き起こした。 隋の成立後、九位制は廃止された。隋の文帝は秀才制度を制定し、各州に毎年3人を選出するよう命じた。煬帝の治世中に進士号が設けられ、官吏を選抜する科挙制度が形成され始めた。 唐代は高度に発達した封建経済と官僚政治に適応するために、官僚を選抜する科挙制度を改善し、あらゆる階層から才能と知識のある人々を広く吸収して政府に参加させました。貴族階級の特権を保障した九階制に比べ、科挙はより民主的で歴史的な進歩であり、中央集権体制の基盤を拡大し、馬周、孫家、張英蘇など、庶民出身の学者を選抜した。 科挙に合格して地位を得た者は、官僚となって官吏に任命される前に、人事省による再試験を受け、雄弁さと文章力の優秀さをテストされなければならなかった。この試験に応じない者は、人事省から定期的に呼び出され、「体格」(体格が強いかどうかを選択)、「話し方」(方言の話し方を選択)、「書道」(美しい楷書体を選択)、「判断力」(文学的・論理的能力を選択)の試験を受ける。試験に合格した者は、適切な官職に任命される。 中央政府の選出権に加えて、地方の州知事や郡知事も部下を任命する権限を持っています。地方自治体から任命されると、人事部が適格選考措置を行います。また、五位以上の都の官吏や各州の知事や監察官には人材を推薦する義務があるが、「間違った人を推薦した」「推薦すべき人を推薦しなかった」場合には懲役1~3年の刑が科せられる。 官僚の予備軍を養成するために、中央政府と地方政府は多くの学校を建設した。唐の玄宗皇帝の治世中、国家の教育法制度と学校制度が「唐の六法」に正式に取り入れられ、各種学校の教師と生徒の数、入学目標、学習内容、教師と生徒の待遇などが詳細に規定されました。唐代の学校は予備官僚の教育と訓練において重要な役割を果たした。 高度専門職の公務員については、特定の選考手続きがあり、例えば技術専門職の公務員は関係部署で選考され、人事省に提出されます。司法官の任命については、人事省と法務大臣が共同で検討し決定し、承認されなければならない。太昌医師の任命は太昌清と協議して決定されなければならない。 公職の任命は法定証明書「高神」に基づいて行われます。唐代の制度によれば、『高神』は一般的に中書省の中書社人によって起草され、一定の規定があった。しかし、19世紀半ば以降、公職は不要となり、公職に就く権限を持つ者は、賄賂の額に応じていつでも記入できる空白の「証明書」を保持するようになりました。 宋代初期、科挙制度は唐代の科挙制度を模倣し、毎年1回の科挙を実施していたが、英宗皇帝の時代から3年に1回の科挙に変更され、それ以降はそれが常態となった。中央権力を強化し、支配基盤を拡大し、人材を積極的に登用するため、科挙の受験者数を増やし、合格すれば官吏となることができ、その順位に応じて官位の等級が定められた。科挙のほかに縁故主義の制度も施行され、王族や高官の子息や親族が縁故主義によって官職に就くことがあり、その数は膨大かつ過剰であった。 洪武15年(1382年)、学者を募集するために3年ごとに科挙を実施し、合格者には官職を与えることが規定されました。官吏になるには科挙のほかに推薦や書記官としての勤務も必要であった。貢献した文官は息子を任命することができ、武官は爵位を継承することができる。明代の代宗皇帝の時代から、草や粟を寄進することで官職を得ることができた。穆宗皇帝の治世中、朝廷に銀を納める慣行、いわゆる「法監」が実施され、官吏の行政は大幅に悪化した。 清朝は依然として、官吏を選抜する「正当な方法」として科挙を採用していた。通常科目に加えて、「博学宏文科」や「経済特別科」などの特別科目が追加されることもあります。宰相府、翰林学院、人事部、礼部などの官職は、科挙に合格した者しか就けなかった。皇帝が直接任命した官吏は「帝監」、大臣が推薦した官吏は「会意」と呼ばれ、功績のあった官吏や殉職した官吏の息子は官職を継承することができた。徳が高く、有能で、誠実な人も政府に推薦される可能性がありました。乾隆帝の治世中、彼は多くの命令を出し、朝廷の役人に徳が高く有能な人を秘密裏に推薦するよう指示しました。 清朝では、官吏になるために寄付金を払う制度も広く実施されました。康熙帝の治世13年、「三藩」の反乱を鎮圧するために、軍事資金の不足を補うために寄付制度が実施されました。3年以内に500人以上の県知事が寄付金を寄付しました。余剰役人が国民に迷惑をかけないように、「在職3年を過ぎたら、献金した役人は有能なら昇進させ、無能なら辞職させる」というルールが作られたが、実際には実行されなかった。献金して官吏になる制度は清朝政府に一時的な財政収入源を提供したが、封建官僚の悪質な拡大を招いた。さらに、「官吏は卑しい地位に満足せず、学者は学問に満足せず、民は分裂して利益を追求する」という状況が続き、官吏の行政はさらに腐敗した。 清朝における官吏の任命方法は以下の通りであった。 代理職:当初任命された職員は2年間(後に3年間に変更)の試用期間を経て、適格と判断されれば正式に任命される。パートタイムの仕事: 大秘書官は通常大臣を務め、総督は陸軍大臣と右翼検閲官を務めます。看護:下級士官および上級士官。追加称号:本来の官職名に加えて、少し上の位の官職名を追加すること。追加の任命:個々の役人に対する皇帝の寵愛。 清朝は、同じ省の出身者が同じ省で官僚になることを禁じただけでなく、たとえ出身地から 500 マイル以内の別の省の出身者であっても官僚になることを避けるよう義務付けました。人事省によって選任されない地方公務員は、知事によって選任され、総督に報告されて承認されるものとする。清朝では、内外の官吏は互いに昇進することができ、一定の任期がありました。 |
<<: 古代の死刑囚は新年に家に帰ることができたのでしょうか?唐の太宗皇帝が囚人を釈放した政策の背景にはどんな物語がありますか?
>>: 明朝はなぜ農業を重視し、商業を抑圧したのでしょうか?農業を重視し、商業を抑制することの本質は何でしょうか?
推薦する
李庸と杜甫の関係:英雄が英雄を称えるように年齢を超えた友情
李勇(ヨン、第四音)、西暦675年に生まれ、西暦747年に亡くなりました。姓は太和、祖先の故郷は広陵...
司馬懿の死後、魏の蜀漢にとって最も厄介な敵は誰だったでしょうか?
諸葛亮の北伐は、三国時代の蜀漢の宰相である諸葛亮が漢王朝を支援して中原を統一するために曹魏に対して行...
「劉公事件」第12章:知事の息子が権力を利用する
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
宋代の詩『西和金陵郷愁』を鑑賞するとき、作者はどのような芸術技法を用いたのでしょうか?
西和金陵郷愁、宋代周邦厳、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします、見てみましょう!...
「緑世春秋・神分蘭」でやり方を知る原則は何ですか?
『緑氏春秋・神分覧』の知度の原理とは何ですか? どのように理解しますか? これは多くの読者が知りたい...
拓跋鈞の発音は?拓跋鈞の生涯の簡単な紹介。拓跋鈞はどのようにして亡くなったのか?
Tuoba Junの発音方法トゥオバ・ジュン拓跋濤(440年 - 465年)は、太武帝拓跋濤の孫で、...
后梁の創始者、呂光についての略歴 呂光はどのようにして亡くなったのでしょうか?
呂光(337-399)、号は石明、ディ族の人で、洛陽(現在の甘粛省天水)の出身。彼は、前秦の太守であ...
少数民族における三国志演義の普及と影響
『三国志演義』は出版以来、漢民族によく知られているだけでなく、少数民族の間でも広く流布され、多大な影...
嫦娥が不老不死の薬を盗んだという神話と伝説:嫦娥が月へ飛んだという神話の簡単な説明
はじめに:古代中国の神話や伝説によると、嫦娥は夫の后羿が西王母に懇願した不老不死の薬を盗み、月宮に飛...
なぜテナガザルは単純ではないのでしょうか?真実とは何でしょうか?
『西遊記』では、花果山は東勝神地の奥来国にあります。花果山は多くの種類の猿を生んだ仙人の山であり、そ...
「美しい女性は短命である」ということわざがあります。古代の4人の醜い女性の運命はどうだったのでしょうか。
周知のとおり、中国の歴史には西施、貂蝉、楊貴妃、王昭君という四人の美女がいます。 「美は短命である」...
北斉史第44巻伝記36の原文の鑑賞
◎ルリン○ 李玄、貂柔、馮維、張邁女、劉貴思、包吉祥、星志、劉周、馬景徳、張景仁、全慧、張思博、張貂...
もち米団子と元宵には何か違いがありますか?湯園は本当に元宵ですか?
今日、Interesting Historyの編集者は、皆さんに質問します。湯圓と元宵には何か違いが...
春節連句と門神の歴史的起源 門神の起源と伝説について
門神の由来:門神は赤い馬に乗っており、家の守り神としてドアに貼られています。門の神様は大きな剣を持ち...
古代人は清明節をどのように祝ったのでしょうか?古代において、清明節は実は食べ物のお祭りでした。
春が来て清明節になると、人々は外出をしなければなりません。また、清明節は多くの季節の珍味が市場に出回...