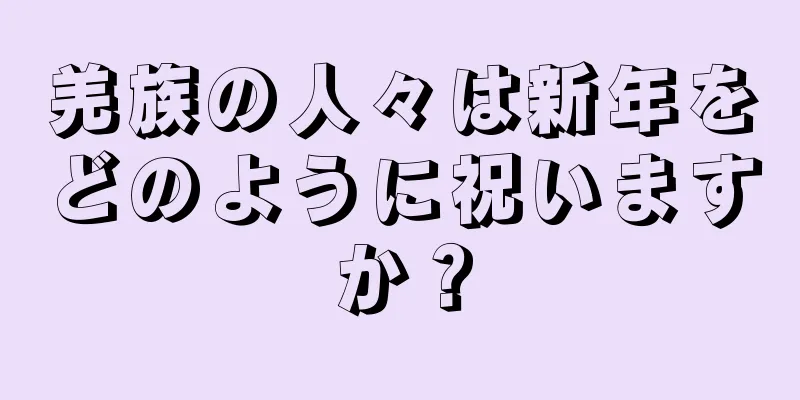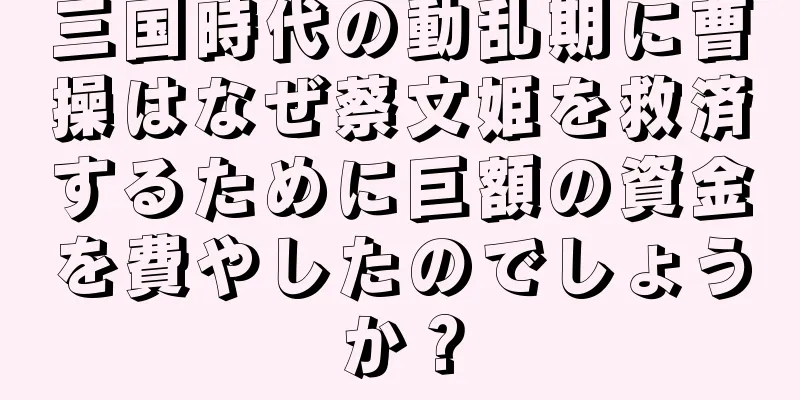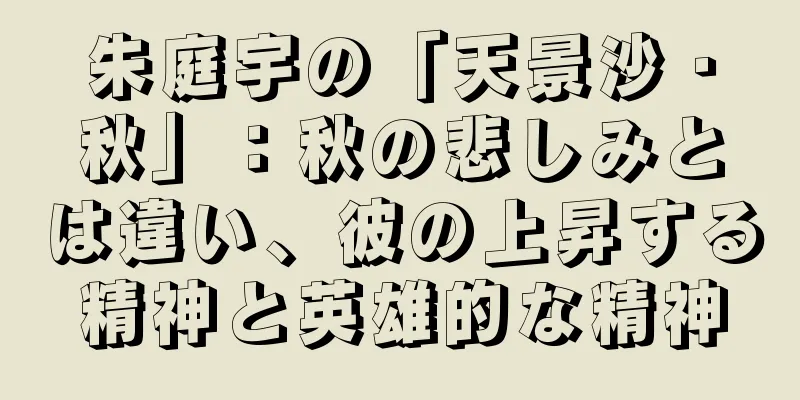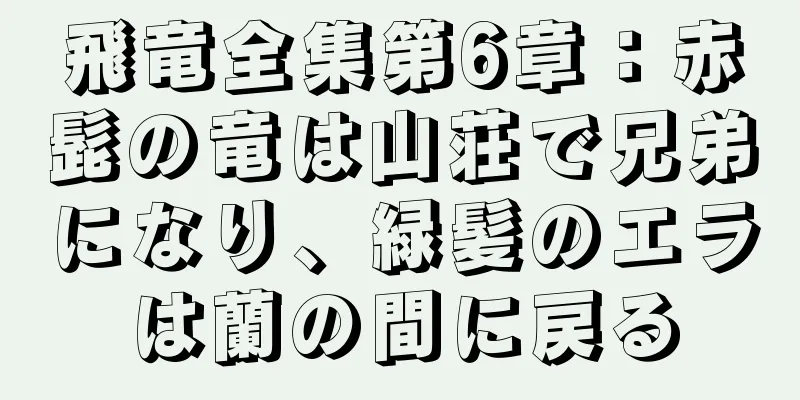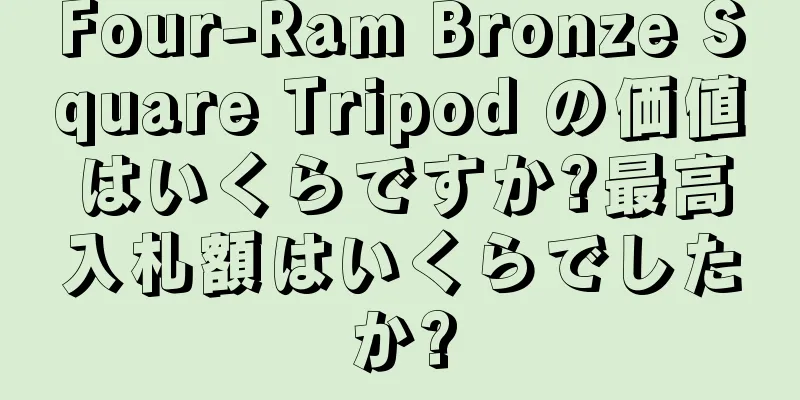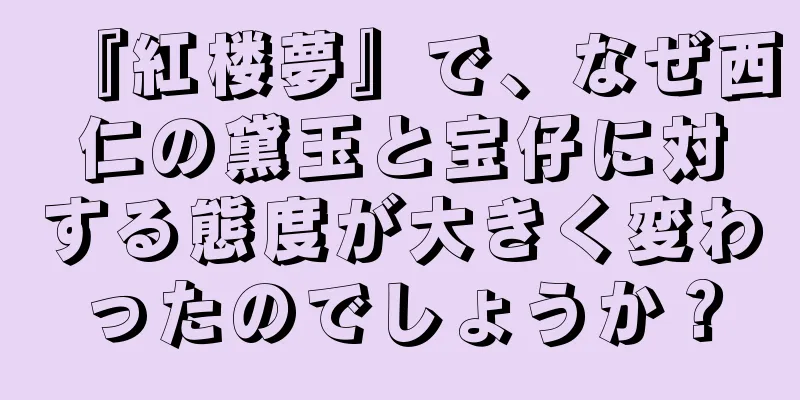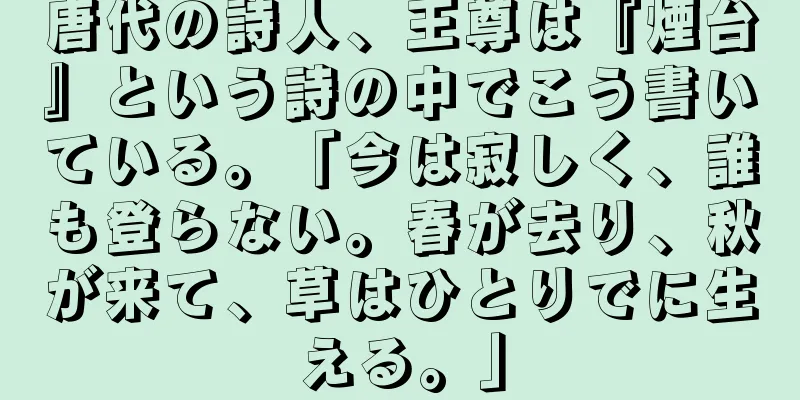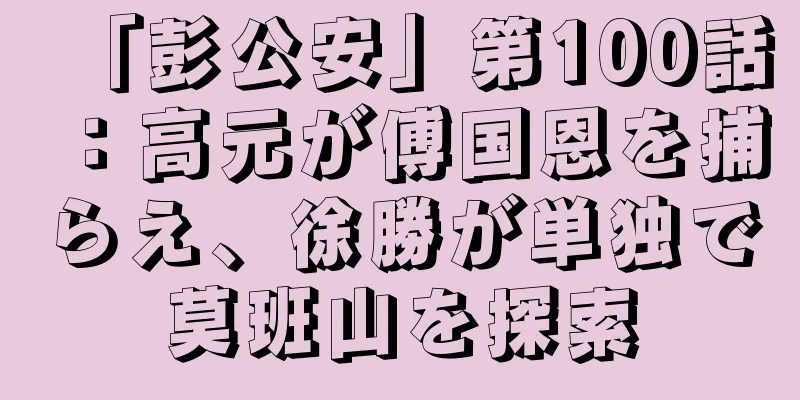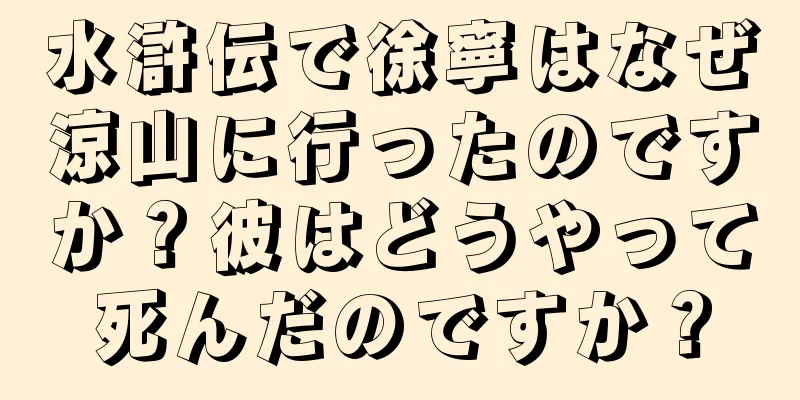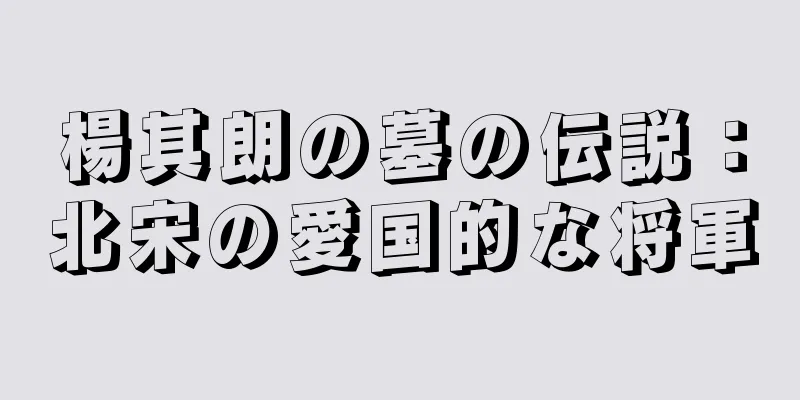明朝はなぜ農業を重視し、商業を抑圧したのでしょうか?農業を重視し、商業を抑制することの本質は何でしょうか?
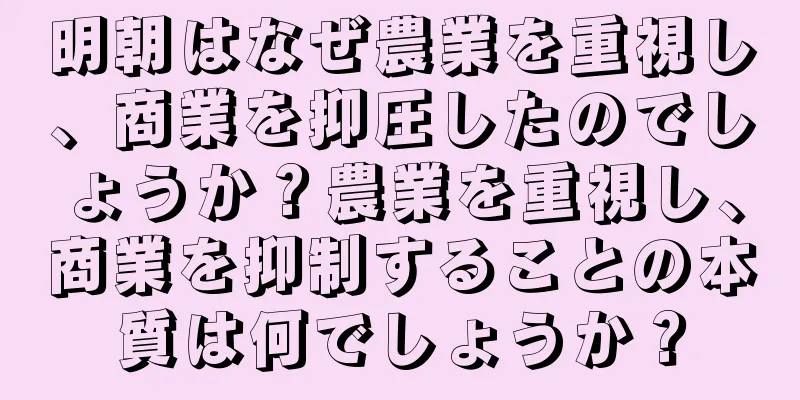
|
今日は、Interesting Historyの編集者が、明朝がなぜ農業を重視し、商業を抑圧したのかをお伝えします。皆さんのお役に立てれば幸いです。 序文;周知のように、封建時代の政権の多くは「農業生産」のレベル向上を重視する傾向があり、「商品経済」を抑制する代償を払ってでもそうすることをいとわなかった。その結果、明代の太祖が実施した「海禁」は、明代の農業重視と商業抑制の表れの一つとみなすのに十分であったと多くの人が考えている。しかし、問題は、元代にはすでに「商品経済」が大きく発展しており、明代初期には明らかに「商品貿易」システムが比較的完成していたのに、なぜ明代の太祖は依然として「農業を重視し、商業を抑制する」のかということです。明代初期に農業が重視されていたのは事実ですが、商業を抑制することは太祖の本来の意図ではなく、単にその時の状況により太祖が一時的に商業を抑制せざるを得なかっただけであることがわかりました。 法家思想の代表である商閻魔の図 「農業を奨励し、商業を抑制する」の本質 まず、「農を奨励し商業を抑える」とはどういうことか理解しましょう。いわゆる「農を奨励し商業を抑える」とは、文字どおりに解釈すれば、「農業生産システム」に基づく「自然経済」を重視し、「商品貿易」に基づく「商品経済」を抑制することに他なりません。 ちょうど戦国時代の法家思想の代表として有名な商鞅が、秦の国で「商鞅の改革」を実施した際、「農を奨励し商業を抑える」という思想をはっきりと打ち出し、「豊かな国では、食料は高価で、非農業税は高く、市場地代は重くならざるを得ない。……そうなれば、民衆は商人や技能を放棄して、土地の利益のために働くしかなくなる。したがって、民の強さは、完全に土地の利益に依存する」と主張したのと同様である。 ——「商王書」第22章 もう一つの例は、西漢の初代皇帝である劉邦です。彼もまた「農耕を奨励し商業を抑制する」という思想を提唱しました。これは「商人は錦、刺繍、絹、穀物、紗、麻、毛皮を身に着けたり、兵士を訓練したり馬に乗ったりしてはならない」という意味です。行間には「商人を蔑む」という不可解な意味さえあります。 ——『漢書・高帝の記録』 「農業を促進し、商業を抑制する」ということは、単に商品経済がもたらす利益を「軽視する」ということでしょうか? 決してそうではありません! 商阳が言ったように、「農民は最も苦労するが、利益は最も少なく、商人や熟練した人々ほど優れていない」。明らかに、彼は「商品経済」がもたらす大きな利益をはっきりと知っていた。では、なぜ商阳は依然として「農業を推進し、商業を抑制する」ことを主張したのでしょうか。その理由は非常に簡単です。「商品経済」の基礎は「自然経済」だからです。 ——「商王書」第22章 明代のビジネスマンのイラスト 考えてみれば、「商品経済」は「商品の交換」とも言えますが、封建時代の「商品」とは何だったのでしょうか?「穀物、雑穀、酒、家具、衣服」でしょうか?結局は「自然経済」に回帰することになります。これらの「商品」に必要な原材料を生み出すのは「農業生産」なのです。 「農業生産」システムの完全性を確保するには、まず国民に「安定した」「生産環境」を提供することが必須である、ということになりますが、これは正しいでしょうか? ということは、やはり「戦争」が絡んでくるわけですが、戦争があるところには消費があり、戦争は何を消費するのでしょうか? 人力の消費に加えて、残りは「食料、武器、衣服」などの「物質的資源」に過ぎず、これらも「農業生産システム」に大きく依存しています。 これを「国境で利益を得る者は強くなり、市場で利益を得る者は富む。従って、戦争をすれば強くなり、休めば富む」というのです。つまり、「農業を重視する」ことで「富農強兵」を実現し、「兵を強くする」ことで「国を強くする」という究極の目的を実現できるのです。 ——『商王書』第22巻 したがって、「農業を奨励し商業を抑制する」という本質は、「商品経済を軽視する」からではなく、当時の政治情勢や時代背景が、「商品経済の発展」に必要な「政治的安定」と「比較的完備した農業生産システム」という外部条件を満たせなかったからであるという結論を暫定的に導くことができる。 『史記・平淮書』の記録にあるように、「天下が初めて平定されると、商人に対する法律は再び緩和された」。前漢の「孝慧・高祖の時代」には、漢の高祖の勤勉な働きにより、民衆のために実施された「回復」政策は初期の成果を上げ、国境は比較的安定していたため、「商品経済」の抑圧をやめるのは当然のことでした。 元朝の創始者フビライ・ハーンの肖像画のイラスト 明代初期の「商品貿易」制度は比較的完成していた。 さて、明代初期の商品貿易システムを見てみましょう。実は、明代以前の元代には、すでに「商品貿易」システムにおける「対外貿易」システムが極めて発達しており、特に泉州、広州、清遠の3つの港では顕著でした。 クビライ・ハーンが泉州に設立した「海関」を例に挙げましょう。史料によると、治元15年(1278年)、クビライ・ハーンは泉州海関の多くの商人を通じて海外に次のような布告を配布しました。「誠意を持って朝廷に来られるなら、私は恩恵と礼儀をもって接し、望むように私と貿易をしてもよい。」 ——『元代史・静粛帝七世』 元朝の創始者であるフビライ・ハーンは、元朝の「対外貿易」制度の確立と発展を強く支持し、「泉州海関」を当時世界最大の「海外貿易港」の一つにしたことがよく分かります。 歴史書には「外国の品物、異国の品物、珍しい宝物、奇抜な玩具などが集まる場所で、各地の豪商が居住し、天下一と称された」と記されており、当時の「泉州海関」の繁栄の様子を忠実に再現していると言えるでしょう。 ——『呉文正全集・第16巻』 さらに、この事例だけでも、元代にはすでに封建時代の商品貿易制度が比較的完成していたことが十分に証明されている。では、明代初期の商品貿易制度は悪かったのだろうか。決してそれほど悪くはなかっただろう。 鄭和の宝船のイラスト 同時に、鄭和が永楽年間に7回西域へ航海したこと、そして彼が乗船した「長さ44メートル、幅18メートル」の「鄭和宝船」は、明代の手工芸産業が決して弱く発達していなかったことを証明するのに疑いの余地がなかった。 ——『明代史・宦官 1』 なにしろ、当時の技術条件のもとで、明代の職人たちが「木造構造」を用いて、全長23.66メートル、幅7.84メートルという15世紀末のヨーロッパ最大のコロンブス艦隊の船「サンタ・マリア号」の数倍もある巨大で頑丈な船を建造できたというのは、まさに「造船神話」ではないでしょうか。 これは、明代初期には、元の「対外貿易」の影響により「商品貿易制度」が比較的整っていただけでなく、独自の「手工業」も同様に発達しており、「商品経済」を力強く発展させるだけの資金力があったと思われる。 明代の太祖はなぜ「商品経済」を発展させず、その代わりに「木材を海に持ち込むことを許さない」と明確に要求し、明らかに「外国貿易」を取り締まったのでしょうか。一体何が起こっていたのでしょうか。 上に述べた著者の「農業を奨励し、商業を抑制する」という本質を組み合わせれば、明代の太祖がなぜ「農業を奨励し、商業を抑制する」のかという本当の答えが簡単に得られると思います。これは、明代初期の政治情勢が安定しておらず、内外に問題があったためです。 静天皇の日本遠征の図 明代初期の政治情勢は、内外ともに問題を抱え、不安定であった。 前述の「孝慧・高太后の時代には、天下が落ち着き、商人に対する法律も再び緩和された」という例のように、元朝が「海外貿易」を盛んにすることができた根本的な理由は、「商品経済の発展」に必要な外部条件、すなわち「政治的安定」と比較的完備した「農業生産システム」を満たしていたことにあった。 歴史の記録によると、元朝の創始者であるフビライ・ハーンは、すでに治元3年(1266年)に「江南を平定したので、海外に事を起こす」という勅令を出しました。これは、1266年までに、北から南へと拡大していた元軍が、元朝の領土をほぼ統一し、徐々に海へと拡大の目標を広げていたことを意味します。それは、後の「元の王静子の日本遠征」という歴史的出来事に似ています。 ——『元代史・伝記 第16号』 これは、元朝内の政治情勢が比較的安定していることを意味する。政権が安定していれば、人民が「農業生産」活動を行うための条件は自然に整っている。したがって、これは「商品経済の発展」のための外部条件を満たしていることに等しい。次のステップは当然、「商品経済」の利点を発揮して、より大きな利益を得ることである。 前述のように、「農民は最も苦労するが、利益は最も少なく、商人や熟練者には及ばない」。封建政権が領土を安定させた後、より大きな利益を得ようと思ったら、「農業生産」だけでは需要を満たすことは絶対に不可能であり、「商品経済の発展」は当然避けられなくなった。 ——「商王書」第22章 明代の将軍徐達の肖像画の図 しかし、明代初期を振り返ると、洪武元年(1368年)の「徐達が元の都に入り、宝物や地図を封印し、宮殿の門を警備し、兵士の侵入や暴動を禁止した」事件の後、明代の太祖は元の「首都」を倒しました。北方の草原、山西、陝西、四川、雲南、貴州など他の多くの地域は、依然として元の残党の支配下にあった。 ——『明代史・太祖二』 つまり、明の太祖による元朝征伐戦争は洪武元年に正式に始まった。『明史太祖三』によると、洪武29年(1396年)になってようやく「燕王が車車山で敵を破り、五梁坡突城で追撃して破り、帰還した」とあり、明の洪武年間の第8次北伐は終結した。明の「元朝残党」に対する攻撃は一時的に終結した。 明代の太祖が軍を率いて北上していた時期、洪武元年(1843年)から、明朝の沿岸地域では倭寇の頻繁な侵略が横行し、「山東省を侵略し、次に温、台、明州の沿岸の人々を略奪し、次に福建の沿岸の諸県を侵略した」と伝えられている。沿岸の商船に対する無差別略奪により、多数の死傷者と財産損失が発生した。 ——「明代史・外国編III」 これは、内外のトラブルを抱えた不健全な政治状況を明確に示しており、明代初期には「政治的安定」の基本条件が満たされていなかったことを意味します。人々が「農業生産」に従事するために必要な「安定した生産環境」は当然のことながら問題外であり、どうして「商品経済」を発展させる時間があったでしょうか。 明代の太祖皇帝の肖像画の図 明代の太祖は農業を重視した そのため、明代初期、太祖は軍事的需要を満たすためにあらゆる手段を講じて「農業生産レベル」の向上を推進することしかできなかった。例えば、太祖はかつて「蘇州、松山、嘉興、湖州、杭州の土地を持たない4000戸以上の世帯を臨洛に移住させ、牛、種子、荷車、食糧などを支援した」。 ——「明代の歴史・食べ物と物資1」 その後、「徐達が砂漠を平定した」とき、「北平の山奥の3万5800戸余りの民を各地の県や警備隊に移住させ、兵士として登録された者には食糧や衣服を与え、民には土地を与えた。また、砂漠で生き残った3万2800戸余りの民を北平に定住させ、254の集落を設立し、1343ヘクタールの土地を開拓した。長江以南の14万人を鳳陽に移住させた。」 - 『明史・食糧・物資I』 これらの事例は、明代の太祖が人々を移住させて「荒地を耕作」させた事例のほんの一部に過ぎません。また、明代の軍事制度である「衛朔制度」には、「各県に軍人居住地を設け、政府から牛や種子を提供する者には10%と5%の税金を課し、自ら提供する者には10%と3%の税金を課す」という「軍人居住地」制度もありました。言うまでもなく、その目的は明軍の「戦略物資」の需要を満たすことでもありました。 ——「明代の歴史・食べ物と物資1」 歴史書に記されている通り、洪武帝時代の明朝は「全国の県・県の軍民が開拓に従事する」という「農業重視」の時代であった。 明朝の海上禁制の図 明代の太祖が「商業を抑圧」 明の太祖が農業を重視していたからこそ、明の太祖が実施した「禁海」政策を「商業の抑圧」と結びつける人が多くいるのです。 例えば、洪武3年、明代の太祖は「太倉・黄渡海関を廃止せよ」という勅令を発布したが、これは歴史書に記録されている明代の太祖が発布した「対外貿易」に関する最も古い「海上禁止令」でもある。 ——『明代史・官人篇IV』 その後に続いた一連の「事業抑制」に関連した禁止措置は、ほとんどが「外国貿易」や「海上禁止」政策に関連したものだった。 例えば、洪武4年(1371年)、明代の太祖は「海岸近くに住む人々が私的に海に出ることを禁じる」という禁止令を出した。 ——『明太子実録・第70巻』 洪武7年(1374年)、明の太祖は福建省泉州、浙江省明州、広東省広州の3つの海関を順次廃止した。 ——『明代史・官人篇IV』 例えば、歴史の記録には「私的に外国の部族と取引する者は厳重に処罰される。外国の香や外国の品物は一切売ってはならない。外国の香や外国の品物を所持しているのが見つかった者は、3 か月以内に全て売却しなければならない」と記されている。 - 『日直録知语』第 2 巻 日本の海賊のイラスト これらの数多くの事例は、太祖朱元璋の「商業抑制」政策がほぼすべて「海上禁制」に関連していることを証明するのに間違いなく十分ですが、太祖が「商業抑制」を主張したことを証明できるでしょうか? いいえ。 明太祖はかつてこう言った。「私は税務部に命じて外国人との交流を厳しく禁止した。…現在、広東省、広西チワン族自治区、浙江省、福建省の無知な人々は外国人と私的に交流して商品を売買することがよくあるので、禁止する。」 - 『明太祖実録·第205巻』 この文は、明代の太祖が「禁海」政策を実施した理由は、単に民衆に外国人との私的な貿易を強制したためであり、この「外国人」とは明代の沿岸部で大混乱を引き起こしていた「倭寇」を指していたことを明らかにしている。 洪武年間の明太祖の軍事行動の焦点は、ほぼ完全に「モンゴルと元の残存勢力」に対する北伐に集中しており、倭寇は沿岸地域に頻繁に侵入したにもかかわらず、散在する小さな「海賊勢力」のグループであったため、この時点で彼らが引き起こした影響は、明政権に深刻な脅威を与えるほどではなかった。 明代の日本の海賊とその船のイラスト そのため、明代の太祖は洪武年間に「倭寇」と戦った際、主に「消極的防御」をとった。しかし、問題は「倭寇はネズミのように島に隠れ、風を利用して侵入し略奪する。彼らは逃げる狼のようにやって来て、怯えた鳥のように去っていく。彼らがいつ来るかは誰にも予測できず、彼らが去った後も捕まえるのは困難だった」ということだった。 ——『明太子実録・第78巻』 明代の太祖は「浙江と福建の沿岸警備隊9隊に660隻の海上船を建造させ、倭寇に対抗するよう命じた」①という特別勅令を出したが、「倭船は小型で、カスピ海に入ってしまえば大夫と海滄は入ることができなかった」②という制約があり、網をすり抜けて明代の商船や漁船、沿岸の船舶を略奪し続ける者が出てくるのは避けられなかった。 ——『明代太祖実録・巻75』①、『明代史・軍事編4』② 商船から略奪した「物資」はどこへ行ったのか? それらは「倭寇」の生存に必要な物資となったに違いない。 このままでは、明朝が倭寇と戦う上で隠れた障害になるのではないだろうか? 明朝の太祖はそうする気があっただろうか? もちろん、なかっただろう。したがって、客観的に見れば、明朝の太祖によるこの行動は、実は「倭寇」と戦う上で一定の積極的な意義を持っていた。 また、それはその後の「海上の警戒が徐々に和らぐ」という好ましい傾向と、鄭和が西方へ航海した際の比較的平和な航海環境の強固な基礎を築いた。 ——「明代史・外国編III」 明朝の初代皇帝朱元璋の肖像画の挿絵 結論 つまり、明朝の「農業重視・商業抑制」については、「農業重視」は事実だが、「商業抑制」については確かに議論の余地がある。結局、明朝の太祖が「禁海」を実施した理由は、実は「倭寇」の排除をより効果的に達成するためであったことは、前回の記事から誰もが分かると思う。 したがって、「農業を促進し、商業を抑制する」という本質からすると、明代の太祖が「商業を抑制した」という主張は実際には成り立たない。あるいは、明代の太祖が「商業を抑圧した」という幻想を抱かせるだけであるが、本質的には「農業を促進し商業を抑圧した」という「商業の抑圧」とは比較にならない。 これらの証拠だけでは、明代の太祖が「商業を抑圧しなかった」ことを証明するのに十分ではないと思われるなら、もう1つの証拠を挙げましょう。明代の太祖はかつて、「私は民から一銭も出さずに百万人の兵士を維持している」と述べました。 ——『明機北略・第5巻』 前回の記事で触れた、明代初期の「衛朔制」軍事制度における「軍租」制度を覚えているだろうか。明代の太祖がこのように言ったのは、基本的に「軍租」に頼って軍の「食糧需要」を満たしていたからである。 明朝の軍隊のイラスト これは、明代の太祖が実際に「軍」と「民生」をある程度分離し、軍隊がある意味で自給自足を達成できるようにしたことを意味します。そうなれば、当然のことながら、人民の間の「農業生産」はもはや「軍備増強」のための主要な供給源ではなくなり、明代の発達した手工業に頼ることで「人民の富裕化」を直接達成するのに十分となるであろう。 この場合、明代の「商品貿易」制度は比較的完成しており、人民は軍事的需要を満たすために努力する必要がなかったため、せいぜい「軍事的需要を満たす」ための保証制度としかみなされないだろう!では、なぜ明代の太祖は「商品経済」を抑圧し、「明代の人民が豊かになる」ことを妨げたのか?明らかに、その必要はなかった。 明代の「商品経済」が正常に発展し、明代の領土が統合されるのを待つだけで、比較的完備した「商品貿易」システムを備えた最終的な繁栄段階に入ることができる。永楽年間の「諸国が朝貢に集まる」という壮大な光景は、間違いなくこの点を証明するのに十分である。 したがって、客観的に見れば、明朝の「海上禁制」、あるいは多くの人が明朝の「商業の抑圧」と呼んでいるものは、実は明朝太祖の本来の意図ではなかった。それは、明朝初期、政権が不安定で、国が内外の難局に直面していたときに、明朝太祖が取った一時的な措置に過ぎなかった。それでも、倭寇と戦う上で非常に積極的な意義があった。 したがって、「農業を重視し、商業を抑圧」するかのようにみえた明代の海上禁漁政策を、単に「社会経済体制」の確立と発展を妨げる消極的な政策とみなすことはできず、当時の一般的な背景に照らして分析し、客観的かつ真の答えを導き出さなければならない。 |
<<: さまざまな王朝で官職に就く方法は何ですか?科挙以外に方法はあるのでしょうか?
>>: 明王朝の財政収入源は何でしたか?なぜ明朝の財政は戦争を支えることができなかったのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』で賈元春が林黛玉に対して抱いた第一印象はどうでしたか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
中国神話の二十八星座の紹介。南の七番目の星座はどれでしょうか?
星秀は、朱雀の南の七つの星座の一つで、七星、星日馬とも呼ばれ、全部で7つの星があり、朱雀の首に位置し...
商阳の妻は誰でしたか?歴史上、商阳は何人の妻を持っていましたか?
歴史上、商阳の妻は誰でしたか?商阳には何人の妻がいましたか?商閻魔大王と言えば、誰もが商閻魔大王の改...
彼は誰ですか?なぜ朱棣は建文帝の支持者をより高い地位に昇進させたのでしょうか?
朱棣は建文帝の支持者を数多く殺害したが、明代の成祖帝が殺害を敢えてしなかったばかりか、彼を味方につけ...
『紅楼夢』で平児は賈廉に対してどのような感情を抱いているのでしょうか?
平児は王希峰の侍女であり、賈廉の側室であった。これについて話すとき、皆さんは何を思い浮かべますか?本...
李和の「裏庭の井戸を掘る歌」:昌吉の詩風の活力と生命力を示す
李和(790-816)、雅号は昌吉とも呼ばれる。彼は河南省富昌県長谷郷(現在の河南省益陽県)に生まれ...
『山中雑詩』の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
山中の雑詩武君(南北朝)山からは煙が上がり、竹林の間から夕日が見えます。鳥が軒先に飛び、雲が窓から出...
康皇后は明代宗皇帝の2番目の皇后でした。なぜ彼女は『明朝史』に記載されていないのですか?
明代宗皇帝の皇后蘇孝航は、朱其余の二番目の皇后である。彼女は庶民の出身で、秦の太子であった朱其余の寵...
羌茶文化 羌茶壺にはどんな種類のお茶がありますか?
麺壺茶は大きさの異なる2つの土鍋で淹れられます。大きな鍋は麺の生地を茹でるときに使います。鍋に水を入...
曹雪芹の『菊花に問う』:林黛玉の高貴で孤高で純粋な性格が表れている
曹雪芹(1715年5月28日頃 - 1763年2月12日頃)は、本名を詹、字を孟阮、号を雪芹、秦溪、...
王維の古詩「沈氏の山荘で泣く」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「沈氏の山荘で泣いた」時代: 唐代著者: 王偉楊珠は泣きに来た、そして桑虎は本来の自分に戻った...
『詩経・小夜・玉璽』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
魚類と藻類(先秦)魚は藻の中にいて、頭が見えています。王様はハオにいるのに、どうやってお酒を楽しめる...
地獄の十王:中国の神話と伝説における地獄の十王の秘密を解明する
はじめに:チャクラヴァルティンの十王。宮殿は冥界の肥沃な石の外に位置し、東の五濁世に直接面しています...
なぜ『水滸伝』では宋江は公孫笙を怒らせるわけにはいかず、彼を信頼できなかったと書かれているのでしょうか?
公孫勝は『水滸伝』の登場人物で、愛称は如雲龍、道教名は易清。次回は、Interesting Hist...
張克久の「小桃花:秋雨涼豆腐城」:時間と空間の豊かさと感情表現
張克久(1270年頃 - 1350年頃)、字は蕭山(陸桂布)、一説には本名は伯元、字は蕭山(堯山唐外...