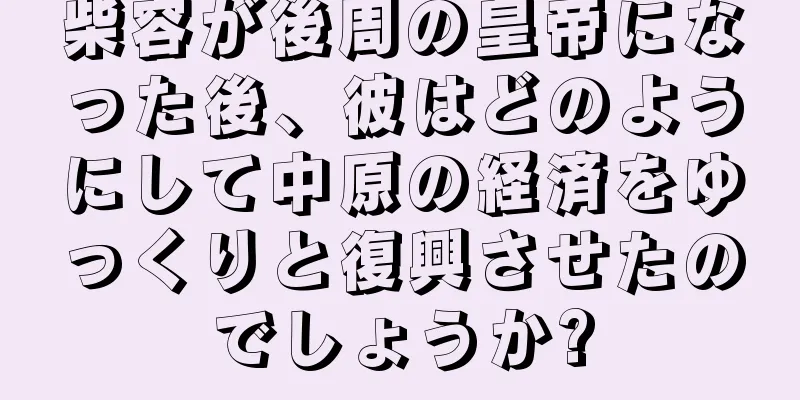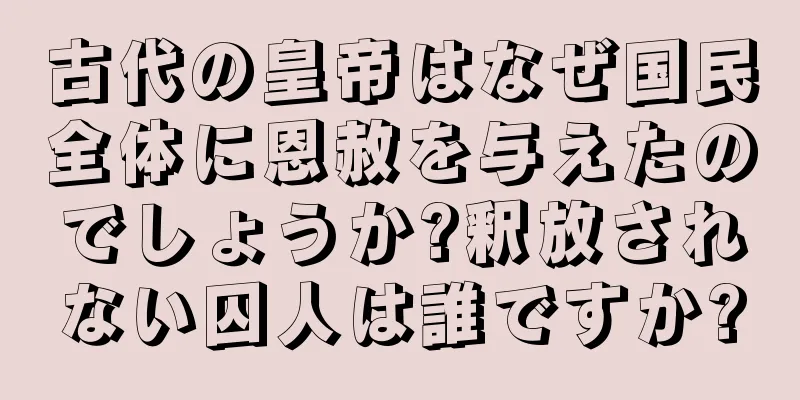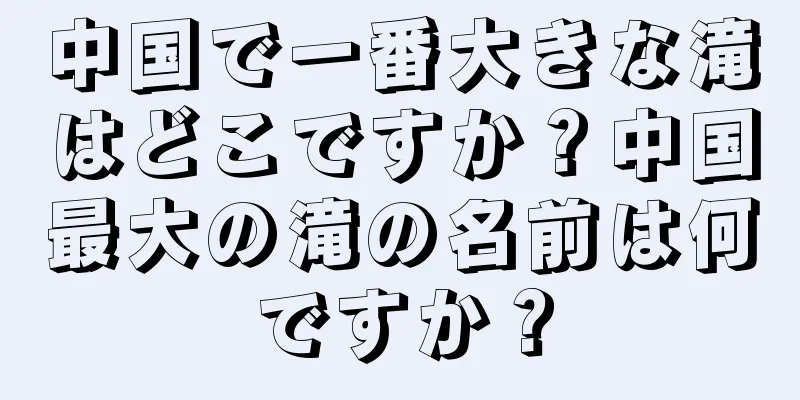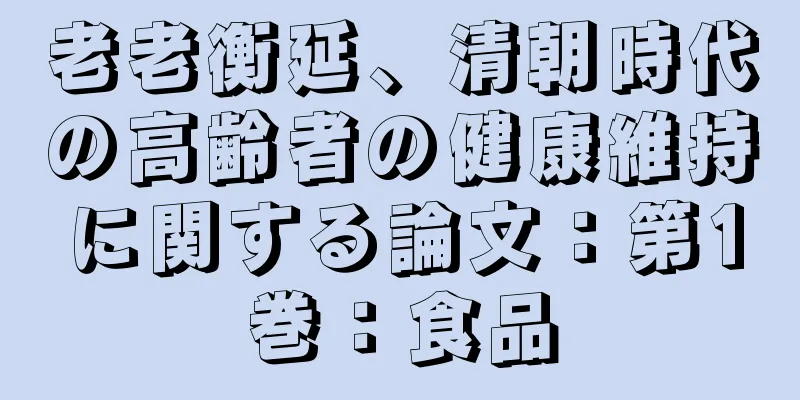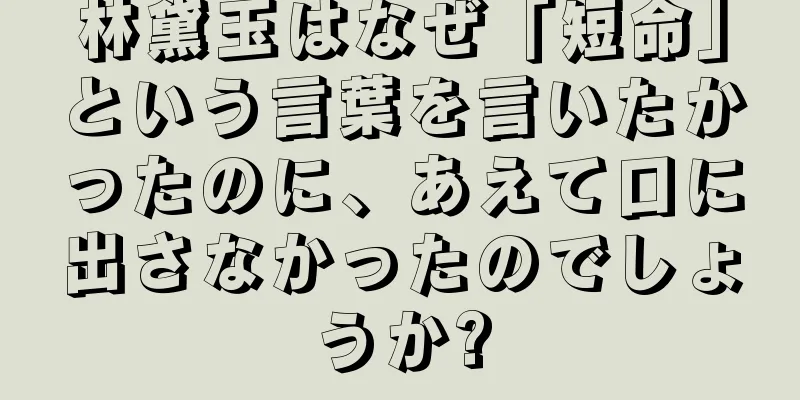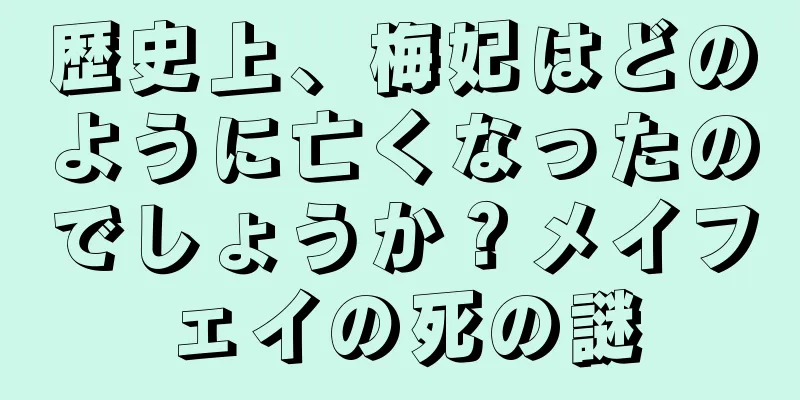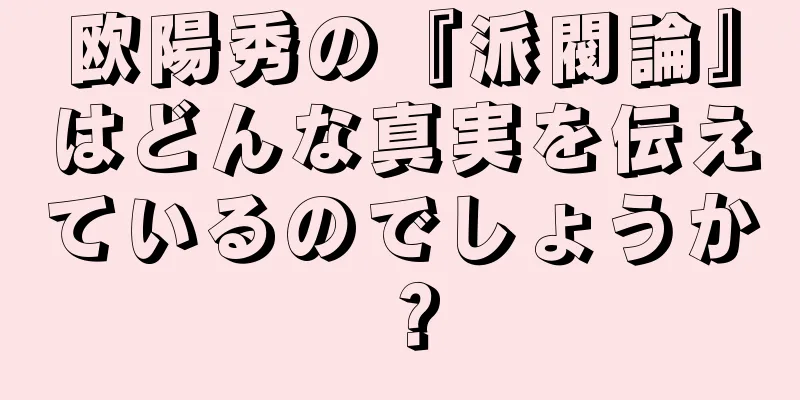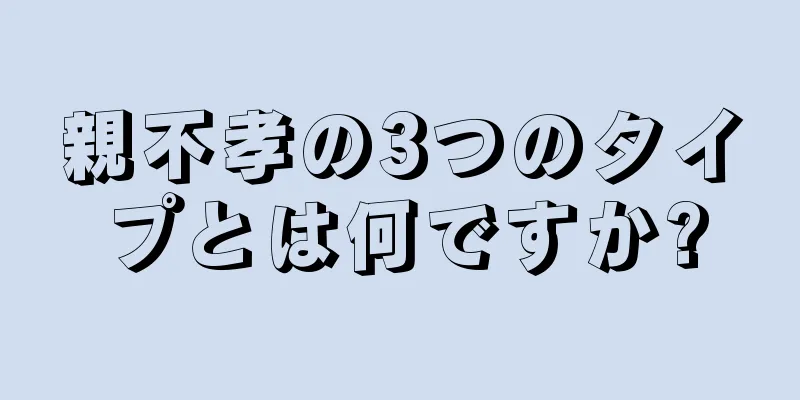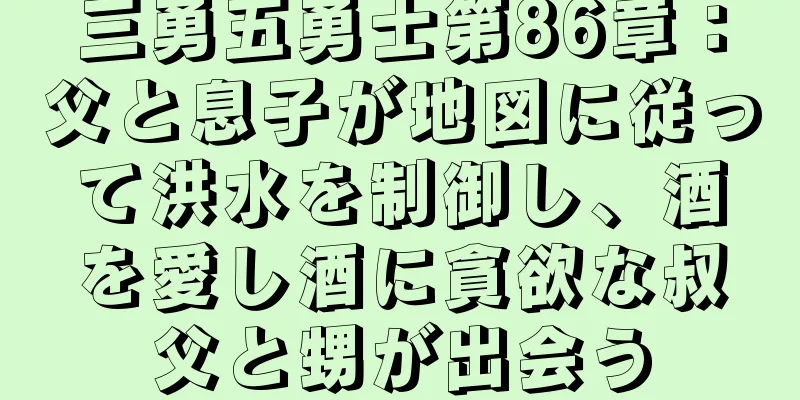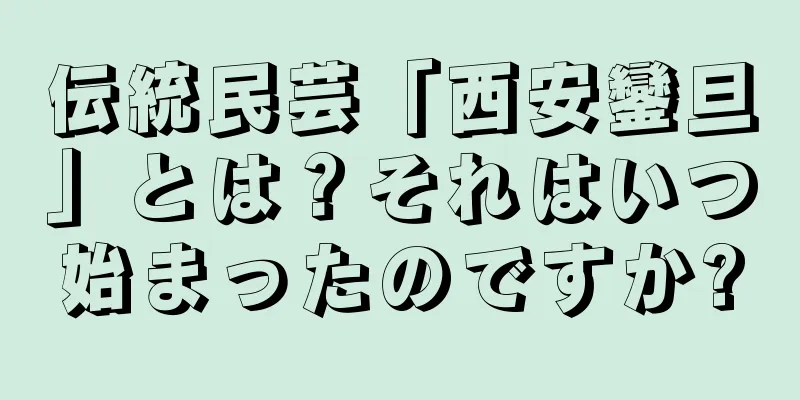商阳の妻は誰でしたか?歴史上、商阳は何人の妻を持っていましたか?
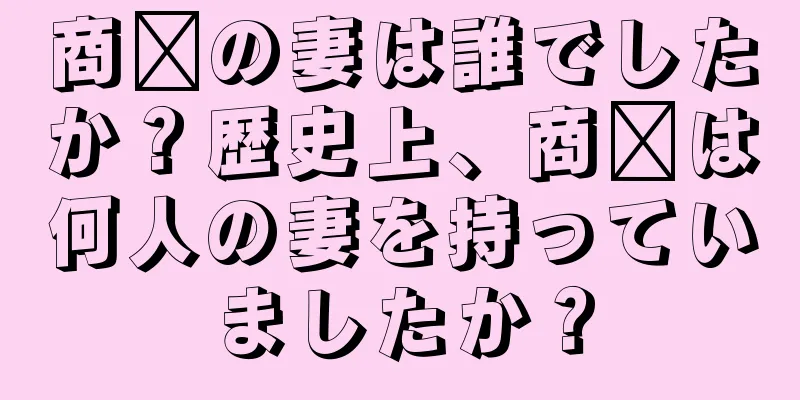
|
歴史上、商阳の妻は誰でしたか?商阳には何人の妻がいましたか? 商閻魔大王と言えば、誰もが商閻魔大王の改革をすぐに思い浮かべるでしょう。商閻魔大王の改革は実は非常に成功しました。秦国を徐々に強くし、秦の始皇帝が六つの国を統一するための強固な基盤を築いただけでなく、中国の歴史における改革の過程を促進し、他の国々も改革運動に追随するようにしました。 商阳は不思議な人物です。人々は彼の政治に注目し、彼の感情生活についてはほとんど語られません。素晴らしい政治的才能と高い野心を持ったこの男の感情生活をお見せしましょう。彼には何人の妻がいたのでしょうか? 商阳は幼い頃、魏の国で育ちました。当時、魏の国は非常に裕福で、楚や斉と肩を並べていました。また、魏の国では商業が非常に発達しており、将棋や食事ができる場所がたくさんありました。その中に、当時最も繁栄していた地域があり、多くの才能のある人々が集まっていました。商阳はよくそこに行って将棋をしていました。商阳の将棋の腕も非常に優れていました。伝説によると、商阳はかつてそこで、知性も美しさも一流の非常に賢い女性に出会ったそうです。 その時、商阳は彼女にとても惹かれていました。その後、二人はよく一緒に将棋をしたり、政治について議論したりしました。女性は商阳をとても尊敬し、老後まで彼と一緒にいることを密かに決心しました。この女性に関する歴史的記録はほとんどなく、この人物が歴史上に実在したのか疑問に思う人もいるでしょう。しかし、別の観点から考えてみましょう。商阳は当時、才能があり、野心的で、将来有望でハンサムな若者でした。彼を尊敬する少女や、一目惚れした女性がいなかった可能性はあるでしょうか? その後、商阳は当時の秦の皇帝で、世界各地から賢者を集める人物であった英屈良と出会った。英屈良は商阳と会い、3日3晩酒を飲みながら政治について質問し、商阳は英屈良の信頼と支持を得た。英屈良の支援を受けて、商阳は改革を実行し、迅速に推進した。 英屈良には妹がいて、彼女も非常に明るく、昔の秦の人々のようで、聡明で情熱的でした。彼女も商阳に一目惚れしました。後に、老いた母后は娘の考えを知り、商阳と結婚させようとしました。商阳は改革を遂行し、政治をよりスムーズに進めるために、王女と結婚しました。 編集者は、この二人の女性は商阳の人生で最も重要な二人の女性であるはずだと推測している。一人は彼の若い頃の初恋の人で、もう一人は成長してからの右腕だった。この秦の公主は文武両道で非常に力があったと言われている。最も重要なのは、彼女は商阳に従順だったことだ。昔から、才能のある男性はロマンチックでしたが、商陽はずっと忠誠心が高い人だったようです。結局のところ、彼の高尚な野望を実現するために、商陽は王女と結婚しなければなりません。さらに、商陽の初恋の人は商陽をより理解できるようでした。彼女は商陽を説得して王女と結婚させ、自分自身も屈辱に耐えました。これは非常に正義の行為のようです。だって、当時は、男が3人の妻と4人の妾を持つのが普通だったでしょ? 商阳は本当に良い人でした。彼の人生は非常に短く、秦の国の改革に全力を尽くしましたが、責任を引き受けることを敢えてしました。彼について何か悪いことを言わなければならないとすれば、彼は最初の妻に対してより同情心を持っていたことでしょう。そのような妻がいれば、夫はそれ以上何を求めることができるでしょうか? 商阳は五頭の馬に引き裂かれるという悲惨な結末を迎えましたが、少なくとも輝かしく幸せな人生を送ったので、人生に後悔はありませんでした。 |
>>: 徐潔の息子は誰ですか?徐潔の息子たちの結末はどうなったのでしょうか?
推薦する
『旧唐書』第36巻には、高宗と中宗の哲学者についてどのような話が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
『マテリアメディカ大全 第3巻 すべての病気と糖尿病の治療』のオリジナルの内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
沈万三の原型が誰であったとしても、なぜ朱元璋による彼の処刑に影響を与えなかったのでしょうか?
明代初期の有名な裕福な実業家である沈万三が太祖皇帝によって処刑を命じられたことは、多くの非公式の歴史...
漢代の十大将軍の一人:魏青、昌平侯、漢の武帝の名将
魏青(紀元前106年? - 紀元前106年)、愛称は中青、河東省平陽(現在の山西省臨汾市)の出身。西...
なぜ賈元春は自分に反論した霊官に対してそれほど寛容だったのか?
元公主が両親を訪ねている間、霊官は元公主と矛盾した。その時、賈強は12人の女優を率いており、彼女たち...
『紅楼夢』で王希峰が賈廉と結婚したのはなぜですか?なぜ彼女はもっといい人を見つけないのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
「肘の緊急処方箋」第 6 巻、第 49 章: 突然の食べ物の窒息と消化不良の治療
『肘の応急処方』は古代中国の医学処方書です。これは中国初の臨床応急処置マニュアルです。漢方治療に関す...
『紅楼夢』で、王夫人と賈正はなぜ最後に疎遠になったのですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
『紅楼夢』で王希峰が賈家で権力を失ったのはなぜですか?彼女がしたこと
王禧峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人です。以下、興味深い歴史の編集者...
第二次世界大戦についての質問:ドイツが敗戦した後も日本軍はなぜ戦い続けたのですか?
日本は1945年8月15日に第二次世界大戦で降伏した。日本は5月にナチスドイツが降伏した後、戦争を終...
焚き火祭りの開会式はどんな感じでしょうか?どのような弔辞を唱えるべきでしょうか?
開会式その後、「ムクンダ」は「聖なる太鼓」を打ち鳴らし、狩猟服を着た十数人の若者が鹿笛を吹いた。皆が...
李公事件第26章:徐国珍の宮廷への誘拐は、最愛の娘である張王石の夢につながる
『李公安』は『李公安奇談』とも呼ばれ、清代の西洪居士が書いた中編小説で、全34章から構成されています...
ヨン・タオの『孫明夫と山を回想する』は、著者の深い創作力を浮き彫りにする
雍涛(834年頃生きた)は、郭君としても知られ、成都(現在の四川省成都市)出身の唐代末期の詩人である...
古典文学の傑作『論衡』第28巻:書評
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
大寒の季節、各地域ではどのような習慣があるのでしょうか?これらの習慣はどのようにして生まれたのでしょうか?
大寒は二十四節気の中で最後の節気です。小寒の15日後に大寒が来ます。大寒は、一年の二十四節気のうち最...