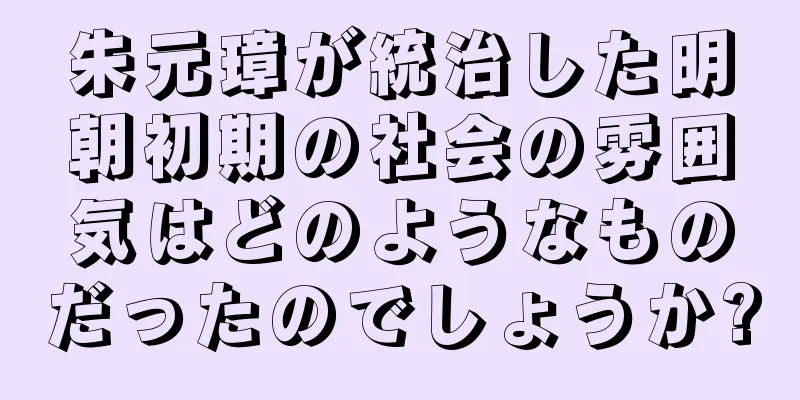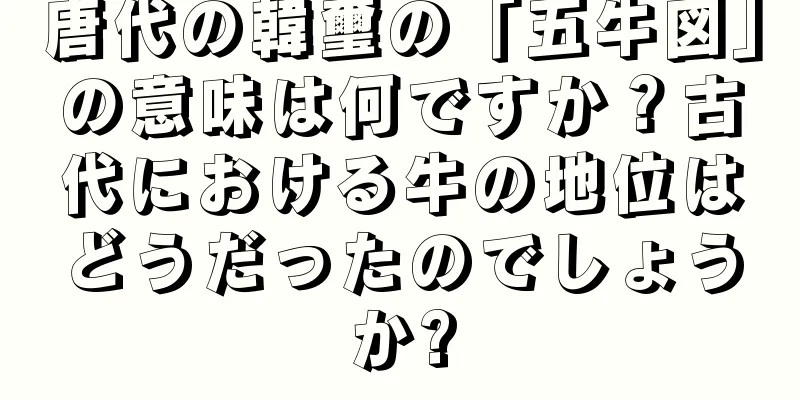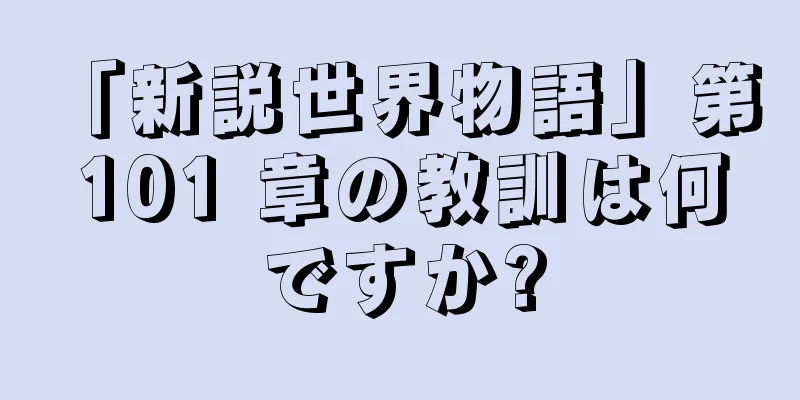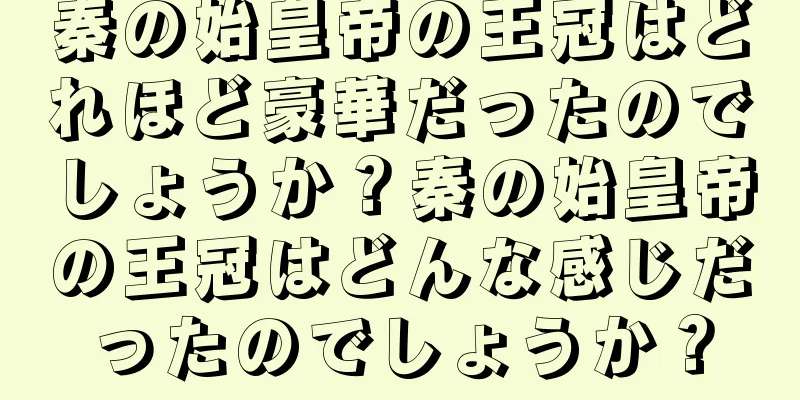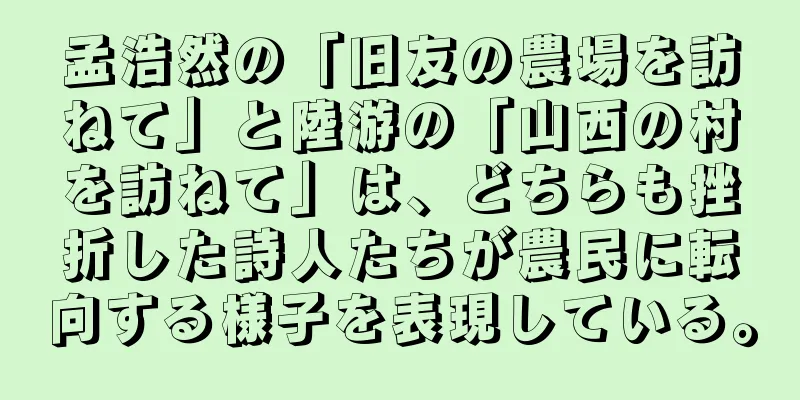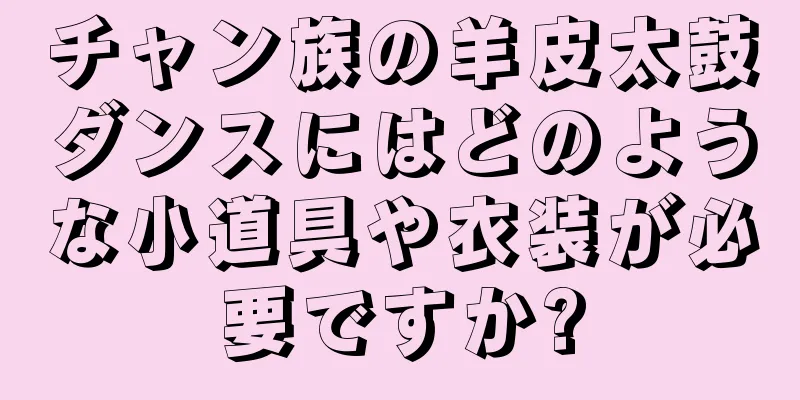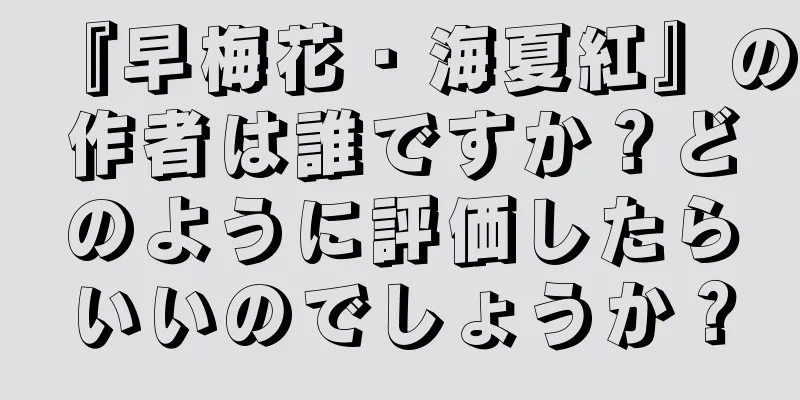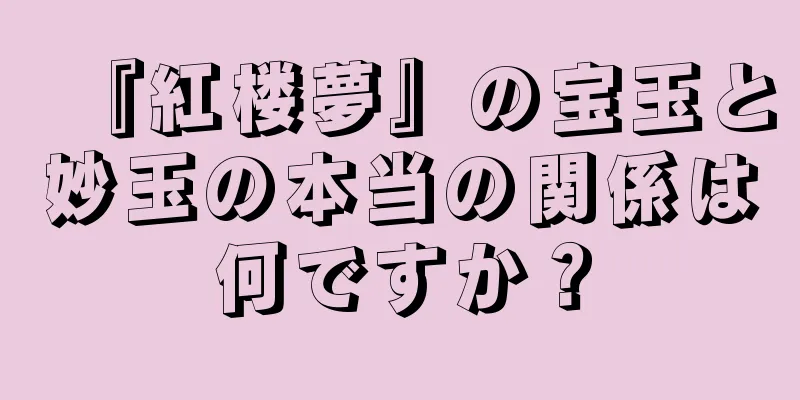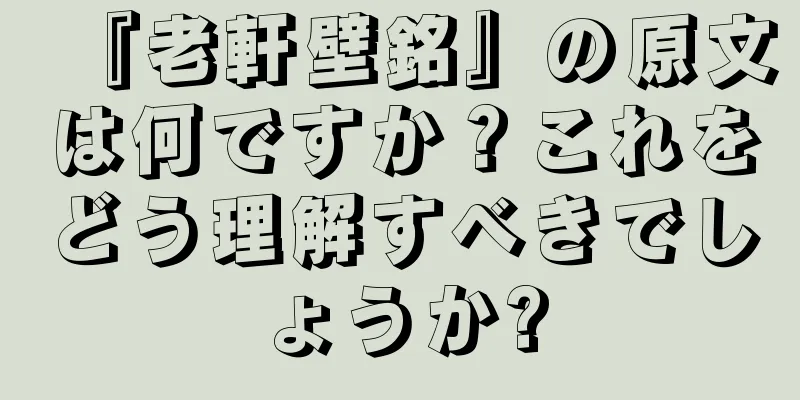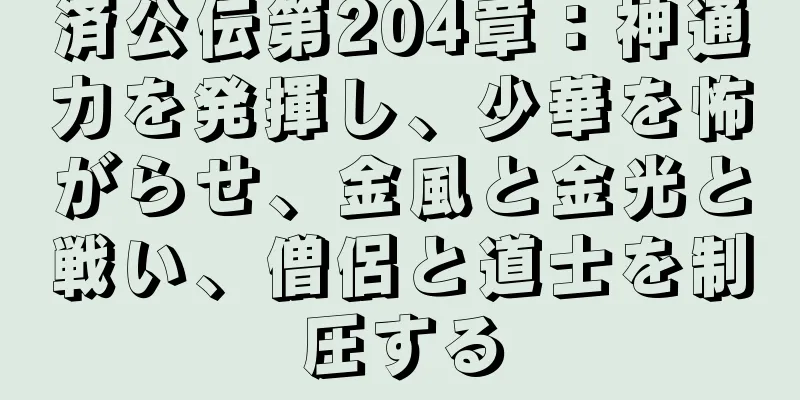北周時代の敦煌壁画には何か特徴があるのでしょうか?
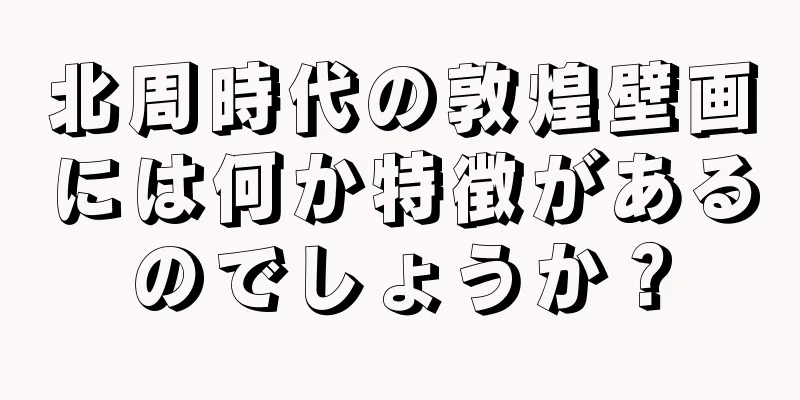
|
北周時代の敦煌壁画には何か特別な特徴がありますか?この頃の敦煌壁画は西域絵画の遺産をまだ残していましたが、全体的には、イメージから芸術スタイルまで、すでに伝統的な漢画でした。今日は、Interesting Historyの編集者が関連コンテンツを皆さんと共有するために持ってきました。 北周時代の石窟は、歴代の石窟と比べると、彫像のスタイルと洞窟の配置に二つの変化が見られます。第一に、西魏時代の「美しく清らかな像」の彫像スタイルが、丸い顔とふっくらとした体つきのスタイルに変わりました。第二に、千体仏の面積が拡大し、もともと重要な位置(壁の中央)に置かれていた仏生涯や前世物語などの仏画が、洞窟上部の従属的な位置に移動されました。その変化は北朝末期の仏教美術の伝播の方向の変化を反映しており、中原仏教が徐々に成熟し、周辺地域に広まっていった様子を体現している。 北朝時代に発掘された洞窟は36ヶ所あり、主に北魏、西魏、北周の時代に発掘されたものです。そのうちのいくつかは北梁時代に発掘された可能性があります。洞窟の種類は主に禅宗窟、中塔柱窟、堂窟などがあり、彩色彫刻は円彫刻と影彫の2種類がある。洞窟の天井と四方の壁は壁画で覆われています。天井と四方の壁の上部には主に天上の音楽が描かれ、四方の壁の下部には夜叉や装飾模様が描かれています。中央の壁には千体仏のほか、主に仏陀の伝記、前世、因縁などが描かれています。北周時代には、この種の物語の主題は増加し、破風や洞窟の天井の四斜面にも描かれるようになりました。釈迦の誕生、四つの門を通る旅、悪魔の征伐などの断片的な描写に加え、連続した内容で釈迦の生涯を描いた長編絵画もあります。ジャータカの物語には、シビ王が鳩と交換するために自分の肉を切り取ったこと、サットヴァが虎の餌として自分の体を差し出したこと、チャンダナ王が自分の首を差し出したこと、シャンジが目の見えない両親の世話をするために山に住んだこと、九色の鹿が人々を救うために自らを犠牲にしたこと、スジャータシャトルが国を復興するために軍隊を動員したこと、スダナ王子が施しをしたこと、シャンシ王子が宝物を求めて海に入ったことなどが含まれています。因果物語には、修行僧が戒律を守るために自殺したこと、500人の盲目の盗賊が仏陀になったこと、須弥陀が仏陀を招いたこと、尼僧の魏妙華が自ら現れて説法したことなどがある。壁画の構成には、単一の正方形または長方形の絵画が含まれますが、横スクロール漫画の形のものも多くあります。北魏の壁画の多くは土赤を背景色とし、青、緑、黄土色、白などの色彩を彩色に用いています。色調は暖かく重厚で、線はシンプルで太く、人物は直立しており、西洋仏教の特徴を備えています。西魏以降、背景色は主に白壁が使用され、色調は新鮮で優雅な傾向があり、スタイルは自由で、中原の雰囲気を醸し出していました。 |
<<: 宋代には仏教が徐々に衰退しました。この時代の敦煌壁画の特徴は何でしたか?
>>: 北魏時代に敦煌壁画の全体的なスタイルにはどのような変化が起こりましたか?
推薦する
清代の『修雲歌』第22章の主な内容は何ですか?
道教の心を捨て去るのは、巧みな議論と儒教の崇拝によるものである。幸いにも、清津七孔は三封の言葉を聞い...
『紅楼夢』の邢秀燕はどんなキャラクターですか?
邢秀燕は『紅楼夢』に登場する邢忠とその妻の娘であり、邢夫人の姪である。 Interesting Hi...
韓愈が『張世義公曹への返答』を創作した背景は何ですか?
韓愈の『張世義公曹への返事』の背景を知りたいですか?これは詩人が広東省陽山に左遷されてから2年目の春...
『紅楼夢』で青文と希仁は問題にどのように対処しましたか?違いは何ですか
「紅楼夢」は女性を主人公にした有名な作品です。以下の記事はInteresting Historyの編...
康熙帝の4人の側室の一人、易果洛妃の簡単な紹介
懿妾(?-1733)は、郭洛洛氏の一員であり、満州族の黄旗の一員であり、大尉の三官宝の娘であった。康...
『中国のスタジオからの奇妙な物語』の公孫霞の章はどんな物語を語っていますか?原文はどのようなものですか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「公孫霞」の原文保定に[1]という学生がいて、県知事になるた...
『ザ・マグパイ・マーダーズ』は面白いですか? 「マグパイ殺人事件」のあらすじは何ですか?
「カササギ殺人事件」の豆瓣スコアはどうですか?「カササギ殺人事件」のあらすじは何ですか?次の興味深い...
『紅楼夢』で賈宝玉はどんな犯罪を犯したのですか?彼は不当に殴られたのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
北宋時代になぜ靖康の変が起こったのか?なぜ「静康恥辱」と呼ばれるのでしょうか?
西暦1127年は特別な年となる運命にあった。なぜなら、この年に歴史上有名な「靖康の変」、別名「靖康の...
老齢の黄忠は、典韋、許褚、顔良、文周と単独で戦うことができたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『漁夫の誇り 趙康景公とともに』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
漁師の誇り:趙康景公とともに欧陽秀(宋代)彼の才能と名声は40年にわたって世界中で高く評価されてきま...
古典文学の傑作『太平天国』:年譜第二巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
「新月拝」は唐代の耿玄によって書かれたもので、恋に夢中の女性の芸術的なイメージを描いたものである。
耿玄(耿玄は、号を洪源といい、唐代の詩人で、大理十才の一人である。生没年や平均年齢は不明である。 『...
陸智深は追放条項に違反していたのに、智深長老はなぜ彼を処罰しなかったのか?
『水滸伝』は中国史上初の農民反乱をテーマとした章立ての小説である。作者は元代末期から明代初期の史乃安...
有名な哲学書『荘子』外篇:秋水(2)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...