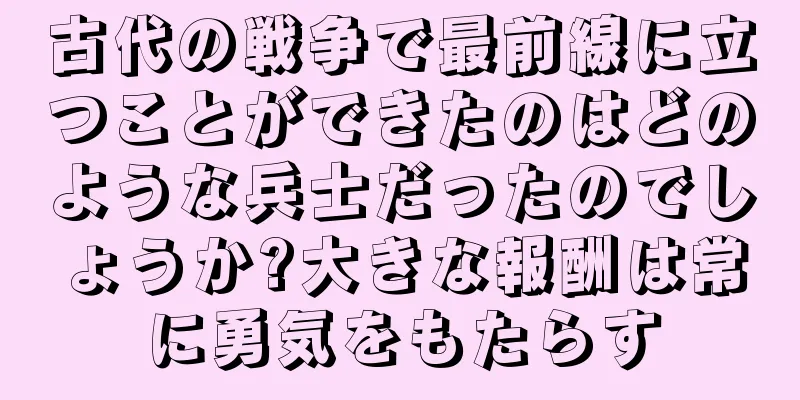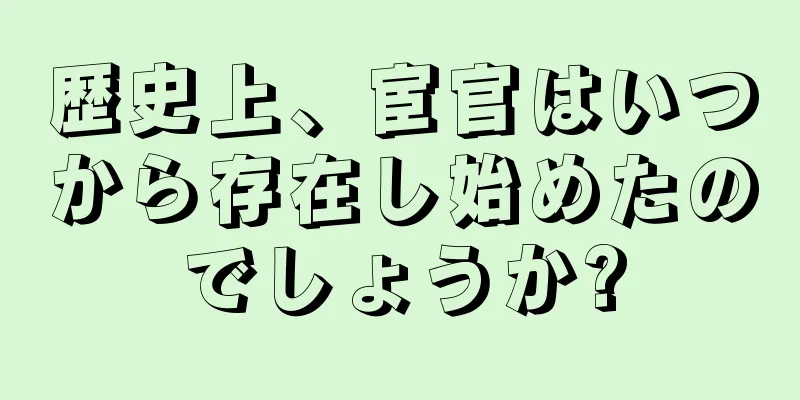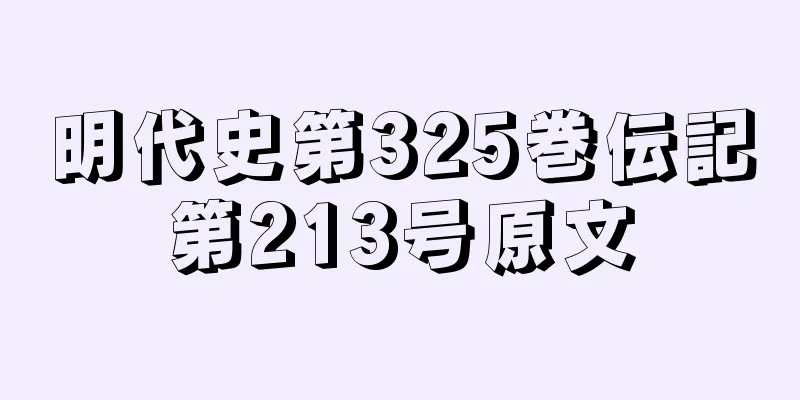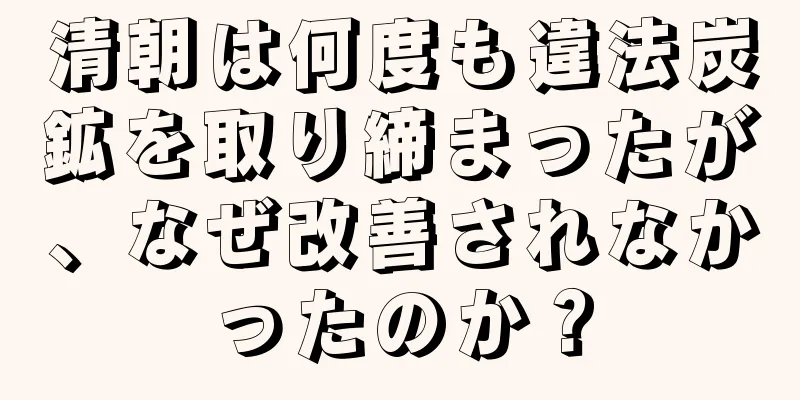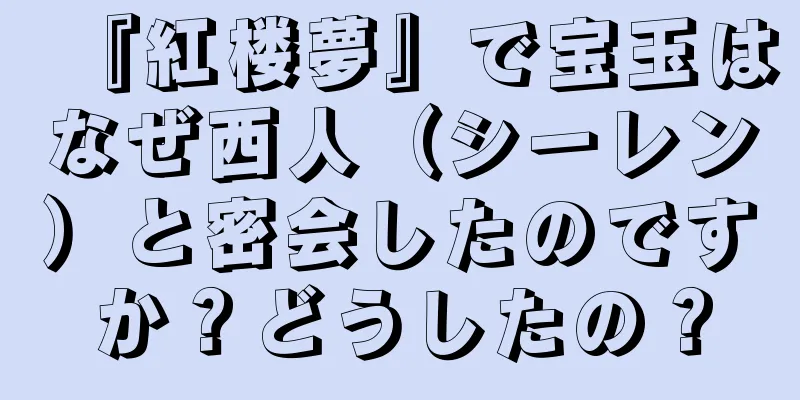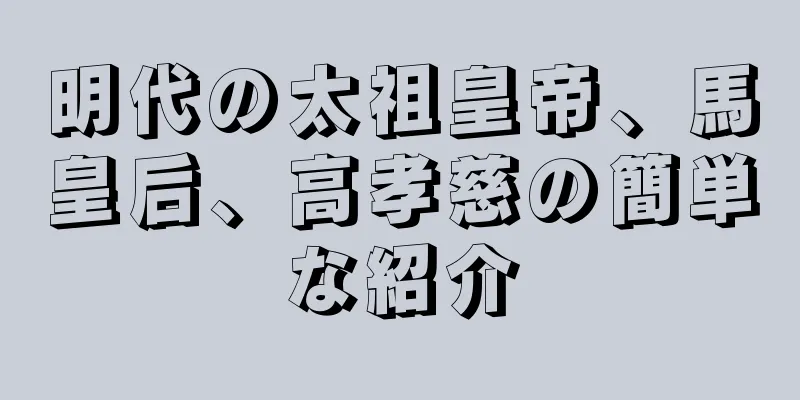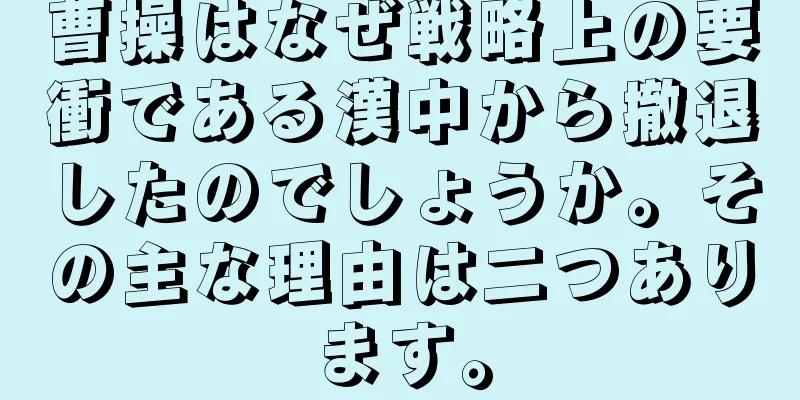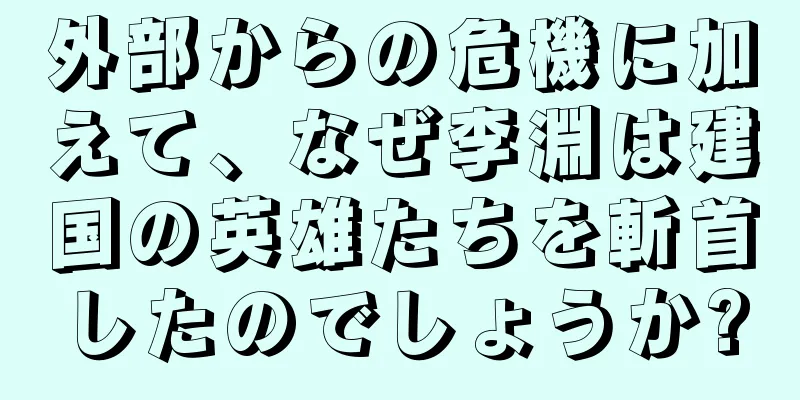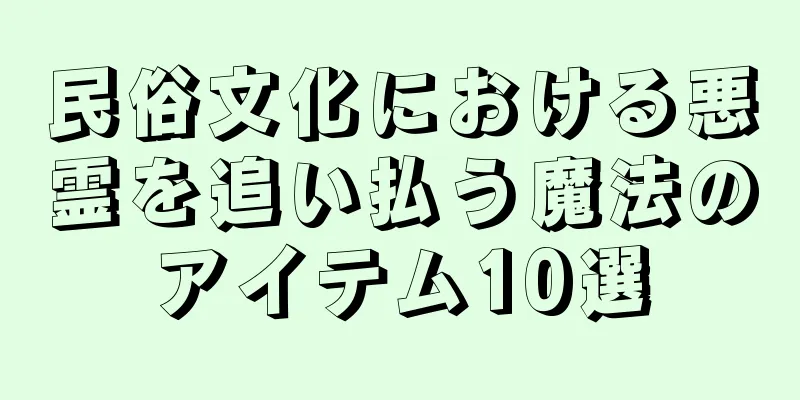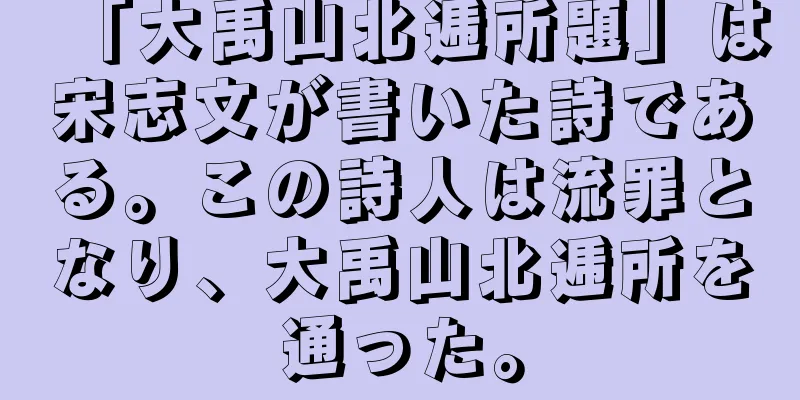歯ブラシはいつ発明されたのでしょうか?古代にはどんな歯の掃除器具があったのでしょうか?
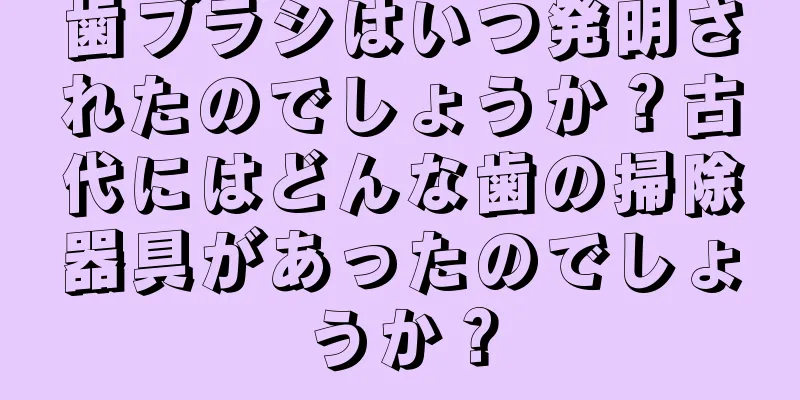
|
今日は、Interesting Historyの編集者が、古代ではどんな歯の掃除道具が使われていたのかをお伝えします。皆さんのお役に立てれば幸いです。 歯は食べたり消化したりするための大切な器官です。歯は雪のように硬くて真っ白です。歯がきれいだと、生活の質が向上するだけでなく、社会活動でも有利になります。このため、私たちの友人たちは子供の頃から朝と夜に歯を磨く習慣を身につけました。実際、古代の人々も歯の健康に大きな注意を払っており、あらゆる種類の歯の洗浄製品が利用可能でした。 古代には、洗練された歯ブラシや高級な歯磨き粉はありませんでしたが、人々はすでに歯磨きを非常に重視していました。 『詩経・衛風・説人』では、美人の白い歯を「瓢箪犀の角のような歯」と表現しています。これに対し、古代人は歯並びが不揃いな状態を「龃龉」と表現し、後に両者の対立や嫌悪の状態を表すようになりました。 『史記 蒼公伝』では、虫歯の原因は「口をすすがないで食べること」に関係していると指摘されています。 上:『紅楼夢』の静止画、リン・ダヤユがうがいをしている 上の画像_古代の歯磨き粉の原料の一つであるポリア・ココス 古代人は一度に歯のケアをするのではなく、段階的にケアを行っていました。 儒教の古典『礼記』には「鶏が初めて鳴いたら、塩水で口をすすぐ」という記述があり、朝、鶏が鳴いた時に塩水で口をすすぐべきだという意味です。東漢の時代になると、人々は歯磨きについてよりよく理解するようになりました。 『金毒全書』によると、「食べ物や飲み物の毒は歯の隙間に溜まります。夜に歯を洗って磨けば汚れが落ちて虫歯になりません。」 「そのため、朝だけでなく夜も歯をすすぐと、歯の健康を保つのに役立ちます。」当時、朝と夜の歯磨きは歯を清潔に保つための生活習慣となっていました。同時に、この本では、夜の歯磨きは朝の歯磨きよりも効果的で、歯に残っている汚れをすべて洗い流すことができ、歯の健康にさらに有益であると指摘しています。 上の画像: 秦漢時代の青銅のパイプのような形、中に動物の毛が入っている 問題は、古代人が歯を磨くのに何を使ったかということです。 秦の時代には、パイプのような形をしていて、丸い穴に布切れを詰めて歯磨きの道具として使われていた青銅製の歯ブラシがありました。それでも、このタイプの歯ブラシは貴族だけが愛用していました。三国時代の古代人は指で歯を磨いていました。上質の塩に浸してスパをすると、とてもオリジナルな気分になります。正確に言うと、これは歯磨きというべきもので、歯をきれいにする行為ではあるが、実際の効果は平凡である。敦煌の壁画「老都茶頭聖図」には、僧侶が左手に水筒を持ち、右手で丁寧に歯を磨いている様子が描かれている。 上:敦煌の壁画「老都頭聖図」では、僧侶が地面にしゃがみ、左手にうがい薬の瓶を持ち、右手の中指で前歯を拭いている。 それに比べると、同時代のつまようじはより進歩しているように見えます。 1976年、江西省南昌で三国時代の東呉の高容の墓が発見され、2つの小品が出土しました。専門家の調査により、小品の一方の端は耳かきで、もう一方の端は爪楊枝であることがわかりました。小品は小さいながらも非常に実用的でした。 西晋の学者陸雲は、弟の陸季に宛てた手紙の中でこう書いている。「ある日、曹公の所持品の中に爪楊枝が一つありました。今、あなたに一本送ります。」陸雲が弟に贈った爪楊枝は、曹操が使っていた爪楊枝だった。当時、つまようじを贈り物として贈ることは、流行でありエレガントなトレンドでした。二つの時代のつまようじには共通点が一つあります。両方とも純金で作られているということです。現代の竹製や木製のつまようじはあまりにも低品質です。 上の画像: 古代のつまようじ 歯磨きの効果が理想的ではないのは、良い歯ブラシを使っていないことが原因です。実際の歯ブラシはインドからの「輸入品」です。インドの仏教僧侶は食後に歯を磨く習慣があり、これは仏教の戒律で義務付けられています。観音菩薩の瓶には水のほかに、水を撒いたり歯ブラシとして使われたりする2本の柳の枝も入っています。玄奘三蔵は『大唐西域記』にも同様の記録を残している。帰国後、彼はインドから木製の歯ブラシを持ち帰り、柳の枝を使って改良しました。 中国で仏教が普及するにつれて、古代の人々も柳の枝で歯を磨き始めました。まず柳の枝を水に浸して膨らませます。そして歯磨きのときに、浸した柳の枝の片方の端を噛み切ります。柳の繊維が広がってブラシになります。それを塩に浸すと、すぐに歯磨きの効果が感じられます。これが「朝に噛む歯木」ということわざの由来です。 柳の枝のほか、イナゴの枝、桃の枝、葛の蔓も歯をきれいにする効果がありますが、苦くて辛い味は本当に不快です。この目的のために、唐代の医学書『外大密用』には、歯磨き粉に似た秘伝のレシピが記されています。「ショウキョウ9グラム、トウキ9グラム、モウ本9グラム、アサルム9グラム、沈香9グラム、含水石18グラム。薬を細かく砕いて粉にし、粉をすりつぶしてふるいにかけます。毎朝、柳の枝を柔らかくなるまで噛み、薬を塗って歯を磨きます。歯は香りがよく、滑らかになります。」 上の画像: 唐代後期に柳の枝で作られた歯ブラシ 時代の発展とともに、歯の掃除用具は常に改良され続けています。文豪蘇東坡は松脂と松脂を原料として、乾燥させて粉砕し、細かい粉末をふるいにかけて「蘇の歯磨き粉」を作りました。この歯磨き粉は歯を磨くためではなく、口をすすぐために使います。さらに、蘇東坡は濃いお茶でうがいをする独自の方法を編み出しました。食後に濃いお茶を数口飲むと、脂っこさと味が和らぎ、歯がきれいになり、香りも残ります。北宋時代の医学書『太平聖会方』には歯磨き粉について「柳の小枝、イナゴの小枝、桑の小枝を煮てペースト状にし、生姜汁、アオイなどを加えて歯を磨く」と記されています。これが薬用歯磨き粉の原型です。 南宋時代には、歯ブラシを専門に製造・販売する店が登場しました。南宋時代の学者、呉子牧は『夢記』の中で杭州の生活を次のように記している。「雑品の中に歯ブラシがある」。街路や路地には百軒以上の歯ブラシ店が点在し、その中で最も有名なのが「金子巷口の川官人歯ブラシ店」である。 上の画像: 宋代の灰坑から発掘された歯ブラシの残骸と宋代の貨幣 上の画像:五代十国時代にはすでに歯ブラシの柄は象牙で作られていた 歯ブラシは象牙、トラの骨、ロバの骨、牛の角、竹、木などの材料で作られ、頭部に穴が開けられ、馬の毛が植えられています。歯ブラシの長さは約25cmで、毛穴の数は少ないもので4つ、多いものでは24つあります。植毛には、目立つタイプと目立たないタイプの2種類があります。目立つタイプは外側に小さな穴があり、内側には大きな穴があり、金属ワイヤーで補強されています。目立たないタイプは美しくエレガントですが、手順が困難です。歯ブラシの値段は約25セントで、ろうそくの値段と同額です。誰にとっても手頃な価格で公平です。 『各流派養生宝集』には、朝の歯磨きについて特別な論議がある。「朝早く起きたら歯ブラシを使ってはいけない。歯の根がゆるんで、歯がゆるんでゆるみやすくなり、長い間使っていると歯痛を引き起こす恐れがある。歯ブラシはスギナでできており、非常に有害である。」スギナは硬く、頻繁に使用すると歯がゆるんだり痛みが生じたりする後遺症を引き起こすことが判明した。 元代末期の詩人郭毓は次のような詩を書いた。「今日は南州から歯ブラシが送られてきた。金貨を添えて脂を落とし、悩みを洗い流す。短いかんざしは軽いべっ甲で切り、氷の絹で飾って銀のかんざしを留めている。」この詩に「歯ブラシ」という言葉が登場するのはこれが初めてである。詩人は南から送られてきた歯ブラシを受け取りました。その価値は金1枚でした。柄は短いヘアピンのようなもので、べっ甲でできていました。銀色の毛は白い馬のたてがみのことです。馬の毛は質感が柔らかく、ブラシに最適な素材です。 上の写真:民芸品市場に展示されていた、遼王朝時代の植毛された骨の歯ブラシの表と裏。 虫歯だけでなく、歯も口臭の原因になります。社会的な礼儀作法を非常に重視していた古代人にとって、これは非常に恥ずべきことでした。東漢の桓帝の治世中、侍従の岱村は口臭がひどく、桓帝の顔が青ざめてしまった。桓帝は、嬌村の口臭を改善するために、彼にあるものを与え、朝廷に行くときにそれを口にくわえるように命じました。 最初、岱村は皇帝から授けられた毒だと思ったが、口に入れると香りが漂い、口臭が消えたことは予想外だった。桓帝が褒美として与えたのは、丁子で作った鶏舌香であり、非常に貴重で、奇跡的な効果があったことが判明しました。東漢の学者、英邵は『漢観意』の中で、「尚書郎は鶏舌香を口にくわえて礼をして報告し、黄門郎は礼をしてひざまずいてそれを受け取る。そのため、尚書郎は香を持ち、蘭を持ち、赤い階段を歩くと言われている」と記している。尚書が香を持つことは宮廷の礼儀作法となり、王に仕えることを指すことが多い。 皆さんには見覚えがあるでしょう?これはチューインガムのクラシックバージョンです。このタイプのチューインガムは、『奇民妖書』や『孟熙壁譚』などの作品に記録されています。隋唐時代の歴史家、李白堯はかつて「寒さに別れを告げるために緑の服を着、太陽を迎えるために梅の香りを抱く」という詩を書いた。唐代の詩人、劉玉熙も「最近、私たちは一緒に犬の土地を管理し、昨日は一緒に鶏の舌の香りを抱いた」と書いた。明・清の時代には、鶏の舌の香を口にくわえるという古い習慣が役人の間でまだ一般的でした。 上の画像: 現代の歯磨き粉の広告 古代の人々は、良い歯並びを保つためには、歯の衛生状態を維持し、歯をきれいにする良い習慣を身につけなければならないと信じていました。 通常、舌を360度回転させ、最初は外側、次に内側に回転させ、これを1日36回行います。また、朝と夜に1回ずつ、1日72回歯をカチカチ鳴らします。さらに、唇をしっかりと閉じて、うがいをするように36回うがいをします。これらの方法は古代に人気があっただけでなく、現代にも応用できます。自分の口腔の健康のために、ぜひ試してみてください。 |
<<: 古代の測定単位は何ですか?缗、钧、跬、迅、樛の単位は何ですか?
>>: 西周の時代に女性はどのようにして官僚になったのでしょうか?古代中国の「女性官吏制度」!
推薦する
漢字はどのようにして作られたのでしょうか?漢字が足りない場合はどうすればいいでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が漢字がどのように作られたかをお話しします。皆さんのお役に立てれば幸いです...
北斉皇帝の一覧と紹介。北斉王朝最後の皇帝は誰だったのでしょうか?
北斉皇帝の一覧と紹介北斉は、中国の南北朝時代の北方王朝の一つです。550年に、東魏に代わった文宣帝の...
宋代の経済は非常に発展していたのに、なぜ住宅価格は一般の人々が買えないほど高かったのでしょうか?
21世紀以降、「家を買う」ことは、愛憎入り混じった複雑な問題となってきました。結婚したら家を買う必要...
『後漢民謡』第二章の主な内容は何ですか?
古い寺院を破壊し、古い女王を哀れみ、外国の侵略を誘発し、外国人を怒らせるしかし、前漢の哀帝の時代に、...
「莫余弗:私が幼い頃、皆がいた場所」は南宋時代の何孟貴によって書かれた作品で、誰かを思い出し、恋しいと思う気持ちを表現しています。
何孟貴は、字を延蘇、号を千寨、諡号を文堅と称し、南宋の詩人で、咸春元年に科挙で三位を獲得した。 In...
楊昭は『郷愁譜』でどのような感情を表現したのでしょうか?
楊昭は『懐古譜』でどんな感情を表現したのでしょうか?実は、それは主に作者と懐かしい人との間の誠実で純...
古典文学の傑作「劉公安」第82章:金持ちの楊はしぶしぶ罰金を支払う
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
唐代の詩人崔浩の初期の詩はどれもエロチックなものだったのですか?
崔浩は唐代の詩人であった。彼は進士で、唐の開元年間に太府寺の書記を務め、天宝年間に司仁勲の元外郎を務...
なぜ周おばさんは趙おばさんの影として生きざるを得ないと言われるのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
宋代の詩の鑑賞:散りゆく花。作者はこの詩の中でどのような比喩を用いているでしょうか?
宋代の宋斉の『散花』については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!降り注...
第88章:崔判事が王明を導き、王可心は冥界を旅する
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
海上禁輸は明王朝にどのような影響を与えたのでしょうか?海上貿易は明王朝の滅亡の問題を解決できるのか?
本日、Interesting Historyの編集者は、海上貿易が明王朝の終焉の問題を解決できるかど...
『紅楼夢』の賈宝玉は本当に女性が好きで男性を嫌う男なのでしょうか?真実とは何でしょうか?
『紅楼夢』の男性主人公、賈宝玉。 Interesting History の編集者が詳細な関連コンテ...
『桃花国柳に酔う』の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
酔桃花地・柳翁元龍(宋代)何千もの風と雨の糸、そして何千もの晴れ渡った空。毎年、さまざまな長さのパビ...
唐代の四つの詩のうち最初の詩『月下独酒』をどのように評価すればよいのでしょうか。また、李白がこの詩を書いた意図は何だったのでしょうか。
唐代の李白の『月下独酌詩四首』。以下、Interesting History編集部が詳しく紹介します...