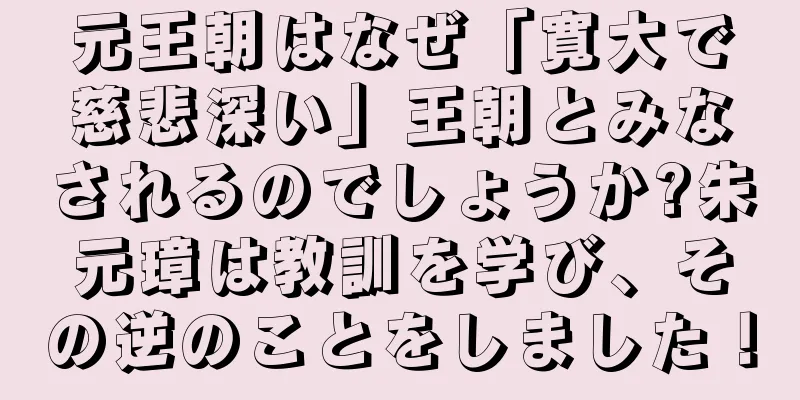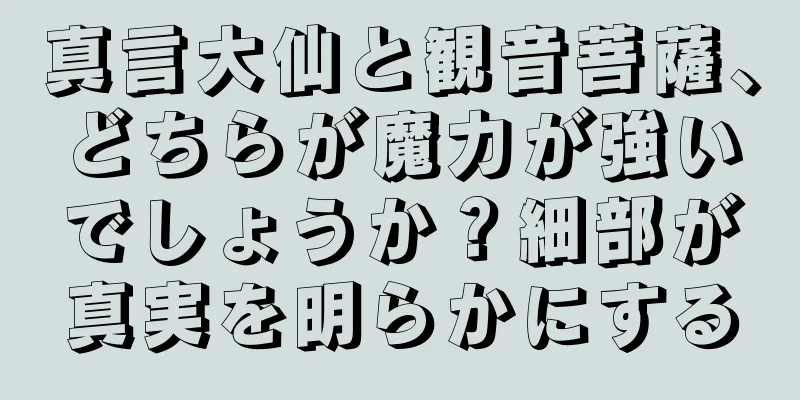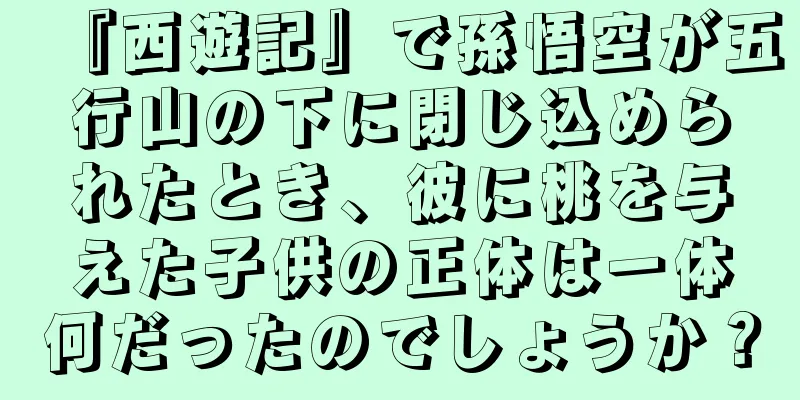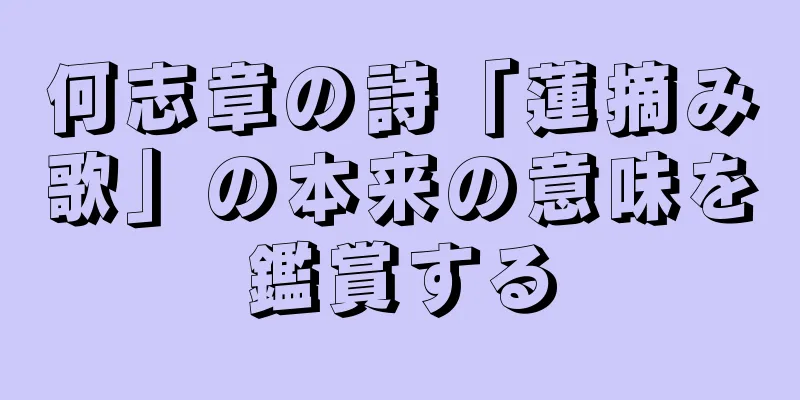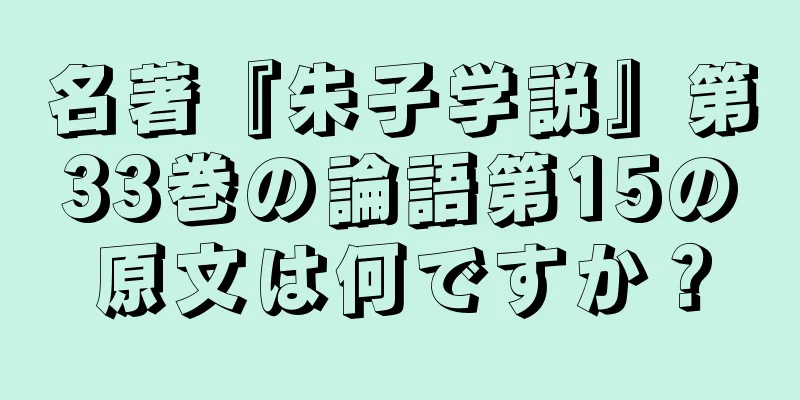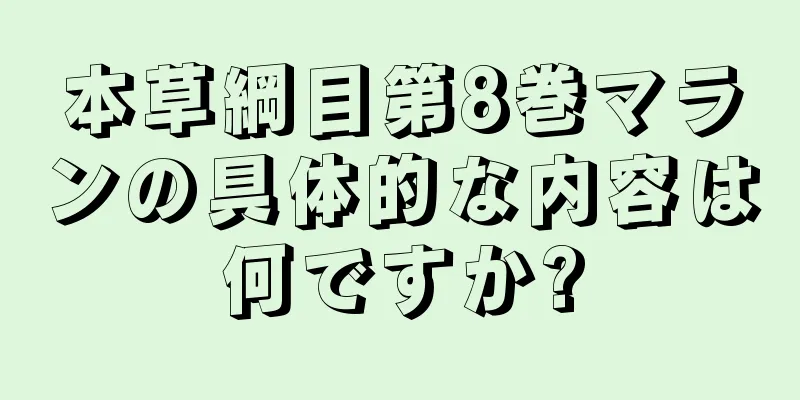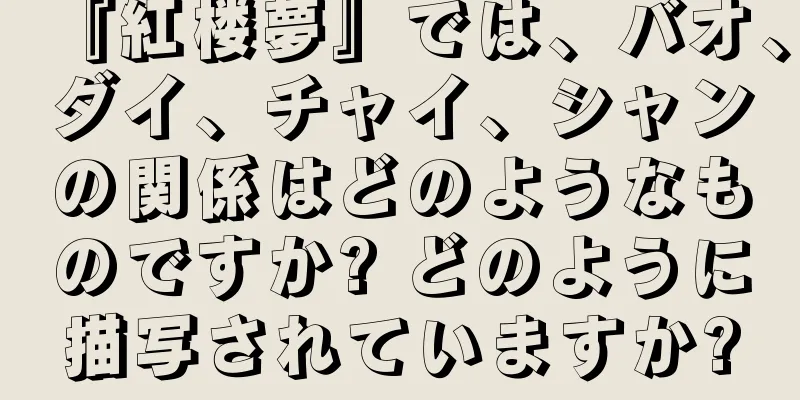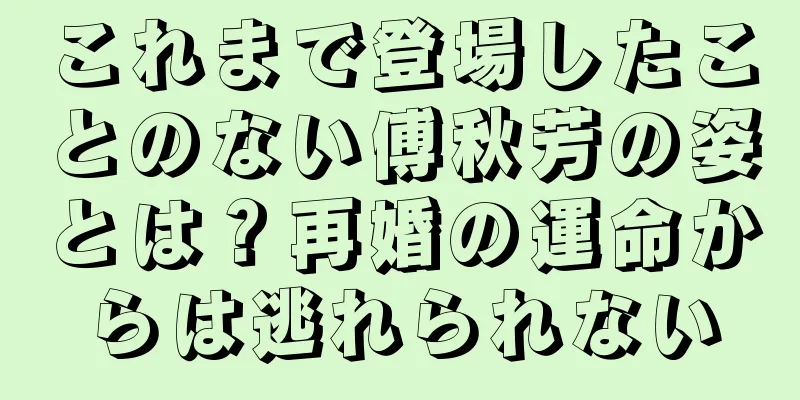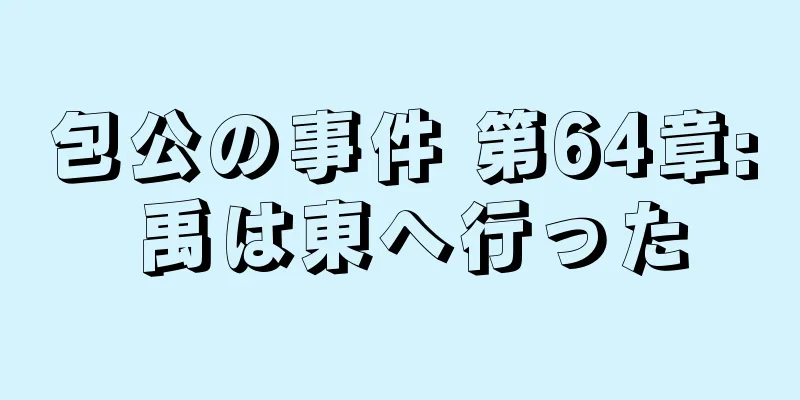戦国時代は優秀な人材が大量に出てきた時代だった。なぜ正統な周王族からは誰も助けに来なかったのか?
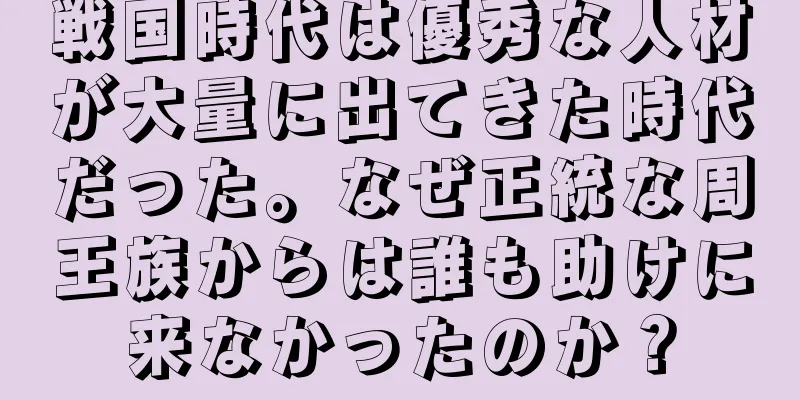
|
戦国時代に周王朝の王族を助けたのはなぜでしょうか?Interesting Historyの編集者が関連コンテンツをお届けします。興味のある方はぜひご覧ください。 古代中国の歴史において、戦国時代は三国時代と同様に優秀な人材が大量に輩出した時代でした。また、戦国時代には人材の流動が比較的多く、例えば呉起は最初は魯の国の将軍を務め、その後、魏、楚へと次々と亡命しました。例えば、商阳は魏の国では挫折しましたが、秦の国では秦の孝公王に評価され、「商阳の改革」を始めることができました。張儀、蘇秦、公孫燕などの外交官は、戦国時代の七大国を渡り歩き、情勢を操り、かき回した。 しかし、戦国時代には優秀な人材は多かったものの、周の皇帝に仕える者はほとんどいなかった。戦国時代、東周の王族は衰退していました。まず、三家が晋を分裂させ、田家が斉に取って代わったとき、無力でした。さらに、徐州が王になり、五国が王になった後、天子としての地位を完全に失いました。そこで疑問なのが、戦国時代には才能豊かな人材がたくさんいたのに、なぜ周の皇帝のもとに誰も入らなかったのかということです。 1つ まず、私の考えでは、以下の理由から、戦国時代に周王家に亡命した人材はほとんどいなかったと思います。一方、周の王室は弱く、発展の見込みもなかったため、こうした人材を引きつけることは困難でした。周の平王が東の洛邑に移動して以来、周王家の権力は衰え始めました。春秋時代、鄭のような小国でさえ周の王族と競争しようとし、周の王族の衰退が露呈した。もちろん、春秋時代においては、斉の桓公にせよ、晋の文公にせよ、名目上は周の王家の旗の下に君臨し、つまり表面上は周の皇帝の権威を尊重していた。 しかし、三家が晋を分裂させ、田家が斉に取って代わったとき、周の皇帝は家父長制と封建制度に違反するこれらの行為を罰することを敢えてしなかっただけでなく、魏、韓、趙、斉を君主として封建することを選択し、周王室の権威はほぼ消滅しました。この文脈において、周王家の領土は戦国時代の七大国によってさらに侵食され、その総合的な力はすでに魯、魏、鄭などの小国の力と同等であったことを意味します。戦国時代、これらの属国は戦国七国との間に大きな隔たりがあったことは明らかです。 二 このように、戦国時代の三才、呂不韋、商阳、呉起はいずれも魏出身である。しかし、彼らはいずれも魏に仕えることはなかった。これは魏の君主が人材の活用方法を知らなかったためであり、魏に対する信頼の欠如とも直接関係していた。同様に、戦国時代、周の王族が位置していた領土は、魏の国のような場所でした。都市の数も限られていただけでなく、魏、漢、趙、斉といった大国に囲まれており、四方八方から戦火に囲まれた場所だったと言えます。そのため、呂不韋、商阳、呉起などの才能が周の皇帝に加わることを選択しても、大きな業績を達成することは困難であり、これは周王家の客観的な強さによって決定されました。 さらに、戦国時代の七大国の中でも、弱小国であった漢は、当然のことながら、魏、秦、斉などの大国に比べると、人材にとって魅力がはるかに低かった。例えば、孫斌が魏国で龐攸に陥れられた後、孫斌が最初にとった行動は、隣国の漢国ではなく斉国に戻ることだった。なぜなら、当時斉国は魏国と競争できるほどの力を持っていたからだ。例えば、商阳は魏を離れ、秦に加わることを選びました。これは秦が関中、竜游などを占領し、台頭する基盤を築いていたからです。 三つ 一方、戦国時代の七大国の君主と比べると、周王家の歴代君主は人材登用の努力をほとんどしませんでした。戦国時代の七大国の中で、人材発掘に熱心な君主は、当然、人材を引き寄せやすい傾向がありました。例えば、秦の孝公、燕の昭王、趙の武霊王、魏の文侯、斉の衛王、楚の道王などは、いずれも人材発掘に熱心な君主でした。対照的に、周の王室は積極的に人材を採用しなかったため、当然ながら人材に対する魅力は低下した。 また、周王室は家父長制と封建制度を堅持しており、戦国時代の実情から明らかに遅れをとっていたため、型破りな方法で才能を活用することも困難でした。春秋時代、多くの属国では君主の王族から多くの優秀な人材が輩出されました。しかし、戦国時代になると、学者の台頭により、諸属国の君主は王室にあまり頼らなくなりました。例えば、白起、司馬攘、王翦、蒙恬などの秦の有名な将軍は秦王家の子孫ではありませんでした。 4つ しかし、結局、周の王室は依然として「皇帝-王子-大臣-学者」という階層秩序を堅持しており、つまり周の皇帝が学者を直接雇用することは困難であり、ましてや学者を活用することは困難であった。これに対し、楚の道王は、呉起のような学者に霊隠(宰相)の地位をあえて任せたが、これは周の王室では採用しない人材の登用方法であった。さらに、商鞅の改革後、秦は軍功に応じて爵位を与える制度を採用し、兵士が軍功を挙げて土地や家屋などの褒賞を得ることを奨励したが、これも周王家の封建制度や家父長制に反するものであった。そのため、たとえ優秀な人材が周王室に加わったとしても、周王室の領土内で商阳の改革や呉起の改革のような改革を遂行することは不可能であり、つまり周王室には改革を実行する土壌がなかったのである。 まとめると、戦国時代には優秀な人材がたくさんいたが、周の皇帝に仕える者はいなかった。これも両者の共同選択の結果だった。つまり、優秀な人材は秦、魏、趙、斉、楚などの大国に仕えることを好み、周王家には人材を採用する誠意と、その潜在能力を刺激する条件が欠けていたため、最終的に周王家の状況はますます衰退していった。戦国時代末期、秦は山東六国を滅ぼす前に東周王族を併合し、六国滅亡の基盤を築きました。これについてどう思いますか? ぜひご意見をお寄せいただき、一緒に議論しましょう。 |
<<: 戦国時代の七大国の一つ、斉はどれほど強かったのでしょうか?その領土は秦と楚に次ぐものです!
>>: 歴史上、大規模な移民の時代はいくつありましたか?なぜ移民が五代十国の形成を促進したと言われるのでしょうか?
推薦する
もし劉封が関羽を救出するために軍隊を派遣したなら、劉備はまだ世界を征服する希望を持っていたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
哲学の名著『荘子』 内篇 徳と美徳(2)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
古典文学の傑作『太平天国』:天部第二巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
明代史二十四史第184巻第72伝原文
周洪墨、楊守塵(弟の守之、息子の茂源茂人)、張元真(陳寅)、傅漢、張勝、呉寛、傅貴、劉俊、呉燕、顧青...
秦克清が亡くなった後、賈真はなぜ長男の家に誰も残っていないと言ったのですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』で賈舒が王夫人を元陽との結婚に強要したことで叱責された後の王夫人の態度はどうでしたか?
元陽は賈夫人のお気に入りの侍女であり、彼女の私室の鍵を握っている。 今日は、Interesting ...
唐代の人々は夏をどのように過ごしたのでしょうか?楊貴妃は夏の暑さを避けるためにどのような方法を使ったのでしょうか?
暑い夏の日、現代人にとって最も楽しいことは、室内に座ってエアコンを楽しむことです。しかし、エアコンが...
「漁師の誇り 五月に咲く絢爛なザクロの花」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
フィッシャーマンズプライド - 5月のザクロ焼き欧陽秀(宋代) 5月にはザクロの花が美しく咲きます。...
『紅楼夢』で賈廉と幽二潔の情事を知った後、王希峰は何をしたのでしょうか?
『紅楼夢』を読んで、王禧鋒に感銘を受けた人は多いでしょう。次は『おもしろ歴史』編集者が歴史物語をお届...
岳飛伝説第27章:岳飛の哀花山での戦い、阮良が水中で武術を習得
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
金陵十二美人とは?なぜユウは選ばれなかったのか?
金陵十二美人に非常に興味がある方のために、『Interesting History』の編集者が詳しい...
3,000年前の公衆トイレはどのような様子だったのでしょうか?古代のトイレはとても「豪華」でした!
3000年前の公衆トイレはどんな様子だったのでしょうか?古代のトイレはとても「豪華」でした!興味のあ...
曹操が馬を失い野原に落ちた後、兵士たちはなぜ彼を救う代わりに称賛されたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
星堂伝第8章:茶碗を見て、杜茶は友人を作ることについて話し合い、金の棍棒について尋ね、洛易は追放された兵士を解放する
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
唐代の科挙による人材選抜制度はどのようなものだったのでしょうか?制限やルールは何ですか?
周知のとおり、唐代には人材や官吏を選ぶ主な方法が5つありました。科挙、家系のつながり、召喚、軍功、そ...