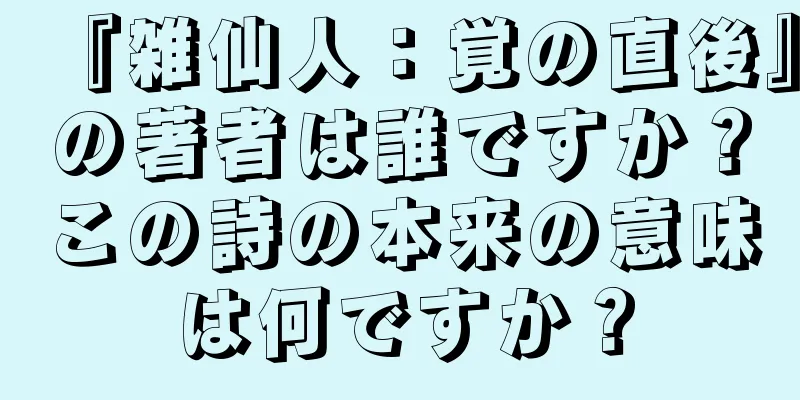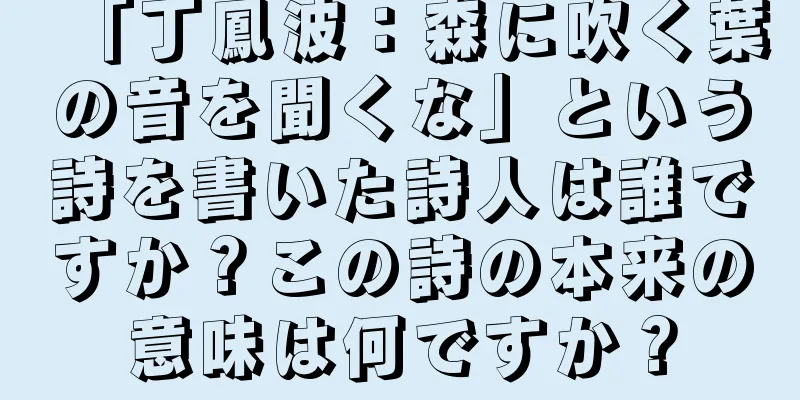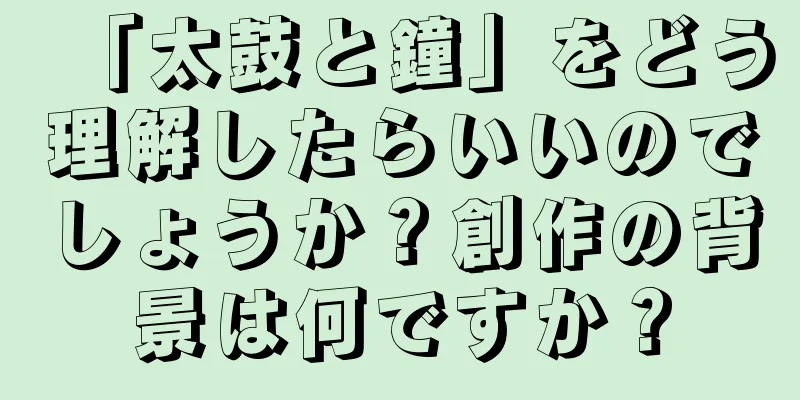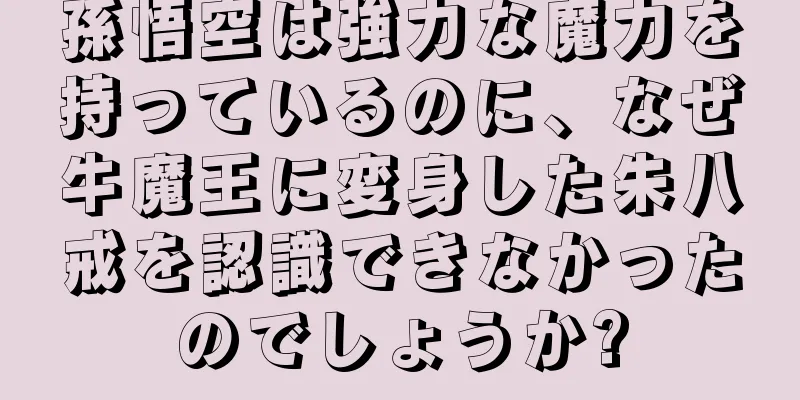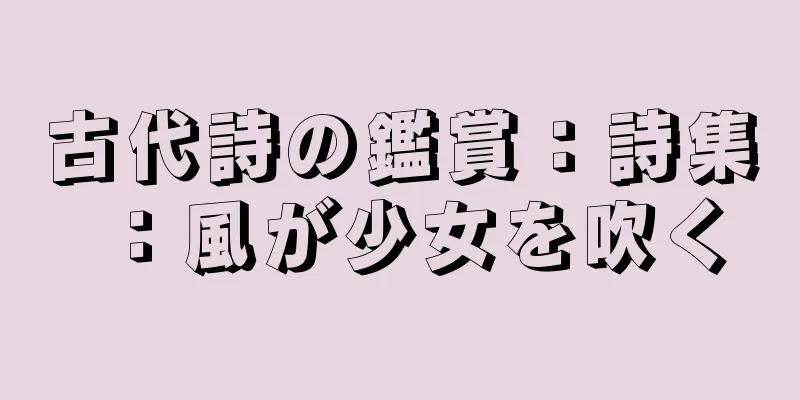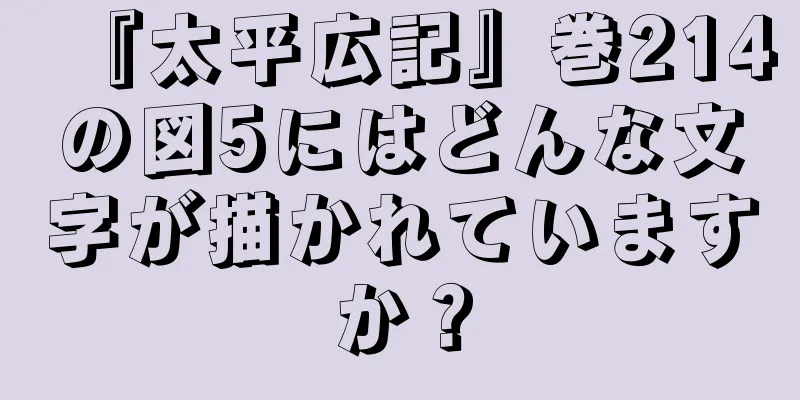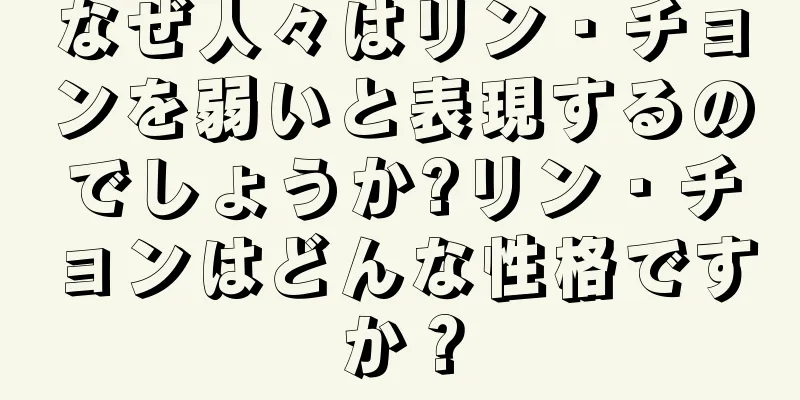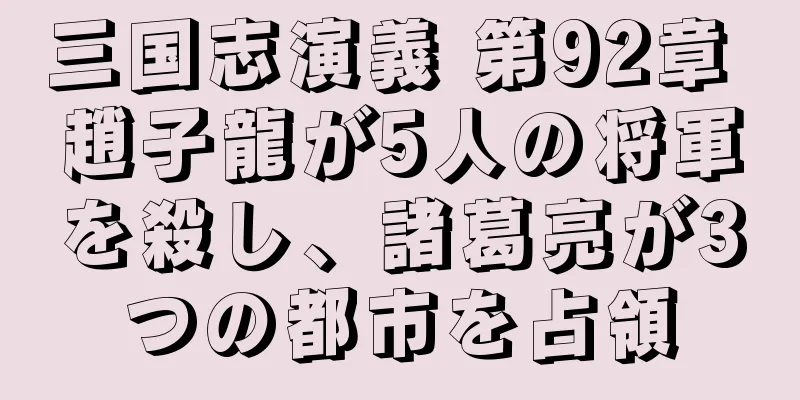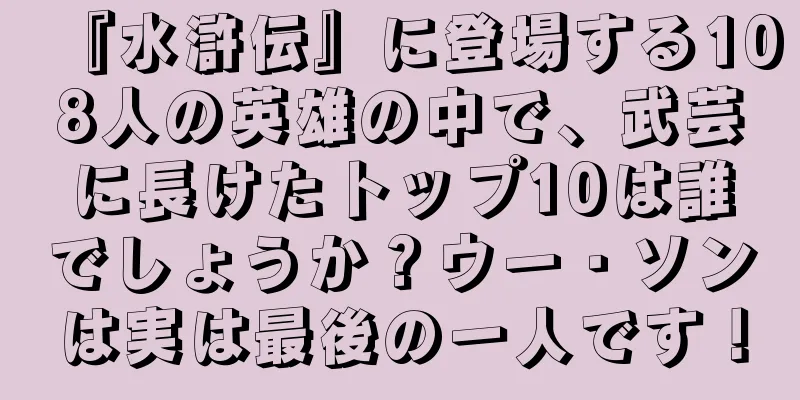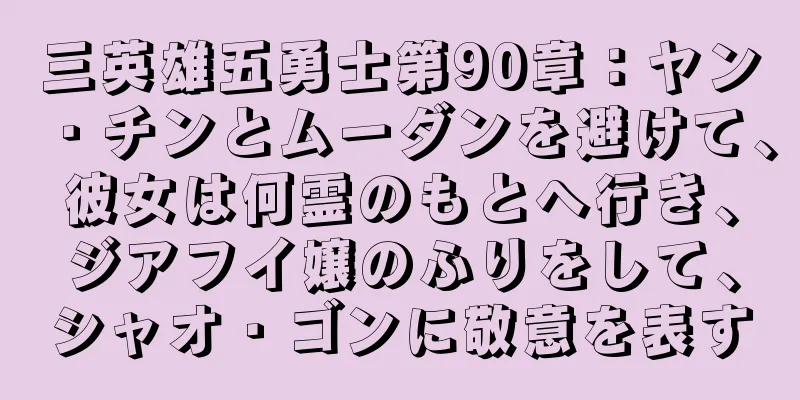8 部構成のエッセイの 8 つの部分とは何ですか?なぜ科挙では八本足の論文が必要だったのでしょうか?
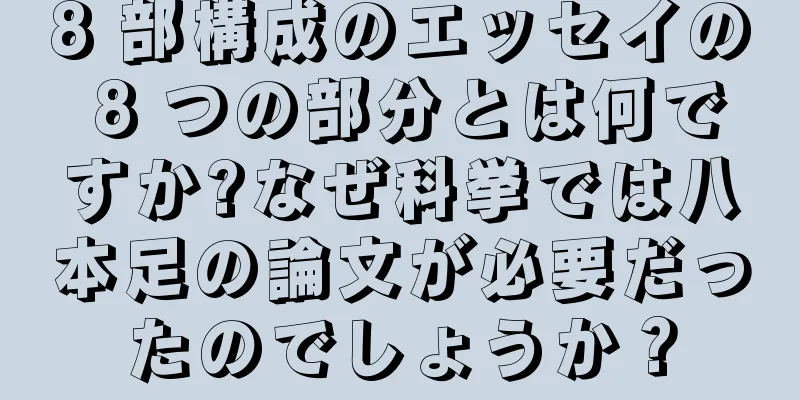
|
なぜ科挙では八字熟語が必要なのでしょうか。これは多くの読者が気になる疑問です。次に、Interesting History では読者に八字熟語の学習方法と参考資料を紹介します。 八部構成のエッセイは、論点の切り出し、論点の継続、講義の開始、論点の導入、序論、中間、終論、結論の8つの部分から構成されています。論点はすべて『四書五経』の原文から取られており、形式は現代の読解問題に似ています。我が国の科挙制度は隋の時代に始まり、清の末期に終了し、千年以上続きました。その中で、明・清の時代は科挙において「八部作文」と呼ばれる文体を採用した。 いわゆる「八部作」とは、一つの文章を八つの部分に分けることを意味します。文章の題名は「四書五経」の原文から取らなければならず、文章の形式、文調、内容には厳しい規定があります。八足論文では、受験者に古代人の口調を真似て「賢人に代わって話す」ことが求められるため、受験者に自由な表現の余地がなく、学者の考えが制限されます。これが八足論文の主な欠点です。 八足文は歴史上全く役に立たないわけではありません。まず第一に、学者たちは八足文を研究することで儒教の倫理や道徳の影響を受けています。第二に、8部構成のエッセイの執筆理論とテクニックは、将来の世代の参考資料として使用できます。もう一度言いますが、8 本足のエッセイは、将来の世代に簡潔かつ包括的な文章のモデルを提供します。さらに、八字随筆は、連句などの後世の特定の文学形式の成熟と発展を促進する役割を果たしました。 八本足のエッセイには確かに重大な欠点があり、当時の支配階級はそれを実に明確に認識していました。康熙帝から乾隆帝に至るまで、八字文を残すか廃止するかをめぐる議論は一度も止むことがなかった。しかし、結局、清朝の支配階級は、科挙に八字文を使うことを主張することに決めました。その理由は何だったのでしょうか?実は、八字文は非常に厳格でしたが、当時の歴史的状況下では、人材を選抜する良い方法でした。 1. 八足論述試験の内容はすべて『四書五経』から出題されました。これらの本は当時すでに非常に人気があり、価格も一般大衆にとって手頃でした。このようにして、学生が首都にいても、何千マイルも離れた国境地帯にいても、統一された教科書が存在します。誰もが同じスタートラインに立って競争することができ、貧しい学生たちに「朝は農民として、夕方には皇帝の宮殿に入る」機会が与えられる。そうでなければ、試験内容が多様であれば、書籍がまだ広く入手可能でない時代に教育の不平等が必然的に生じてしまうでしょう。 2. 8 部構成のエッセイは形式が決まっているため、試験官は比較的公平かつ公正に採点することができます。候補者の 8 部構成のエッセイがすべての面で基準を満たしている限り、試験官は個人的な好みを理由に候補者を排除することはできません。これにより、試験不正の発生率も比較的減少します。 3. 八本足のエッセイの内容は非常に漠然としていますが、文章力の向上に非常に役立ちます。 8本足のエッセイを上手に書ける人は、他の記事も楽に書けることが多いです。 八つ足の随筆文学の内容は空虚で役に立たないと言う人もいます。しかし実際には、8本足のエッセイテストの主な目的は、世界中の学生の中で最も勤勉な学生を選ぶことでした。具体的な仕事の能力については、試験に合格した後もゆっくりと培っていく時間があります。学生が一生懸命努力し、困難に耐える意志を持っている限り、特定の職業スキルを習得できないのではないかと心配する必要はありません。この点で、8本足のエッセイ試験は、実は今日の大学入試と非常によく似ています。私たちは今日、読書から多くの知識を学びますが、そのほとんどは、決して使うことのない知識です。大学入試の目的は、最も賢い学生を選ぶことではなく、最も勤勉な学生を選ぶことです。 |
<<: 古代では科挙における不正行為はどのように扱われたのでしょうか?科挙不正への対策は?
>>: 古代の科挙にはどれくらいの時間がかかりましたか?なぜ9日間と6泊なのでしょうか?
推薦する
国の起源:中国文明は世界最古の文明の一つである
中国文明は世界最古の文明の一つです。中国帝国は他の古代文明と同様に、原始的な小さな部族と小さな地域か...
『紅楼夢』で宝玉と黛玉はなぜ結ばれなかったのでしょうか?
『紅楼夢』では、宝玉と黛玉は結局結ばれませんでした。今日は、おもしろ歴史の編集者が詳しく説明します~...
朱熹の古典詩で、詩の一行一行に月が描かれており、非常にレベルが高い。
今日は、Interesting Historyの編集者が朱熹についての記事をお届けします。ぜひお読み...
斉の衛王はどのようにして有名になったのか?斉の衛王の物語の紹介
「一声で皆を驚かす」とは、中国に古くから伝わる慣用句です。もともとは森の中の鳥を指し、普段は飛んだり...
『旧唐書』第19巻前半にはどんな物語が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
画家顧凱之に関する逸話や物語にはどんなものがありますか?顧凱志のニックネームは何ですか?
顧凱之の雅号は長康、通称は虎頭であった。東晋時代の優れた画家、絵画理論家、詩人で、曹丕興、呂旦偉、張...
秦を強化するための商閻の改革は、後世にどのような教訓を残したのでしょうか?商法が成功と失敗の理由である
「秦の王は虎のような雄大な姿で世界を席巻した。」中国は春秋時代を経て、紀元前4世紀以降に戦国時代に入...
『西遊記』で、唐の僧侶が仏典を探していたときに経験した5番目の困難は何でしたか?
唐和尚が仏典を求めて西方へ旅した物語は、老若男女を問わずよく知られています。次に、Interesti...
ムーランの伝説 第30章: ムーランの最初の嘆願、悲しみの詩とともに天国へ帰還
『木蘭奇譚』は清代の長編小説です。正式名称は『忠孝勇敢木蘭物語』で、『忠孝勇敢女物語』とも呼ばれてい...
『紅楼夢』では、黛玉は優雅で才能に恵まれています。なぜ王夫人は彼女を好まないのでしょうか?
林黛玉は『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女の第一人者です。次の『興味深い歴史』編集者が詳しい記...
秀雲閣第125章:大道の深さはファンタジー世界の心のレベルによって決まる
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
涼山の賞罰制度の創始者は誰ですか?涼山に関する規則と規制
北宋末期のある日、三人の人が荊昭府から沙門島へ向かう道を歩いていた。そのうちの一人は荊昭府の六判検閲...
歴史上の寿熙和碩公主は本当に宦官が好きだったのでしょうか?
ドラマ「太宦官」に登場する首熙和碩公主は道光帝の8番目の娘であり、歴史上にも実在した人物である。ただ...
「大きな耳は幸運をもたらし、邪悪な目と邪悪な心は幸運をもたらす」!古代人は知り合いの人たちをどのように判断したのでしょうか?
「耳が大きいと幸運が訪れるが、目が悪ければ心は悪くなる」という言葉を、あなたはどう解釈しますか?次は...
太平広記・巻65・女仙・趙旭の原作の内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...