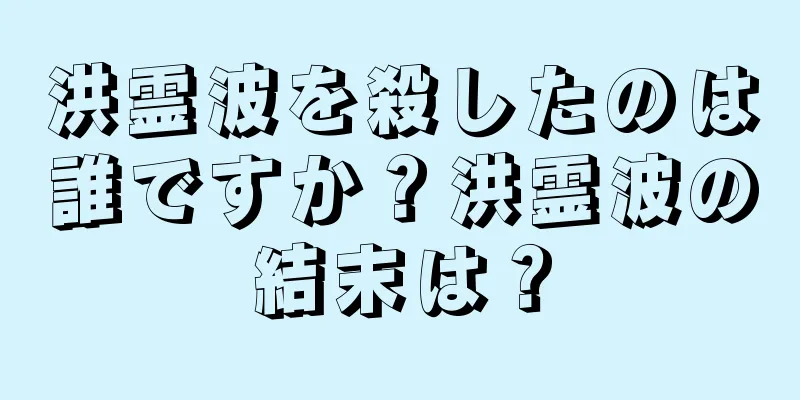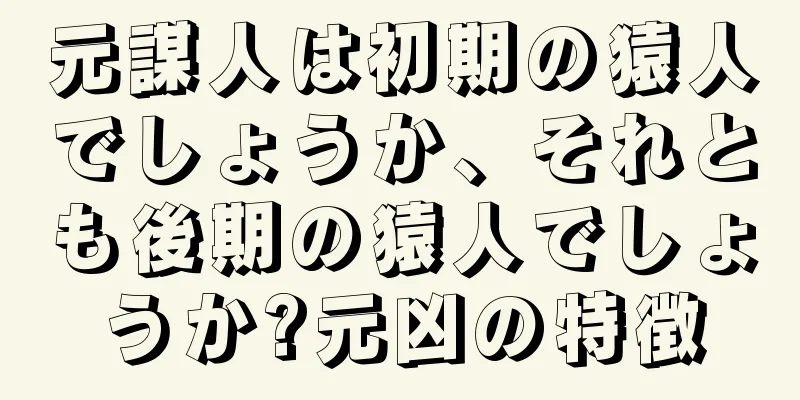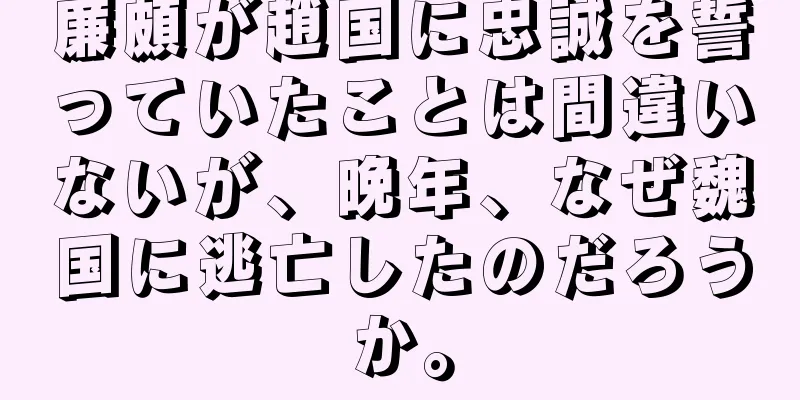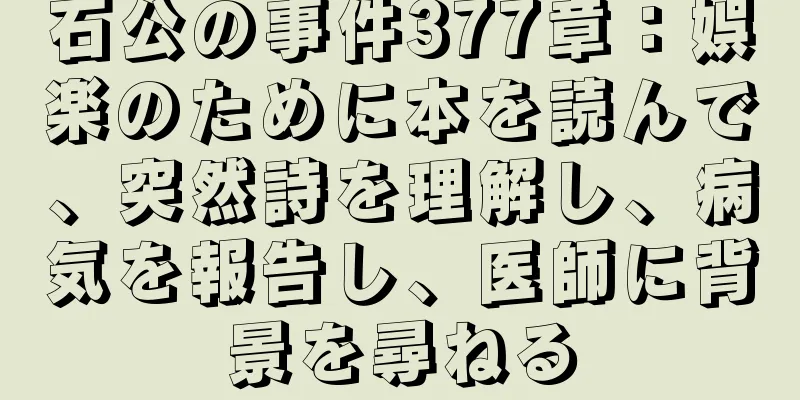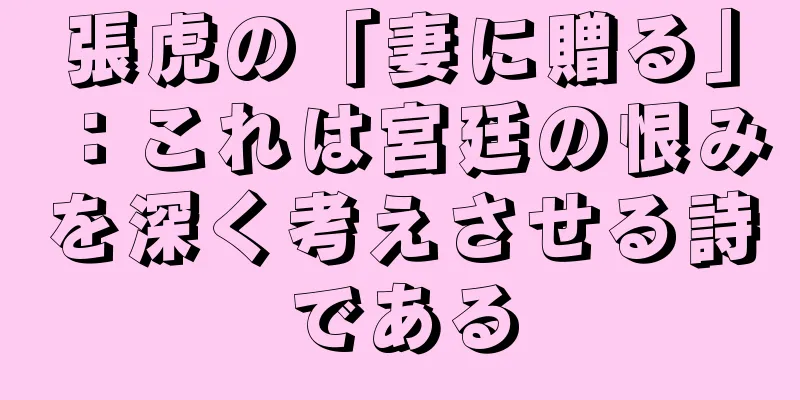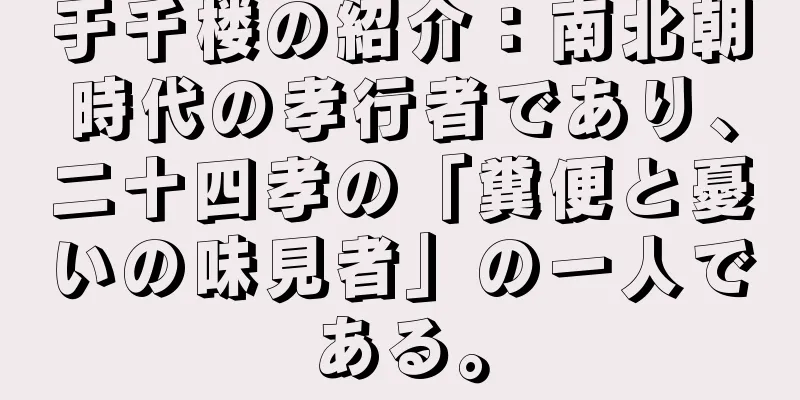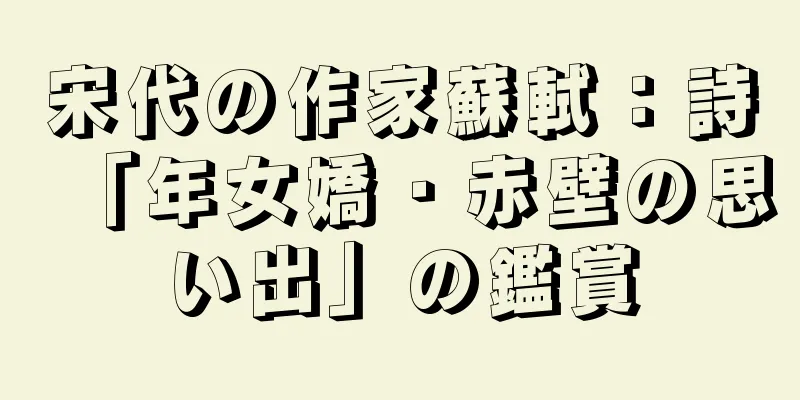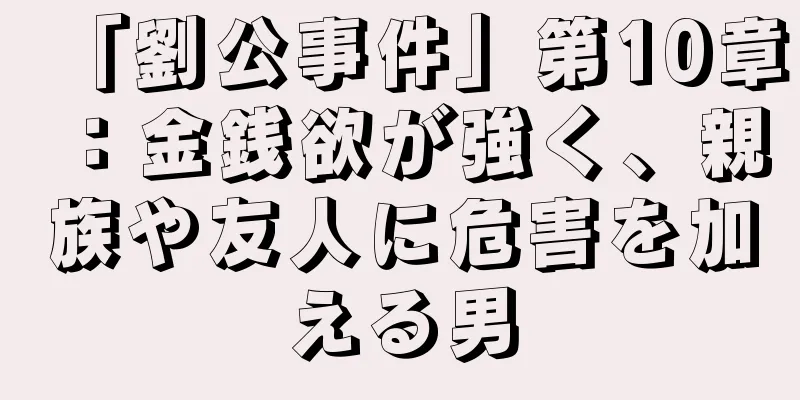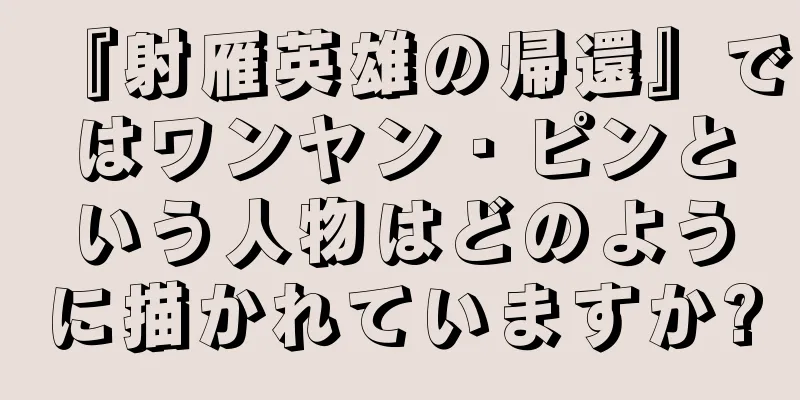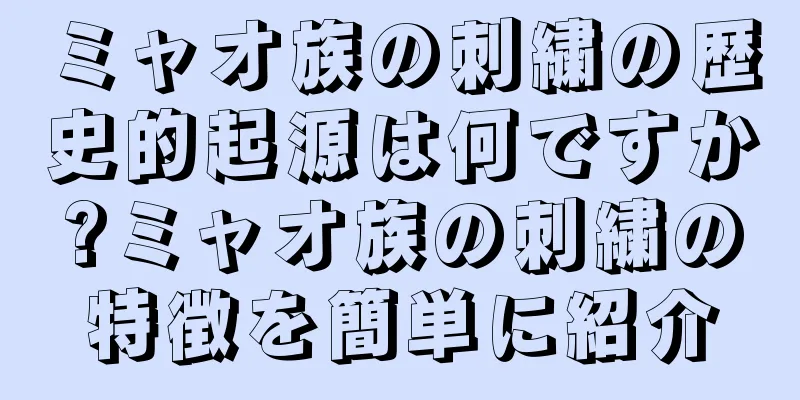古代の包囲戦でよく使われたはしごと私たちが普段目にするはしごの違いは何でしょうか?
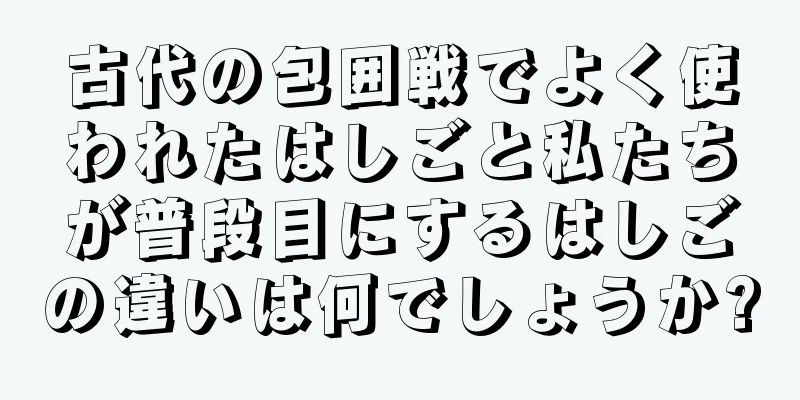
|
古代の包囲戦の際、なぜ人々は梯子を倒さなかったのでしょうか。そうした方がよかったのではないでしょうか。梯子を倒したくなかったのではなく、それは役に立たなかったということが鍵です。興味のある読者は、Interesting History の編集者をフォローして読み進めてください。 時代劇を見ていると、誰もが疑問に思うことがあると思います。敵が都市を攻撃するとき、彼らはよく梯子を立て、城壁の上の兵士たちは下の敵が次々と登ってくるのを見ています。転がる丸太や石を投げたり、熱い油をかけたりすることは別として、彼らは梯子を押そうとはしません。梯子を押せたらもっと簡単だと思いませんか?一回押すだけでたくさんの敵を倒せますから。 少し前に公開された「ハクソーリッジ」という映画があります。日本軍が高地を守っていて、米軍が多額の費用をかけて高地までロープを数本運びました。下にいる米軍はロープを伝って登り、攻撃を仕掛けました。では、なぜ日本軍は米軍の攻撃を止めるためにロープをきっぱりと切断しなかったのでしょうか? 実際、理論的に言えば、はしごを押すこともロープを切ることもどちらも解決策ではあるが、それが一度きりの解決策であると言うのは誇張だろう。なぜなら、たとえロープを切っても、米軍は再びロープを上げて攻撃を続けるからです。ロープを切ることによる効果は、敵の攻撃時間をわずかに延長することだけです。 しかし、最終結果から判断すると、ロープが切断されただけでは米軍が攻撃を止めることは不可能だった。そんなことをするより、陣地を守り、敵を次々と撃破していく方がよい。高地を占領していたため、日本軍は大きな優位性を持っていた。彼らは要塞に留まり、アメリカ軍は登るのに多大な労力を費やさなければならず、要塞に隠れている日本軍の攻撃にも警戒しなければならなかった。 そのため、米軍はこの高地を占領するために多大な犠牲を払った(その背景は第二次世界大戦の沖縄戦である)。したがって、日本軍がロープを切らなかったのは、それが一時的な措置であり、実質的な効果がなかったからである。日本軍がアメリカ軍の進撃を阻止し、主力部隊の後方を掩蔽することを目的とした閉塞戦闘を行っていた場合、ロープを切断することは非常に効果的であった。 君が一つ建てれば、私は一つ切る。君がそれを倒すまでには長い時間がかかるだろう。後方の大部隊はとっくの昔に撤退しているだろう。そのため、抗日戦争の際には橋や鉄道を爆破する作戦が頻繁に行われ、敵の輸送路を破壊するためや、後方の大部隊の退却を援護するためなど、時間を遅らせるためにこの方法が使われました。 古代の戦争で梯子を押さないのと同じ理由です。梯子を下に押し下げると、敵はまた上げます。そして梯子は実際には押すのがそれほど簡単ではありません。なぜでしょうか?重すぎるからです。考えてみてください。古代の城壁は基本的に数十メートルの高さでした。たとえば、西安の古代の城壁の高さは12メートルです。12メートルの長さの梯子が斜めの角度で城壁に立てかけられています。 その底部は力点を形成します。まず、梯子を正面から倒したい場合、基本的にはできないと言えます。城壁は90度の直線壁であり、城壁に置かれた梯子は20〜30°の傾斜角を形成するためです。梯子を正面から倒したい場合、手は十分に長く、この角度よりも大きくなければなりません。そうすれば、梯子を正面から倒すことができます(具体的なパターンは想像力を使って考えてください)。 正面からでは無理なら、横から押すこともできますが、もっと力が必要です。さらに、はしごの上には平均体重150~200ポンドの兵士が3~4人立っていることを考慮する必要があります。したがって、はしごをひっくり返すのはそれほど簡単ではありません。はしごの上部を引っ張るには、少なくとも2~3人の兵士が必要です。 しかし、梯子の上部は2か所しかなく、2〜3人が密集して操作するのは困難です。また、梯子は必ずしも城壁よりも高いわけではありません。梯子の上部が城壁よりも低ければ、押すことはさらに不可能になります。無理に押そうとすると、体の半分を城壁に掛ける必要がありますが、どうやって一人で押すことができますか? また、下にいる兵士がナイフで首を切り落としたり、遠くにいる敵が弓矢を向けてきたりする可能性もあるので、警戒する必要があります。さらに、古代の梯子の先端はすべて鉤状になっており、基本的に城壁にしっかりと固定されていたため、押すのはおろか、ナイフで切ることも不可能だった。まとめると、はしごを倒すことは不可能ではないが、実際の運用ではおそらく良い方法ではないので、はしごを登ってくる敵を継続的に消費する方が良い。 もちろん、はしごを押すことは実用的な操作を伴わないわけではありません。街を守る兵士もはしごを倒すことがあります。しかし、違いは手で押すのではなく、道具を使うことです。前述の通り、はしごには傾斜角度があり、はしごをひっくり返したい場合は20~30度以上の長さの道具が必要です。 さらに、もう一つの最も重要な変化は、攻城梯子も変化を遂げたことです。戦闘環境に適応するために、多くの攻城梯子には梯子を安定させるために底に車輪が追加されました。下の図に示すように、このタイプの梯子はまったく押すことができず、火で燃やすことしかできません。 例えば、諸葛亮が第二次北伐の際に陳倉を攻撃したとき、彼は梯子をかけてこの都市を攻撃したが、都市は灰燼に帰した。 その後、彼は軍を前進させて趙を攻撃し、梯子と破城槌を使って城に近づきました。趙は梯子に矢を放ち、梯子は燃え上がり、梯子の上にいた人々全員が焼け死んだ。 - 魏禄 もちろん、すべての包囲戦でこの戦車型の梯子が使われるわけではありません。 例えば、安史の乱の決戦である綏陽の戦いでは、張勲率いる唐軍7000人の守備隊が反乱軍の尹子奇率いる18万人の兵士を10か月間食い止め、反乱軍に12万人の死傷者を出した。これは中国軍事史上前例のない防衛戦であったと言える。 この戦いで張勲とその部下たちは、唐朝廷からの支援がほとんど受けられなかったため、非常に苦戦しました。完全に孤立した都市で、補給も自力で賄わなければなりませんでした。兵士は合計でわずか数千人しかいませんでした。敵の攻撃を防ぐため、彼らは梯子を突き立てたり、桐油をかけて燃やしたりと、あらゆる手段を講じました。 敵はそれを知っていたので、雲充を使って城壁を攻撃し、城壁を巡回して鉤や棒で支えて前進を阻止し、梯子を燃やすためにかがり火を放った。 泥棒たちは荷車や木馬を持ってやって来て、それらを見つけるたびに壊しました。敵は敗北し、攻撃をやめた。彼らは塹壕を掘り、柵を立てて防御した。 - 『新唐書・張勲伝』 しかし、梯子を押しても敵の攻勢を一時的に止めることしかできず、10か月の苦闘の末、弾薬と食糧の不足により遂に綏陽は陥落した。最終的に戦死したのはわずか36名の兵士だけだった。まさに英雄の物語だった。まとめると、梯子を押すことは古代の戦争では存在しなかった方法ではなかった。結局のところ、それは短期的で効果的な方法だったが、梯子を押し下げても敵はそれを上げてしまうので一時的なものだった。 張勲のような人々は飢えがひどく、結局木の皮しか食べられず、梯子を押す力さえありませんでした。数十倍の数の敵の攻撃を受け、最終的には数の多さで敗北しました。諸葛亮が陳倉を攻撃したとき、陳倉は守るのは簡単だが攻撃するのは困難であり、後に魏軍の支援を受けたため、諸葛亮は軍を撤退させた。 もし張勲とその部下たちが当時有効な支援を受けていれば、隋陽は間違いなく守ることができただろう。 |
<<: なぜ宮殿のほとんどの人は宮殿の井戸の水を飲まないのでしょうか?
>>: 秦と漢の王朝の首都は北にあったのに、その後の多くの王朝は首都を南に移したのはなぜですか?
推薦する
謝玄はかつて「史上最強の軍隊」の一つである「北宮軍」を創設した。
謝玄(343-388)、雅号は有度とも呼ばれる。彼は陳君楊夏(現在の河南省太康市)の出身であった。謝...
『紅楼夢』で、王夫人は林黛玉を監視するために誰を派遣したのですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
清朝の順治帝が著した『徳を積む心』の内容を簡単に紹介します。
順治12年、清朝の聖祖は「さまざまな本の要点をまとめて1冊にまとめ」、『勧徳要』と名付けました。福林...
古代軍事書『江源』:巻一:将軍訓示、全文と翻訳注
『江源』は、将軍の在り方を論じた中国古代の軍事書です。『諸葛亮将軍園』『武侯将軍園』『心中書』『武侯...
【李飛の伝記】原文訳、李飛、敬称は淑章、広平出身
李飛の伝記(宋代史)李飛は、名を淑章といい、広平の出身であった。生まれつき賢く機敏。彼は初め南安の司...
蒋魁の「赤い花びら・古城影」:この詩は「興奮が終わり、悲しみがやってくる」というテーマで書かれた。
蒋逵(1155-1221)は、字を堯章、号を白石道人、鄱陽(現在の江西省)に生まれた南宋時代の作家、...
嘉慶帝の五女、恵安公主の簡単な紹介
慧安和碩公主(1786-1795)は、清朝の嘉慶帝の五女である。母は賈王の側室である沈嘉である。彼女...
『紅楼夢』における賈家にとって賈夫人の重要な意味は何ですか?
『紅楼夢』の賈おばあさんは賈家にとってどのような重要な意味を持っているのでしょうか?実は、賈おばあさ...
李時衡が収集した原本は模写されたものであるのに、なぜ模写が原本であると言われるのでしょうか?
北宋時代の学者、李時衡は書道の収集を好みました。彼は金代の偉大な書道家の真作である書道作品のコレクシ...
『隋唐代記』第58章:秀城景徳が唐に降伏したと偽装
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
パートリッジ・スカイの詩「蓮の開花を待つ」にはどのような場面が描かれていますか?この宋代の詩をどのように鑑賞すればよいのでしょうか?
ヤマウズラの空:蓮の花が咲くのを待って一緒に旅行する[宋代] 顔継道、次の興味深い歴史編集者があなた...
若い時に軽薄でなければ、人生は無駄になる:清朝末期の曽国藩と胡臨沂の物語
曾国藩はかつて、胡臨沂の才能は自分より10倍優れていると言った。これは誇張ではありません。胡臨沂の名...
鄭光祖の『鄭公・才紅秋』:著者の人生観と人生哲学を示す
鄭光祖(1264年?)、号は徳恵、平陽湘嶺(現在の山西省臨汾市湘汾県)の人。元代の著名な劇作家、曲作...
『紅楼夢』で芙蓉の娘を弔う場面で、宝玉は青文をどのように評価したのでしょうか?
清文は、金陵十二美女の第一号、第二巻第一号で、賈宝玉の部屋の四大侍女の一人です。今日は、興味深い歴史...
「ノクターン」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ノクターン欧陽秀(宋代)浮かぶ雲が明るい月を吐き出し、流れる影が翡翠色の階段に影を落とします。私たち...