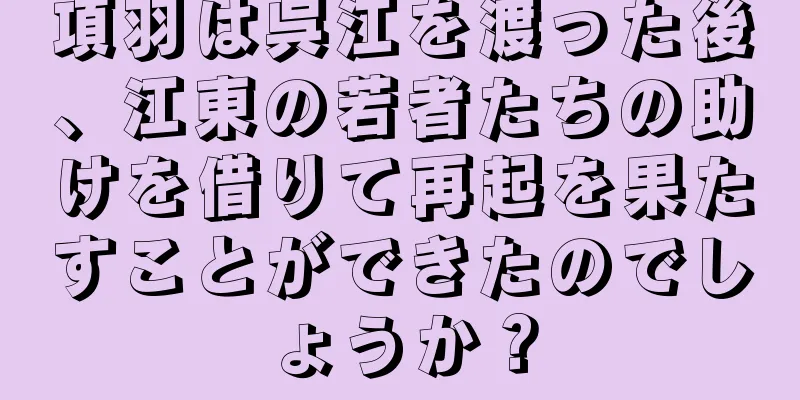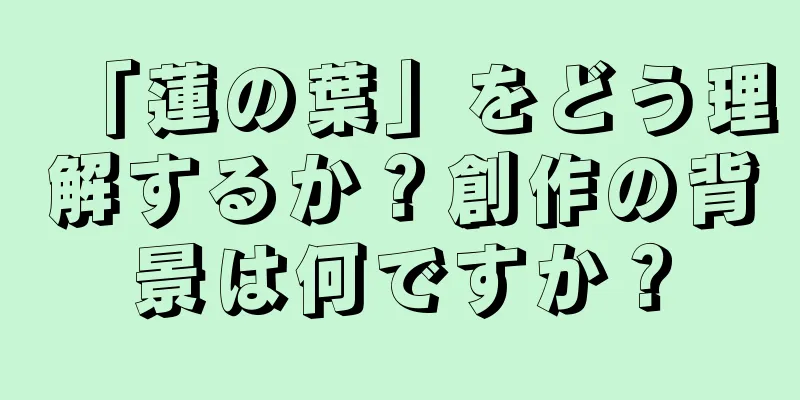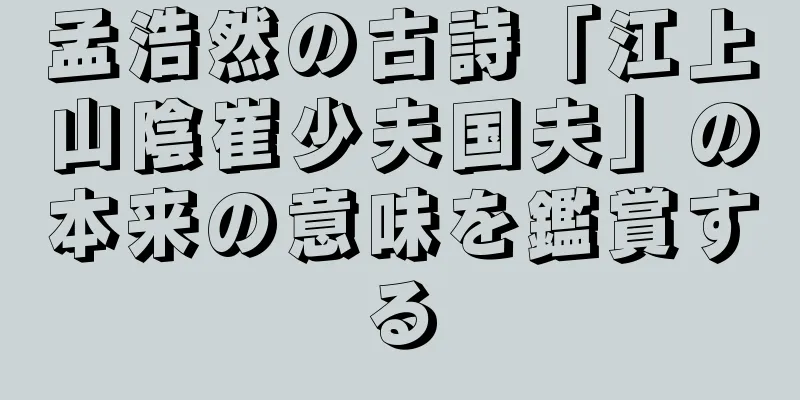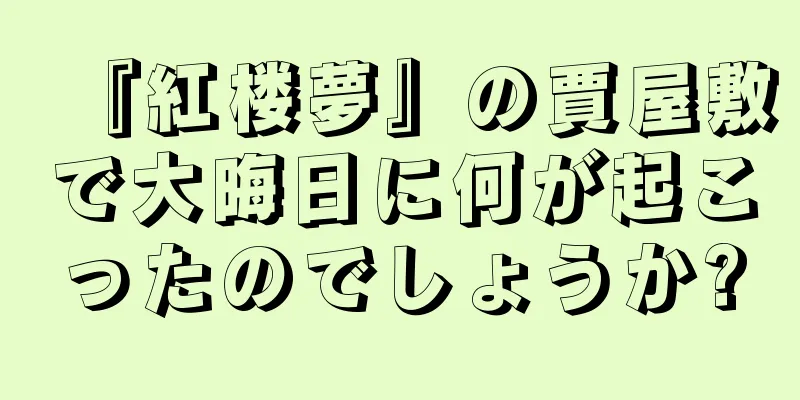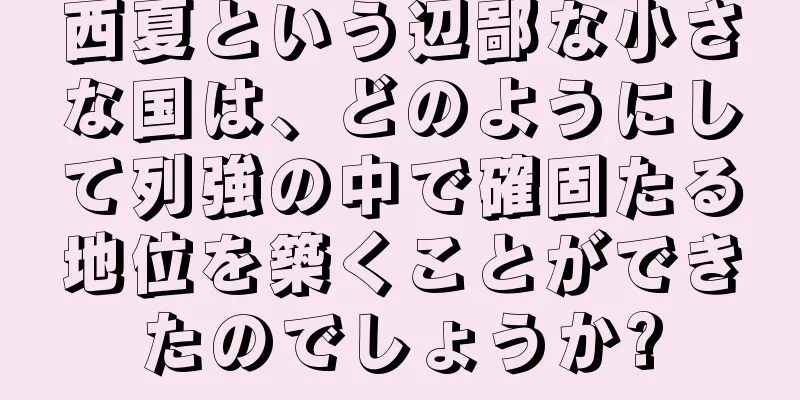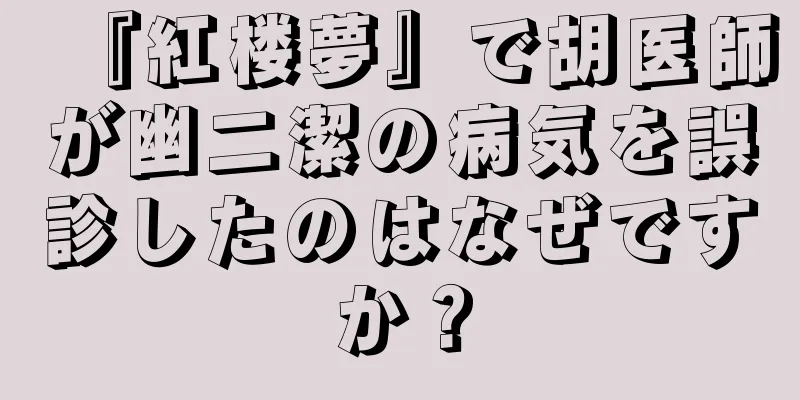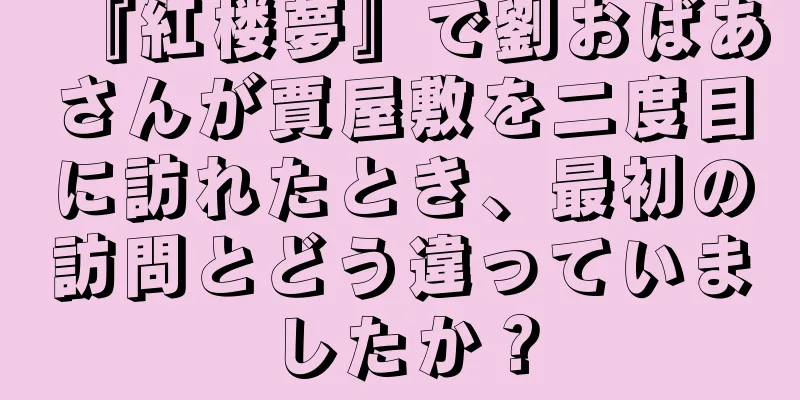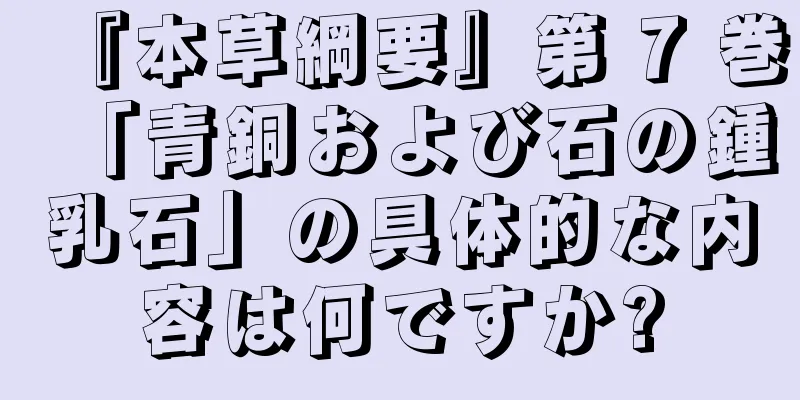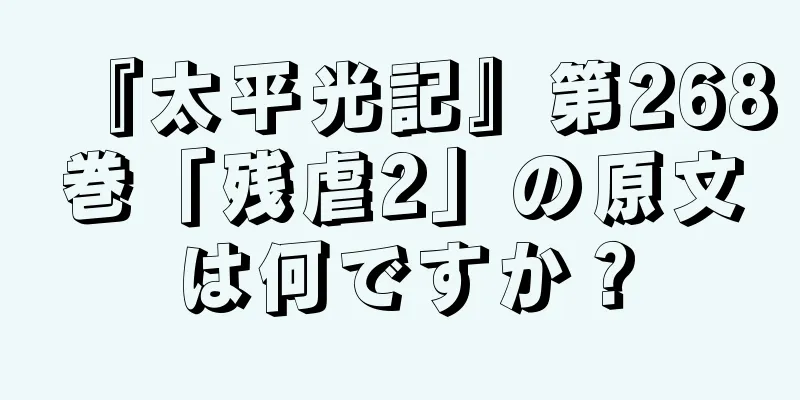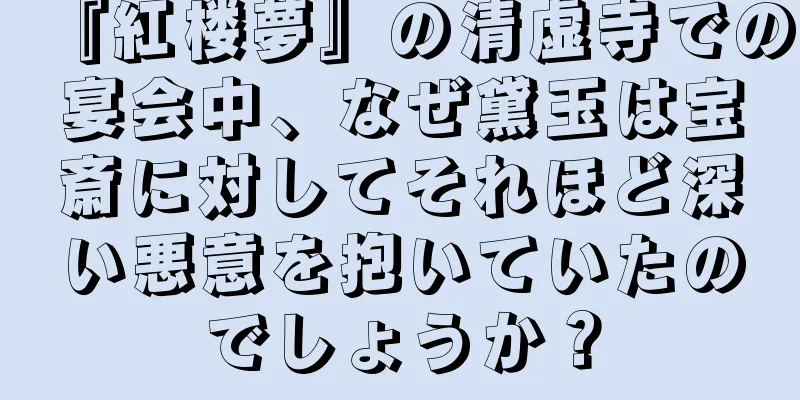司馬遷の誕生日に関する論争は何ですか?歴史書にはどのように記録されているのでしょうか?
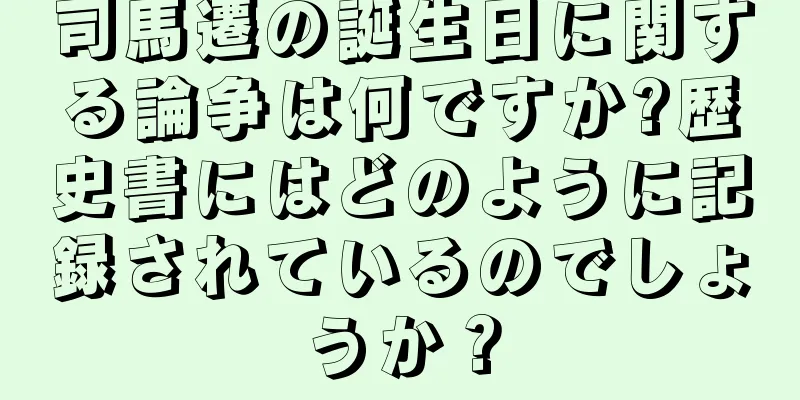
|
司馬遷の出生時期に関する論争とは?次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 生年月日 司馬遷の生年は『史記 司馬遷自伝』には記載されておらず、班固の『漢書 司馬遷伝』にも記載がない。その後の研究者は司馬遷が紀元前145年(景帝の治世中元5年)に生まれたと主張し、また別の研究者は司馬遷が紀元前135年(武帝の治世建元6年)に生まれたと主張したが、その差は10年であった。 『司馬遷自伝』の「正義」は紀元前145年に書かれたもので、唐代の張守傑によって注釈がつけられた。 『義経』の注には「太初元年、銭は42歳であった」とある。紀元前104年(太初元年)から41年遡ると紀元前145年(景帝の中元5年)となる。王国衛、梁啓超らがこの見解を主張した。紀元前135年は『司馬遷自伝』の「蘇记」から取られたもので、晋の張華の『伯武志』によると、「官司馬遷、28歳、彝暦6月に生まれ、石であった」と記されている。つまり、紀元前108年(漢の武帝の治世の元豊3年)、司馬遷は28歳で史官に昇進した。このことから、27年前の紀元前135年(漢の武帝の治世の建元6年)が司馬遷の生まれた年となる。郭沫若らはこの見解を主張している。一般的には前者が採用されます。 建元六年 「建元六年説」を唱える人たちは、あらゆる手段を使って「伯武志」が正しいことを証明しようとし、張守傑の「義」は間違っていると信じている。主な理由は次のとおりです。まず、『伯武志』のこの項目には漢代の登記簿が記録されており、そこには司馬遷の名前、年齢、居住地、官職、就任年月、給与などが記録されています。漢代の文書から記録されたものなので、非常に詳細かつ正確であり、本物であることに疑いの余地はありません。これは、一般の歴史書の価値をはるかに超える独自の資料です。第二に、司馬遷の『任安宛書』には「不幸にして私は幼くして両親を亡くした」という一文がある。『義経』によれば、司馬遷は紀元前145年(景帝中元5年)に生まれ、父の司馬譚は紀元前110年(元豊元年)に亡くなったとすれば、司馬遷は36歳のはずである。通常、36歳で両親が亡くなることは「早すぎる死」とは言えません。 『伯武志』によれば、司馬遷は紀元前135年(武帝建元6年)に生まれた。つまり、司馬遷が26歳の時に父が亡くなったということである。彼は幼くして両親を失ったと言っても過言ではない。第三に、司馬遷が『任安宛書』を書いたのは紀元前91年(正和2年)である。もし彼が紀元前145年(景帝中元5年)に生まれたとすれば、その年55歳だったはずである。彼は20歳くらいで医者になり、諸国を旅して帰ってきた。したがって、30年以上も軟禁されていたはずである。司馬遷は自分がしたことさえ忘れなかった。彼が10年後、つまり紀元前135年(武帝の建元6年)に生まれた場合にのみ、この理論は真実となる。 景帝中元5年説 「経帝中元五ヵ年説」を唱える人たちは、張守傑の『正義』に依拠するだけでなく、次のような疑問や議論も提起した。まず、王国衛は『司馬遷年譜研究』の中で、後世の人が『伯武志』を引用したと信じており、したがって「二十八年」は「三十八年」の間違いであるはずだと主張した。 『義経』の注釈では「太初元年」とあり、司馬遷の「四十二歳」は正しい。第二に、『史記・徽章列伝』によると、紀元前127年(漢の武帝の元碩2年)、地方の有力者と資産300万束以上の富豪を茂陵に移住させる命令が出された。郭潔は財産があまりなかったが、強制的に移住させられた。司馬遷も郭潔と会って、「郭潔の容貌は凡人のそれとは程遠く、言葉も信用できないと思う」と言った。司馬遷が紀元前135年(建元6年)に生まれたとしたら、当時9歳だったはずで、これほど深い人に対する観察力や心理活動を持つことは不可能だっただろう。 司馬遷が紀元前145年(景帝の治世中元5年)に生まれたとすれば、彼の年齢は19歳となり、こちらの方が適切と思われます。第三に、『漢書・汝林伝』によれば、司馬遷は孔安国から古代中国語を学んだことがある。しかし、『史記・孔子家伝』と『資治同鑑』によれば、孔安国は紀元前127年(漢の武帝の治世の元碩2年)に医者だった。司馬遷は当時9歳だった。9歳の子供が官学院に行って儒教の古典の達人に助言を求めたり、問題を議論したりすることは不可能である。もし彼が紀元前145年(漢の景帝の治世の中元5年)に生まれたとしたら、彼はその年に19歳であり、より合理的であるように思われる。司馬遷の生涯については多くの論争がありますが、最も議論を呼んでいるのは彼の生年です。 |
<<: 西南夷は今どこにいるのでしょうか?司馬遷と西南夷との関係は何ですか?
>>: 司馬遷の家族背景はどのようなものでしたか?私たちの祖先である司馬匡はかつて張毅と議論した。
推薦する
黄景仁の「都秋の思索四詩第3」:詩全体はタイトルの日付に基づいているが、制限されるという欠点に縛られていない。
黄景仁(1749-1783)は清代の詩人であった。号は漢容、別名は鍾沢、号は呂非子。楊湖(現在の江蘇...
王維の古詩「王川集臨湖閣」の本来の意味を鑑賞
古代詩「王川集臨湖亭」時代: 唐代著者 王維軽快な船がゆっくりと湖を渡ってお客様をお迎えします。館内...
水滸伝の涼山における孫礼の順位は何ですか?なぜ天崗星に入らなかったのですか?
孫礼は古典小説『水滸伝』の登場人物で、「病弱な衛一」という異名を持つ。今日は、Interesting...
神話の傑作の原文を鑑賞する:『封神演義』第41章:文師の軍隊が西斉を攻撃する
その詩はこう述べています。グランドマスターは軍隊を孤山から出撃させ、西風が沈む太陽を吹き飛ばしました...
東晋の葛洪著『包朴子』内章精励全文と翻訳
『包朴子』は晋の葛洪によって書かれた。包埔([bào pǔ])は道教の用語です。その由来は『老子』の...
『紅楼夢』で宝仔が易虹院に現れ、昼休みに針仕事をしていたのはなぜですか?
薛宝柴は曹雪芹の長編小説『紅楼夢』のヒロインの一人です。以下の興味深い歴史編集者が詳しい記事の紹介を...
金陵十二美女の関係は?彼らと賈宝玉との関係は?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
孫権の三男、孫和の側室は誰でしたか?孫和には何人の息子がいましたか?
孫和(224年 - 253年)、雅号は子霄、三国時代の呉の初代皇帝孫権の三男。王夫人は孫和の姉妹の一...
隋唐演義 第六章 五花結 柴思昌は山寺で婚約、足の不自由な秦叔宝は窮地に
『隋唐志演義』は清代の長編歴史ロマンス小説で、清代初期の作家朱仁火によって執筆されました。英雄伝説と...
馮延思の『長寿女・春の宴』:古代女性の幸福な生活の追求を表現する
馮延嗣(903-960)は、正忠、仲潔とも呼ばれ、南唐の丞相馮霊懿の長男であった。彼の先祖は彭城出身...
『隋唐代記』第65章:竇建徳が唐軍と戦う
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
チニング宮殿には普段誰が住んでいますか?チニング宮殿の歴史的発展を明らかにする
慈寧宮には普段誰が住んでいるのでしょうか?慈寧宮は明代嘉靖15年(1536年)に初めて建てられました...
曹操の『渡海記』原文、注釈、翻訳、鑑賞、創作背景
曹操の「峠越え」については、興味のある読者はInteresting Historyの編集者をフォロー...
「神々の叙任」に登場する四大侯爵とは誰ですか?四大侯爵たちの最後はどんなものだったのでしょうか?
本日は、Interesting History の編集者が「神々のロマンス」に登場する 4 人の偉大...
中原の王朝は非常に進歩的で裕福でしたが、なぜ遊牧民によって支配されることが多かったのでしょうか?
歴史に少し詳しい友人は、常に避けられない疑問を持っているかもしれません。たとえば、なぜ先進的で裕福な...