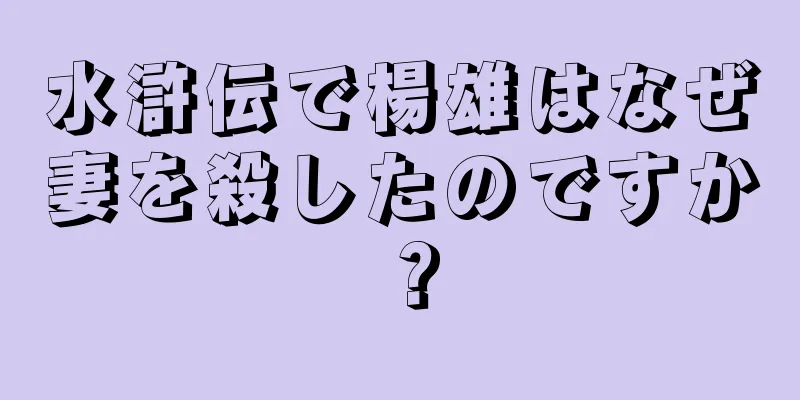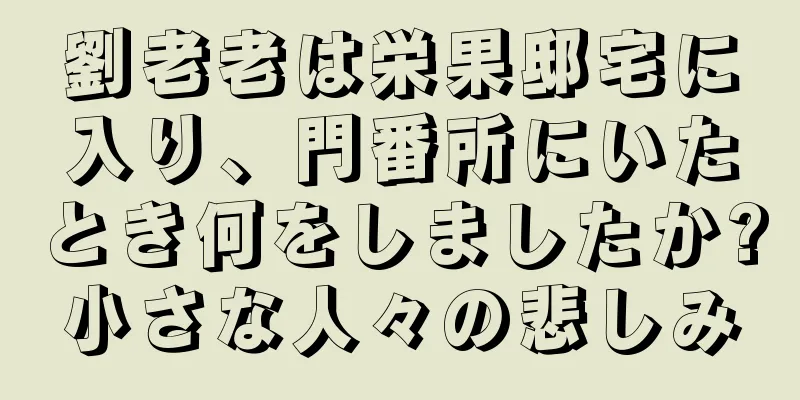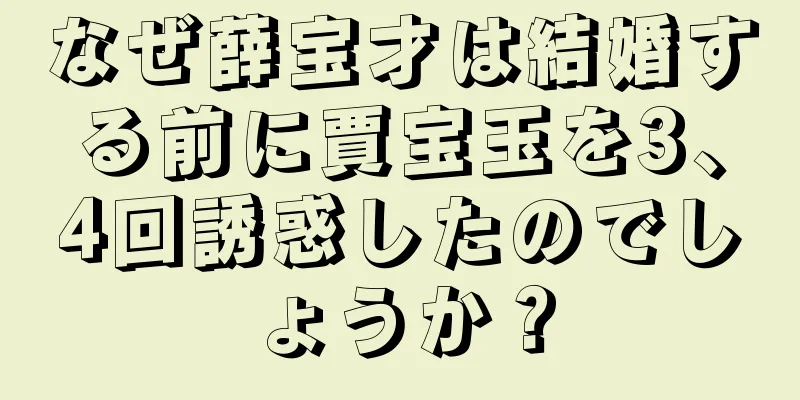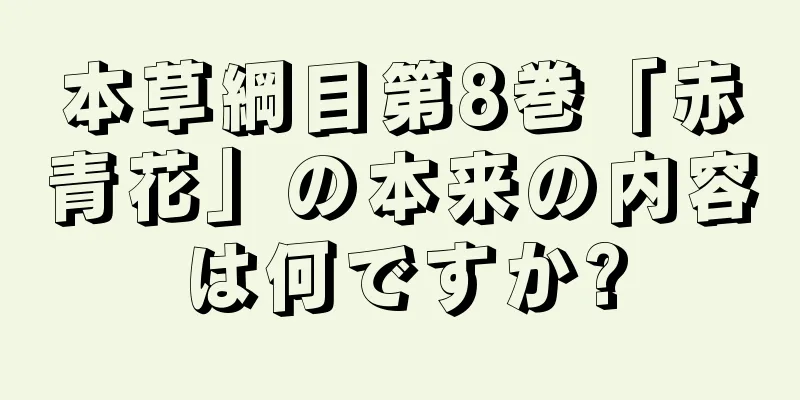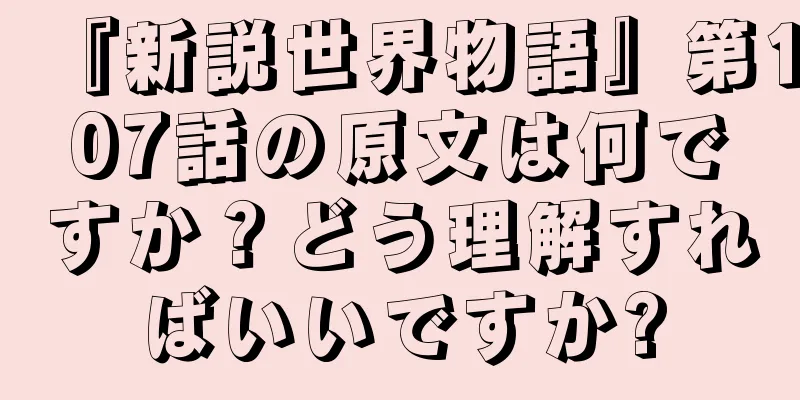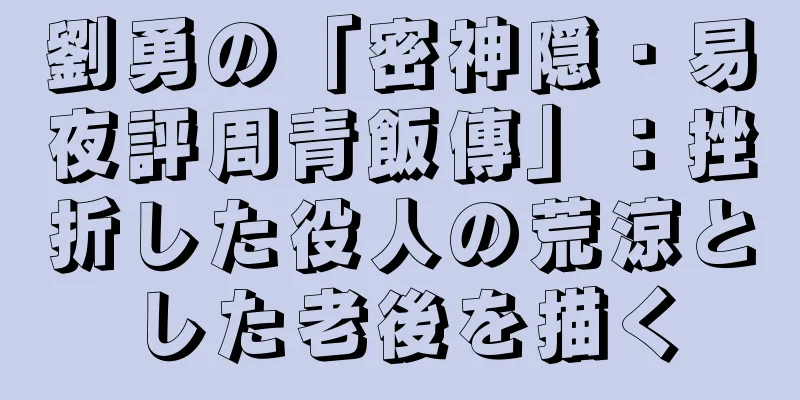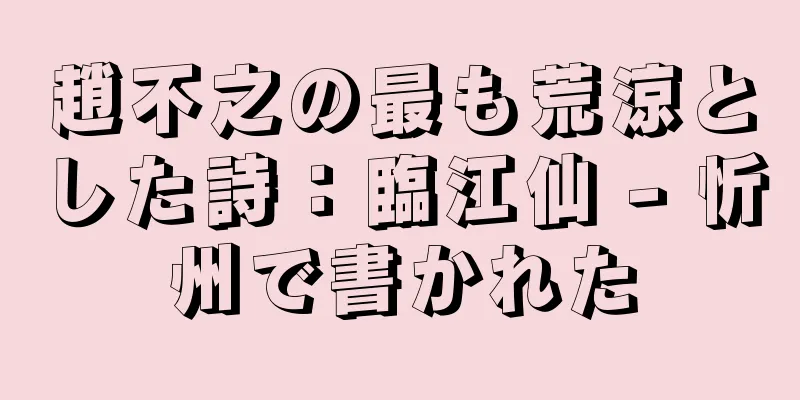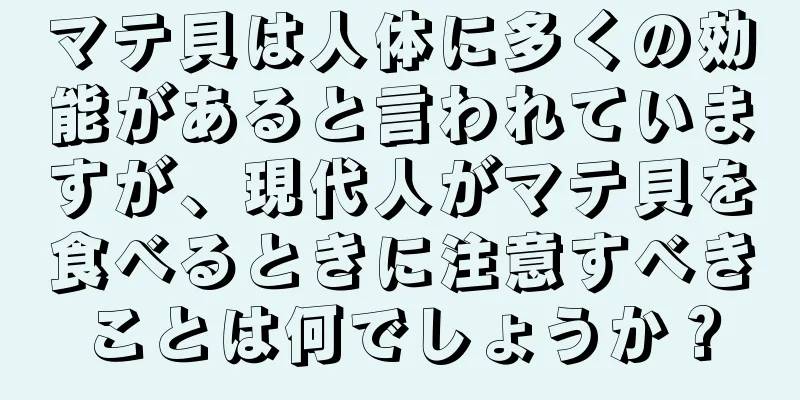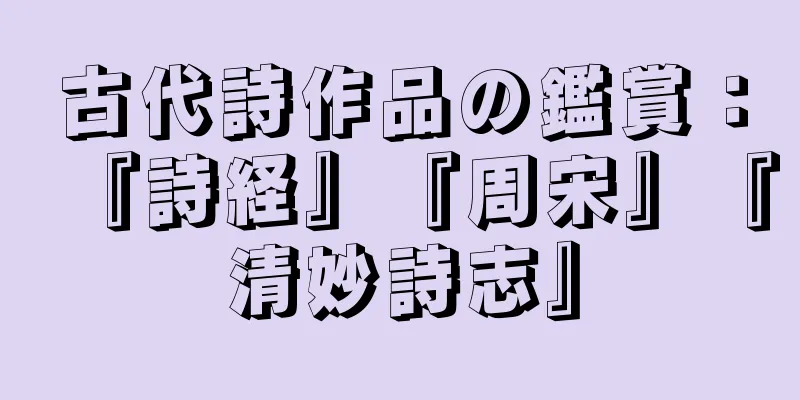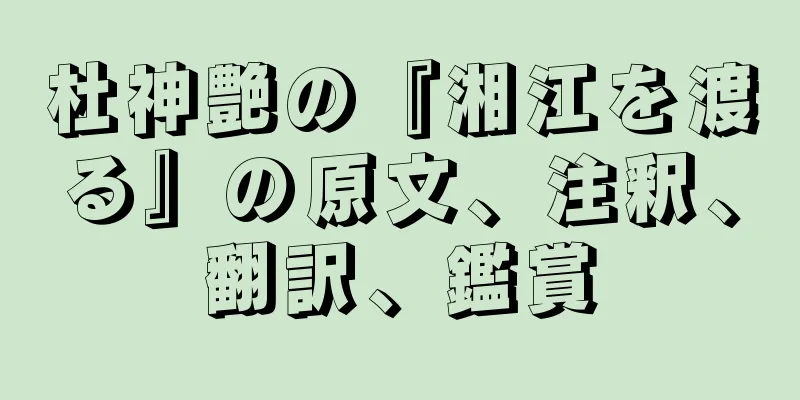竹林七賢の竹林は本当に地名なのでしょうか?七賢人は後世にどのような影響を与えたのでしょうか?
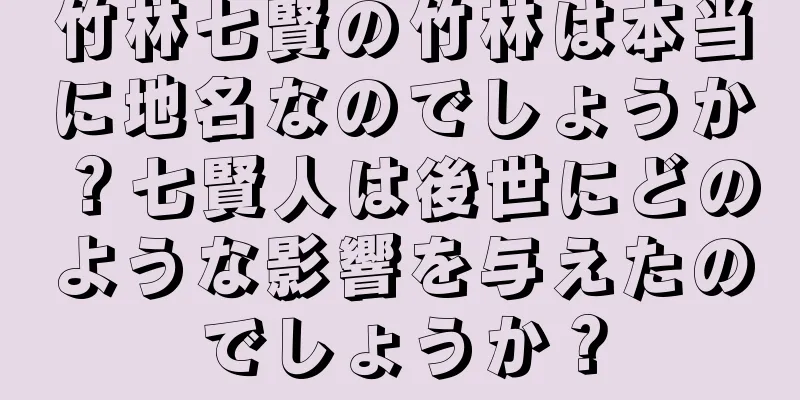
|
竹林の七賢とは、三国時代魏の正始年間(240-249年)に生きた紀康、阮季、善涛、項秀、劉霊、王容、阮仙のことで、彼らは最初七賢として知られていました。彼らは山陽県(現在の河南省恵県地区)の竹林の下でよく酒を飲み歌を歌っていたため、「七賢」と呼ばれていました。後に、この名前が竹林という地名と結びつきました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 西晋末期には、内なる経典と外なる書物とを比較して意味を解釈する「格意」(意味を解釈する)の風潮が流行し、東晋初期にはインドの「竹林」の名が採られ、「七賢」に加えられ、「竹林七賢」となった。 「竹林」は地名ではなく、実際に「竹林」が存在するわけでもありません。竹林七賢の作品は、基本的に建安文学の精神を受け継いでいるが、当時の血なまぐさい統治のため、作家たちは自分の感情を直接表現することができず、隠喩、象徴、神話などの技法を使って、曖昧で曲がりくねった方法で自分の考えや感情を表現しなければならなかった。彼らは常に人々から尊敬されてきました。 ジ・カンと他の7人は仲が良く、よく一緒に竹林の下を散歩したり、心ゆくまでごちそうを食べたりしていました。その後、「竹林宴会、竹林歓楽、竹林遊覧、竹林会談、竹林興趣、竹林狂乱、竹林笑」は、気ままな宴会や娯楽、あるいは切っても切れない友情を指す言葉として使われ、「七賢」は主流から外れた文人を比喩的に表現するために使われました。 「竹林七賢」の中で、山涛は最年長でした。紀康と阮季はどちらも山涛によって発見され、向秀も山涛によって発見され、紀康と阮季に紹介されました。したがって、山涛は竹林ツアーの実際の主催者であり、人員の中心でした。 主な影響 形而上学は、自然と宇宙を超越した「道」と「無」の精神的な追求と哲学的領域を強調します。形而上学の勃興は、漢末期の社会危機の深刻化、漢王朝の崩壊、儒教経典の衰退と密接な関係がある。正史形而上学の影響下で、季康などの名学者の不条理で奇妙な行動は、実は私利を捨てて公益を重視し、自意識と精神を覚醒させ向上させたことの表れであった。彼は独特の作風で、風変わりで自己満足的な「竹林神秘主義」の名士たちの精神世界を表現した。劉謝は『文心と彫龍』の中で、「正始年間に道が初めて明らかにされたとき、詩は仙思想と混じり合っており、何や燕の弟子たちはほとんどが表面的だった。ただ季康の志は明確で高尚であり、阮の志は深遠であったため、彼らは際立っていた」と評している。「仙思想」は「漠然として幽玄で、言葉が尽きない」という作風を呈している。季康の詩や随筆からは、後世に多大な影響を与えた魏晋の名士たちの神秘的な風格と作風を垣間見ることができる。 玉彫刻では、上海風の玉彫師、穆玉静が竹林七賢の文学的影響を利用して玉彫刻を制作しました。竹林七賢の玉彫刻は両面が浅い浮き彫りで、紀康、阮吉、山涛、項秀、劉玲、王容、阮仙が竹林の下に集まって将棋をしたり、音楽を楽しんだり、書画を論じたりして、自由奔放な様子が表現されています。彫刻は新鮮で洗練されています。2011年には「上海玉彫神匠賞」の金賞を受賞しました。これも古代文学と現代の職人技の完璧な融合であり、我が国の深遠な文学と思想観を反映しています。 |
<<: 「竹林の七賢」という名前はどのようにして生まれたのですか? 『晋書・済康伝』にはどのように記録されているのでしょうか?
>>: ジ・カンさんの人生経験はどのようなものでしたか?なぜ司馬昭は彼を処刑するよう命じたのでしょうか?
推薦する
『西遊記』に登場する七人の聖人とは誰ですか?孫悟空
はじめに:孫悟空としても知られる孫悟空は、中国明代の小説家、呉承恩の作品『西遊記』の登場人物の一人で...
崇禎はなぜ死ぬ前にすべての文官を殺してもいいと言ったのでしょうか?崇禎が商業税を徴収できなかったからでしょうか?
多くの人の印象では、古代中国の皇帝は最高権力を持っていました。皇帝は望む者を誰でも殺すことができ、望...
『世界の物語の新記録: 賞賛と報酬』の第 118 記事の教訓は何ですか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。それでは、『十碩心於·賛·118』に表現さ...
唐代の詩「科挙に失敗して帰国した斉無謙に別れを告げる」をどのように鑑賞するか?王維はどのような感情を表現したのでしょうか?
科挙に失敗した斉無謙を帰国させる [唐代] 王維、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますの...
韓国の葬儀文化の紹介 韓国の葬儀の習慣は何ですか?
朝鮮民族は古来より孝行をすべての徳目の中で最も重要視しており、そのため葬儀や祭祀においては他の儀式よ...
秦克清は一日に何度も着替えなければならなかった。その理由は何だったのか?
今日は、Interesting Historyの編集者が秦克清についての記事をお届けします。ぜひお読...
リン・ダオユのメイド、チュンシェンのイメージは?ダイユウの死の油に関連する
Interesting Historyの編集者がお届けする春仙に関する記事を見てみましょう。林黛玉の...
『紅楼夢』で賈の母親は宝仔の誕生日にいくら使いましたか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。興味深い...
歴史上6人の皇帝と結婚した蕭美娘の簡単な紹介
歴史上、皇帝を魅了し、多くの人々の心をつかんだ美女は数え切れないほどいますが、孝皇后のように王朝の変...
漢の武帝はどのようにして脱税を防いだのでしょうか?絹糸の計算と報告のシステムはどのくらい前から導入されていますか?
漢の武帝はどうやって脱税を防いだのか? 絹算と絹報はどのくらい続いたのか? 次の興味深い歴史編集者が...
「The Road Is Hard, Part Three」をどう鑑賞するか?創作の背景は何ですか?
道は険しい パート3李白(唐)耳があるなら、銀川の水で洗ってはいけません。口があるなら、寿陽草を食べ...
『紅楼夢』では、妾として戴冠し賈邸に戻った黛玉に対して、元春はどのような態度をとっていましたか?
袁春が両親を訪ねる場面は『紅楼夢』の壮大なシーンで、「花が咲き、燃える火に油が沸き立つ」。今日は『お...
『紅楼夢』でシエルの運命はどのように変わったのでしょうか?
思兒は曹雪芹の古典小説『紅楼夢』の登場人物である。今日は、Interesting Historyの編...
秦王朝の滅亡後、項羽の国はなぜ「東楚」ではなく「西楚」と呼ばれたのでしょうか?
秦末農民反乱は、秦末農民反乱とも呼ばれ、中国本土では秦末に多くの英雄が台頭した事件に付けられた名前で...
鉄樹地獄とは何ですか?中国神話における地獄の18層を明らかにする
はじめに:鉄樹地獄。中国の民間伝承における地獄十八階層の第三階層。生きている間に親族を疎遠にし、父と...