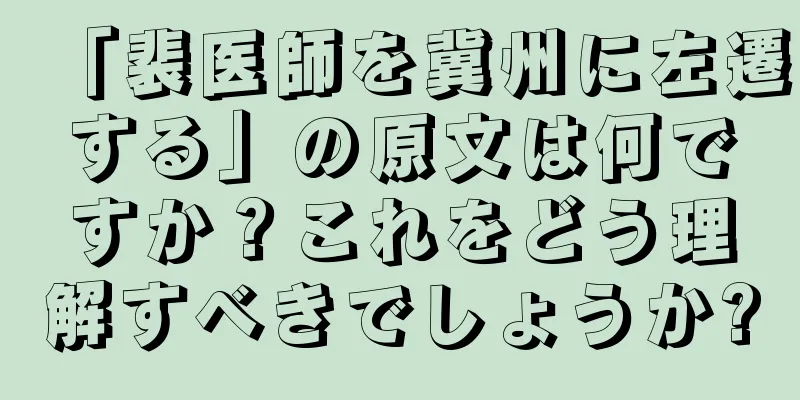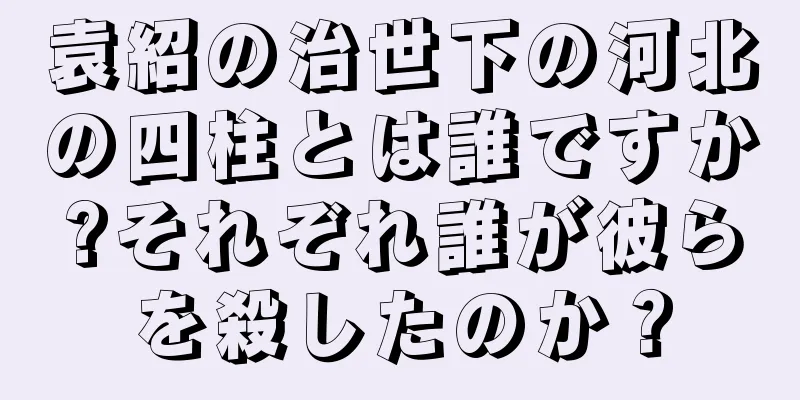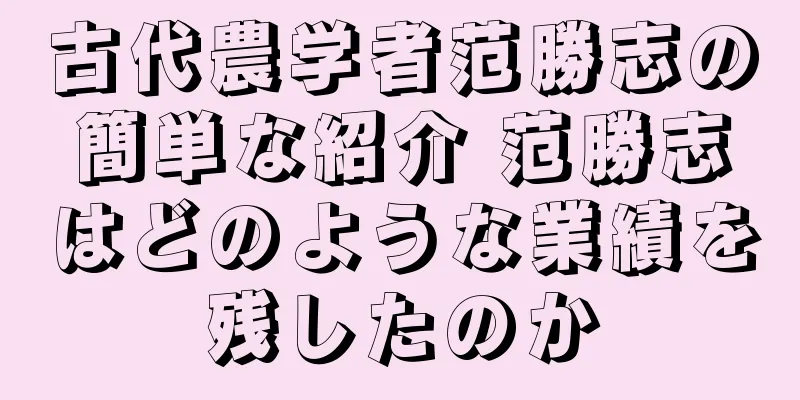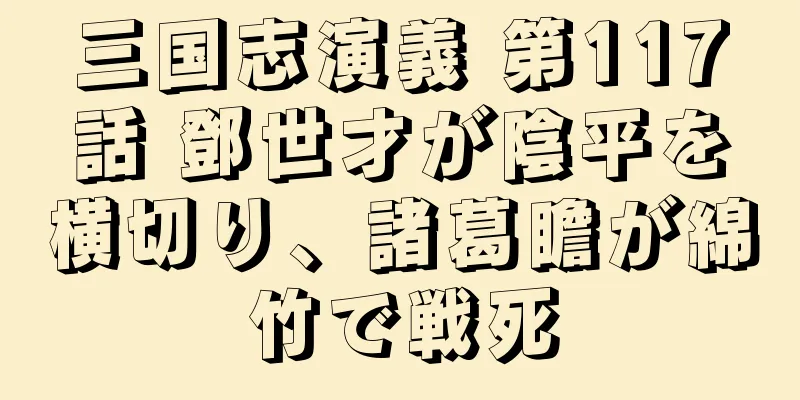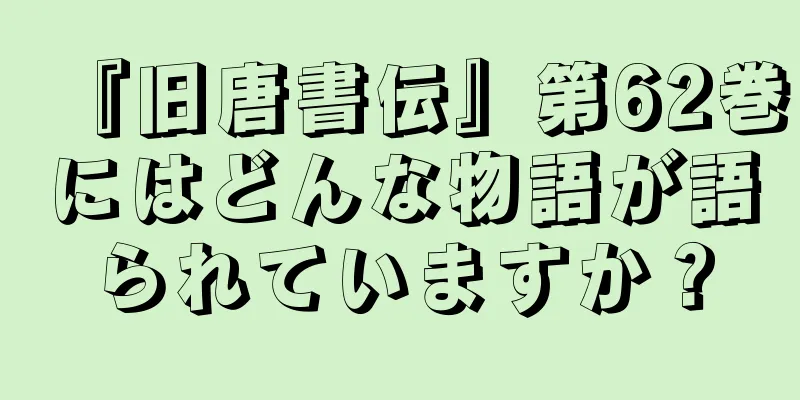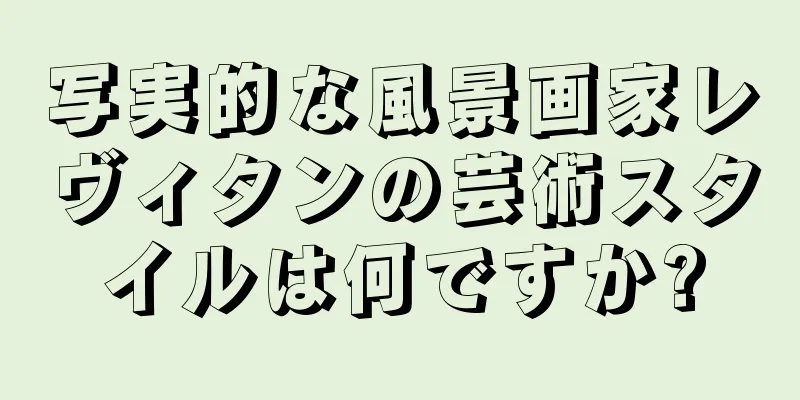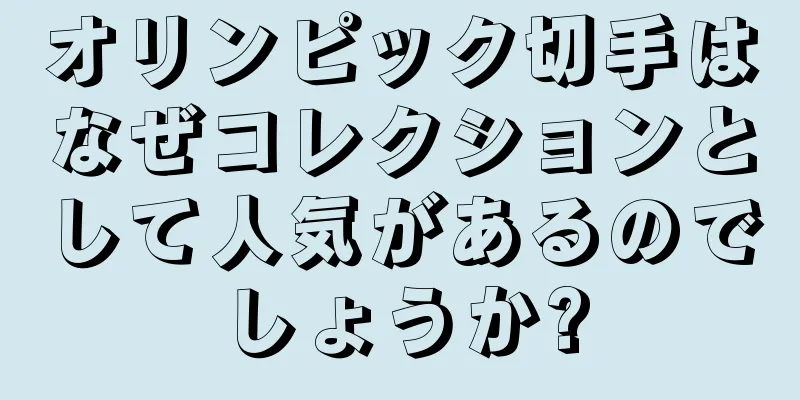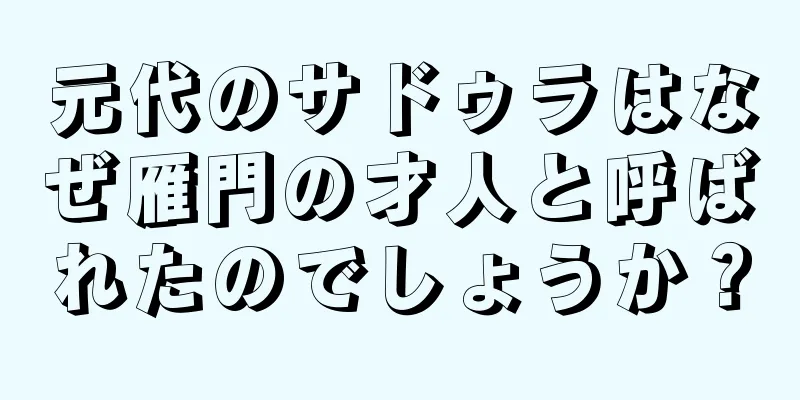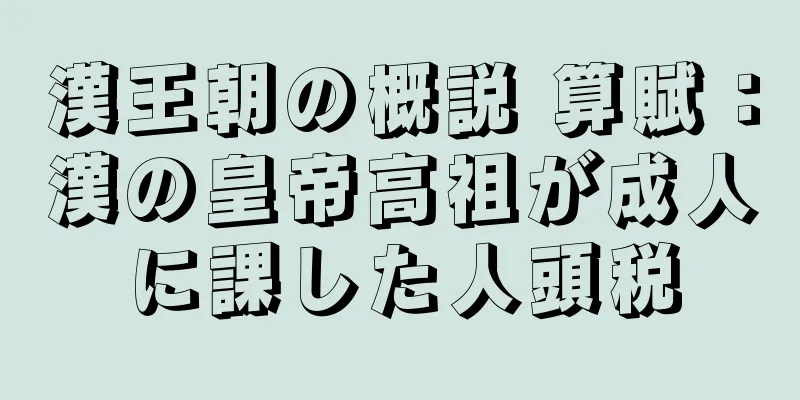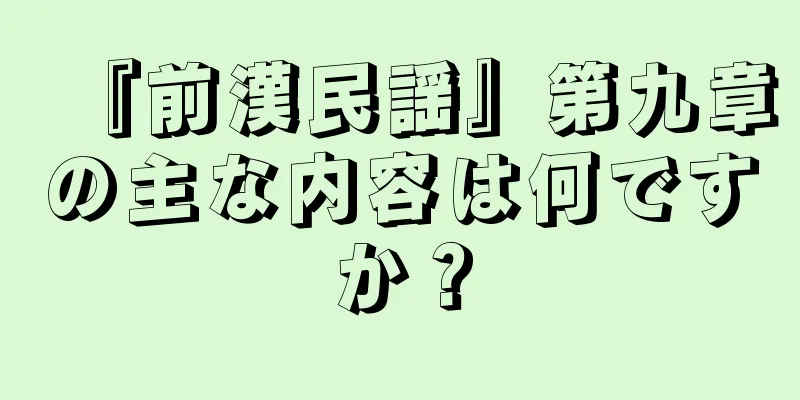春秋戦国時代の有名人は誰ですか?なぜ今の時代にはこんなにも才能ある人が多いのでしょうか?
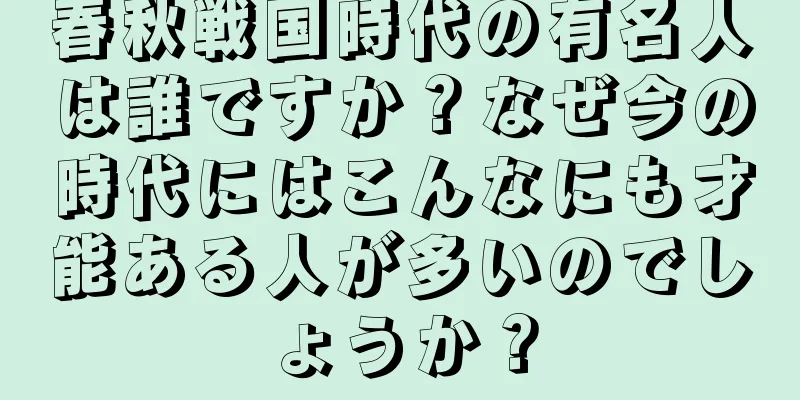
|
春秋戦国時代は、中国で大きな争いがあった時代であり、中華文明と思想の頂点でもありました。この時代は非常に素晴らしく、才能のある人が大量に現れ、ほとんどすべての叙事詩の達人が大量に現れました。この時代は当然、中国文明の枢軸時代と呼ばれるに値します。 この時代の国宝には『論語』『道徳経』『荘子』『韓非子』『兵法』『魯班書』などがあり、どの書物もその高さは後世のものに匹敵するしかない。 その時代を代表する偉人、老子、孔子、墨子、荘子、商阳、孫武、桂姑子、龐煥、蘇秦、張儀、李冰、魯班について話しましょう。 。 。彼らはそれぞれがそれぞれの分野で最高の人物であり、後世を振り返ってみると、これほど多くの優れた人物が同時に現れた時代はかつてなかったように思われます。では、なぜこの時代はこれほど多くの優秀な人材を輩出したのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 理由1:競争の激しい時代では、優秀な人材に対する需要が高い 春秋時代、中国には数十、数百もの属国がありました。より多くの土地と富を得るために、彼らは皆、国を改革し強くするために人材を求めていました。多くの国が人材を必要としているとき、彼らはどうすればよいのでしょうか? 君主たちは行動を抑制し、人々を尊重し、さまざまな国から人材を引き付けるために非常に良い政治環境を作ろうとしました。この緩やかな状態の下で、人々の間の学術交流は非常に便利になり、自然に多くの人材が生まれました。 理由2:平和な王政時代は学習環境が良かった 春秋時代には属国が最も多く、互いに併合したり分裂したりして人材の流出が頻発し、さまざまな思想が競い合いました。周の皇帝を支持するもの、君主を支持するもの、他国を守るものなど、さまざまな思想が生まれました。その結果、儒教、道教、墨家、兵学など、さまざまな学派が生まれました。7つの属国が比較的安定した後、各国の君主の統治下で世の中は比較的平和で、学習環境も良好でした。当然、学派の継承も良くなりました。官職を求めるために、多くの官僚が各国に自らを推薦しに行き、当時は人材が大量に生まれました。 理由3: 大きなステージ、多くの選択肢 春秋戦国時代は、どこで生まれても必ずしも特定の国に忠誠を誓う義務はありませんでした。例えば、蘇秦は6カ国の印章を与えられ、さまざまな国と同盟を結びました。孔子は国家統治の考えを広めて回っていました。張儀は魏の生まれですが、秦に着くまで評価されませんでした。墨家は国のバランスを保ち、どこでも正義を守ることに尽力しました。当時は、後から決着をつけるような人はいませんでした。つまり、良い関係であれば留まり、そうでない場合は去るのです。他に何ができるでしょうか。春秋戦国時代、ある国で雇われなかった人が次の国で雇われることが可能だったのは、まさにこのような段階的な選択があったからです。 理由4: 一般的な傾向 現時点では、世界全体を見渡すと、この段階で世界全体がほぼ特定の瞬間に入っています。中国には数百の思想学派があり、同時代の古代ギリシャにもソクラテス、プラトン、アリストテレスなどがいました。古代インドにも釈迦牟尼がいました。 後期には、全世界が合意した後、統治者たちはもはや世界を征服する方法を追求するのではなく、思想を統一して世界を統合する方法を模索しました。そのため、ほとんどの統治者はすべての思想の流派を廃止し、これらの目的のために1つの流派のみを尊重するようになりました。 |
<<: 古代における「世襲制」の相続制度とは何だったのでしょうか?それはどの時代に始まったのですか?
>>: 春秋戦国時代は戦争が絶えなかったのに、なぜ民衆の蜂起が少なかったのでしょうか?
推薦する
グリーンファントムの効果と機能は何ですか?着用時に注意すべきことは何ですか?
グリーンファントムの機能や効果は?着用時に注意すべき点は?読者の皆さんと一緒に学んで参考にしてみまし...
書家ヤン・ジェンチンの書道の特徴:太くて不器用な筆遣いで、鋭さは感じられない
顔真卿は有名な書家です。彼が発明した顔の書風は、唐代初期の書風とは対照的です。彼の書風は主に豊かで力...
清朝の男性の髪型の起源。清朝の男性はなぜ三つ編みをしなければならなかったのでしょうか?
清朝時代の男性は三つ編みをし、額の髪をすべて剃っていました。この髪型は清朝時代のテレビドラマで何度も...
諸葛亮の兄として、諸葛瑾はどれほど才能があるのでしょうか?
『三国志演義』では、諸葛亮は知恵と徳の体現者であり、輝く星のような存在です。しかし、諸葛亮の栄光の下...
『西山秋涼図に詠まれた水の旋律』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
水の旋律の歌:西山秋の絵に刻まれたもの那蘭興徳(清朝)空っぽの山の中では仏の祈りの声が静まり、月と水...
『青春の旅 春にひとり欄干に寄りかかる』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
若い旅人:春の手すりに一人でいる十二人欧陽秀(宋代)春に一人で欄干に立つと、澄み切った青空が遠くの雲...
李玉の『死後の姿を見る詩』は作者の生活状況を描写している
李郁は五代十国時代の南唐最後の君主であり、唐の元宗皇帝李靖の6番目の息子でした。李毓は皇帝の座に就く...
モンゴルと清朝が中原を侵略したとき、中国最古の家族は何をしたのでしょうか?
モンゴルと清朝が中原を侵略したとき、中国最古の家族は何をしたのでしょうか。Interesting H...
喬記の「水の妖精:心を揺さぶる、別れ、悲しみ、病気」:ビジネス界の多くの言葉が、
喬基(1280年頃 - 1345年)は、雅号を孟頌といい、聖和文、興星道人としても知られた。太原(現...
西遊記続編第29章:陰陽を逆転させて創造を探る
明代の神話小説『続西遊記』は、『西遊記』の3大続編のうちの1つです。 (他の2冊は『続西遊記』と『補...
熙公10年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記されているか?
古梁邇が熙公10年に書いた『春秋古梁伝』には何が記録されているのでしょうか?これは多くの読者が関心を...
8人が乗る輿とは何ですか?古代では、8人がかりで担ぐ輿にどの程度の官吏が乗れたのでしょうか?
八人乗りの輿とは、8人が乗る大型の輿のこと。昔の結婚は正式な仲人がいて、夫の家族が輿で花嫁を迎えに行...
古代人は、「三度の犬の日」は悪霊によって引き起こされると信じていました。つまり、彼らは犠牲として犬を殺し、その食べ物を分け合ったのです。
「最初の土用の丑の日に餃子を食べ、2番目の土用の丑の日に麺を食べ、3番目の土用の丑の日に卵でパンケー...
何卓は亡き妻を懐かしみ、「江澄子」に匹敵する詩を書いた。
本日は、『Interesting History』の編集者が何朱の物語をお届けします。ご興味のある読...
皇帝の物語:もし項羽が呉江で自殺していなかったら、再起できたでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...