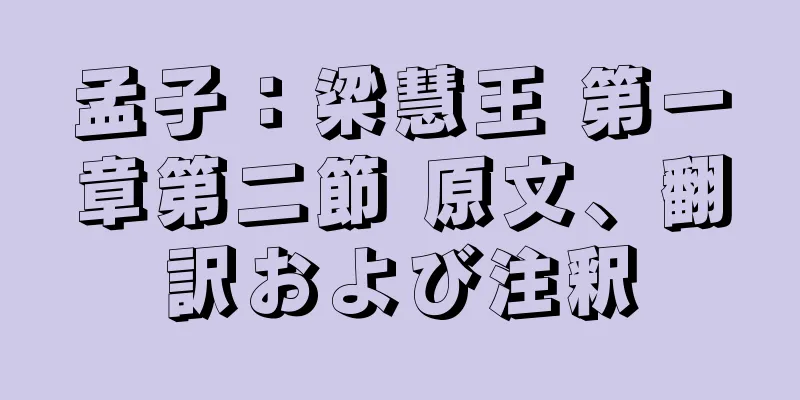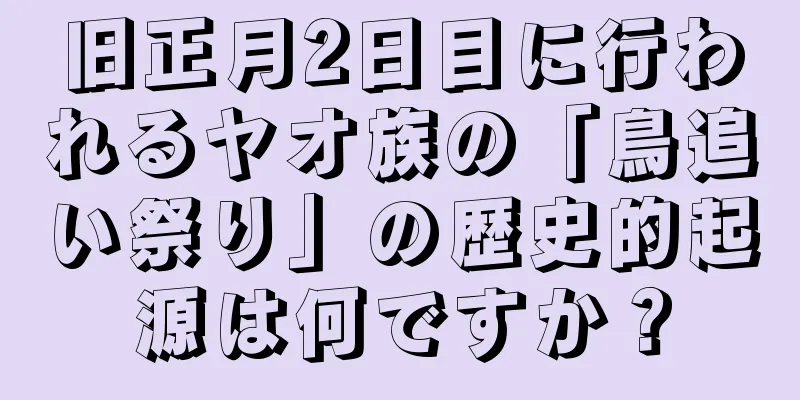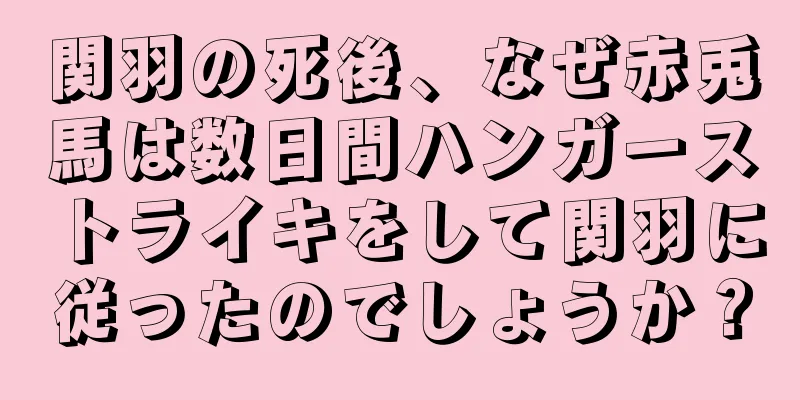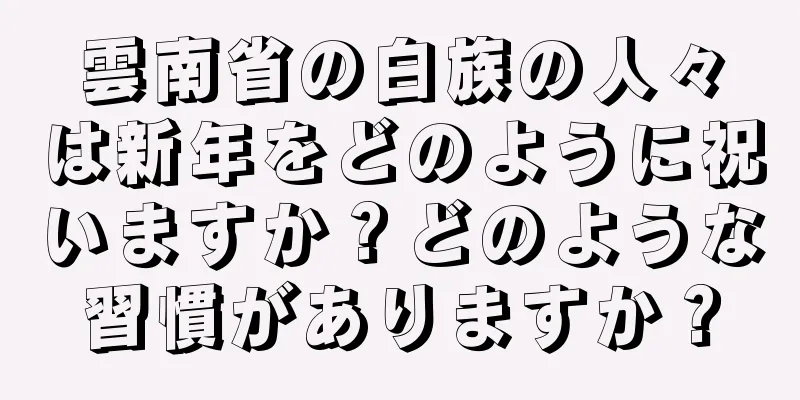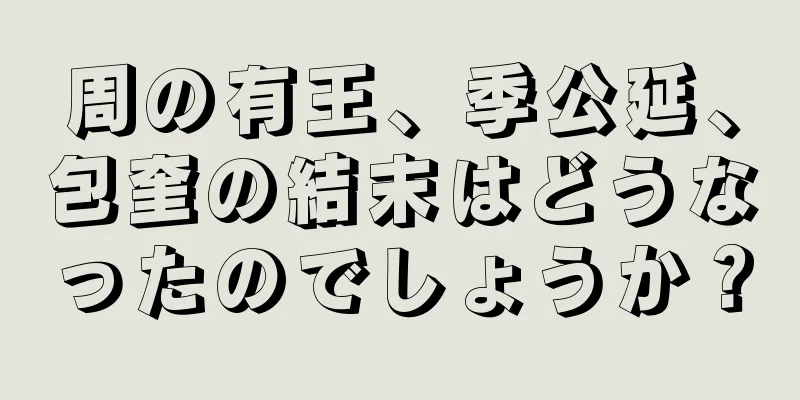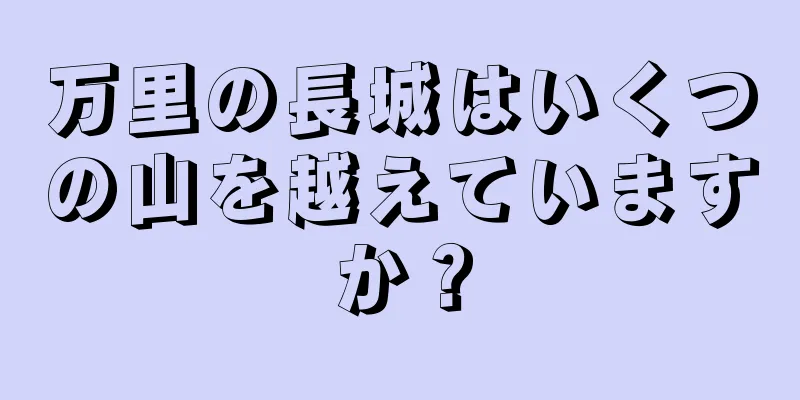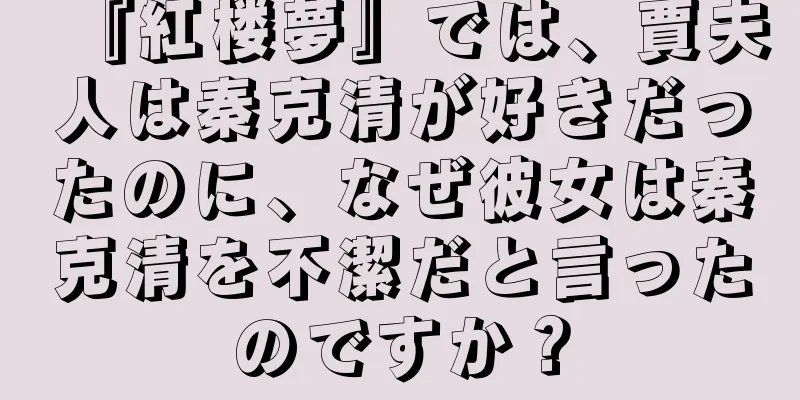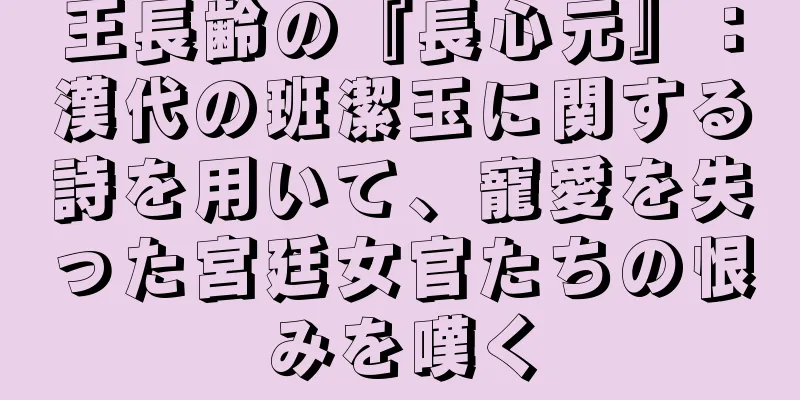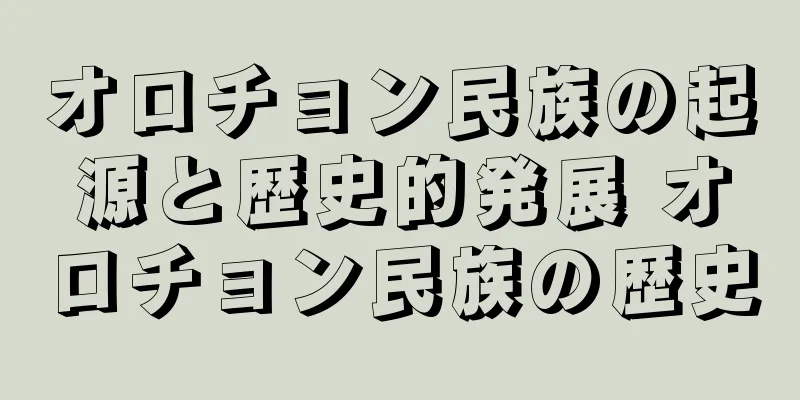宋代には中書と書密院という二つの機関が設立されました。それぞれの特徴と機能は何ですか?
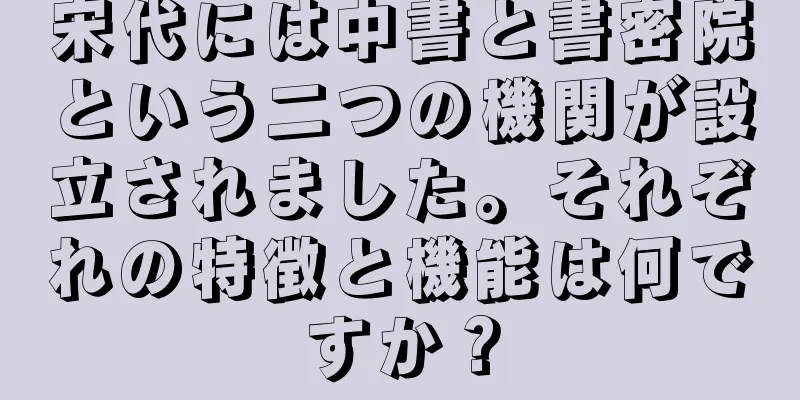
|
宋代の中央機関は「二省制」であり、つまり、官房と枢密院という二つの機関があり、「文武二つの権力を有し、二省と呼ばれた」。二政府体制の特徴は、民政と軍事の権力分立である。それは首相の権力を弱め、天皇の権力を強化するための重要な措置でした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 中書 宋代の「中書」は唐代の「中書門舎」と同じ性格を持ち、宰相が執務する場所であった。中書に加えて、尚書と門下の名称もまだ存在していたが、それらは首相官邸ではなく外廷となっていた。 宋代初期には、唐代末期の制度が踏襲され、「董中書門下平章氏」(略称「董平章氏」)が宰相、滄芝政氏が副宰相となった。尚書程、朗、三師に至るまで、誰もがそのような称号を与えられ、首相や副首相になることができます。上書陵、世忠陵、中書陵など三州の長官は高位かつ重要な地位にあったが、任命されずに空席になることが多かった。 元豊年間に制度が改革され、上書左普社(門下士郎)が士中として宰相となり、上書有普社(中書士郎)が中書令として宰相となった。名目上は三省が復活したが、実質的には一つの省となった。二代目宰相は官房長官と書記官を兼務し、勅命を発令できるなど天皇に近い存在となった。副宰相には孟夏丞相、中書丞相、左右の宰相などがいた。徽宗皇帝の治世中に、宰相は太宰に、二番目の宰相は少宰に改められた。 南宋初期には、左右の尚書普社と中書門下平章師が宰相に任命され、門下士郎と中書士郎は滄之政師に改められて副宰相となり、左右の尚書官は廃止された。首相の肩書から判断すると、3つの省庁が1つに統合されたことになる。孝宗の治世には、上州の左・右の普社と中州の門下平章司が単に左・右の宰相に改められ、滄芝政司の地位は変更されなかった(左・右の宰相は、唐の玄宗の治世には上州の長官、宋では中州の長官であった)。 宋代には宰相に与えられる特別な称号もいくつかありました。蔡靖が全盛だった頃、彼は「三省を司る太師」を務めた。文延伯と呂公主は「平章軍事国務」と「平章軍事国務共同」としてベテランとして務めた。南宋代に韓托州が権力を握っていたとき、彼は「平昌君国師」として仕えた。彼は「重要な」軍事と国事という称号を使用しなかった。「重要な」という言葉を加えると彼の権限が制限され、重要な事柄についてのみ尋ねることができるためであり、「同じ」を使用すると彼の権限が排他的でないことを意味するためである。蔡と漢の称号はどちらも権力のある官僚が影響力を行使するために使った策略であり、宋代には一般的ではなかった。枢密院の起源もまた珍しいものである。唐代には左右の枢密顧問官がおり、伝統的に宦官が務めていた。唐代末期の枢密院は三省の外のもう一つの省であり、枢密院内閣は宰相の外のもう一つの宰相であった。それは通常の国家機関の外にある冗長な機関であり、専制君主制の下での宦官の権力濫用の産物であった。朱文は唐代末期に権力を掌握する前に、朝廷で実権を握っていた宦官を殺害し、学者を枢密顧問官に任命した。同時に、枢密顧問官を全権掌握から軍事権掌握へと変更した。宋代は五代体制を継承し、軍事を専門に担当する枢密院や枢密使の職を設けた。二省制による枢密院の設置は、宰相の権限を分割し、文武三権を形成するとともに、本来軍事を担当する陸軍省の権限を侵害することになった。宋代の枢密院長官は「本兵」と号した。 枢密院 枢密院長の正式な称号。宋代初期には枢密使、枢密副使であったが、あるいは枢密院長官、枢密院共同長官、枢密院書記(官)および枢密院共同書記とも呼ばれた。元豊改革の際には、枢密院長官や枢密院副長官といった官職名が独占的に使用されました。改革の過程では枢密院を存続させるべきかどうかの議論があり、その権限を陸軍省に統合すべきだと提案する者もいた。神宗は祖先の制度を重視した。「祖先は官吏に軍事権を与えず、特別な官吏を任命して軍事権を指揮させ、制度を維持させた。どうして廃止できようか」と述べた。そのため、元豊の改革が行われたとき、枢密院だけが残された。宋代には枢密顧問官や枢密院長官は文官から任命されることがほとんどで、軍人が副官に任命されることもあった。これは、文官を軍人より重視する政治体制を如実に反映している。 二つの政府の分離 宋代には宰相と統治官を合わせた「宰相」という用語がありました。宰は宰相を指し、東平章氏、尚書左普社・門下士朗、尚書有普社・中書士朗、尚書左・有普社、中書門下平章氏、左・有承祥、南宋代の宰相・副宰相に限定される。副首相には、副首相、帝国官房長官、官房長官、左翼首相、右翼首相、枢密院議長、枢密院副議長が含まれ、総称して「統治大臣」と呼ばれます。 宋代初期には、官房と枢密院が文武両権を握っており、両者の権力を併合することはできなかったため、宰相が枢密院議員を兼務するような事態はなかった。その後、西夏での軍の投入により、宰相と枢密院議長の連絡が途絶え、軍の指揮に支障をきたしたため、清暦の頃は宰相が枢密院議長を兼務することもあった。西夏の軍事作戦が終わった後、状況は元に戻り、パートタイム労働は制度化されなかった。南宋時代には秦檜、史密遠、賈思道などの有力官僚が宰相を務めながら枢密顧問官を兼務していたが、これは慣例ではなかった。寧宗皇帝の時代以降、宰相が枢密顧問官を兼務することが慣例となった。大臣の権力が天皇の権威を脅かすのを防ぐため、首相は枢密顧問官を兼務することはできない。その後、有力な官僚が同時に二つの地位を占めるようになり、皇帝の権力に影響が及ぶようになった。 |
<<: 唐代後期の制度とは異なり、宋代の中央機関はどのようなものだったのでしょうか。
>>: 金王朝の滅亡後、南宋は何をしましたか?むしろ、それはモンゴルが南部を侵略する口実となった。
推薦する
『後漢書 崔師伝』の原文と翻訳、『崔師伝』より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
農民反乱の指導者である呉広について簡単に紹介します。呉広の知恵はどこで発揮されたのでしょうか?
呉広(?-紀元前208年)、雅号は蜀、秦の国の陽夏(現在の河南省太康)の出身。秦末期の農民反乱の指導...
過去と現在の驚異 第19巻: ユ・ボヤは魂の伴侶に感謝するために琴を叩き壊す
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
『太平広記』第90巻に登場する四奇僧の登場人物は誰ですか?
北斗市宝子カップクロッシング木のコップを持って水を渡る人は北斗と呼ばれ、本名は不明です。彼はよく木の...
「暇なときから兄弟に送る手紙」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
余暇から兄弟たちへの手紙魏英武(唐代)庭に秋の草が生え、白い露が落ちると、故郷の兄弟たちはますます私...
諸葛亮はなぜ「歴代最も有名な宰相」と呼ばれてはいけないと言われているのでしょうか?
諸葛亮が時代を超えて有名な宰相であるというのは歴史的な結論のようです。実際、諸葛亮は歴代の名宰相では...
南宋の時代は詩において大きな成功を収めました。復興四大詩人として知られるのは誰でしょうか?
愛国心と抗敵心は南宋詩の最も重要なテーマとなった。北宋滅亡の悲劇は詩人たちの現実を顧みる熱意を再び呼...
周王朝には何人の皇帝がいましたか?周王朝の皇帝の姓は何でしたか?
周王朝は791年間続き、30代37人の皇帝が在位しました。周王朝の皇帝の一覧は次のとおりです。西周時...
漢王朝と河南の関係:河南は漢王朝の成功の理由であり、河南は漢王朝の滅亡の理由でもある!
漢王朝(紀元前202年~220年)は、前漢と後漢に分かれたが、秦王朝の後に強大な統一帝国となった。ほ...
『詩経・国鋒・孝行』の原文は何ですか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
リトルスター(先秦)あの小さな星は東に3つか5つあります。私は暗い夜の旅に出発し、昼も夜もあなたに仕...
『紅楼夢』で黛玉が賈屋敷に入ったとき、なぜ彼女の叔父二人は現れなかったのですか?
黛玉は『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女のリーダーであり、賈夫人の孫娘です。この点についてよく...
数十億年前の古代の鳥はどのような姿だったのでしょうか?凶暴な古代鳥の琥珀標本の簡単な分析!
数十億年前の古代の鳥はどんな姿だったのでしょうか? 凶暴な古代の鳥の琥珀標本の簡単な分析です! 興味...
戦国七雄の分布図を復元します。戦国七雄の滅亡の順番は?
戦国時代の七大国は、すべて同時に滅亡したわけではなく、残りの六つの国は秦国に併合され統一され、最終的...
斉門屯嘉とは何ですか? Qi Men Dun Jia はどのようにして誕生したのでしょうか?
奇門遁甲が何なのか分からない人が多いでしょうか?Interesting Historyの編集者に従っ...
『紅楼夢』で邢秀燕と薛可が一緒にいるのはなぜですか?彼らは結局どうなったのでしょうか?
「紅楼夢」に登場する女性たちの運命は、ほとんどが非常に悲劇的です。次に、Interesting Hi...