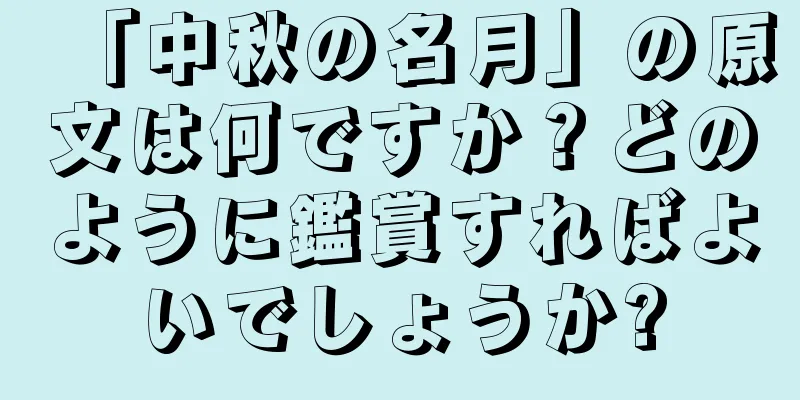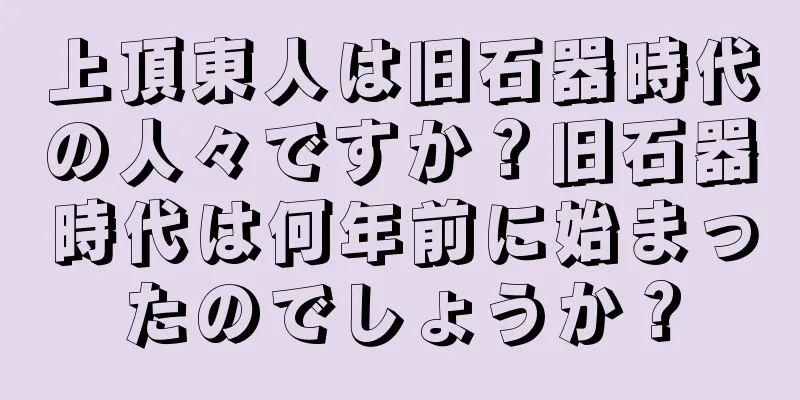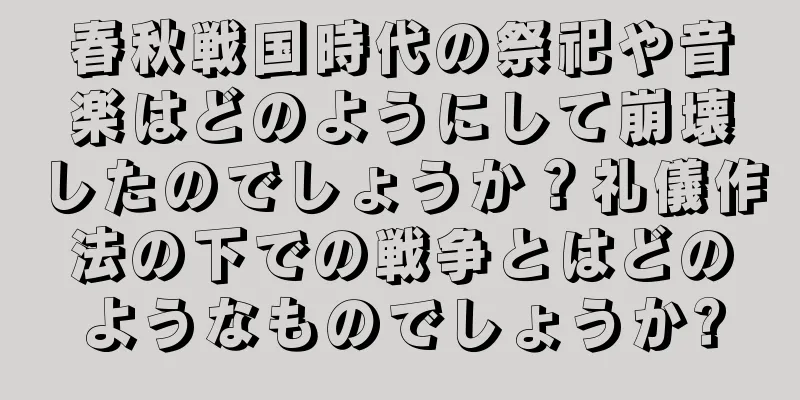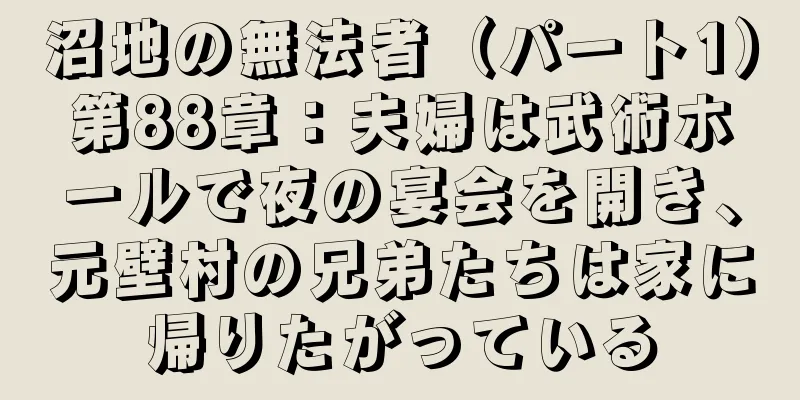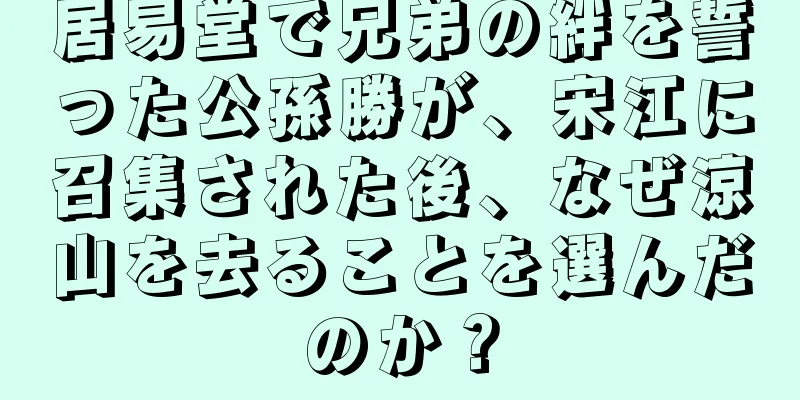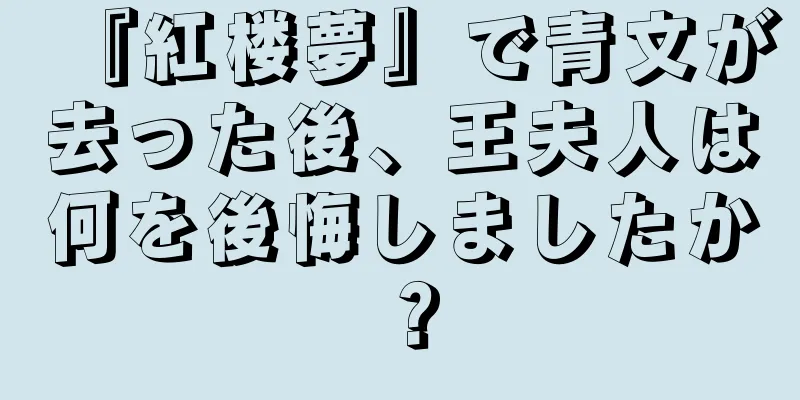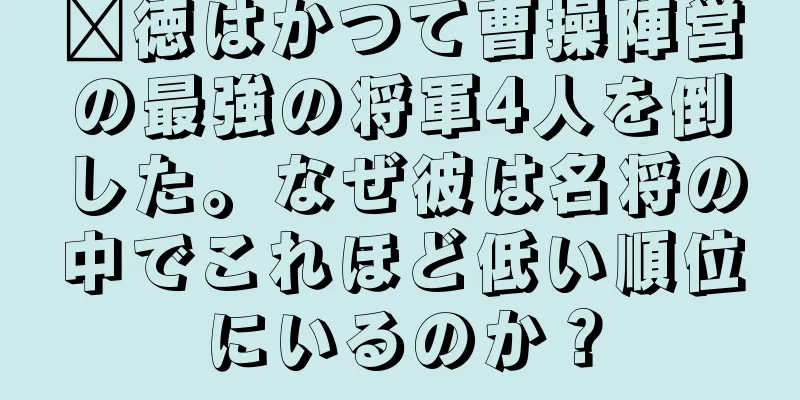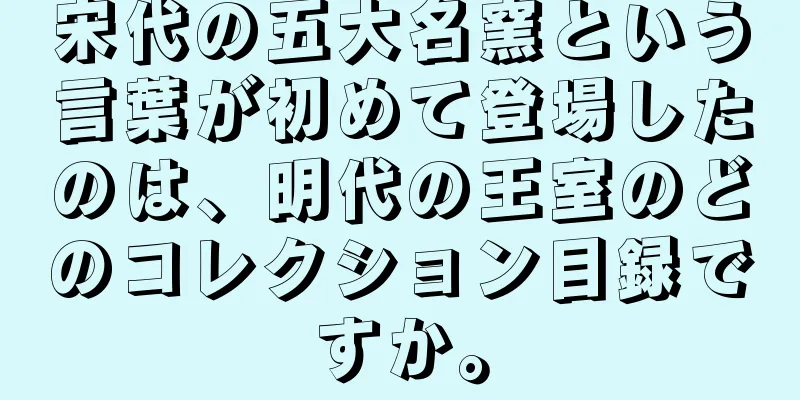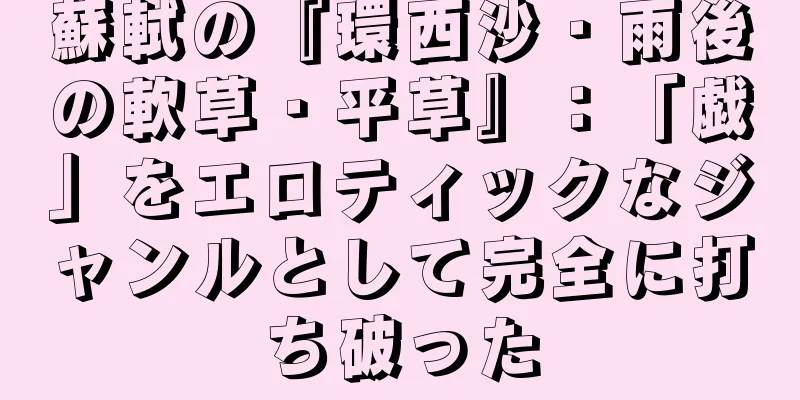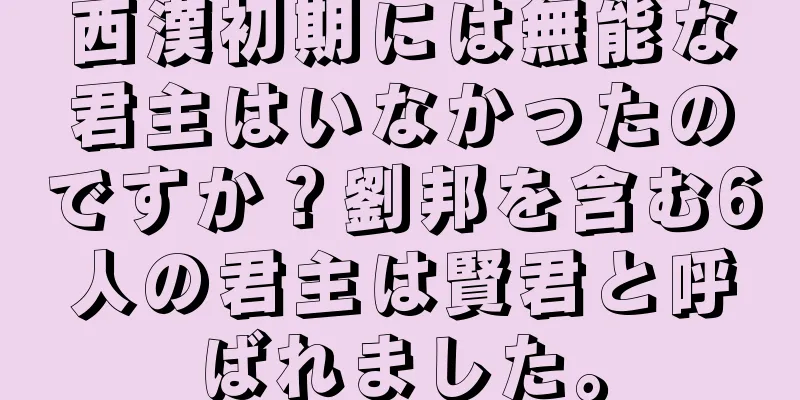中国ではお茶の歴史が非常に長いですが、功夫茶はいつ始まったのでしょうか?
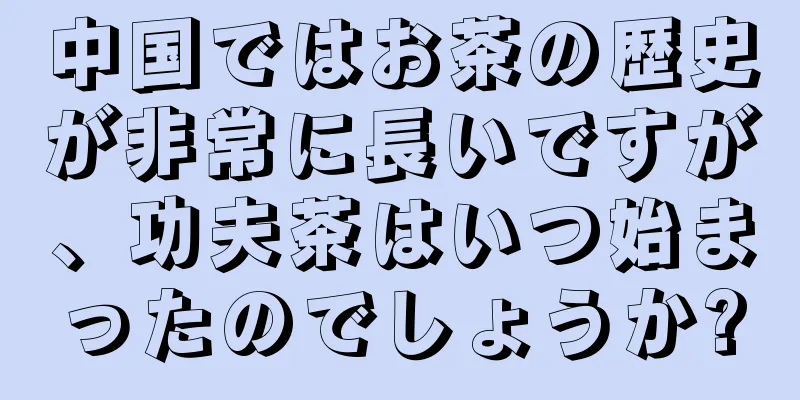
|
潮州功夫茶は明代に始まり、清代に盛んになり、潮汕地域の喫茶習慣の文化的現象となり、潮州の食文化の重要な一部となっています。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 唐代、宋代の「茶葉」飲用法に基づいて開発されたもので、茶葉の抽出法の範疇に属し、究極の抽出法です。 唐代に韓愈が潮州に左遷されてから鄒魯のスタイルが始まりました。お茶を飲むことについての最も古い文献は、北宋時代の蘇軾が書いた「子業宛」である。そこには「あなたの名を冠した数種類のお茶をお送りします。どれも素晴らしいものです。あなたの国ではなかなか手に入らないものです。あなたのご厚意に深く感謝いたします。」とある。子業とは、潮州の八賢の一人である呉富姑(呉元有)であり、蘇軾の親友である。作家の蘇軾は茶の研究において深い業績を持ち、茶芸にも精通していた。 呉福固が送った福建茶の数種類は、蘇軾に「どれも素晴らしい」「あの地ではめったに手に入らない」と賞賛された。これは、呉福固が非常に高いレベルの茶の味見の技術を持っていたことを示し、宋代の潮汕地域では、少なくとも上流階級の間では、お茶を飲む習慣があったことを示している。その後、この地域は戦争や混乱、特に宋代末期の朝廷の南下によって人口移動を経験しました。文天祥は潮州で敗れ、朝陽笛音楽など多くの中原文化が潮州にもたらされました。潮汕地域の多くの氏族や姓の起源を遡ってみると、その祖先はすべて朝廷の南方への移住から始まったことがわかります。相次ぐ人口移動により、中原の喫茶習慣が潮州にもたらされ、それが地元の習慣と融合して「潮州式喫茶習慣」を形成し、次第に後の「功夫」喫茶習慣へと形を変えていきました。 昔、潮州功夫茶は半発酵烏龍茶を主に使用していたため、功夫茶の形成時期は半発酵茶の製法が確立された後であるべきである。荘仁は論文「烏龍茶の発展史と飲用術」の中で、清代康熙56年(1717年)の王草堂の『茶論』、石超全の『武夷茶歌』、阮燕の『安渓茶歌』などに基づいて、烏龍茶は17世紀中期から後期、つまり明代中期から後期に生まれたと推論した。烏龍茶に適した功夫茶の飲用法も、まず武夷で生まれ、その後福建南部と潮州で生まれた。 功夫茶芸が潮州に伝わった後、地元の洗練された習慣と結びつき、元々の大きな茶碗は小さな茶碗に変更され、商売を尊重する習慣と結びついて、商売プロセスの重要な部分とリンクとなり、潮州における功夫茶芸の中心と手順が定着しました。 功夫茶の茶器から判断すると、昔の潮州の人々は皆、江蘇省宜興で生産された紫色の粘土の急須である蘇壺を好んでいたようです。古い世代の茶愛好家たちは、今でも「孟辰壺」(江蘇省宜興市出身の有名な急須職人、徽孟辰は天啓・崇禎年間に生きたという説もあれば、清朝の康熙・雍正年間に生きたという説もある)や「若塵杯」(若塵は江西省景徳鎮の有名な杯職人)についての口承伝承を持っている。研究によると、宜興紫土急須の生産は明代に始まり、明代中期から後期にかけて比較的完成された工芸体系が形成されました。紫土急須の発展のピークは明代の万暦年間から明代末期までで、基本的には潮州功夫茶の形成期と一致しています。 潮州功夫茶は、通常、小サイズの急須(容量約120cc)で淹れますが、他の地域で使用されている急須はすべて中サイズ(容量200cc以上)以上です。そのため、潮州は宜興小サイズ急須の主な販売地であり、現在もそれは変わりません。潮州功夫茶を使った急須の作り方も、宜興の紫土職人の製作技術に影響を与えています。一部の急須職人は潮汕地区に赴いて功夫茶の淹れ方を学び、そこで学んだ急須の重心、容量、形状、湯の通し具合、土への適応性、蓋の密閉度などのポイントを紫土急須の製作技術に応用しました。 中華民国時代には、潮州功夫茶が潮汕地域で広く消費されるようになりました。当時、潮汕地区では功夫茶を飲むことが社会的な流行となっていたが、当時の一般家庭にはきちんとした茶器が揃っていなかった。解放が始まるまで、潮汕地区の村々で茶を点てる蘇壷を持っている家庭はほんの一握りしかなく、家に客が来たときは、近所の人からきちんとした茶器を借りてもてなすのが一般的だった。解放後、潮汕では庶民が功夫茶を飲む習慣が広まりました。しかし、功夫茶が最も急速に普及したのは改革開放後の過去30年間で、現在ではほぼすべての家庭で毎日功夫茶が飲まれています。 1980年代以前は、潮汕地区はウーロン茶の主な販売地域と輸出港であり、現在でも国内で一人当たりの茶の消費量が最も多い地域です。 |
<<: 中国ではお茶の歴史が長いですが、功夫茶専用の道具は何でしょうか?
>>: 中国ではお茶の歴史がとても長いです。功夫茶の「功夫」という言葉はどこから来たのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』の薛おばさんはどんな人ですか?あなたは息子のXue Panをどれくらい好きですか?
薛叔母さんは優しさと礼儀正しさ、言葉遣いの良さで知られ、子供たちを溺愛していました。彼女は貴族の出身...
「李少福を送る客間に書いたもの」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
李少福を見送る際にゲストハウスで書いたもの高史(唐代)私たちは残念な気持ちでホテルに集まり、夕方に雪...
ファンタジードラマに出てくる舒山とは一体何なのでしょうか?
最近『花の旅路』がヒットし、蜀山の話題が再び熱くなっている。日本のドラマには走るシーンが一切なく、童...
「道士梅の部屋での清明節の宴会」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
清明節宴会メイ道教室孟浩然(唐代)森の中に横たわりながら、春の終わりを憂い、カーテンを開けると、自然...
明朝末期に明朝の軍隊が度々敗北したのはなぜでしょうか?根本的な原因は何ですか?
今日、Interesting History の編集者が皆さんのために準備しました: 明朝後期に明朝...
玄昭帝の苻堅の物語 苻堅に関する逸話や物語は何ですか?
前秦の玄昭帝、苻堅(338年 - 385年10月16日)は、雅号を雍固、また文有といい、劍頭とも呼ば...
太平広記・第85巻・奇人・交方音楽家の原作の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
曹魏、蜀漢、東呉について言えば、彼らの統治者はどのようにして皇帝になったのでしょうか?
東漢末期、大小数十人の君主が互いに争い、ついに天下は三つに分かれました。三つの勢力が相次いで皇帝を名...
黄風怪物はどれくらい強いですか?彼の力はどうですか?
周知のとおり、西方への旅において、唐の僧侶とその弟子たちにとって最大の障害となったのは、道中に存在す...
古典文学の傑作『論衡』:巻13:効能篇全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
本草綱目第8巻「カラーリリー」の本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
鄭謝の「竹と石」:竹の粘り強さと持続性を示す
鄭板橋(1693-1766)は、本名を鄭謝、別名を科柔、連安、板橋といい、板橋氏とも呼ばれた。江蘇省...
水滸伝で趙蓋を射殺した人物は誰ですか?宋江か華容か?
趙蓋の死が宋江と関係があるかどうかは、『水滸伝』を読むときに常に大きな疑問となっていた。今日は、In...
『紅楼夢』で青文が追い払われ、最終的に病気で亡くなるという深い意味は何ですか?リン・ダイユに関連する
以下は『興味深い歴史』編集者による短い紹介です。『紅楼夢』で青文が追い払われ、最後には病死したことの...
武侯祠に選ばれるための条件は何ですか?功臣である法正はなぜ入ることができなかったのか?
三国志の最高顧問の一人である法正は、『三国志』の著者である陳寿によって、曹操の時代の程毓や郭嘉に匹敵...