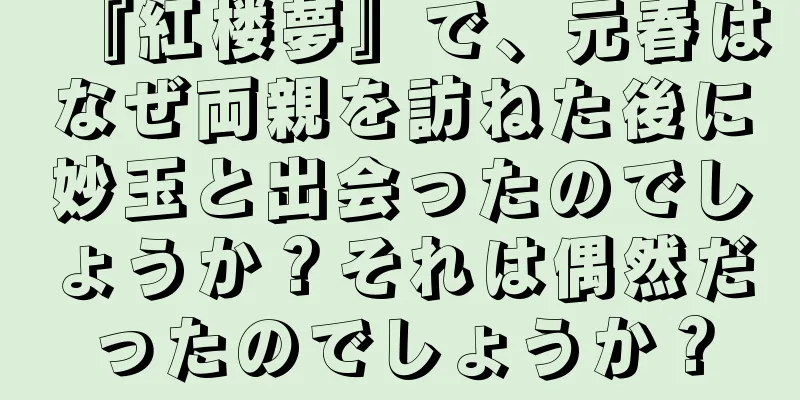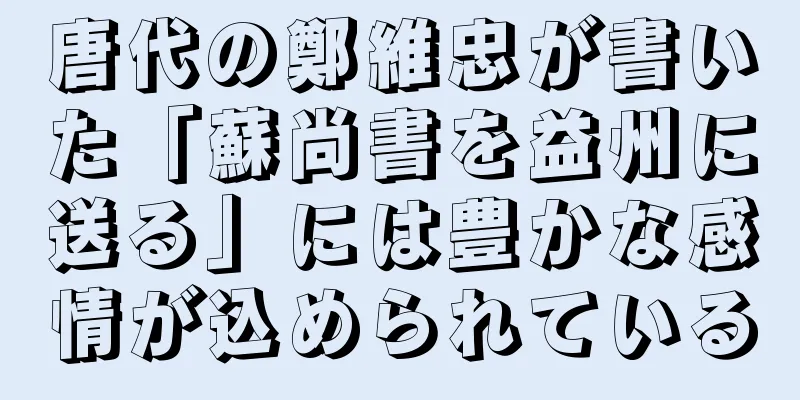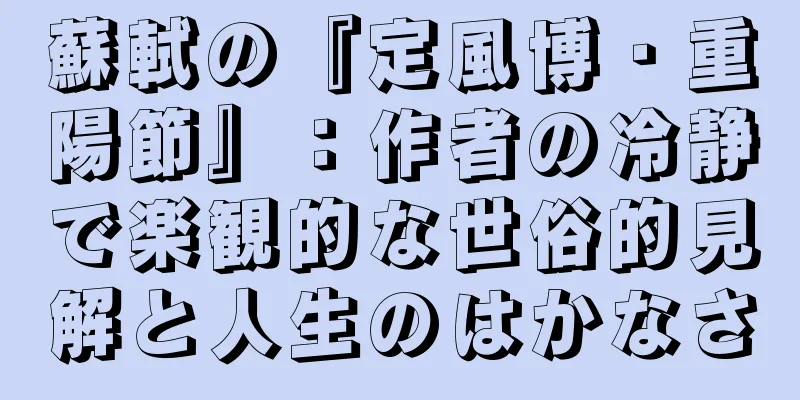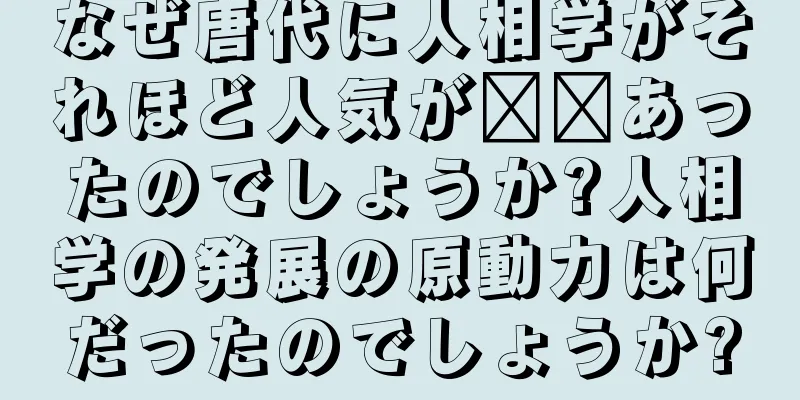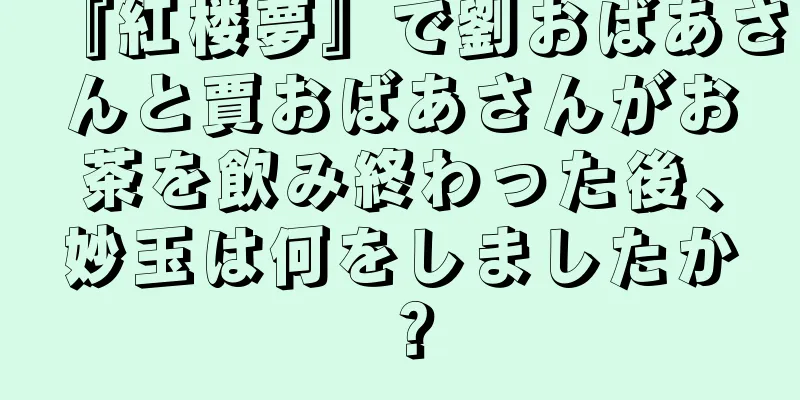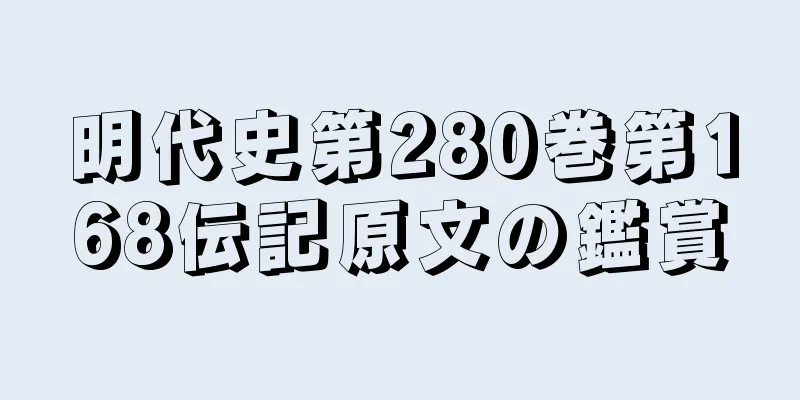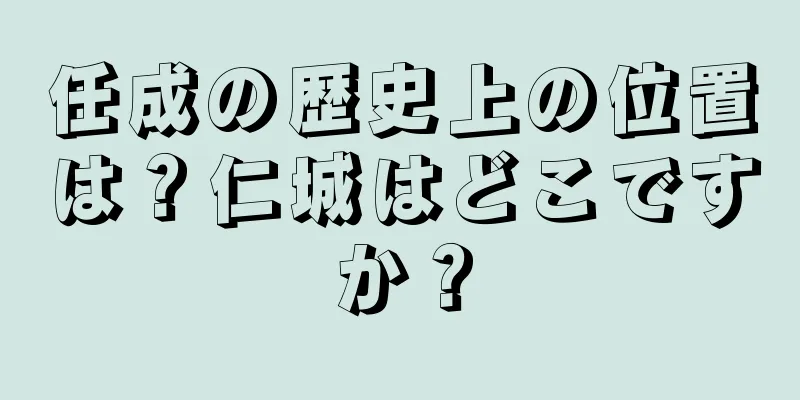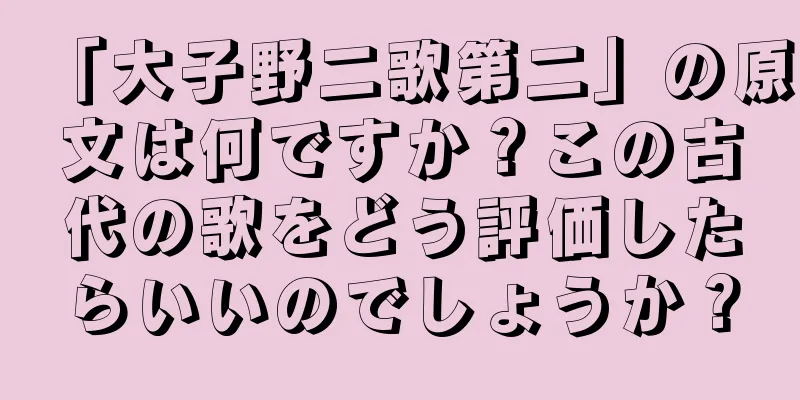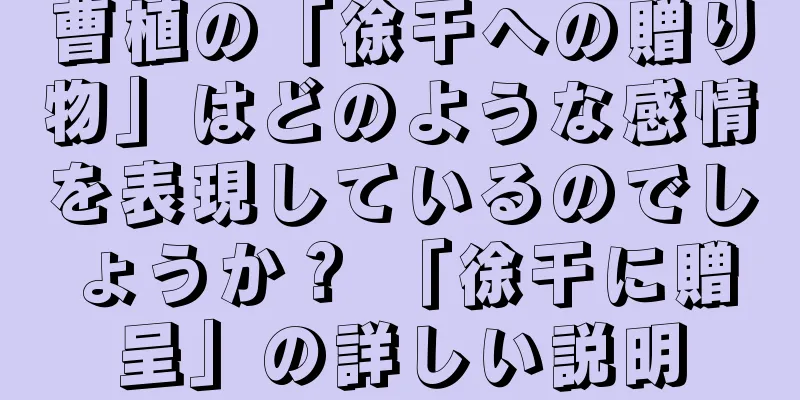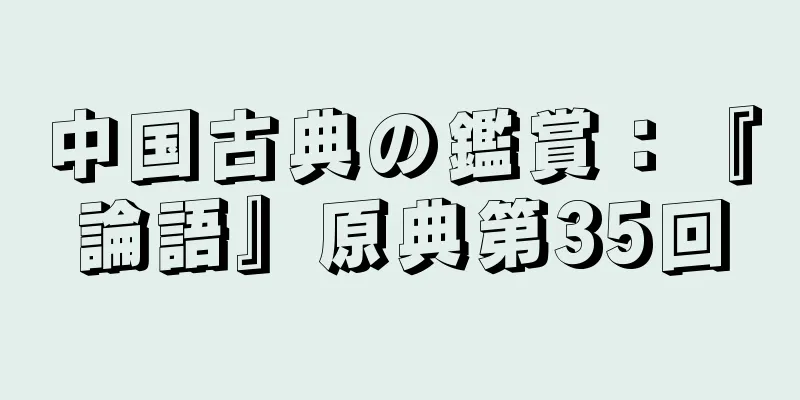曹叡は後継者のために権力体制を再建するために、自分の人生の残り時間をどのように活用したのでしょうか?
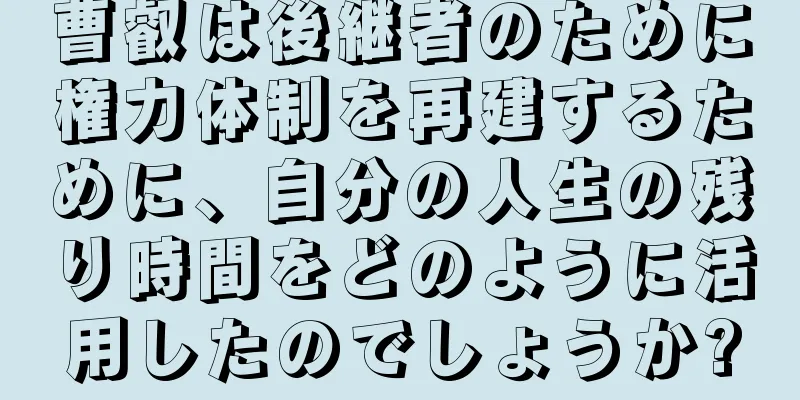
|
曹叡と司馬懿の関係は常に微妙なものでした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! これは「鷲の目と狼の背中」のような冗談によるものではなく、すべての君主は摂政と自然な対立を抱えているのです。 曹叡が即位すると、曹丕は司馬懿、曹真、曹休、陳群を摂政として任命した。 曹叡が自ら権力を掌握したいのであれば、当然、強力な摂政と競争しなければならなかっただろう。 曹叡は牽制と均衡の技術を使って摂政大臣たちを抑圧した。 曹真、曹休、司馬懿は一年中朝外で軍を率いており、政府に対する影響力は限られていました。洛陽に留まった陳群には軍事力はありませんでした。曹叡は状況をチェックし、バランスを取り、全体の安定を保つことができました。 司馬懿は曹叡の治世中は行儀よく振る舞っていたが、曹叡とその大臣の何人かは依然として司馬懿を警戒していた。 司馬懿はかつて陳嬌に尋ねた。「司馬懿は忠義に厚いが、大臣になれるのか?」 陳嬌はこう答えた。「司馬懿は朝廷が期待する人物だが、彼が国の大臣であるかどうかは『不明』だ」 (三国志:陳嬌伝、史蹟より引用) もちろん、曹叡の司馬懿に対する警戒は、基本的には君主と摂政の間の通常の警戒であり、特に特別なことではありませんでした。彼が意図的に司馬懿を抑圧した程度は、曹真と曹休を抑圧した程度と基本的に同じであった。 曹魏の皇帝にとって、王族であろうと貴族の家系であろうと、彼らは皆警戒すべき対象だった。 曹叡の治世中、曹真や曹休などの王族や、司馬懿や陳群などの重要官僚を容易に統制することができ、政権は皇帝自身の手中にしっかりと握られていました。 曹昭、夏侯献、秦朗などの一族、蔣記、高唐龍などの外国の役人たちは、皇帝の秘密を預かる孫子と劉芳の権力が強すぎると不満を漏らしていた。これは曹叡によって一族と外国の役人の権力が厳しく制限されていたことを示している。 曹叡の支配下で、司馬懿は皇帝の権力を脅かすことなく、その才能を十分に発揮することができ、二人は互いに補い合っていました。 例えば、諸葛亮が第五次北伐を開始したとき、配下の将軍たちは皆戦闘を要請しましたが、司馬懿は彼らを止めることができず、曹叡に許可を求めました。曹叡は彼の意図を理解し、将軍たちに戦闘しないように命じました。 この一節は、賢明な君主と忠実な大臣たちとの協力のモデルとして考えることができます。 曹叡は司馬懿より25歳年下だったので、通常であれば、この賢明な君主と徳の高い臣下の物語は続いていたかもしれない。 ところが、若き曹叡は突然病気にかかってしまいました。 曹叡は当然ながら王族や貴族をしっかりと抑え込むことができたが、帝位を継承した若い皇帝がすぐにそれを行うことは不可能だった。 古い権力体制は不均衡になっており、曹叡は後継者のために権力体制を再建するために最後の命を賭けなければならない! 曹叡の第一選択は王族だった。 彼が最初に編成した摂政チームは、曹操の息子である曹禹、曹操の養子である秦朗、曹休の息子である曹昭、曹真の息子である曹爽、そして夏侯家の夏侯仙といった王族のグループでした。 同時に曹瑜は、遼東戦線から戻った司馬懿に洛陽に戻る必要はなく、直接関中に赴いて軍を指揮してもよいと提案した。 (中央電力システムの圧迫を継続) 曹叡は父曹丕のように貴族と王族が共助して政治を行うという形式をとらず、王族と皇帝の権力の結合によって貴族を抑圧しようとした。 曹叡は貴族階級の危険性に気付いたようだ。 漢王朝末期以降、貴族階級は大量の経済的、政治的資源を掌握し、時事問題に影響を及ぼす重要な勢力となった。 曹操が天下を争っていたとき、袁紹と袁術を排除し、楊彪を弱体化させ、東漢の政治生態における最高貴族を皆打ち負かした。曹丕は司馬懿や陳群などの二級貴族を獲得することで漢王朝に取って代わることができた。 曹操と曹丕の時代、曹一族には強力な君主と、権力を牽制し均衡を保つ有能な下層民がいたため、貴族階級は依然として権力を抑えることができました。 しかし、数十年にわたる発展、特に「九階制」の継続的な実施を経て、貴族階級は再び経済的および政治的資源を掌握し、当時の二級貴族であった司馬懿、陳群、王玲は、現在では最上級貴族に成長しました。 王室も危険ではありますが、権力のある大臣達に比べれば、結局は私達の家族です。 曹叡が尊敬していた大臣の高唐龍はかつてこう言った。「我々は『タカ派の大臣』に警戒し、王族が軍隊を率いて状況を制御できるようにしなければならない!」 曹叡が最初に行った取り決めは、基本的に高唐龍の意見を採用したものでした。 しかし、すべての貴族階級を最高権力システムから排除し、それらを抑圧するために王室に全面的に頼ることはうまくいくでしょうか? 当時、高唐龍が王族を率いて軍を率いて「鷲」の大臣たちを鎮圧しようと提案したとき、曹叡はまだ非常に健康で、それは雨の日のための計画でした。 さて、そんな急いでいる時に、王室が貴族家を直接鎮圧できるのでしょうか? 曹允は地位は高かったが実権を持たなかった。曹昭と曹爽は父の影響力を持っていたものの、名声と実権は父ほど大きくなかった。 力が足りない、能力が足りない! 曹昭と夏侯献が行政の補佐に任命された後、彼らは木の上の鳥を指差して言った。「木の上に長く留まりすぎている。そろそろ降りる時だ!」(孫子と劉芳を指して) 孫子と劉芳が味方につくべき人物かどうかは議論しないでおこう。たとえ彼らを倒したいと思っても、そんなに焦っていたらどんな偉業を成し遂げられるというのか? 孫子と劉芳はすぐに曹叡を説得し始めた。 『韓進春秋』の記録によると、孫と劉の説得の要点は2つある。 (1)王室は必ずしも信頼できるわけではない! 王室は皇帝の権力をも危険にさらすでしょう! 曹丕はかつて、王が行政に協力することを許可しないという勅令を出しました! さらに、曹允、曹昭、夏侯献、秦朗はいずれも信頼できない人物だ! あなたはまだ病気なのに、曹昭と夏侯嬪はすでにあなたをからかっています!燕王(曹禹)はすでに軍隊を南に導き、宮殿に入るのを禁止しています! (2)王族たちは状況をコントロールできない! 「外部の分裂により、国は危険にさらされている。」この凡庸な男たちが、他所の強大な司馬懿と王陵を抑えられるのか? そこで孫子と劉芳は曹爽と司馬懿が協力して政務を補佐することを提案した! 曹丕原作の「王族+貴族幹部」を引き続き補佐官チームとして参戦! 曹叡はそれを採用した。 しかし、曹叡もまだ不安定だと感じていました! 曹叡は最初、劉芳と孫子の提案に同意したが、その後考えを変え、さらに考えを変えて優柔不断になった。 彼は曹爽に尋ねた。「あなたはその任務を遂行できますか?」 曹爽は恐怖に震えていたが、孫子は彼に代わってこう答えた。「私は国のために死ぬ覚悟があります。」 同時に、曹叡は最後の活躍で司馬懿を味方につけた。 曹叡は司馬懿の手を握りました。「あなたに会うために死に耐えました。あなたに会えば、もう憎しみは消えます!」 しかし、曹叡は依然として司馬懿に対する支配を放棄しなかった。 曹一族は中央軍をしっかりと掌握し、曹爽の政府内での影響力を強化するために、国書記の孫礼が曹爽の首席秘書に任命された。 こうして曹叡の最終的な考えは基本的に形成された。 1. 貴族階級のリーダーとしての司馬懿の地位を利用して、貴族集団を統治する。 陳群の死後、司馬懿は貴族の絶対的な指導者となった。 2. 洛陽の曹爽と孫礼の力を利用して司馬懿を鎮圧する。 司馬懿は非常に強力であったが、洛陽では弱かった。 事実が証明しているように、司馬懿の一族は洛陽に入った後、長い間抑圧された立場にあった。これは、目立たないようにするという司馬懿の戦略だけでなく、中央軍が曹氏の手中にあったためでもあった。 もし曹爽が自殺していなかったら、これは信頼できるバランスシステムだったと言えるでしょう。 しかし、曹爽は想像していた以上に頼りない人物だった…… 曹叡は孫礼を足手まといとみなし、追放した。 曹爽を補佐するよう周到に手配されていた孫礼は、後に曹爽のやりたいことを何でもやらせた司馬懿を責めた。 いつの時代でも、若い君主を支えるチームを編成し、円滑な権力移譲を実現するのは極めて困難である。 魏、晋、南北朝の時代になると、状況はさらに困難になりました。 漢王朝の終焉以来、貴族階級の権力は拡大し、国の主要な経済資源と人口資源を支配してきました。 これらの貴族を統制できるかどうかが、帝国の権力安定の鍵となる。 強い君主であれば状況をコントロールすることはできたが、若い君主を支えるチームを編成することは当時は解決不可能な問題だった。 劉備は諸葛亮に賭けたので幸運であり、基本的に何も問題は起きなかった。 孫権は「有力な大臣+王族」の組み合わせを採用し、諸葛恪と孫峻が共同で政権を補佐した。このとき王族が勝利し、諸葛恪は殺害された。しかし、東呉は長年にわたり内紛に苦しみ、国力は大きく損なわれた。 司馬炎が王族に軍を統率させるという決断は、基本的に高唐龍が曹叡に提案したのと似ていた。その結果、王族は「鷲のような」大臣となり、八王子の乱は... それ以来、南北朝時代に至るまで、若く愚かな君主が権力を握るたびに、流血事件や王朝交代が必ず起こった。 |
<<: 三国時代の有名な将軍、張飛が夜中に部下によって殺されたのはなぜですか?
>>: 三国時代には多くの軍師がいましたが、なぜ夏侯は武将の中で最高だったのでしょうか?
推薦する
古代コインの収集について知らない詳細がコレクションの価値を決定します
コインコレクション市場がますます人気になるにつれて、多くの人がコインコレクションをコレクションの主要...
『後漢書』巻79にある『儒学者伝』の原文は何ですか?
『旧史』によれば、魯の沈公は伏丘伯から『詩書』を授かり、伏丘伯はこれに注釈を加えて『魯書』とした。斉...
「西村」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
西村陸游(宋代)混沌とした山奥に小さな楽園があります。去年、水をもらうためにそこのドアをノックしたの...
『紅楼夢』では、夏金貴は薛の家でどれほど傲慢だったのか、そして薛覇はなぜ気にしなかったのか?
夏金貴は夏家の一人娘であり、母方の家族における地位は薛家における地位と同じです。これについて言えば、...
Nezha はどれくらい強いですか?彼は孫悟空に勝てないというのは本当ですか?
仏教の経典における「哪吒」は、サンスクリット語の「ナラクヴァラ」の音訳の略語です。 『西遊記』では、...
李和の詩が色彩豊かで素晴らしいと言われるのはなぜでしょうか?彼は色彩を使って芸術的な概念を創り出す
李和は、字を昌吉といい、中唐時代の浪漫詩人である。李白、李商隠とともに「唐の三里」の一人とされ、後世...
『紅楼夢』では「季」と「気」が共存しています。「季」とは何のことですか?
「紅楼夢」は何度も登場し、「側室」が共存しています。側室はわかりやすいですが、「妾」とはどういう意味...
林黛玉はなぜ『紅楼夢』で劉おばあさんを描写するのに雌のイナゴを使ったのでしょうか?
『紅楼夢』を読んだことがない人もいるが、劉おばあちゃんは誰でも知っている。次回はInterestin...
なぜ王陽明は嘉靖に評価されなかったのでしょうか?この結果の理由は何ですか?
王陽明は同世代の聖人として、基本的に「功を立て、徳を立て、言葉を発する」という三仙境を修めたが、なぜ...
『紅楼夢』では、甄一家が北京へ皇太后を訪ねた直後に略奪に遭いました。何か関係があるのでしょうか?
『紅楼夢』では江南に甄家、都に賈家が登場します。多くの人が理解していないので、Interesting...
「目覚めの結婚物語」第49章:若い学者の結婚は終わり、老婦人は母親を愛し、孫たちと遊んだ
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
宋代の詩「曼亭坊茶」を鑑賞します。この詩はどのような場面を描いているのでしょうか?
曼亭坊茶[宋代] 黄庭堅、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう!...
王爽は諸葛亮の北伐と戦った曹魏の有力な将軍です。魏延は彼を倒すことができたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
劉克荘の月に関する詩『薄雲掃き跡』には月に関する言葉は一つも含まれていない。
以下、Interesting Historyの編集者が劉克荘の『清平越仙雲索記』の原文と評価をお届け...
劉勇の『海潮を観る 東南の美しい風景』は杭州の繁栄と美しさを描写している。
劉勇は、本名を三扁、後に劉勇と改名し、字は啓青。七番目の子であったため、劉啓とも呼ばれた。北宋時代の...