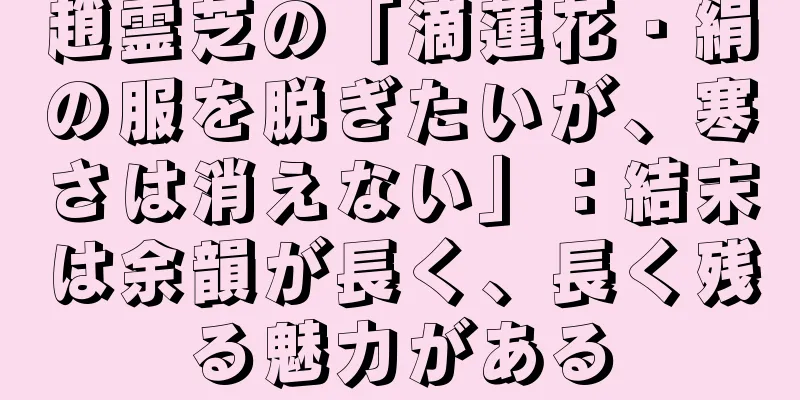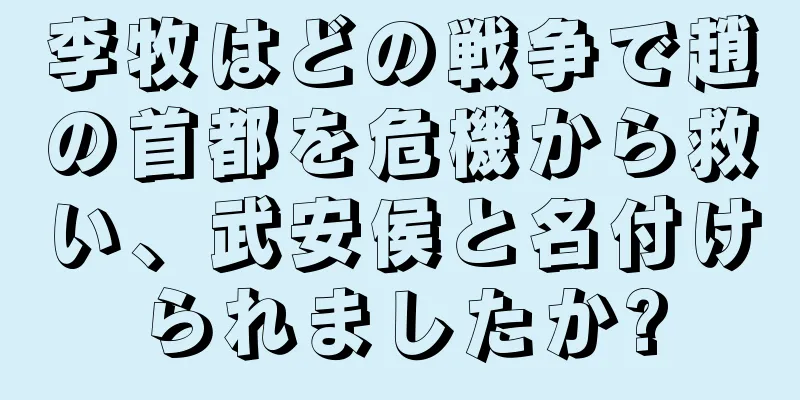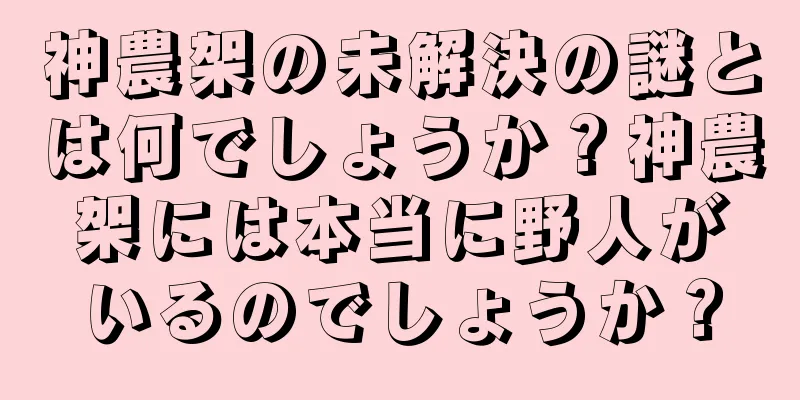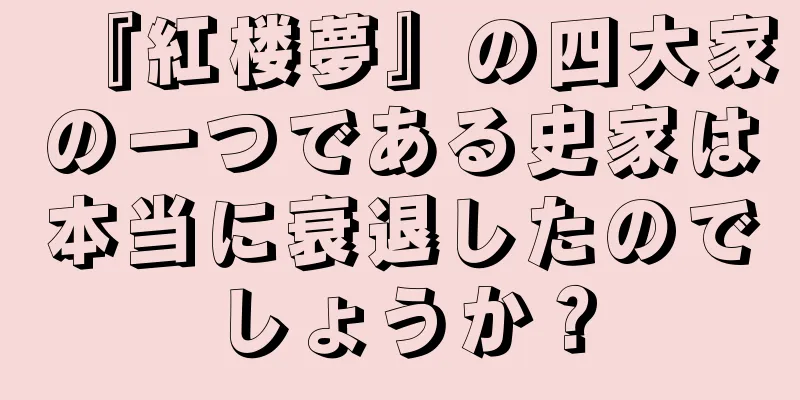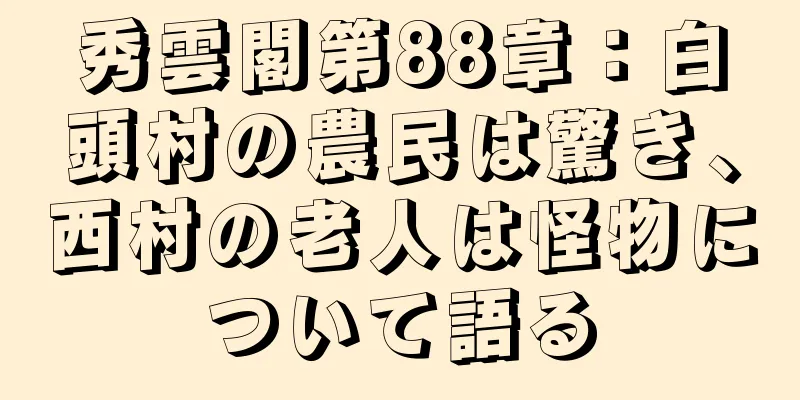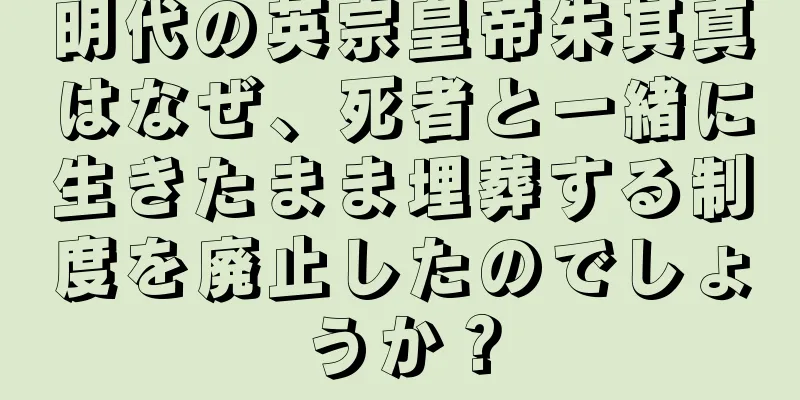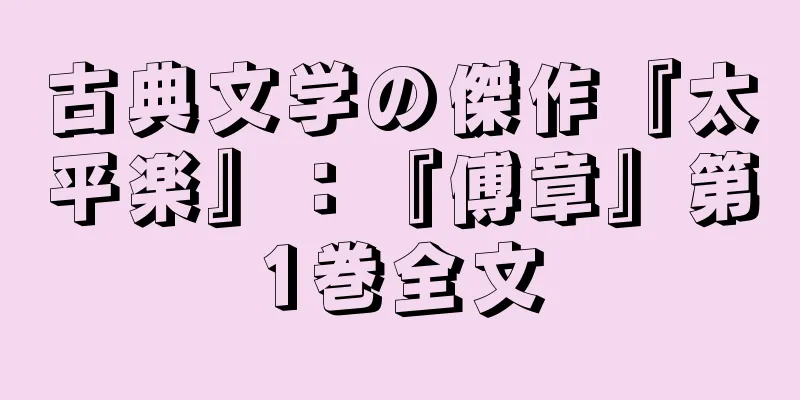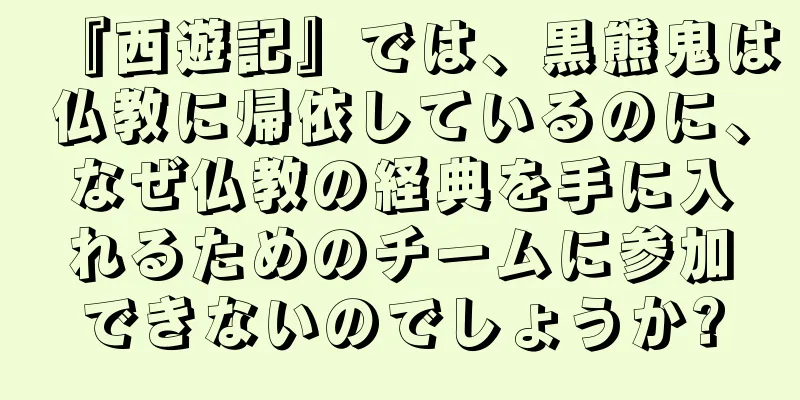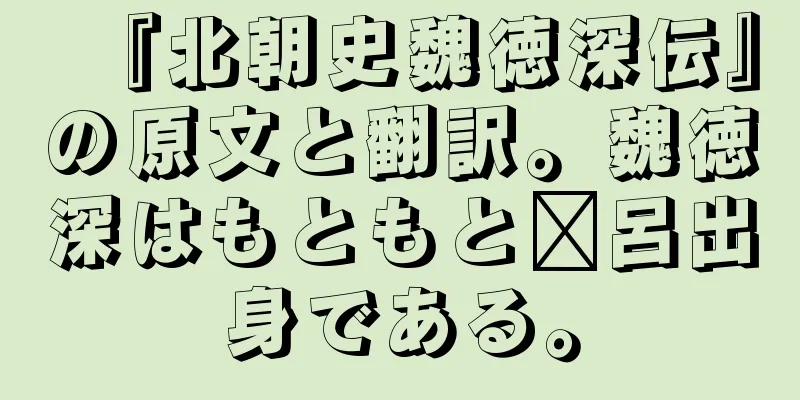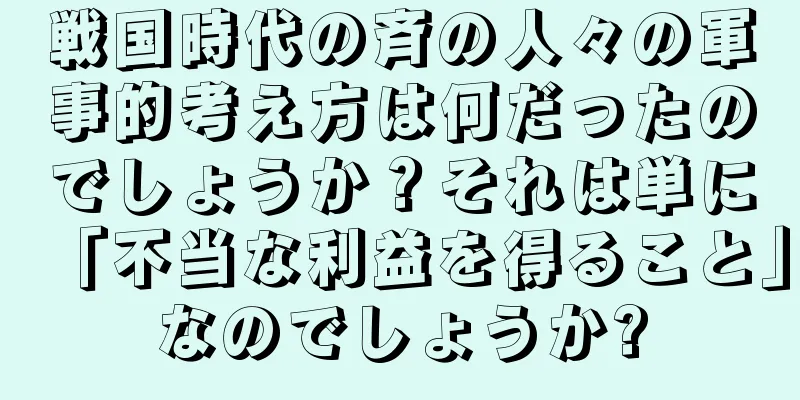湿式冶金はどこで始まったのでしょうか?銅胆汁法とは何ですか?
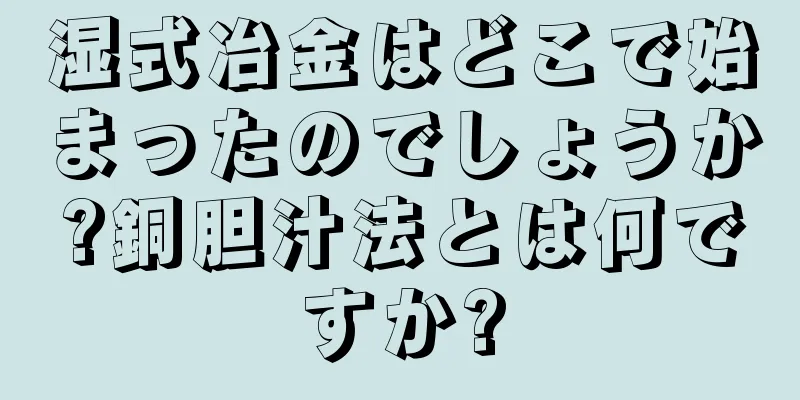
|
湿式冶金はどこから始まったのでしょうか?銅胆汁法とは何でしょうか?実は、この技術は我が国で初めて登場し、世界の冶金史上重要な位置を占めています。次の興味深い歴史の編集者が、関連する内容を詳しく紹介します。 沈括の『孟溪壁譚』によると、忻州前山県に苦い泉(硫酸銅溶液)があり、川に流れ込んでいた。湧き水をすくって沸騰させると硫酸銅ができます。硫酸銅を沸騰させると銅ができます。硫酸銅を沸騰させた鉄鍋も、時間が経つと銅に変わります。 沈括によるこの記録は、化学置換反応を利用して金属を精錬する湿式銅製錬法について言及しています。 中国では、漢代にはすでにミョウバン水と鉄の化学反応が認識されていた。淮南王劉安が著した『淮南万備書』には、「白藍は鉄を得ると銅に変わる」という記録がある。 1957年にヤン・ユーは「宋代における胆銅の生産」と題する論文を執筆し、宋代における胆銅の生産と起源について論じた。同氏は次のように指摘した。「鉄を銅に変える胆石、あるいは胆明礬の金属置換現象は、秦漢の時代から知られていた。」 「胆汁水による『銅浸法』の発明は、少なくとも唐代末期から五代初期には始まっていたはずだ。五代初期、玄元書の『宝論』(注:玄元書のほか、『宝論』の著者は『宋史』巻205の「文芸」にも記載されている:「清夏子の『宝論』は一冊の本。この本は現存しない。また、『集書』には唐代の僧侶僧昭の『宝論』も収録されているが、内容が異なる本である。)では、「苦胆水」に浸した銅を「鉄銅」と呼び、当時流行していた十種類の銅の一つに挙げている。」 顔宇が引用した『宝論』という本はもうこの世に存在しません。そこにある十種類の銅についての記録は、李時珍の『本草綱目』第8巻の「赤銅」の項に保存されています。 実際、北宋初期まで、胆汁が鉄を銅に浸出させる現象についての知識は、ごく少数の人々に限られており、ごく限られた範囲の民衆による私的生産を通じてのみ実践することができました。残された歴史記録から判断すると、こうした実践活動は主に忻州前山県から始まったものと思われます。 池、饒、江の各県の銅銭監督官は貨幣鋳造用の銅材料が不足していたため、三部の要請により、朝廷は銭恂と江南東路運輸長官を派遣して銅の供給問題を解決する実験を行ったが(『巻120』景有4年9月15日)、この実験の結果については明確な記録がない。 さらに、宋哲宗元有年間の沈括の著した『孟熙秘譚』には、「忻州前山県に苦い泉があり、川に流れ込んでいる。その水をすくって煮ると胆石になる。胆石を煮ると銅になる。鉄鍋で胆石を長時間煮ると銅になる。水が銅になることもあり、物事の変化は予測できない」(巻第25「雑記2」)と記されている。 この文献記録が沈括の個人的な調査記録であるかどうかについては、郭正益が論文「水法による銅製錬に関する史料の起源を辿る」の中で研究を行っている。それは沈括が自分の目で見たものではなく、中唐時代に書かれた『丹方経源』から記録された沈括の読書メモであると彼は信じた。 この記録は、中唐時代には、鉄が製造過程で明礬と接触すると銅に置き換わる可能性があると知られていたことを示していますが、沈括はこの文章を引用する際に新しい内容を加えていません。これは、宋哲宗の初年まで、政府がまだ明礬銅法の生産を推進しておらず、忻州では公然と明礬の生産のみが行われていたことを示しています。 しかし、張騫が率先して『銅浸要』を朝廷に献上したのは、宋の哲宗皇帝の紹勝5年(1098年)になってからであった。北宋政府の強力な推進により、胆嚢法による銅の生産は急速に促進された。 |
<<: 私の国の古代の人々はどうやって時間を計算したのでしょうか?
>>: 歴史上、間質蓄積の技術はいつ発明されたのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』では、秦克清は宝玉を自分の寝室で寝かせました。彼女がそうした目的は何だったのでしょうか?
秦克清は仙女の国、仙境の浄土からやって来て、仙女の景環であり、太虚の幻想世界の主人です。 Inter...
なぜアオハン・モンゴル人は清朝と54回も結婚したのでしょうか?アオハン・モンゴルと清朝との関係は何ですか?
なぜアオハンモンゴル人は清朝と54回も結婚したのでしょうか? この点がよく分からない読者は、Inte...
「清渓」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
清渓王維(唐代)黄花江に入ると、私はいつも緑の流れに沿って進みます。山を何千回も曲がりながら辿ってい...
「李家が天下を制する」という予言が出たとき、なぜ隋の煬帝は李淵を疑わなかったのか?
隋王朝(581年 - 618年)は、中国史上、南北朝の継承と唐王朝の先駆けとなった統一王朝で、37年...
「蘭」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
蘭方慧(元代)雪が解けると、深い森からは不思議な香りが漂い、枯れた松や枯れ木があちこちに散らばります...
Shangxieの原文は何ですか?詩「尚慧」をどう鑑賞するか?
尚羲[漢代] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきますので、見てみましょう...
戴樹倫の『大晦日に石頭駅に泊まる』:唐代の五字律詩の中でも常に名作とされている。
戴叔倫(732年頃 - 789年頃)は唐代の詩人で、字は有公(慈公ともいう)で、潤州金壇(現在の江蘇...
「野望」をどう評価するか?著者は誰ですか?
野心杜甫(唐代)西丘陵の白い雪の下には三つの都市が駐屯し、南浦の清流には数千里に渡る橋が架けられてい...
黎族の創世神話とは何ですか?情報源は何ですか
「ヘラクレス」の神話は黎族の間で広く伝承されている。神話によると、「空と地球は互いに非常に近かった。...
「緑水曲」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
盧水区李白(唐)秋の月が澄んだ水面に明るく輝き、南湖では白い睡蓮が摘まれます。蓮の花はまるで何かを語...
古典文学の傑作「劉公安」第56章:劉公安は一連の事件を慎重に検討する
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
カザフ人の起源と歴史的発展は何ですか?
外国人学者の多くは、「カザフ」という名前が初めて登場したのは 15 世紀初頭だと考えています。白いガ...
地壇公園の建物はなぜすべて四角いのですか?
天は丸く、地は四角いという「四角い」原理は、地への供儀に使われる方澤祭壇の形だけでなく、方澤祭壇を取...
「柳への頌歌」をどう鑑賞するか?創作の背景は何ですか?
柳への頌歌何志章(唐)翡翠は背の高い木に形作られ、何千もの緑のリボンが垂れ下がっています。誰がこの立...
『清代名人故事』第13巻原文の「学問と行状」の項には何が記されているか?
◎朱高安の学問と行い朱高安は幼い頃から勉強が好きで、全力を尽くす決意をしていました。一度、家庭教師が...