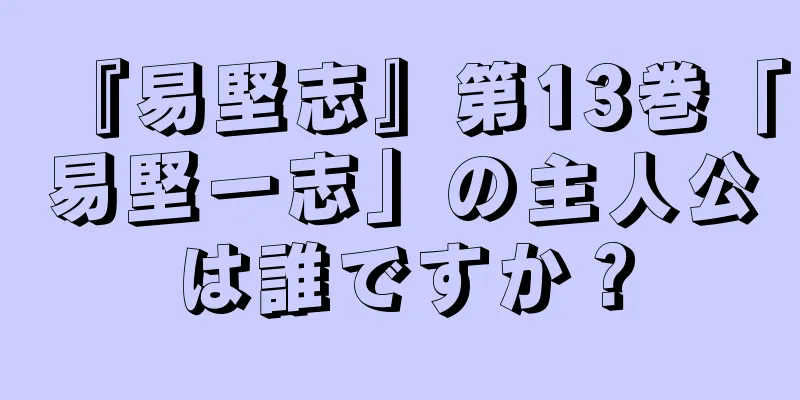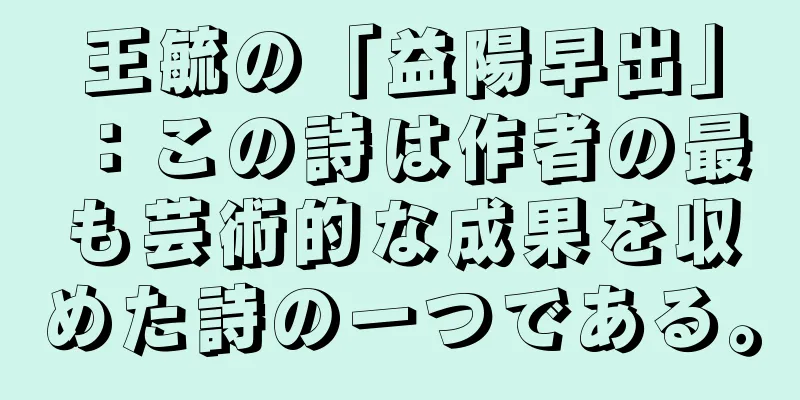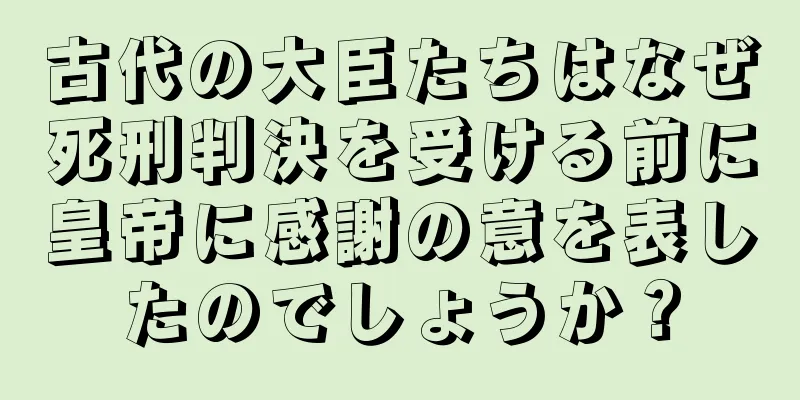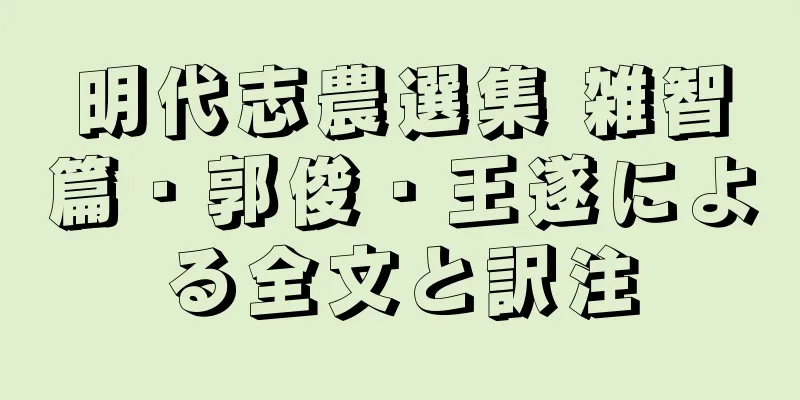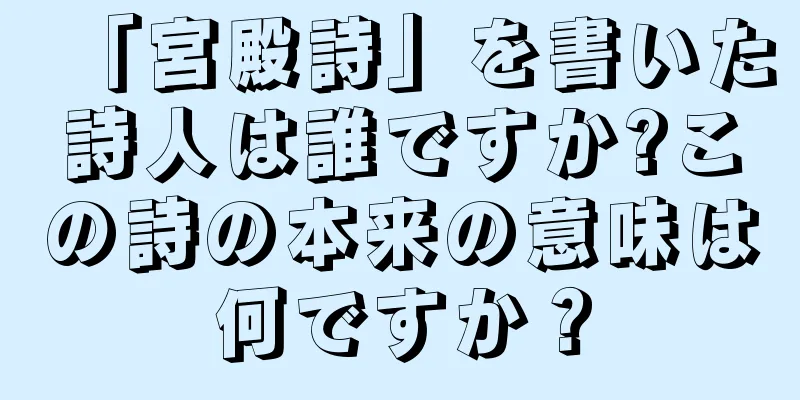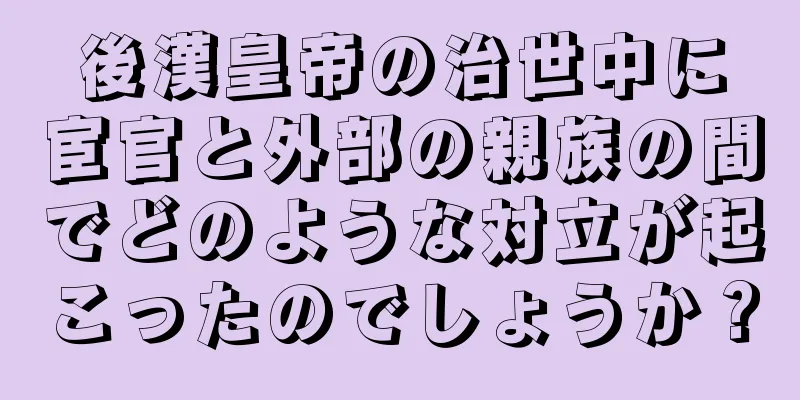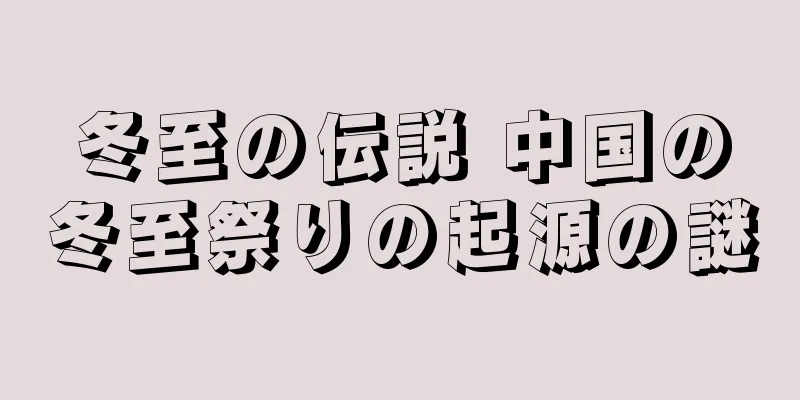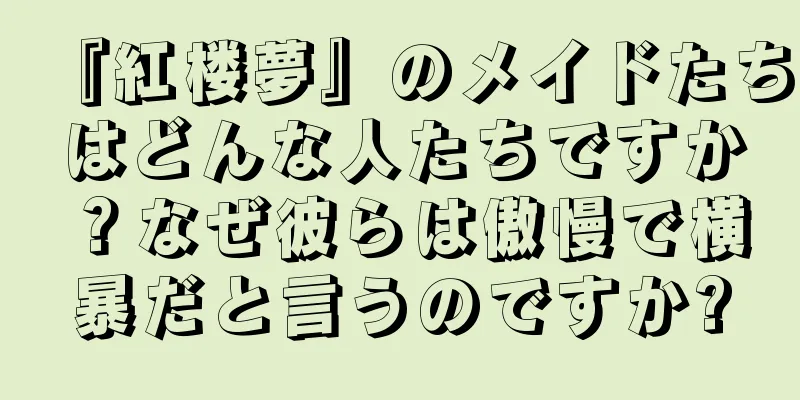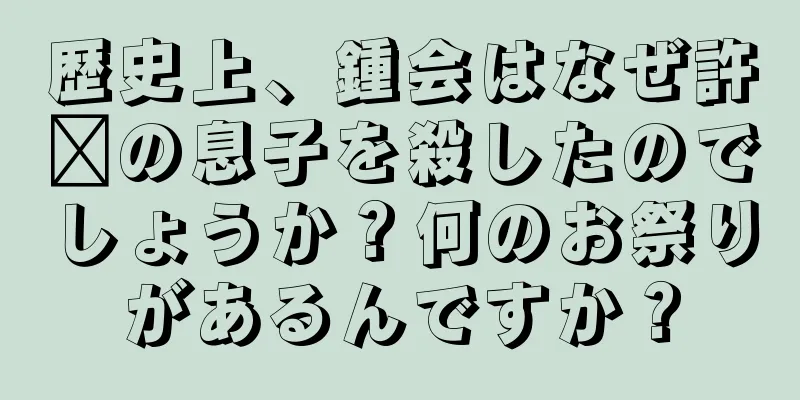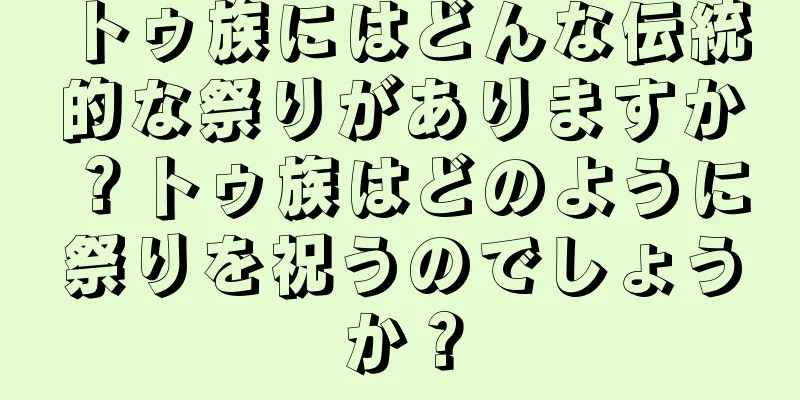戦国時代の斉の人々の軍事的考え方は何だったのでしょうか?それは単に「不当な利益を得ること」なのでしょうか?
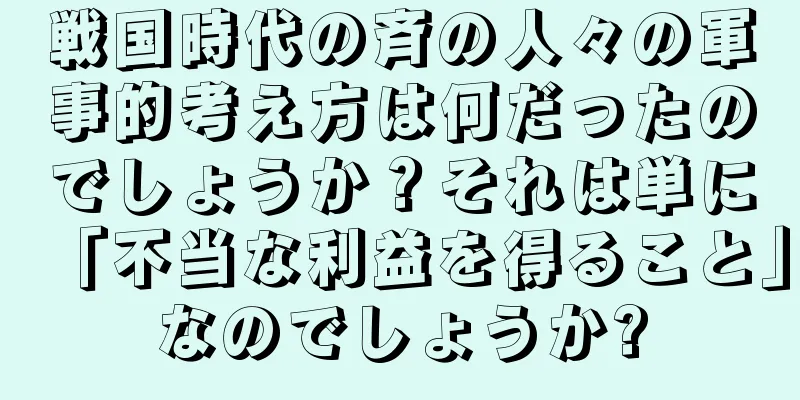
|
今日は、戦国時代の斉人の軍事思想について、おもしろ歴史編集長がお届けします。興味のある方は、編集長をフォローしてご覧ください。 戦国時代には七英雄がいたが、英雄は七人だけではなかった。 春秋戦国時代は、属国が多かったのが特徴でした。戦国時代初期には属国の数は激減しましたが、それでも数十の属国が存在していました。しかし、最も強大だったのは、韓、趙、魏、楚、燕、斉、秦の7つだけでした。 これら7つの属国は代表的なものであるため、その強さは決して誇張ではありません。韓、趙、魏は晋を分裂させて成立し、残りの4つはいずれも古い属国であり、特に楚、秦、斉はいずれも春秋時代を支配した大国でした。 斉の桓公小白は春秋五覇のリーダーでした。斉の強さは「貿易と産業が開かれ、魚と塩の恩恵があった」ことに由来し、建国初期には急速に東方の大国になりました。『史記 斉太公一族』には次のように記されています。太公が国に到着すると、政治を改善し、慣習に従い、儀式を簡素化しました...多くの人が斉にやって来て、斉は大国になりました。 孫 春秋戦国時代は、属国同士の覇権争いと併合が主なテーマとなり、大小さまざまな戦争が頻発しました。もちろん、それまでの陣形を整えてから攻撃する戦争と比べると、この時期の戦争はより「技術的」なものになっていきました。 斉国は古くから武術を奨励し、軍事の実践を総括することを重視していたため、独自の軍事理論体系が形成されました。その中で最も注目すべきは孫子の兵法であり、これは千年以上にわたって中国の戦争史に影響を与え、今日でも高く評価されています。 斉の豊かな軍事思想の影響を受けて、斉の人々は利益を上げることを目的として戦争をしました。斉の軍事思想の核心は利益であり、形成された具体的な戦術も「利益」を中心に展開されていたと言えます。 しかし、斉の人々は戦いにおいて利益を重視していたものの、道徳を捨てたり戦略を欠いたりはしませんでした。『兵法』に反映されている軍事思想を見てみましょう。そのためには、まず孫武の生涯から始めなければなりません。 孫武の生涯。 孫子の名前は呉で、斉の出身です。 ——『史記 孫子と呉起の伝記』 孫武は春秋時代後期の斉の人です。有名な軍師、政治家でした。彼は尊敬されて孫(武)子と呼ばれていました。もちろん、この「子」は現在の意味での「息子」を意味するのではなく、多くの意味を持っています。姓の後に付けると、百家思想の中の孔子、老子、墨子、韓非子などの教師や道徳的で知識のある人を表す尊敬語になります。 しかし、孫武は斉で目立った軍事的功績はなく、呉南部で名声を博した。斉で発展しなかったのは、紀元前532年(周の景王13年、斉の景公16年)、斉で「四姓の乱」が勃発したためである。この乱の原因は、「斉の慧洛と高は皆酒飲みで、恨みが多く、陳と鮑よりも強かったので、孫武は彼らを憎んだ(斉の景公10年、左伝より)」というものであった。 斉の景公の治世中、斉の貴族間の争いは最高潮に達し、田、鮑、阮、高の4つの大家の間で最も激しい戦いが繰り広げられました。この内紛は、田家が鮑家と手を組み、鮑家が宴会の最中に支配する老貴族の阮家と高家を包囲したことで最高潮に達しました。激しい戦いの後、阮家と高家は敗北し、その中心人物である賈施と高強は魯の国に逃げました。 孫の像 しかし、これらの人々は、権力と利益をめぐる争いが、軍事戦略の達人である孫武が呉に逃げ込むことにつながるとは予想していませんでした。もちろん、孫武は傑作「兵法」を携えていきました。『史記 孫子呉起伝』には次のように記録されています。「(孫武は)兵法を呉の郝崙王に献上しました。郝崙王は「私はあなたの13章をすべて読みました」と言いました。 これは孫武が斉国にいた頃にはすでに軍書が出版されていたことも示しており、この軍書に反映されているのは主に斉国の軍事思想である。これについては後で詳しく説明するが、今は脇に置いておいて孫武についての話を続けることにする。 孫武が呉に到着すると、彼は実践的な行動で呉王に軍事的才能を示し、「和陸は孫子が軍隊を指揮する能力があることを知り、ついに彼を将軍にした」、つまり孫武は望みどおり呉の将軍になった。もちろん、彼はその後も名を上げ、西の強大な楚を破り、鄴に入り、北の斉と晋を脅かし、諸侯の間で有名になった。 それで孫武は結局どこへ行ったのでしょうか? 実のところこれは謎ですが、彼の最終的な結末には 2 つのバージョンがあります。引退したか、殺されたかです。 まずは撤退について話しましょう。 『唐太宗李衛公問答』には、張良、范礼、孫武が跡形もなく退役し、彼らの行方を誰も知らないと記されている。これは、張良、范礼、孫武が大きな功績を残した後、適切な時期に退役したことを意味する。孫武は、呉王扶差がますます暴君的になり、忠告を受け入れなくなり、親友の伍子胥が殺害されたのを見て意気消沈し、最終的に山中に隠遁して軍書の改訂に専念することを選んだことを意味する。 孫武の像 ましてや殺されるなんて。 『漢書刑法』には、孫、呉、商、白などの人々が過去に殺され、彼らの業績は未来に破壊されたと記されている。明らかに、ここでの孫は孫呉を指しており、つまり、孫呉、呉起、商陽、白起はいずれも大きな功績を残したが、結局は処刑されたということである。 しかし、「孫」は孫臏のことを指すと考える人もいます。しかし、古代人は本を書くときに非常に慎重でした。著者は、孫、呉、商、白は年代順に並べるべきだと信じているため、「孫」は孫武のことを指す可能性が高くなります。また、両方を指すという言い伝えもありますが、今は深く掘り下げません。 この2つの記述のどちらがより信頼できるかは、個人の意見次第です。孫武の最期は謎に包まれていますが、彼が残した『兵法』は永遠に残る傑作となっています。この軍書は主に斉国の軍事思想を反映していると前述しましたが、以下で詳しく分析してみましょう。 斉国の軍事思想の特徴。 斉文化の特質は斉の軍事思想に明確な特徴を与え、戦争で十分に発揮されました。これらの戦争は斉の軍事思想の形成を促進しました。『兵法』を通じて、私たちはこれらの特質を明確に理解することができます。その特質には主に次の側面が含まれます。 人々と興味を大切にします。 大衆を敬い、親族を団結させる。大衆を敬えば和があり、親族を団結させれば喜びがある。これを仁義の修行という。 ——「6つの戦略:文学戦略」 それは、自分の民を尊重し、自分の一族を団結させるべきだという意味です。民を尊重すれば和が生まれ、一族を団結させれば幸福が訪れる。これは仁義を実践する原則です。この作品は「太公の兵法」とも呼ばれています。この言葉は、蒋太公が文王に返した言葉でもあります。そのため、斉国には昔から民を重んじるという伝統的な考えがありました。 斉の関仲 『管子・覇道』には、「覇の始まりは人民を第一とする。人民をうまく統治すれば国は堅固になる。人民が乱れれば国は危うくなる」とも記されている。これは斉の強国化を助けた管仲が、覇権達成の出発点は人民を第一とすると考えていたことを意味する。人民をうまく統治してこそ国は堅固になる。しかし人民が乱れれば国は危うくなる。これは斉の人民を重んじる考えの延長である。 もちろん、このような考え方は斉の軍事思想、特に兵士の重視と配慮にも反映されています。孫子の兵法書にある「すべての戦いに勝つことがすべての技術の最善ではない。戦わずして敵を倒すことがすべての技術の最善である」という一節は、これを解釈したもので、兵士の犠牲を最小限に抑えて戦争で最大の勝利を得ることを主張しています。 また、斉の軍事思想は、兵士を重視することを基本として、実質的な利益を得ることを主張しました。もちろん、ここでの「利益」は国家利益と戦争利益に分けられます。 1. 国が利益を得る。 斉は、少なくとも斉の桓公と管仲の時代においては、現状に満足する属国ではなかった。斉の軍事思想における国益とは、斉の優位性と覇権を指す。例えば、斉の桓公の時代には、魏と興を救い、容人を征服し、燕に土地を譲ったが、これらはすべて世に仁義を示す行為であった。彼の意図は覇権を確立することであり、最終的に「九つの国を統一し、世に平和をもたらす」という偉業を達成した。 戦争の芸術 2. 戦争から利益を得る。 人民を重んじる思想の影響を受けて、斉の軍事戦略家たちは戦争においても具体的な勝利を追求した。その原則は、戦争による兵士や財産への損害を最小限に抑えることであり、それは孫子の兵法にも反映されている。すなわち、「利益がなければ行動せず、必要でなければ使用せず、危険でなければ戦わず...利益があれば行動し、利益がなければやめる」というものである。つまり、戦争を行うべきかどうか、またどの程度行うべきかは、国の利益とどれだけの利益が得られるかによって完全に決まるということである。 また、斉の利益重視の軍事思想は内政に限らず、対外的にも現れ、つまり「利益」を使って敵を動かし、戦争の主導権を握ろうとした。孫子の兵法書『兵法の初歩』に記されている通りである。「利益で敵を誘い込み、敵が混乱しているときに攻撃する...敵が準備ができていないときに攻撃し、不意を突く。つまり、戦争では、わずかな利益を犠牲にして敵を誘い込み、敵を不利な状況に陥れ、戦争の最終的な勝利を得ることができるのです。」 道徳を重んじ、戦略を追求する。 人々の蓄財を焼かず、人々の宮殿を破壊せず、墓や木や灌木を切り倒さず、降伏した者を殺さず、捕らえられた者を虐殺せず、彼らに慈悲と正義を示し、親切に接しなさい。 ——「6つの戦略:タイガー戦略」 戦争は残酷であり、降伏した兵士を殺すことはさらに非人道的であり、これも「六策」で禁止されています。前述のように、都市を征服した後、穀物の入った倉庫を焼かない、住民の家を破壊しない、墓や寺院の周りの木を切り倒さない、降伏した兵士を殺さない、捕虜を虐待しないという意味です。これは敵国の人々に親切を示し、道徳心を示すためです。 斉の対外戦争 「道」は斉国の軍事思想を貫く理念にもなりました。もちろん、戦争に勝った後に仁義を実践する道徳だけでなく、政治のやり方も含まれています。孫武が『兵法』で述べた戦争の勝敗を左右する5つの要素の中で、「道」は「一は道、二は天、三は地、四は将軍、五は法」と第一位に位置付けられています。では、「道」とはいったい何なのだろうか。孫武は「道とは民と君主を一致させること」とも説明している。つまり、民と君主が政治的に同じ考えを持つことでのみ、「君主とともに死に、君主とともに生きる」という力を発揮できるということである。つまり、民は君主と生死を共にし、死ぬまで君主に仕えることを誓い、迷いはないということである。 『孫子兵法』では、戦いに勝つための原則として「戦争は欺瞞の術である」と指摘している。斉国の軍事思想を反映するもう一つの著作である『孫薙兵法』も、これに関して独自の洞察を示しており、特に戦闘方法の「道」に焦点を当てている。『孫薙兵法・魏王問答』では、力を譲る、本性を見せるなど、戦況に応じて異なる戦闘方法も提案されており、大きな影響を与えた。 斉国の軍事思想は、道を重視するだけでなく、戦略も提唱しました。斉国の軍事戦略家が戦略を重視するようになった要因は、第一に、戦争がもたらす害と損失を認識していたこと、第二に、春秋戦国時代の属国間の力が比較的均衡していたことです。最小のコストで最大の勝利を達成することは、自国の力を維持する効果的な方法でした。 戦争の芸術 孫武の軍事思想も戦略に基づいています。彼は13章の軍事戦略を著し、その最初の章は「戦略の始まり」です。さらに、彼は敵を攻撃する戦略を具体的に分析した「攻勢戦略」も著しました。「最良の軍事作戦は敵の計画を攻撃することであり、次に良いのは敵の同盟を攻撃することであり、次に良いのは敵の兵士を攻撃することであり、最悪ののは敵の都市を攻撃することである」という部分は、戦争における戦略を新たな高みに押し上げました。 これにより、春秋戦国時代の戦争は勢いによるものから戦略によるものへと変化しました。その後の戦争で、数の少ない敵が大軍を破った例が数多くあることからも、戦略が戦争において常に重要な役割を果たしてきたことがわかります。 民事と軍事の両方を考慮する。 秩序と混沌は数の結果であり、勇気と臆病は勢いの結果であり、強さと弱さは形の結果です。 ——「孫子の兵法」 斉の軍師たちは、単に戦争を基準に軍事を論じるのではなく、軍事と非軍事の要素をしっかりと結びつけました。これは、民事と軍事の両方を考慮した斉の軍事思想の総合性を反映しており、戦争に影響を与える要素は実際には多くの矛盾で構成されており、一定の条件の下では相互に転化できることを指摘しています。 前述の「軍事力章」で論じられているように、軍隊の秩序や混乱はその組織によって決まり、兵士の勇敢さや臆病さは状況や勢いによって決まり、軍事力の強さや弱さは日々の訓練によって生み出される固有の強さによって決まるという転換可能な条件が提示されている。 春秋戦国時代の武具と武器 もちろん、この論文は、戦争の勝敗を決める要素の中で、人間の主体的な自発性も重要だと提唱し、この自発性を十分に発揮させることで矛盾を有利な状況に転化させることをさらに促進できると主張している。そのため、常に戦争の主導権を握り、最終的に「戦わずして敵を倒す」という目標を達成できるように、「他人に攻撃されるのではなく、他人を攻撃する」という考え方を提唱している。 戦況は急速に変化しており、この民軍一体の包括性は戦争に勝つための決定的な要素である。この包括性は斉の軍事思想が一つの意見に限定されず、あらゆる思想流派を包括し、順応していることも反映している。これは斉の軍事思想理論体系の形成にも決定的な要素であり、当然その影響は広範囲に及ぶ。 斉国の軍事思想の影響。 『兵法』に代表される斉国の軍事思想は、当時の斉国に大きな影響を与えただけでなく、同時代の他の属国にも広く影響を与え、もちろん後世にも多大な影響を与えた。 戦国時代初期、魏は唯一の強国であったが、改革を主導し強大化するという優位性を維持できず、覇権の座から引きずり下ろされたのは斉であった。孫斌は桂嶺の戦いと馬陵の戦いという二つの美しい戦いを戦い、実際の戦争で斉の軍事思想を十分に示し、「兵法とは欺瞞を用いること」という含意を改めて解釈した。 戦国時代に入ると、属国同士の戦争は白熱した状況にまで達した。生き残り、強くなるためには、最小のコストで最大の勝利を得ることも有効な手段であった。そのため、「兵法」が広く普及し、応用されるようになった。数え切れないほどの戦争の背後には、実は斉の軍事思想の影が見えるのだ。 さまざまな言語に翻訳された『孫子の兵法』 漢代初期の三英傑として知られる張良と韓信も斉の軍事思想に深く影響を受けた。『唐太宗・李衛公問答』には、張良は太宗の「六兵法」と「三兵法」を学び、韓信は「郎誅」と「孫武」を学んだと記されている。ここで言及されているこれらの軍事著作の「発祥の地」は、実は斉である。 ここで特に指摘しておきたいのは、秦漢の時代から近代に至るまで、『兵法』が後世に高く評価され、中国の軍事文化や思想が斉国の軍事思想に深く影響を受けてきたということである。各王朝における具体的な影響については、ここで改めて一つ一つ指摘することはしない。 結論: まとめると、斉の人々は戦いにおいて利益を重視していたが、理を捨てて戦略を欠いていたわけではないことがわかる。『兵法』に代表される斉の軍事思想は、実際には、戦争で利益を得ることが目的であり、戦略で勝つことが基礎であり、戦闘戦術と方法に注意を払うことが道であり、主体的なイニシアチブを十分に発揮することが保証であるという一連の軍事思想理論を反映している。 『兵法』は斉国の軍事思想の中で最も優れた軍事書であり、斉国の軍事思想体系の構築は『兵法』に基づいていると言える。斉国は乱世に最終的な統一を果たせなかったが、その軍事思想は今日まで受け継がれている。 |
<<: 「三宗教九階級」とは何ですか? 「9つのクラス」には何レベルありますか?
>>: 春秋時代初期の楚国最強の王族!なぜ若澳一族は三代後に滅亡したのか?
推薦する
呉広の死の謎:秦末の農民反乱の指導者である呉広はどのようにして死んだのか?
呉広の死の謎 秦末期の農民反乱の指導者である呉広はどのようにして死んだのか?紀元前209年、陳勝と呉...
古代において、死刑判決を受けた囚人はどのような状況下で死刑を免れたのでしょうか?
古代であれ現代であれ、国が正常に機能するためには、必要な法律や規則がなければなりません。これらの法律...
白居易は生涯でどのような親友に出会ったのでしょうか?彼はそれを詩の中でどのように記録したのでしょうか?
白居易に関する以下の物語は、Interesting History の編集者がお届けします。ご興味が...
楽毅が燕のために斉を倒した物語。楽毅は燕王に手紙をどのように書いたのでしょうか?
楽毅が燕のために斉を倒した物語。楽毅は燕王に手紙をどのように書いたのでしょうか?楽毅は非常に聡明で機...
三国志演義第80章:曹丕が皇帝を廃位して王位を奪い、劉漢王が王位を継承した
しかし、華鑫と他の文武の役人たちは献帝に会いに行きました。辛は言った。「私は魏王を見ました。王位に就...
司馬懿には忠実な兵士が 3,000 人しかいなかった。なぜ曹魏の元部下たちは反乱を起こさなかったのか?
古代の最も有能な君主といえば、曹操はトップ3に入るでしょう。曹操は偉大な野心と野望を持った英雄的な人...
本草綱目第4巻水部温スープの本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
なぜ曹歓は世襲の身分を下げて従兄弟の曹叡の養子になったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』で薛宝才が王夫人にこれほど好かれるのはなぜですか?理由は何ですか?
薛宝才は曹雪芹の小説『紅楼夢』とその派生作品のヒロインの一人です。以下の記事はInteresting...
廖世宗の若涛皇后とは?若涛皇后の妻、甄皇后の紹介
遼の世宗皇帝、野盧阮(917年 - 951年)は、遼王朝の3代目の皇帝でした。彼は、遼の懿宗皇帝(死...
なぜ崇禎が魏忠賢を殺さなかったとしても、明王朝は滅びたと言われるのでしょうか?
1644年、清朝が北京を占領し、明王朝は滅ぼされました。魏忠賢が殺されなければ国は滅びなかったかもし...
『旧唐書伝』巻23にはどのような出来事が記録されていますか?原文は何ですか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
彭石、愛称は春道、安府出身。『明史 彭石伝』の原文と翻訳
彭石は、名を春道といい、安府の出身であった。正統13年、科挙で首席となり、編纂官に任命された。来年、...
『紅楼夢』で黛玉が死んだ後、子娟に何が起こったのですか?
『紅楼夢』の登場人物である子娟は、もともと鶯歌という名前で、賈夫人の部屋の二等女中だった。 Inte...
白居易の古詩「衛八に答える」の本来の意味を理解する
古代詩「魏覇への返答」著者: 白居易あなたに美しい言葉をかけましたが、楽しい時間を逃してしまったこと...