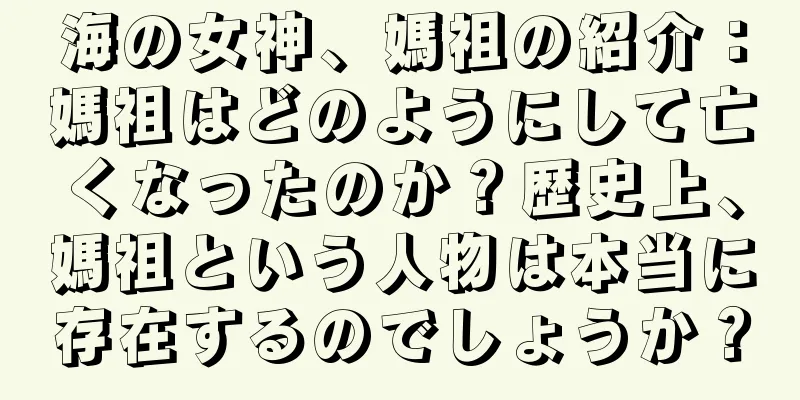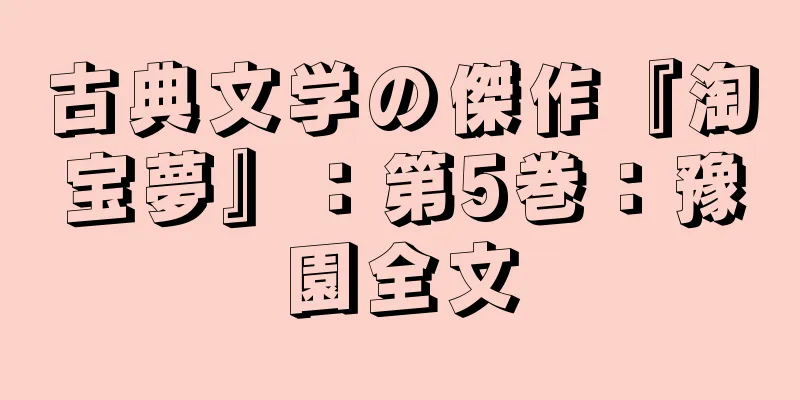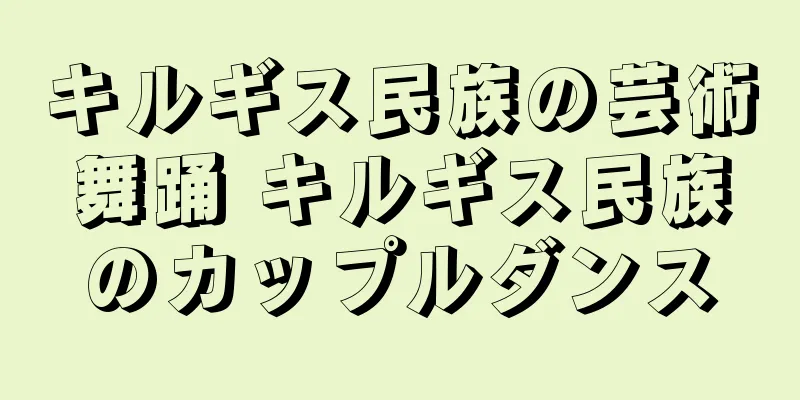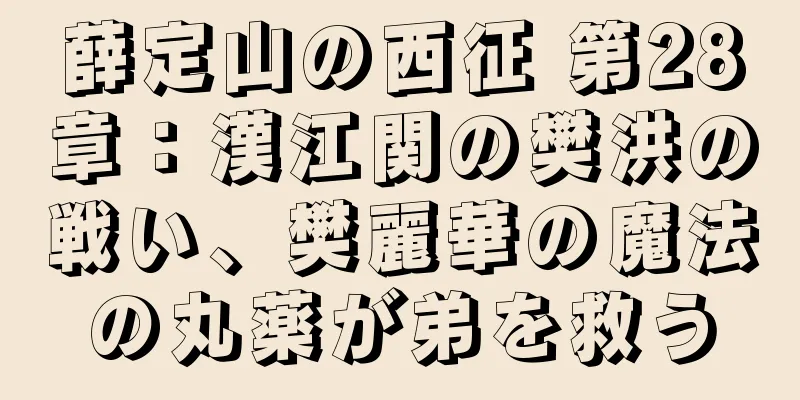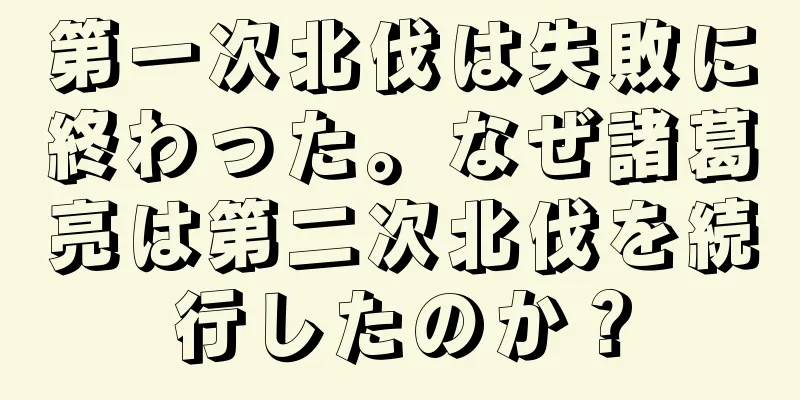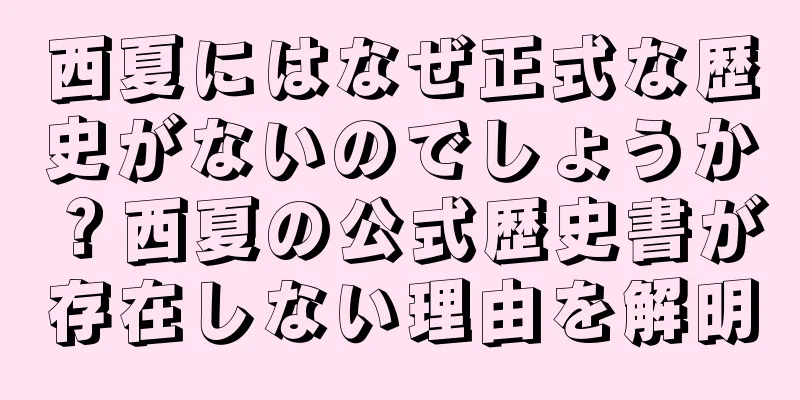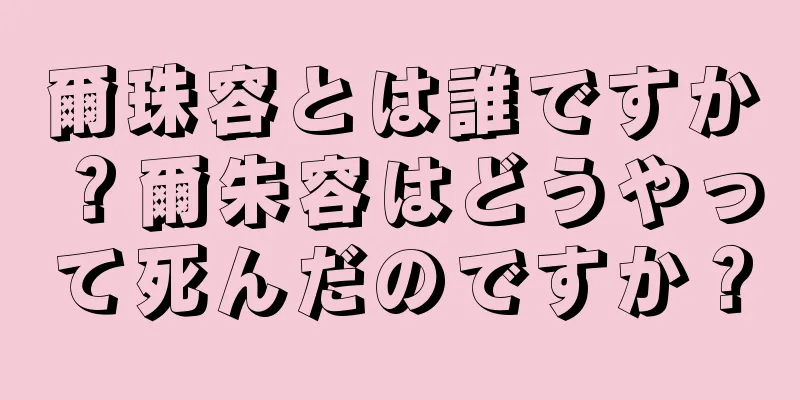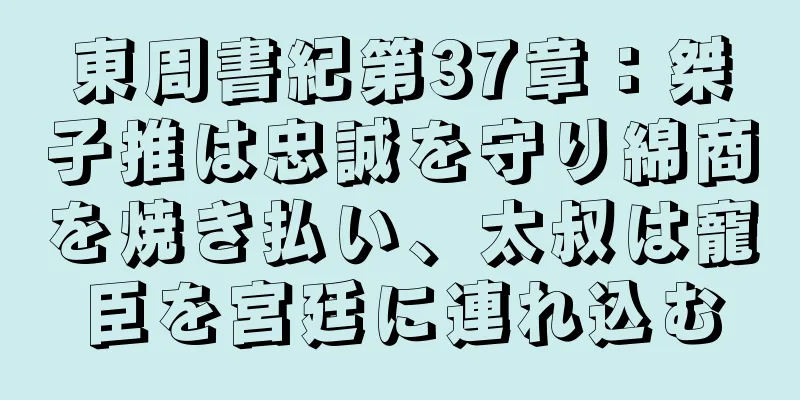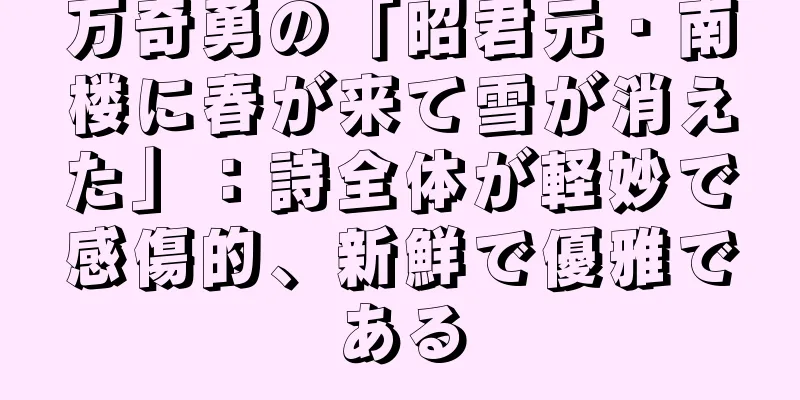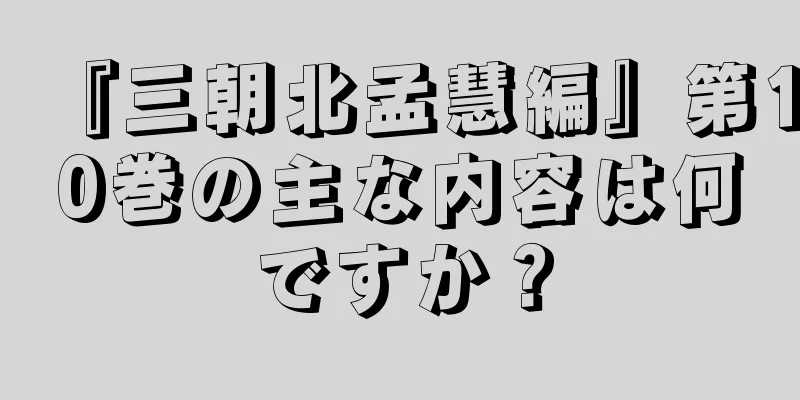三国時代のライバル同士だった司馬懿は諸葛亮を本当に恐れていたのでしょうか?
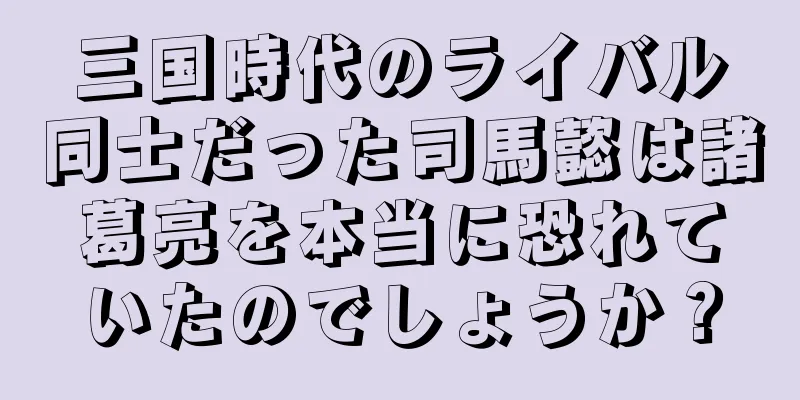
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、司馬懿が諸葛亮に対して臆病だった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 諸葛亮と司馬懿は三国時代のライバルであり、両者とも当時の有名な政治家であり軍事戦略家でした。しかし、諸葛亮が北伐に出ていたとき、司馬懿と諸葛亮の戦いは皆を驚かせました。司馬懿は諸葛亮に鎮圧され、外に出ることを拒んだ。諸葛亮の死後も、司馬懿は偽の軍隊に脅かされ、“死んだ諸葛亮が生きている中道を追い払う”という伝説を残した。それで、司馬懿は本当に諸葛亮をそれほど恐れていたのでしょうか? 1. 司馬懿と諸葛亮の戦い。 『三国志演義』では、諸葛亮の独創的なイメージを表現するために、作者は司馬懿を引き立てる人物として用いました。本書では、諸葛亮が初めて北伐を開始した瞬間から、司馬懿は諸葛亮の敵として描かれている。そこから、空城作戦、木門路の奇襲、上房谷の焼き討ちなど、一連の物語が展開されました。これらの物語では、司馬懿は諸葛亮に操られ、何度も命を落としそうになった。このため、司馬懿は諸葛亮を虎のように恐れ、簡単には諸葛亮と対決する勇気がなかった。 現実では、司馬懿と諸葛亮の戦いは三国志演義に描かれているほど長くは続かなかった。諸葛亮が第四次北伐を開始したとき、司馬懿は曹真に代わって関龍軍を指揮し、諸葛亮と戦った。司馬懿が諸葛亮の真の敵となったのは、諸葛亮の第四次北伐と第五次北伐のときであった。 しかし、これによって司馬懿が笑いものになることは防げなかった。諸葛亮の北伐に抵抗するこの二度の試みで、司馬懿は大きな損害を受け、不名誉な行為を行った。 『晋書』でさえ彼のパフォーマンスに耐えられず、本の中で彼を厳しく批判し、次のようにコメントしている。 その後、彼は軍隊を西に導き、諸葛亮と膠着状態を保った。彼らの鎧や武器を抑えれば、彼らは戦う気力を失い、女性を無視すれば、彼らは怒り出すでしょう。杖と皇帝の印章が門の前に突きつけられ、彼の野望は突然挫折した。彼は見せびらかすふりをして、1000マイル離れた場所での戦いを要求した。さらに、秦と蜀の民は勇敢さも臆病さも同等ではなく、安楽と楽に対する態度も異なっています。このように功績を競うことの利益は明らかです。しかし彼らは戻ってきて、軍隊を閉じて陣地を強化し、誰も戦う勇気はなく、生きている間は臆病で前進せず、死んでも疑い深く逃げ続けました。これが優れた将軍の失敗なのでしょうか? このコメントで言及されている司馬懿の活躍は、基本的には諸葛亮の第五次北伐の際に起こったものです。諸葛亮は司馬懿を戦争に駆り立てるために、女性の装飾品を与えて嘲笑した。司馬懿は軍内の怒りを鎮めるために、死ぬまで戦う決意をしているふりをしながらも、軍内の対立を解決し、自らの立場を守り続けるために、何千マイルも旅して戦いを求めるという策略も使った。さらに、司馬懿と諸葛亮は軍事的資質が異なり、仕事のやり方も異なっていたため、司馬懿が完全に有利であったにもかかわらず、司馬懿はあえて戦いに出ようとはしなかった。 最も滑稽なのは、諸葛亮が生きていたとき、司馬懿は彼と死ぬまで戦う勇気がなかったことだ。諸葛亮の死後、蜀軍を追撃していた司馬懿は、蜀軍の突然の反撃に恐れをなし、諸葛亮がまだ死んでいないと疑って逃げた。これが「死んだ諸葛が生きている中大を追い払う」という物語である。これにより、後世の人々は、司馬懿と諸葛亮の対決が、名将としての彼の評判に完全にふさわしいものであったと嘆くことになった。 2. 諸葛亮との戦いにおける司馬懿のジレンマ。 司馬懿は『晋書』の中で容赦なく批判されているが、彼の苦境については指摘されていない。実際、司馬懿と諸葛亮の戦いは非常に困難でした。当時、曹魏の朝廷では諸葛亮の北伐を恐れる者が多く、中には司馬懿に手紙を書いて戦況を尋ねる者もいた。 司馬懿は諸葛亮を恐れる必要はないと答えたが、諸葛亮が去った後に諸葛亮の軍営を視察した際、司馬懿は諸葛亮を「天下の天才」と絶賛した。これは、司馬懿にとって諸葛亮と戦うことは非常に困難な任務であったことを示しています。これらの困難は主に以下の理由によります。 まず、数回の北伐を経て、諸葛亮は実践的な経験を積み、軍事力が大幅に向上しました。諸葛亮は、自分を管仲や岳毅と比較しました。国を治める能力と比べると、彼の軍事的業績も非常に豊かでした。しかし、劉備の時代には、諸葛亮の統治能力に注目し、彼を宰相に任命した。これにより諸葛亮は戦場で戦い、実践的な経験を積む機会を失った。 劉備の死後、諸葛亮が蜀軍の総司令官の責任を引き受けた。しかし、深い理論的知識があっても、実践的なトレーニングも必要です。諸葛亮の第一次北伐の際、彼は実戦経験不足のため街亭の戦いで大きな損失を被った。しかし、第二次、第三次北伐の訓練により、諸葛亮は徐々に戦争に適応し、独自の戦闘スタイルを形成し、戦争で何度も敵を倒しました。司馬懿と戦う頃には、諸葛亮の軍事力は次第に頂点に達しており、司馬懿にとっては対処が困難な状況となっていた。 第二に、実際の戦闘訓練を経て、蜀軍は強力な軍隊になりました。諸葛亮は軍司令官になる前は劉備の軍事顧問および中将を務めていた。彼の主な責任は十分な食糧と兵士を確保することであり、これには軍隊の訓練という任務も含まれていた。夷陵の戦いの後、諸葛亮は軍を再編成するために成都に大規模な駐屯地を設け、新たな軍隊を再編成し訓練した。 武勇に恵まれた諸葛亮は、すぐに訓練し、装備が充実し、指揮が厳格な蜀軍を組織した。第一次北伐の際、この軍は「隊列がよく組織され、賞罰が厳しく、命令が明確」で、敵を驚かせた。残念ながら、この軍隊は実践経験に欠けており、戦闘経験豊富な張郃と曹真に敗北した。 諸葛亮は自らの失敗から学び、軍隊を再編成した。軍隊の強力な戦闘力は一夜にして形成されるものではないため、諸葛亮は蜀軍の特徴に基づいて特別に八卦陣形を策定しました。蜀軍が八卦図をうまく学び、実践した後、諸葛亮は友人たちに、蜀軍はこれから無敵になるだろうと嬉しそうに語った。 やがて、蜀軍の強大な力が戦場で実証され、両軍が正面から対峙する限り、魏軍は敗北する運命にあった。しかし、八卦陣は極めて強力である一方で、機動力が弱く、戦闘方法が硬直的であるという欠点も持っています。それでも、司馬懿は八卦陣を前にして、それを破る術がなく、野戦では不利な状況に陥った。 第三に、司馬懿の強さには絶対的な優位性はありません。諸葛亮と曹魏の対決では、曹魏が常に不利であった。その最大の原因は、曹魏の関龍軍の戦力が絶対的な優位ではなかったことであった。当時、関龍一帯は戦争による荒廃で広大な土地が無人となっていた。このような状況下では、地元の資源で大規模な軍隊を支えることはほとんど不可能でした。 諸葛亮は軍を送るたびに、必ず曹魏の急所を狙った。千里の防衛線に沿ってあらゆる場所に防御を敷く必要があったため、曹魏の軍事力は限界に達していた。また、蜀漢に比べ、曹魏の心を直接脅かす東呉は曹魏にとって主敵とみなされていた。曹魏は軍の主力を東呉の攻撃に対する防衛に使用し、関龍地域の残りの軍隊は主に防御に使用されました。 諸葛亮の第五次北伐の際も、総動員された蜀軍を前に、曹魏は依然として主力を東方戦線に配置し、東呉の侵攻に抵抗した。曹叡は東呉からの攻撃を撃退した後、関龍を援軍せよという部下の提案を無視した。これは、司馬懿の軍隊が防御任務を遂行することしかできず、諸葛亮との決戦を戦うための兵力の絶対的な優位性がなかったことを意味していました。 上記の理由により、司馬懿は諸葛亮を倒して排除するという任務を遂行することができませんでした。逆に諸葛亮と戦う際に注意しないと、予想外の損失を被ることになります。そのため、司馬懿は戦わずに持ちこたえるという防御戦略を採用し、蜀軍が撤退するまで諸葛亮と最後まで対峙した。 3. 司馬懿は諸葛亮を恐れていなかったこと、そして「死んだ諸葛亮が生きている鍾馗を追い払った」という事実。 司馬懿と曹叡は曹魏の防衛戦略について議論しながら戦略を立てた。諸葛亮の蜀軍が攻撃に来たとき、曹魏は地の利に頼って戦わずに地盤を固めるという計画だった。しばらくの対立の後、諸葛亮の兵站補給が困難になると、諸葛亮が撤退した際に蜀軍を追撃し、最終的な勝利を収めた。 諸葛亮の第五次北伐の際、司馬懿は四方八方からの圧力に耐え、作戦を厳格に実行した。諸葛亮の死後、ついに司馬懿にチャンスが訪れた。蜀軍が撤退しているという情報を得た後、彼はすぐに魏軍を率いて追撃した。しかし、蜀軍に近づくと、蜀軍は反撃の準備を整えた。これを見た司馬懿は慌てて撤退し、「死んだ諸葛が生きている鍾大を追い払った」というジョークを残した。 では、司馬懿が諸葛亮を恐れているというのは本当でしょうか?司馬懿の活躍を見れば、そうではないと感じるでしょう。諸葛亮は司馬懿が遭遇した最も困難な敵であったが、司馬懿が諸葛亮を恐れていることを示すような発言や行動は見られなかった。これは、司馬懿が第4次北伐の際に張郃に諸葛亮を追撃するよう命じたときに見ることができます。 諸葛亮の第五次北伐の際、司馬懿は蜀軍が食糧を尽きて撤退する機会を待っていた。蜀軍が撤退すると、彼はすぐに軍を率いて追撃し、完全な勝利を収めようとした。撤退後、蜀軍の陣地を視察し、諸葛亮が死亡したことを確認した。彼は直ちに再び軍を派遣し、あらゆる手段を講じて蜀軍を茨の道から阻止しようとした。これは彼の強い闘志を反映している。 司馬懿が撤退した理由は、戦う機会を掴んだかどうか自信がなかったからである。もし彼の情報が正確で、諸葛亮が死んだか蜀軍の食糧が尽きたことを知っていたなら、彼は絶対に撤退しなかっただろう。しかし蜀軍が反撃を開始したため、司馬懿は自分の判断が間違っていたのではないかと考え、逃亡することを決意した。 司馬懿が蜀軍の反撃を恐れたのにはもう一つ理由があります。それは、蜀軍には反撃という特殊な戦法があったからです。この戦術は劉備によって考案され、諸葛亮によって開発され、戦場で効果があることが証明されました。劉備が伯王を守っていたとき、夏侯惇と于禁との戦いは膠着状態にありました。劉備は自らの陣地を焼き払い、撤退を装い、曹操の追撃を待ち伏せ、一撃で夏侯惇の軍を破った。 この戦術は諸葛亮の手によって常に効果的であった。諸葛亮の第二次北伐の際、諸葛亮は陳倉を占領できなかった。魏の将軍王爽は軍を率いて撤退する諸葛亮を追撃したが、諸葛亮に敗れ、王爽は殺害された。諸葛亮の第四次北伐の際、諸葛亮は木門路で待ち伏せし、追撃してきた魏の将軍張郃を打ち破り、その場で張郃を射殺した。 これらの戦闘例は司馬懿に衝撃を与え、彼は追撃者が同じ過ちを繰り返すのではないかと恐れて震え上がった。そのため、蜀軍が反撃の準備をしているのを見て、蜀軍に待ち伏せされるのではないかと恐れ、急いで撤退した。これが「死んだ諸葛が生きている中大を追い払った」という真実です。諸葛亮の死後、司馬懿にとって最大の試練は終わった。安堵した司馬懿は、この件で人々が嘲笑しても気にせず、ただ笑い飛ばした。 結論: 諸葛亮の第4次北伐と第5次北伐の際、諸葛亮と司馬懿は戦場で出会った。司馬懿は諸葛亮の前で臆病な態度を取り、ついには戦うことを拒否した。特に諸葛亮の死後、司馬懿が蜀軍を追撃していたとき、蜀軍の反撃に恐れをなし、すぐに軍を撤退させたため、「死んだ諸葛亮が生きている中大を怖がらせた」というジョークが残された。 実際、司馬懿は諸葛亮を恐れてはいなかった。諸葛亮の優れた軍事指揮と強力な蜀軍を前に、力不足の司馬懿は、確立された戦闘戦略に従い、戦わずに持ちこたえる防御戦術を採用することしかできず、蜀軍が撤退するまで待ってから追撃して勝つことを望んでいた。しかし、司馬懿は蜀軍の突然の反撃という秘密兵器に怯えていた。そのため、蜀軍に関する正確な情報がなかったため、司馬懿はまず自らの安全を確保するために軍隊を撤退させることを選択した。 |
<<: 孫権は曹操と劉備という二人の敵を失った後、なぜ天下統一に失敗したのでしょうか?
>>: 諸葛亮と並ぶ劉備配下の軍師として名高い龐統が死ななかったらどうなっていたでしょうか?
推薦する
洛因の諸葛亮に関する詩は古典である
諸葛亮は三国時代の蜀漢の宰相であった。三国時代の多くの優れた人材の中でも、諸葛亮は間違いなく最も注目...
秦観は春に旅をしていたとき、「星香子・村の周りの木々」を鑑賞する詩を書いた。
秦観は春の遠出の際、「星香子・村の周りの木々」という詩を書いた。次の興味深い歴史の編集者があなたに詳...
『孟子』を書いたのは誰ですか?この本の主な内容は何ですか?
孟子(紀元前372年頃 - 紀元前289年頃)、名は柯、字は子豫。彼は鄒邑(現在の山東省鄒県の南東部...
甘露改が失敗した理由と甘露改の影響を明らかにする
甘露の変とは、大和朝廷9年11月に起こったクーデターのことである。このクーデターでは最終的に宦官が主...
伝統料理「クリスピーポーク」の起源と蘇大吉の物語
クリスピーポークの起源:クリスピーポークと言えば、祭りや結婚式、葬式などの際に人々の食卓に欠かせない...
司馬懿はクーデターを起こした当時、実質的な権力を持っていませんでした。彼はどのようにしてクーデターに成功したのでしょうか?
司馬懿はクーデターを起こした当時、実質的な権力を持っていませんでした。司馬懿はどのようにしてクーデタ...
唐代の薛延托王国について簡単に紹介します。薛延托王国と唐王朝の関係はどのようなものだったのでしょうか?
中国北部の古代民族、薛岩沐(シュエヤントゥオ)族。それはハン国の名前でもあります。もともとは薛族と塩...
中国古典の鑑賞:『朱熹于礼』第4巻の原文:自然と倫理
◎キャラクターの気質や性質これらの言葉は、古代から何千年もの間、賢者や賢人によって唱えられてきました...
現在世界で最も高価な本トップ10
はじめに:世界で最も高価な本がいくらかご存知ですか? どの本が莫大な価値があり、いくらで売られている...
東郷建築 東郷住居の特徴は何ですか?
東郷民家の特徴とスタイル東郷族は甘粛省に居住しており、長い歴史と多様な文化の融合を持つ独特の少数民族...
漢字の解説:古代ではなぜ妻や妾は「家重荷」と呼ばれたのか?
「レイ」が「妻と妾」という意味であるのは、「重荷」や「荷物」という意味から来ているのではなく、「疲労...
「秀雲閣」天嶼池の蓮の怪物が道を買い、象馬嶺の黄色い蝶が復讐を狙う
天嶼池の蓮の怪物は復讐のためにゾウマリンから黄色い蝶を買う三嶺の盗賊たちは皆、三間によって変身させら...
劉玉熙の『韓信廟』の何が良いのでしょうか?どのような感情が表現されるのでしょうか?
まだ分からない:劉玉熙の『漢信寺』の何がそんなに良いのか?どんな感情を表現しているのか?これは唐...
「陸吉は才能がたくさんあるのに、どうやって自分を守れるのか」の次の文は何ですか?
「陸機は才能が多すぎる、どうやって身を守ることができるか」の次の文は何ですか? 「陸機は才能が多すぎ...
『紅楼夢』に登場する無視できないメイドは誰ですか?意味は何ですか
『紅楼夢』では、主人だけでなく、メイドたちの物語もかなりの部分が占めています。次回は『Interes...