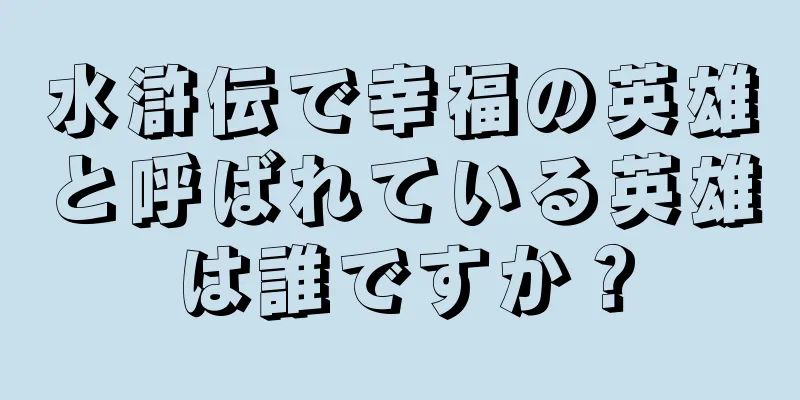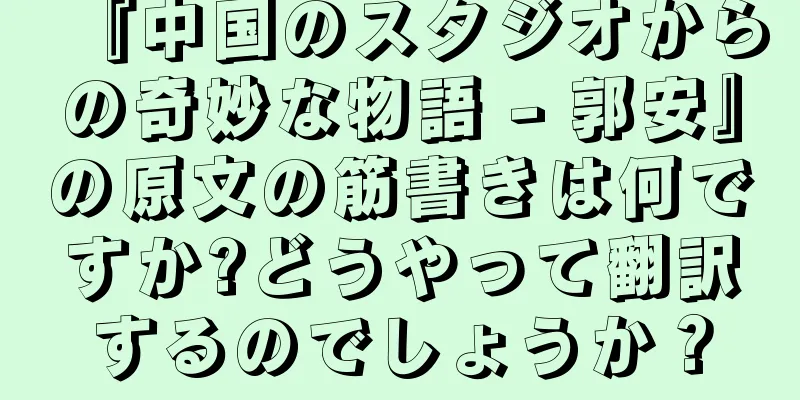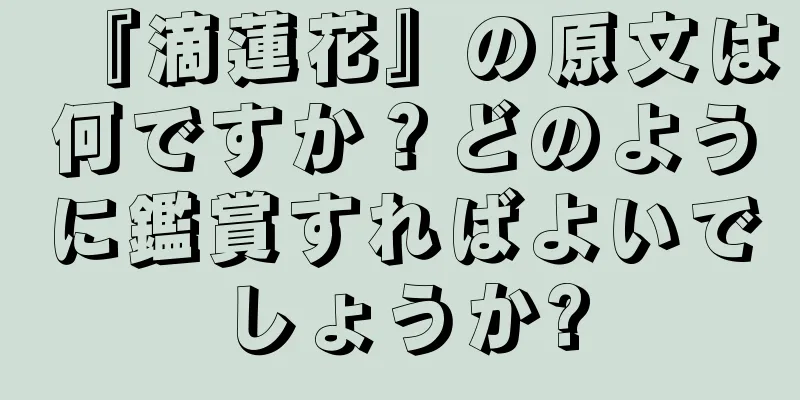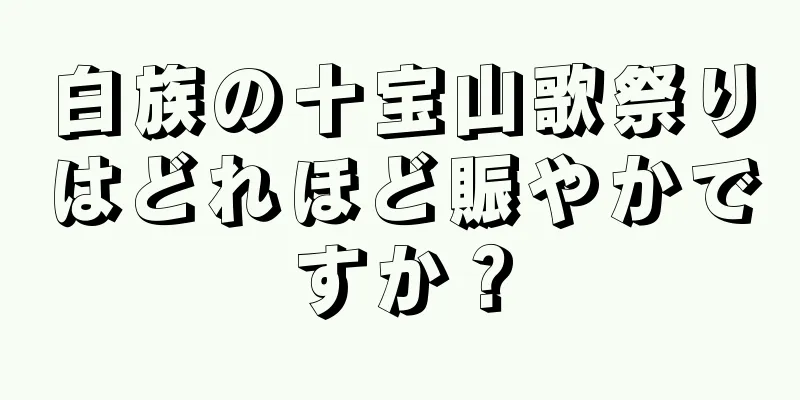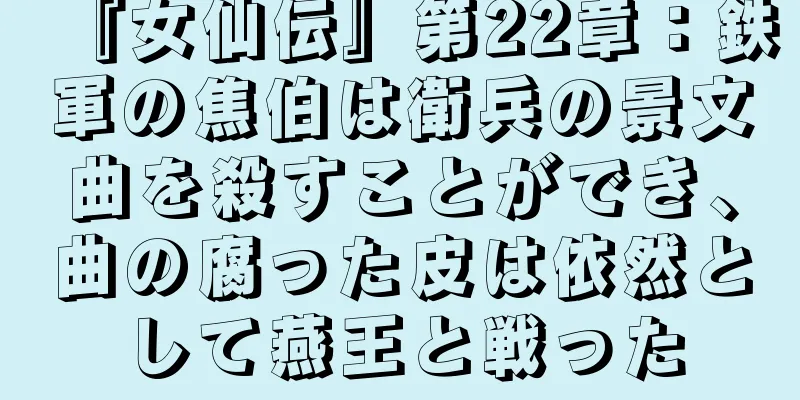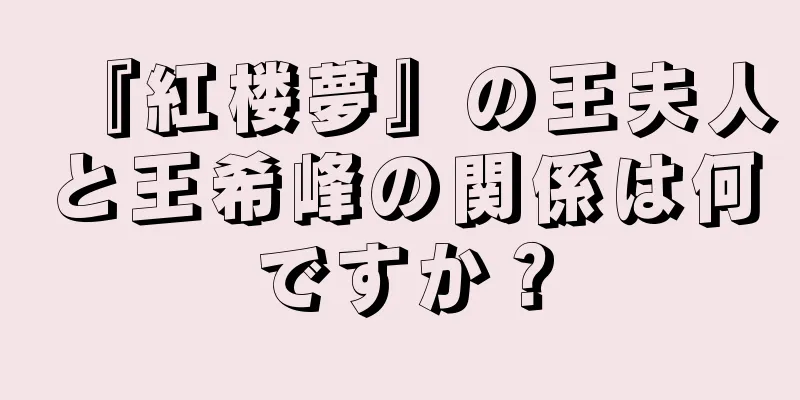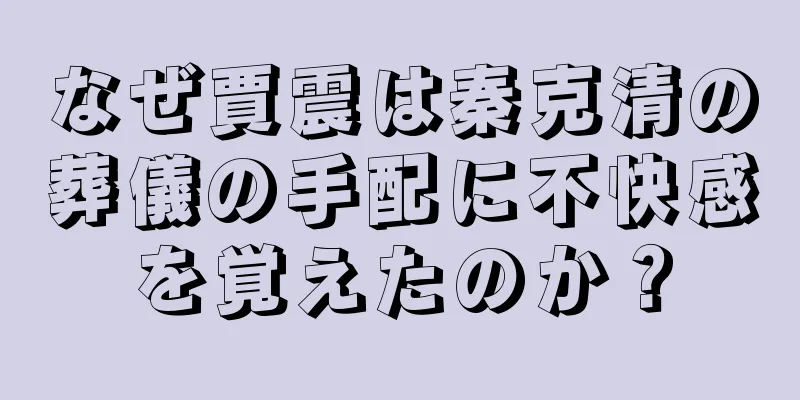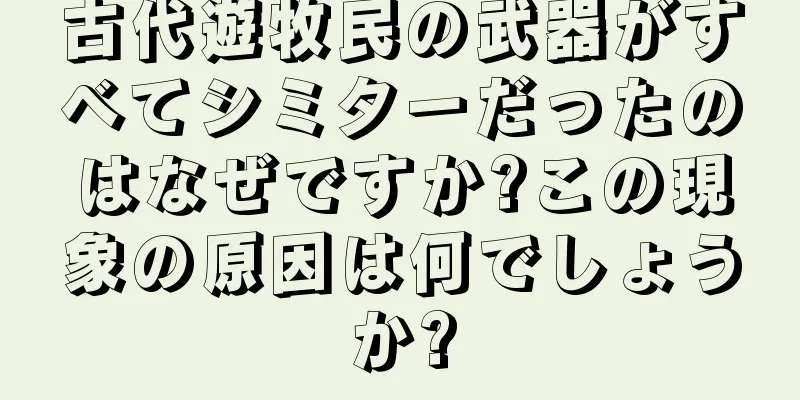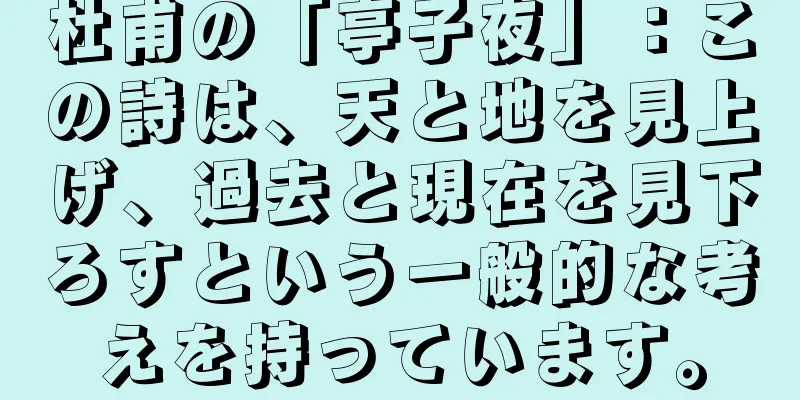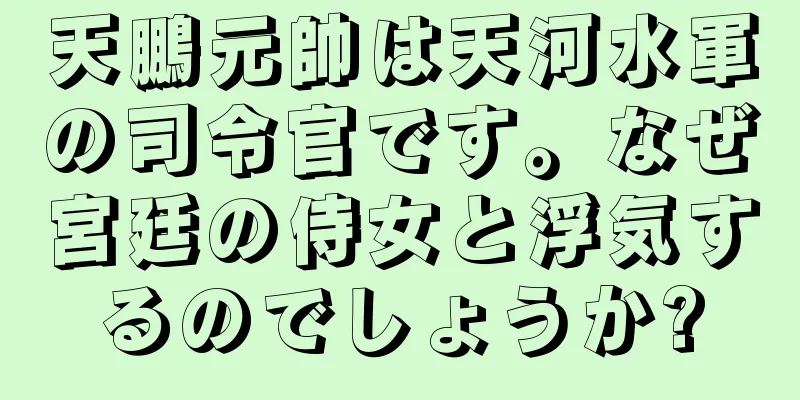諸葛亮が空城計画を展開した後、司馬懿はその陰謀を見抜いたのでしょうか?
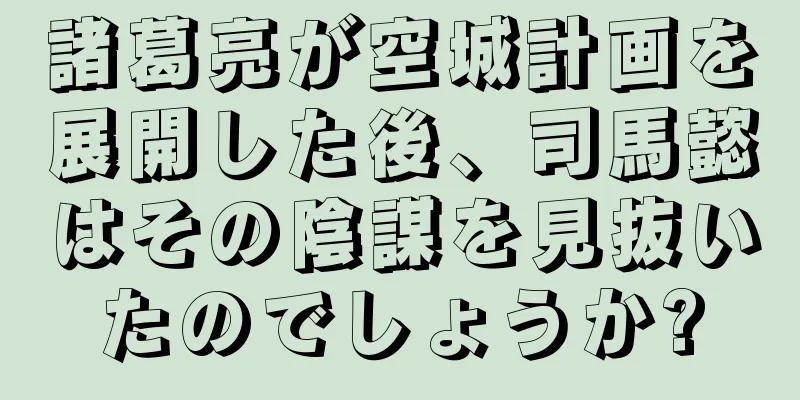
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、司馬懿が諸葛亮の空城計画を実際にどのように見抜いたかについて、詳しく紹介します。見てみましょう! 中国には、諸葛亮が空城計画を利用して司馬懿を追い払ったという有名な話があります。京劇では『世空戦』もよく歌われる古典劇です。この物語は、諸葛亮が最初の北伐を開始したとき、当初は街亭で司馬懿と決戦をしようと考えていたことを伝えています。しかし、諸葛亮は人の使い方を知らず、傲慢な馬素を街亭の守護者に選び、司馬懿に敗れました。その時、司馬懿は勝利に乗じて敵を西城郊外まで追撃した。諸葛亮の軍勢はすべて撤退任務に派遣され、手元にあったのは数人の官僚と少数の兵士だけだった。そこで諸葛亮は空城計画を展開し、4つの門を開いて司馬懿が城に入ることを許可した。司馬懿は城の外で何度も躊躇したが、最終的に撤退を決意し、諸葛亮が危険から逃れられるようにした。 この物語は素晴らしいですが、「三国志演義」にしか存在しません。諸葛亮が空城戦術を現実世界で使うのを見ることは不可能です。諸葛亮は空き城計画を利用する機会がなかったので、どうやってそれを利用するのでしょうか? これは諸葛亮の性格とやり方によって決まります。桓温が蜀を攻撃したとき、彼はかつて諸葛亮に仕えていた老兵に出会った。彼は老兵に諸葛亮の何がそんなに特別なのか尋ねた。老兵は答えた。「諸葛亮に特別なところはないが、私はこれまで人生であれほど着実に物事をこなす人を見たことがありません。」桓温は最初はそれに同意しなかったが、よく考えると諸葛亮をますます尊敬するようになった。 諸葛亮は物事を慎重に行う人物でした。彼は注意深く考え、秩序正しく物事を進めました。司馬懿の言葉によれば、諸葛亮は生涯を通じて慎重で、危険を冒すことを好まなかった。そのような人物がどうして空都市戦略に頼ることができるのでしょうか? 実際の街亭の戦いを例に挙げてみましょう。街亭を守る馬蘇の軍を破った2万人の軍隊が、なぜ王平の1,000人の軍隊に怯えてしまったのでしょうか。さらに、街亭の諸葛亮の軍隊は敗北し、散り散りになって逃げ場を失ったことが歴史の記録に残されており、悲惨な光景であった。なぜ彼は勝利を利用して諸葛亮の拠点である西城への攻撃を続けず、代わりに隴西三県の反乱を鎮圧しようとしたのでしょうか。諸葛亮は冷静に兵站を避難させ、西城の千戸余りを漢中に避難させた。 これは諸葛亮の主力がまだそこにあり、張郃は危険を冒す勇気がなかったためである。諸葛亮は馬謖に街亭の警備を命じ、兵力はわずか2万しか与えなかった。今回、諸葛亮は北伐に6万の軍を派遣し、戦闘開始時に降伏に応じた3つの郡に加え、さらにいくつかの軍も組み込んだ。そのため、諸葛亮は、魏延、呉毅などのベテラン将軍を含め、少なくとも3万から4万人の軍隊を率いていました。したがって、張郃が諸葛亮の西城を攻撃すれば、長い道のりを旅して疲れ果てた諸葛亮の軍隊は困難に陥ることになるだろう。そこで張郃は、今のうちに退却して、軍を休ませて統治を再開するために隴西に向かった。諸葛亮も街亭を失い、攻撃の拠点を失ったため撤退を余儀なくされた。 街亭の戦いでは、王平は千人の兵と馬に太鼓を鳴らして頼りにしたため、張郃は待ち伏せがあるのではないかと疑い、攻撃をしなかった。この計画は、実は「空都市戦略」の原型です。 『三国志演義』では、諸葛亮の栄光のイメージを確立するために、作者は芸術的な加工を施して諸葛亮にこの細部を加えました。実際のところ、諸葛亮は空の城計画を利用する機会を決して自分に与えないと決めました。 さて、「三国志演義」の仮想的な雰囲気に戻りましょう。司馬懿の軍隊が西城城に到着したとき、諸葛亮は空城計画を使わざるを得ませんでした。司馬懿はこの計画を見抜いたのでしょうか?彼は何を考えていたのでしょうか? 司馬懿は当時諸葛亮の空城計画を見抜いており、他の配慮があったため城に入らなかったという説もある。この配慮は主に司馬懿自身の将来を考えたものでした。これは曹操の時代に、司馬懿は鷲の目と狼のような視線を持っていたため、曹操から信頼できない人物とみなされていたためである。死に際、曹丕に司馬懿に注意を払うよう特に注意した。そのため、曹丕の時代、曹丕は司馬懿を非常に信頼していたものの、軍事力は与えなかった。 ついに曹丕が亡くなり、司馬懿は孤児の世話を任された重臣として曹叡を助けた。司馬懿は孟達を鎮圧することで軍事力を掌握し始めた。諸葛亮とのこの戦いの間に、司馬懿は正式に大軍の統制権を獲得した。この時、司馬懿と諸葛亮は西城で会見した。司馬懿の激しい圧力により、諸葛亮は空城作戦を取らざるを得なかった。司馬懿が城内に軍隊を派遣した限り、城が陥落すれば諸葛亮は必ず殺されるだろう。 もし諸葛亮が捕らえられ、殺されたなら、それは前例のない偉業となるだろう。諸葛亮の死後、蜀漢政権は崩壊した。こうして曹魏は天下を統一する機会を得た。しかし、この時点では司馬懿は軍事力を掌握したばかりで、曹魏軍の中では独自の権力を持っていませんでした。蜀漢を滅ぼした後、主君よりも優れた能力を持っていた司馬懿は、殺されるという災難に直面した。 司馬懿自身も曹操から評論を受けており、曹叡も即位したばかりであったため、司馬懿と曹叡の関係は浅かった。そして曹魏軍では、司馬懿には自らの権力を強化する時間がなかった。司馬懿は大きな貢献をしたが、報われず、さらに同僚から妬まれ、自ら災難を招く可能性もあった。たとえ曹叡が司馬懿を殺さなかったとしても、天下はすでに決まっており、司馬懿は役に立たないだろう。彼は幸運にも、自宅で老後を穏やかに過ごすことができる。司馬懿は曹家に一生無償で仕え、悲惨な老後を送った。野心的な司馬懿はどうしてこのようなことをすることができたのでしょうか? そのため、城壁の上で真面目な顔をする諸葛亮を前に、司馬懿は心の中で嘲笑した。彼は諸葛亮の罠にかかったふりをして軍を撤退させ、諸葛亮と自分自身のために退路を残した。その後の諸葛亮との対決で、司馬懿は徐々に関龍軍における自身の権威を確立していった。特に諸葛亮の第四次北伐の際、司馬懿は諸葛亮を利用して張郃を射殺し、軍内の反対勢力を完全に排除した。それ以来、関龍軍団は司馬懿の切り札となった。その後、司馬家が権力を簒奪する過程で、彼は司馬家に多大な貢献をした。 もちろん、上記の推測は合理的かつ妥当なものです。しかし、当時の状況から判断すると、抜け穴があったようです。司馬懿は諸葛亮に生きるチャンスを与えたかったのだから、現実の張郃のように西城を攻撃しないのはなぜだろうか。司馬懿はただ事後の処理をし、諸葛亮が撤退するのを見守るしかなかった。司馬懿は軍を派遣して諸葛亮を追って漢中に送り返すこともできたのに、なぜ西城で諸葛亮を絶望的な状況に追い込まなければならなかったのか? したがって、司馬懿が西城に到着したとき、彼の心理は上で分析したほど複雑ではなかった。司馬懿は勝利を拡大するために西城を攻撃したが、諸葛亮を捕らえることができればさらに良いだろう。しかし、なぜ司馬懿は諸葛亮の空城計画に怯えたのだろうか。その主な理由は、諸葛亮に対する司馬懿の先入観にあった。つまり、諸葛亮は生涯を通じて慎重で、決して危険を冒すような人物ではなかったのだ。 司馬懿と諸葛亮は昔から交流があり、司馬懿が曹操の配下だったころから諸葛亮のことは聞いていた。諸葛亮が初めて小屋から出てきた時、彼は3回の火で曹操の軍を打ち破り、曹操の軍を恐怖に陥れた。諸葛亮の戦略に対する評判は曹の軍隊の間でもよく知られていた。 司馬懿の心の中にはもう一つの疑問があった。それは、司馬懿の軍隊と諸葛亮の軍隊の人数に常に不均衡があるということだった。諸葛亮が率いる軍隊は、街亭で遭遇した軍隊とは大きく異なっていた。では、行方不明になった軍隊はどこへ行ったのか?これは司馬懿の心の中では未解決の謎である。ウェストシティが廃都市であるならば、この質問を説明することはさらに不可能になるでしょう。 結局、司馬懿は遠くからやって来て、現地の状況について何も知らなかった。司馬懿は不慣れな環境の中でより慎重に行動し、決して不注意になることはなかった。彼は諸葛亮が少数の軍勢で大軍を倒す能力があることを知っていたため、さらに心配していた。 上記のような状況では、これまで決してリスクを冒さず慎重に行動していた人が、突然冒険的な態度を取るようになります。司馬懿は心の中で諸葛亮が西城の周囲に罠を仕掛けたに違いないと感じた。しかし、状況が不明瞭なため、諸葛亮がどのような罠を仕掛けたのか判断する術がなかった。司馬懿は疑い深く、柔軟な性格の持ち主で、あらゆる面から長所と短所を検討した結果、諸葛亮の罠にはまらないことを決意した。 なぜなら、司馬懿はすでに街亭の戦いで勝利しており、諸葛亮が撤退しなければ退路が断たれてしまうからである。司馬懿はただ様子を見て、諸葛亮が撤退したら状況に応じて追撃するだけでよかった。戦争の技術にもあるように、絶望的な敵を追いかけてはいけない。司馬懿が諸葛亮の追撃により予想外の挫折を味わったとしても、それは余計なことである。このため、すでに勝利を確定していた司馬懿は諸葛亮と正面から戦う必要がなかった。そのため、司馬懿は撤退を選択し、諸葛亮を解放した。 結論: 諸葛亮が空城の計略を使ったとき、司馬懿はすでに諸葛亮の計画を見抜いていたという人もいます。しかし、司馬懿は自身の権力のため、そして将来曹魏の政権を奪取するために、諸葛亮を解放した。これは理にかなっているように思えますが、実際にはそうではありません。 曹魏の建国体制の観点から、皇帝を孤立させ、その親族を厳しく監視していたため、将来、曹魏の権力は間違いなく有力な官僚の手に渡ることになるだろう。司馬懿が忍耐と長生きを続ける限り、忍耐によって必要な力を得ることができる。空城作戦当時、司馬懿にはそのような条件はなく、軍事的功績を積み上げて皇帝の信頼を得て、徐々に自らの権力を築き上げることしかできなかった。 空城作戦が開始されたとき、状況は実は非常に単純でした。司馬懿は敵を敵と勘違いさせる諸葛亮の戦略に陥りました。司馬懿は諸葛亮が危険を冒さない慎重な人物であると信じていた。しかし、そのような人物が突然空城計画を提起したとき、司馬懿は自分が罠に落ちたのではないかと思わずにはいられなかった。状況がはっきりせず、すでに戦いで完全な勝利を収めていたため、司馬懿は諸葛亮と賭けるリスクを負うことを望まなかった。彼は勝利を維持するために安全な方法を取り、諸葛亮の命を救い、撤退を許した。 諸葛亮は逆の発想で危険な行動を取り、司馬懿を倒しました。実は『三国志演義』にはこのような戦いの例が数多くあります。例えば、諸葛亮が関羽に火をつけて曹操を華容路に誘い出すよう提案するなど。著者はこれらの戦闘例を用いて諸葛亮の機転の利いた芸術的なイメージを描き出し、『三国志演義』に多くの輝きを加えています。 |
>>: 龍の起源: 龍のトーテムは中国の伝統文化の中でどのように生まれたのでしょうか?
推薦する
中国古典風刺文学の傑作『士人』の簡単な紹介
『士人記』は清代の呉敬子が書いた長編小説で、乾隆14年(1749年)かそれより少し前に完成しました。...
『晩秋の曲江一人旅』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
晩秋の曲江一人旅李尚閔(唐代)春の憎しみは蓮の葉が成長すると生じ、秋の憎しみは蓮の葉が枯れると生じま...
歴史上、川の夜景を描写した詩にはどのようなものがありますか?詩人はどんな場面を描写しているのでしょうか?
歴史上、川の夜景を描いた詩は数多くあります。興味のある方は、Interesting History ...
歴史上の大工皇帝は誰でしたか?
大工帝と呼ばれたのは明の徽宗の朱有嬌である。明の徽宗朱有嬌は、明の光宗朱昌洛の長男であり、明の時宗朱...
古代詩の鑑賞: 詩集: 白い子馬: 明るい白い子馬が私の畑の苗を食べます
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
漢王朝時代に人口にどのような変化が起こりましたか?変化の原因は何ですか?
我が国が解放されたとき、その人口は4億人でしたが、古代の人口はそれほど多くありませんでした。長年にわ...
北派の風景画家とは誰ですか?彼らはどんな作品を残したのでしょうか?
北派の山水画は伝統的な中国絵画の重要な流派の一つであり、大胆で力強く力強い作風で有名です。では、有名...
『梁書』徐文勝伝にはどのような歴史物語が記録されているのでしょうか?
梁は、中国史上、南北朝時代に南朝の第三王朝として存在した謎の王朝です。蕭延が斉に代わって皇帝になりま...
『紅楼夢』では、官仲人が丹春に結婚を申し込んだ。なぜ王夫人は賈正に言わなかったのか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
三国志演義第44章:孔明は知恵を使って周瑜を奮い立たせ、孫権は曹操を倒す決意をする
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
数世代にわたる進化を経て、北斉の高歓は鮮卑に同化したのでしょうか?
高歓は渤海の高氏族に生まれ、もともと漢民族であった。彼の先祖は前燕と後燕の高官であった。北魏の時代に...
徐福が東方への航海の後に最終的にどこに行ったのか、最も考えられる説明は何でしょうか?
秦の始皇帝は晩年、不老不死の術を信じていた。不老不死を求めて、始皇帝は徐福らを海に派遣し、不老不死の...
明朝の四つの家はどのように順位づけられていますか?明朝の四つの家のリーダーは誰ですか?
明代四大家とは、明代に絵画の分野で優れた業績を残した4人の画家を指します。彼らは、沈周、文正明、唐寅...
康熙通宝は価値があるのでしょうか?全部でいくつのバージョンがありますか?
康熙通宝は価値があるのでしょうか?全部で何種類あるのでしょうか?康熙通宝貨幣の直径は2.5~2.8セ...
中国に現存する最大の湖はどこですか?彼らの名前は何ですか?
本日は、Interesting History の編集者が、中国に現存する最大の湖のランキングをご紹...