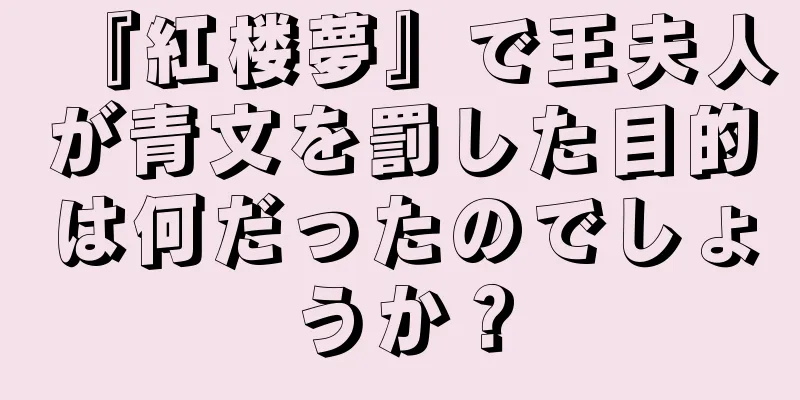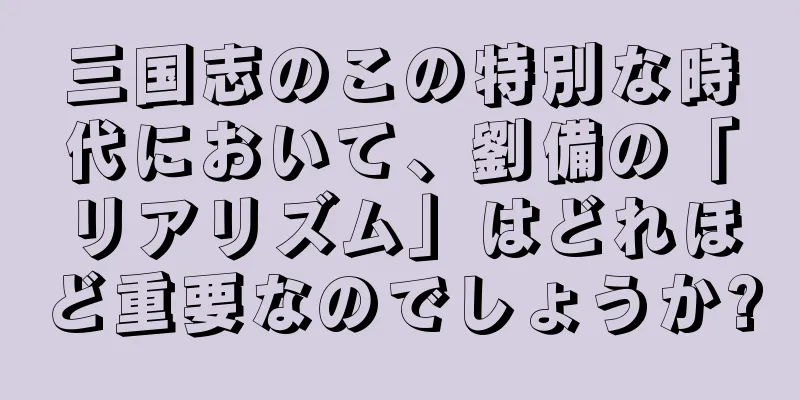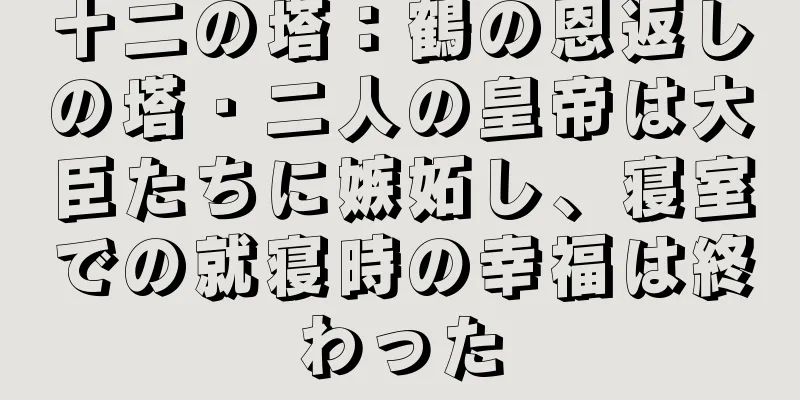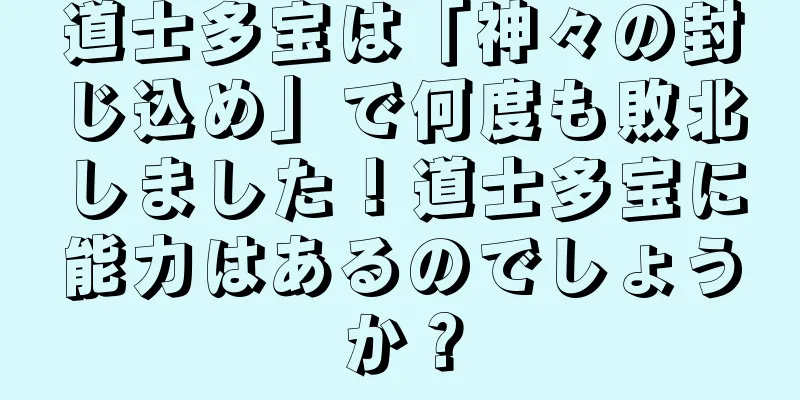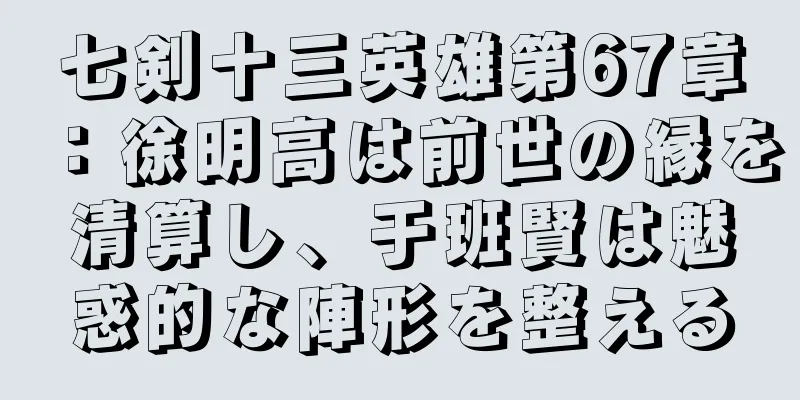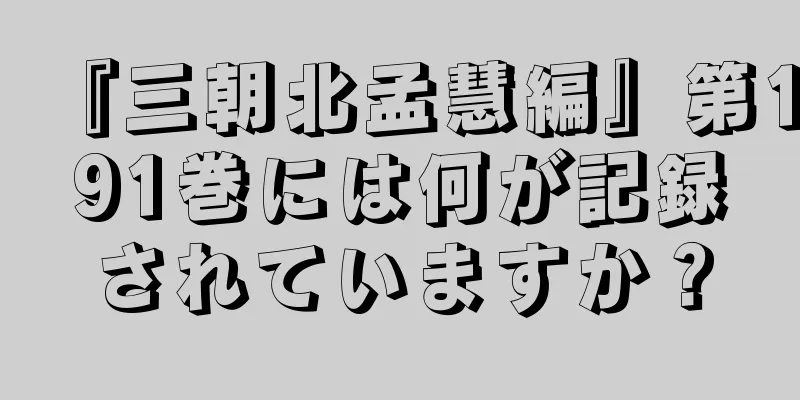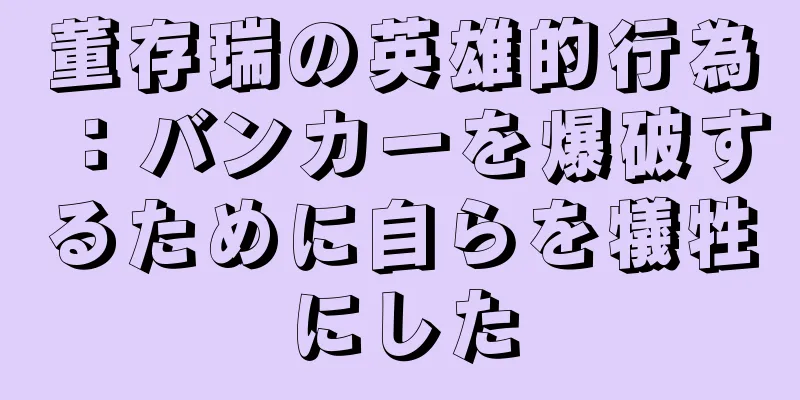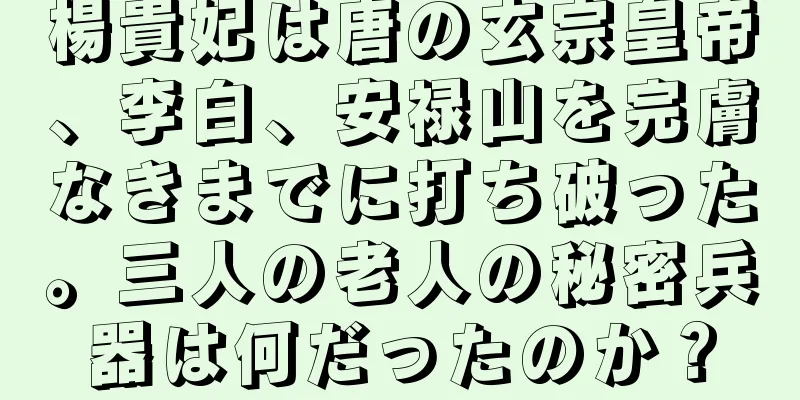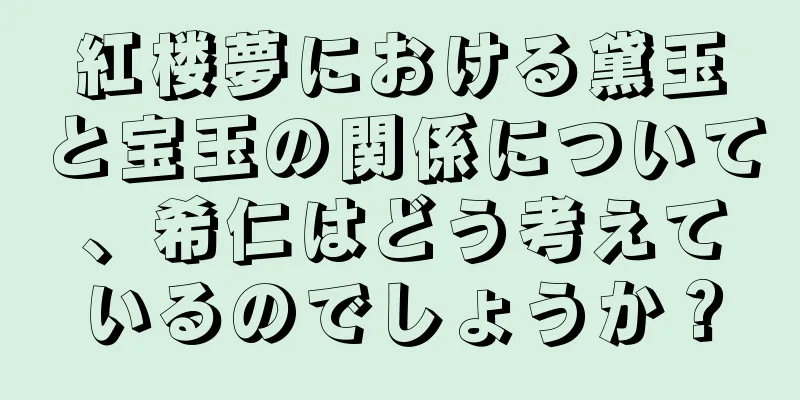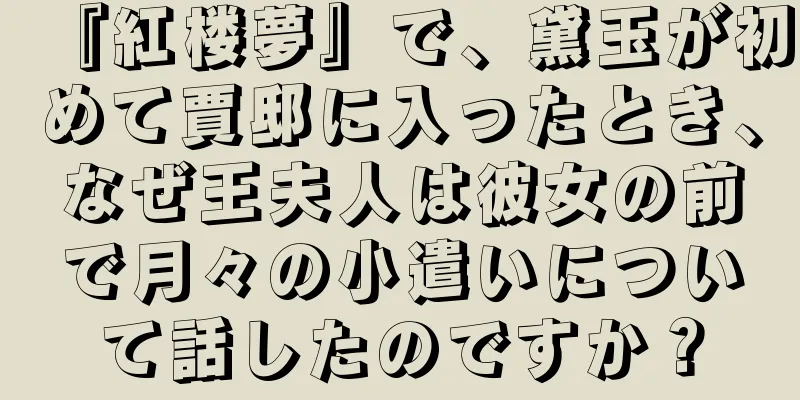諸葛亮らの死後、蜀漢はなぜ才能を失っていったように見えたのでしょうか?
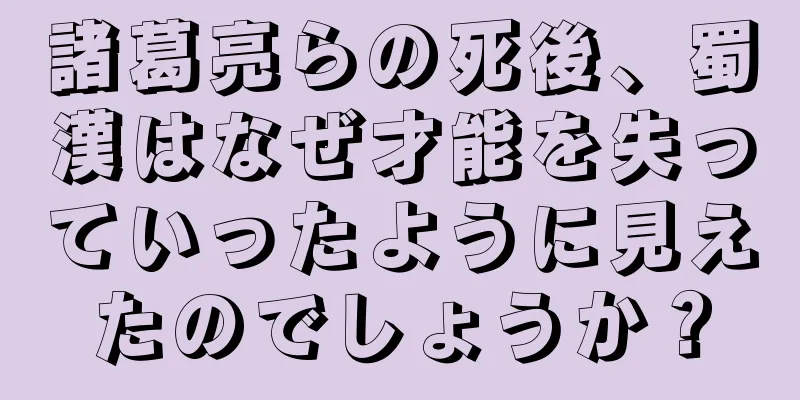
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が「蜀には名将がいない、廖華が先鋒だ」について、かつては才能に溢れていた蜀漢がなぜここまで才能を失ってしまったのか、詳しく紹介しますので、見てみましょう! 理由の一つは、『三国志演義』の影響で、他の文官や将軍についての記述が少ないからです。 人材についてだけ言えば、蜀漢は諸葛亮の死後初期ほど人材は多くなかったものの、文武両道では蔣万、費易、董雲など、軍事では姜維、呉儀、王平、馬忠などの将軍がおり、人材が失われたとは言えない。人材が乏しいという印象を人々に与えたのは、『三国志演義』の影響が大きい。 『三国志演義』には約120章あり、そのほとんどは漢末期の物語を描いている。劉備即位は第80章の物語で、この時点ですでに本の3分の2が経過しており、諸葛亮の死は第104章で、本の終わりまであと12章しか残っていない。 つまり、羅貫中は劉備の起業期と蜀漢初期の記述に重点を置き、後期の記述は比較的単純で、少々雑なところさえある。姜維を除いて、他の文官や将軍についての記述はほとんどない。ほとんどの人は三国志演義を通してこの時代の歴史を学んだため、他の文官や武将が人々に深い印象を残すことは困難でした。 例えば、呉毅と王平は相次いで漢中を守った。呉毅は魏延将軍とともに楊西で魏の将軍郭淮と費瑶を破っただけでなく、諸葛亮の死後漢中知事を務め、漢中守備の責任を負った。しかし、『三国志演義』では、彼は姜維の副将軍となった。漢中守護の王平は、興市の戦いで曹爽の10万以上の軍を3万にも満たない兵で阻止し、永安に駐屯していた鄧植、南中に駐屯していた馬忠とともに「三和侯」とも呼ばれた。 「蜀漢には名将がおらず、廖華が先鋒」と揶揄された廖華も、並の人物ではなかった。諸葛亮や姜維に従って何度も北伐し、曹魏の雍州太守郭淮を何度も破った。郭淮配下の南竿県知事有毅や広衛県知事王雲をも敗北させ、死に至らしめた。 また、羅貫中の記述によれば、蜀漢初期の諸葛亮、関羽、張飛、趙雲、馬超、黄忠はあまりにも目立ちすぎて、他の文武官僚たちの輝きを曇らせてしまったのである。そのため、諸葛亮らの死後、蜀漢は才能を失っていったようでした。 この現象の原因は、羅貫中のほかに、『三国志』の著者である陳寿にも帰せられる。廖化を例に挙げよう。蜀漢の名将である廖化の伝記は100字余りしかなく、人物紹介の簡略版に過ぎないため、廖化の軍事的功績は曹魏の史料を通じて見つけるしかなかった。実は、蜀漢だけがそうだったわけではなく、三国志演義の影響で曹魏や東呉もこのような印象を残しました。 理由2:荊州を失った結果、人材プールが大幅に減少した 諸葛亮の死後も蜀漢には多くの才能が残っていたが、実際には蜀漢が人材不足の危機に直面していたことは否定できない。蜀漢末期の文武官の経歴を見ると、彼らのほとんどが実は益州以外の地域から来た人々だったことが容易にわかる。数十年が経過し、この人々が死滅すれば、蜀漢は本当に人材不足に陥るだろう。 周知のとおり、蜀漢内部では深刻な派閥争いが繰り広げられていました。劉備は、初期に彼に従った張飛、関羽、趙雲、簡雍などの直系の子孫と、諸葛亮、馬良、馬素、黄忠、魏延などの荊州派を主に頼りにしていました。また、法正、李延、徐静、黄権、劉覇などの東州派も味方につけ、益州の地方の有力者に対しては抑圧的な態度をとっていました。 夷陵の戦いの前後で劉備直系と荊州派は甚大な被害を受けており、劉備は死の床で国内の勢力均衡を保つために荊州派を継続しつつも東州派の再利用も検討せざるを得なかった。劉備が李厳を中央護府将軍に任命し、内外の軍事を統括するよう命じたのは、こうした考慮に基づくものであったはずだ。 しかし、荊州の喪失は蜀漢の人口と経済に大きな損失をもたらしただけでなく、さらに重要なことに、蜀漢は荊郷から人材を引き抜き続ける可能性を失った。このままでは荊州出身の人材がいなければ荊州派は衰退せざるを得ず、蜀漢の人材も減少せざるを得ない。 たとえ東州派を人材補充に利用できたとしても、それは長期的な解決策にはならないだろう。結局のところ、東州派は当時劉炎が育成した勢力であり、荊州派と同様に外部勢力であり、効果的に補充することができず、時間が経つにつれて人材喪失の状況にも直面した。 実際、『二の書』にもあるように、「これらは過去数十年にわたって四方八方から集められた精鋭部隊であり、一国だけから集められたものではない」。劉備の起業期や蜀漢初期には優秀な人材が多かったが、それは劉備が幽州から益州へと勢力を拡大した結果であり、常識では全く判断できないものであった。 漢末期の混乱期には、劉備はさまざまな手段で外部から人材を集めることができたが、天下が三分され、魏・蜀・呉の統治が安定するにつれ、人材の流入も安定することになった。このように、荊州を失った後、荊州と東州の両派から人材が流出し、蜀漢の人材が衰退するのは時間の問題でした。 理由3:制度レベルの問題、人材選抜の仕組みが崩壊している 前述のように、統治が安定するにつれて、人材の流動性が比較的固定化され、人材の現地化が必須となった。曹魏の九階制もそうであったし、東呉の魯・顧・朱・張の四大家もそうであった。諸葛亮が政権を補佐していた時期には、蜀漢もある程度人材の現地化を試み始めた。 諸葛亮は実は蜀漢の人材問題に気付いていたため、人材の登用が上手なだけでなく、各党の勢力バランスを取ることにも努めていた。彼の人材登用は派閥争いをある程度放棄しただけでなく、年功よりも人材を重視し、自分より上の人を昇進させることも珍しくなかった。例えば、張毅は東呉から蜀漢に戻ったばかりだったが、諸葛亮から宰相府の武官に任命され、宰相の政務を代行する責任を負い、益州知事も務めた。 漢末期以降、推薦制度は徐々に崩壊したが、人材を育成するさまざまな手段を通じて、特定の人材を選抜することは依然として可能だ。諸葛亮の時代に「西域の民衆は皆、諸葛亮を崇拝し、その時代の人材を十分に活用することができた」からこそ、蜀漢に人材が再び急増したのである。さらに、この動きは人材を補充するだけでなく、内部の派閥争いをある程度弱め、蜀漢政権に対する益州の地方貴族の支持を獲得することもできる。 実際、蜀漢末期の人材のほとんどは、諸葛亮が摂政時代に残した政治的遺産から来ています。たとえば、摂政大臣の蒋万、費宜、馬忠、姜維、董絶はいずれも宰相府の役人でした。内廷の陸毅、范堅、馬奇、李福はいずれも諸葛亮の推薦者でした。将軍の呉毅、呉班、高祥、胡季、王平、張毅、廖華、鄧志、宗愈などは宰相府の役人か、諸葛亮の北伐の際に訓練された将軍でした。 諸葛亮の死後、蒋万と費毅は「諸葛亮の定めた規則を守り、変更せずに従う」ことができ、諸葛亮の政策を継承しました。しかし、蜀漢末期、特に陳志が宰相になってからは、「上から皇帝の指示に従い、下から宦官と結びつく」ようになり、蜀漢の政権は完全に崩壊しました。 統治が安定し、朝廷の進取の精神が徐々に薄れていくと、蜀漢末期の権力は基本的に既得権益者によって分割されました。これらの権力者は荊州出身者か、袁従の二代目の官僚でした。人材を選ぶ際には、才能よりも経歴や資格を重視しました。姜維は10回以上の北伐を指揮したが、諸葛亮の時代のような将軍の昇進は難しかった。その典型的な例が姜爾である。 まとめると、蜀漢中後期の人材衰退には『三国志演義』の影響もあったが、根本的な原因は荊州の喪失と人材選抜機構の崩壊であった。蜀漢中期には、諸葛亮が形勢を逆転させたものの、蜀漢に多くの才能を見出し、才能の衰退傾向を緩やかにした。しかし、諸葛亮の死後、蜀漢の「体制は徐々に衰退」し、人材不足にまでは至らなかったものの、人材格差はすでに現れていた。時が経つにつれ、人材衰退の傾向は逆転しにくくなってきた。 |
>>: シェ族の歴史 シェ族はなぜ自分たちを「シャンハ」と呼ぶのか
推薦する
宋代の皇帝はなぜ名誉皇帝になることを好んだのでしょうか?安全だからでしょうか?
人間の権力欲は限りないと言われている。おそらく「十分な安心感」だけが、人間に最高権力を手放させるのか...
「慈雲培中毛同年」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
裴仲茂と同じ年黄庭堅(宋代)春風が汝江を渡って吹き、客のベッドは僧侶の毛布と向かい合っています。五羊...
貧しく弱体だった清朝末期がなぜ繰り返し他国を支援したのか?
清朝末期、国家が不安定な状況に陥り、財政が赤字に陥ったとき、中国は繰り返し他国に援助の手を差し伸べた...
なぜ蜀の劉備は荊州の戦いの間ずっと関羽を無視したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清王朝はいつ建国されましたか?清王朝はなぜ清王朝と呼ばれるのですか?
清朝(1644年から1911年まで中国を統治)は満州族のアイシン・ジョロ氏によって統治されていました...
張遼と徐晃は顔良を倒せなかったのに、なぜ顔良と同じくらい有名な文周を生け捕りにしようとしたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
史公の事件 第83章:王震は真実を語り、玉山は本心を語る
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
清朝時代の宦官の最高官位は何でしたか?清朝はどのように統治されたのですか?
清朝の宦官の最高官位は何だったかご存知ですか? Interesting History の編集者が解...
ナラン・シンデとは誰ですか?ナラン・シンデは生涯で何人の女性を愛しましたか?
納蘭星徳は22歳で壬氏となった。康熙帝は彼の才能を高く評価した。納蘭は名家の出で、家系は王族と縁戚関...
李清昭の閨房での孤独な生活:「滴蓮花·暖かい雨と澄んだ風が霜を破る」
以下、興味深い歴史の編集者が、李清昭の『滴蓮花・温雨晴風破霜』の原文と評価をお届けします。興味のある...
『梁書』に記されている顧献之とはどのような人物でしょうか?顧献之の伝記の詳細な説明
南北朝時代の梁朝の歴史を記した『梁書』には、6巻の史書と50巻の伝記が含まれているが、表や記録はない...
唐代の詩の有名な詩句の鑑賞:一杯の酒を置き、白い雲を眺めると、商の風が冷たい梧桐の木から立ち上がる
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
『世界の物語の新記録: 賞賛と報酬』の第 98 記事の教訓は何ですか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。それでは、『十碩心於·賛·98』に表現され...
政治の渦から抜け出したばかりの理想の心境を追求するために、汪維は『桓家来』を執筆した。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
『紅楼夢』で宝玉に蹴られた後、西仁にどんな変化が起こりましたか?
Xiren は Baoyu の部屋の主任女中である。次はInteresting Historyの編集...