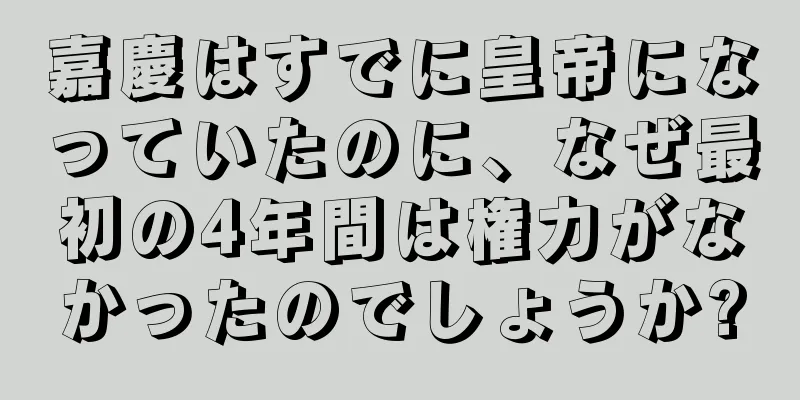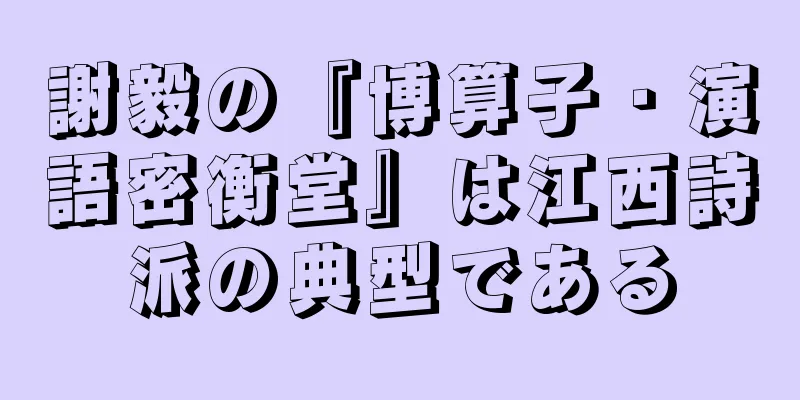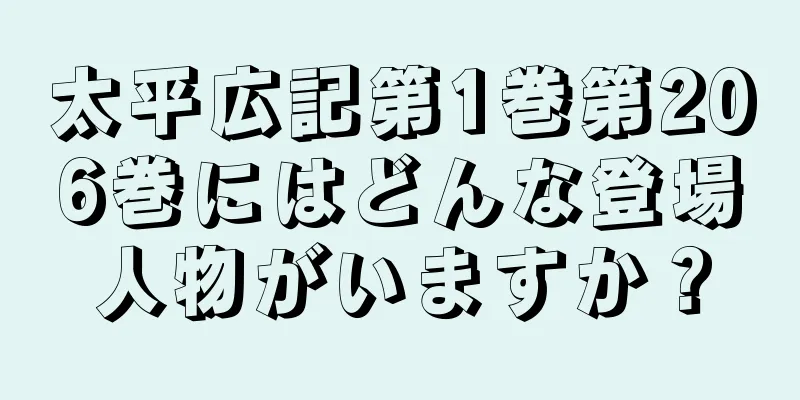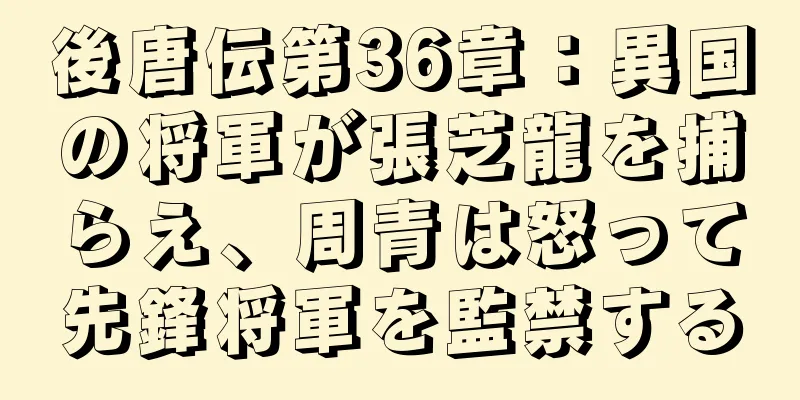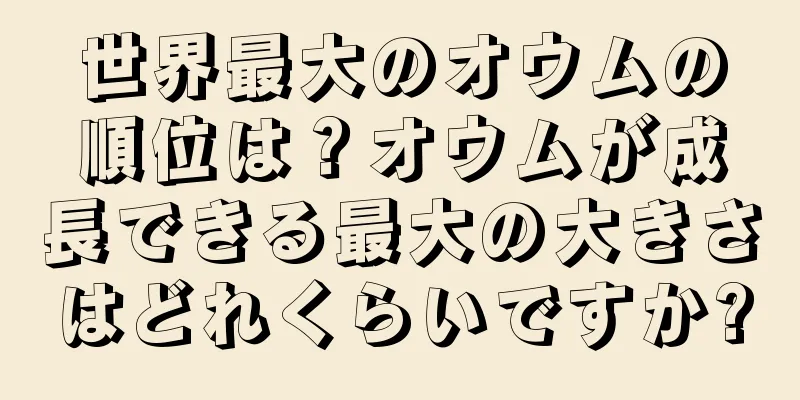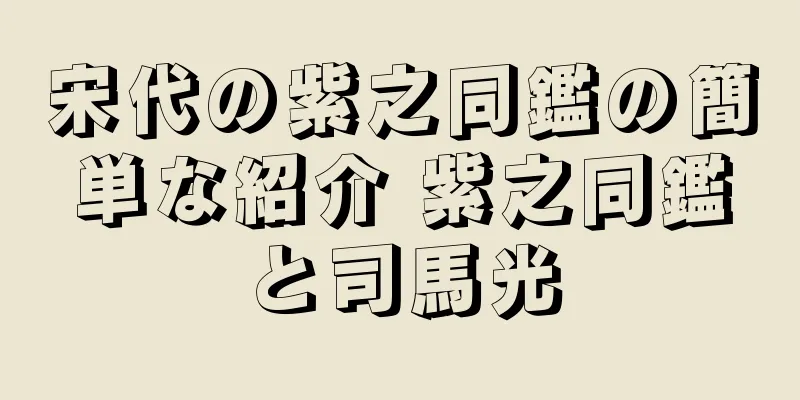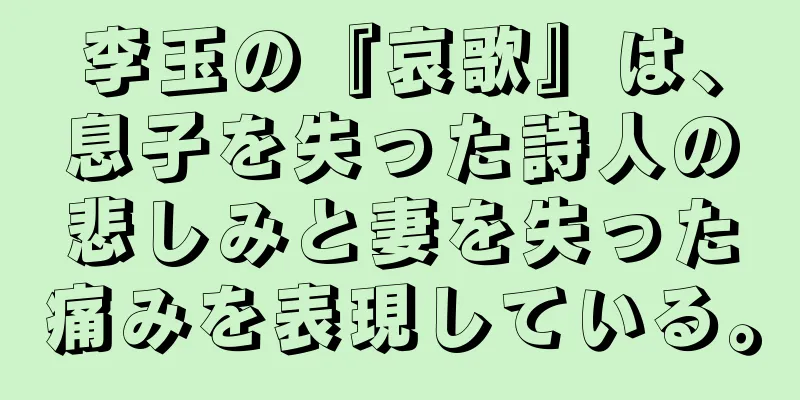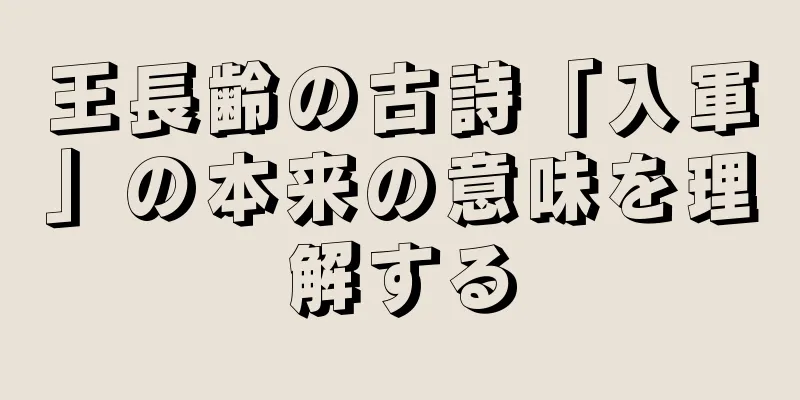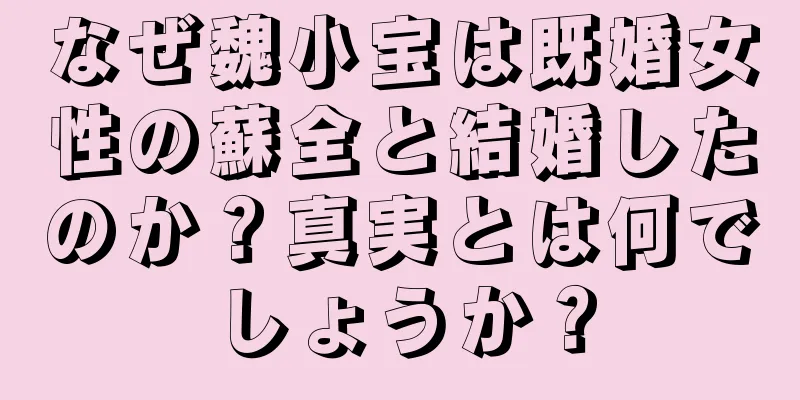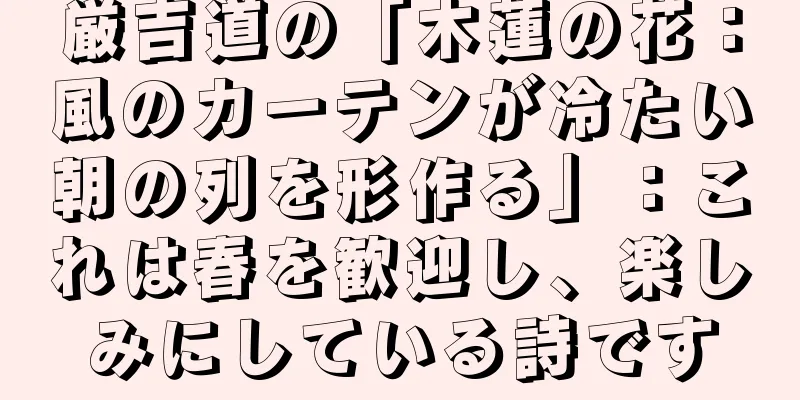清代詩鑑賞:新菊:張建陽と凌江華を韻で送る。この詩にはどんな隠喩が隠されているのでしょうか?
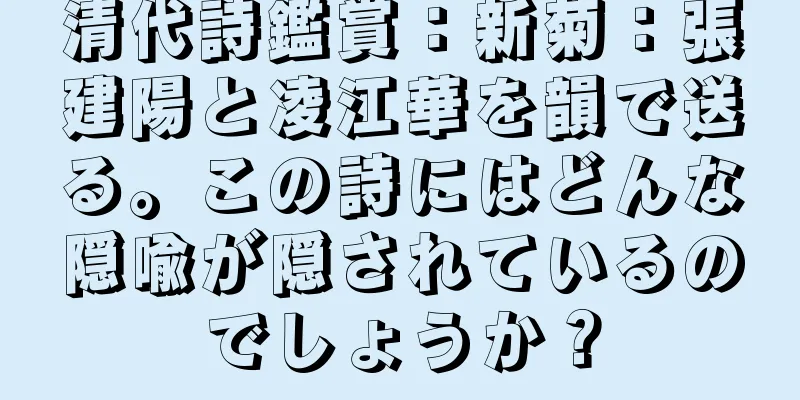
|
菊花新·韻を用いて張建陽霊江花を送る[清代] 那藍興徳、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう! 空が暗くなってきたので、旅人は心配になり、ウズラの鳴き声の方へ歩いて行きます。洞庭湖の波は広く、木の葉の下には楚の国がどこにあるのでしょうか? 折れた柳は無数にあるはずで、亭主を退出する際には笛の音が鳴り響く。南へ飛んでいくと、数羽の渡り鳥が一緒に飛んできます。 最初の部分は想像上の場面を描写しており、建陽が着任しようとしている場所の広大で荒涼とした風景を描いています。 「旅人が悲しむにつれ、空は暗くなる。」 人が旅立つとき、彼が保持できないのは恋人への憧れだけです。まるで天が容若の心の悲しみを知っていて、彼でさえそれを見続けることができないかのようです。 旅人が悲しむにつれ、夕暮れは暗くなります。 「ヤマウズラの鳴くところへ行け」、「ヤマウズラの鳴くところ」は語呂合わせで、道中の景色だけでなく、友人の特別な呼びかけ「もう行けないよ、兄さん」にも言及し、留まりたい気持ちと憧れを表現しています。 「洞庭湖の波は大きく、落ち葉の下、楚の空はどこにあるのか?」 友人がどこへ行くのか知りながら、一緒に行けないというのは、本当に悲しいことです。 詩の後半では、別れの気持ち、別れを惜しむ気持ち、離れたくない気持ちが描かれているが、別れは避けられない。容若は悲しみを慰めに変えることしかできず、友人たちはただ遠くへ行ってしまうだけで、まだ長い道のりがあり、いつかまた会えるだろうと自分に言い聞かせている。 「折れた柳は数知れず、笛の音が私に去るように促す。」そうは言っても、私はまだ去ることをためらっています。何マイルも歩いたのか、いくつのあずまやを通り抜けたのかはわかりませんが、別れを言うのが耐えられません。しかし、良いことは必ず終わりが来ます。たとえ何千マイルも離れたところに誰かを送り出したとしても、最終的には別れを告げなければなりません。友人を行きたいところへ送り出すことはできません。別れを告げるために柳の枝を折るのは古代人の伝統であり、「折る」という言葉は別れを惜しむ気持ちを十分に表現しています。しかし、彼は道中、友人の安全を心配していた。ちょうど頭上を数羽の野生のガチョウが旋回していたので、私はそのガチョウに友人を南まで案内してもらうことにしました。詩人は、旅の途中で孤独を感じた友人を慰めるため、また友人への気遣いをさりげなく表現するために、南に向かう旅に同行する「旅する雁」を巧みに創作した。最後には感情の真摯さが一気に高まり、お互いの気持ちを理解し合った友人同士の友情についてはこれ以上言う必要もなかった。 別れを描写する時、たいていの人は別れを惜しむ気持ちから始めますが、容若は違ったアプローチを取り、まるで自分の目で剣を見たかのように、旅の途中でのさまざまな暗いイメージを直接描写します。詩の後半では現実に戻り、長亭での送別会で笛の音とともに親友を旅に送り出す場面が描かれています。いつものように友達の後を追うことはできません。ただ、私の横には一羽のガチョウがいて、ずっと南へ友達と一緒に歩いています。 |
<<: 清朝詩の鑑賞:木蘭花曼:秋の初めの夜の雨が梁汾を南に流す。この詩にはどんな隠喩が隠されているのでしょうか?
>>: 清代の詩の鑑賞:西風に手を握りながら涙が流れ続ける。この詩の比喩は何でしょうか?
推薦する
劉秀の弟、劉炎の最後はどうなりましたか? 劉秀の先祖は誰ですか?
劉秀兄弟劉秀と劉燕は同じ母を持つ兄弟でした。彼らは崇陵で一緒に反乱を起こしましたが、結末はまったく異...
「忠勇五人男物語」第四章の主な内容は何ですか?
燕公は泣きながら金毛鼠の公孫策に印章泥棒を騙すよう説得した。封印が解かれたとき、五代目師匠は密かに嘆...
「紅楼夢」の趙叔母さんは人生の勝者であり、彼女の子供たちは二人とも幸せな結末を迎えた
実は『紅楼夢』の趙おばさんは人生の勝者で、子供も二人ともハッピーエンドです。なぜそう言うのでしょうか...
『紅楼夢』で、宝仔が引っ越したことを知ったタンチュンは、何と言いましたか?
宝仔は大観園の捜索について知ったとき、非常に冷静かつ賢明に行動した。 今日は、Interesting...
拓跋桂とはどのような人物だったのでしょうか?北魏の始皇帝である拓跋桂は歴史上どのように評価されているのでしょうか?
拓跋桂(371年8月4日 - 409年11月6日)は、拓跋楷、拓跋世義、拓跋一義とも呼ばれ、号は社義...
「ジャスミンの花」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ジャスミン劉勇(宋代)彼女は指輪とペンダントが付いた緑のドレスを着ており、色白の顔をしており、風に向...
『紅楼夢』の親友として最もふさわしい人物は誰でしょうか?賈宝玉には何人の女性の親友がいますか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
唐代の詩人張季はどのような背景で「虎行」という詩を創作したのでしょうか?どのように鑑賞しますか?
「虎行」は唐代の詩人、張季によって書かれた。興味のある読者は、Interesting History...
羅巴族の人々は新年をどのように祝うのでしょうか?ロバ族にはなぜ新年が3回あるのでしょうか?
羅巴族は、長い狩猟、採集、農耕活動を通じて、地元の自然環境、動植物の成長パターン、太陽の昇りと沈み、...
ファンラ蜂起はどのような成果をあげましたか?彼はどうやって捕まったのですか?
実績29日、反乱軍は杭州を攻撃し、良浙路知事の陳建と信義監察の趙月を殺害し、知事の趙廷は逃亡した。長...
『南斉書』巻五「海霊王」にはどのような歴史物語が記録されているのでしょうか?
『南斉書』は、斉の高帝元年(479年)から斉の和帝2年(502年)までの計23年間の南斉の歴史を主に...
大晦日に春聯を掲示したり、大晦日の晩餐で爆竹を鳴らしたりする以外に、どんな風習がありますか?
大晦日の習慣:大晦日のディナーを食べる大晦日の夕食は、春節期間中、どの家族にとっても最も賑やかで楽し...
冬に家に帰ることについての歴史上の詩は何ですか?詩人の郷愁を表現している
冬は寒くて荒涼とした季節です。冬に一番の暖かさは家族と一緒にいることであり、放浪する人たちの家に帰り...
北宋時代の作家、蘇哲:彼が編纂した『古史』の内容と背景の簡単な紹介
宋代の蘇哲が著し、明代万暦39年(1611年)に南京の皇書院から出版された全60巻の『古史』。次は興...
バックドアとは何ですか?裏口政策は北宋時代に始まった
今日は、Interesting Historyの編集者が「バックドア」という言葉がいつ生まれたのかに...