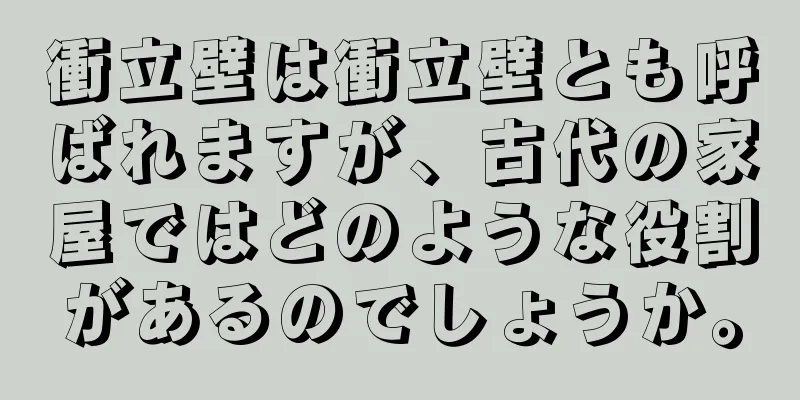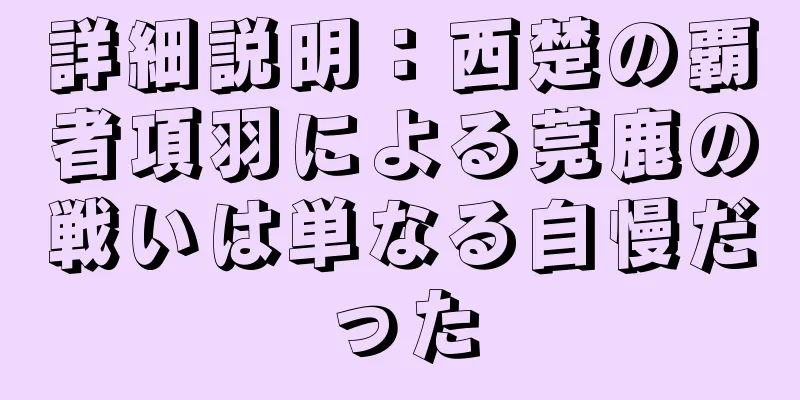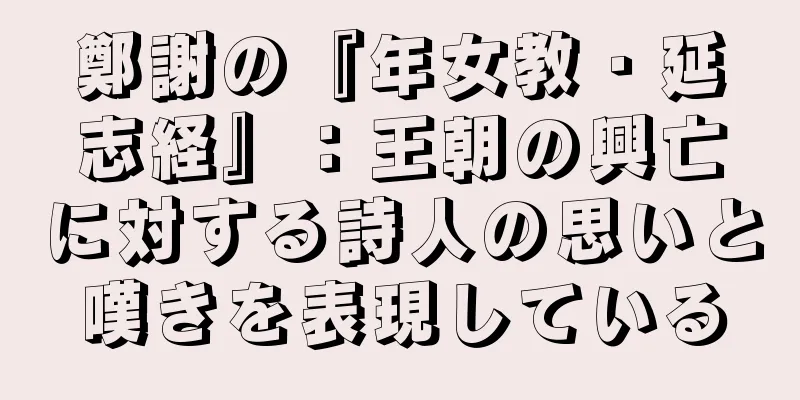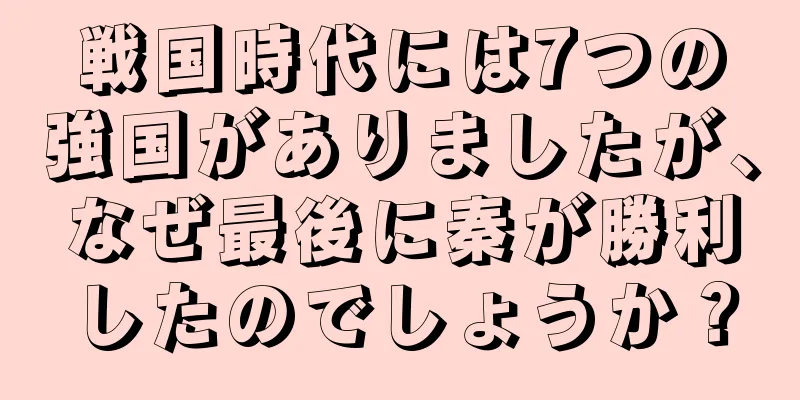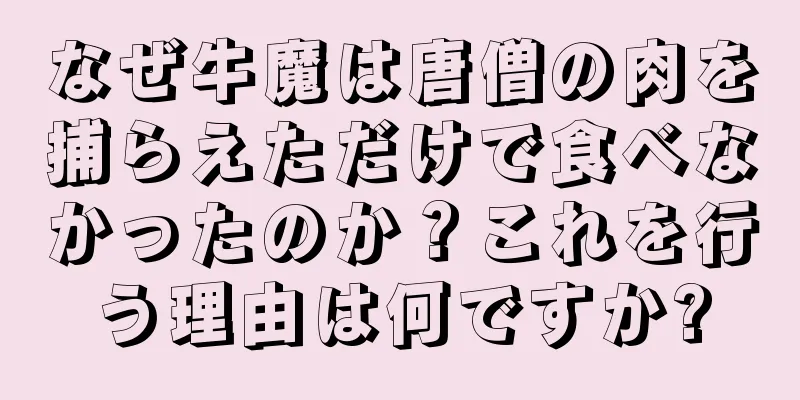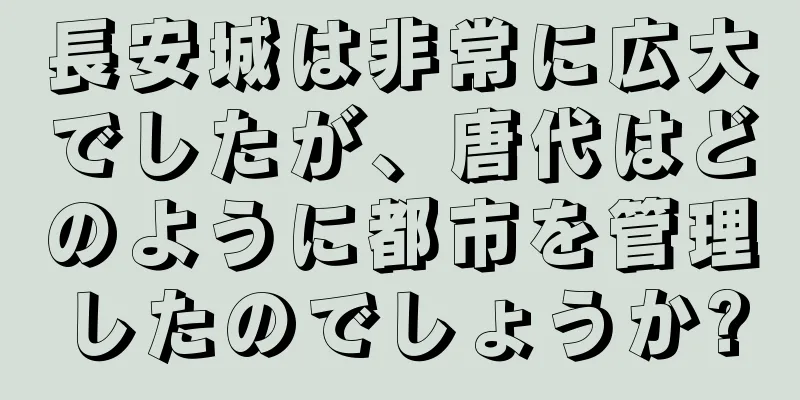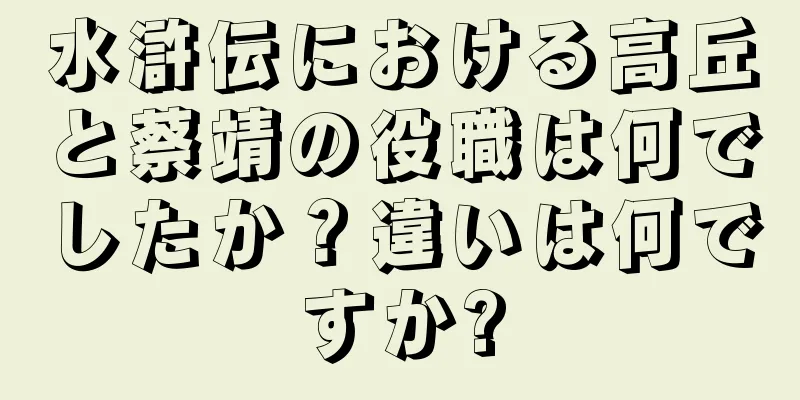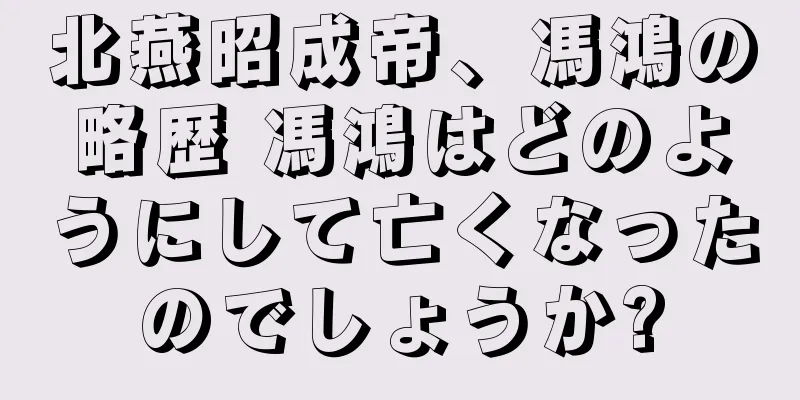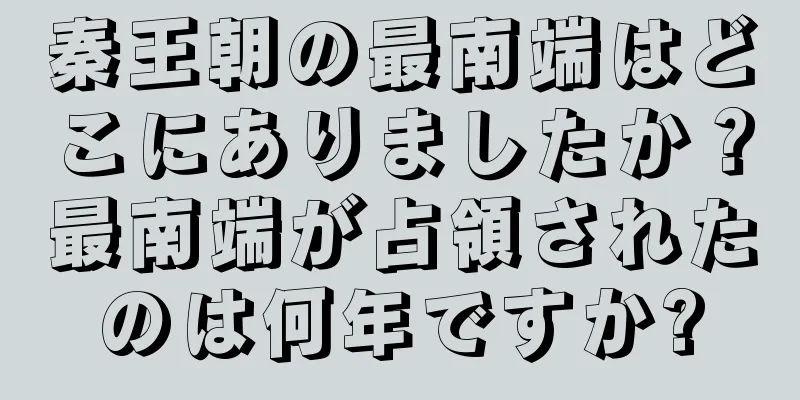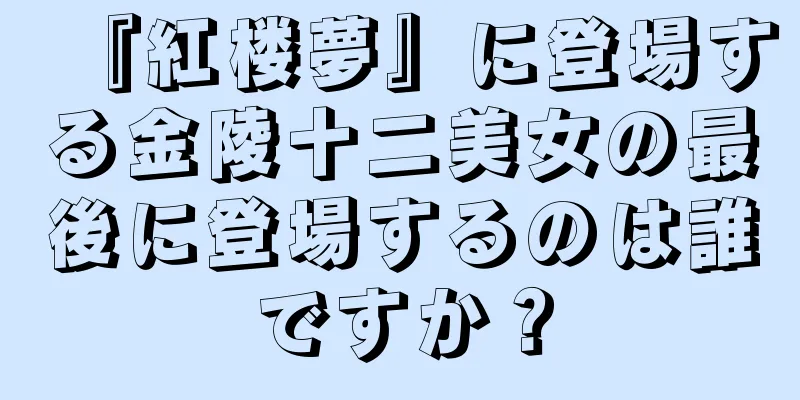ナラン・シンデの『菩薩男:日が吹き、冬も半ば』:行間に漂う優しさ
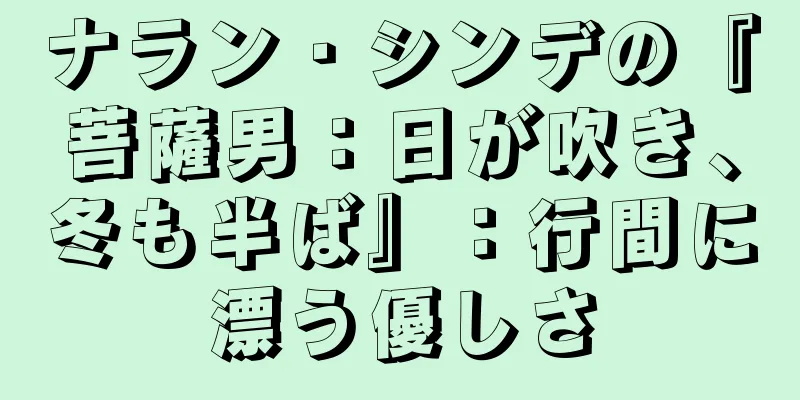
|
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家山人、元々は納藍承徳と名乗っていたが、後に宝成皇太子の禁忌を避けるために納藍興徳に改名された。満州平黄旗の一員であり、清朝初期の詩人であった。彼の詩は、場面を生き生きと生き生きと描写し、「真実」であることによって勝利を収めています。彼のスタイルは、「気品があり優雅、悲しく美しく、高尚なスタイルと広範囲に及ぶ韻、そして独特の特徴」を持っています。著書に『同智堂集』『策謀集』『飲水辞』などがある。それでは、次の興味深い歴史編集者が、Nalan Xingde の「菩薩男:日は衝撃的、冬は半ば」をお届けします。見てみましょう。 菩薩男:昼間に風が吹き、冬も半ば 那蘭興徳(清朝) 強風が国中を吹き荒れる中、冬もほぼ半分が終わり、カラスが騒ぎ立てる中、鞍は外されている。川は凍り、悲しみは深い。 焼け跡は遠くに見え、街の壁の高いところからは太鼓や角笛の音が聞こえます。明日は長安に近づきますが、私の心はまだ心配でいっぱいです。 最初の部分は、真冬の真昼に詩人が家に帰る旅の情景を描いています。「真昼に風が激しく吹き、もう冬の半ば。カラスが乱れて飛ぶように、私は鞍を降りる。」風の強い冬の日、家に帰る途中、カラスは乱れて飛び、詩人は鞍を降りて、旅の初めにしばらく滞在します。その絵は壮大でありながらも憂鬱で、言葉では言い表せないほどの憂鬱感を感じさせます。 「静彪」は冬の風の厳しさや悪天候を的確かつ鮮やかに伝えています。次の二行「川は凍り、悲しみは広大」は、冬景色の壮大さをさらに引き立て、帰路を限りない壮大さへと引き伸ばし、「長い川に沈む夕日」の荘厳な壮大さを感じさせます。 詩の後半の帰路の情景は縦にも横にも広がっています。 「遠くに焼け跡が見え、高い城壁には太鼓と角笛の音が響いている。」遠くを見渡すと、広大な平原に山火事の跡が残っており、見上げると太鼓と角笛、城壁がぼんやりと見え、家からそれほど遠くないようです。 「明日は長安に近づくが、心はまだ不安でいっぱいだ。」 明日は都に戻るが、道中の苦難は消えていない。これはナランの旅がいかに困難であったかを物語っている。最後の2行は謝条の『下都に一時赴き、新林を出て都に夜行く』から引用したもので、「川は昼も夜も流れ、旅人の心は悲しみで満たされている」という部分があり、詩全体に最後の仕上げを加える効果があります。このような悲しみは、言葉はシンプルですが意味が深く、深い思考を呼び起こす、ナランの典型的な悲しみです。 詩全体に描かれている風景は暗く、悲しく、情緒に溢れていますが、その雄大な景色には独特の魅力があります。文章は悲しく、調子は悲痛で、行間には優しさが漂い、詩人の本当の心情が表現されています。 |
<<: 李尚銀の「冬の夕暮れの隠遁」:この詩の感傷的な雰囲気が詩全体に浸透している
>>: 蘇軾の『臨江仙:冬の夜、井上の氷』:詩全体が誠実で感動的である
推薦する
黄月英が美しかったか醜かったかについて、人々の意見はどうですか?
「才男と美女は天が結びつけた縁」諸葛亮が才男であることは疑いようがないが、その妻である黄月英は実は才...
遼・金・元の衣装:元朝皇帝の衣装
中国の皇帝の冠と衣服には長い歴史があり、上流階級と下流階級、貴族と賤民の区別があり、封建階級の違いを...
北宋時代の詩人、周邦彦の「寒窓・冷飯」の原文、翻訳、鑑賞
周邦彦の「寒窓と寒食節」、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう!...
「于潔元」は李白の作です。詩の中では背中に白粉を塗っており、「元」という文字は全く見られません。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
五代十国の画家、黄居才の名画「山茜図」鑑賞
この構図の重心はほぼ画面の中央にあり、北宋時代の山水画の中軸構図に似ています。棘、シダ、竹、飛鳥など...
サルガッソー海はどこにありますか? サルガッソー海はどこから来たのですか?
サルガッソー海では、何千キロもの海がサルガッソーで覆われています。これらのサルガッソーはどこから来る...
西遊記第二章:宝陀山の龍王が宝物を献上し、龍津門の古仏が生まれ変わる
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
李毅の「秋の始まりの前日に鏡を見る」:作品全体が現実的で興味深い
李懿(746-829)、号は君有、隴西省古蔵(現在の甘粛省武威市)の出身。後に河南省洛陽に移住。唐代...
水滸伝の梁山泊の英雄108人の中で、強さで有名なのは誰ですか?
『水滸伝』では、涼山には勇敢で騎士道精神にあふれ、誰からも愛される英雄がたくさん登場します。以下の記...
甲骨文字の起源。古代文字である甲骨文字を発見したのは誰でしょうか?
甲骨文字の起源:甲骨文字は、商王朝(紀元前17世紀頃~紀元前11世紀)の文化産物であり、約3,600...
乾隆帝は雍正帝の側室の子ではなかったと言われていますが、ではその母親は誰だったのでしょうか?
乾隆帝は、本名を愛新覚羅洪麗といい、康熙帝の治世50年に生まれた。雍正帝(雍因親王とも呼ばれる)の4...
『霜空暁角:宜鎮河夜泊』を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
霜の空と朝の角笛:宜鎮河の夜の停泊(宋代)漢江で一泊。長く口笛を吹く川の歌。水中の魚や龍は驚き、風が...
『紅楼夢』で賈夫人が嬪玉を宝玉の妻にすることを支持した理由は何ですか?
賈おばあさんは『紅楼夢』の中で最も尊敬されている長老だと言えます。これは今日、Interesting...
韓湘子全伝第20章:美しい女性荘玉喬が雪山の羊飼いを啓発する
『韓湘子全伝』は、韓湘子が仙人となり、韓愈を導いて天に昇るまでの物語です。本書は、明代天啓三年(16...
岳飛伝第56章:王左が地図を提示して善悪の真実を明らかにし、曹寧が父を殺す
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...