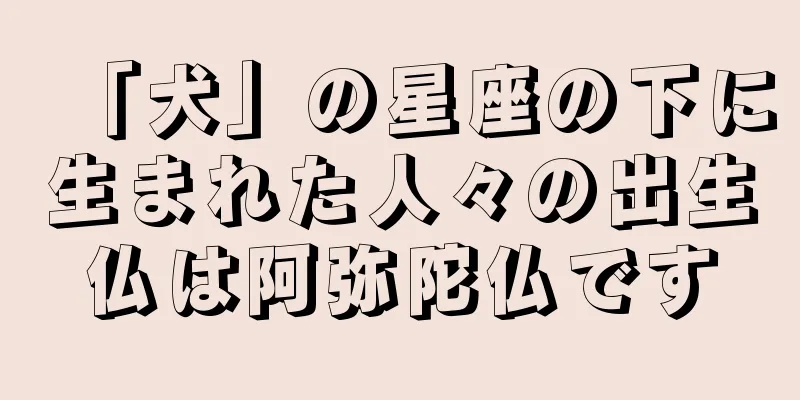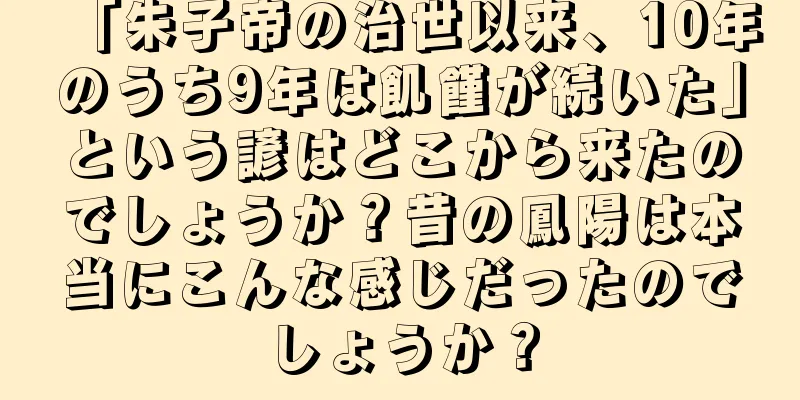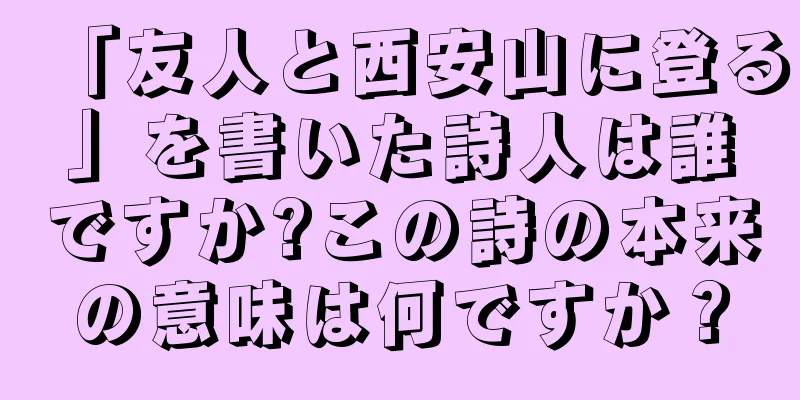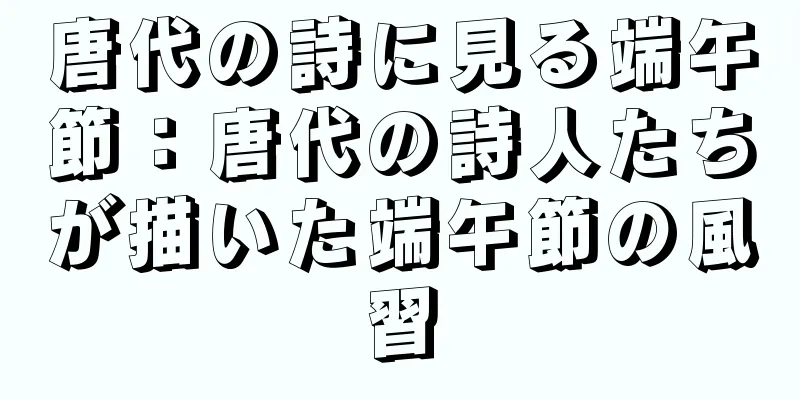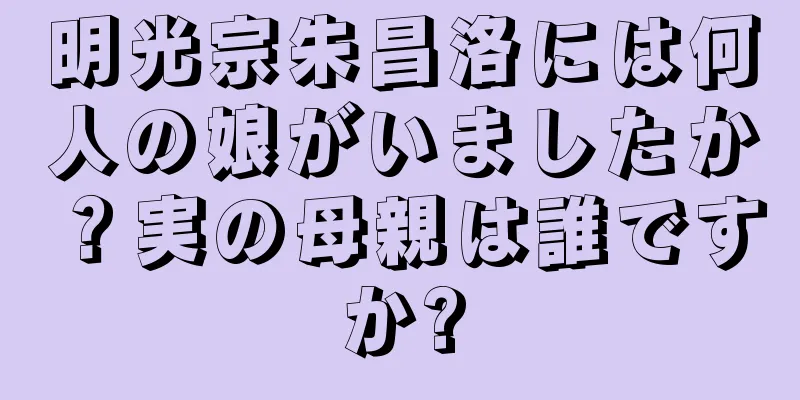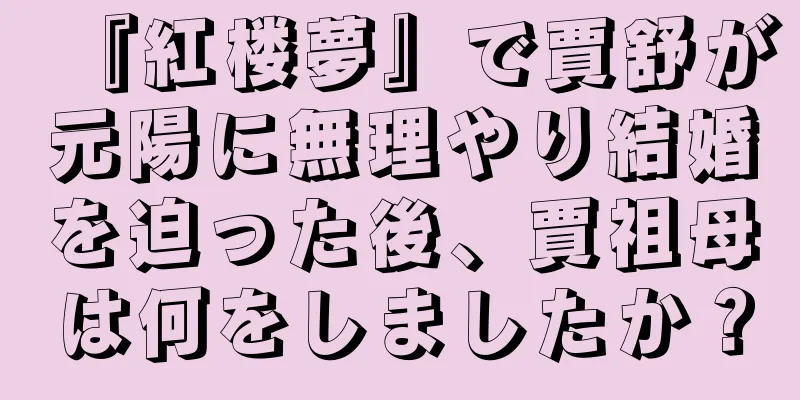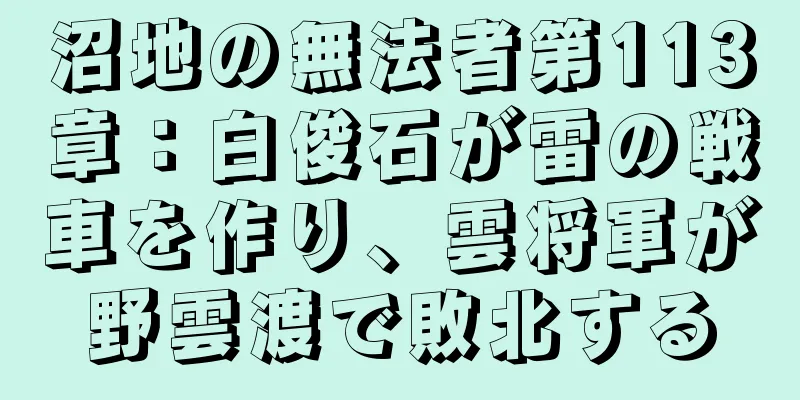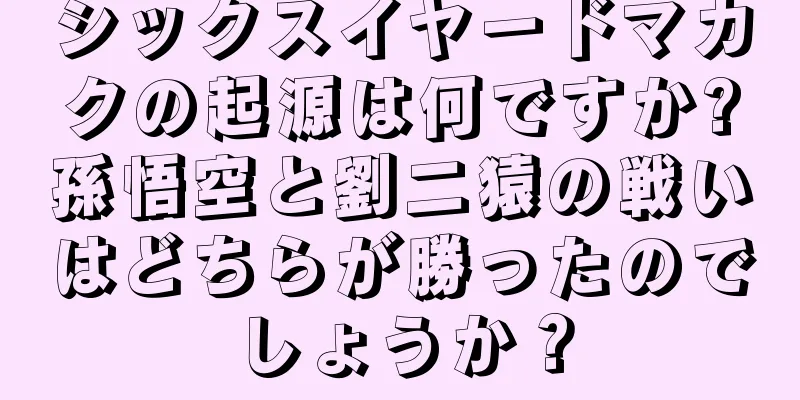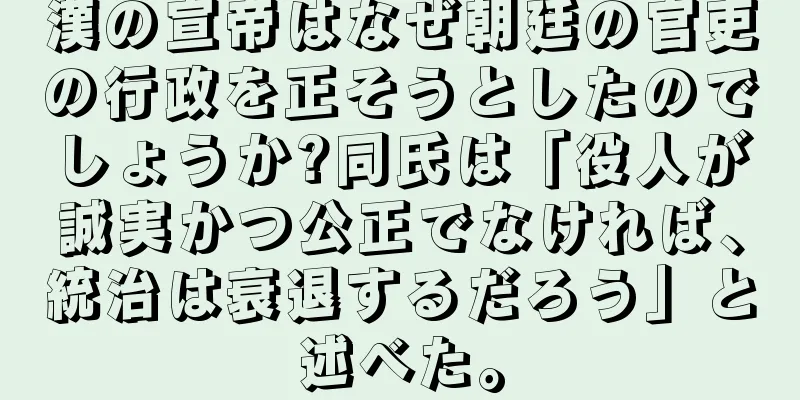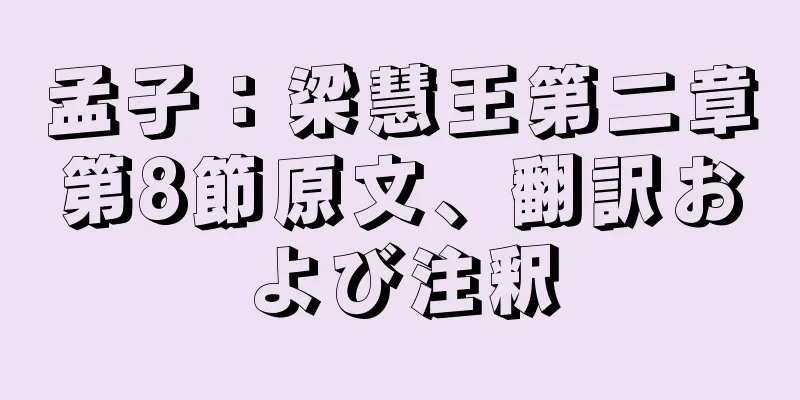李白の「自慰」は、一人でいるときの悲しみと孤独を表現している。
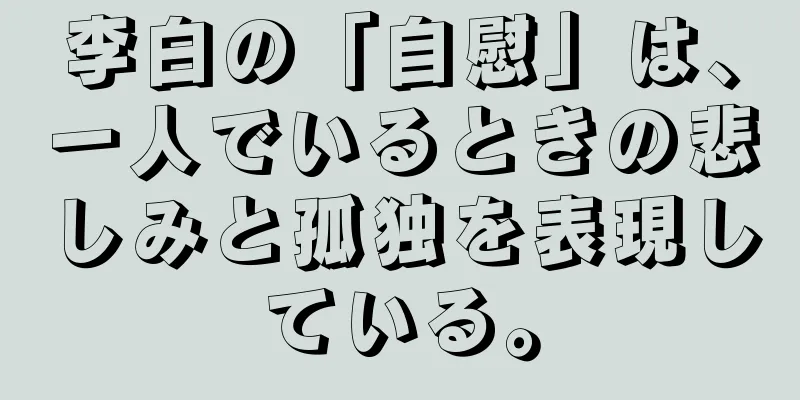
|
李白は、雅号を太白、雅号を青連居士としても知られ、屈原に続くもう一人の偉大なロマン派詩人で、後に「詩仙」と称えられました。興味深い歴史の編集者と一緒に、李白の『自慰』について学んでみましょう。 この世界では、私たちは旅人のようなものです。引き返すことのできない旅だとわかっていても、後退したり隠れたりできず、歯を食いしばって前に進むしかありません。この旅で私たちは喜びや笑いを経験しましたが、それ以上に私たちに付きまとうのは果てしない孤独の旅だけです。日没時に私たちはどこへ行くのでしょうか。私たちは歩き続け、立ち止まり続けます。 人間は社会的な生き物であり、孤独に生きることを好む人は結局のところ少数派です。しかし、この歌にあるように、「孤独は嫌だけど、誰かと一緒にいるのは怖い」。これは明らかに一種の苦痛です。この矛盾した心理現象は、最終的には、ますます多くの人々が自分の本当の気持ちに直面することを恐れるという結果につながります。たとえそれが偽りの喜びであっても、私たちは毎日自分自身のために何らかの人工的な幸福を見つけなければなりません。しかし、結局のところ、周りにたくさんの人がいるとき、私たちは最も沈黙し、笑顔はより孤独になります。 自己慰め 【唐代】李白 私はワインについては知らないが、 落ちた花びらが私の服を埋め尽くす。 酔って月明かりの下を歩いていると、 鳥はまだいるけど人はほとんどいない。 「詩仙」李白について言えば、世間の目には、彼は非常に優雅な人物であり、穏やかで、束縛がなく、心が広く、細かいことにこだわらず、自称し、自然に解放され、個人的な感情の模範となっています。もし彼の詩の中に時折表される本当の気持ちがなかったら、仮面の裏の李白はおそらく無視されていただろう。 最初の一文「お酒を飲みすぎて暗闇を感じない」は、時間の速さを物語っています。時間があっという間に過ぎていくことへの後悔は当然ありますが、その後悔はうっかりと少しだけ表に出ています。曹操には「酒を飲み歌を歌う、人生はいつまでか?朝露のようで、過ぎた日々は苦しみに満ちている」(『短歌』)という詩があり、強い不安感を内包し、無力な人生詠唱となっている。 当時の詩人の感情的背景を理解することはできませんが、人が一人でいるときに感じる悲しみや孤独を想像することはできます。 「飲み比べ」はヒントのようなもの。目立たないけれど、誰もいないときの寂しさは簡単に表に出てしまう。このとき、長く続く「仲間」、つまりワインを探すしかない。 「悩みを解消するには?ドゥ・カンだけです。」 ここでの時間は一瞬にしてワインに合う料理に変わったようだ。ワインが人をもっと悲しくさせるかどうかについては、それは草鞋のように長い間捨てられてきた。長い時間さえ忘れられるのなら、他に忘れられないものなどあるだろうか? 少しの星の光と少しの心配事なんて、些細なことなのだ。手の届かないところにあるのは、実は自分の心なのです。 2番目の文章「落ちた花びらが私の服を埋め尽くす」は、予測できない時間の流れを視覚化し、時間がゆっくりと消えていく様子をはっきりと捉えさせてくれます。薄暗い夕暮れの中、夜風がそっと吹き、木々の枯れた花がゆっくりと散っていく様は、まるで一つの時代の終わりを静かに世に告げているかのよう。 誰もが時間が漏れていることを知っていますが、それを詳細に説明することはできず、ましてやそれを保持することはできません。しかし、ここで詩人は小さな詳細から始めて、花が散るという自然界の微妙な現象をしっかりと捉えることができ、時間にも痕跡があることをはっきりと示しています。詩人は人生において思いやりのある人々ですが、感情の担い手でもあるのでしょうか? 幸せな恋人もいれば、悲しい恋人もいます。恋人は常に無情な人に傷つけられます。 最も同情的なのは、詩人が明らかに酔っていたのに、なぜ花が落ちることに気づいたのかということです。彼の心は静かで、また不本意に満ちていたからです。酒が人を酔わせるのではなく、人が自ら酔うのです。最も恐ろしいのは、人は酔っていても心は冷静であることです。そうでなければ、なぜ散りゆく花びらが詩人の心を突然躍らせ、驚かせ、「花びらが私の服を満たしている」という無力感を詠唱させるのでしょうか。結局のところ、彼は「自分自身を慰めること」ができなかったのです。 3番目の文「月明かりの下、川辺で酔っぱらって起きる」は、時間の長さを表現している。ここで「酔っぱらって起きる」という表現は、詩人の酔いを強調するために使われており、最初の文の「飲む」という言葉の反響のようだ。しかし、これは不必要な無意味な発言ではない。ここでの「酔った」は詩人の感情の重ね合わせであり、詩人が酔っていることを何度も言及しており、隠そうとしている気持ちがさらに明白になっています。 ここで詩人が隠そうとしているのは、まさに彼の心の中にある、消し去ることの難しい孤独である。彼はまるで今の恥ずかしい状態がすべてお酒のせいであるかのように、酔っていると言い続けました。彼は弱々しく謙虚な性格で、他人が信じてくれないのではないかと恐れていたため、「酔っ払った」後に自分が犯した「罪」を詳細に語った。それは、小川のそばを歩き、水面に映る月を眺めたことだ。退屈?面白くない?私が最も恐れているのは、これらの退屈で面白くないシーンさえも、今後数年のうちに見られなくなることです。 前には花があり、ここには月があります。詩人の文章では、花と月は主に美の代表です。しかし、今はどうでしょうか。花は散りゆく花であり、枯れて死んでいきます。月は流れ月であり、孤独の悲しみです。この状況と場面では、本来の美しさと優雅さがすべて背景となり、詩人が「自分を慰めること」のできない孤独と悲しみを際立たせている。 最後の文「鳥はまだいるが、人はほとんどいない」は、場面の描写であるだけでなく、出来事全体の最終的な結末を予兆するものでもある。太陽は西に沈み、疲れた鳥たちは戻ってくることを知っています。陶淵明の詩に「籠の中の鳥は昔の森を懐かしみ、池の魚は昔の池を懐かしむ」(『帰園野原』)というものがあります。ここで鳥を見ると、夢想にふけります。詩人が何の理由もなく昔の記憶を思い出すのはこの瞬間なのだろうか。過去は風とともに去ったが、この感情は彼の眉を上げるだけである。 鳥は巣に帰って行くのに、人はどこへ行くのでしょうか。「人影が少ない」とは言うものの、人の姿を見たことがあるでしょうか。詩人がもう一つの有名な詩「月の下で独り酒を飲む」の中で「花の間に酒瓶を一杯、一緒に飲む人もいない。杯を掲げて明るい月を招き入れると、影と私は三人になる」と書いたのはそのためです。この詩には花、月、酒がありますが、それでも一緒に飲む人はいません。 最初の 3 つの文が次々とクライマックスを迎える主旋律だとすると、この文は余韻を残す部分です。その瞬間、私たちの視線は巣に帰る鳥の尾を追い、夕暮れに溶け込み、一人で生きることの大きな孤独と悲しみを味わい始めた。 「夕闇が迫り、人も少なくなり、心は涙でいっぱいで、去るのが惜しい」(何恕『司馬衛告別』)ほどの寂しさや悲しみはないが、心の中にあるもどかしさや悲しみは、私を悲しくさせるのに十分である。結局、家に帰ると、そこには一人の人間と一つの影だけが残っていた。 この詩を鑑賞すると、まるで生きているかのような絵画の中にいるような強い没入感を覚えます。これは詩人の優れた文章力と関係があり、意図的であろうとなかろうと、詩人は日常の物事を利用して心の中の複雑な感情を伝え、「言葉は優雅、雰囲気は明瞭、興味は深く、意味は遠大」(呉易一『唐詩正音』)という芸術概念を生み出し、息を呑むほど美しい。自分の感情を表現するこの純粋で自然な方法を鑑賞するとき、人は詩人の感情を共有し、自分の感情を忘れ、月と花を楽しみ、酒への思いを忘れるようです! |
<<: 石大祖の「斉洛湘・春雨頌」:深く優しい感情、作者の最も優れた対象描写の作品の一つ
>>: 李白の「老老亭」には、切っても切れない別れに対する深い愛情と友情が込められている。
推薦する
『射雁英雄の帰還』で郭甫は本当に楊過が好きなのでしょうか?郭福と楊過の関係は何ですか?
今日、Interesting Historyの編集者が皆さんのために準備しました: 郭甫は本当に『神...
閻吉道のあまり知られていない作品「ヤマウズラの空:酔い覚めたら春は去っている」を鑑賞
以下、Interesting History 編集者が Yan Jidao の「ヤマウズラの空: 酔...
清朝詩の鑑賞:籠の中のオリオールズへの頌歌。この詩にはどんな隠喩が隠されているのでしょうか?
オリオールズへの頌歌 [清朝] 那蘭星徳、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします、...
漢の元帝の側室である傅昭義の息子は誰ですか?傅昭懿には何人の子供がいましたか?
傅昭懿(? - 紀元前2年)は、姓を傅といい、漢の元帝劉世の側室であり、定道公劉康の実母であり、漢の...
「魏平氏送別」をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
魏平石を送る王維(唐代)彼は将軍を追って幽仙を捕らえようと、戦場の固遠に向かって馬を走らせた。漢の使...
古代中国の武器として、斧は王朝を通じてどのような改良が加えられてきましたか?
越は古代中国の武器です。斧に似た形状をしており、主に薪割りに使用されます。また、斧の背に鉤や釘が付い...
古典文学の傑作『太平天国』:食品飲料第14巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
項羽が渡ることを拒否した江東という場所は何ですか?古代の江東は現代の江東と同じですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、項羽が渡ることを拒否した江東とは何かをお話...
チベットの衣服はいつ誕生したのでしょうか?
現在見られるチベットの衣服によく似た羌族の衣服は、金寧市石寨山の戦国時代と前漢時代の墓から出土した青...
第6章:碧峰山はすべての生き物に悟りをもたらし、武夷山の仏は悪魔を倒す
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
馬陵の戦いの立案者として、この戦いの後、孫斌の運命はどうなったのでしょうか?
周の宣王28年(紀元前341年)、魏国は漢国を攻撃するために軍隊を派遣し、漢国は斉国に救援を求めた。...
ディパンカラ仏は西遊記の武超禅師ですか?なぜ彼は唐僧とその弟子たちを助けたのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が西遊記に登...
第71章(第2部):猛将が軍隊を率いて盗賊を鎮圧し、宋の皇帝が軍隊を訓練し検査する
『水滸伝』は清代の作家于完春が口語で書いた長編英雄小説である。道光帝の治世6年(1826年)に起草さ...
「詩についての五つの詩、第2番」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
五つの詩について、その2趙毅(清朝)李白や杜甫の詩は口伝で広く伝えられたため、もはや耳に新鮮ではなく...
張飛の死後、蜀漢に勇敢な若い将軍が残されました。それは誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...