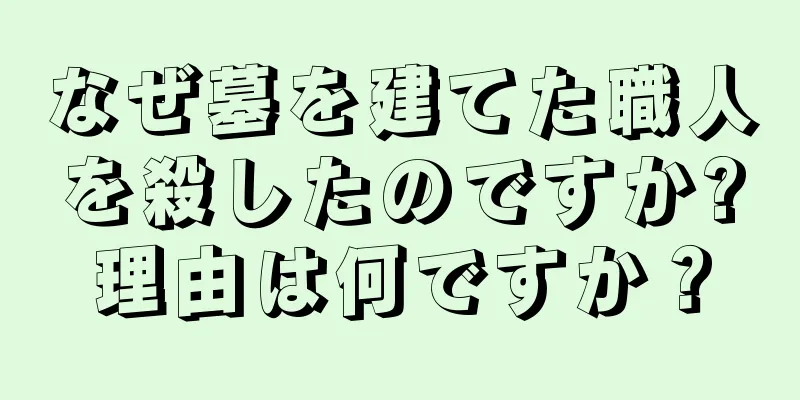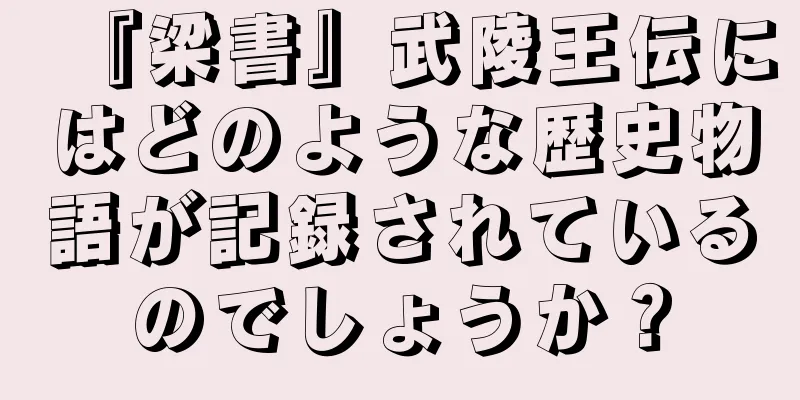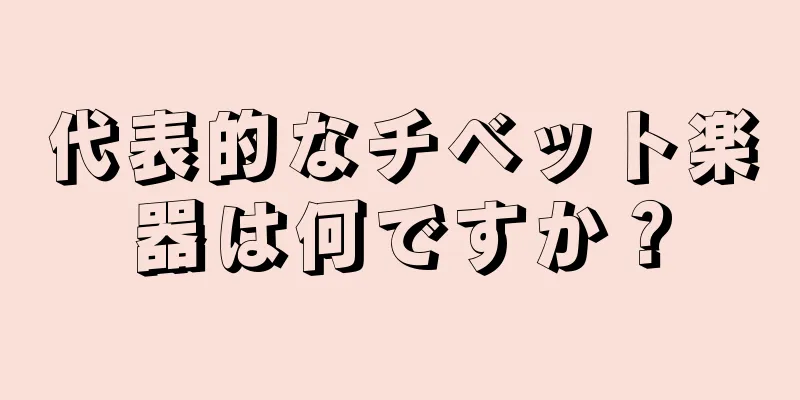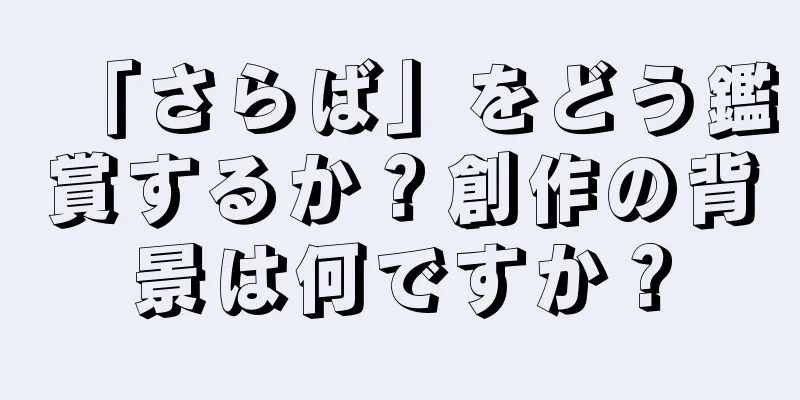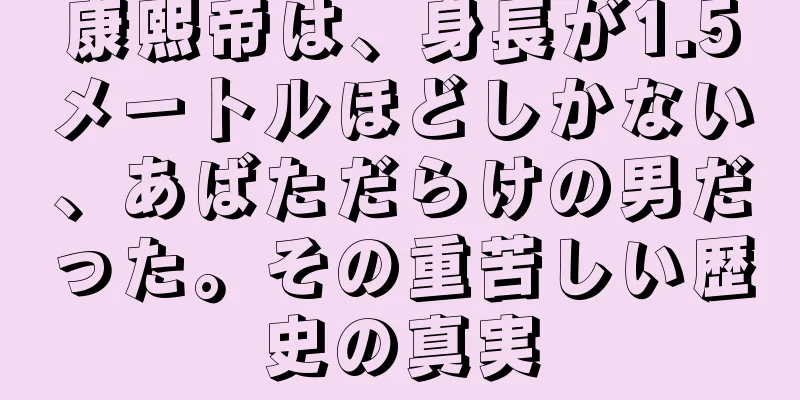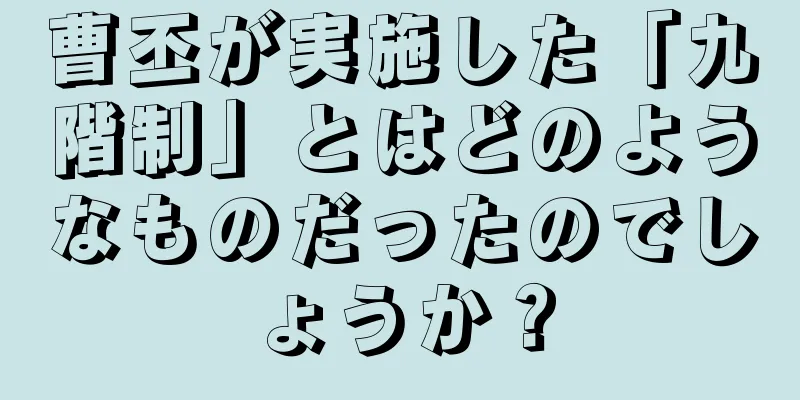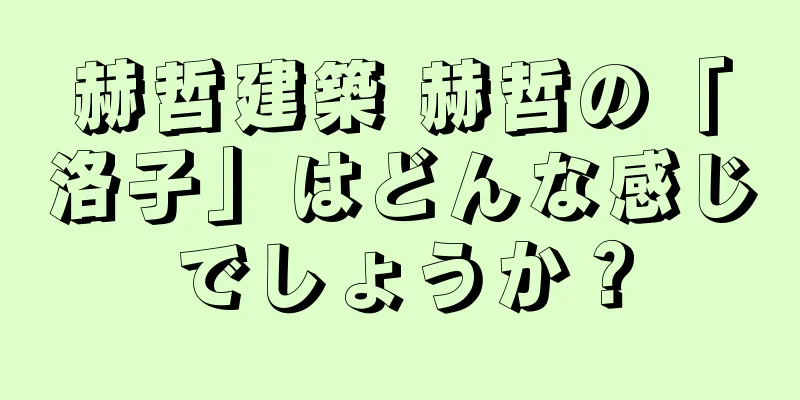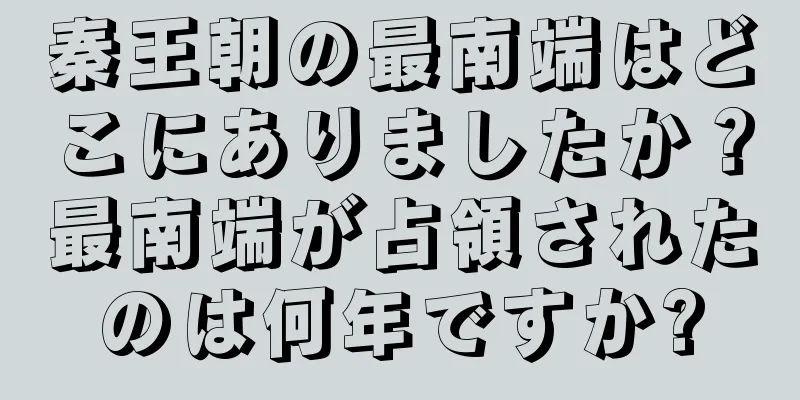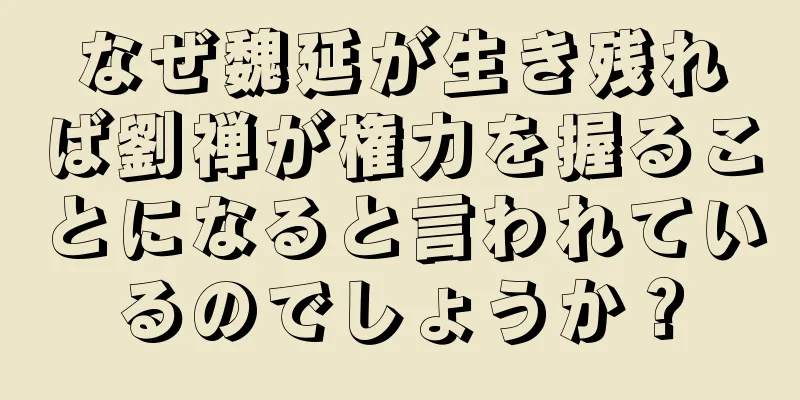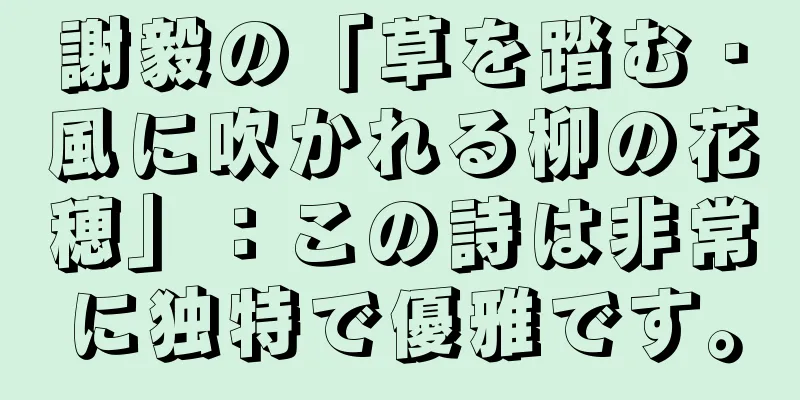周邦雁の『曼庭房・老鶯とその幼鳥』:さまざまな場面で悲しみと喜びの感情を表現する
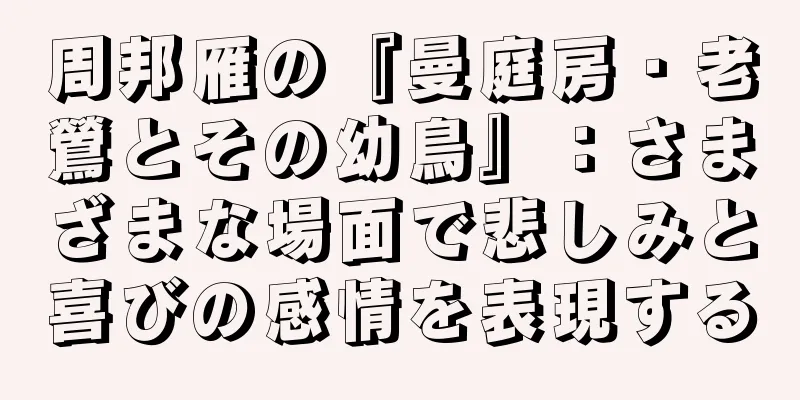
|
周邦厳(1057-1121)、号は梅成、号は清真居士、銭塘(現在の浙江省杭州市)の人。北宋時代の作家であり、宋詩の「雅流」を代表する詩人の一人。彼の作品は、優美な詩人たちの間では「本物」として長い間尊敬されてきた。昔、詩学では「最高の詩人」あるいは「詩界の杜甫」と呼ばれ、宋代に多大な影響を与えた「同世代で最も名声の高い詩人」として認められています。 「清真居士集」と呼ばれる作品集があったが失われ、現在は「片羽集」のみが残っている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、周邦彦の『曼庭房・馮老応初』をお届けしますので、見てみましょう! 風は若いコウライウグイスを老けさせ、雨はプラムを実らせ、木々は正午の日陰で丸く澄んでいる。土地は低く、山は近く、衣服は湿っていて、ストーブの煙は無駄になっている。人が静かになるとカラスやトビが楽しく遊びます。小さな橋の外では新緑がはねています。長い間欄干に寄りかかっていると、黄色い葦と渋い竹が見え、まるで九江の船に乗っているかのような気分になります。 彼らは毎年、広大な海を渡るツバメのように、修復された建物の垂木の上に止まりにやって来ます。自分以外のことは考えず、上司の近くにいてください。揚子江の南から来たやつれて疲れた旅人は、管楽器と弦楽器の慌ただしい音楽を聞くのに耐えられない。歌宴の横に、酔っ払って寝られるように枕とマットを置いておいてください。 【感謝】 宋の哲宗皇帝の元有八年、周邦厳は麗水の知事に任命された。彼は長年、県や郡の下級官吏として働いており、非常に不満を抱いていた。この詩は、さまざまな場面を使って悲しみや喜びといった理不尽な感情を表現しています。第一部はバルコニーから見た長江南側の早春の風景を描いています。最初の3文は中庭の夏の風景を描写し、次の2文は室内の雰囲気を描写し、6文目と7文目は遠景で「欄干に寄りかかる」という最後の仕上げとなり、李白の九江への配流の物語を続け、前後の文を要約している。詩の後半は、手すりに寄りかかって詩人が考えていることについてです。彼は自分の人生についてため息をつき、長期の放浪の憂鬱な気分を表現しています。前の詩のテーマを引き継いで、コミュニティのツバメを使って詩人の孤独を哀れんでいます。「自分の外のことは考えないでください」は詩人を慰める方法です。「揚子江の南の疲れた旅人」は再びため息をつくしかありません。次の部分では、詩人の気持ちをさらに説明しています。「酔って眠る」は「主人に近づく」の続きで、詩を慰めで締めくくっています。このような場面の起伏は詩全体にわたっており、作者の慰めようのない憂鬱を反映しています。著者は複雑な物語を使って自分の不満を表現している。鄭廷卓はこうコメントした。「言葉は悲しいが、激しいものではない。憂鬱と苛立ちの中に、多くの含みがある。」 |
<<: 秦観の「曼亭坊・山に薄雲」:官職に就けなかった詩人の気持ちを表現している
>>: 周邦雁の「夜飛ぶ鵲:河橋の別れ」:詩全体が別れと郷愁についてである
推薦する
「石倉書随墨堂」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
石倉樹随墨堂蘇軾(宋代)人生の悩みは、読むことを学ぶときに始まります。ですから、名前を覚えることだけ...
皮日秀の『浙江西に贈る蟹の頌歌』:詩全体に「蟹」という言葉は出てこない
皮日秀(838年頃 - 883年頃)、号は希美、号は易紹、かつて襄陽の鹿門山に住み、鹿門子とも呼ばれ...
小氷期とは何ですか? 「明清小氷期」とはどんな時代だったのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が「明清小氷期」とはどんな時代だったのかをお届けします。皆様のお役に立てれ...
『紅楼夢』では、宝仔は着飾ることを決して好みません。なぜでしょうか?
『紅楼夢』では、宝仔は着飾ることを好まなかった。なぜだろう?今日は『おもしろ歴史』の編集者が記事をお...
古典文学の傑作『太平天国』:資産第8巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
呉江での自殺の物語:項羽が呉江で自殺したとき、彼は何歳でしたか?
項羽が呉江で自殺した話: 『史記 項羽伝』によると、項羽は楚漢戦争で劉邦に敗れた後、800人の兵を率...
『十七日目に潮を見る』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
17日の潮見陳世道(宋代)果てしなく続く平らな砂の上に白い虹が架かり、翡翠のテラスの翡翠の杯は空っぽ...
『早梅花・海夏紅』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
早咲きの梅·海霞紅劉勇(宋代)海の雲は赤く、山の霧は緑です。古都は美しい景色が広がる繁栄した場所です...
「春風」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
春風王安石(宋代)ツバメは春風に乗って北へ駆けていくが、昔の山や川に戻ってきたような気がする。楊夫樹...
古代、息子が皇太子に立てられると、なぜ母親が自殺する人がいたのでしょうか?
古代の宮廷では、側室の地位は皇帝の皇位継承者を産めるかどうかに大きく関係していた。しかし、妾が息子を...
歴史家として、陳寿は関羽のイメージについてどのような真実の記録を持っているのでしょうか?
関羽が歴史上の人物として記録されている最も古く、最も信頼できる文献は、陳寿の『三国志』である。関羽に...
「過去を憂うな、人生の秋を悲しむな」とはどういう意味ですか?他に似たような古代の詩や引用文にはどのようなものがありますか?
「過去を心配せず、残りの人生の秋を悲しまない」とはどういう意味ですか? 似たような古代の詩や有名な引...
『易軒志』第4巻の主な内容は何ですか?
鄭林の復活3月4日、14年生は、江田Xiansiの騎手は、2人のメッセンジャーが彼を追いかけていると...
『紅楼夢』の賈応春の僧侶の物語はどれほど悲劇的でしょうか?結末はどれほど悲劇的でしょうか?
『紅楼夢』の悲劇は非常にユニークです。次回は、Interesting History編集長が歴史の真...
なぜ曹操は張遼と臥覇を征服しただけで、最も強大な高順を殺したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...