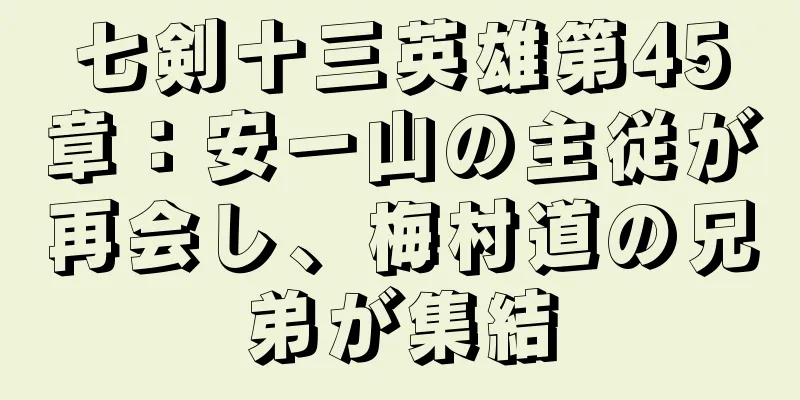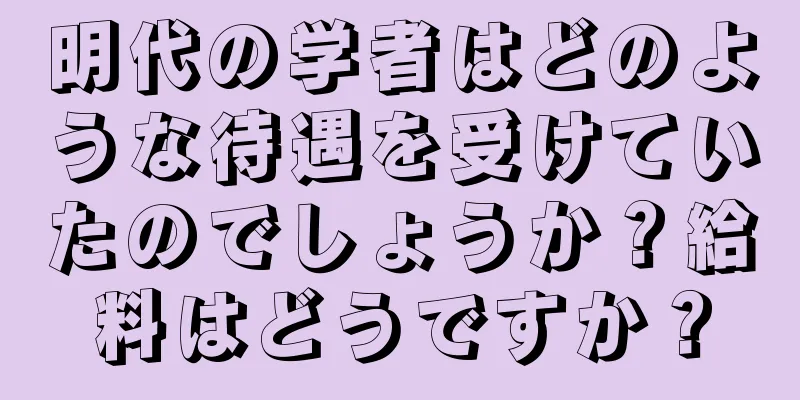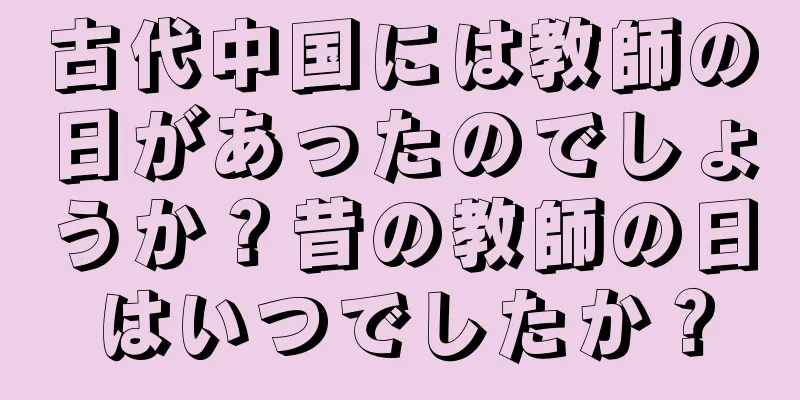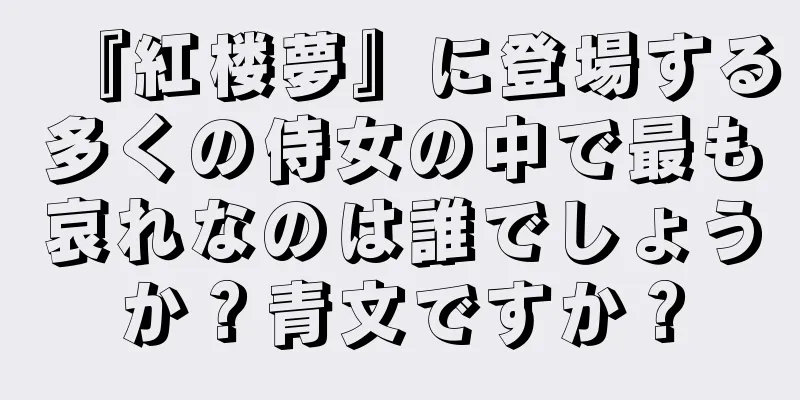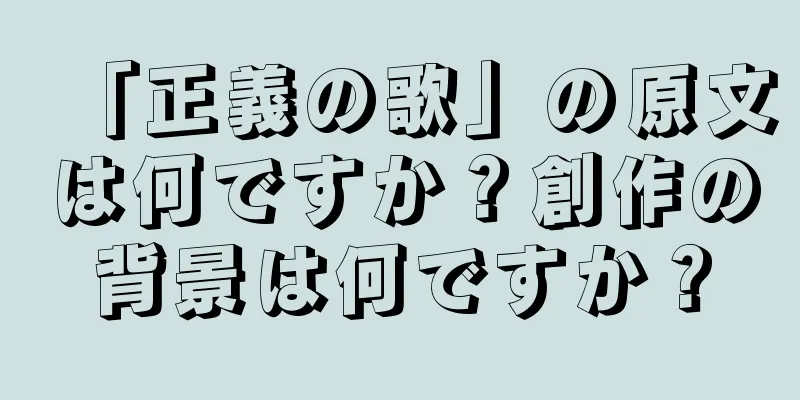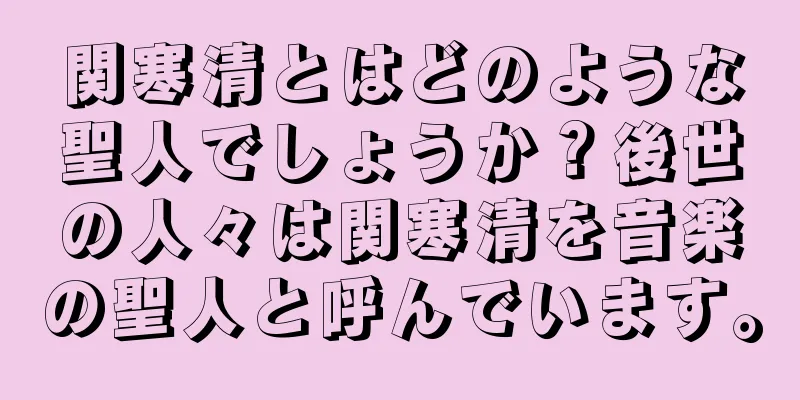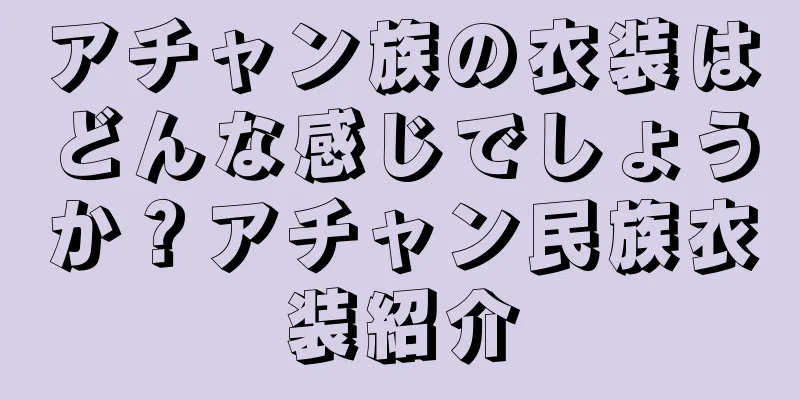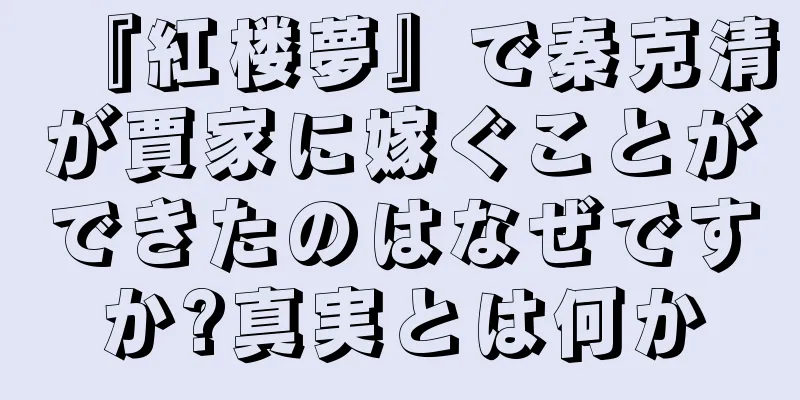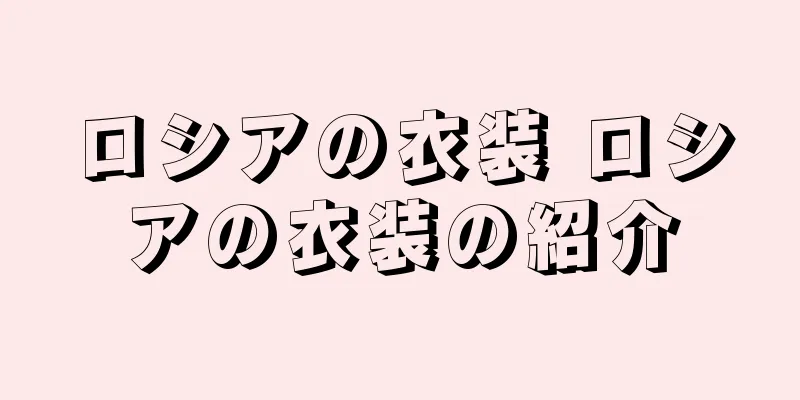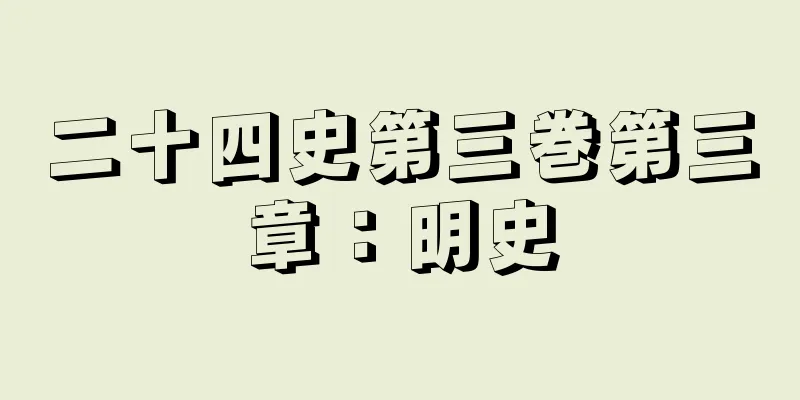当時、杜甫は洛陽から潼関を経由して華州に戻る途中で、『石鎬官伝』を執筆した。
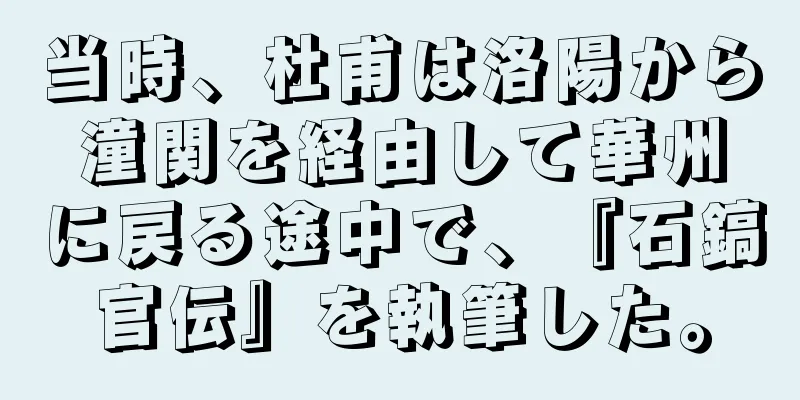
|
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人である。李白とともに「李都」と呼ばれている。河南省公県生まれ、湖北省襄陽市出身。他の二人の詩人、李商胤と杜牧(別名「小李杜」)と区別するために、杜甫と李白は総称して「大李杜」と呼ばれ、杜甫は「老杜」と呼ばれることが多い。杜甫の思想の核心は仁政の理念であり、「国王を堯や舜のように善くし、風俗を再び清廉にする」という壮大な野望を抱いていた。杜甫は生前は有名ではなかったが、後に有名になり、中国と日本の文学に大きな影響を与えた。杜甫の詩は合計約1,500編が保存されており、そのほとんどは「杜公夫集」に収められています。それでは、次の興味深い歴史編集者が杜甫の「十郝歴」をお届けしますので、見てみましょう! 【コンテンツ】: 夕暮れ時、私は役人が夜間に人々を逮捕している石昊村に到着した。 老人は壁を乗り越え、老婆は外へ出て様子を見ました。 役人はなんと怒って叫んだことか! 女性はなんと悲しんで泣いたことか! 女性のスピーチを聞いてください。「3人の息子がイェチェンに駐留しています。 一人は手紙を持って来ており、二人は戦闘で亡くなったばかりだった。 生きている者はただ生き延びようとしているだけであり、死んだ者は永遠に消え去るのです。 部屋には、まだ授乳中の孫以外誰もいなかった。 孫の母親が生きている限り、外出時に着るスカートが完成しないのです。 老婆は体が弱っていたが、夜は家に帰らせてほしいと役人に頼んだ。 河陽での急務に対応するために、彼にはまだ朝食を準備する時間があった。 「 長い夜が過ぎ、声は止み、すすり泣く声が聞こえるかのようでした。 夜明けとともに、私は老人に一人別れを告げて旅に出発した。 【感謝】: 唐の粛宗乾元2年(759年)の春、郭子儀と他の9人の軍知事は60万人の軍を率いて、鄴城の安慶緒を包囲した。しかし、統一された指揮が取れなかったため、軍は石思明の率いる援軍に全滅した。唐は軍事力を補充するために、洛陽以西の潼関の人々を強制的に捕らえて兵士として働かせ、人々に大きな苦しみを与えた。この頃、杜甫は洛陽から潼関を通過し、華州の駐屯地へ急いで帰ろうとしていた。その途中で見聞きしたことをもとに『三官』『三告』を著した。 「石鎬官」は「三官」の一人です。詩全体のテーマは、「役人が夜中に人々を逮捕する」という生々しい描写を通して、役人の横暴を暴露し、人々の苦しみを反映することです。 最初の 4 つの文は最初の段落とみなすことができます。最初の文「夕暮れに石昊村に到着」は、要点を突いて出来事を直接的に語っています。 「暮」「投」「村」という言葉は、どれもよく考えなければならず、簡単に放っておくべきではありません。封建社会では、社会秩序が乱れ、旅は荒涼としていたため、旅人は「手遅れになる前に泊まる場所を探す」のが常でした。戦争が絶えない時代ですからね!しかし、杜甫は日暮れに宿を探すため、急いで小さな村に逃げました。この珍しい光景は示唆に富んでいます。彼が幹線道路を通ろうとしなかったか、近くの町が無人で休む場所がなかったか、あるいは... 要するに、この 5 つの単語は、宿泊の時間と場所を示しているだけでなく、戦争、不安、そしてあらゆる非日常の光景を明らかにし、悲劇を演じる典型的な環境を提供しました。浦其龍は、この詩は「虎が人を捕らえる勢いから始まる」(『杜の心を読む』)と指摘し、これは「警官が夜中に人を逮捕する」ことだけでなく、最初の文の環境設定にも言及している。 「役人が夜中に人々を逮捕した」という文章が記事全体の骨子であり、その後の筋書きはすべてここから生まれている。 「兵士を募集する」「兵士を選抜する」「兵士を募集する」という代わりに、「人を捕らえる」という表現には、真実の描写で暴露し批判する意図がすでに暗示されている。 「夜」という言葉を加えることで意味がさらに豊かになります。まず、政府による「逮捕」が頻繁に行われ、人々は昼間に隠れたり抵抗したりして「捕まる」ことができなかったことを示している。次に、郡役人の「逮捕」の手段は残酷であり、人々がすでに寝静まった暗い夜に奇襲を仕掛けることを示している。同じ頃、詩人は夕暮れ時に石昊村に到着した。夕暮れから夜まで数時間が経過しており、詩人は当然その時には寝床に就いていた。そのため、詩人はその後の展開には参加せず、ドア越しにそれを聞いた。 「老人は壁を乗り越え、老婆は様子を見に行った」という2つの文章は、人々が長い間徴兵に苦しみ、昼夜を問わず落ち着かず、夜遅くになってもまだよく眠れないことを示しています。ドアの外から物音が聞こえたとき、彼らは郡役人が再び「人々を捕まえる」ために来たことを知りました。老人はすぐに「壁を乗り越えて」逃げ、老婆はドアを開けて事態に対処しました。 「役人が怒鳴ったとき、彼はどれほど怒っていたか」から「朝食を準備する時間はまだある」までの16文は、第2段落とみなすことができます。 「歴史家が叫ぶとき、なんと怒っていることか!女性が泣くとき、なんと悲しいことか!」この2つの文章は、「役人」と「女性」の間の鋭い矛盾を非常に簡潔かつ鮮明に表現しています。 「呼ぶ」と「泣く」、「怒り」と「苦々しさ」が強いコントラストをなし、「なんと」という副詞が感情の色彩を強め、郡役人の無礼で攻撃的な勢いを狼と虎のように力強く誇張し、老婆のその後の語りに悲しみと怒りの雰囲気を醸し出している。矛盾の二つの側面は、主と従、原因と結果の関係を持っています。 「なぜ女性はそんなに激しく泣いているのか?」という質問は、「役人はどれほど怒って叫んだか」という言葉によって押し出された。次に、詩人はもはや「役人の呼び声」について書かず、「女の泣き声」について書くことに焦点を当てており、「役人の呼び声」は自明である。 「女性のスピーチを聞く」は、次の部分への前置きです。ここでの「聞く」は詩人が「聞く」ことを指し、「話す」は郡役人の「怒鳴り声」に応えて老婆が「激しく泣く」ことを指します。 「演説」の内容を含む 13 行の詩は、何度も韻を変えており、多くの紆余曲折がはっきりと示されており、郡役人の多くの「怒りの叫び」と質問を暗示しています。この 13 行の詩を読むとき、郡の役人が注意深く聞いている間に「老婆」が一気にそれを言ったとは思わないでください。実際、「役人はなんと怒って叫んだことか!女性はなんと悲しんで泣いたことか!」という叫びは、事件の初めに起こっただけでなく、事件の最後まで続いた。 「葉城を守る三人」から「死者は永遠に消え去る」までが最初の転換点です。郡の役人が尋問され、苦情を申し立てられたのはこれが初めてだったと想像できる。これに先立ち、詩人は「夜中に人を捕らえる役人がいる」という一文を使って、虎が人を捕らえるような郡役人の凶暴な力を表現していた。 「老婆が探しに出た」とき、男は駆け込んであちこち捜したが男は見つからず、無駄に襲い掛かった。そこで彼は怒鳴りました。「あなたの家族の男たちはどこにいるのですか? 全員私に引き渡してください!」老婆は泣きながら言いました。「私の3人の息子は皆、イェチェンを守るために軍隊に行きました。息子の一人が、他の2人の息子が死んだという手紙を持ってきました!」彼女は泣きながら、おそらく郡書記が信じなかったため、手紙を取り出して郡書記に見せました。つまり、「生きている者は生き延びることしかできず、死んだ者は永遠に消え去る」のです。この状況は非常に同情的であり、彼女は郡役人の同情を勝ち取り、慈悲を示してもらうことを心から望んでいます。予想外に、郡の役人は再び激怒した。「あなたの家族には他に誰もいないのですか? すぐに渡してください!」彼女はこれについて文句を言うしかなかった。「部屋には他に誰もいません。まだ母乳を飲んでいる孫だけです。」この2つの文は一息で言ったのではなかったかもしれない。なぜなら、「他に誰も」はその後の答えと明らかに矛盾していたからだ。合理的な説明は、老婆が最初に「もう家には誰もいない!」と言ったことです。この瞬間、義理の娘に抱かれてどこかに隠れていた小さな孫は、轟音に驚いて泣き出し、口を覆っても無駄でした。そこで県の役人は彼女を捕まえて、「よくも嘘をついたな!泣いている子供がいたじゃないか」と脅した。老婆は「私には孫しかいない!まだ母乳を飲んでいるし、とても小さいんだ!」と答えるしかなかった。「誰の乳を飲んでいるんだ?母親がいるはずだ!私に引き渡せ!」 老婆が心配していたことがついに起こった!彼女は「孫には母親がいます。夫は鄴城の戦いで亡くなり、子供に母乳を与えなければならなかったので再婚しなかったのです。服がぼろぼろなのは残念です。どうやって人に会えばいいのでしょうか?どうか優しくしてください!」と説明するしかなかった。(「孫の母はまだ出かけておらず、出入りするスカートもまだありません」という2つの文章は、一部の本では「孫の母はまだ出かけておらず、役人に会うスカートもまだありません」と訳されており、県の役人が彼女に出てくることを望んでいたことがわかります。)しかし、県の役人はそれでも諦めませんでした。老婆は、未亡人となった嫁が逮捕され、孫が餓死するのではないかと恐れ、立ち上がってこう言った。「私は年老いて体が弱っていますが、夜は役人について帰りたいです。朝ごはんは用意して、河陽の急務に対応できます。」老婆の「演説」はここで終わり、県役人がしぶしぶ同意し、「怒鳴り散らす」のをやめたことが示された。 最後の段落はたった 4 つの文しかありませんが、冒頭の内容を反映し、登場人物全員が登場し、出来事の結末と作者の気持ちが書かれています。 「長い夜が過ぎて、人の声は止み、かすかなすすり泣きが聞こえるようだった。」これは老婆が連れ去られ、嫁が静かに泣いていたことを示している。 「長い夜」という言葉は、老婆の度重なる泣き声と郡役人の脅迫の長い過程を反映しています。 「聞いたような」という言葉は、一方では、夫が戦争で亡くなり、姑が「捕虜」になったことに対する嫁の涙を表現しています。他方では、詩人が心配して注意深く聞き、一晩中眠れなかったことも示しています。 「夜明けに私は老人に別れを告げて一人で旅に出た」という2行が記事全体を要約しており、物語には限りない愛情が込められています。想像してみてください。昨日の夕方、彼女がチェックインしたとき、老人と老婆の両方が彼女を迎えに来ました。しかし、一晩後、老婆は誘拐されました。嫁は泣き崩れ、逃げて戻ってきた老人に別れを告げることしかできませんでした。老人はどう感じているのか?詩人は何を考えているのか?読者の想像の余地を残している。 邱昭澗は『杜少陵集詳注』でこう述べている。「昔は兄弟のうち一人だけを軍隊に送っていたが、今は老人や虚弱者も含めて健常者は皆追い出されている。詩にこうある。三人辺境に送られ、二人が死に、孫は乳を飲ませ、嫁はスカートをはかず、義父は壁を乗り越え、妻は夜そこに行く。一家で父と息子、兄弟、祖父母と孫、叔母と嫁が皆このように残酷に扱われ、民は悲惨な暮らしをしている!当時は唐代も危うかった!」つまり「人民は国の根本」であり、人民がこのように扱われると君主の王位も危うくなるということだ。こうした状況に直面して、詩人の杜甫は現実を美化せず、政治の闇を正直に暴露し、「一部の官僚が夜中に人々を逮捕している」と叫んだが、これは高く評価されるべきことである。 芸術的表現の面から見ると、この詩の最も顕著な特徴はその簡潔さです。陸世勇は「なんと長い物語だろう!言葉はなんと簡単なのだろう!」と褒めた。これが彼の言いたかったことである。記事中の文章はどれも叙情的で、叙情的または議論的な言葉は一切使われていないが、実際には著者は物語を通じて自分の感情を巧みに表現し、非常に強い好き嫌いと非常に明確な傾向をもってコメントしている。賞賛と批判を物語に取り入れることで、多くのインクと紙を節約できると同時に、概念化の感覚も排除されます。この詩では、答えの中に疑問を隠すという技法も使われています。 「役人はなんと怒って叫んだことか! 女性はなんと悲しんで泣いたことか!」 対立の双方の立場をまとめた後、著者は「女性」に焦点を当て、「役人」についてはもう書かない。しかし、老女の「発言」の転換点と事件の結末には、「役人」の残忍さと横暴さがほのめかされている。詩人は編集も非常に上手で、物語の中には無限の意味が隠されています。詩の冒頭では、宿舎についての一文だけが述べられており、その後すぐに「役人が夜中に人々を逮捕する」というテーマに移ります。例えば、記事には「老人は塀を乗り越えた」とだけ書かれていて、いつ帰ってくるのかは書かれていない。「すすり泣く声が聞こえたようだ」とだけ書かれていて、誰が泣いているのかは書かれていない。老女は「役人に夜に帰るように頼んだ」とだけ書かれていて、連れて行かれたかどうかは書かれていない。しかし、「私は一人で老人に別れを告げた」という一文が記事の始まりと終わりを言い表しており、物語的かつ叙情的で、老人は家に帰り、老女は連れて行かれた、そして涙を飲み込み、大声で泣く勇気がなかったのは、当然、子供に乳を飲ませていた若い未亡人だった、と読者に伝えている。詩人の文章が簡潔で洗練されているからこそ、120語の詩全体が、驚くほどの広さと深さで人生における矛盾や葛藤を反映しており、非常に価値がある。 |
<<: 杜甫は親戚や友人に助けを求め、茅葺き屋根の家を建てて「秋風に倒された茅葺き屋根の歌」を書いた。
>>: 詩経・周宋の「在山」の意味は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
推薦する
張岱散文集『西湖を夢みて』第3巻・西湖中路・秦楼全文
『西湖夢想』は、明代末期から清代初期の作家、張岱が書いた散文集で、全5巻72章から成り、杭州周辺の重...
春秋戦国時代、古代の人々は夏を乗り切るためにどのような衣服を着るようになったのでしょうか。
熱風が吹き、どんどん暑くなってきました。道は焼けつくほど暑い。木の下に隠れても仕方がない。暑すぎて友...
唐代の詩『咸陽雨』文廷雲の鑑賞
【オリジナル】咸陽雨(1)咸陽橋⑵には雨が激しく降り、漁船は空に無数の霞んだ点⑶によって隔てられてい...
張燕の「街連環・楚江孔湾」:この詩はガチョウを讃えているが、ガチョウにこだわらず、空気を清めている。
張炎(1248年 - 1320年頃)は、字を叔霞といい、玉田、楽暁翁とも呼ばれた。彼は臨安(現在の浙...
「秦元春・孟風若」は南宋時代の劉克荘が書いた作品です。劉克荘は亡くなった友人を懐かしみ、心の中で悲しみを感じていました。
劉克荘は、字を千福、号を后村といい、南宋時代の詩人である。彼の詩は江湖詩派に属し、辛其記の影響を受け...
『女仙秘史』第10章:東家荘の本物の蘇娥は妹の斌山門を認識し、偽の端女は魔神を鎮圧する
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
『紅楼夢』では、林黛玉と石向雲のどちらの地位が高いのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
明代の数秘術書『三明通会』第4巻:温進
『三明通卦』は中国の伝統的な数秘術において非常に高い地位を占めています。その著者は明代の進士である万...
秀雲閣第117章:説得されて都に戻るも、貴族の地位を享受し、ファンタジーの世界に夢中になっている
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
古代人の飲酒習慣はどのようなものだったのでしょうか? 「紅楼夢」の日々の飲酒記録!
今日は、Interesting Historyの編集者が古代人の飲酒習慣についての記事をお届けします...
牛飼いと織女の物語とは何ですか? 七夕祭りはどのようにして始まったのですか?
牛飼いと織女の物語を知らない読者のために、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をします。読み続けてくだ...
『崔濮陽吉忠兄弟の山中情』を鑑賞するにはどうすればいいでしょうか?創設の背景は何ですか?
崔濮陽兄弟 吉忠千山星王維(唐代)秋の景色が素晴らしく、池のほとりでくつろいでいます。広大な西部の森...
「彭公安」第306章:英雄を解放し、義理の兄弟である周百玲をゲストに迎える
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
ディアン・ウェイが一流の達人と対峙したとき、彼はどのようなパフォーマンスを発揮するのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「紅楼夢」の西人はなぜ冷静さを失い、青文をクズだと罵ったのでしょうか?
『紅楼夢』の西人はなぜ冷静さを失い、青文を「雌犬」と罵ったのでしょうか? これは多くの読者が気になる...