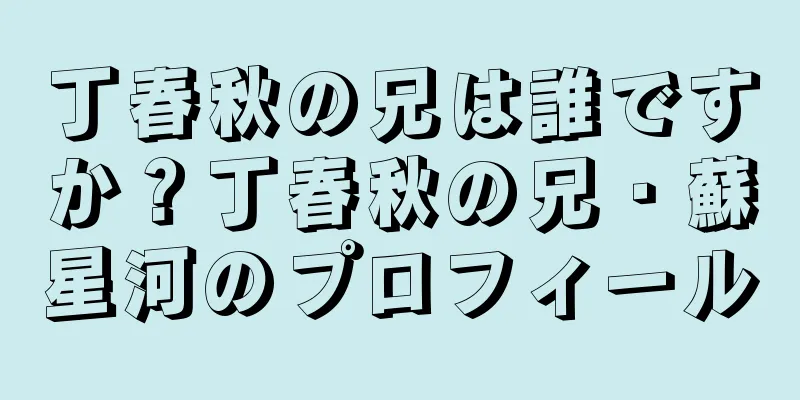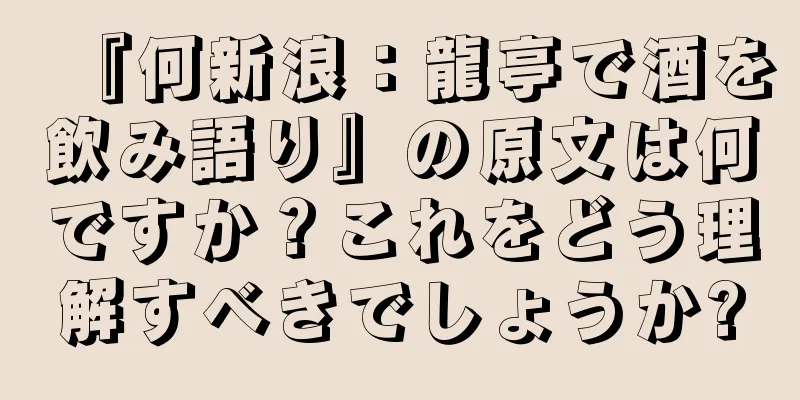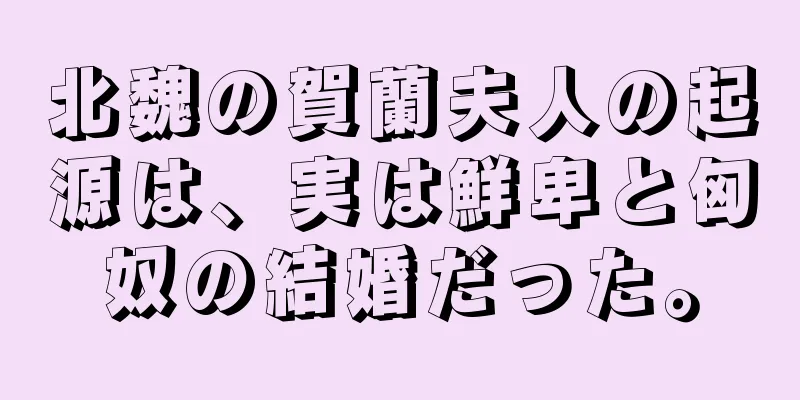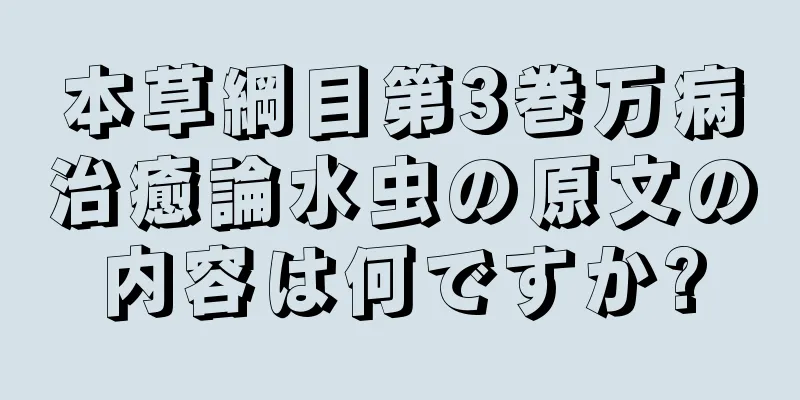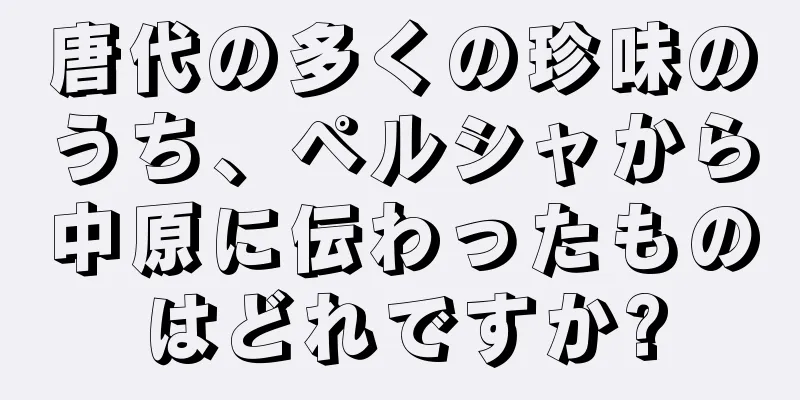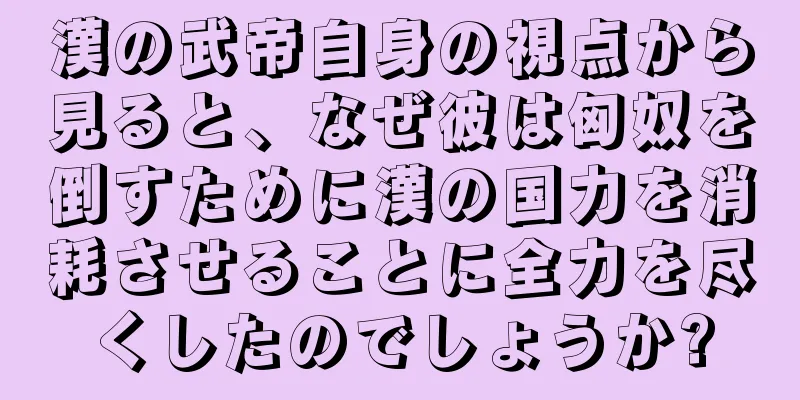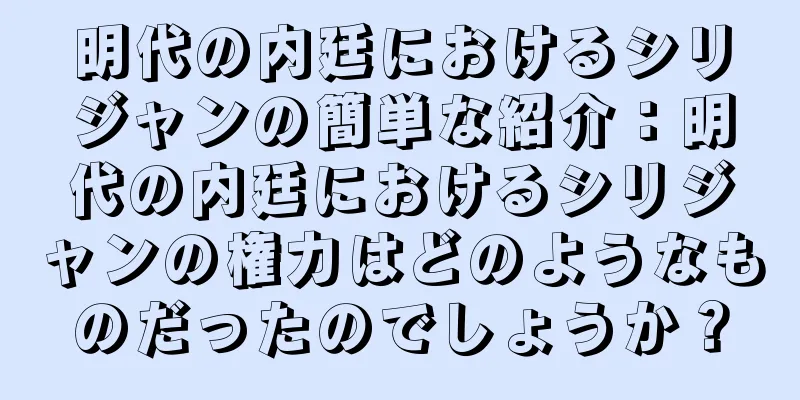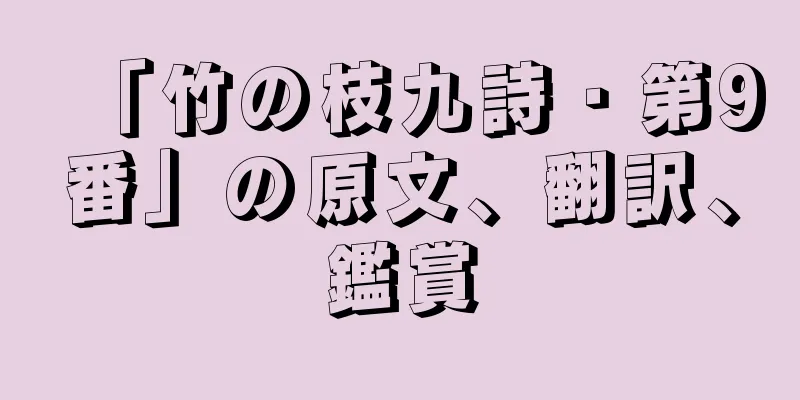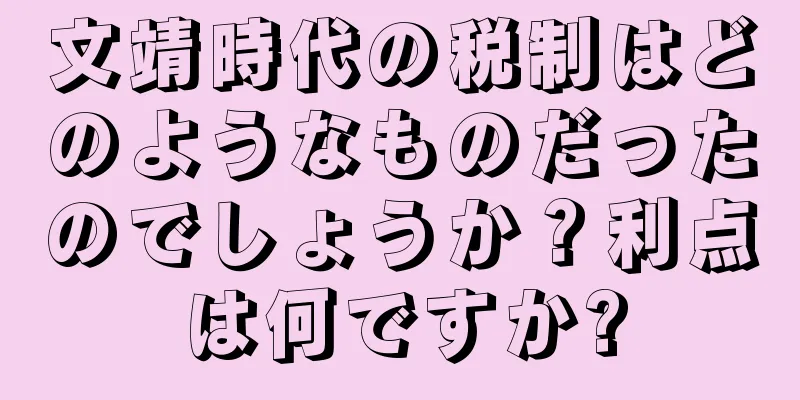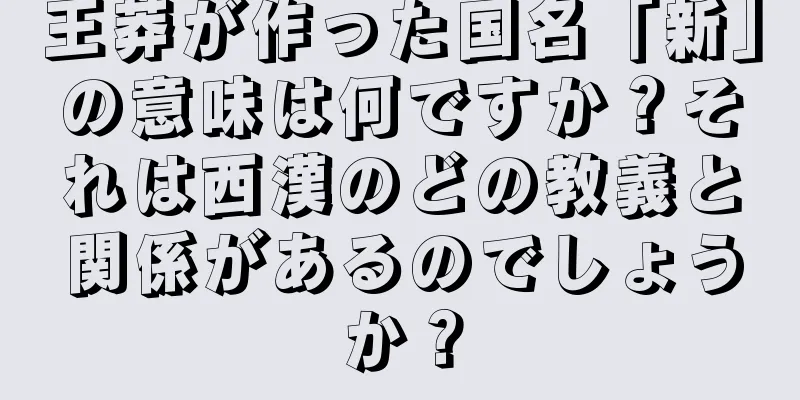『Compendium of Materia Medica Volume 1 Sequence Rise and Fall』の元の内容は何ですか?
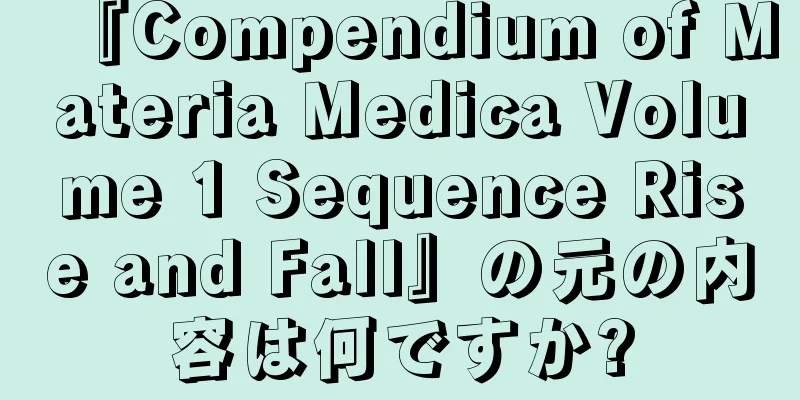
|
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の Interesting History 編集者は、皆さんと共有するために関連コンテンツを用意しました。 この本は「要綱に従って列挙する」という文体を採用しているため、「綱目」と名付けられました。 『正蕾本草』に基づいて改正された。この本には190万語以上が収録されており、1,892種類の医薬品が収録され、11,096の処方箋が収録され、1,160枚の精巧なイラストが掲載されています。16のパートと60のカテゴリに分かれています。本書は、著者が数十年にわたる実践と研究を重ね、これまでの生薬学の成果を継承・総括し、長期にわたる研究と聞き取り調査を通じて蓄積した広範な薬学知識を結集してまとめた傑作です。この本は、過去の生薬学におけるいくつかの誤りを訂正するだけでなく、大量の科学的データを統合し、より科学的な薬物分類方法を提案し、先進的な生物進化の考えを取り入れ、豊富な臨床実践を反映しています。この本は世界的な影響力を持つ自然史の本でもあります。 本草綱目 第 1 巻 興隆と衰退の順序 李高氏はこう語った。「薬には四季に応じて、昇ったり下がったり、浮いたり沈んだり、生長したり貯蔵したりする働きがある。春に昇り、夏に浮かび、秋に収穫され、冬に貯蔵され、土がその中間にある。」したがって、気の薄いものは上昇して生まれ、気の薄いものは下降して集まり、気の濃いものは浮いて成長し、気の濃いものは沈んで隠れ、気と臭の薄いものは変化して形成される。しかし、辛味、甘味、温味、熱味、淡味を補うと、春夏の昇浮を助け、秋冬の溜めを清める薬となる。人体では肝臓と心臓がそれにあたります。しかし、酸味、苦味、塩味、寒味、味の濃いものを補うと、秋冬の沈静を助け、春夏の成長を清める薬となる。人体では、肺と腎臓がこれにあたります。淡香の生薬は、浸透時には上昇し、瀉下時には下降する作用があり、他の生薬の補助として作用します。この規則に従って薬を飲めば生きられるが、この規則に反すれば死ぬ。死ななくても危険である。王浩谷は言った。「何かを持ち上げたり、落としたりするには、それを抑える方法を知らなければならない。何かを沈めたり、浮かべたりするには、それを運ぶ方法を知らなければならない。」辛味は拡散し、その作用は水平です。甘味は減速し、その作用は上向きです。苦味は消耗し、その作用は下向きです。酸味は収縮し、その性質は調和的で収縮します。塩味は柔らかく、その性質はリラックスします。これらがそれらの違いです。手を叩くと音が鳴り、火を注ぐと沸騰します。この2つが合わさると、その間にイメージが生まれます。五味は互いにコントロールし合い、四気は調和し、その変化は軽やかに利用されます。本草書には淡味や冷気については触れられておらず、本文も欠落している。 味が薄いものは上行作用があり、甘くて中性、辛くて中性、辛くてわずかに温かく、わずかに苦くて中性の薬です。 気虚の人は下向性があり、甘くて冷たい、甘くて冷たい、甘くて穏やかで冷たい、酸くて温かい、酸くて平坦、塩辛くて平坦な薬です。 気が濃いものは浮いています。これは甘辛または辛辛の薬です。濃い味は重い:これは苦くて冷たい、塩辛くて風邪薬を指します。平らな香りと味の薬には、甘くて平ら、甘くて温かい、甘くて冷たい、甘くて辛い、甘くて少し苦いという4つの性質と4つの味があります。 李時珍は言った。「酸っぱいものや塩辛いものは上がらず、甘いものや辛いものは下がらず、冷たいものは浮かばず、熱いものは沈まない、これがその性質だ。」上昇するものが塩気と寒さに導かれると、沈んで体の下部にまっすぐに行きます。沈むものが酒に導かれると、浮かんで頭のてっぺんに上がります。天地の神秘を垣間見て創造の力を理解した者だけがこの境地に到達できる。一つの物でも、根は上がり、先端は下がり、生は上がり、調理したものは下がる。上昇と下降は物にも存在するし、人にも存在する。 |
<<: 本草綱目・第1巻・序・標本陰陽の具体的な内容は何ですか?
>>: 本草綱目·第一巻·順序·六腑の補瀉と瀉下のための薬の匂いの使用の具体的な内容は何ですか?
推薦する
軍事著作の鑑賞:孫子の兵法第 1 巻第 1 章「兵法の始まり」の原文は何ですか?
孫子はこう言った。「戦争は国家にとって極めて重大な問題であり、生死に関わる問題であり、存続か破滅かの...
タタール料理 タタール独特の食文化
タタール人は一日三食の食生活を送っており、正午に主食、朝と夕方に軽食をとる。麺類、肉、牛乳は彼らの毎...
伏羲は三帝の一人です。彼の子孫はどの氏族ですか?彼とヌワの間には子供がいましたか?
伏羲は姓が馮で、古代の三皇帝の一人です。では、伏羲の子孫の名前は何でしょうか?次の興味深い歴史の編集...
愚かな少女とその母親は誰かを傷つけるつもりはなかったのに、なぜそんなに罪深いのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
秦の始皇帝による焚書と学者の埋葬は歴史上本当に起こったのでしょうか?秦の始皇帝はなぜ書物を燃やし、学者を埋葬したのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が秦の始皇帝...
李克用は何人の妻がいたか?李克用夫人、真堅皇后の簡単な紹介
李克用(856-908)は、神武川新城出身で、唐代末期の将軍であり、沙托族の一員であった。愛称は「李...
唐の武宗皇帝、李厳には何人の息子がいましたか?唐の武宗皇帝の子供は誰でしたか?
唐の武宗皇帝(814年7月1日 - 846年4月22日)は、本名は李禅であったが、後に顔に改名した。...
劉邦は40代で秦に対する反乱を起こした。彼はどのようにして世界に名高い功績を残したのか?
宋の太祖趙匡胤は34歳で皇帝に即位し、明の太祖は41歳で明王朝を建国し、秦の始皇帝は39歳で天下を取...
『紅楼夢』で賈家が大観園を造ったのはなぜですか?
大観園は、『紅楼夢』で賈家が元春の両親訪問のために建てた別荘です。元春の訪問後、元春は宝玉と朱柴にこ...
中国伝統文化作品の鑑賞:『商書』唐氏章の原文は何ですか?
易寅は唐王が桀王を攻撃するのを助けたとき、山から上って明条平原で桀王と戦い、『唐の誓い』を書いた。王...
秀雲閣第130章:二つの光が道を共有しようとし、二つの蜂が原因を理解するために一緒に行く
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
歴史の謎:「赤印」は輸入品の税関申告に使われる証明書
最近、大手メディアは、10年以上低迷していた切手市場が突然急騰したと報じている。 しかし、今日では、...
明朝はなぜ礼家制度を導入したのでしょうか?理由を説明する
周知のとおり、礼家制度は明代の草の根組織形態でした。これは、明朝政府が黄書制度を実施するための基礎の...
水滸伝の豹頭林冲とはどんな人物でしょうか?彼は卑劣な人間ですか?
英雄といえば、まず思い浮かぶのは『水滸伝』です。『水滸伝』の原題は「百八英雄」だからです。これら 1...
『後漢書 黄襄伝』の原文と翻訳、文学伝第70巻より抜粋
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...