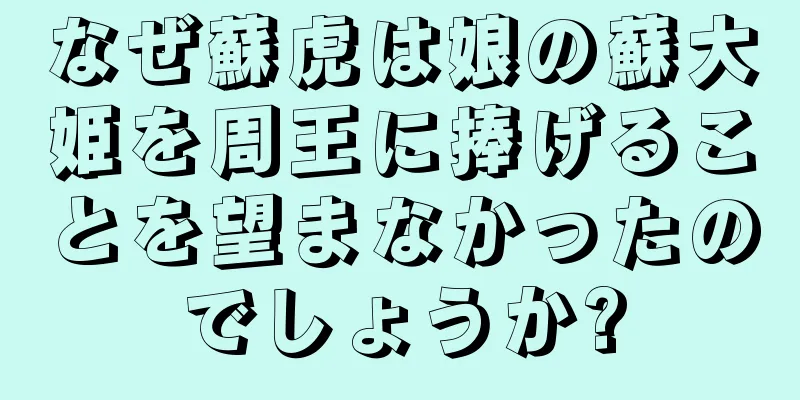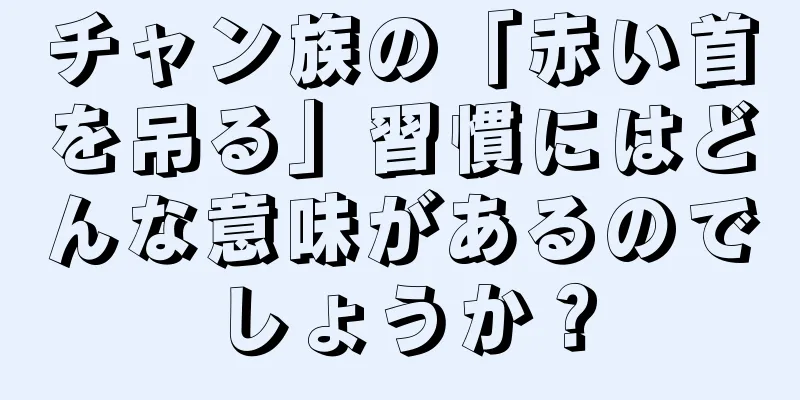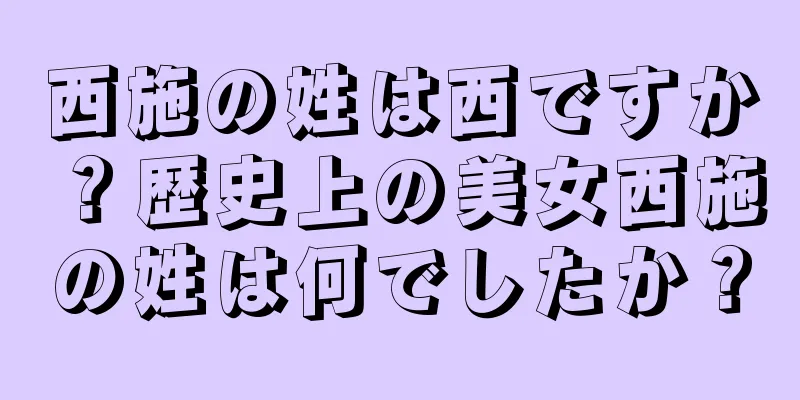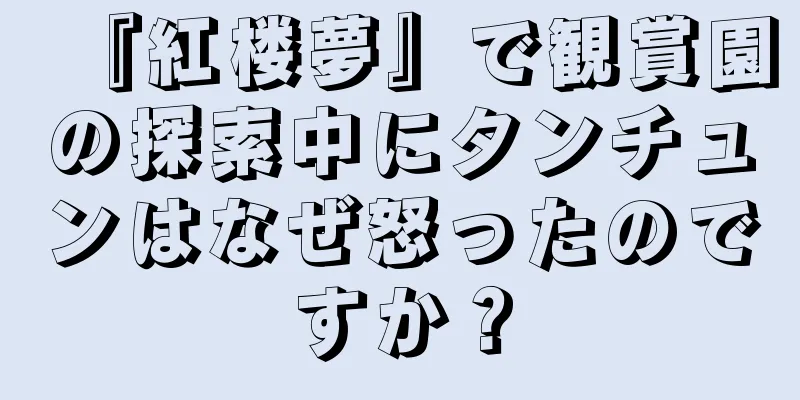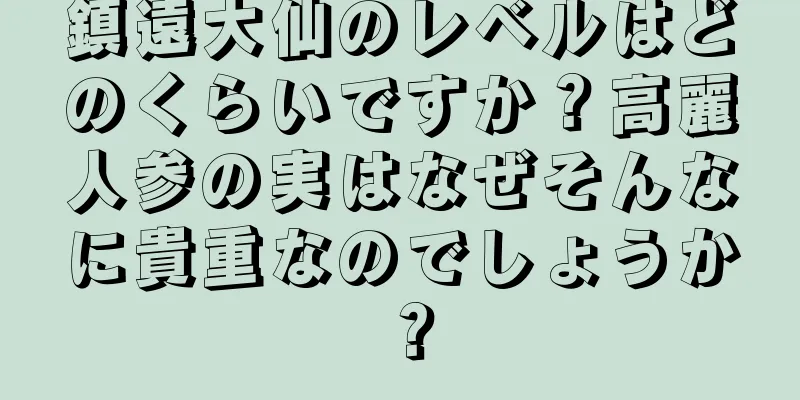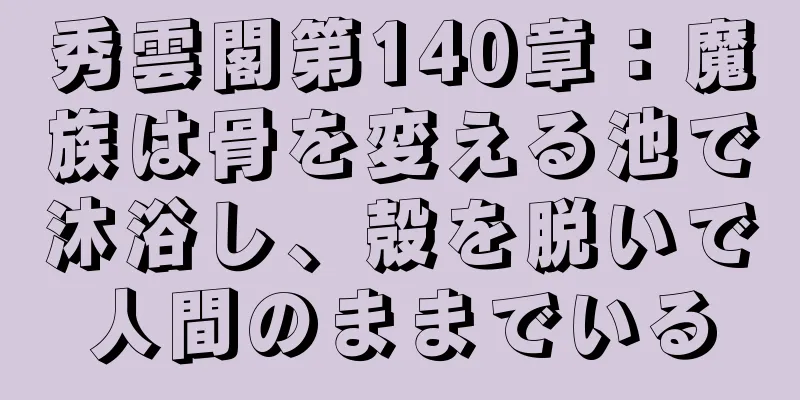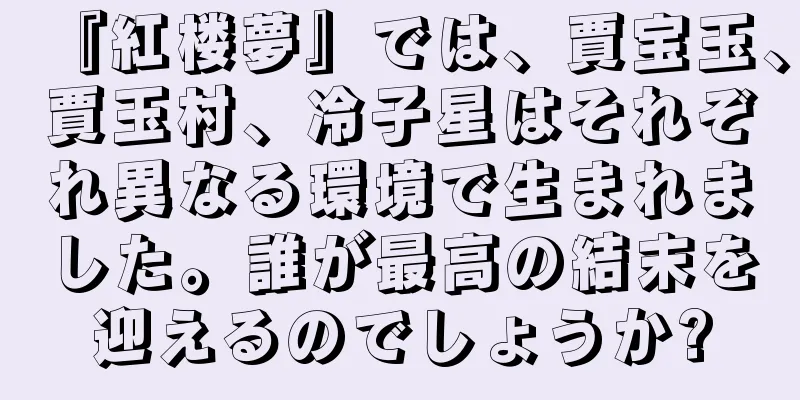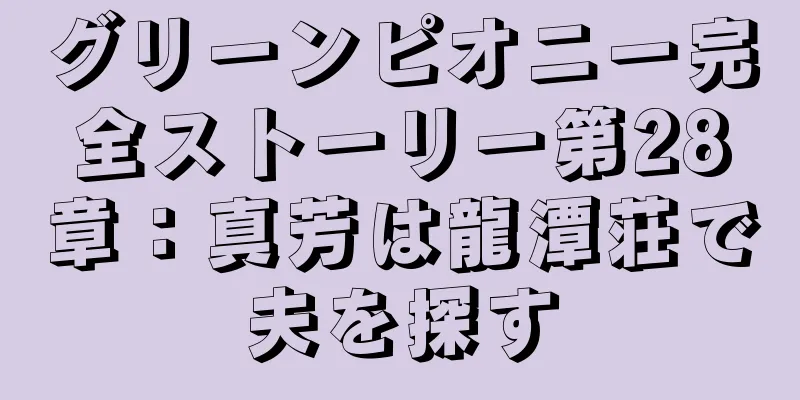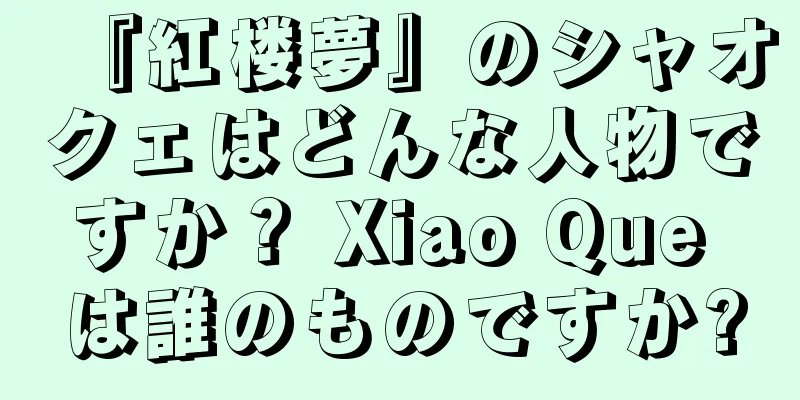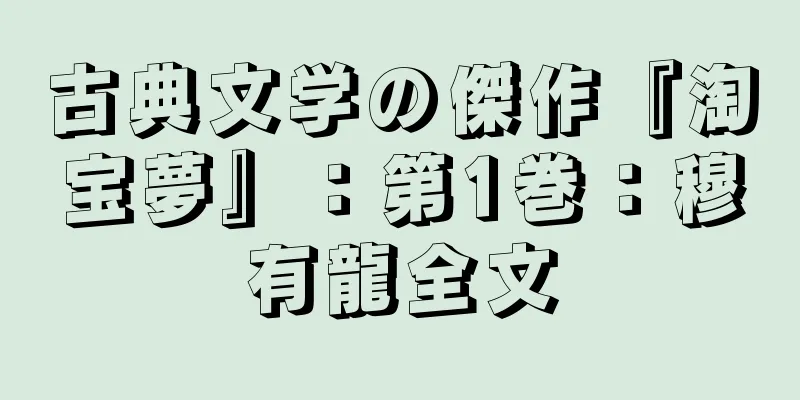三国志における薛凌雲の紹介:常山出身の絶世の美女、曹丕は彼女に恋をした
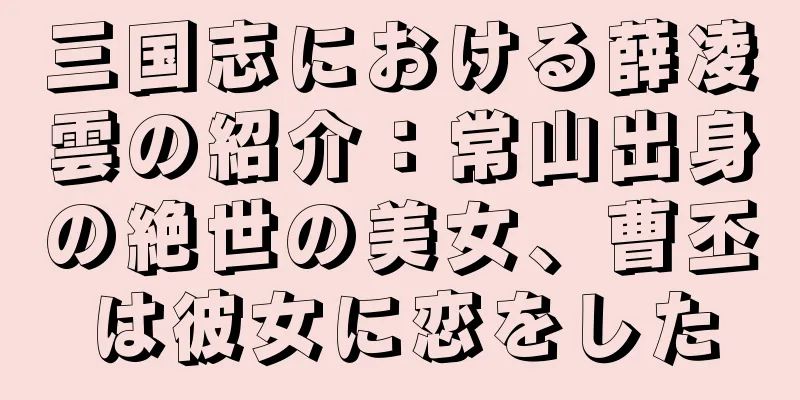
|
薛凌雲は魏の文帝曹丕の側室で、名前を野来と改めました。彼女は裁縫が得意で、深いカーテンで囲まれていても、ろうそくの明かりを頼りにせずに裁断や縫製ができます。裁縫は夜にしないと皇帝は納得しないので、宮殿では針神と呼ばれていました。 薛凌雲は17歳の時に地方の役人によって選ばれ、魏の文帝に献上されたと言われています。薛凌雲さんは両親と別れなければならないと聞いて、一日中泣き続け、服は涙で濡れていた。彼女が首都洛陽行きの馬車に乗るとき、玉の痰壺を使って涙をこらえました。故郷の常山から首都の洛陽まで、壺の中の涙は血の色に凝縮しました。 東晋の王嘉は著書『遺物記』の中で次のように記している。 文帝が愛した美女は、常山出身の15歳の薛凌雲で、比類のない美しさを持っていました。咸熙元年、文帝は良家の子女を六つの宮殿に入れるよう選抜した。常山の知事、西固は彼に金千枚の賄賂を申し出た。彼が都に着くと、皇帝は10台の馬車で彼を迎え、道端で石の葉で作った香を焚いた。彼が数十マイルも行かないうちに、蝋燭の灯りは消えることなく続いた。馬車は交通で混雑し、ほこりが舞い上がって星や月が見えなくなった。彼はまた、土で高さ三十丈の台を築き、台の足元にろうそくを立てた。遠くから見ると、まるで星が地面に落ちているように見えます。また、幹線道路の脇には、マイル数を示すために、1マイルごとに高さ5フィートの青銅の銘板が立てられていました。そこで旅人は「こんな感じだよ、こんな感じだよ」と歌いました。 魏の文帝に献上 顧熙は莫大な金で薛凌雲を雇い、魏の文帝に献上した。薛凌雲さんが両親に別れを告げたとき、彼女の服は涙で濡れていた。バスに乗ると、彼女は涙を抑えることができず、玉の痰壺で涙を集めましたが、涙は痰壺の中に落ちて赤くなりました。 都に着く前に、壺の中の涙はすでに血のように赤く染まっていた。文帝は文様を刻んだ十台の車を用意して薛凌雲を出迎えた。戦車はすべて、金で彫刻された車輪の縁、塗装されたハブとヨークを備え、前後には宝石がちりばめられていました。鐘は調和して鳴り、澄んだ音が森に響きました。青い蹄の牛が駆られ、1日に300マイルも移動できました。この種類の牛は石図国から献上されたもので、その蹄は馬の蹄と同じです。道端で石の葉の線香を焚く。この石は雲母のような形をしており、層状になっています。この石が放つ香りは病気を防ぐと言われています。フティ国から贈られたものです。 薛凌雲は都へ向かう途中、数十里にわたってろうそくに火を灯し、長い間消えることはなかった。車が通る道路の埃で星や月が見えにくくなり、当時の人々はそれを「埃空」と呼んでいました。高さ 30 フィートの赤い土で作られた台が建てられました。台の下にはオイル キャンドルが置かれ、それは「キャンドル スタンド」と呼ばれていました。遠くから見ると、流れ星のように見えました。 道の両側には、距離を示すために 5 フィートの高さの青銅の銘板が 1 マイルごとに鋳造されていました。そのため、道行く人々は「道には緑のニセアカシアが並び、埃が舞い、龍の塔と鳳凰の宮殿がそびえ立ち、そよ風と霧雨が香りを運び、金色の火が地面から出て台を照らす」と歌った。当時、距離は銅板に刻まれており、「地中から金が出てくる」という意味だった。 「火昭泰」とは、油を塗ったろうそくの火が地の下にあることを意味します。漢王朝は火徳王によって統治され、魏王朝は地徳王によって統治されました。「火昭泰」とは、漢王朝が滅び、魏王朝が興ったことを意味します。 「土から金が出てくる」は、魏の衰退と晋の台頭を象徴する言葉です。 薛凌雲は都から十里離れた所に住んでいた。文帝は玉で彫った馬車に乗って遠くから彼女を見て、ため息をついて言った。「昔の人は『朝には雲が流れ、夕方には雨が流れる』と言っていた。今は雲も雨もなく、朝も夕方もない」。そこで文帝は薛凌雲の名前を「葉来」と改めた。後の花名「塊茎咲きジャスミン」は薛凌雲に由来する。 魔法の針 薛凌雲は宮廷に入ってから寵愛を受けた。外国から贈られた火珠龍鳳簪はとても重かった。文帝は薛凌雲の弱々しさを哀れに思い、「真珠や緑玉の羽でも重いのに、こんなに重い龍鳳簪はなおさらだ」と言った。薛凌雲の服を縫う針仕事は見事で、深いカーテンの中にいても、ろうそくを灯さずに夜中に服を縫うことができた。文帝は薛凌雲が縫ったもの以外の衣服を着ることを拒否した。宮殿の人々は彼女を「針神」と呼んだ。魏の文帝は「葉来」に名前を変えました。 黄初七年、魏の文帝が崩御し、薛霊雲の行方は分からなくなった。 赤い涙 薛凌雲の物語は正史には記録されていないが、『史易記』『太平広記』『顔一篇』など多くの非公式の歴史記録に時折言及されている。李尚胤は「蓮は一夜にして多くの赤い涙を流した」と書き、何卓の『四州韻』には「塗られた建物に香る酒、赤い涙、澄んだ歌、突然軽い別れになる。何年も経ったが、あなたからの知らせはない。あなたの心の中にどれほどの悲しみがあるのか知りたいですか?」とある。ここでの「赤い涙」は薛凌雲を暗示している。 『世易記』には、薛凌雲が両親に別れを告げて車に乗り込み出発するとき、玉の痰壺で涙を受け止めたと記されており、その痰壺の色は赤かった。都に着くと、鍋の中の涙は血のように固まっていた。そのため、後世の人々は女性の涙を「赤い涙」と呼ぶようになりました。その後、赤いろうそくから「赤い涙」が滴ったり、カッコウが血の涙を流したりするなど、一般的な暗示となりました。 唐代に楊玉環が宮廷に召される前に、「彼女は涙を流しながら車に乗りましたが、その時は寒く、彼女の涙は赤い氷に変わった」と言われています。 清代の毛和亭は『太清易詩』の中で「太平街太平湖畔、葉来は春深き南谷に埋葬される。人は城中一番の美女、姓は国中一番の美女、ライラックの花が咲き誇る」と書いている。ここでの「葉来」も薛凌雲のことである。 『紅楼夢真夢』第64話では、皆が象牙のチップで遊んでいる様子が描かれている。「黛玉と宝仔は数枚取り出して眺めた。片面には古代の美女が刻まれ、もう片面には詩と様々な飲酒ルールが刻まれていた。皆は面白いと思い、すぐに宝仔がゲームを始めることにした。宝仔は一枚引いた。刻まれていた美女は薛凌雲で、反対側の詩は「春に玉脈が赤くなるのはなぜか問う」で、注意書きには「よく泣く人は飲む、濃い化粧をする人は飲む」とあった。彼女は笑って言った。「林姉さん以外に、よく泣ける人は誰?」」泣く技術で薛凌雲に匹敵できるのは、林黛玉だけかもしれない。 注: 薛凌雲の物語は後世の創作であり、公式の歴史書には登場せず、非公式の歴史書や小説にのみ登場します。 |
>>: 楊志の簡単な紹介:晋の武帝、司馬炎の皇后、楊志の伝説的な生涯
推薦する
太平広記・巻59・仙人・南陽公主の具体的な内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
ハニ音楽文化の紹介 ハニ音楽の特徴とは
民謡には主に、「ハバ」(物語歌)、「アチ」(遊び歌)、「ラングチャ」(子供の歌)、「アニト」(ロッキ...
「杭州春景」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
杭州春景色白居易(唐代)望海塔は朝焼けに照らされ、川の堤防は澄んだ砂の上に白く浮かび上がっています。...
晋の歴史:八王の乱の展開
魏の咸熙二年十二月八日(266年2月8日)、司馬炎は魏の元帝に退位を迫り、自ら皇帝に即位し、国名を大...
石公の事件第455話:郵便局を出て琅瑾山を訪れ、酒場に入って益州鎮で騒ぎを起こす
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
美しい「臨江仙」詩十編の鑑賞:異なる芸術概念と多様な感情
臨江県:揚子江は東に流れる明代楊深揚子江は東に流れ、その波はすべての英雄たちを押し流す。成功も失敗も...
文廷雲の『柳八句二』:比較によって柳の感情が深まる
文廷雲は、本名は斉、雅号は飛清で、太原斉県(現在の山西省)の出身である。唐代の詩人、作詞家。彼の詩は...
漢の武帝はなぜ「封土令」を発布したのか?土地封建令の機能と影響は何ですか?
漢の武帝はなぜ「封土令」を発布したのか?封土令の機能と効果は?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しま...
明代の重慶公主についての簡単な紹介。重慶公主の実母と夫は誰ですか?
明朝の英宗皇帝の長女、重慶公主の簡単な紹介。重慶公主の実母と夫は誰ですか?重慶公主(1446-149...
「城南の戦い」は李白が書いた古典的な詩であり、強い反戦感情に満ちている。
唐代の詩人たちが書いた辺境の詩には、しばしば矛盾した心理が反映されている。岑申、高石、王維などの辺境...
王安石の最も古典的な梅の花の詩は世界を驚かせた
王安石の最も古典的な梅の花の詩は世界を驚かせました。興味のある読者と「Interesting His...
本草綱目第3巻万病治癒法腸音の本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『後漢演義』第44章の主な内容は何ですか?
忠臣たちを救い、宦官党は互いに攻撃し合い、高貴な女性がついに女王となるしかし、燕太后が別の宮殿に移っ...
清朝時代に蜀にはいくつの属国がありましたか?まだ残っている国はどこですか?
今日は、おもしろ歴史編集長が、清朝時代に蜀王国の属国がいくつあったかをお話しします。皆さんの参考にな...
楊万里の『南渓早春』:この詩の利点は退廃的な調子ではないことだ
楊万里(1127年10月29日 - 1206年6月15日)は、字を廷秀、号を程斎、程斎野客と号した。...