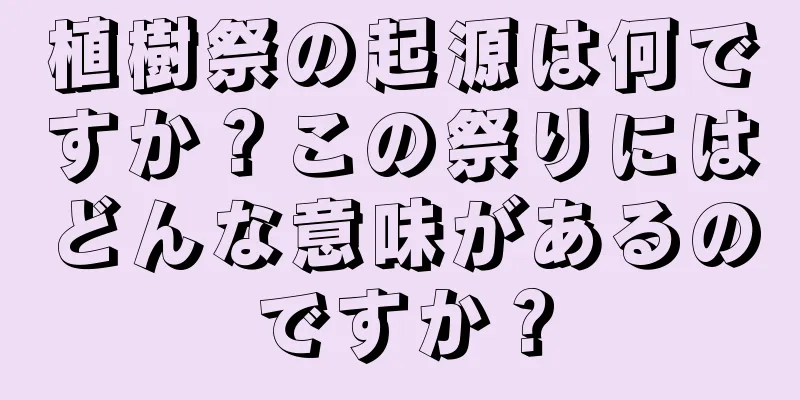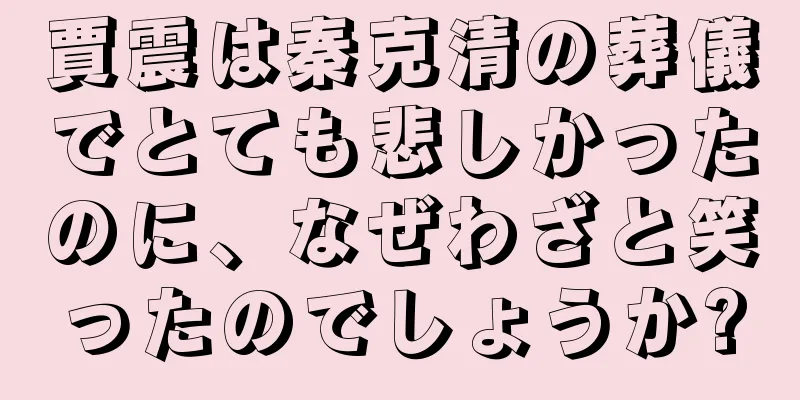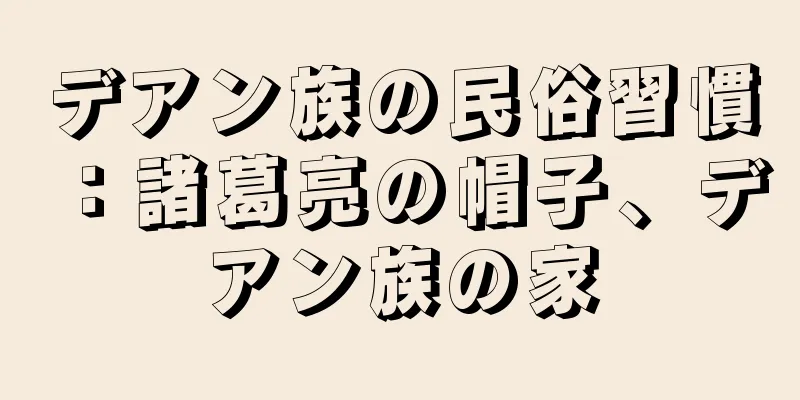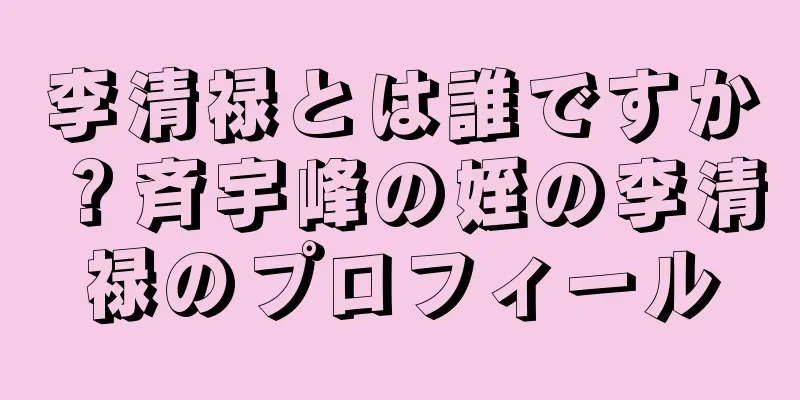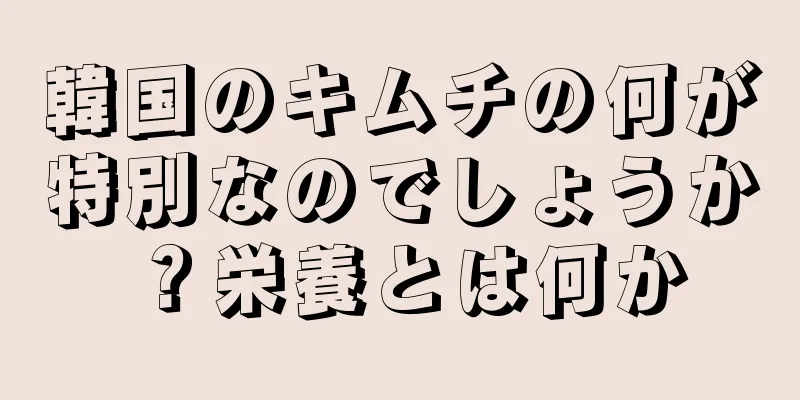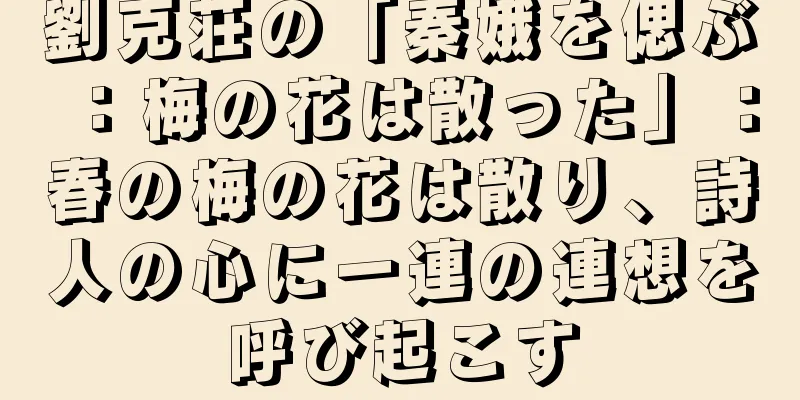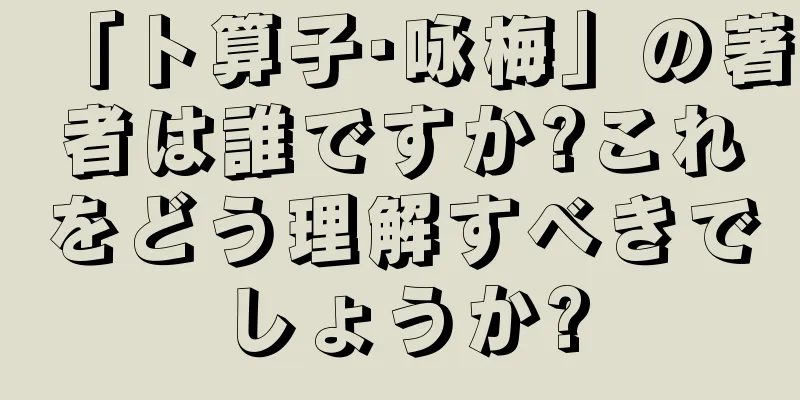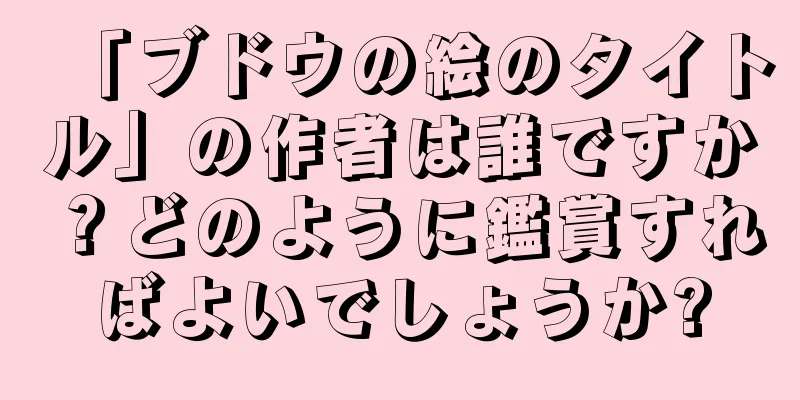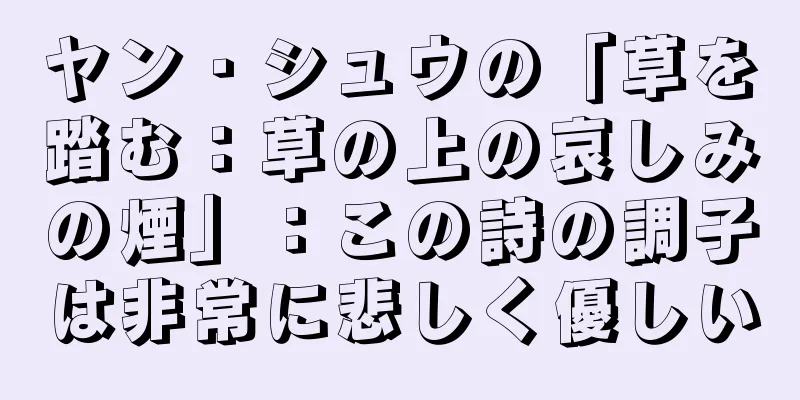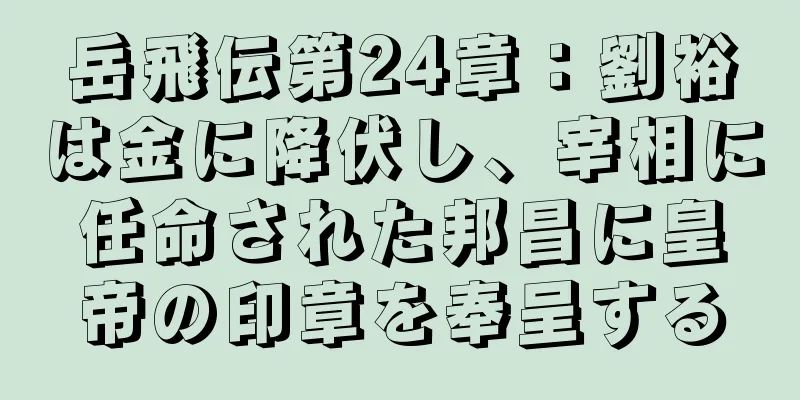「本当の自分を見せる」というフレーズはどのようにして生まれたのでしょうか? 「人間の足を見せろ」とか「豚の足を見せろ」ってどうしてダメなの?
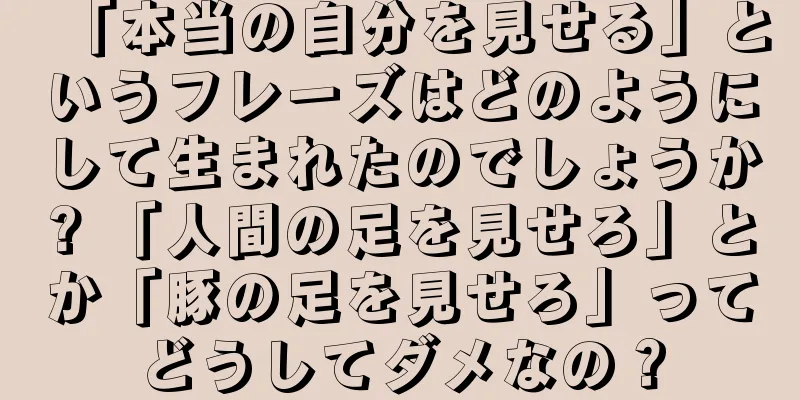
|
今日は、Interesting Historyの編集者が「自分の本性をさらけ出す」というお話をお届けします。気に入っていただければ幸いです。 通常、何かの真実が暴露されたことを表現したいときは、「本性を現す」と言います。しかし、「本性を現す」という言葉の起源は何でしょうか? 伝説によると、「本性を現す」は朱元璋と馬皇后に関係しています。当時、女性は足を包む必要がありましたが、馬皇后は子供の頃からそれを拒否したため、他の女性に比べて足が大きいのです。かつて馬皇后の足が外部の人から見えたことから、「馬の足が見える」ということわざが生まれました。しかし、歴史の記録によると、「露馬脚」という言葉は唐代にはすでに登場していましたが、馬皇后の物語の方が有名です。 1. 本性を現す。 なぜ「人間の足」ではなく「馬の足」を使うのでしょうか? 人はよく「露马脚」という言葉を誰かの嘘を表すときに使いますが、なぜ「露人脚」ではなく「露马脚」を使うのでしょうか? 伝説によると、朱元璋は足を縛られていない馬という少女と結婚した。 ある日、馬さんは金陵の街で車に乗っていました。突風が車体のカーテンをめくり、馬さんの大きな足が露わになりました。 噂は一人から十人へ、十人から百人へと広まり、たちまち金陵中に大騒ぎとなった。 「馬嬌」という言葉は後世に受け継がれました。 2. 不注意。 宋代、都の画家が虎の頭を描き終えたところ、馬を描いてほしいと頼まれました。画家は虎の頭の後ろにある馬の体を何気なく描きました。 誰かが彼に、馬を描いているのか、それとも虎を描いているのかと尋ねると、彼は「まあまあ、まあまあ」と答えた。 訪問者がそれを欲しがらなかったので、彼はその絵をホールに掛けた。 長男は絵を見て、何が描かれているか尋ねました。長男は、虎だと答えました。次男が尋ねると、馬だと答えました。 その後間もなく、長男が狩りに出かけ、トラと間違えて馬を射殺してしまいました。画家は馬の所有者に賠償金を支払わなければなりませんでした。 末の息子は外に出て、トラに出会いました。彼はそれを馬だと思って乗りたいと思いましたが、結局トラに噛まれて死んでしまいました。 それ以来、「不注意」という言葉が広まりました。 3. 老人。 街では、年老いたおばあちゃんが配偶者を「おじいさん」と呼んでいるのをよく耳にします。これは人の老齢を表すために使われているとは思わないでください。実際、「おじいさん」の意味はそれよりもずっと深いのです。 記録によると、真夏のある日、季小蘭が胸と背中を露出した状態で原稿を校正していたとき、乾隆帝が彼に向かって歩いてきた。季小蘭は服を着るには遅すぎたので、机の下に潜り込んだ。 しばらくして、乾隆帝が去ったと思い、ホールの人々に尋ねました。「老人は去りましたか?」 彼が話を終えるとすぐに、乾隆帝が彼の隣に座っていることに気づいた。 乾隆帝は怒って季小蘭に尋ねた。「『老人』という三つの単語をどう説明するんだ?」 意外にも、季小蘭は落ち着いて答えた。「長寿を老といい、背丈が高いことを頭といい、天地の父母を天子といい、要するに『老人』というのです。」 4. 恐喝。 近年、運転中に「車にぶつかる」というニュースが多く報道されています。「車にぶつかる」は「恐喝」とも言えます。 「恐喝」の起源は実は密輸と深く関係しています。 清朝時代、朝廷はアヘンを厳しく禁止し、各地の水上要塞や陸上要塞に検問所を設置した。 水運商人が、成長し始めたばかりの若い竹を切り開き、その中にアヘンを隠して検査を逃れた。 かつて、商船が紹興埠頭に到着したとき、関所の弁護士が船に乗り込み、パイプで竹竿をたたき、「カチカチ」という音を立てました。商人は弁護士が欠陥を見抜いたと思い、数両の銀貨を取り出して弁護士のポケットに詰め込み、竹竿を「カチカチ」と鳴らさないように頼みました。 それ以来、「恐喝」という言葉が人々の間で広まった。 5. ケチ。 「Stingy」は2人であることが判明しました。 「stingy」はけちな人を表すのに使われることは誰もが知っているはずですが、それが実際には 2 人の人の名前であることは知らないかもしれません。 昔、王林という男がいました。中秋節の前夜、彼は古い友人の李世を訪ねました。しかし、月餅を買うのをためらっていたので、月餅を描いて李世の家に持って行きました。 結局、李世は家にいなかったので、息子は「王おじさんが月餅を持って家に来たので、お返しに贈り物をしよう」と言いました。そこで、大きなカボチャを描いて王林に渡しました。 その後、李世は息子の王林に何か贈り物をしたかどうか尋ねた。 息子は答えました。「月餅を一箱あげたよ。」 「贈り物は返しましたか?」 息子は答えました。「僕はこんなに大きなカボチャを手に入れたよ。」 後に、人々はこの物語の二人を、意地悪でけちな人々を表すために「けち」と名付けました。 6. 愚かなふりをする。 水仙は咲いていない ― 咲いているふりをしているだけ。 「バカなふりをしないで」というのは、誰かと決着をつけたいときに相手がバカなふりをしているときによく使われる表現です。では、「バカなふりをする」というのはどこから来たのでしょうか? 伝説によると、乾隆帝はある春に南方へ視察に行き、青々としたニンニク畑を見て賞賛したそうです。 翌年の冬にもう一度確認しに行きましたが、残念ながらその季節には青ニンニクはまだ育っていませんでした。 皇帝を喜ばせるために、地方の役人は人を遣わしてたくさんの水仙を植えさせました。遠くから見ると、その葉は青ニンニクのように見えました。乾隆帝はそれを見て大いに賞賛し、役人はこれによって昇進しました。 それ以来、人々は不正行為をしたり、何も知らないのに知っているふりをすることを「愚か者を演じる」と嘲笑するようになりました。 |
<<: なぜ陸俊義は水滸伝の十大槍の名人の中で第一位にランクされているのですか?
>>: なぜ燕青は『水滸伝』の秘武器名人トップ10の中で4位にしかランクされていないのでしょうか?
推薦する
発明家諸葛亮の古くからのライバルであった魏国は、科学技術においてどのような功績を残したのでしょうか。
科学技術は主要な生産力であり、古代の人々はこれに大きな注意を払っていました。三国時代の諸葛亮の『木馬...
「情と出会いの三十八首 第2番」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
出会いの詩三十八篇 その2陳奎(唐代)蘭は春から夏にかけて成長し、とても青々とした緑になります。寂し...
『紅楼夢』の王希峰の話し方はどれくらい上手ですか?彼女はどうやって賈夫人を喜ばせたのでしょうか?
「紅楼夢」の王希峰は口下手なのは有名ですが、彼女はどのくらい口下手なのでしょうか?どうやって賈おばあ...
宋孝宗昭深皇帝の3番目の皇后である宋孝宗成粛の謝皇后の簡単な紹介
成粛皇后(?-1203)、姓は謝、宋の孝宗趙深の3番目の皇后。丹陽の出身。幼い頃は孤児で無力だったが...
李玉は南唐の李靖の六男です。なぜ彼は南唐の王位を継承したのですか?
南唐の最後の君主である李郁は、古代中国史上最高レベルの詩作力を持つ非常に才能のある作家だったことは誰...
呉文英の有名な詩の一節を鑑賞する:長い間、西側の窓に一人で座っていると、古い友人に会い、ろうそくの明かりで彼と話をした
呉文英(1200年頃 - 1260年頃)は、雅号を君特、号を孟荘といい、晩年は妓翁とも呼ばれた。思明...
『紅楼夢』の賈家の希仁と青文の給料の差はどれくらいですか?
賈家には非常にユニークな賃金制度があり、日々の生活費は家族全員で負担しますが、全員が毎月給料を受け取...
韓愈の『東野酔』は、孟嬌に対する尊敬の念を豊かかつ暗示的に表現している。
韓愈は、字を徒子といい、自らを「昌里の人」と称し、通称は「韓昌里」または「昌里氏」であった。唐代の著...
『詩経』の「千尚」の意味は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
スカートをまくる子慧は私のことを思い、スカートをまくり上げて秦河を渡っていった。私のことを考えないな...
古典文学の傑作『道安の夢』:第7巻:六院寺の四角柿の全文
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...
1898 年の改革運動の本来の意図は何でしたか?五穀改革の六君子が処刑されたとき、なぜ人々は歓声をあげたのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、五穀改革の六君子が処刑されたときに人々が拍手喝采した理由をお話ししま...
古典文学の傑作『太平天国』:病魔篇第5巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
「長江南の春・波は霧」を鑑賞して、詩人崔俊は長亭での別れの時を回想した
孔鈞(961年 - 1023年10月24日)は、字を平中といい、華州下桂(現在の陝西省渭南市)の人で...
皇帝の物語:周世宗柴容はどんな皇帝だったのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
張磊の「夏の詩三篇1」:詩人は名声や富に無関心だが、世俗的な世界を嫌う
張磊(1054-1114)は、法名は文乾、号は克山で、亳州橋県(現在の安徽省亳州市)の出身である。彼...