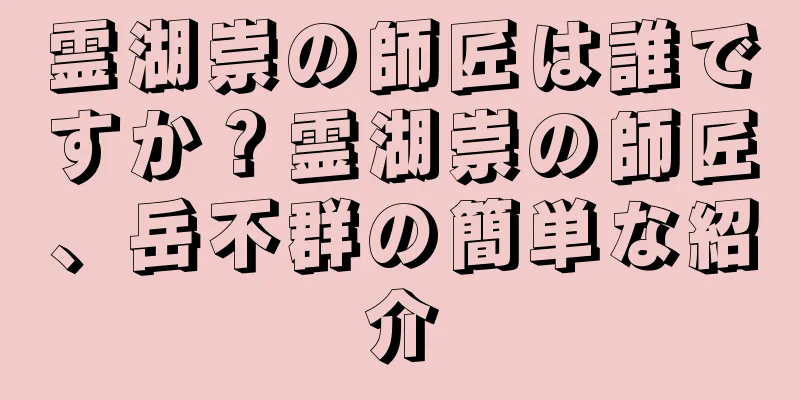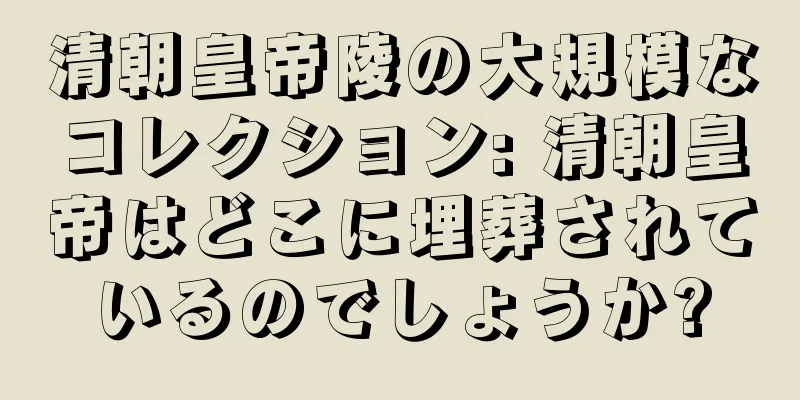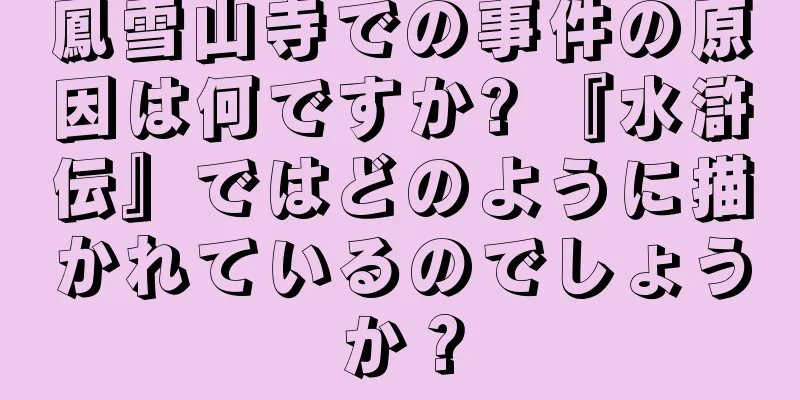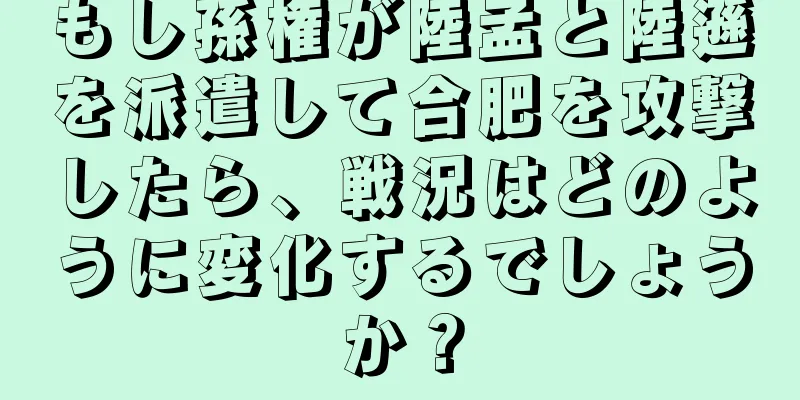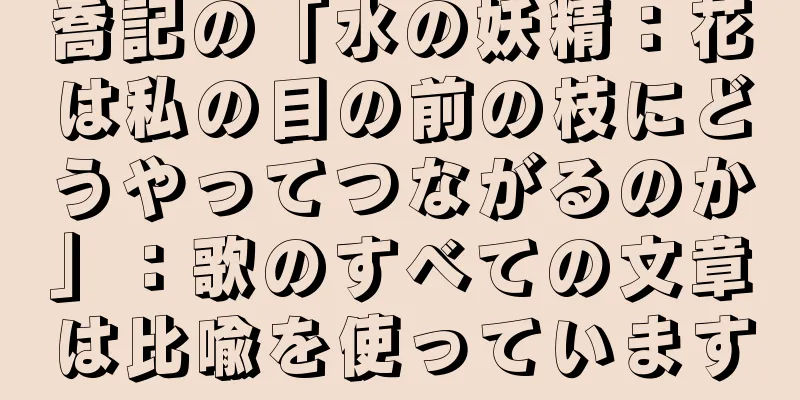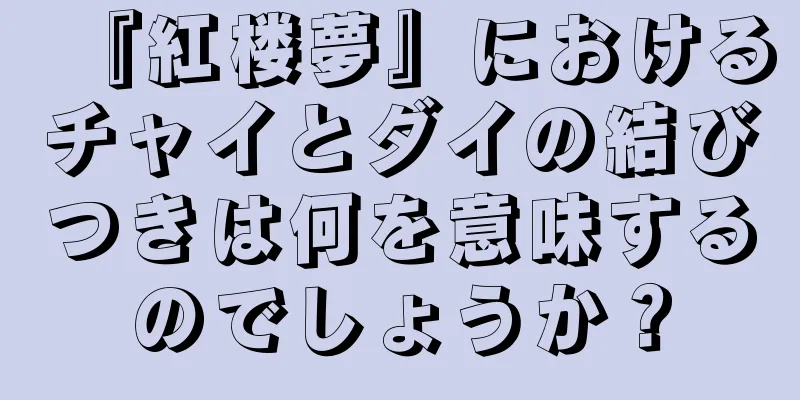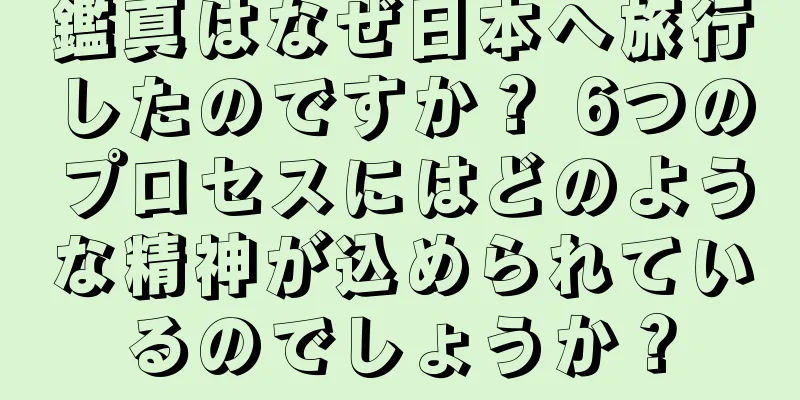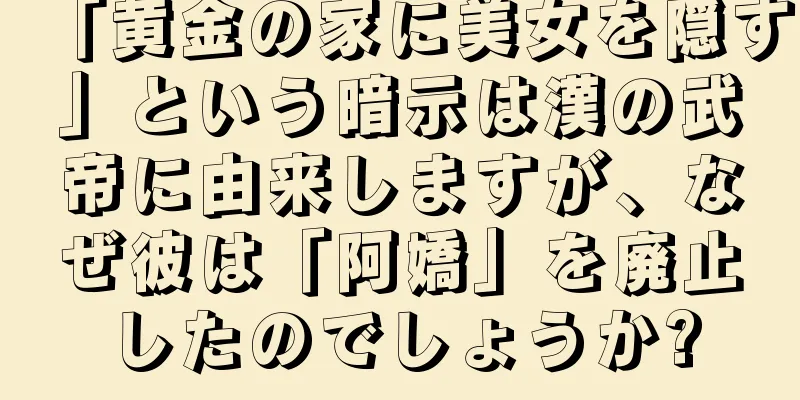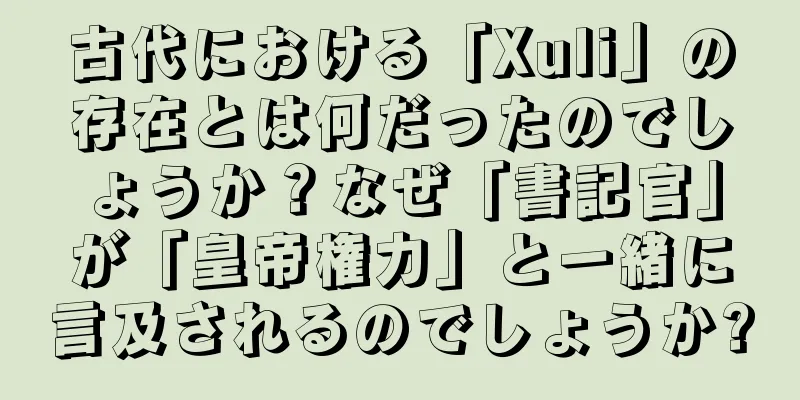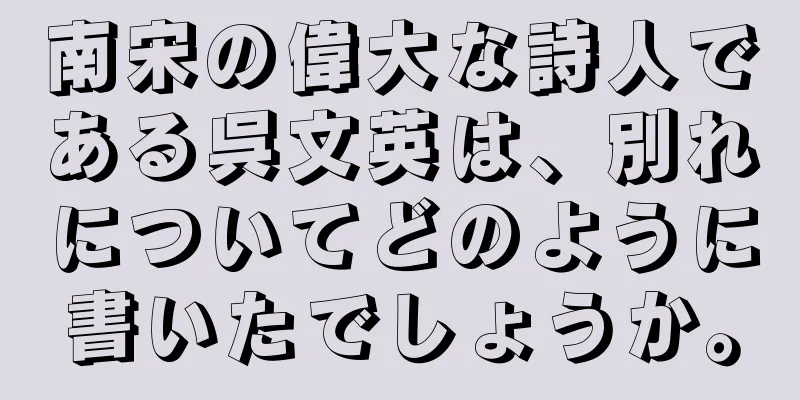ヌルハチの孟嘗妃と黄太極の関係は何ですか?
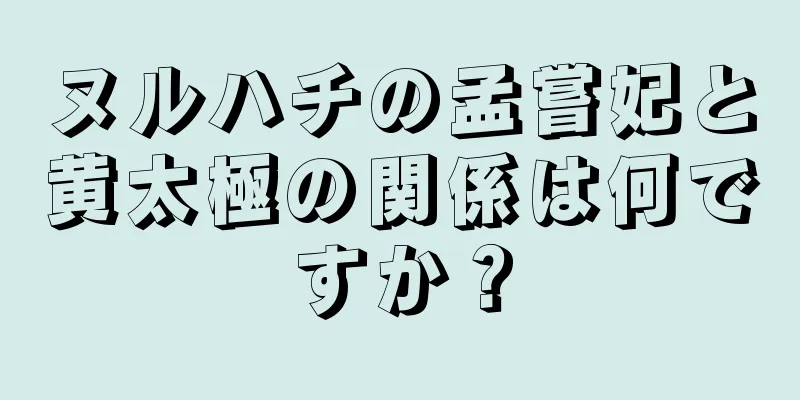
|
孟姑と黄太極の関係は何ですか? 孟姑は清朝の太宗皇帝、黄太極の生母であった。 姓がイェヘナラである孟谷は、孟谷姉さん(孟谷ジェジェ)と呼ばれました。彼女は清朝の太祖皇帝アイシン・ジョロ・ヌルハチの側室であり、清朝の太宗皇帝アイシン・ジョロ・黄太極の生母である。彼女は清朝で死後に皇后に叙せられた最初の人物である。万暦20年、彼女は8番目の息子である黄太極を出産しました。黄太極は後に清朝の太宗皇帝となりました。彼は万暦31年、29歳で病死した。 清朝の太宗皇帝、愛新覚羅黄太極(1592年11月28日 - 1643年9月21日)は満州人。「黄太極」「洪太珠」「洪大師」とも訳された。乾隆帝の時代に現在の訳が採用され、現在も使用されている。 彼は清朝の初代皇帝ヌルハチの8番目の息子でした。ヌルハチの死後、黄太極が皇帝の位を継承するよう選出されました。 1636年、黄太極は砂漠南部のモンゴル族から「ボグダ・チェチェン・ハーン」、別名「天宗ハーン」として崇拝された。同年、黄太極は女真族の国名を満州と改め、瀋陽で皇帝を称し、清朝を建国した。 黄太極は17年間統治した。彼の治世中、生産を発展させ、軍事力を強化し、明朝と継続的に戦い、次の段階で清朝が中原に急速に拡大するための強固な基盤を築きました。寺号は太宗、諡号は英天帝、興国帝、弘徳帝、章武帝、寛文帝、仁勝帝、睿帝、孝静帝、閔帝、昭定帝、龍道帝、湘公帝、文帝であった。 |
<<: ヌルハチの王妃メングはどのようにして亡くなったのでしょうか?孟姑女王は何歳でしたか?
推薦する
太平天国軍はどうやって南京を占領したのですか?かつて三藩を滅ぼした緑陣営の兵士たちはなぜ太平天国の軍を滅ぼすことができなかったのか?
かつて三藩を滅ぼした緑陣営の兵士たちはなぜ太平天国軍を滅ぼすことができなかったのか?次の『興味深い歴...
晋の懐帝の皇后、司馬懿とは誰ですか?金の淮帝皇后、梁蘭弼の簡単な紹介
司馬遷(284年 - 313年)は、愛称は馮都、晋の武帝、司馬炎の25番目の息子であり、晋の恵帝、司...
『紅楼夢』で、王夫人がわざと困難な状況に陥れたとき、黛玉はどのように反応しましたか?
『紅楼夢』のヒロイン、林黛玉。金陵十二美女本編の2冊のうちの1冊。次は、興味深い歴史の編集者が関連記...
戴富久は妻と10年間別居していたため、「木蘭花男」を執筆した。
戴富姑(1167年 - 1248年頃)は、字を世智といい、南唐の石平山によく住んでいたため、石平、石...
東方の仏陀、弥勒菩薩の金輪はどこへ行ったのでしょうか?誰に?
如来は仏典を手に入れるための事業を始め、観音を東に派遣して集団を作ったと言われています。巡礼者たちが...
「私たちは生まれたときから兄弟なのだから、血縁なんて気にする必要はない」という有名な格言はどこから来たのでしょうか?
まだ分からないが、「私たちは最初に上陸したときから兄弟だった、なぜ血縁にこだわる必要があるのか...
唐の玄宗皇帝の娘、宣義公主の紹介。宣義公主の夫は誰だったのでしょうか?
献頤公主(? - 784年)は、献智公主とも呼ばれ、唐の開元の時代の皇帝玄宗の娘であり、武帝真順の娘...
老子の『道徳経』第 41 章とその続き
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古...
公孫勝は歴史上に実在したのでしょうか?公孫勝の終焉
公孫勝とは誰ですか?公孫勝について語るとき、人々は必ずその名前の前に「水滸伝」という言葉を付け加えま...
『紅楼夢』におけるチュニャンとその娘の存在の深い意味は何でしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立ての長編小説で、中国古典四大傑作の一つです。 Interesting H...
学者第22章:祖父と孫の玉浦を認め、家族とつながり、友人や友人雪寨を愛し、客を迎える
『士人』は清代の作家呉敬子が書いた小説で、全56章から成り、様々な人々が「名声、富、名誉」に対してど...
韓国文化 韓国人の教育方法は何ですか?
韓国の人々は教育を非常に重視しており、1930年代初頭にはすでに多くの学校を設立していました。 「子...
李白は模倣に満足せず、大胆に創作し、「北風歌」を書いた。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
南宋時代にはどのような特異な現象が起こりましたか? 2、3人の皇帝が皇太子に譲位した
歴史上、父と息子が殺し合ったり、兄弟が王位をめぐって争ったりする話は数え切れないほどある。私たちはそ...
後漢末期の作家曹操:「九漢行」に関する注釈とコメント
『九漢行』は、後漢末期の軍事戦略家であり作家でもあった曹操が高干を征服した際に書いた楽府の詩です。肖...