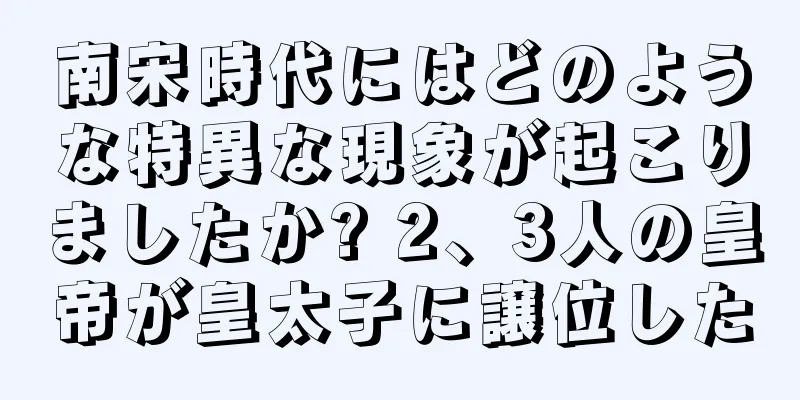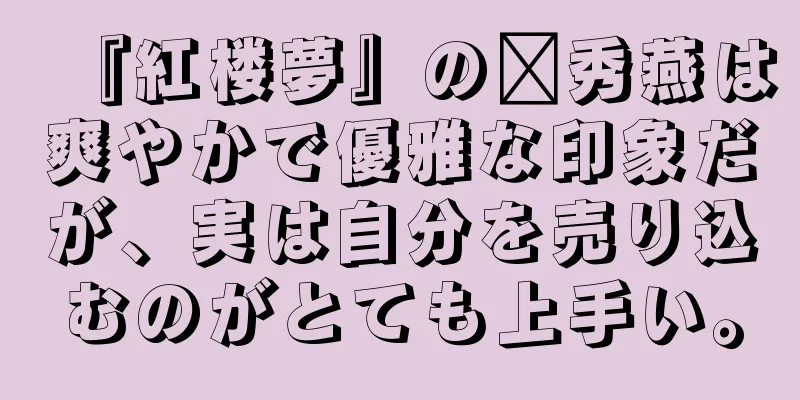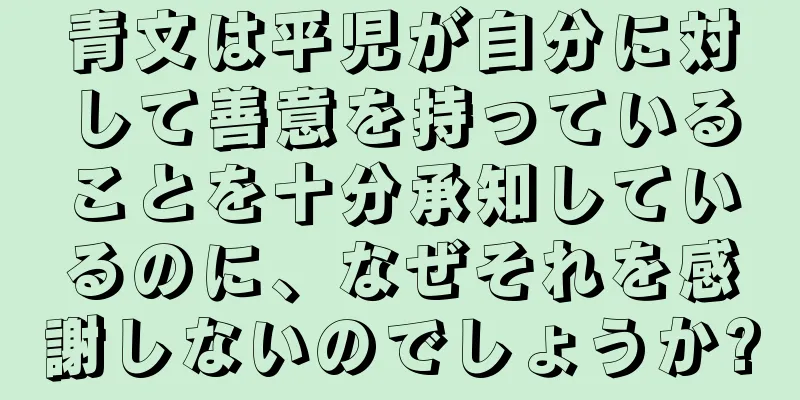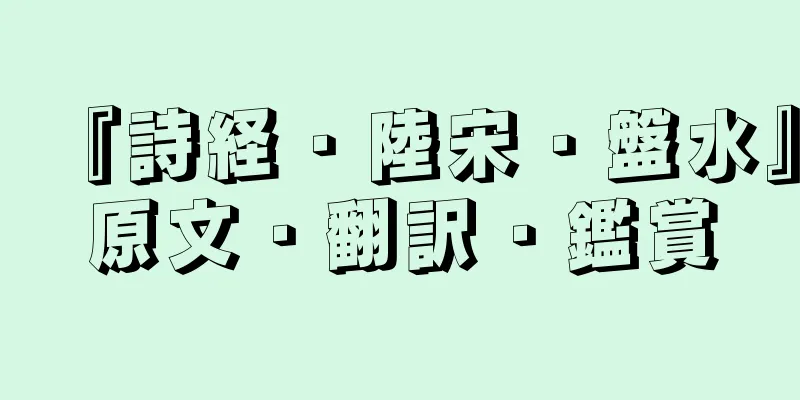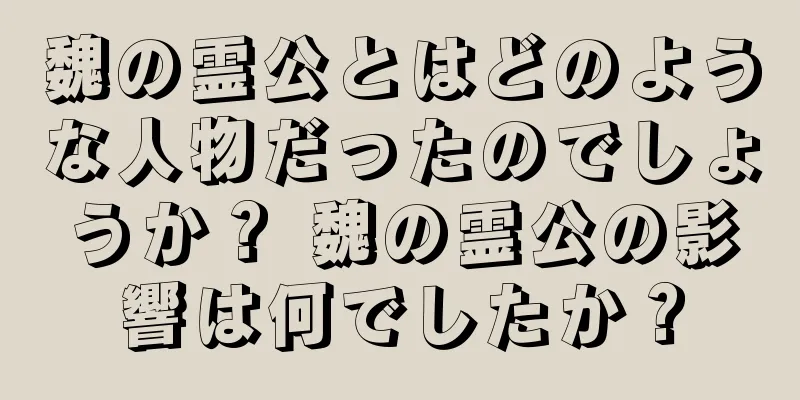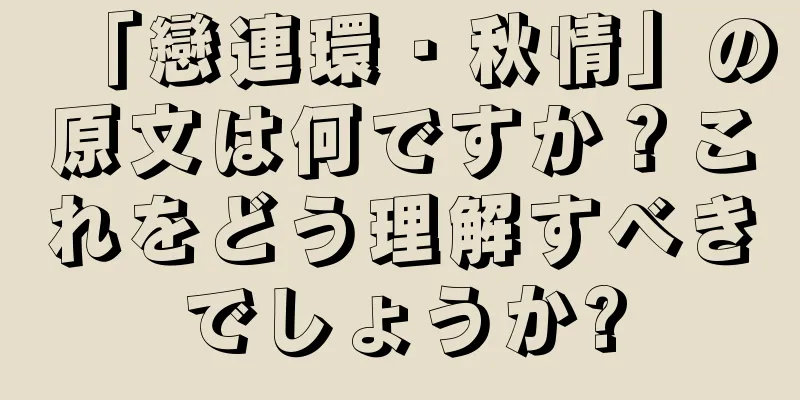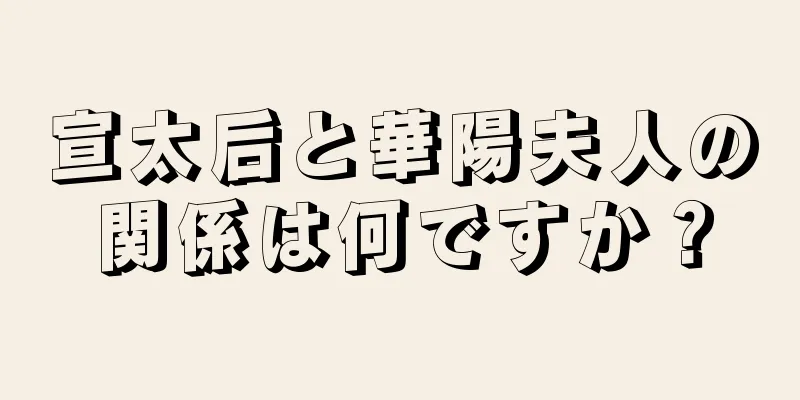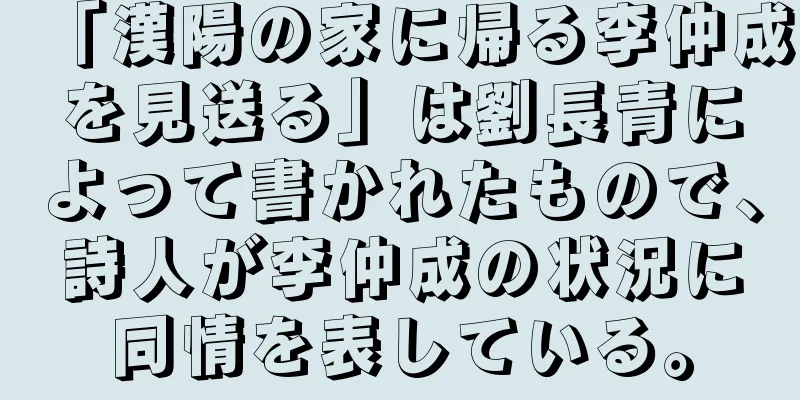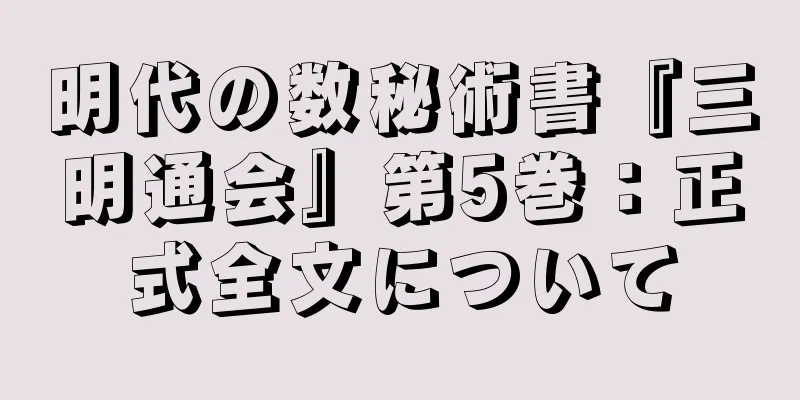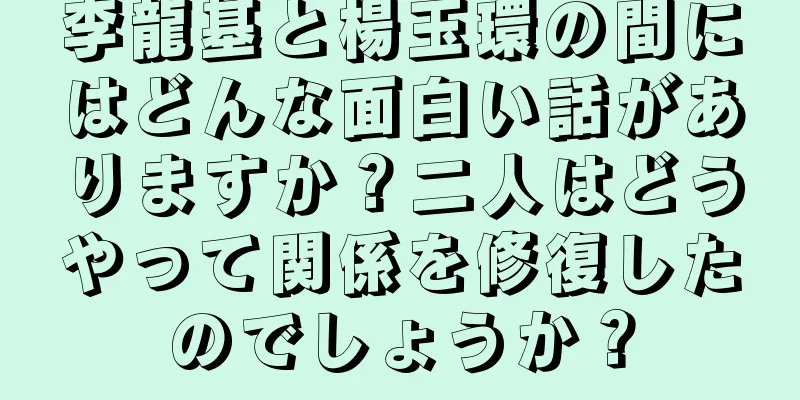なぜ文明開化運動や百日天下の改革は明治維新に繋がらなかったのか?
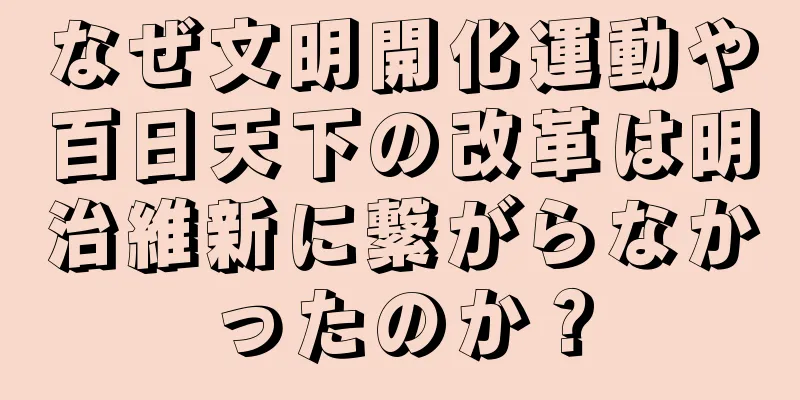
|
約150年前、日本では明治維新が始まり、同時期に中国では文明開化運動とそれに続く百日天下改革が起こりました。前者は大成功し、島国である日本は急速に近代国家へと向かったが、後者は失敗に終わり、清朝は欠点に固執し続け、最終的には崩壊した。 両国が同時に改革を進めた結果の相違を示す最も良い例は、1894年から1895年にかけての日清戦争における清政府の敗北である。中国の損失は、朝鮮戦争に敗れて撤退し、台湾と澎湖諸島を失ったことに加え、賠償金として支払われた銀2億両をはるかに上回るものであった。日本の関連資料によると、日本が獲得した賠償金と略奪品の総額は約3億6千万両銀、日本円に換算すると5億1千万円にのぼり、これは当時の清国政府の2年半の財政収入総額に匹敵し、当時の日本の年間収入の6.4倍(3.8倍という説もある)に相当した。日本はこうして戦争の甘さを味わい、軍国主義的な侵略と拡張の道を歩み始めたのである。中国から得た莫大な富のおかげで、日本の経済力と軍事力は急速に拡大し、1930年代の中国に対する本格的な侵略戦争の基礎が築かれました。 両国の改革の結果が全く異なっていることを嘆くとき、よく次のような疑問が持ち上がる。「大清」の文明開化運動とそれに続く1898年の改革開放運動は、なぜ「小日本」の明治維新にはならなかったのか。この問題を考えることは、決して古い歴史の記録にとらわれることだけではない。そのより大きな意義は、歴史を鏡として、今日の中国の改革開放がどこに向かうべきかを考えることにある。 Phoenix.com には、この問題を 4 つの側面から体系的に分析した特別記事があります。 1] 改革の基盤は異なっていた。清朝には日本のような有利な条件がなかった。日本には地方分権と自治権があったが、中国には高度に中央集権化されていた。日本は外の世界に対して閉ざされていたが、世界を理解するためのチャネルがあったが、中国は外の世界に対して閉ざされており、外の世界について何も知らず、興味もなかった。 2] 日本の幕府打倒は多数派と少数派の共同の努力であり、改革の主体は強力な武士商人同盟であった。一方、文明開化運動は、先見の明のある清朝の少数の役人による多数派を覚醒させるための苦い試みであった。 3] 明治政府は社会の最下層で近代化を推進し、日本人は清国の人々よりも重い税負担を負うことを可能にした。清国政府は文明開化運動を支援するために重い税金や賦課金を課し、農村部の人々の生活は衰退した。 4] 明治維新により、中央集権的で効率的な政治権力を持つ近代的な国民国家が誕生したが、清朝は伝統的な制度を維持し、西洋化によって地方政府が拡大し、国の分裂につながった。 この分析記事は根拠、論理、客観性に欠けるところがなく、人々に多大なインスピレーションを与えていると言えるでしょう。しかし、よく考えてみると、何かが欠けているように思えます。私の意見としては、その内容を改善し、表面的な結論を避けるという観点から、少なくとも 2 つの簡単な追加を行う必要があると思います。 (1)原文は、社会背景を深く分析し、中国と日本の思想・文化の軌跡の違いを明らかにすることができなかった。これが清朝の改革運動の失敗のより深い理由であった。 簡単に言えば、5000年の文明の歴史を持つと主張する中国は、振り払うことのできない重い思想的、文化的重荷を背負っているのだ。当時の清朝支配階級の典型的な主流概念では、偉大な中国は文明世界を代表する「天の帝国」であり、外部の世界はいくつかの未開の「蛮族の国」に過ぎませんでした。支配階級はうぬぼれと自己中心的な精神に満ちている。 この傲慢な精神を悪化させるもう一つのより深刻な思想的欠陥は一元論です。この難題は、西漢時代に董仲舒が「すべての学派を廃し、儒教のみを尊重する」と唱え、中国の春秋戦国時代に各学派が始めた「百花繚乱、百家争鳴」の優れた伝統を窒息させたことから始まった。それ以降、個々の王朝や正統な思想を除いて、異なる思想や教義についての議論は許されなくなった。支配階級を賛美する独裁政治が蔓延している。 「奇妙な考え」や「異端」を唱える反対派は最大限に抑圧され、死刑に処されることさえ望まれている。 林則徐と魏源の『海国図録』は1852年にようやく完成し、全100巻となった。これは「外国の先進技術を学んでそれを制御する」という啓蒙思想が初めて提唱されたものである。この本はその後の日本に大きな影響を与え、明治維新のきっかけとなり、天皇や大臣たちの必読書となった。中国では、この本は上流階級に無視されただけでなく、非難もされました。 1877年、中国の初の海外公使である郭松濤は日記形式の『西遊記』を著し、西洋の先進的な経営や政治・宗教制度を清政府に紹介し、政府もそれに倣うよう提案した。その結果、郭松濤は清朝の朝廷から叱責され、その原稿は破棄された。黄遵憲は4年間日本に駐在し、顧問を務めた。1887年に『日本史』という原稿を完成させた。この原稿には、明治維新後の10年近くにわたる日本の政治体制やさまざまな面の変化が詳細に記されていた。黄遵憲は、日本はもはやかつてのような「蛮国」ではないと信じていた。李鴻章や張志東などの高官らが総統衙門に勧告したが、何も起こらなかった。この本が著者の自費出版で出版され、世界中で人気を博し、センセーションを巻き起こしたのは、日清戦争が終わり、屈辱的な下関条約が調印された1895年のことだった。これらの本の運命から、清朝の宮廷が新しい思想に対して無知で拒絶的な態度をとっていたことが分かる。 長い歴史的伝統によって形成されたこの硬直した思考パターンは、極めて強力で頑固な惰性と怠惰を表しています。二度のアヘン戦争での血なまぐさい敗北でさえも、東洋の眠れる獅子である中国を目覚めさせることはできず、その結果、支配階級は西洋の「野蛮人」から学ぶことに極度に抵抗するようになった。先見の明のある少数のエリートや啓蒙された進歩的な人々は、「漢学を基礎とし、西洋学を実践に生かす」や「野蛮人から学んで野蛮人を制御する」といったことを主張することしかできなかった。最高権力者である西太后の承認と光緒帝の支援があったにもかかわらず、西洋化運動と短命に終わった百日改革に依然として少数の支持者がおり、巨大で腐敗した清朝官僚機構全体を揺るがすことができなかった理由は、理解しにくいことではない。 日本は違います。生存と発展の余地が非常に限られている島国として、日本には生まれながらの危機感があります。明治維新以前の歴史や文化には、外部勢力から学ぶという長い伝統があり、その最も典型的なものが「漢学」でした。明治維新では、西洋の学問、すなわち「蘭学」(オランダから伝来)が提唱されましたが、これはそれまでの「漢学」と思考様式において本質的な違いはなく、強者から学ぶ対象が変わっただけなのです。したがって、日本の明治維新における思想的、文化的抵抗と負担ははるかに小さいものでした。これが、中流階級や下流階級から幅広い反響を呼び起こし、最終的に大きな成功を収めることが容易である根本的な理由です。 (2)少数の満州族王朝が大規模な漢民族を統治していたため、清朝は常に政治的危機感に直面していた。これは、「清風は読めないのに、なぜわざわざ本をめくる必要があるのか」といった文学的な尋問からもわかります。彼が中国を統治した2世紀半の間、最も不変だった国家政策は「漢民族を漢民族から守り、漢民族を漢民族の支配に使う」ことだった。彼は「国内の奴隷に与えるよりは友好国に与える方が良い」とさえ言った。このような政治生態学においては、制度内でいかなる改革をも追求する際には、越えることのできない一線、すなわち清朝による漢民族の支配を危険にさらしてはならないという一線がなければならない。これはまた、孫文が「韃靼を追放し、中華を復興する」という旗印を掲げた根本的な理由でもある。 そのため、体制内部での文明開化運動や1898年の改革運動は、当初から表面的な改革しか達成できない運命にあり、政治や社会体制の根本的な変化を期待することは不可能であった。実際、過去数十年間にわたる西洋化運動の主な成果は、基本的に軍事や産業などの限られた分野に限られていました。その後の1898年の改革運動では、康有為と梁啓超の提案の多くが清朝のタブーに違反していた。保守派はこれを口実に改革運動を「中国は守っても清朝は守らない」と批判した。百日天下の改革は西太后の突発的な行動によって頓挫し、康有為と梁啓超が国外に逃亡、光緒帝が英台に投獄され、1898年の改革運動の六君子が処刑されるという悲劇的な結末を迎えた。 しかし、日本の明治維新は根本的に違っていました。特にこの島国には民族問題がなかったのです。改革派は、中下級武士や商人などの強大な権力をフル活用するとともに、「天皇を君主に統べる」という同様の戦略を採用し、尊皇の旗印を掲げ、中国の清朝とほぼ同じ長さだった徳川幕府の統治を一挙に打倒し、改革の最も重要な基盤、条件、無限の可能性を提供した。一言で言えば、明治維新は、まず政治・社会制度の改革であり、次に科学技術や産業などの分野における西洋化改革でした。 上記の 2 つの基本的な側面に加えて、国の大きさや国民性などの要素も二次的な要素となります。インターネット上のいくつかのオリジナルテキストでは、すでに他の重要な側面が非常によく説明されています。詳細については付録を参照してください。 付録:「文明開化運動はなぜ明治維新に繋がらなかったのか?」 はじめに: 150 年前に起こった明治維新は、同時期に東の隣国で起こった文明開化運動と常に比較されてきました。文明開化運動の最終的な失敗と明治維新の大きな成功を嘆くとき、私たちはそれらの発展を決定づけた要因は何であったのか、そしてなぜ文明開化運動は明治維新にならなかったのかを考えなければなりません。 1] 改革の根拠は異なっていた。清朝は日本のような有利な条件を持っていなかった。 同じ時期に行われた改革ではありますが、文明開化運動と明治維新の根幹は当初大きく異なっていました。スタートラインで両者に差が開いた。 日本は分権的な自治権を持ち、中国は高度に中央集権化されている 日本は中央集権国家ですが、地方レベルではある程度の地方分権化が進んでいます。日本の地方分権化の特徴は、同じく中央集権制を採用している中国とは大きく異なっており、言い換えれば、中国の長年にわたる絶対的な中央集権化と比較すると、日本は欧米諸国の分権化の特徴を備えていると言えます。そのため、唐徳剛氏は『清末七十年』の中で次のように書いている。「一部の人々は、明治維新以前の日本の社会構造は、封建時代後期の西欧の社会構造と非常に類似していると考えている。そして、この類似した構造は、ヨーロッパの「産業革命」の温床である。日本にはこの温床があり、準備ができている。したがって、西欧と接触すると、東洋の産業革命が発生する。この「ヨーロッパの社会構造」理論は、その機会をうまく説明できる。」 日本は閉鎖的な国だが、世界を理解するチャンネルはまだある 16世紀以降、主にオランダ人によって西洋の自然科学や技術が日本に導入されました。研究は主にオランダ語で行われるからです。日本人はこのような知識を「蘭学」と呼んだ。 1633年から1639年にかけて、幕府は日本と外国とのあらゆる交流を制限する「鎖国令」を5回連続で発令した。長崎だけが中国とオランダとの弱いつながりを維持していた。しかし、蘭学の普及により、日本人は中国学の欠点と西洋の科学文化の進歩に気づき始め、1720年に第8代将軍徳川吉宗がついにオランダ書の輸入禁止を解除した。その結果、日本の知識層の間で「蘭学熱」が再び高まった。蘭学は主に医学、天文学、物理学などの分野で発展しました。日本人はオランダ語を通じて、地理学、博物学、化学などの近代西洋自然科学も学びました。一方、日本自体も明治維新以前には教育が発達していました。江戸時代末期には、男性の40~50%、女性の15%が読み書きができた。当時の識字率は世界で最も高かった。 中国は外の世界について何も知らず、興味も持たない閉鎖的な国です。 アヘン戦争でイギリス軍が大砲を使って国境を突破するまで、清朝の人々は国外の世界についてほとんど何も知りませんでした。 「世界に目を開いた最初の中国人」として知られる林則徐でさえ、実は外の世界についてはほとんど知らなかった。戦争が勃発するまで、彼はイギリス兵は陸地に到着すれば「永遠に死ぬ」と信じていた。彼は英国が中国産のお茶とルバーブを買わなければならないとさらに確信した。 「外国人がこれを手に入れられなければ、生き残るすべはなく、彼らはみな便秘で死んでしまうだろう」これは彼らが世界に対していかに無知であるかを示しています。林則徐でさえそうであったのだから、当時の清朝の一般臣民がどのような気持ちであったかは容易に想像できる。イギリスの大砲によって国の扉が開かれたにもかかわらず、清朝の国民は世界に興味を持っていなかった。アヘン戦争終結から22年後の1862年、幕府は貿易のため商船「千歳丸」を上海に派遣した。当時23歳だった高杉晋作(後に有名な「奇兵隊」を結成)は、視野を広げるためにこの船に乗船した。上海では、日本ではほとんどの家庭に知られているベストセラー本、魏源の『海国絵譜』が跡形もなく消え、知られていないことを知り、大きな衝撃を受けた。このことからも、清朝と日本とでは世界を理解し受け入れる姿勢に大きな違いがあることが分かります。 2] 明治維新が順調に進み、文明開化が困難だった理由 明治維新は、強力な多数派が主導した革命であったため、当然その過程は比較的スムーズに進みましたが、文明開化運動は、少数の先見の明のある人々の苦闘に過ぎず、頑固な多数派を揺るがすことはできませんでした。 幕府を倒すのは、多数派が少数派を倒すための共同の努力だった。 日本の改革機関は比較的規模が大きく、その方法も比較的洗練されていた。日本の明治維新の際、幕府の権力は非常に弱まり、極めて孤立した状況に陥りました。改革勢力は中下級武士(徳川幕府時代、日本の武士とその家族は全人口の6~10%程度を占め、武士が強かった薩摩藩では藩人口の25%を占めていた)を中心に、天皇を旗印に掲げ、幕府に対抗する有力諸藩と連携。拠点と軍隊を持ち、大多数の農民や民衆も積極的に討幕軍に参加・支援した。ブルジョワジー、封建領主、農民、その他の階級を団結させて強力な勢力を形成し、幕府の支配を速やかに打倒し、天皇に権力を戻し、改革を実行した。日本の政治体制を決定する過程で、明治維新が強固な大衆的基盤を持っていたことを証明する議論が起こりました。64件の請願があり、そのほとんどは下級武士と民間人からのものでした。そのため、強力な改革派が形成され、旧幕府体制を一挙に打倒しました。 明治維新が成功したのは、改革の主体が武士と商人の強力な同盟だったからだ。 日本の明治維新における主な改革者は、日本の中級および下級の武士でした。武士の多くは生計を立てるために副業や商売に従事し、中にはブルジョア階級と直接「特別同盟」を結び、ブルジョア的な経済活動を行う者もいた。したがって、日本の中級および下級武士は、実際には日本のブルジョアジーの代理人として行動していました。この同盟の武士エリートたちは、日本の後進性につながった旧体制に対して深い思索と合理的な批判を行い、既存の地位と権力を利用してこの変革を全面的に推進した。明治維新の主要指導者の多くは、それまでの幕府や藩の改革に参加し、豊富な政治経験を積んでいました。これらの「官僚型」エリートの指導の下、改革プロセス全体が「中央統制-権力掌握-政治体制の転換-経済の発展-全面的改革」の道に沿って一歩ずつ進み、各段階で最も重要な任務を一つずつ達成した。彼らは現実的で、断固として粘り強く、改革指導者の政治戦略と行政能力を存分に発揮した。先見の明があり、優れた才能と高い名声を備えたこのようなエリート指導者集団がいなければ、明治維新と日本の近代化の成果は想像もできなかったでしょう。 西洋化運動は、清朝時代の先見の明のある少数の役人による、大多数の人々を目覚めさせようとする苦い試みでした。 西洋化運動は、少数の先進的な「西洋化派」によって始められた自助運動でした。千年もの間、外界に対して鎖国を続けてきた中国では、こうした「外来のものを崇拝し、外国人にへつらう」という習慣に強く反対する、啓蒙されていない学者や官僚がまだ多くいる。西洋化派と頑固派の間では「西洋化運動」を始めるべきかどうかで激しい議論が交わされた。頑固な支持者たちは、西洋の学問を推進する西洋化運動を「礼儀、正義、誠実、恥の基本原則を放棄し」、「野蛮人を利用して中国を変える」という「災難」を利用しているとして「厳しく非難」した。その結果、西洋化運動は「過去30年間、噂に囲まれてきた」。易鑫が天文学と数学の学校を設立したとき、彼は頑固な支持者たちからの強い反対に遭遇した。衛仁太書記は手紙の中でこう書いている。「蛮族が攻撃を仕掛け、皇室社会に衝撃を与えた。彼らは頤和園を焼き払い、多くの民間人を死なせた。これは清朝が200年以上経験した最大の屈辱である。憎しみをもって和平交渉をするとき、朝廷は復讐を忘れてはならない。どうして蛮族から学べるだろうか?」権力を失い、後進性に陥り続けることを嫌がる中央政府と、依然として「天帝の夢」に浸っている学者の大半が強力な政治勢力を形成し、西洋化運動が本来の社会に何らかの変化をもたらすことを困難にしていた。 3] 近代化が下層階級に与えた影響:明治政府は清政府よりも下層階級から多くのものを奪うことができた。 明治政府も清政府も、国家権力を使って西洋の産業を発展させるにあたって、その資金をどこから調達するかという問題に直面したことは間違いありません。両者の解決策はまったく同じです。つまり、農民を搾取することです。しかし、なぜ明治政府は農民からより多くの金を搾り取ることができたのでしょうか? 明治維新の際の増税は、多数の農民一揆を引き起こした。 1873年、政府は「地租改正条例」を公布した。その主な内容は、「(1)課税の基準を従来の不安定な物資収受量から一定の地価に改める。(2)物納を現金納に改め、税率は地価の3%とする。(3)地主を納税義務者とする」というものであった。しかし、地租の課税基準については、旧来の年貢を下げない方針をとったため、地価の査定に際しては「できるだけ地価を引き上げるように努めた」ため、地方民の負担は重く、民衆の苦難は続いた。統計によれば、明治元年から明治10年、すなわち1868年から1877年にかけて、農民嫌がらせの件数は500件にも上る。なかでも、地租改正反対の代表的な一揆としては真壁一揆、伊勢一揆などがあり、山重県の農民一揆は政府にとって最大の打撃となった。頻発した農民一揆は、国家の重税や賦課金に対する民衆の反対を反映したものであり、明治初期における国家による民衆の略奪に対する抵抗でもあった。 清朝政府による西洋化運動のための重い税金と賦課金も、農村の生活の衰退を招いた。 混乱した財政・財政運営のもと、清朝政権の根幹をなす康熙帝の「増税しない」という厳粛な約束は期限切れの無効切符となり、「上流階級も下流階級も税金を納めなければならない」新しい客船に乗れなくなった。もちろん、康熙帝の約束は厳粛なものであったため、将来の指導者たちは表面上はそれを守らなければならなかった。つまり、「税金」は増やさず、「追加料金」のみを追加するということだった。年貢による「賦課」は全国に広がり、その数も膨大で、農民にとっては耐え難いものであった。地方政府は隠して追加の土地税を課しましたが、康熙帝の厳粛な約束を守るために「土地税」という言葉を意図的に避けました。一時期、「穆献金」「減税」「穀物値上げ」「貨幣穀物復権」など新しい言葉が次々と登場した。さらに、土地が豊かであればあるほど、負担は重くなります。各級政府は、地租のほか、国民の生活必需品である塩についても大騒ぎした。「塩さえ買えない」という言葉は、人々の生活苦を最も如実に表し、物価を高騰させた。 明治政府は下層社会の近代化を推進し、日本国民に清朝国民よりも重い税負担を負わせた。 1878年から1880年にかけて、明治政府は日本の近代的な地方自治体に三新法制度を導入しました。明治政府は、課税権の強化、税源の確保、手数料目的の合法化などにより、それまで無秩序だった府県財政を整理・制度化することで、地方財政制度の近代化を図りました。社会の下層階級に限定的な自治権が最初に導入されたことで、日本の地方制度の近代化が促進され、同時に国の官僚支配も強化されました。その結果、日本国民は清朝の下層階級よりも重い税負担を負いながら、改革や革新などの公共事業に従事することができた。学者が指摘しているように、「税金や賦課金が軽いのは専制政治の特徴である。なぜなら、国民に選ばれていない政府は、あまり高い税金を徴収する勇気がないからである。さもないと、国民が反乱を起こす。一方、共和制政府は、非常に高い税金を課す可能性がある。したがって、当時のイギリスとフランスの発展の重要な違いは、イギリス政府の平均税率がフランスのそれよりはるかに高かったことである。しかし、イギリスの税法は非常に公平であった。フランスでは、貴族など、税金を払う必要のない人がたくさんいる。まさに不公平な税法のせいで、フランスの平均税率はイギリスよりはるかに低く、大規模な公共サービスを実施する能力がない。」 4] 日本の近代政府は効率性が高く中央集権的であるが、清朝の保守的なシステムは遠心分離に向かっている。 文明開化運動と明治維新は二つの異なる方向に進みました。明治維新による近代国家建設の進展により、効率的で中央集権的な中央政府が樹立されました。しかし、旧態依然とした状況を維持するために開始された西洋化運動は、地方の有力集団の台頭を招き、その後の中国における軍閥分離主義の種をまいてしまった。 明治維新により、中央集権的で効率的な権力を持つ近代国家が誕生した。 当時、新日本が統一を果たす唯一の方法は、藩と藩主の封建制度を廃止し、朝廷直轄の郡制に置き換えることだった。明治維新政権は、旧封建領主の土地所有と臣民統治の権力を徐々に廃止していった。その後、政府の段階的な再編により、多くの旧貴族が中央政府から排除された。 「王政復古」「戊辰戦争」「国民の復帰」「廃藩置県」に至るまで、改革派は軍事力を担保に巧みな政治戦術を駆使して、わずか3年半で政権の本質を変え、国家権力を中央政府に返還した。明治維新により日本は封建国家から、天皇を存続させつつ議会を設立し憲法を施行する近代国民国家へと変貌した。新たな法的政治権力を確立する。四つの階級の平等に基づく近代国民国家を樹立する。これをもとに、明治18年に官制が改革され、日本の近代的な官僚制度が徐々に形作られていきました。それは、近代的な国家機構の中央集権的かつ効率的な特徴を備えています。 清朝は伝統的な制度を維持し、地方は西洋化を利用して拡大し、国は分裂した。 太平天国の乱の鎮圧により、中央政府の軍事力と財政力は徐々に地方レベルに分散されていった。文明開化運動の時代、軍事力で財を成した地方官僚たちは、清朝の統治を支える強力な軍事力を資本として、中央政府から継続的に財力を得て自らの権力を強化していった。李鴻章率いる地方の有力グループが西洋化企業のほとんどを支配し、中央政府との対話のための資本を強化した。しかし、地方の有力グループの偏狭さと利己主義は、彼らの地位が上がり続けても弱まることはなかった。彼らの「主な関心事は、地方の権力基盤を潜在的なライバルより優位にし、弱い中央政府と競争できるほど強く保ち、同時にこの政府で最も名誉ある大臣として仕えることに喜びを感じること」である。これが地方の独立と自己防衛につながった。彼らは、自分たちの重大な利益に関係しない限り、完全に目をつぶることができる。地方の独立と自衛の姿勢は、中国を特定の地方官僚が率いる勢力圏に明確に分割している。各圏は独自の財政収入と軍事力を所有し、自ら管理している。特に政府の命令が地方の利益を侵食する場合、中央政府をほとんど無視できる。当時は李鴻章や張之東などの地方官僚が実権を握っていたが、彼らは道徳や倫理を固く信じていたため、清朝に対して横暴な態度を取ることはなかった。しかしその後、中央政府の権力が絶対的に弱まり、帝政期における天皇への忠誠の思想が失われると、地方政府はますます傲慢になり、中央政府による制御が効かなくなり、最終的には軍閥分離主義の状況に発展しました。 結論:一時代の革命、すなわち、完成したすべての破壊と建設は、その国の社会生活の範囲を超えてはならない。この観点から見ると、文明開化運動と明治維新の運命は、それらが始まるずっと前から決まっていたことになります。近代化改革の成功は、社会全体の近代化に基づいていなければなりません。なぜなら、中世の下層階級に頼って近代、あるいは現代の上流階級を支えるのは不可能だからです。 |
<<: 1898 年の改革運動において、改革者たち自身はどのような間違いを犯したのでしょうか?
>>: MSGを発明した国はどこですか? MSGはどのようにして生まれたのでしょうか?
推薦する
李玉の詩「雨美人:風は小庭に帰り、庭は緑」には現実に対する不満と悲しみが込められている。
李郁は五代十国時代の南唐最後の君主であり、唐の元宗皇帝李靖の6番目の息子でした。李毓は皇帝の座に就く...
もし孫権が荊州に奇襲を仕掛けず、代わりに軍を派遣して合肥を攻撃したらどうなるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
張元安の「蘭陵王・巻真珠箔」:詩人は暗黙の慈悲の領域を暗くも優雅に表現する
張元干(1091年 - 1161年頃)は、字を中宗といい、呂川居士、真音山人とも呼ばれた。晩年は呂川...
慕容甫の部下は誰ですか?慕容甫の部下、龔野謙のプロフィール
公業千は金庸の小説『半神半魔』の登場人物。姑蘇慕容甫の配下の四将軍の一人。七下荘の主人。江南で二番目...
『紅楼夢』で薛宝琴はどこに行き着いたのでしょうか?彼女の結婚生活はどうですか?
薛宝琴は小説『紅楼夢』の登場人物で、四大家の一つである薛家の娘である。本日は、Interesting...
宋江はなぜ朝廷への降伏を主張したのでしょうか?恩赦を受け入れない場合、どのような結果になるのでしょうか?
誰もが『水滸伝』をよく知っているはずです。基本的に、私たちはみんな若い頃にこの有名な作品を読んだこと...
お茶を最初に発見したのは誰ですか?古代の人々がお茶を飲み始めたのはいつ頃でしょうか?
お茶を飲む習慣の起源は、いくつかの歴史的資料の中に見ることができます。 1. 神農時代:唐代の陸羽の...
古典文学の傑作『太平楽』:文学部第11巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
唐代の詩人李和の『天歌』の原訳、注釈、鑑賞
『天歌』は唐代中期の浪漫詩人李和が書いた仙境詩です。ご興味のある方は、Interesting His...
『前漢民話』第87話はどんな物語を語っているのでしょうか?
傑格図名標林世進車使命功績眉しかし、監察大将の地位が空席となったため、蕭王志がその地位に就くこととな...
嘉慶帝の二代目皇后、小河睿皇后の簡単な紹介
嘉慶皇后小河睿の簡単な紹介: 牛軾氏族の一員である小河睿皇后(1776-1850)は、満州の黄旗の一...
『紅楼夢』では、賈おばあさんには孫がたくさんいます。なぜ彼女は賈宝玉と林黛玉を好むのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
「封土令」はなぜ「あらゆる時代にとって素晴らしい計画」と呼ばれているのでしょうか? 「土地封建令」はどれほどの威力を持つのか?
今日は、おもしろ歴史編集長が「封土令」がいかに強力であるかをお伝えします。皆様のお役に立てれば幸いで...
なぜ12星座の中で有害なネズミが第一位なのでしょうか?
古くから伝わる有名な連句があります。「ネズミは大きくても小さくても、みんな老人と呼ばれ、オウムは雄で...
王希峰は家計を補うために持参金を何回質入れしたのだろうか?彼女の本当の意図は何でしょうか?
王希峰は家計を補うために何回持参金を質に入れたのでしょうか?これは多くの読者が気になる質問です。一緒...