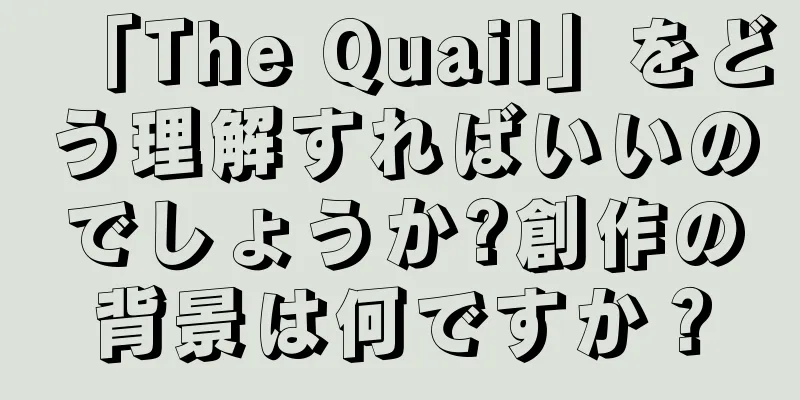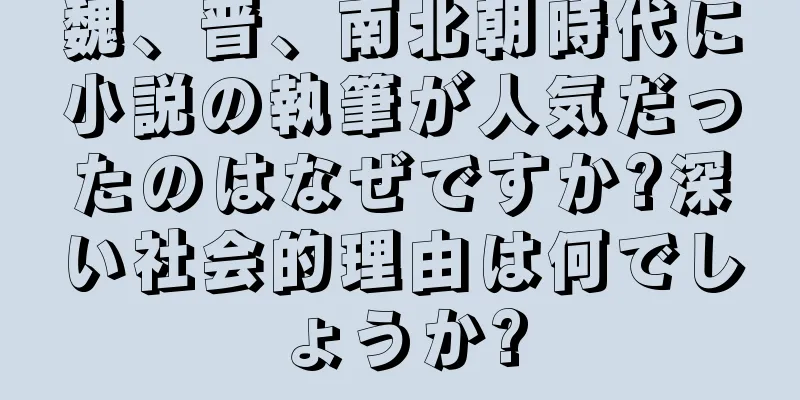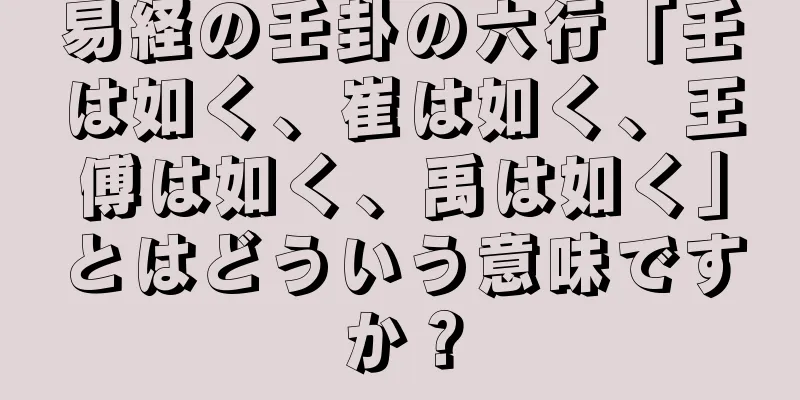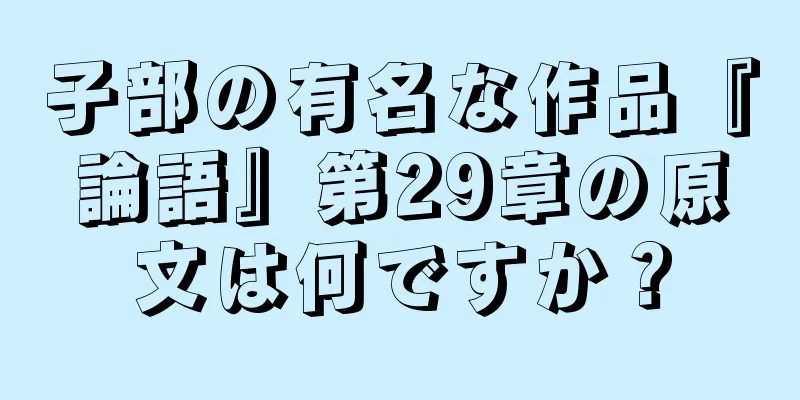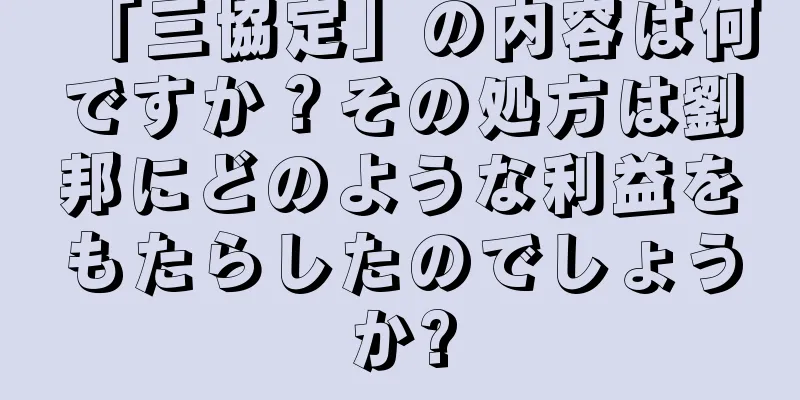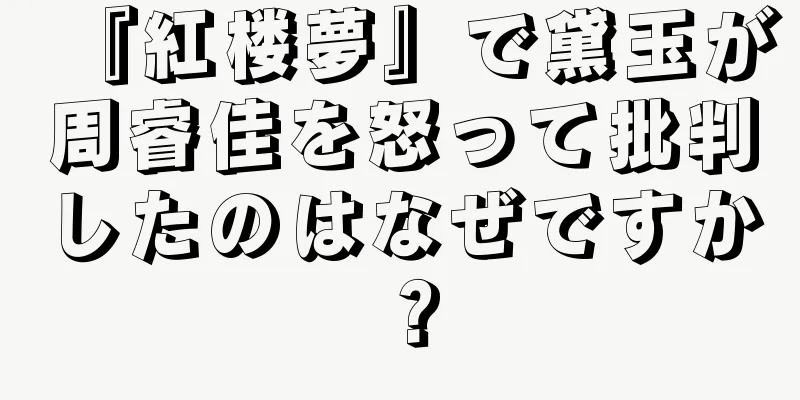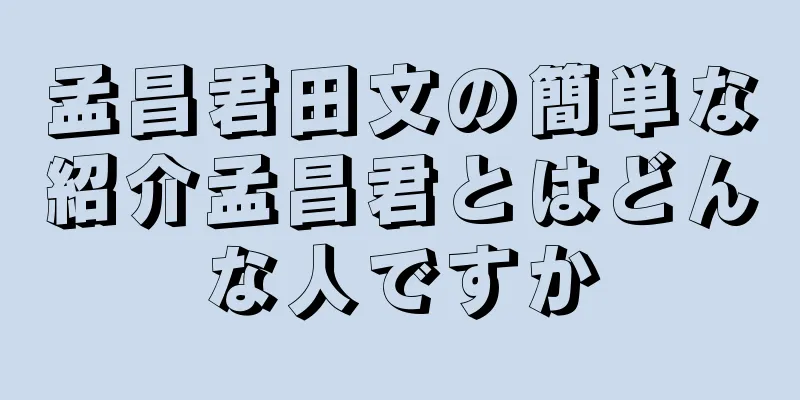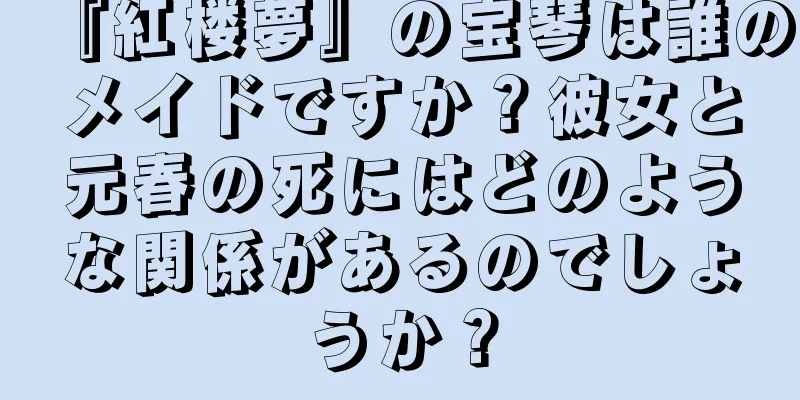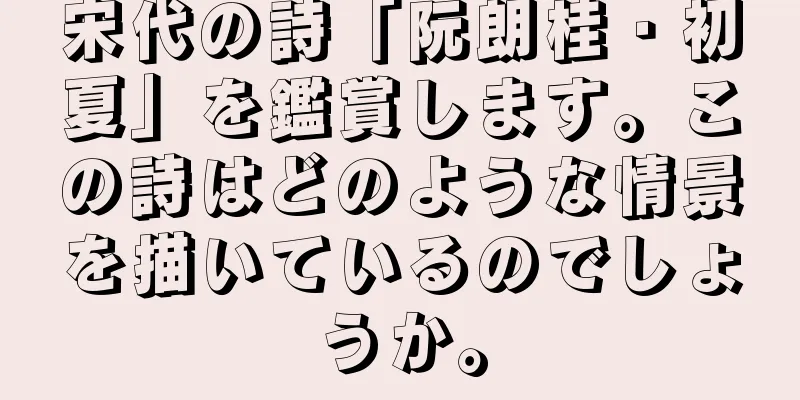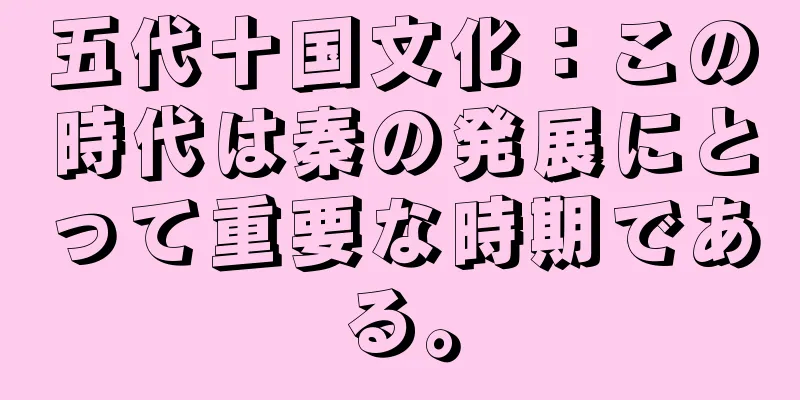日本の着物の過去と現在を紐解く:日本の着物の歴史
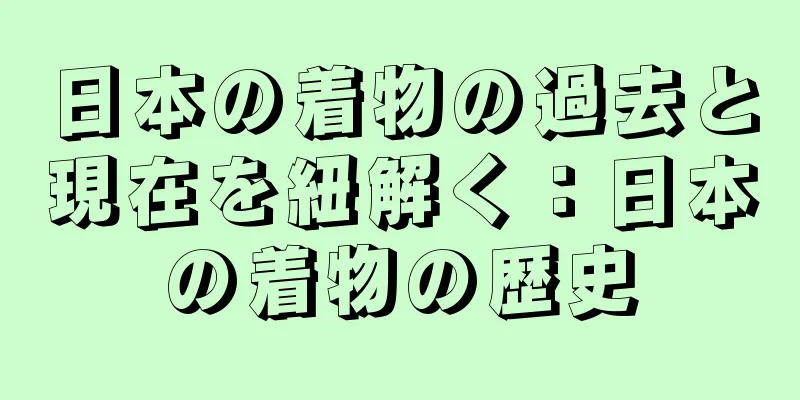
|
日本の伝統的な衣服といえば、誰もが日本の着物を思い浮かべるでしょう。着物は、ゆったりしたもの、細身のもの、優雅なもの、華やかなものなど、さまざまな形をしています。特に女の子はこのユニークな服に特別な感情を抱くはずです。次は日本の着物の特徴を理解していきましょう! 着物(わふく)の歴史は約1,000年です。中国の衣服が日本に伝わった最古の記録は、奈良時代に遡ります。奈良時代は中国の唐王朝の全盛期と重なり、日本は多くの学者や僧侶を中国へ留学させました。これらの使節は唐代の文化、芸術、法制度を日本に持ち帰りました。 「衣服秩序」は、奈良時代に唐の時代を模倣して確立された制度の一つです。 「衣服令」は正装、宮廷服、制服について規定している。奈良時代の衣服の色彩はより単純でした。平安時代になると、当時の国風の影響で衣服の色彩が多様化し、袖も広くなりました。 当時、古代の女性は宮殿に入るときや祭りに参加するときに「十二単」と呼ばれる一種の服を着ていました。それは唐服、単衣、外衣に分かれており、合計12層でした。鎌倉時代には元が中国を統一しました。何十回も日本を侵略した元の影響を受けたのか、貴族の贅沢が終わった後、戦闘を容易にするために衣服は簡素に戻り、広い袖は再び細い袖になりました。室町時代の特徴は、衣服に家紋がプリントされていることです。古代日本では、どの家にも苗字に応じた家紋があり、普段着のデザインがフォーマルな服装へと変化していきました。 桃山時代になると、場面に応じて着こなしを変えることが意識されるようになり、結婚披露宴や茶会などに着る「訪問着」(左肩、左袖から衿、裾にかけての模様)や、各種の祝賀会や成人式、宴会、合コンなどに着る「留袖」が登場しました。江戸時代は日本の衣服の歴史の中で最も繁栄した時代でした。この時代の着物は現代のスタイルに近づきました。今日私たちが目にする着物の多くは、江戸時代の衣服の特徴を引き継いでいます。明治時代になると、現在の意味での着物が形作られました。 日本では、茶道や生け花、文化的なパフォーマンスの鑑賞、さまざまな儀式への参加、伝統的な祭りのお祝いなどに参加する際には、美しい着物を着る必要があり、それが雰囲気を大いに盛り上げます。日本では毎年「ひな祭り」と「端午の節句」があります。日本の母親は子供たちに着物を着せて祝福します。伝統的な「七五三」の祭りでは、子どもたちは新しい着物を着て、両親に連れられて神社へお参りします。成人の日には、20歳以上の女性が未婚女性専用の着物である「振袖」を着て、成人したことを示す祝賀行事に楽しく参加します。 日本の結婚式では、花嫁は神聖さと清らかさを象徴する「白無垢」の着物を着ます。普段、主婦や仕事帰りの男性は、お風呂上がりに着物を着るのがお好きですよね。それが、新レーベル第1弾に登場する「浴衣」です。 絵画、演劇、舞踊、彫刻などの日本の芸術は着物と密接な関係があります。例えば、日本の民俗画である浮世絵に描かれた美人画は、着物と切り離せないものです。もう一つの例としては、演劇の中でダンサーが感情を表現するために長い袖を使うことがあり、時にはダンサーが観客に背を向けて、観客が着物の美しさを鑑賞できるようにすることがあります。 日本の着物の着方は、非常に複雑で特殊です。女性を例にとると、着物を着る場合、一番内側はぴったりとしたペチコート、その下にはぴったりとしたアンダーシャツ、その下にはロングシャツ、最後に着物を着ます。次に「細いストラップ」と「ポケット袋」を結びます。着物を着る時は裸足か布製の足袋を履き、外出時には草履や木靴を履くのが一般的です。日本の女性が着物を着る時は、必ずそれに合わせた頭飾りをつけなければなりません。 |
<<: モンゴル帝国の4つのハーン国とは何ですか?四汗国はどのようにして滅亡したのでしょうか?
>>: 魏文厚首相の選出:李克は中国史上最古の面接基準を確立した
推薦する
薛剛の反唐戦 第20章:薛剛が鉄丘陵を掃討、馬登が同城湖を救出
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
『易堅志』易堅定志第16巻の主な内容は何ですか?
胡飛英夢Chunxiの2年目、地元の学者であるZhang Xiは、Wushan Templeに行きま...
「高山に登る」は杜甫によって書かれた作品で、憂鬱と挫折を悲しい秋の風景に溶け込ませています。
杜甫は、字を子美、号を少霊葉老といい、唐代の写実主義詩人である。李白とともに「李都」と呼ばれ、後世に...
公孫勝が涼山を去った後、李逵は宋江に叱られるようなことを何をしたのでしょうか?
みなさんこんにちは。水滸伝の李逵といえば、みなさんも聞いたことがあると思います。 『水滸伝』で最も謎...
もし孫権が関羽を捕らえて曹操に送ることを選択した場合、曹操は関羽をどのように扱うでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
歴史記録によると、漢唐時代以降の西涼の音楽と舞踊の特徴は何ですか?
西涼の音楽と舞踊は漢唐の時代から古代涼州で始まり、中原に広く普及し、優れた評判を誇っています。 4世...
岳飛の「満江紅」は取り替えられました。もう一つの「満江紅」はどこから来たのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が「Man Jiang Hong」についての記...
「四大天才」の一人である徐振卿がなぜ周文斌に取って代わられたのか?
徐真卿は、唐寅、朱志山、文徴明とともに「武中四天王」の一人として知られています。しかし、映画やテ...
軍功制度:春秋時代になると、指名の基準は「血縁」ではなく「功績」になりました。
軍功制度の発展の歴史は何ですか?軍功付与の原則は何ですか?次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介...
魏延の「紫霧谷の策略」といえば、諸葛亮があまりにも臆病で、リスクを冒すことを敢えてしなかったからでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「閔中」という名前の由来:古代の医師はなぜ閔中と呼ばれていたのか?
宋代以前は、医師の名称はより複雑で、一般的には食医、病医、傷医など、専門分野に応じて呼ばれていました...
『紅楼夢』の賈屋敷で大晦日に何が起こったのでしょうか?
大晦日は古代で最も重要な祭りです。今日は、興味深い歴史の編集者がまったく新しい解釈をお届けします〜寧...
「翡翠を集める老人の歌」の内容は何ですか?詩「翡翠を集める老人の歌」の鑑賞
本日は、Interesting History の編集者が「翡翠を集める老人の歌」という詩の解説をお...
遊女・辛耀秦の結末は?なぜ油売りが遊女を独占できるのか?
辛耀欽は南宋時代の杭州の遊女であった。彼女は幼い頃、戦争で両親と離れ離れになり、売春宿に売られました...
元陽はどのようにして栄果屋敷の誰もが最も感謝すべき女性になったのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...