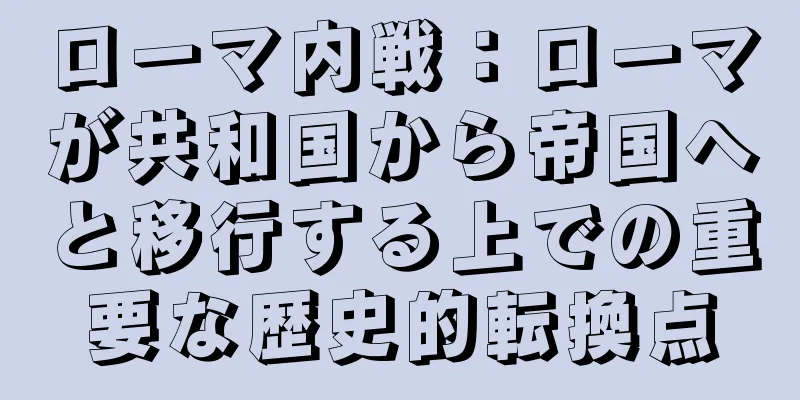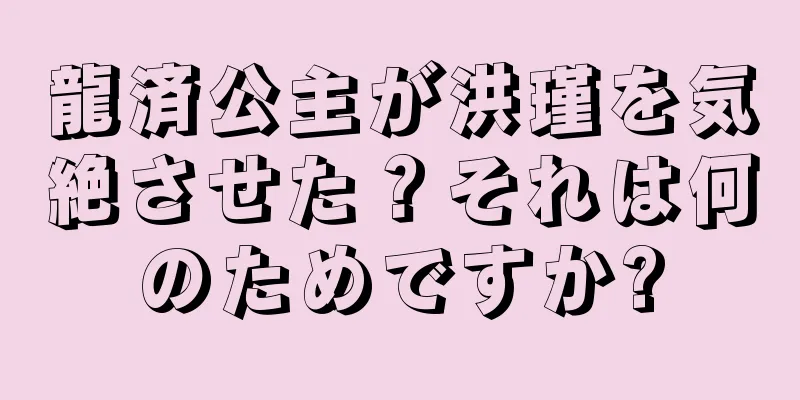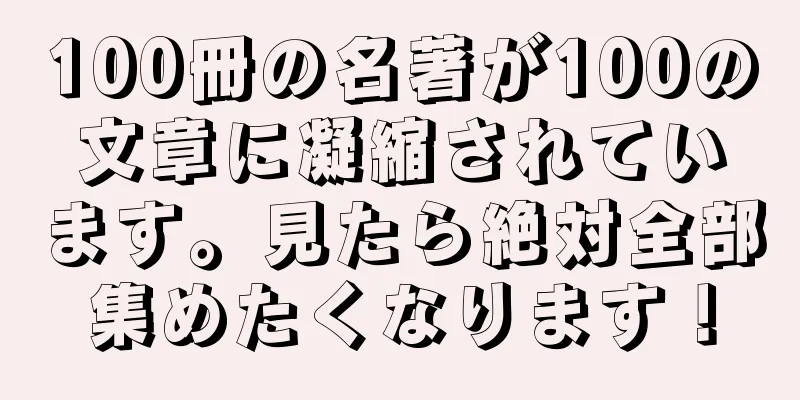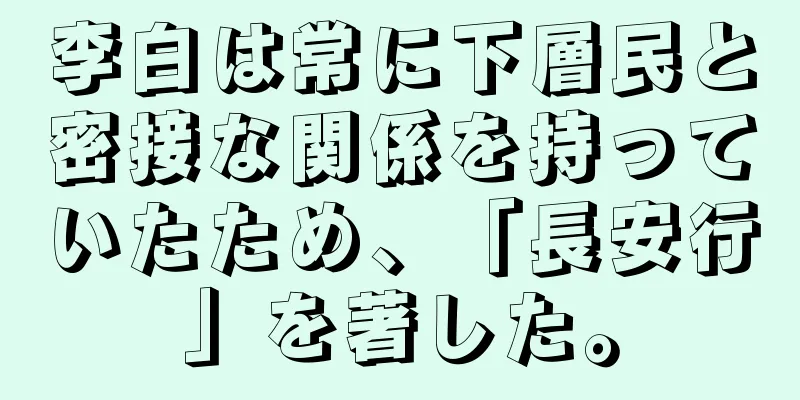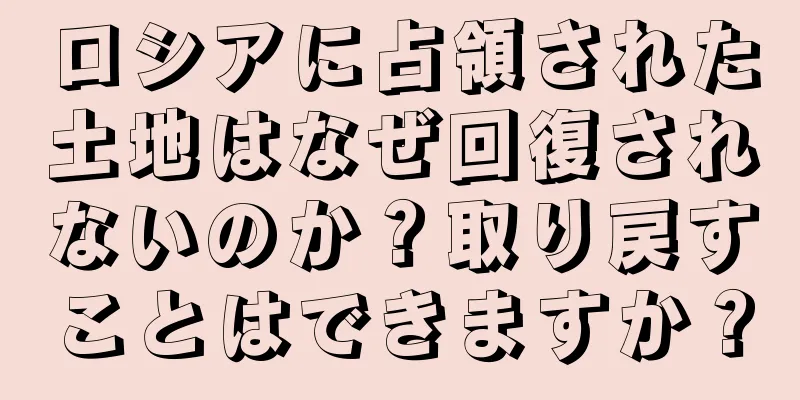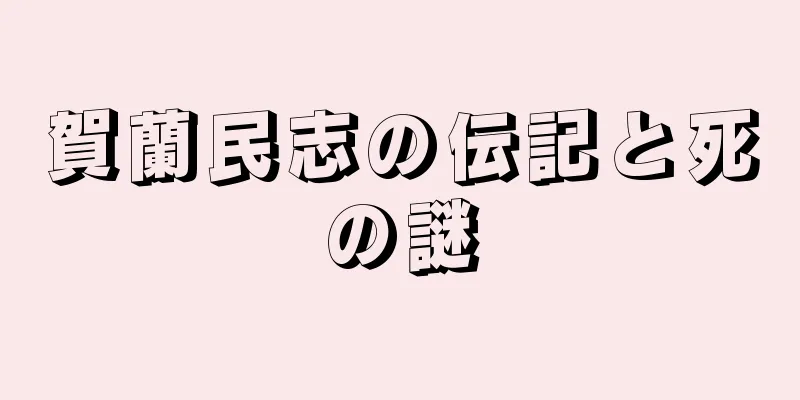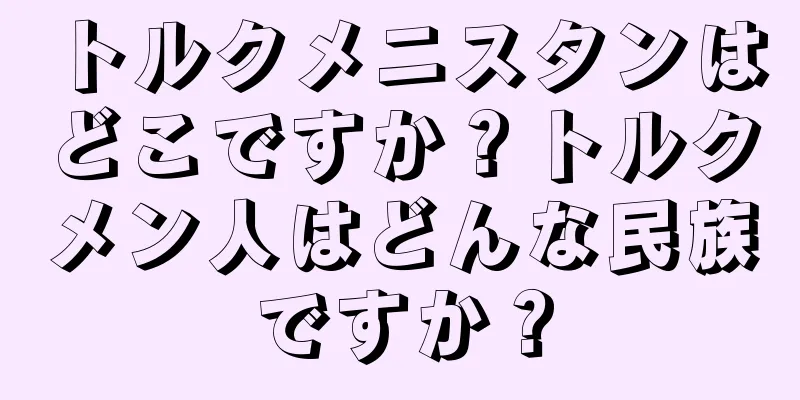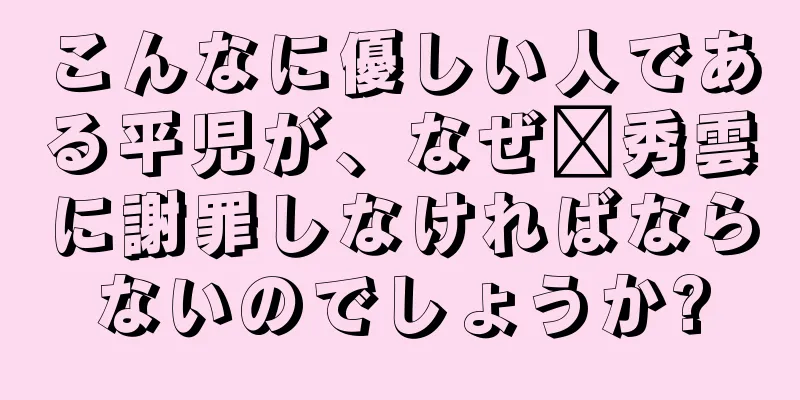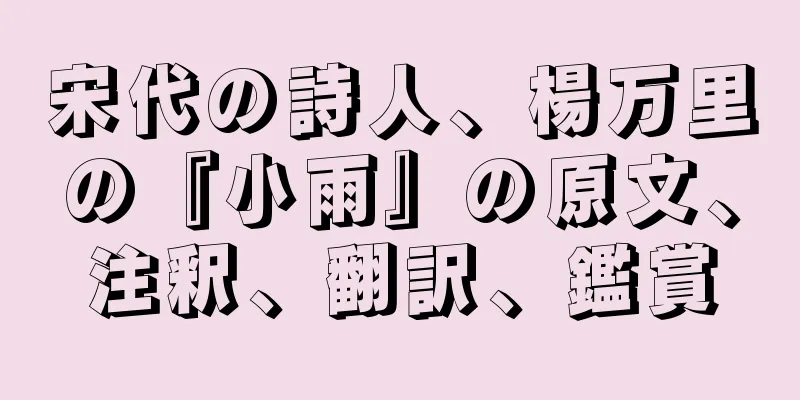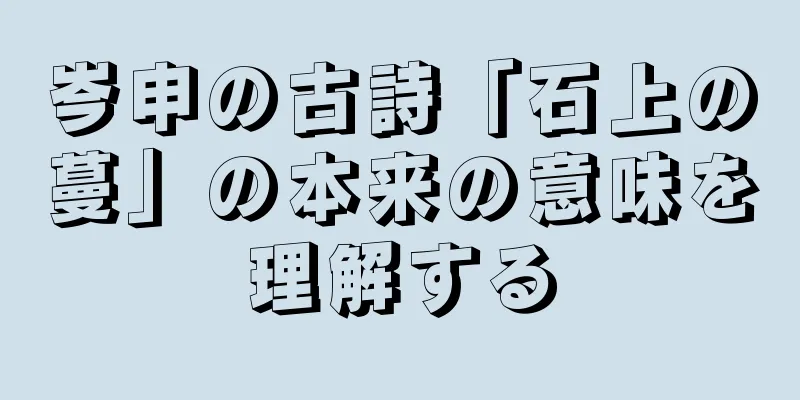古代中国のトップ10の名家
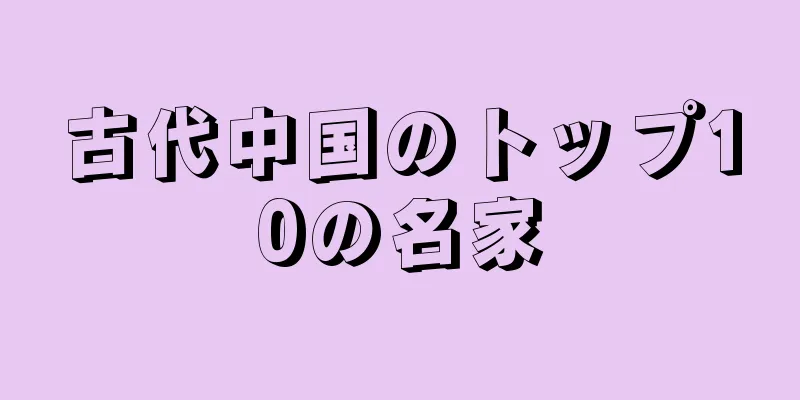
|
1. 龍西李家 龙西李家は李家の最も著名な一族です。古代、龍渓は龍游とも呼ばれ、一般的には龍山の西側にある甘粛省の東部地域を指します。秦漢時代には隴西県が置かれ、李姓の県の一つとなった。 秦の時代に竜渓県の最初の知事を務めたのは李充であり、後に竜渓李家の祖先として尊敬された。李一族は、李充の先祖と孫の三代にわたって隴西県の名家となった。李充の次男の堯は南郡の知事となり、地道侯の称号を授けられた。その孫の李鑫は将軍となり、隴西侯の称号を授けられた。漢代、龙渓李家からは将軍の李広とその従兄弟の李才という二人の重要人物が輩出されました。李広の孫である李凌は戦いに敗れ、捕らえられて匈奴に降伏したため、郡内での龙渓李家の評判は低下した。魏晋の時代、混乱の時代に隴西李一族が台頭し、西涼王李浩が李一族の初代皇帝となった。 隋代までに、龙渓李家は政府内で絶大な権力を持つ名家となった。隋の李氏の李淵は隋を滅ぼし、唐を建国し、李姓を国姓とした。唐代には、龍渓李家の名声は昭君李家の名声を上回った。唐の太宗皇帝は『氏録』を編纂し、李氏を貴族の姓の頂点に置き、功績のある官僚に李姓を授けた。それ以来、隴西李氏は血統制のある氏族から「多元的かつ統一された」巨大な氏族へと発展した。唐代の『姓氏系譜』には「李氏には13の大家があり、龍渓はその第一である」と記されている。南宋の鄭喬が『李氏故事』を編纂したとき、「李と称するものは隴渓のこと」と記されていた。後世、李家の多くの一族は自らを龍熙と名乗ったが、その中には捏造された者もいた。 2. 昭君の李家 昭君李家は李姓の二番目に大きな支族であり、龍渓李家に次ぐ。唐代以前は、その名声は龍渓李家よりも高かった。昭君は李姓の郡の一つです。趙県は現在の河北省趙県に位置し、後魏の時代に初めて県として設置されました。李家のこの支族の始祖は、秦の太夫李冀の次男李牧である。李季は、李龍渓家の祖先である李崇の四番目の兄弟でした。李牧は戦国時代の有名な武将です。趙国の宰相であり、武安侯の称号を与えられました。彼はもともと趙県に住み、趙県の李家の祖先でした。昭君李家は北斉王朝で重要な地位を占めていた。この一族には多くの分家があり、そのうち17人が唐代の宰相を務めた。龙熙李家に次いで2番目に大きな一族である。 3. 楊洪農一家 漢代に洪農県の所在地は現在の河南省霊宝にあり、華陰などを管轄していた。秦漢初期には楊氏の子孫が洪農に集中し、最も大きな影響力を持っていた。今日でも「天下の楊氏はすべて洪農から始まった」という言い伝えがある。楊洪農家は多くの人材を輩出しましたが、その中で最も有名なのは「四智」で有名な「関西の孔子」楊伯奇です。 『後漢書』によれば、楊震は号を伯斉といい、洪農華陰の人であった。彼は漢の光武帝30年(西暦54年)に生まれました。彼は当時の偉大な儒学者でした。彼は若い頃から勉強が好きで、「経典に精通し、徹底的に研究した」のです。当時の人々は彼を「関西の孔子、楊伯奇」と呼んでいました。彼は数十年間湖州で隠遁生活を送り、50歳で官吏として働き始めました。彼は何度も昇進し、ついに太衛になりました。 楊真は東莱の知事に就任する途中、昌邑を通りました。当時の昌邑の知事であった王密は楊真を推薦しました。楊真が昌邑を通り過ぎると聞いて、彼を訪ねました。夜、出発するときに、金十斤を取り出し、楊真に渡しました。楊震は言った。「私はあなたのことを理解しているのに、なぜあなたは私のことを理解してくれないのですか?」 王實は助言した。「今は暗闇です。誰も知りません。ただ受け入れてください。」 楊震は答えた。「天は知っています。神は知っています。私は知っています。あなたも知っています。どうして誰も知らないと言えるのですか?」 王實は恥ずかしさを感じて立ち去った。その後、楊震は卓県の知事に任命されました。彼は正直な役人であり、贈り物を受け取らなかったため、彼の子孫は貧困に苦しみました。彼らは馬車に乗る代わりに歩くことが多かったため、肉を食べることもできませんでした。かつての友人の中には、彼らのために土地を買ってあげたい人もいたが、楊震は「私の子孫が『誠実な官僚』の子孫として知られ、彼らにこれを引き継げたら素晴らしいと思いませんか」と言って断った。 楊震の子孫は彼の言行に影響を受け、皆博識で誠実であった。『後漢書』には「震から彪まで四代にわたり太魏であり、その徳と功績は代々受け継がれている」と記されており、そのため「東京の名家」となった。 洪農の楊家は「四智」を誇りとし、「四智」を堂宇名に、「清廉なる家」を門の額に掲げており、その伝統は今日でも見ることができます。楊震の14代目の孫である楊堅は、かつて強大な勢力を有した隋王朝を建国し、楊家の地位を頂点に押し上げました。北宋の楊将軍の祖である楊業は、楊真五男の楊鋒の子孫で、国に忠誠を尽くし、遼と戦って国を守り、五侯爵の家系で、歴史に名を残した。洪農楊家の落日とも言える人物である。 4. 太原王家 太原の王家の祖先は周の霊王の王子、晋公子である。彼の名前は晋、字は子喬。彼は紀元前565年頃に生まれ、紀元前549年に亡くなった。彼の元の姓は冀である。晋王の子宗景は後に司徒として仕えたが、周王朝の衰退と天下の混乱を見て、隠居を願い出て太原に住んだ。当時の人々はまだ彼らを王氏と呼んでいたので、彼らは王を姓として太原王氏の祖となり、金公を姓の祖として尊敬しました。宗景は死後、晋陽城の北5マイルの場所に埋葬され、その墓は「司徒墓」と呼ばれた。宗景の子孫は数が多く才能に恵まれ、太原の名家となった。その後、彼の子孫は増えて各地に広がった。 こうして太原は王家の二十一の地の最初の地となり、また王家の総称となった。 18代目の孫である王建公とその息子である王本、孫である王礼は、祖父と孫の三代にわたり、いずれも秦の名将であった。簡公は将軍、本公は典武侯、礼公は武霊侯と呼ばれた。秦が六国を併合して天下を統一したとき、簡公は北の燕国を征服し、東の楚の領土を平定し、南の白越を征服し、無敵で軍事的功績が目覚ましかった。始皇帝は功績に応じて人々に褒賞を与え、簡公と孟田将軍が共同で権力を握り、王姓と孟姓は世界で最も強力な一族となった。始皇帝の死後、二代皇帝胡亥が即位し、扶蘇王を処刑する勅旨を偽造し、孟天から軍事力を奪い、李公を将軍に任命した。二代皇帝は無謀な行動を取り、重い税金を課して民の生活を苦しめた。陳勝と呉広は反乱を起こし、劉邦と項羽はそれに応じて兵を集めた。李公は軍を率いて莞鹿で項羽と戦ったが、敗北して自殺した。長男の袁は戦争を避けるために山東省琅雅に移住し、「王家の琅雅の祖先」となった。 5. 琅牙の王一族 琅邪王家は高貴な王家の代表です。三国時代から唐代まで700年にわたり、琅邪王家は代々高貴で天下一の名家でした。代々名高い王翔のような孝行な息子を輩出しただけでなく、多くの宰相を輩出し、中国社会の安定と発展に大きな役割を果たしました。琅牙(現在の山東省臨沂市)の王家は、秦の名将・王離の子孫であり、古代中国の東晋から南北朝にかけての貴族の家系であった。陳君の謝一族と合わせて「王謝」と呼ばれる。琅牙の王家は、王族が南下した際に東晋政権の安定に大きく貢献し、「第一の名家」と呼ばれていました。司馬睿はかつて彼らと天下を分け合おうとしたと言われており、一時は朝廷の官僚の75%以上が王家出身者または王家と関係がありました。「王と馬は天下を分かつ」「王が女王でなければ宰相にならなければならない」と言われていました。漢代と唐代に丞相を務めた琅牙王氏出身者は計104人。2つの王朝の丞相を務めた者を除くと、実際には丞相は計92人いたことになる。彼らが宰相を務めた時期は、東晋と南朝に最も集中している。 当時、琅牙の王家は華僑の有力な一族であり、この一族だけで90人以上の宰相を輩出しており、これは実は古今東西を問わず、中国国内外で類を見ない出来事であった。そのため、「公爵・侯爵は代々受け継がれ、宰相は代々受け継がれる」というのが彼らの家の特徴となった。そのため、南朝の学者である沈月は、琅牙の王氏について「創建以来、王氏のように連続して爵位を享受した家系はかつてなかった」と評した。歴史上、郭、何、桓、張、袁、楊といった姓を持つ一族もかつては勢力を誇っていたが、琅牙の王氏に比べればはるかに劣っていた。琅牙の王氏は蝉冠を織り交ぜ、恭燕王朝を継承してきた千年の歴史を持ち、南朝以前にはこれに匹敵する家がなかっただけでなく、隋唐王朝以降もこれに匹敵する家はなかった。有名な書家、王羲之は琅牙の王家に生まれました。上昇したものは必ず下降する。南涼の侯景の乱の際、琅牙の王一族と陳君の謝一族は、同盟への嫁入りを拒否したため侯景の一族に滅ぼされ、それ以来姿を消した。 6. 謝陳俊一家 陳君謝家は、古代中国の東晋から南北朝にかけての貴族の家系で、陳君陽夏(現在の河南省太康県)に起源を持つ。琅牙の王氏、高平の西氏、毓川の于氏、桓県の桓氏に続いて、東晋最後の「有力貴族の家系」となった。宋代から梁代にかけて、常に貴族の家のリーダーであり、琅牙の王家とともに「王謝」と呼ばれています。 陳県の謝家は、もともとは平凡な貴族の家系に過ぎなかった。「謝家は江左の名家であったが、万・安兄弟の頃からその名が知られるようになった。謝宝の父衡は儒学者として知られていたが、帝室の学長に過ぎず、その業績は知られていなかった。……後に太夫となり、当時比類のない徳を積んだ。胡族や桀族の間で爵位を授かり、名誉と才能を競い合った。その結果、王家と謝家は同等に名声を得た。」謝尚の時代には、諸葛慧に求婚したが断られたという事件もあった。謝琬が就任して豫州を支配してから初めて王朝は勃興し始め、謝安が宰相を務めていた時代に最盛期を迎えた。陳君謝氏の最大の功績は、毗水の戦いで少数の軍勢を率いて大軍を打ち破り、東晋を救ったことである。毗水の戦いの後、謝一族のほとんどは社会から引退したが、彼らは依然として最も名声のある一族としての地位を維持した。 東晋から梁(317-557)の時代まで、歴史書には謝一族の12代、100人以上が記録されている。彼らの家柄は非常に高く、皇帝も時には彼らの影響力に頼らざるを得なかったほどである。謝家は多くの資産を持ち、その子供達の多くは才能に恵まれ、200年以上もの間貴族の家の長としてみなされていました。侯景の乱の際、陳君の謝一族と琅牙の王一族は侯景一族との婚姻を拒否したため侯景一族によって滅ぼされ、その後姿を消した。南北朝時代に隆盛を誇った王家と謝家が衰退した後、唐代の詩人劉玉熙は金陵を訪れた際に次のように感想を述べています。「かつて王殿や謝殿の前を飛んでいたツバメが、今では庶民の家に飛び込んでくる!」今日これを読むと、ため息が出ます。 7. 清河崔家 崔姓は西周時代の斉国に由来し、かつては山東省の名家であり、全国的に有名な姓であった。現在、人口規模順では中国の姓の中で74位にランクされている。斉国は、西周初期に周の武王から与えられた重要な属国の一つであった。首都は臨淄(現在の山東省淄博の北東)であり、建国者は呂尚であった。呂尚の本来の姓は江であったが、彼の先祖が呂(現在の河南省南陽市の西)の称号を与えられたため、彼はその姓を名乗った。呂尚の息子である丁公徽は斉の二代目の王である。嫡子は冀子と名付けられ、王位を継承するはずであったが、弟の叔易(易公徳とも呼ばれる)に王位を譲り、崔義(現在の山東省章丘県の北西)に移り、そこで食料や財産を与えられた。後に、彼はその町の名前を姓として崔となった。 季子の子孫は斉国の大臣を歴任した。9代目の孫である崔恆は斉の宰相であった。崔朱はかつて荘公と景公を皇帝に立て、右の宰相を務めた。 17代目の孫である崔一如は秦の時代の大臣で、東莱侯の爵位を授けられた。彼には伯基と鍾毛という二人の息子がいた。その後、一族は分家して繁栄した。 漢の時代から宋の時代にかけて、官吏の交代が続いた。魏晋時代から唐代初期にかけて、姓は貴族の身分に応じて「崔・呂・王・謝」または「崔・呂・李・鄭」のように順位づけられ、崔は一級姓として挙げられていた。宋代の『光韻』には崔一族は「清河と伯陵から来た」と記されている。清河崔家は漢代から隋・唐代にかけて中国北部で名を馳せた一族で、北魏時代には梵陽呂家、滕陽鄭家、太原王家とともに四大氏族の一つとして知られていました。南北朝時代の崔一族の著名人の多くは、清河東部の武城(現在の山東省武城西部)の出身で、北魏の人事大臣・白馬公の崔洪、宰相の崔浩、儒学者の崔霊恩、歴史家の崔洪、書家の崔月などがいます。唐代には崔国甫、崔昊、崔虎といった詩人がいた。また、宰相を務めた崔姓の人物は27人もおり、当時としては高い地位にあった。 8. 滕陽の鄭家 滕陽の鄭氏は古代の鄭国に起源を持つ。春秋時代の末期に鄭国は滅亡し、王族の子孫は他の地に移りましたが、彼らは皆、国の名前を名乗っていました。この方法は「国を姓とする」と呼ばれ、鄭という姓が形成されました。鄭氏の後代は、滕陽の名家へと発展した。東漢末期、鄭当流の鄭渾、鄭泰らから始まり、次第に名家へと発展した。南北朝時代、滕陽の鄭氏は代々高官を輩出しており、清河の崔氏、樊陽の呂氏、太原の王氏とともに、滕陽の鄭氏は中国四大名家の一つとされている。唐代以降、滕陽の鄭氏は相次いで9人の宰相を輩出し、さらに大臣、副大臣、軍知事など多くの人物を輩出した。その名声は頂点に達し、先人たちは朝廷で勤勉に働いたり、県や郡で教授したり、辺境で功績を立てたりして、社会の経済や文化に貢献しました。その後、科挙制度の実施により、その影響力は徐々に衰えましたが、それでも世界で最も著名な鄭氏の一門であり続けました。 9. ファンヤン・ルシ 歴史的に、呂家は樊陽、涛州(県)、または幽州の出身であると主張した。紀元前385年、田和が斉に代わると、呂氏と高氏は追放された。呂邑は山東省長清県を離れ、燕と秦の間に散らばった。主な支族の1つは樊陽に定住した。秦の始皇帝の時代、樊陽の呂家には有名な五経博士の呂敖や天文学博士の呂勝がいた。その後、西漢初期の燕王・陸湾、東漢末期に国内外で「学者の模範、国の柱」と称えられた偉大な儒学者・陸志(陸志の旧居は河北省涛州市陸家場)が范洋の出身である。魏晋南北朝と隋の時代、陸志の子孫である陸志、陸陳、陸延、陸妙、陸玄などは、すべて官家や学者の家系の出身でした。陸玄から曾孫まで、一族は百人ほどで、財産を共に暮らし、そのうち18人は歴史に名を残す名官であった。 皇室の息子は呂氏族の女性との結婚を希望しており、歴史には「梵陽呂氏には三人の王女がいた」と記録されている。皇室はまた、梵陽呂氏の娘を皇室の側室として迎えたいと考えていた。歴史家は、世界で最も有名な 4 つの姓、崔、呂、王、謝について、「これらは樊楊に由来し、北部諸州で最も有力な一族である」と言っています。この傾向は唐代に特に顕著で、科挙の成績優秀者を輩出しただけでなく、「唐代八臣補佐」や「初唐四英雄」の一人である陸兆麟や、「大理十傑」の一人である陸扁など、多くの優秀な人材を輩出しました。漢末から唐代までの600年以上の間に、正史に記録された呂氏の歴史上の著名人は840人以上にのぼり、樊陽呂氏からは多くの徳の高い人物、輝かしい業績を残した人物、有名な文豪が輩出されました。乾隆帝はまた、「昔から幽岩は比類のない場所であり、梵陽は天下第一の国である」という詩を書いた。梵陽の名家は数百年にわたり呂家の栄華を誇っており、呂家は「梵陽殿」とも呼ばれています。 10. 太原文史 温家の祖先は冀姓から来た。西周の唐叔は、名を禹、字を子禹といい、周の成王の弟であった。周公は唐(現在の山西省宜城の西側)を滅ぼし、唐の地を与えた。息子の謝が跡を継ぎ、南に晋江があったことから国名を晋と改めた。その後、金の王族は河内(現在の河南省温県)で温の爵位を賜り、これを姓とした。晋の高官であった西之は、文に領地を与えられて文季と名付けられ、それを姓としても名乗った。前漢の功臣である文潔は瓊侯の爵位を授けられた。文潔の孫である何世は太原に住み、名家となった。彼らの子孫は太原を郡名とした。 太原の文氏一族の有名人には、東漢の鄒平侯の文旭、北魏の涼州知事の文慧、南朝の皇室大夫の文献、南朝の将軍の文喬などがいます。最も有名なのは、唐代初期の文氏の三人の英雄、文大牙、文延伯、文大有の兄弟です。温家の三人の英雄は皆、大臣になれる才能を持っています。太原に駐屯する高祖李淵皇帝は彼に多大な贈り物を与え、李世民は彼とさらに深い友情を育んだ。文三兄弟は李家の父子を助け、太原の反乱を率いて劉武周を平定し、トルコ軍を破り、西へ南へと進軍して多大な貢献を果たし、唐代初期の有名な大臣となった。文大牙は礼公・礼相の爵位を授けられ、文延伯は尚書有普社の爵位を授けられ、太宗皇帝とともに昭陵に葬られた。文大有は中央書記・清河県公であった。文真、文廷、文季、文璋などの文家三大家の子孫は、主に唐代の公爵や官僚であり、その中でも文廷雲は唐代末期の「華厳学派」文学の名家であった。 文家は太原斉県の名家であり、多くの人材を輩出し、代々繁栄してきました。漢代から宋代まで、代々「王に仕えて堯や舜に劣らず、風俗を洗練させる」名官や賢人、あるいは才能ある詩人や画家を輩出してきました。中国文明の歴史において、このように繁栄した国家はほんの一握りしかありません。文家は王室から最も寵愛された家系の一つであり、庶民や官僚たちがその家系に入ろうと競い合う家系でもあった。唐の文宗皇帝でさえ、「李家は200年もの間天下を治めてきたが、王家に嫁ぎたいと望む人の数は、王家や文家などの名家に嫁ぎたいと望む人の数に比べて驚くほど少ない」と嘆いています。これは、文家の社会的地位が王族の李家に決して劣っていないことを示しています。 魏晋南北朝の貴族は、封建的大規模土地所有の継続的な発展と奴隷制度の残滓の頑固な存在という特殊な社会的・歴史的条件の下で出現した。当時、農民革命はまだ初期段階にあり、地方の有力者は分離主義的で、戦争が頻発し、中央政府は弱体であった。貴族は封建的大規模土地所有と奴隷制度の残滓の有機的な結合であった。隋唐の時代以降、こうした歴史的条件が消滅するとともに、貴族階級も消滅した。隋唐の時代、統治者は国家権力を強化するために、貴族の家を厳しく取り締まり、賤民の出身者を昇進させた。貴族の家系制度は歴史の舞台から完全に消滅し、上記の名家は栄華を失い、歴史の遺物となった。 |
<<: 黄色いローブを着た最初の皇帝は誰ですか?宋太祖趙匡胤ではない
>>: なぜ宋の高宗皇帝は兄の宋の欽宗皇帝の帰国を拒否したのでしょうか?
推薦する
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第100巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『三朝北孟慧編』第24巻の主な内容は何ですか?
政治宣言の第24巻。それは宣和定為七年十二月十日に始まり、仁子十五日に終わった。 10日目にオリブ(...
宋代の『辞 典江春 - 桃園』を鑑賞して、作者はどのような感情を表現しているのでしょうか?
典江春・桃園[宋代]秦管、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう!...
宋代の詩人が書いた酔っぱらいの詩には、飲酒が眠ることと同じくらい一般的であることが表現されています。
なぜ詩人は酒を飲むのが好きなのでしょうか。考えてみましょう。おそらくそれは、詩人が人生において別のレ...
清朝の4つの主要な統治基盤は何ですか?清朝の滅亡は四大統治基盤に関係していた!
清朝はなぜ突然崩壊したのか? 四大統治基盤はいかにして崩壊したのか?中国最後の封建王朝であった清王朝...
「雨柳行」は唐代の李端によって書かれた作品で、感情を呼び起こし、内面の悲しみを表現しています。
李端(本名:正義)は唐代中期の詩人で、大理時代の十傑の一人である。彼の詩のほとんどは社交の場で書かれ...
オロチョン族の最高の景勝地:オロチョン大厦湖国家森林公園
ダルビン湖国立森林公園達浜湖国家森林公園は、オロチョン自治旗内、ノミン川とビラ川流域の中上流域、大興...
南北朝の代表的な詩人の伝記:有名な「江南哀歌」を書いた于新
于鑫(513-581)は、字名は紫山、愛称は藍城としても知られ、北周の時代に生きた人物である。彼は南...
尚思祭とは何ですか?清明節と何の関係があるのでしょうか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が尚思節と清明...
三国志演義第10章:王家の忠実な一員である馬騰が父の仇討ちをし、曹操が軍を起こす
しかし、二人の盗賊、李と郭は献帝を暗殺しようとしていた。張季と樊州は助言した。「いや、今日彼を殺した...
【蓮葉杯・当時の出会いを思い出す】著者顧英、原文鑑賞
顧英九の詩「蓮葉杯」は、女性の恋煩いの全過程を描写しているようだ。この詩は、ある女性が恋人と密会した...
三国志演義には才能と勇敢さにあふれた男たちが数多く登場します。五虎将軍を倒せるのは誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
人間皇帝とは何ですか?人間の皇帝と天子の違いは何ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、皇帝と天子の違いについてお伝えします。皆さ...
趙公17年に古梁邁が書いた『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
『紅楼夢』で、寶玉に仕えるために派遣された希仁と王希峰との関係は何ですか?
希仁は『紅楼夢』の重要キャラクターです。彼女は『金陵十二美女』第二巻の二人目であり、宝玉の部屋のメイ...