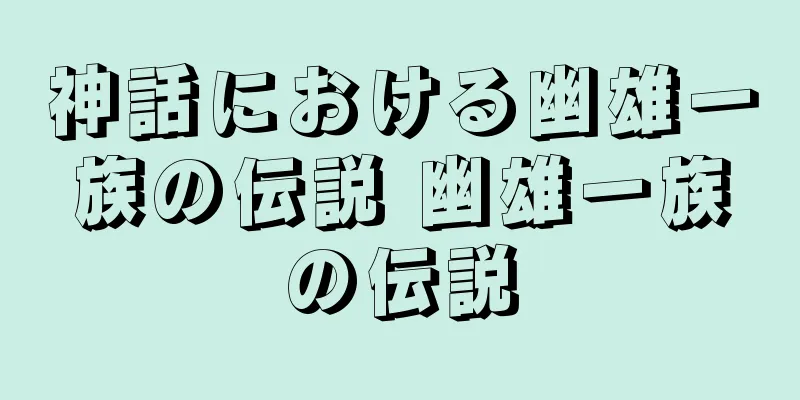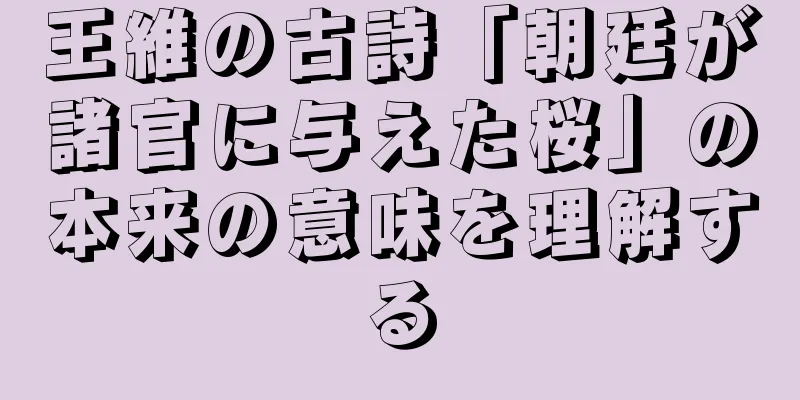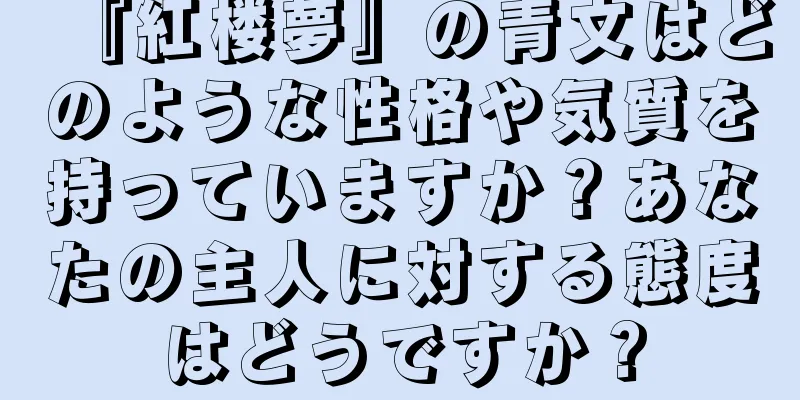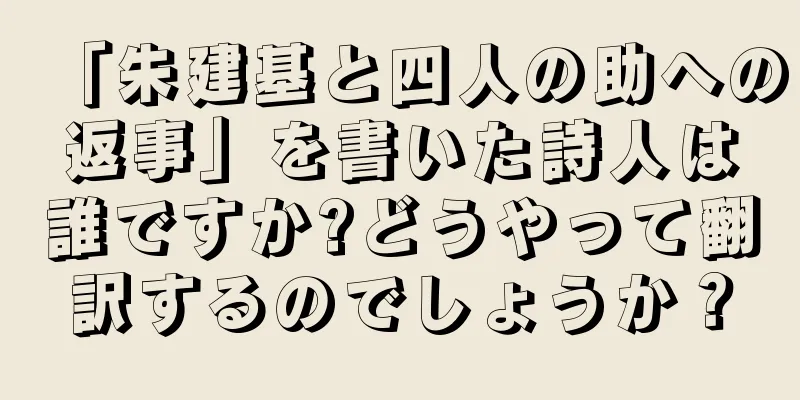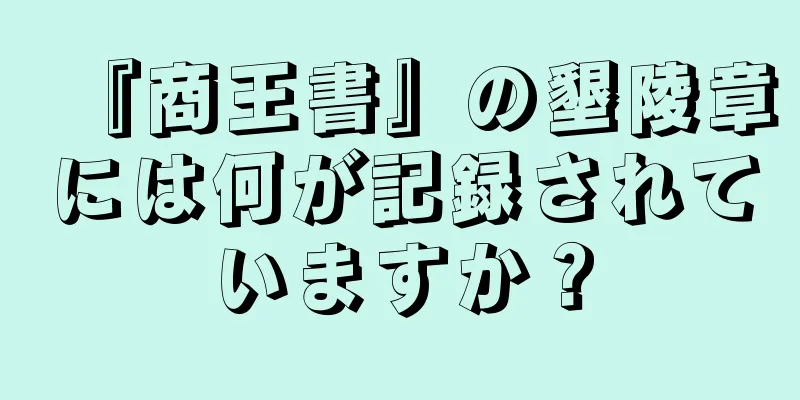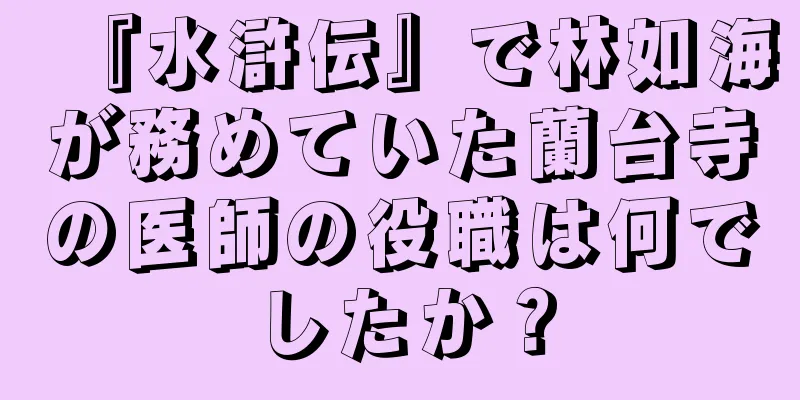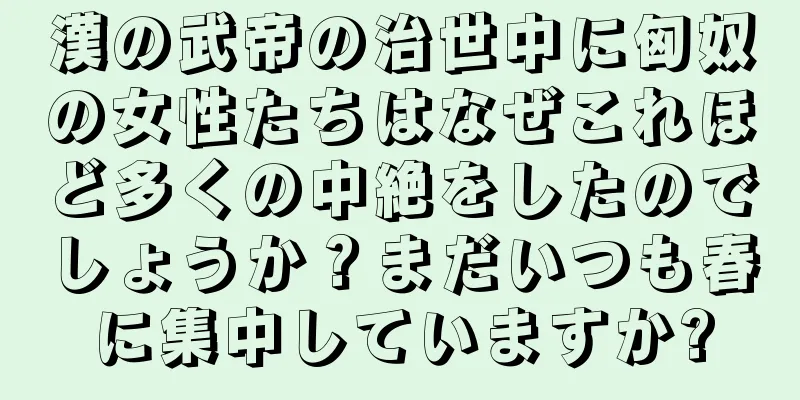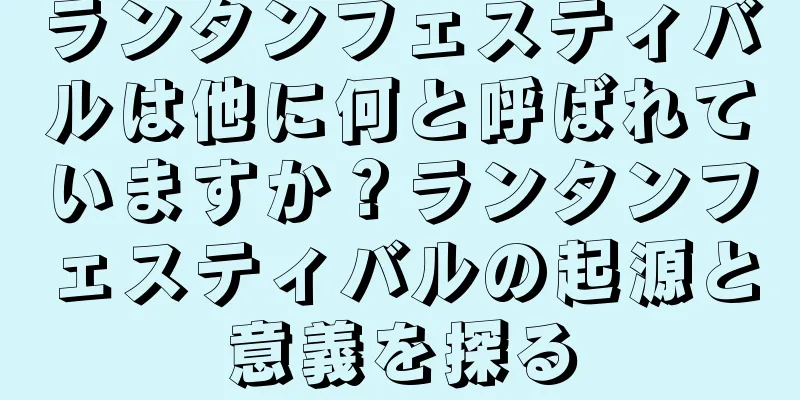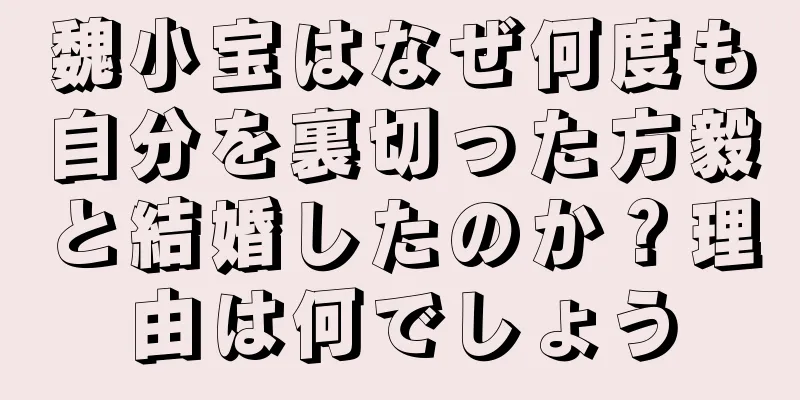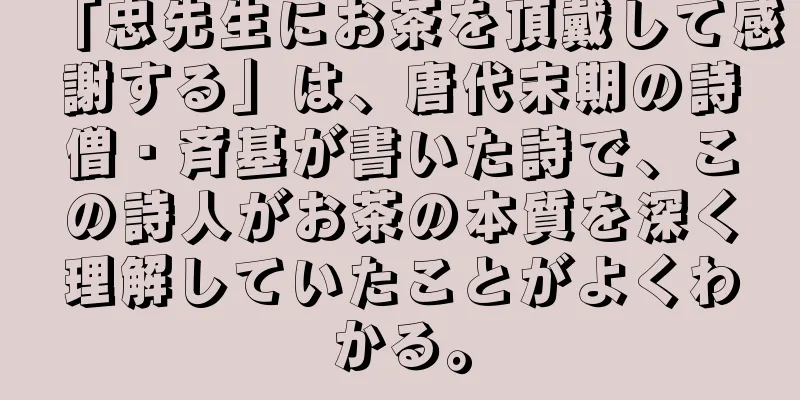当時の日本の知識人は日本軍の侵略犯罪をどのように見ていたのでしょうか?
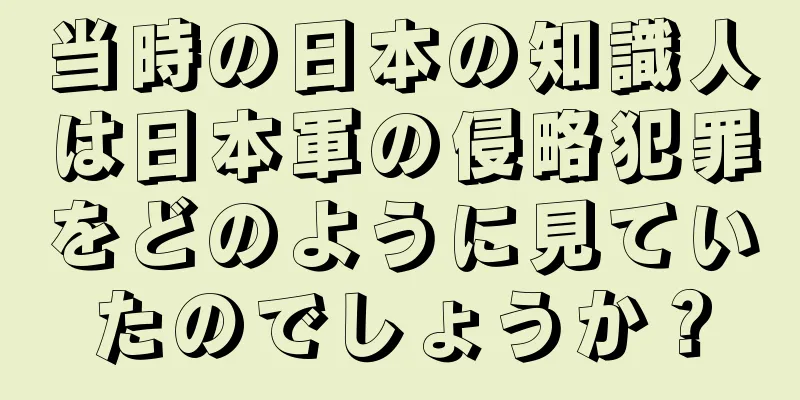
|
他人を見る目が鋭かった横光隆一が、どうして自国が道を踏み外したのか、東アジアで罪を犯したのか、どうして見抜けなかったのか。それなのに、彼は「人命を何よりも尊重する」という日本の「高い合理性」を語り、「今日の日本の叫びは『東アジアの平和』である」と宣言した。これは本当に大嘘であり、大ジョークである。(編集者注:横光隆一(1898-1947)は日本の著名な作家である。) 「首都に行ったとき、韓国のホテルの優雅さに感銘を受け、私はこう叫びました。「ここは間違いなく日本で一番のホテルだ!いや、これは誰もが評価する東洋の一流ホテルだ!」(『トラベル』) 韓国人や北朝鮮の人がこんな言葉を聞いたら、きっと著者の顔を平手打ちするでしょう!ここでの「首都」は東京でも京都でもなく、韓国の首都「ソウル」です。かつては「漢陽」または「ソウル」と呼ばれていました。日本が韓国を併合していた時期(1910-1945)に「脱中国化」のために「首都」に変更されました。同時に、朝鮮が「日本」の一部となったため、日本はそれに応じて「内地」となり、いわゆる「内朝一体」となり、宗主国と植民地の「大統一」が強調された。横光隆一郎の言葉の裏には、「大陸と朝鮮は一体である」から、北朝鮮のあなたのホテルは、もちろん日本の私のホテルでもある、というメッセージがある。彼の著作では、「大陸」は「中国の上海とハルビン」(『旅』)と対比して使われることがあり、その裏の意味はさらに興味深い。当時の日本人にとって、「内陸」という言葉は、広大な植民地の存在を暗示する、非常に「性的」な言葉だった。 横光隆一は1936年2月から8月にかけてヨーロッパを旅し、ベルリンオリンピックを取材した。そのオリンピックには、国が滅ぼされた韓国人である孫基禎と南善栄の二人が日本代表として出場し、マラソンでそれぞれ金メダルと銅メダルを獲得した。もちろん、そのメダルは日本チームの戦績としてカウントされたが、韓国人は今でもそのことを話すと憤慨する。横光隆一の『オリンピック記録』には、孫と南のトレーニングについて「城塞の喧騒の中、孫と南は疾走していた」と漠然と記されている。しかし不思議なことに、ベルリンオリンピックに関する彼の記事のすべてにおいて、孫と南がマラソンでメダルを獲得したことについては触れられていない。マラソンは、そのオリンピックにおける日本チームのハイライトであり、もっと詳しく書かれるべきだった。さらに、オリンピックの初めに、横光隆一は「日本の選手の成績があまりにも悪いので、記事を書くつもりはない」と不満を述べた(「ヨーロッパ紀行」8月2日)。マラソンは当然含まれていない。その後の数日間、彼は山本のやり投げ、紫の1万メートル走、西田と大江の走り高跳び(「オリンピック開会式:8月3日」と「8月5日」)など、それほど目立ったとは言えない日本の選手たちのパフォーマンスの多くを記録することに全力を尽くした。実際、それらのパフォーマンスはマラソンよりはるかに重要ではない。おそらく彼は、マラソンでメダルを獲得した孫選手とナン選手を「大陸人」とはみなさず、競技で「大陸人」が「北朝鮮人」に及ばないことを密かに羨ましがっていたのだろうか。この場合、彼の心の中にはまだ「大陸人」と「北朝鮮人」の区別があったのだろうか。 しかし、日本のメディアは2つのメダルに注目し、マラソンのドキュメンタリーを撮影した。大阪毎日新聞は横光隆一郎に、朝日新聞は別の日本人実業家に依頼して、2つのメダルを日本に持ち帰らせた。 「(8月9日の)夕方、突然マラソンの記録フィルムを日本に持って帰って欲しいと頼まれた。レースの結果が出ていた。私は依頼を受けることにした」(『オリンピック開会式・8月9日』)「この2紙にとって、マラソンはオリンピックで最も重要なショットであることは間違いない」(『ヨーロッパ紀行・8月11日』)――だが、横光隆一にとっては明らかにそうではなかった。面白いのは、競争するために、2つの新聞社はそれぞれ別の人に委託したが、2人の受託者は同じ列車に乗っていたことだ。シベリアではスピードで競争できず、小包の交換や新聞社へのいたずらも話し合った。その後、8月20日に満州里に到着すると、横光隆一郎の依頼人が先導し、ハイラルから新聞記者を派遣して飛行機で迎えに来た。 横光隆一は、このヨーロッパ旅行で、行きはインド洋をクルーズし、帰りはソ連を鉄道で横断することを選択した。箱根丸の船上での彼の世界観には、すでに植民地主義的な色彩が漂っていた。「上海からシンガポールまでの旅は、特に長く感じる。その間を通過する国々はほとんど未開である。この距離の3倍の長さの未開の地がずっとマルセイユまで続くと考えると、戦争は無意味ではないと感じる。これに無関心でいられる人がいるだろうか」(『ヨーロッパ旅行記』3月2日)これは、数年後に勃発した「大東亜戦争」の驚くべき予言である!「イギリス政府が通貨制度を革新するとき、いつも最初にインドに適用して実験するようだ。未開発地域に適用するからには、無理はない。最も顕著だったのは、この地域の先住民の反応だった。現在、英国で最も優秀な経済学者は、皆インドで勤務した経験がある。日本の実験場は満州だ」(同、3月4日) 偽満州の傀儡ども、聞いたか? 「インド洋を巡ることは、未開の地からヨーロッパ文化の頂点へ向かうことであり、長い歴史から近代へ向かう過程の再現である」(同、3月7日) 横光隆一にとって、これは「巡礼」の旅であると同時に、植民地意識の強い旅でもあり、どちらも気持ちがいいはずだ。 横光利一が多くの噂を耳にしたのは「箱根丸」の船上でのことだったが、その一つは「船にはアメリカ人の大物がいて、甲板の手すりに肘をついて、長谷部少将に話しかけていた。『日本がバイカル湖の東の地域を占領すれば、他の国々は何も言わない。もっと早く占領すべきだが、その際にあまり騒ぎ立てないように』と。」(「二月二十八日」に同じ)芥川龍之介の前で放尿した傲慢なアメリカ人と比べると、このアメリカ人横光利一はもはや以前と同じではない。彼は日本人に媚びへつらい、日本の悩みをソ連に転嫁しようとしていた(あるいはソ連のナイフを使って日本を殺そうとしていた)。このアメリカ人が知らないのは、日本人が実は昔からこのように考えていたということだ。わずか数ヵ月後、日本は国防政策を策定し、ソ連を第一の敵国として位置づけ、ひそかに戦争の準備を進めた。しかし、その3年後のノモンハン事件で日本軍は大きな損害を被り、「ロシア」の強さを思い知らされた。「北進」を断念し、「南進」に切り替えざるを得なくなった。そして真珠湾を奇襲し、アメリカ軍を完膚なきまでに叩きのめした。これは芥川龍之介の「放尿を見させられた」という当時の深い憎悪を慰めるには十分だったし、横光隆一郎のようなアメリカ人にとっては報復とみなすことができた。 同年8月、横光隆一郎はソ連経由で東側に帰国した。列車が広大なロシアの地を横断し、満州里に到着したとき、彼はまるで祖国に帰ってきたような気持ちになり、中ソ国境を日本とソ連の境界線であるかのように直接「国境」と呼んだ。 「私が満州へ向かうために乗ろうとしていた列車は、当然ながら私にとって非常に馴染み深いものだった」(『人間の研究』)。 「満州まではたったの三時間。ベッドにもぐりこんだが眠れなかった。楽しみにしていたのは日本がどんなふうに見えるかということだった」(『欧州紀行』八月二十日) 見てください。「満州」と「日本」が同一視され、偽の「満州国」の影さえありません! なぜなら、彼の目には「満州」は「日本の実験場」、つまり植民地、ちょうどイギリスにとってのインドと同じようなものになっていたからです(『三月四日』と同じ)。 「ここには日本兵がかなりいる」彼らは悪名高い関東軍だ。 「日本の影響力はここまで及んでいる」と彼はまだ満足していなかったが、「ポーランドからここまで勢力圏が広がっているロシアと比べれば、取るに足りないことだ」と語った。満州里駅で彼を迎えたのは「中国服を着た特高警察」たちだった。東北地方の一般人が子供を怖がらせるために使うような人たちだったが、彼はそれを何ら不思議に思わなかった。「私にとっては特高警察であろうとなかろうと関係ない。日本人であれば、何よりも安心できる」。満州で彼は故郷に足を踏み入れたような安心感と、故郷ならではの温かさに心を満たされた。 「夢のように美しい、波打つ広大な国境の野草を、初めてじっくりと眺めた」(「8月20日」に同じ)70年、80年経った今でも、彼の温かさと安心感を今読むと、やはり居心地が悪いです。本当に居心地が悪いです! 「大連から長春にかけての地域にとどまっている日本人に、日本に帰りたいかと問えば、多くの人はいやと答えるだろう。しかしハルビンに着くと、皆、できるだけ早く帰りたいと言う。日本の北から中国の長春にまで及んだ日本語の波は、もう力尽きたのかもしれない。」(『旅』)いわゆる「日本語の波」とは、大連から長春まで広がって、中国という国に潰瘍、癌となってしまった日本植民地化の波である。横光隆一さんの描写はとてもリアルです。しかし、歴史はこれが「欲しいか欲しくないか」の問題ではないことを証明しています。戦後、何百万人もの日本人難民が帰還した日本沿岸の舞鶴のような港に聞いてみれば、すべてがわかるだろう。横光隆一は終戦から2年後に亡くなったが、日本の植民地史の終わりを見届けるまで生き続けた。ああ、助かった! 芥川龍之介は『中国紀行』の中で、中国の「抗日運動」をいたるところで非難している。日中戦争勃発前夜、横光隆一も中国の「抗日戦争」がなぜ始まったのか理解できなかった。「しかし、中国の知識人はとっくに世界をひっくり返し、何の良心も持っていない。伝統を壊すことは彼らの習慣となり、戦争はその目的を達成するために不可欠な武器となった。抗日戦争の方法は自覚の結果ではなく、他国から学んだ武器である」(『静安寺碑文』)瓊瑶の自伝的小説『私の物語』には、抗日戦争中、日本兵が最も嫌ったのは中国の知識人だったと書かれている。彼らは中国の抗日戦争が彼らの利益になると信じていたからだ。これらはすべて学者によって広められ、煽動されたものである。「日本軍が最も嫌うのは知識層で、学者を見つけると容赦なく殺すと言われています。私の家族は祖父、父、母が教師で、反日活動家です。教室では、祖父と両親が飽きることなく学生に国家観念を教え込んでいました。このとき、私たちが日本軍の殺害の標的になるのは当然です。実際、日本軍の鉄の蹄が踏みにじったところでは、命が失われ、国土は荒廃しました。老人、弱者、女子供、学者、農民、商人、労働者を問わず、学者だけでなく、すべてが残酷に殺されました。しかし、学者、特に教師は確かに逃げにくいのです!」横光隆一郎の発言をどう見ても、日本軍の残虐行為を反映しているようです。 このことから、芥川龍之介から横光隆一に至るまで、彼らは依然として中国を理解できず、中国人の日本観も理解できなかったことがわかります。日本の右翼の見解を代表する扶桑社の『新しい歴史教科書』では、今でも当時の「反日運動」の原因の一つは、ソ連の暴力的な革命思想の影響と「過激」な性格にあるとされているが、これは横光隆一郎の見解と全く同じである。また、日本の政治家は、現代中国人の「反日感情」について語るとき、中国人全員が、実は歴史と歴史歪曲が原因であると何度も繰り返し伝えてきたにもかかわらず、常に「プロパガンダ」の結果であると希望的に信じている。日本のテレビ番組で、「ゲスト」が戦争犯罪者を「英霊」と呼び、「歴史の記述」に「巻き込まれている」中国人を「洗脳されている」と非難するのを何度見ただろうか。 「この世の中で、中国人の心理を理解することはおそらく非常に難しい。すべての国の外交は上海で転覆した。」(『静安寺の碑文』) 「私は中国で長年暮らし、優れた人格を持つ多くの人々に会った。彼らがため息をつくのをよく聞く。中国で何が起こっているのか、本当にわからない。」(『北京とパリ(覚書)』) 実際、何を混乱する必要があるだろうか?中国人は「洗脳されている」という偏見を捨て、中国人自身の言うことに謙虚に耳を傾ければ、それで十分ではないだろうか? 他人を知ることは簡単ではありませんが、自分自身を知ることはさらに困難です。 On the way back through the Soviet Union, Yokomitsu Toshiichi passed through Moscow and saw the headquarters of the KBO (predecessor of the KGB?). While lamenting the Soviet Union's autocratic tyranny, he thought of how "rational" Japan was and how much it respected human life: "I don't have any special hatred for Russia, but every time I hear that many talented people in Russia have been arbitrarily deprived of their lives, I can't help but realize that this is a country that is completely different from Japan. I think the most noble thing about a culture is that it respects human life far more than it respects other things. Standing in front of the KBO, I thought that if Japan became Russia, it would probably not even have the time to turn around. Thinking of the many outstanding friends I was able to meet safely in the past, I couldn't help but feel that Japan is a place with highly developed rationality. Faced with this rationality, I was completely unaware of it before. With this high level of rationality, Japanese culture will definitely have a good future." ("Study of Man") 彼の言う「人命」に日本人以外の人命も含まれていたかどうかはわからないし、翌年末に起こる南京大虐殺を予見していたかどうかもわからない。ただ、日本が侵略と拡張政策を推し進め、軍国主義が跋扈していた時代に、俳句仲間が警察に理由もなく逮捕され10日間拘留され(『四季』)、小林多喜二が警察署で拷問死した時、彼はむしろ自国の高圧政策を弁護し賞賛し、自国の戦争犯罪に目をつぶっていた。彼や日本の知識人の限界と悲しみにため息をつくしかない。 しかし、ジッドに対する彼の観察は深いものだった。偶然にも、ジッドもその旅行でモスクワを訪れました。横光隆一は、ジイドがソ連を絶賛していることに困惑した。「フランスは世界一の文化大国であり、最も理性的な精神を持った国と言える。そんな国に属するジイドが、それをロシアの精神的植民地にしようとしている。これは精神世界の重大な歴史的事実なのか。私には全く理解できない現象だ」。その後、彼はジイドの『ロシア紀行』を読み、そこにもソ連に対する懸念が秘められていた。その時初めて、彼はジイドがジイドたるにふさわしく、フランスの理性的な精神を代表していると感じた。「そして、私が最も興味を引かれるのは、これまで誰も言ったことのないことで、ジイドが言ったことだ。最初に言ったのは、ジッドである。ロシアには幸福で質の高い生活がたくさんあると語り、それを絶賛した。そして、それにもかかわらず、ロシアでは、最善のものが最悪のものに負けることがあると述べた。この発言はフランスの合理性を示しており、フランスの伝統の美しさがここに反映されていると思います。」また、彼はジッドの言葉を引用して自分の立場を示した。「私にとって、世界には私自身やソ連よりも重要なものがあります。それは、人類とその運命とその文化です。」(以上、すべて『人間の研究』より)この言葉から、鋭い目を持つ横光利一が見える。 しかし、他人を見る目が鋭い横光隆一が、どうして自国が道を踏み外したことに気づかなかったのか。東アジアで罪を犯したことに気づかなかったのか。それなのに、彼は「人命を何よりも尊重する」という日本の「高い合理性」を語り、「日本の今日の戦いの叫びは『東アジアの平和』である」(『考える葦』)と宣言した。これは本当に大きな嘘であり、大きな冗談です。 1947年12月30日、日本の敗戦後の最も悲惨な時期、そして寒くて風の強い年の終わりに、横光隆一郎は50歳で亡くなりました。 「新感覚主義の二本柱」の一人が亡くなり、もう一人の川端康成は悲痛な思いで、次のような嘆きに満ちた哀悼文を書いた。「祖国が滅びてますます寒さに閉ざされた私の骨は、あなたからの支援さえも奪われたために、やがて凍える寒さに砕け散るだろう」「祖国が滅びたために、あなたたちの骨も砕け散った。この戦争、特に敗戦が、あなたたちの心身にどれほどの苦しみをもたらしたか」。これは心のこもった言葉だと思うし、日本人なら読んで泣くだろう(中国人の中にもそうする人がいるかもしれないが)。しかし、私は、上に書いたことすべてを考えると、侵略と拡張に快楽を感じていた人たちは皆、祖国が滅んだ後に敗北の痛みを負うべきだといつも思う。当然です。そうでなければ許されません! ですから、川端康成の弔辞は、大変な思いで書かれたものであり、日本で最も有名な弔辞の一つになったと言われていますが、少なくとも上記の言葉に関しては、共感も感動も涙も出ない私をお許しください。まるで広島の原爆の跡地を何度も訪れたかのようだ。悲惨な災害に見舞われた広島市民に同情すると同時に、中国や東南アジアに民間人を虐殺しに行く「帝国軍」(悪魔)を見送るために、広島市民が何千回も「万歳」を叫んだ広島港をいつも思い出す。私の協会が十分に「高貴」ではないことはわかっていますが、自分自身を「高貴」になろうとは思いません。 |
<<: 曹操の八虎騎の配下の8人の将軍は誰ですか?それぞれの貢献は何でしょうか?
>>: なぜドイツは自らを第三帝国と呼んだのでしょうか?第一帝国と第二帝国とは何でしたか?
推薦する
公孫六娥の父親は誰ですか?公孫六娥の父、公孫志の簡単な紹介
公孫之は金庸の小説『射雁英雄の帰還』の登場人物で、無縁谷の主人です。彼は高貴な青い繻子のローブを着て...
杜神艶の『北京春思』:始まり、発展、移行、終わりが極めて自然で、仮想と現実が互いに補完し合っている
杜神艶(645年頃 - 708年頃)は、雅号を畢堅といい、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身で、晋...
「雷が鳴ると箸がなくなる」という慣用句はどういう意味ですか?その背後にある歴史的な物語は何ですか?
「雷鳴を聞くと箸を失う」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その裏にはどんな物語があるので...
10月の黄金の秋を表現した詩にはどんなものがありますか?詩の内容は何ですか?
本日は、Interesting History の編集者が 10 月の黄金の秋を描いた詩をご紹介しま...
西遊記における真元子の地位はどのようなものですか?なぜ桃の節句に彼を招待しなかったのですか?
唐の僧侶とその弟子たちは休息のために五荘寺に来ました。偶然にも、真元子は講義を聞くために天国へ行きま...
『黄帝内経霊書』原文の鑑賞:五邪第20章
邪気が肺にある場合は、皮膚の痛み、悪寒、発熱、息切れ、発汗、肩や背中を震わせる咳などの症状が現れます...
洛因の「自慰」:この詩は唐後期の社会の暗い現実を描写している
洛隠(833年2月16日 - 910年1月26日)は、元の名は洛衡、字は昭建で、浙江省杭州市阜陽区新...
『紅楼夢』で黛玉の兄はどうやって死んだのですか?意味は何ですか
『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、金陵十二美人本編の最初の二人の登場人物の一人です。以下の記事は、I...
清朝の空飛ぶギロチンとはどのような組織だったのでしょうか?具体的にはどのような責任を負っていますか?
ギロチン、名前を聞くだけでも十分怖いですね。血のギロチンは雍正帝が発明したと言われています。では、清...
詩経 詩経の紹介 中国最古の詩集
『詩経』は中国で最初の詩集です。西周初期から春秋時代中期、つまり紀元前1100年から紀元前600年ま...
劉備と曹操のどちらがより強いかは、どのような経験からわかるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐代の裴厳が書いた詩『切花頌』は、切花の美しさを強調しています。
裴延は、玄宗皇帝の開元年間の宰相裴耀卿の息子で、同氏世人を務めた。以下に紹介する『Interesti...
小説『紅楼夢』の中で、元陽の最終的な運命は何ですか?
『紅楼夢』では、金元陽は賈夫人の年長の侍女であり、賈家の侍女たちの中で非常に高い地位を持っています。...
七剣十三英雄第78章:徐明高が左天成を生け捕り、梅の陰謀が呉芳傑を倒す
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
蜀漢と曹魏は宿敵同士だったが、蘇州はなぜ二人と時には戦い、時には和平を結ぶことができたのだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...