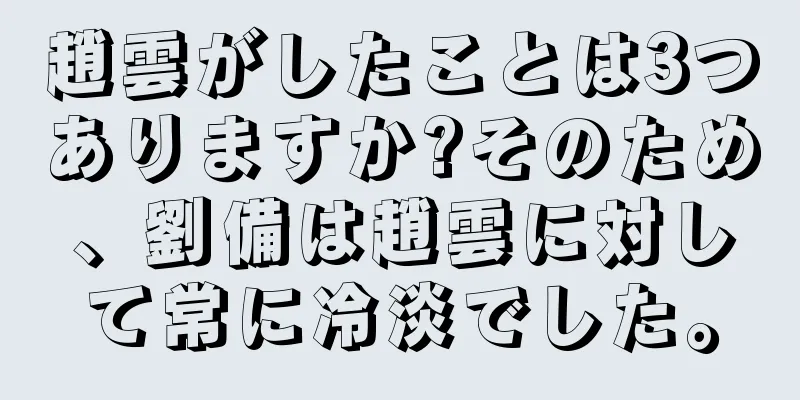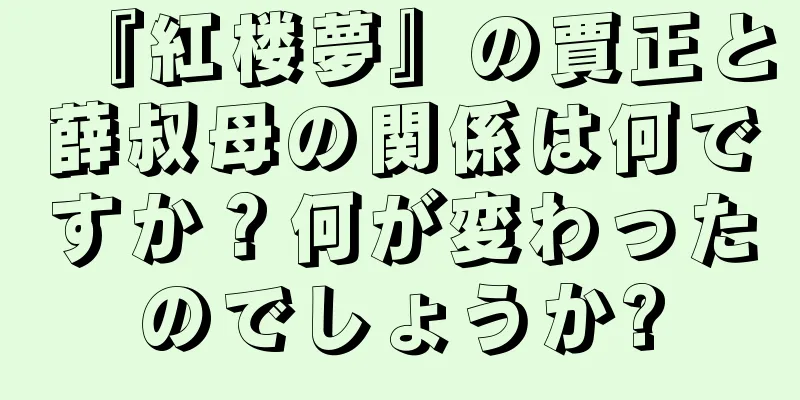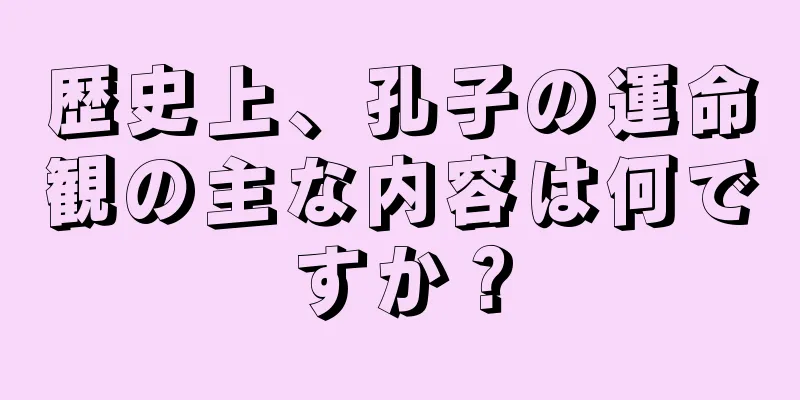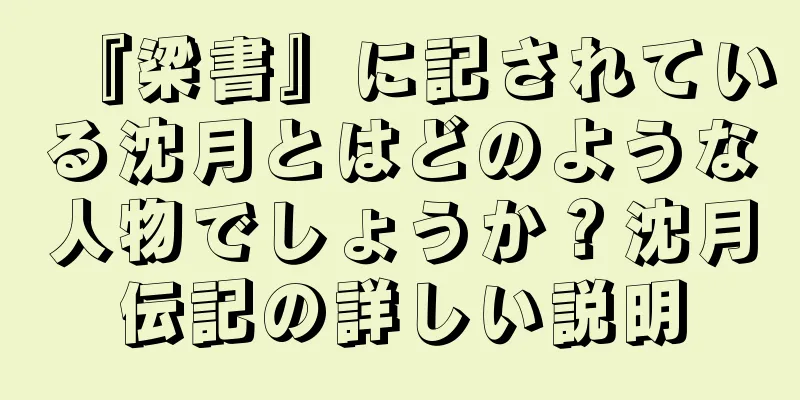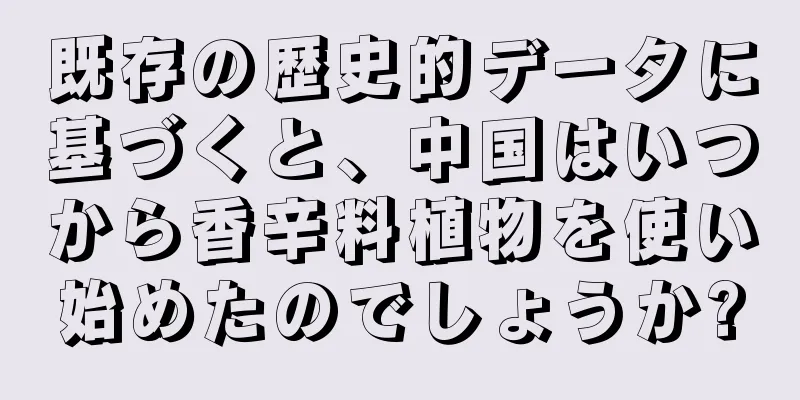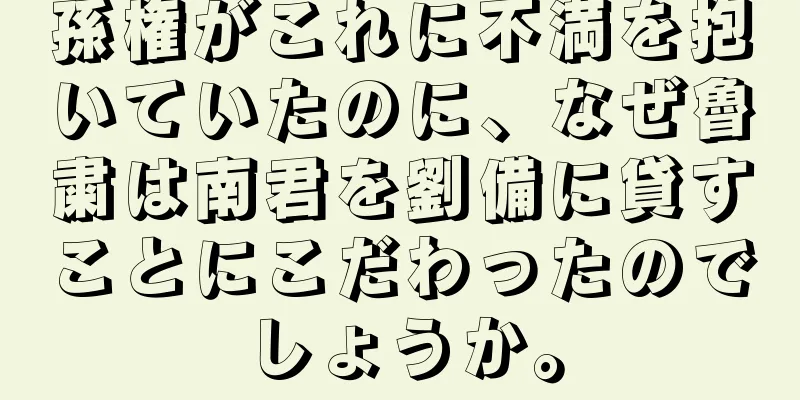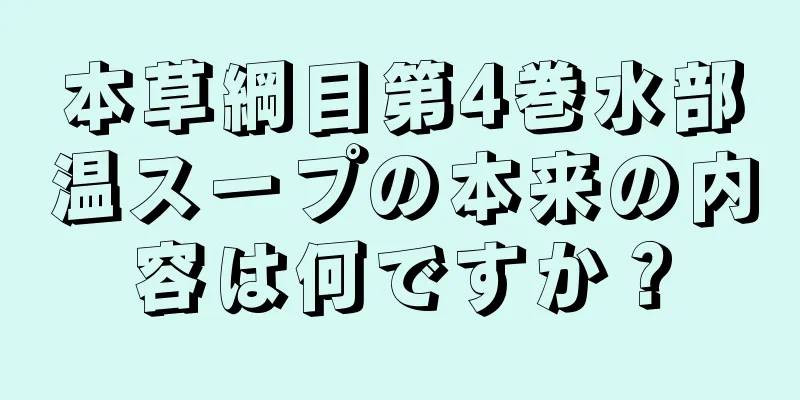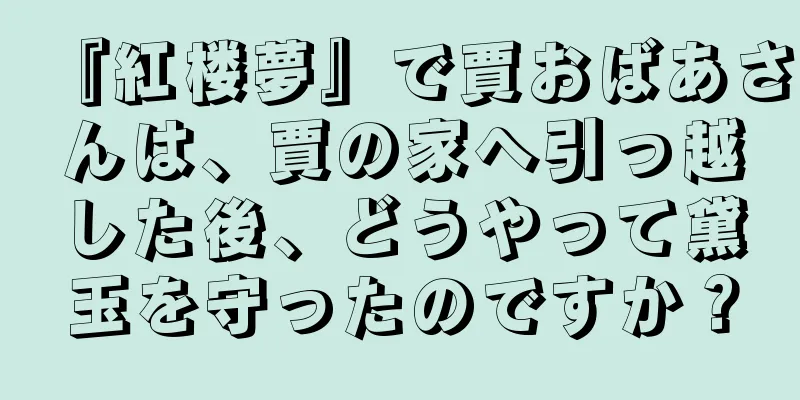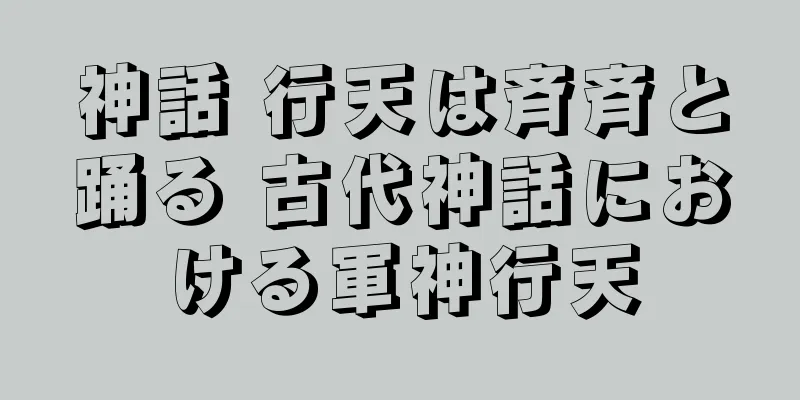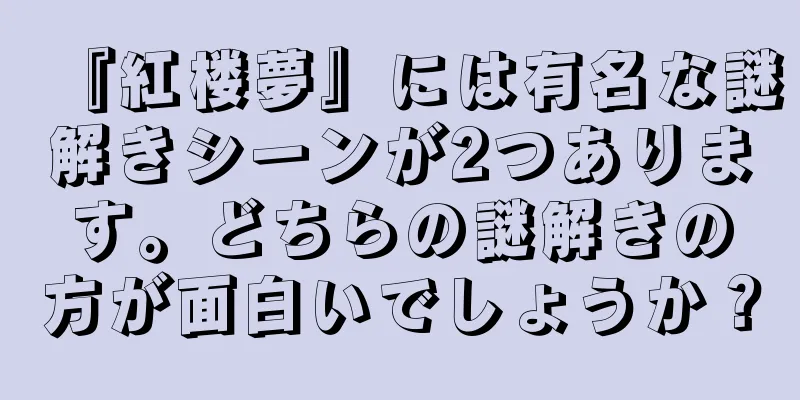関羽が5つの峠を越え、6人の将軍を殺したことで軽蔑されているのは誰ですか?
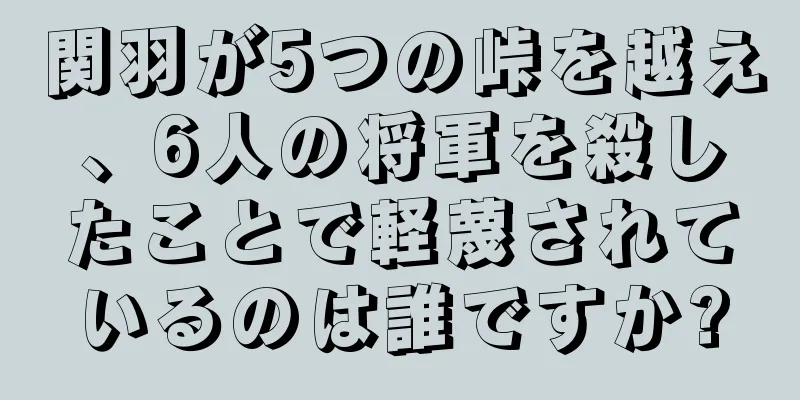
|
関羽は曹操から劉備の居場所を聞き、曹操に別れを告げて袁紹の領地へ向かった。彼は東陵関、洛陽、樊水関、滄陽、華州を通過し、曹操の関を守る5人の将軍を殺した。これは関羽の生涯における典型的な戦いであり、関公が忠実で勇敢な男であるというイメージも生み出しました。 しかし、この事件について羅貫中が関羽を称賛したとき、彼はうっかり誰かを軽蔑してしまった。 まずは関羽と峠を守る将軍たちの戦いのシーンを見てみましょう。東陵関では、「二頭の馬が出会い、一撃で鋼刀が振り上げられ、孔秀の死体が馬の下に横たわった。」洛陽では、「孟旦は三ラウンドも戦わず、馬を回して逃げた。関公が来た。孟旦は関公をおびき寄せることしか考えていなかったが、関公の馬は速く、すでに追いついており、一刀で孔秀を真っ二つに切り裂いた。」韓府では、「関公は刀を振り上げ、馬の下で孔秀の頭と肩を切り落とした。」ハン・フーは自分を守る機会さえもなかった。梵水関では、「関公は剣を使って槌を切り離し、突進し、一刀で卞熙を真っ二つに切り裂いた。」卞熙にも反撃の機会はなかった。滕陽の王志は「馬を走らせ、槍を構えて関公に向かって突進したが、関公の腰の剣で真っ二つに切られた」。逃げるチャンスさえなかった。華州の黄河渡し場で、秦斉の「二頭の馬が出会った。関羽は一振りで剣を振り上げ、秦斉の首が落ちた」。戦った六人の中で、孟譚だけがより優れた武術の腕を持っていた。関羽の剣の下で三ラウンドを耐え、負けることなく、馬の向きを変えて関羽を誘い出した。孔秀と秦起は戦いの末に関羽の犠牲者となり、韓邵、卞熙、王志は関羽の犠牲者となる前に逃げる暇さえなかった。 これらの戦闘状況は、峠を守っている兵士たちが全員無能であり、彼らの能力では峠を守るという任務を遂行することがまったく不可能であることを示しています。特に、黄河の渡し場は重要な位置にあります。黄河を渡ると、袁紹の領土と国境に到達します。秦斉の武術のスキルがあれば、袁紹はどんな将軍を派遣しても簡単に渡し場を突破することができます。 では、これらの人々をここに配置したのは誰でしょうか? もちろん、曹操です。曹操は歴史上軍事戦略家として知られています。彼は南北の戦争で戦い、宰相にまで昇進しました。曹操の軍事的才能と当時の情勢把握力からして、黄河渡しの重要性を知らないはずはなかった。曹操は間違いなく大軍を派遣して黄河渡しを守るだろう。少なくとも、張遼や徐晃のような将軍と、峠の警備を支援する少数の特殊部隊を配置するだろう。 「五関を越え六将を討つ」は、三国志演義で関羽の人物像を描くために羅貫中が創作した架空の物語です。彼は関羽について書くことだけに注意を払っていましたが、うっかり曹操の人を雇う軍事戦術を軽視していました!これは羅貫中自身が気づかなかったことかもしれません。 |
<<: 匈奴を席巻した魏青が、なぜ一介の官吏を畏怖したのだろうか。
>>: なぜ于吉は孫策に殺されたのですか?ユ・ジはどうやって死んだのですか?
推薦する
『紅楼夢』では、宝玉と希仁は密会していました。なぜ黛玉は気にしなかったのでしょうか?
宝玉と黛玉の恋は『紅楼夢』のメインストーリーです。興味のある方は『Interesting Histo...
太平広記・巻96・奇僧・僧嘉法師の具体的な内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
飛龍全伝第40章:鄭子明が園主の陶三春を殴り、拳で漢を制圧する
『飛龍全篇』は清代の呉玄が書いた小説で、全編にわたって趙匡胤が暴君に抵抗する物語を語っています。物語...
頤和園の四十景の一つである「鏡秦図」とはどのようなものですか?
周知のように、頤和園は清代の皇室庭園で、雄大で壮麗です。では、四十景の一つ「嘉靖明琴」はどのようなも...
昔の役人には明確な定年がなかったのに、なぜ定年後に故郷に戻らなければならなかったのでしょうか。
古代には役人に明確な定年はなかった。一般的に言えば、人々は健康状態が深刻で働けなくなった場合にのみ皇...
易経の明易卦第93行「頭を大きくして、焦らず」をどのように理解すればよいのでしょうか?
まだ分からないこと:易経の明卦の九行目「頭が大きくなって、焦ってはいけない」とはどういう意味です...
楊毅はどうやって売り切れたのですか?なぜ彼は蜀漢に見捨てられたのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
9つの頭を持つ鳥とは何ですか?伝説の9つの頭を持つ鳥はどんな姿をしているのでしょうか?
9つの頭を持つ鳥は、九鳳とも呼ばれます。漢の神話や伝説に登場する不吉な怪鳥。 「九」と「鬼」は古代中...
宋代に全国規模の農民反乱が起こらなかったのはなぜですか?宋代の小作制度の特徴は何ですか?
宋代に全国的な農民反乱が起こらなかったのはなぜか?宋代の小作制度の特徴は何だったのか?興味のある読者...
もし許褚が典韋と組んで趙雲と馬超と戦ったら、どちらが勝つでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
衣服制度は政府の基盤です。
周王朝は封建制度に基づいて建国され、帝国を統合するための厳格な階級制度と、社会を統制し世界を安定させ...
『紅楼夢』における賈家と林家のルールの違いは何ですか? Daiyu はこの問題をどのように解決したのでしょうか?
黛玉が賈邸に入る場面は、紅楼夢全体で最も話題になっている章です。「歴史の流れを遠くから眺め、歴史の変...
中国で最も長い川は黄河です。最も短い川は何ですか?
今日は、Interesting History の編集者が中国で最も短い川についてお話しします。興味...
なぜQiu TongのWang XifengはYou Erjieを最初にターゲットにしたのですか?
今日は、Interesting Historyの編集者がQuiu Tongについての記事をお届けしま...
『啓東夜話』第12章の主な内容は何ですか?
○ 蒋耀章の自伝(単文添付) 『梵義』には庶民の蒋奎瑶に関する章があり、その出典は張季宗瑞著『白石伝...