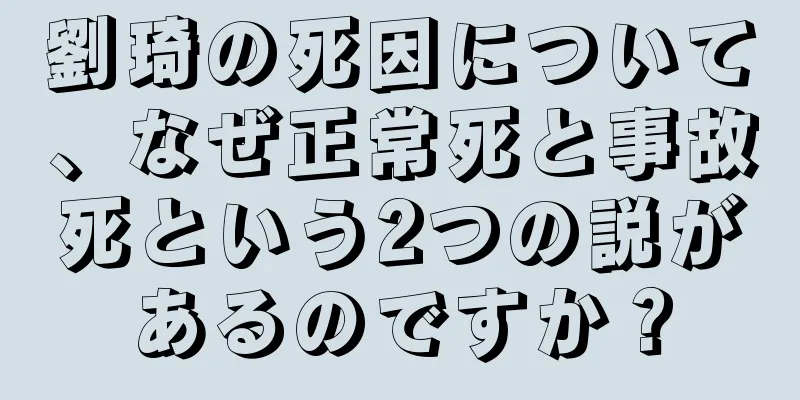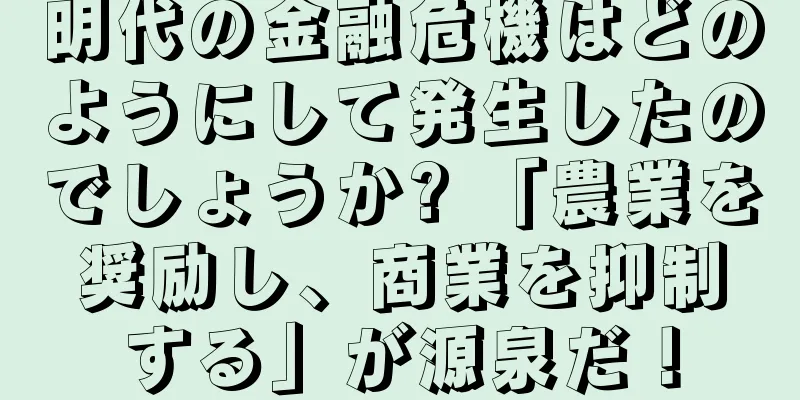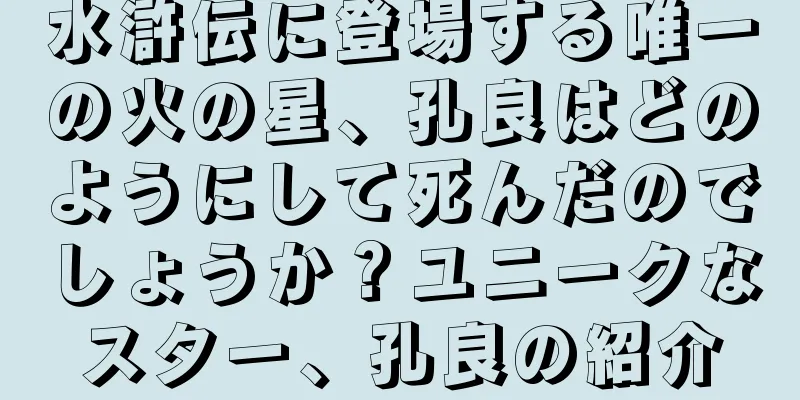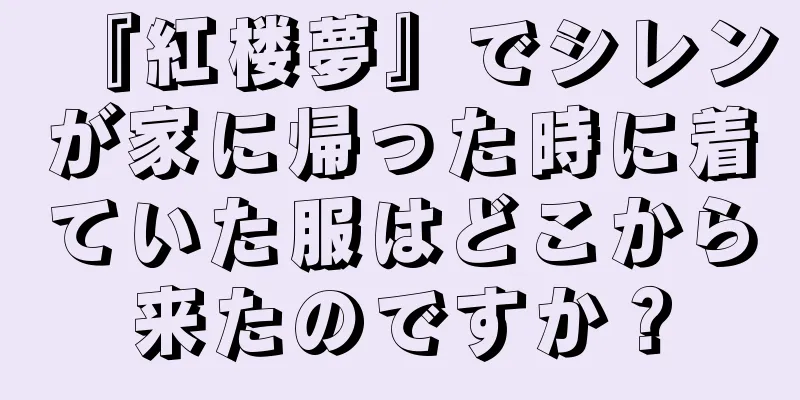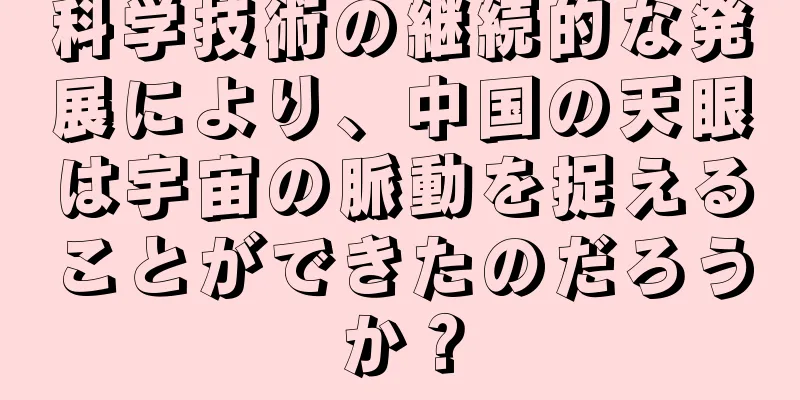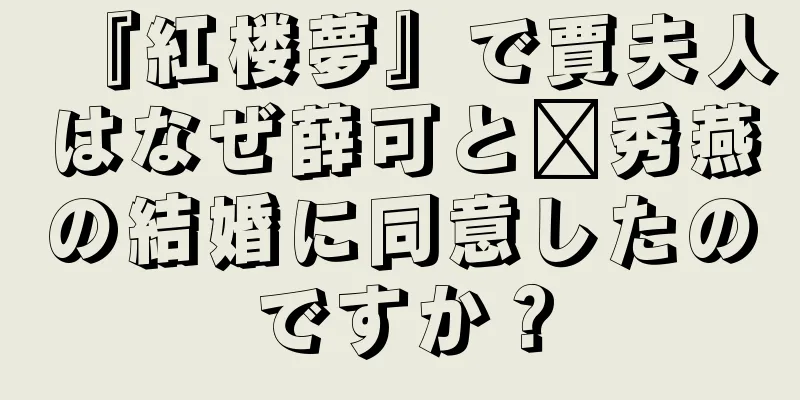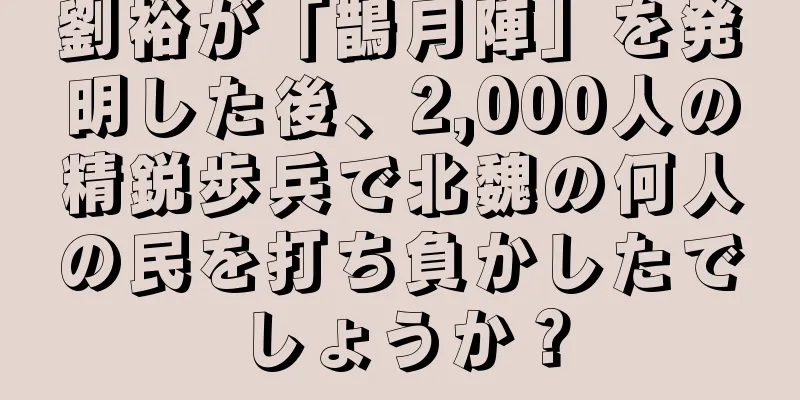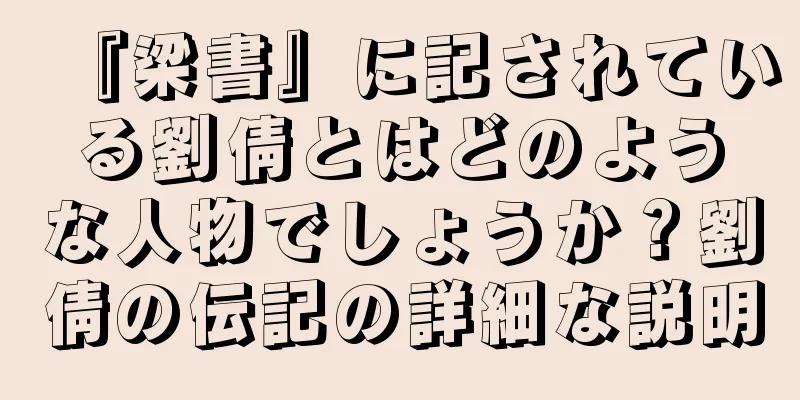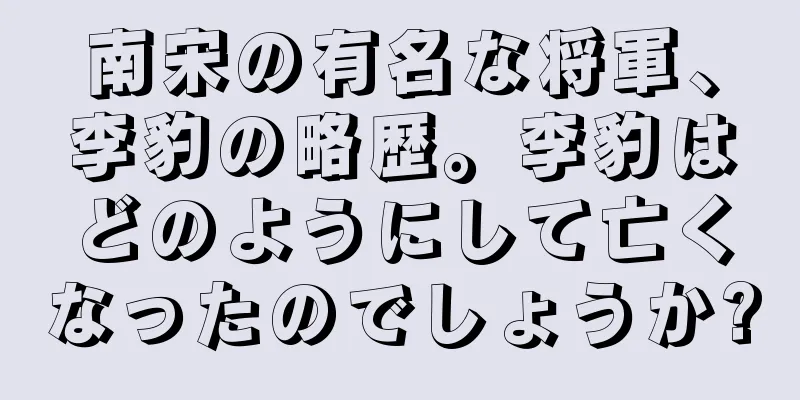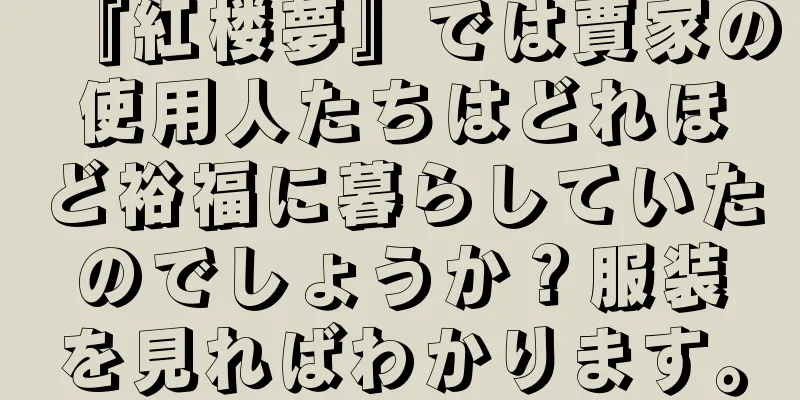清朝の衣装:清朝の役人の宮廷服と吉祥服の違いは何ですか?
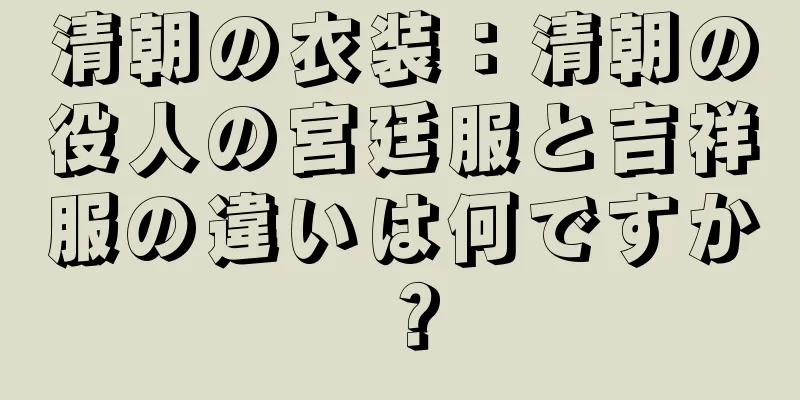
|
公式文書に記載されている清朝の「龍のローブ」はすべて「吉祥のローブ」を指します。 男性の吉祥衣と宮廷服の違いは、大まかに5つの点から説明できます[クリックして大きな画像を表示~~~~クリックして大きな画像を表示~~~~クリックして大きな画像を表示~~~~重要な言葉は3回言います]: 襟の前面は滑らかですが、宮廷服の襟の前面は襟からまっすぐに伸び、内側にカーブして脇の下までつながり、両者の間に折り角が形成され、漢字の「厂」のように見えます。 雍正帝の明るい黄色の吉祥の衣と雍正帝の明るい赤色の宮廷の衣(祭服): 襟 - 儀式用のローブには襟がなく、宮廷用のローブのみに襟があります。 ただし、法衣の襟は法衣とは別パーツになっており、後から付け足すことになるので注意が必要です。初期の文書(古い満州文書)には、確かに「襟なしの法衣」(満州語:ゴクシ、通常の「法衣」は満州語で「エルグメ」と表記される)という用語が存在します。 昔、宮廷服に襟があるかどうかは、階級や礼儀作法の象徴であったと考えられます。 仕立て方: 吉祥衣は上から下に裁断され、宮廷衣は上から下に裁断されます。 袈裟の開き目から下段の裁断箇所までは交互になっており、つなぎ目は長方形の衽(衽)になっており、下段は縦に連続した多数の襞になっている。 装飾 グレードによってパターンが若干異なるため、より複雑になります。等級による図柄の違いについては、『清慧典』を参照することをお勧めしますので、ここでは詳細には触れません。 一般的に、皇帝の吉祥の服には、全身に前後に計8つの龍の模様(下襟にもう1つ)があり、宮廷の服は、肩の龍の模様(清朝初期でない限り、通常は正統な肩越しの蛇/龍の模様ではない)と同様に、縁取りで領域ごとに配置され、両肩と前後に龍の模様があり、その下には八宝平水があります。 装飾の観点から見ると、礼服と宮廷服の最も直感的な違いは、礼服の裾には海水、断崖、水足が描かれているのに対し、宮廷服の裾には水足がなく(平らな水のみ)、裾のスカートには龍やニシキヘビの模様が描かれている(ぼろスカートと同様)ことです。 裾が開いている(男性用のローブを例に挙げてください!男性用のローブを例に挙げてください!男性用のローブを例に挙げてください!女性用のローブは違います!女性用のローブは違います!女性用のローブは違います!3回言うことが大切です!) 男性の吉祥服は前と後ろに裾が開いています(王族は四方に開きます)。男性の宮廷服は前も後ろも裾が開いていません。また、その「開き方」も非常に特殊で、左側を内側に折り込むことで、「隠し裾」のようにしています...説明が難しいため、故宮博物院は時々怠けて「後ろ裾が開いている」または「左側が開いている」と書きますが、実際には宮廷服は伝統的な意味での「裾が開いている」わけではありません。 (注:上の写真の左側と右側も裾が開いていますが、美観上の理由からマークされていません) (注:上の写真の左側と右側も裾が開いていますが、美観上の理由からマークされていません) @BostonTito は Weibo に、法衣の「隠しスイング」の詳細を投稿しました。 一般的に言えば、これらは儀式用の衣服と宮廷用の衣服の違いです。また、「吉祥衣の袖は単色ではない」など、ここでは詳しく説明していない、十分に代表的ではない相違点もいくつかあります。両者の成績の違いについてはここでは詳しく説明しません。 女性の礼服と女性の法衣の違いは男性の法衣の違いと全く同じではありませんが、1から4までは共通していると考えられます。5番目の点については、女性の礼服には左右の裾がありますが、女性の法衣の裾の状況はより複雑なので、ここでは説明しません。 2番目の質問: 公式の衣服は、次の 2 点を除いて、基本的に皇帝の衣服と同じでした。 官吏(王族以外)の衣服は前と後ろのみ開く(女性の衣服は別の開き方が可能)が、皇帝の衣服は四方を開くことができる。 禁止されている色(黄色など - 実際、皇帝は明るい黄色の普段着をめったに着ませんでした...)は使用できませんが、他の色は任意です。 清朝初期のカジュアルなガウンを着た若い男性: |
推薦する
岑申の『陝伯県戦勝歌』にはどのような場面が描かれているのでしょうか。
唐代の詩人坤深に最も大きな影響を与えた人物が馮長清であったことはよく知られています。では、岑申のこの...
韓愈の「百花桃花図」は風景を通して詩人の陽気な気質を表現している
韓愈は、字を徒子といい、自らを「昌里の人」と称し、通称は「韓昌里」または「昌里氏」であった。唐代の著...
『紅楼夢』で賈宝玉はどんな犯罪を犯したのですか?彼は不当に殴られたのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
漢代の有名な楽譜「孔雀飛南東」はなぜこの名前が付けられたのでしょうか?
「孔雀は南東に飛ぶ」は漢代の有名な曲です。詩の最初の行は「孔雀は南東に飛び、5マイルごとに止まる」で...
宝安の衣装が美しくて実用的な理由
宝安族は初期にはモンゴル人の隣に住んでいて、彼らの衣服は基本的にモンゴル人のものと同じでした。男性も...
後漢書第32巻の范洪因伝の原文
范洪(名を米清)は南陽市湖陽の出身で、太祖皇帝の叔父であった。彼の先祖である周中山夫は樊の領地を与え...
張赫蓮の妻は誰?張赫蓮の妻、石平公主の紹介
賀連昌(?-434)は、賀連哲とも呼ばれ、匈奴の鉄楽族の一員であった。彼は、大夏の武烈皇帝賀連伯伯の...
孫子の兵法書にある「借刀殺三十六計」の簡単な紹介。出典は何ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が「借り物のナイフで殺す36の計略」についての...
北宋時代の詩人、黄庭堅の『清平月:春はどこへ行く』の原文、翻訳、注釈、鑑賞
黄庭堅の「清平楽・春はどこへ行くのか?」、興味のある読者はInteresting Historyの編...
謎に迫る:三国志の本体と発展史
「三国時代」には2つの定義がある。狭義の三国時代は西暦220年から280年までである。ただし、狭義の...
日本の天皇はどのようにして国民全員に降伏を説得したのでしょうか?
第二次世界大戦における日本の降伏に関して最も不可解なことは、8月15日、米軍が島に上陸する前、日本国...
唐代の逸話:遊女の涼州の歌は唐代の二人の偉大な作家を凌駕した
梁州慈王志環黄河は白い雲の間を遠く流れ、孤立した都市とそびえ立つ山々が見えます。春風が玉門関に届かな...
南宋はモンゴルと同盟を結んだ後、金王朝を滅ぼしたのですか?南宋とモンゴルの同盟はどのような影響を与えましたか?
南宋王朝の滅亡は多くの中国人に後悔と悲痛な思いを抱かせた。極めて繁栄した経済と文化を持つ先進国が、二...
昔、家を買う余裕のない人が大勢いました。なぜ李白が最も有名な借家人だったのでしょうか?
食、衣、住、交通は、人間が日々の生活で対処しなければならない4つの主要な事項です。これは非常に現実的...
明代史第377巻第195伝の原文
◎お気に入り漢代の歴史に記録されている諂傅、洪如、鄧同、韓燕、李延年、董献、張芳などのおべっか使いは...