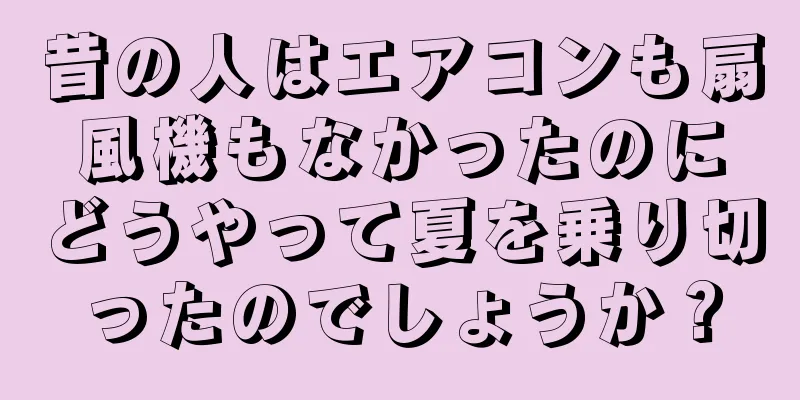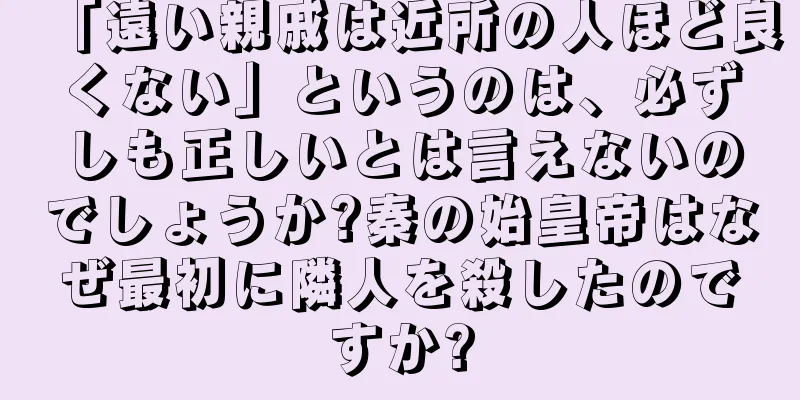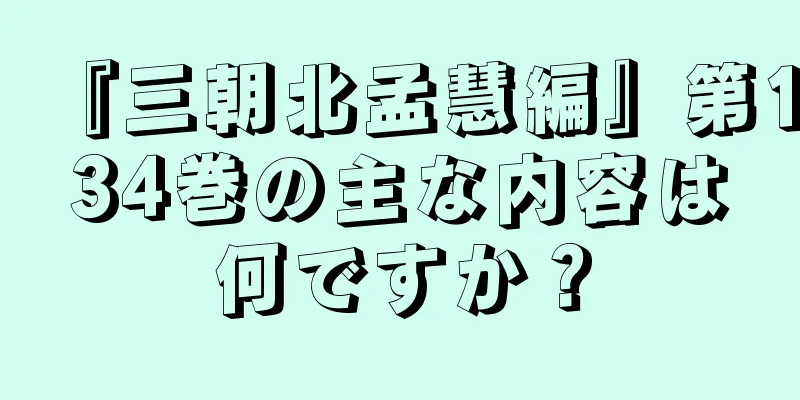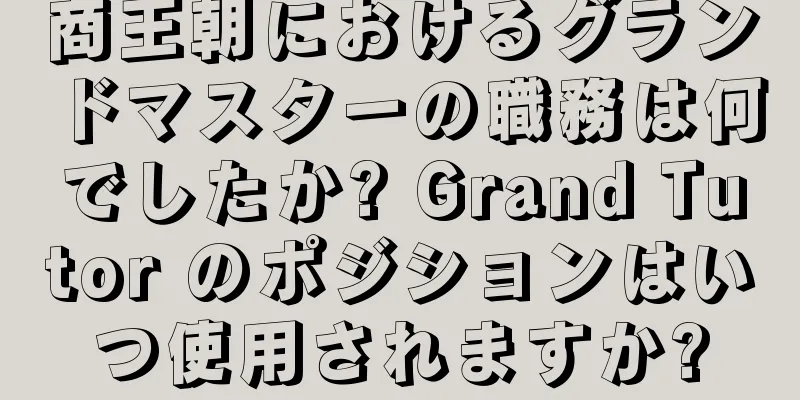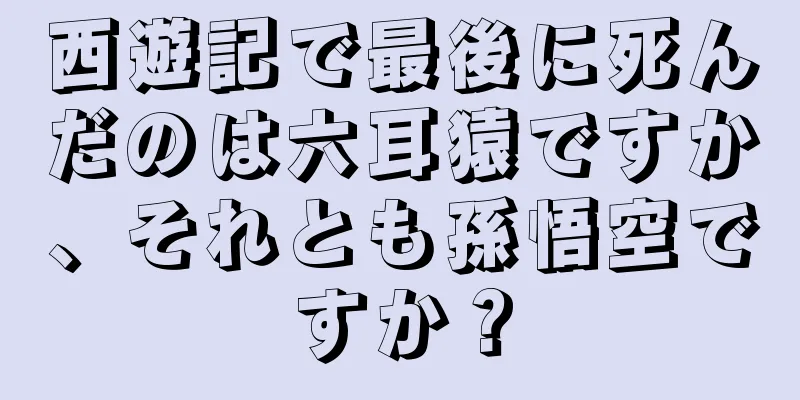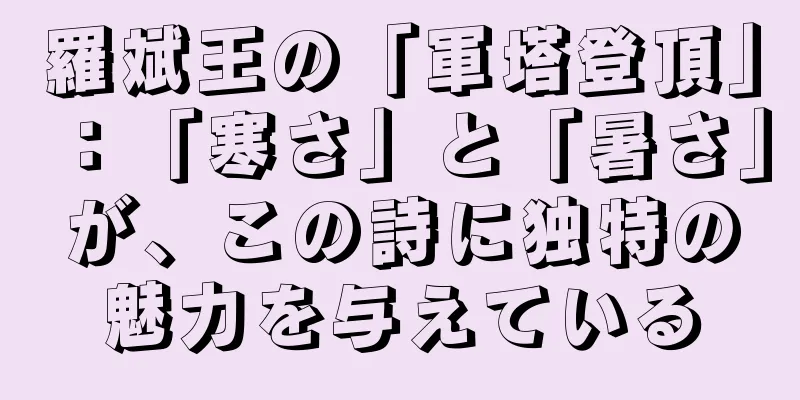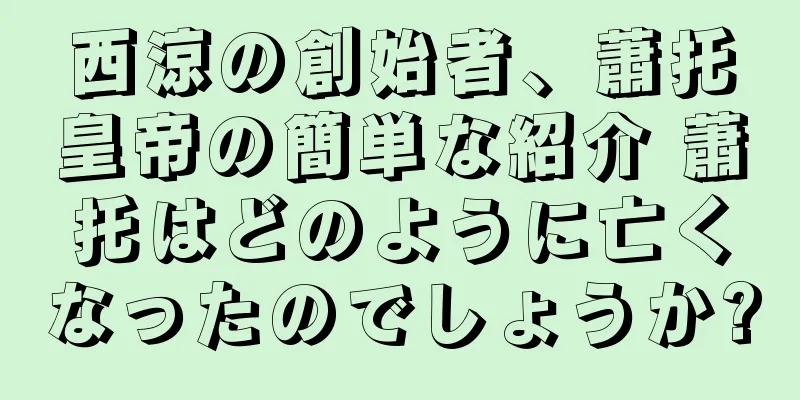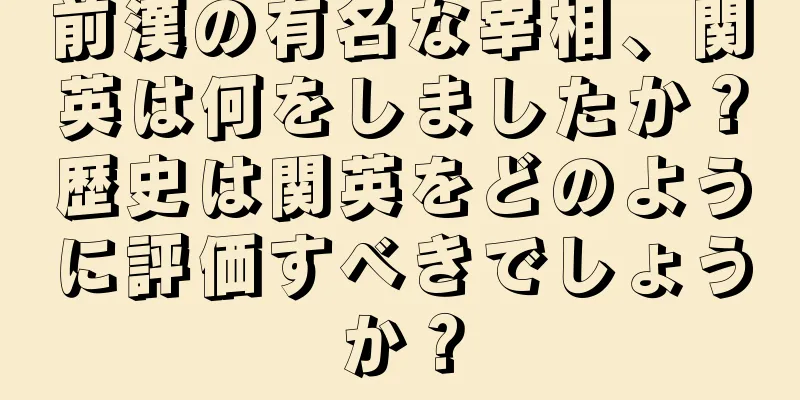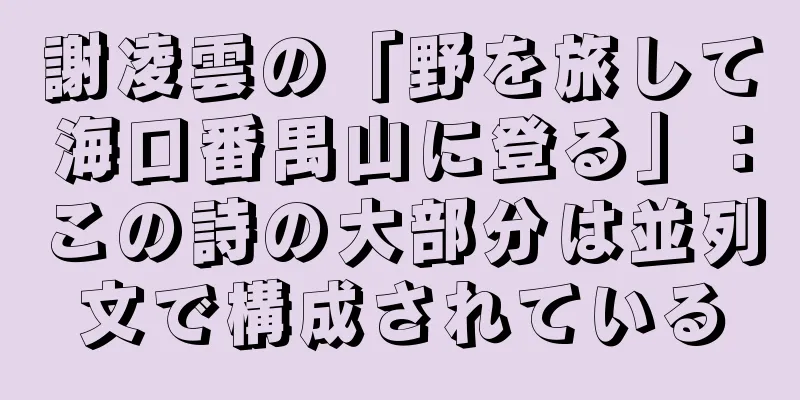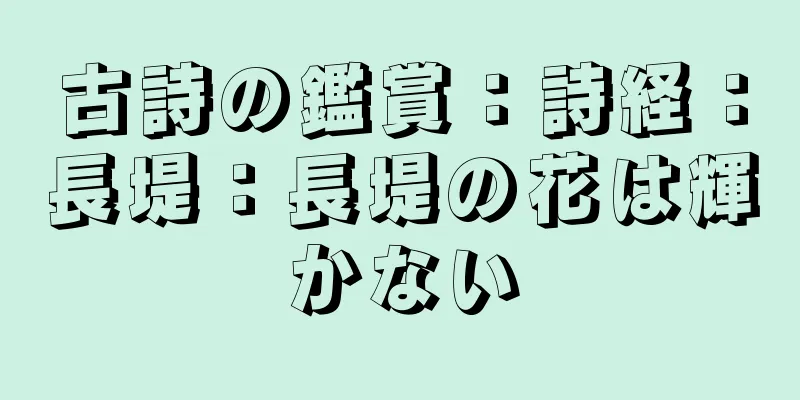晋の孝武、司馬瑶の略歴 司馬瑶はどのようにして亡くなったのでしょうか?
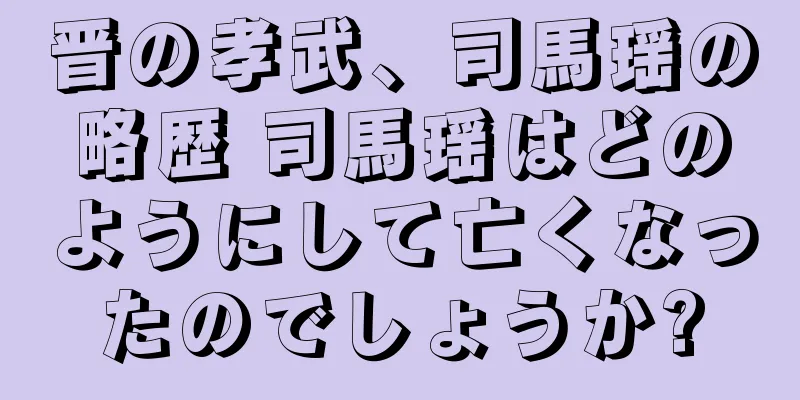
|
司馬瑶(362年 - 396年)、愛称は昌明、中国東晋(在位372年 - 396年)の第9代皇帝。彼は晋の建文帝司馬攝の六番目の息子であり、母は李霊容であった。 司馬瑶は4歳で会稽王に任命され、372年に晋の建文帝が崩御する前夜に皇太子に立てられ、11歳で王位を継承した。当初、桓文大元帥が政権を補佐した。373年に桓文が死去した後、従妹の崇徳皇太后、朱素子が政権を引き継いだ。 376年、皇太后は謝安を代表とする謝陳君家に権力を返還した。 383年、謝安らの助けを借りて前秦の軍を破り、毗水の戦いに勝利し、東晋の運命を守った。 司馬瑶は貴族階級の人材の差を利用し、貴族政治のパターンを打破して司馬朝の権力を回復することに尽力し、謝安に代わって弟の司馬道子を君主とし、東晋建国以来江左で最も強力な君主となった。しかし、享楽にふけり、酒とセックスに溺れ、司馬道子と権力を争い、「君主と宰相の膠着状態」という状況を作り出し、政治はますます暗くなっていった。その後、司馬瑶と彼の愛妾である張貴妃が酒を飲んで冗談を言い合ったため、張貴妃は怒って司馬瑶を殺害した。司馬瑶はまだ35歳だった。死後、廟号は列宗、諡号は孝武帝とされ、龍平陵に埋葬された。 司馬瑶は書道と文学に優れ、二巻からなる作品集を所蔵していたが、現在は失われている。書作品「喬王鐵」は『春花歌鐵』に収録されている。 司馬瑶の伝記 王位継承のプロセス 晋の孝武帝、司馬瑶は、雅号を昌明といい、晋の哀帝の隆和元年(362年)に生まれた。彼の祖父は東晋の初代皇帝である司馬睿、父は会稽王である司馬懿(後の建文帝)、母は李霊容(孝武文皇太后)である。司馬攀には7人の息子がいたが、最初の5人は早くに亡くなり、生き残ったのは司馬瑶とその弟の司馬道子だけだった。庚寧3年(365年)、琅邪王司馬懿が王位を継承した後、司馬懿は琅邪王の位に就き、4歳の司馬瑶が父の後を継いで会稽王となった。太和6年(371年)11月、大将軍の桓温が軍を率いて都に入り、宮廷でクーデターを起こした。崇徳太后の朱素子の命により、東海王の司馬懿を廃し、琅邪王の司馬懿を晋の太宗皇帝に即位させ、司馬瑶を皇太子とした。 司馬睿が江左で東晋を建国して以来、貴族による支配が繰り返され、貴族政治の形態が形成されました。一定の功績を残した元帝の司馬睿と明帝の司馬紹を除いて、他の皇帝はほとんど操り人形でした。建文帝の司馬攸の時代になると、皇帝の権力が弱まり、貴族が独占するという状況が頂点に達した。桓温は朝廷の政務を完全に掌握し、謝安でさえ彼を「王」とみなした。歴史には「政は桓一族が掌握し、祭祀は私が執り行う」と記されている。彼の野望は、金王朝を打倒するという目標を達成するために、建文帝に「王位を譲らせる」ことだった。建文帝は即位後わずか8ヶ月で重病に陥った。咸安2年(372年)7月23日、建文帝は4つの勅を続けて発布し、まだ姑蘇に住んでいた桓温に朝廷に来て政務を補佐するよう促した。桓温はわざと断った。5日後、建文帝の病状が悪化したため、会稽王司馬瑶を皇太子に任命し、「司馬温大君は周公の例に倣って摂政に就くべきである」と遺言を残した。また、「末子が補佐できるなら補佐し、できない場合は自らが摂政に就くことができる」とも言った。このとき、金朝の運命は重大な岐路に立たされていたと言える。なぜなら、桓温は建文帝の遺言の助けを借りて金朝を完全に簒奪し、自らの地位を確立する可能性があり、それは他の貴族たちが見たくないことだった。そのため、太原の王家の大臣である王旦之は、建文帝の前でその勅令を破り捨てた。建文帝は、勅令を「諸葛武侯(諸葛亮)と宰相王(王道)の物語のように、すべての家庭と国の事柄は大元帥に報告しなければならない」と変更することに同意せざるを得なかった。 「建文帝は間もなく崩御した。しかし、桓温の権力に恐れをなした一部の大臣は、「太帥が決定すべきだ」と進言した。琅牙の王家の尚書普社王表之は、「皇帝が崩御すれば皇太子が後を継ぐ。太帥が反対するなどあり得ない。直接相談すれば、必ず非難される」と厳しく言った。そこで朝廷は、皇太子司馬瑶が孝武帝として即位することを決定した。崇徳太后は、司馬瑶が幼く、先帝を喪っていることを理由に、再び桓温に周公に倣って摂政を務めるよう命じた。この命令が下された後、王表之は「これは極めて重大な出来事です。大司馬は必ず帝位を辞退し、すべての物事が停滞し、陵墓は放棄されるでしょう。私はあなたの命令に従う勇気がないので、帝位を返上します」と言った。この命令は実行されなかった。晋の存亡がかかっていたこの重大な局面において、各貴族が力を合わせて桓温の金王朝簒奪の陰謀を阻止し、司馬瑶の順調な帝位継承と東晋の存続を確保した。 孝武帝の司馬瑶が即位してからわずか3か月後、道士の陸松が300人の民を率いて建康宮を襲撃し、宝物を奪い、海西社の馬懿を復権させようとする反乱が起こりました。この反乱は直接桓温に向けられたものであり、客観的には汪氏、謝氏、その他の貴族の桓温に対する抵抗が強まった。寧康元年(373年)2月、桓温は姑蘇から入京した。噂によると、桓温は王・謝を殺し、晋の都を移すつもりだという。王旦之、謝安らは戦闘態勢を整えていた。桓温は前年の冬、彭城の怪物・陸松が群衆を率いて宮廷に侵入した事件についてのみ調査していた。その後、桓温は病気になり、病気の間も朝廷に九つの贈り物を与えるよう求めたが、王譚志、謝安らがそれを遅らせた。その年の7月に桓温は亡くなった。孝武帝の治世初期の危機の時期は、結局大きな問題もなく過ぎ去りました。 謝政権 桓温は死去したが、貴族政治のパターンは継続した。孝武帝は幼かったため、桓文の弟である桓崇や桓一族の喬が権力を独占し続けるのを防ぐため、謝安は孝武帝の義理の妹である崇徳皇太后の朱素子を招き、桓文の死後、三度目の国を統治させた。 歴史にはこう記されている。「当時、皇帝は若く弱く、外部には有力な大臣がいた。謝安と汪汪之は忠実に晋朝を助け、守り、ついに晋朝の安泰を確保した。」謝安と汪汪之は孝武帝を支え、晋朝を助けることに多大な貢献をし、当然ながら報われた。そのため、東晋の実権は依然として貴族の家系が握っていたが、徐々に喬国の桓氏から太原の王氏、陳県の謝氏へと移行していった。寧康3年(375年)5月、王旦が亡くなり、謝安が勢力を強め、桓充とともに中国と海外の両方を統括し、東晋の権力構造のバランスをとった。同年8月、孝武帝は結婚し、太原王家の高名な学者である王孟の孫娘である王法慧を皇后とした。弟の琅牙王子司馬道子も太原王家の王譚志の従妹を妃とした。これにより、太原王家の影響力が東晋の宮廷に存続しただけでなく、孝武帝後期の君主と宰相の膠着状態の基礎が築かれた。 太原元年(376年)正月1日、孝武帝が成人し、崇徳皇太后が政権を返上した。謝安は書記長に任命され、事実上の宰相となった。 謝安の権力における最大の弱点は、信頼できる軍事的支援がなかったことだった。内部では依然として荊州に根を張っている桓充の軍勢を警戒し、外部ではますます勢力を強める前秦政権に対処する必要があったため、陳君の謝一族は緊急に軍事力を必要としていた。太原2年(377年)、謝安は甥の謝玄を兗州太守に推挙し、広陵(現在の江蘇省揚州)に駐在させた。2年後、謝玄は徐州太守も務め、北府(現在の江蘇省鎮江)に駐在した。この時期、謝玄は劉老之、何謙、諸葛貫、高恒、劉桂、田洛、孫武忠などの勇将を募集し、主に難民で構成されていた彼らの軍隊を有名な「北宮軍」に統合しました。北軍は非常に強力で、陳県の謝氏の権力を強化しただけでなく、江左華政権の存続に強力な保証を与えた。 反秦戦争 孝武帝は即位して以来、前秦の濟政権の脅威に直面していた。寧康元年(373年)の冬、東晋西部の益州と涼州は前秦に占領された。太原以降、前秦の皇帝である苻堅は前梁・代を相次いで滅ぼし華北の統一を成し遂げるにつれ、東晋への願望が強まっていった。その後、秦と晋の交わる江淮地域の情勢は緊迫し、戦争勃発寸前となった。太原三年(378年)4月、前秦は傅两を派遣して襄陽を攻撃させた。荊州太守の桓充は抵抗した。孝武帝は謝玄に命じて徐・燕・清の民を動員し、彭城の内史の何謙を派遣して淮河と泗河を巡視させ、援軍とした。 何謙の出兵は北宮軍の最初の戦闘であった。この時から、桓軍と謝軍の上軍と下軍が協力し、互いに支援し合って前秦軍の前線を分断し、東晋の戦略の特徴を形成し、最終的な勝利を確実にする上で重要な役割を果たした。同年7月、秦軍も東西連携の戦略を採用した。秦の将軍彭超は、苻丞の襄陽攻撃と連携して彭城を攻撃するよう要請した。苻堅は彭超の策に賛成し、西部戦線の君安、茅勝らの軍を分け、東の襄陽から淮陰、許義を攻撃して彭超らと合流させた。それ以来、東晋は下流からの圧力を感じ始めた。太元4年(379年)正月、襄陽は陥落し、東晋の将軍朱旭が捕らえられた。その後、彭城、夏邳、淮陰、許義が相次いで前秦に編入された。建康は緊急事態となり、形勢は東晋にとってますます不利となった。 太原4年(379年)6月、北軍は君川で秦軍を破り、前秦軍は淮北に追いやられ、建康の非常事態は解除された。西部戦線の状況は依然として楽観的ではなかったが、君川での勝利は北軍に訓練と士気の向上をもたらし、その後の主戦場の東方移動と毗水の戦いに必要な準備を整えた。翌年、幽州で苻洛と苻仲の反乱が起こった。苻堅は反乱の鎮圧に忙しく、南方へと侵攻する時間がなかった。太原六年(381年)12月から翌年9月まで、桓充は荊州で前秦軍と何度も戦い、守備や攻撃を行い、わずかな戦果を得た。前秦は苻融を南伐将軍に任命し、晋を攻撃する計画を立てた。太元7年(382年)10月、苻堅は臣下に大規模な金攻めの計画を発表した。臣下の多くはこれに反対し、「謝安と桓充は江表の名士であり、君主と臣下は和合し、内外は心を一つにしている」と強調した。しかし、苻堅は必ず成功すると決意し、自ら行動を起こした。孝武帝を尚書左輔社、謝安を人臣、桓充を士中と定め、長安に彼らのために邸宅を建てた。太原8年(383年)5月から7月にかけて、桓充は10万の軍を率いて襄陽に反撃し、劉伯らを派遣して綿陽の北の都市を攻撃させ、楊良を派遣して蜀を攻撃させ、郭権を派遣して武当を攻撃させた。前秦の傅睿と慕容垂は5万の軍勢を率いて襄陽を救出し、張充は武当を救出し、張昊と姚昌は府城を救出した。これは桓充が桓水の戦いの前夜に建康への圧力を緩和し、苻堅の侵攻軍を疲弊させるために行った大規模な支援行動であった。この時、謝宣の部下であった広陵の宰相劉老之も宣城の内史胡斌を派遣し、軍を率いて首陽に向かわせ、襄陽を攻撃していた桓充の軍を支援しさせた。これは東晋の桓氏と謝氏の二大氏が強大な敵に直面した際に団結していたことを示している。 しかし同時に、桓充は王徽を江州太守に推薦し、謝安は謝福を江州太守に推薦した。両者の対立は再び起こった。最終的に謝安は屈し、孝武帝は桓充を江州太守に任命した。 これは氏族間の根底にある矛盾を反映しており、共通の敵に対する共通の憎悪という外見に不協和音を加えています。 太元8年(383年)8月、前秦の皇帝苻堅は中国統一を目指して大規模な晋攻撃の勅を出し、ついに桓水の戦いが勃発した。苻堅は自ら歩兵60万、騎兵27万、楡林郎(近衛兵)3万を含む90万の軍を率いて長安から南へ進軍し、数千里に渡って陸路と水路を進み、穀物を運ぶ船だけでも数万隻に上った。同時に、苻堅は梓潼太守の裴元禄に、巴蜀から7万人の水軍を率いて河を下り建康に向かうよう命じた。苻堅は傲慢にもこう宣言した。「私の兵力では、鞭を川に投げ込むだけで川の流れを止めることができる。」これが「鞭を投げて川の流れを止める」という有名な喩えの由来である。 秦軍と戦うために北上した東晋の総兵力はわずか8万人だった。宰相謝安の指揮の下、謝世を総司令官、謝玄を先鋒、北軍を主力として戦いに臨んだ。当時、秦軍の先鋒であった苻堅の弟苻容は30万の軍を率いて先に営口に到着した。秦軍は最初の戦いで勝利し、首陽を占領し、東晋が救援に派遣した胡斌の軍の退路を断ち、西施で包囲した。苻堅はこの朗報を聞いて大いに喜び、主力を襄城に残し、軽騎兵8000人を率いて首陽に向かった。また、襄陽で捕らえられていた東晋の将軍朱旭を派遣し、金軍に降伏するよう説得させた。朱璋は祖国のことを念頭に置き、秦軍の配置を詳細に明らかにし、秦軍が完全に集結する前に急襲することを提案した。謝石は当初、戦わずに持ちこたえるつもりだったが、朱旭の言葉を聞いて戦略を変え、先手を打って攻撃することにした。 11月、謝玄は劉老之に5千の精鋭部隊を率いさせて羅江を渡河させ、敵の5万の部隊を攻撃させた。彼らは大勝利を収め、梁成を含む前秦の将軍10人を殺した。洛江の戦いは晋軍の自信を高めた。謝世は引き続き軍を陸海から率いて毗江東岸に到達し、八卦山の近くに大きな陣地を築き、河を挟んだ首陽で秦軍と対峙した。謝玄は、両軍の力の差があまりにも大きいこと、また金軍が消耗戦を長引かせることを望まなかったことから、秦軍に使者を派遣し、両軍が戦えるよう、少し後退して少し距離を置くよう要請した。苻堅は、軍が少し後退し、晋軍が川を半分渡ったところで騎兵で突撃すれば勝利できると考え、謝玄の要求を受け入れて秦軍に撤退を命じた。その結果、秦軍は撤退するとすぐに統制を失い、陣形が乱れてしまった。謝玄は8,000人以上の騎兵を率いて沛江を渡り、秦軍に猛攻撃を仕掛けた。この時、朱旭は状況を利用して、隊列の後ろで叫んだ。「秦軍は敗北した! 秦軍は敗北した!」 秦の兵士の多くは強制的に徴兵され、複数の民族で構成されていた。彼らは同じベッドで寝ていても、別々の夢を見ていた。人々の士気はすでに不安定だった。朱旭の叫び声は彼らに本当に敗北したと思わせ、彼らはさらにパニックになり、逃げようと急いでいた。数十万の軍隊が武器や鎧を捨てて、地滑りのように逃げ去った。謝玄とその部下たちは、青岡(現在の首陽の西30マイル)まで敵を追跡した。この時、苻容は戦いで戦死し、苻堅は流れ矢に当たって一人で北へ逃げ、朱旭は混乱に乗じて金の陣営に逃げ、東晋は毗水の戦いに勝利した。 毗水の戦いは中国史上、大国を打ち負かし、弱者が強者に打ち勝った有名な例であり、後世に有名な歴史的暗示や慣用句を残しました。 「鞭を投げて川の流れを止める」、「風の音と鶴の鳴き声」、「八公山ではすべての木と草が敵である」など、常に人気があります。 毗水の戦いの後、東晋は北部の混乱に乗じて巴蜀、山東、河南の失われた領土の大部分を回復し、黄河の北にある鄴城まで戦いを続けた。その後、翟衛、西燕、后燕などの胡氏の反撃や東晋朝内の内紛により、毗水の戦いで東晋が奪還した淮河以北の土地の大半は孝武帝の治世末期までに再び失われた。 メインフェーズの膠着状態 桓水の戦いでの勝利は東晋の活力を継続させたが、内部の権力構造に微妙な変化が起こり、その後、支配グループ内での内紛が続いた。長らく貴族政治に耐えてきた孝武帝の司馬瑶は、太元8年(383年)9月、前秦の南征の際に謝安の権力を分かち合い始め、弟の琅邪王司馬道子を尚書六事の記主に任命した。 陳君の謝一族は毗水の戦いで勝利を収めたが、その功績が報われないというジレンマに陥った。一つは揚子江上流と下流での桓氏と謝氏の対立であったが、桓充が桓水の戦いの直後に死去し、桓氏の一族が一時的に無人となったため、この対立は解決した。もう一つは孝武帝と司馬道子に代表される司馬帝の権力が貴族一族に挑戦したことであり、これが謝氏が危機に直面した主な理由であった。当時、太原王家の王国宝らは「おべっか」を使って孝武帝と謝安の関係を悪化させた。また、謝安は名士であることにコンプレックスがあり、権力争いを好まなかったため、譲歩した。太原9年(384年)8月、謝安は北伐を願い出た。翌年4月、広陵に移り、8月に亡くなった。司馬道子は当然のことながら揚州の知事、書記局の記録官、国内外のすべての軍隊の司令官となった。謝安が疎外されて亡くなると、謝玄は北朝での地位に満足できなくなり、北伐の失敗と病気のため、太元12年(387年)正月に軍事権を剥奪され、会稽内史に退いた。1年後に亡くなった。彼が支配していた徐・清・燕の3国は、王族の司馬道子(徐州太守兼任)と喬王司馬天(清・燕両国太守)の2人によって次々に分割された。謝玄の引退は謝陳君一族の貴族政治の終焉を意味し、孝武帝が皇帝の権力回復を完了したことも意味した。 孝武帝は自ら国を統治し、独自の権威を持っていたが、明らかに君主としての資格はなかった。孝武帝とその弟の司馬道子は酒と性行為にふけり、宮廷を乱れた場所にした。また彼らは仏教を信仰し、僧侶や尼僧を優遇したため、政治はますます不透明になった。しかし、孝武帝と司馬道子の「歌い、努力する」という表面の下には、兄弟の間には深い矛盾が隠されており、それが太原後期の「主宰膠着状態」の構図を形成した。君主と宰相の膠着状態は、太原王家、つまり外戚内部の矛盾、すなわち孝武帝の皇后の子孫である王公の一族と、琅邪公主の子孫である王塵と王国宝の一族との争いに端的に表れた。太原の王家は陳君の謝家の跡を継いだが、才能も功績もなく、皇帝の権力を抑えて政局のバランスを保つことができず、司馬家に頼って家利を追求することしかできなかった。これは貴族の以前の政治構造とは大きく異なります。司馬道子が宰相になった後、彼の権力は増大した。袁月之は司馬道子に政権を握るよう助言した。そこで王公は孝武帝に袁月之を殺すよう命じた。孝武帝は袁月之を他の罪を犯したという口実で市場で処刑し、「その後、派閥争いや反対意見の声が朝廷と国中に広がった。」 太元14年(389年)11月に袁月之が殺害されたことで、主君と宰相の対立が公になった。 太元14年(389年)6月と太元15年(390年)1月、江陵に駐在していた荊州太守の桓世民と荊口に駐在していた青州・兗州太守の司馬懿が相次いで死去し、上流と下流の争いは主君と宰相の膠着状態の焦点となった。江陵と京口の二つの領地はそれぞれ王塵と王公が獲得した。太元15年(390年)8月、司馬道子は共犯者の于凱を豫州の太守に任命した。太元17年(392年)10月、荊州太守を務めていた王塵が病死したため、孝武帝は荊州奪還に動き出し、東晋の政情は再び変化した。司馬道子は、王国宝を兄の後継者として荊州太守に任命しようとした。孝武帝は当然のことながら、荊州のこの大物が司馬道子の手に渡るのを快く思わなかった。彼は迅速に行動し、司馬道子が支配する人事部の選考を経ずに、「中昭」を通じて、信頼する大臣の殷仲幹を荊州太守に任命した。同時に、孝武帝は老齢と病気のため引退した朱旭に代わり、「才才と文才で名声を博した」西慧を雍州知事と襄陽駐屯兵に任命した。こうした一連の人事異動により、孝武帝は君主と宰相の間の膠着状態において優位に立った。 司馬瑶はどうやって亡くなったのですか? 孝武帝の皇后は「酒飲みで傲慢で嫉妬深い」王法徽で、太元5年(380年)に亡くなった。その後、孝武帝は別の皇后を立てず、代わりに美しい陳桂女と張桂人を寵愛した。太元21年(396年)9月20日、孝武帝は清州宮の後宮で張貴妃と酒を飲んだ。孝武帝は酒に酔って張妃に冗談を言った。「あなたはもう30歳近くになり、美しさも以前ほどではなく、子供もいません。貴婦人の地位に就いているのはただの無駄です。明日私はあなたを廃位させて、若くて美しい別の娘を見つけてあげます。」張妃はこれを聞いて嫉妬に燃えたが、酔った孝武帝はそれに気づかなかった。冗談はますます激しくなり、張妃は彼女を殺すことを決意した。彼女はまず孝武帝の周りの宦官たちを酔わせ、孝武帝と宦官たちが眠った後、信頼する宮廷の侍女たちを呼び寄せ、孝武帝が眠っている間に布団で窒息死させた。 その後、張妃は皇帝が眠っている間に亡くなったと嘘をついた。中書大臣の王国宝は夜遅くに紫禁城の門を叩き、皇帝に遺言状を書こうとしたが、王公の弟である朝大臣の王爽に止められた。当時、会稽王に昇格した司馬道子も色欲に耽っており、その息子の司馬元嬪が権力を握っていた。父子はもともと孝武帝と対立していたが、君主と宰相の膠着状態の中で孝武帝に抑圧され、孝武帝の死を願っていたため、張貴妃を追及しなかった。 皇太子司馬徳宗が即位し、晋の安帝となった。晋の安帝は、晋の恵帝よりも精神障害が重かったため、当然ながら父の死を追及することはなかった。歴史家の陸思面は、孝武帝が張妃に酔った冗談で殺されたという噂は真犯人が流した噂ではないかと疑ったが、宮廷女官に殺されたことは間違いなく、孝武帝の死は司馬道子とその息子、そして王国宝などの取り巻きたちによって企てられた陰謀だったのではないかと示唆した。 司馬瑶の死後、彼は孝武帝と諡され、寺号は列宗とされた。孝武定皇后の王法慧とともに龍平陵(現在の南京中山梅花山)に埋葬された。 |
<<: ターコイズの細工の品質をどのように見分けるのでしょうか?
推薦する
史公の事件第276話:本当の地方暴君は処刑され、偽の郡長は民衆を虐待し、残酷な役人になった
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
斉の桓公の台頭
はじめに:斉の桓公が管仲を宰相に任命する書簡が魯の国に届いたとき、魯の荘公は激怒し、目をぐるりと回し...
「高石と薛居と慈恩寺の塔に登る」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
高士と薛菊と一緒に慈恩寺の塔に登る岑神(唐代)塔はまるで湧き出て、空高く聳え立っているようです。世界...
皇帝の物語:なぜ父と息子の関係は最終的に緊張してしまったのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
『紅楼夢』で、趙叔母と方観が喧嘩した後、丹春は何と言いましたか?
長い時間の流れは止まらず、歴史は発展し続けます。『Interesting History』の編集者が...
韓国軍は歴史上弱者だったのか?
最近、韓国の特殊部隊の海外物語を描いた韓国ドラマ「太陽の末裔」が中国で人気を集めている。多くの中国人...
『紅楼夢』で王夫人は賈蘭とその母親に対してどのような態度を取っているのでしょうか?なぜ彼らとコミュニケーションをとらないのですか?
王夫人は四大家の一つである王家に生まれ、名家の令嬢と言えるでしょう。本日は、Interesting ...
『賈怡新書』第1巻の『郭欽中』の原文は何ですか?
秦は周王朝を滅ぼし、国を統一し、諸侯を併合し、南を向いて皇帝を名乗り、四つの海を利用して国を支えた。...
王維の「中南山」:この詩は中南山の雄大さを讃えるものである。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
西晋時代の土地制度はどのようなものだったのでしょうか?西晋時代の土地制度の詳細な説明
西晋の土地制度とは何だったのでしょうか?これは多くの読者が気になる質問です。次に、西晋の土地制度につ...
李青昭は「秦鄂を偲ぶ:高亭に立つ」でどのような芸術技法を使用しましたか?
李青昭が「秦鄂を偲んで高楼に立つ」でどのような芸術技法を使ったか知りたいですか? この詩は作者が東屋...
陳涛の『龍溪行』:詩全体が作者の内なる反戦感情を表現している
陳涛(812年頃 - 885年)、号は宋伯、三教庶人と称し、鄱陽江埔の人であった(『唐詩全集』では嶺...
『紅楼夢』では胡医師はインチキ医者ではなく、王医師が厄介者だ
『紅楼夢』には「胡医者は虎狼の薬を無差別に使う」という章があります。実は、この本に出てくる胡医者は胡...
クラゲの雪うさぎはどれくらい貴重なのでしょうか?中国のどの地域に主に分布していますか?
Saussurea medusa Maxim は、キク科の Saussurea 属の多年生で複数の果...
歴史上、王昭君と胡漢野単于は良好な関係にあったのでしょうか?
『漢書匈奴伝』と『後漢書南匈奴伝』には昭君の辺境への出征の記録が次のように記されている。漢の宣帝の治...