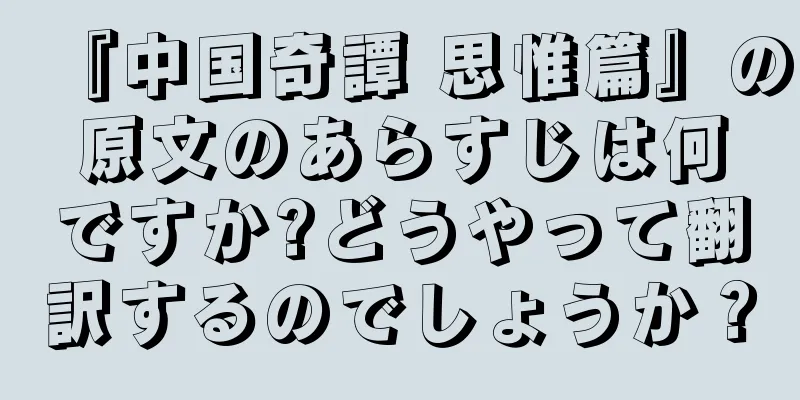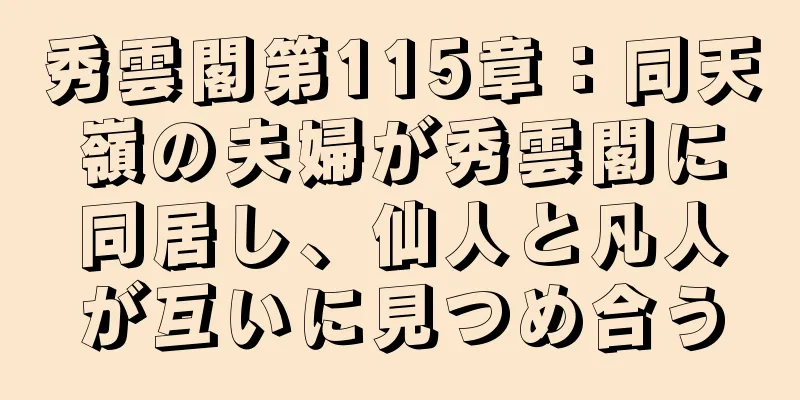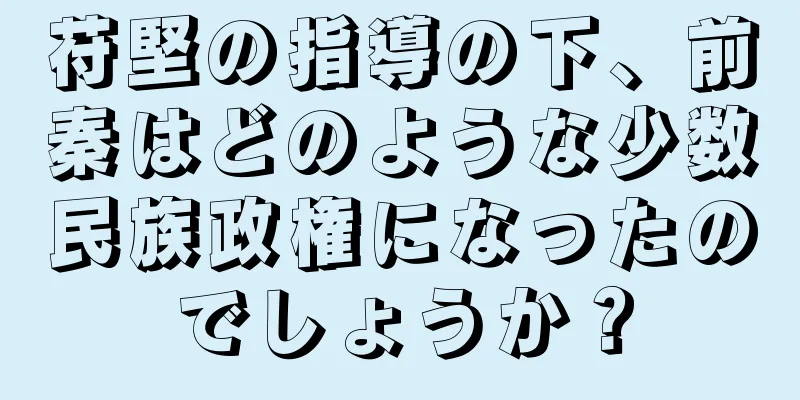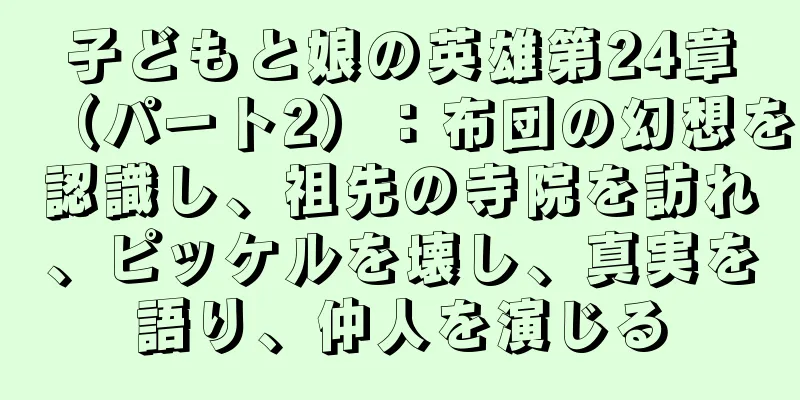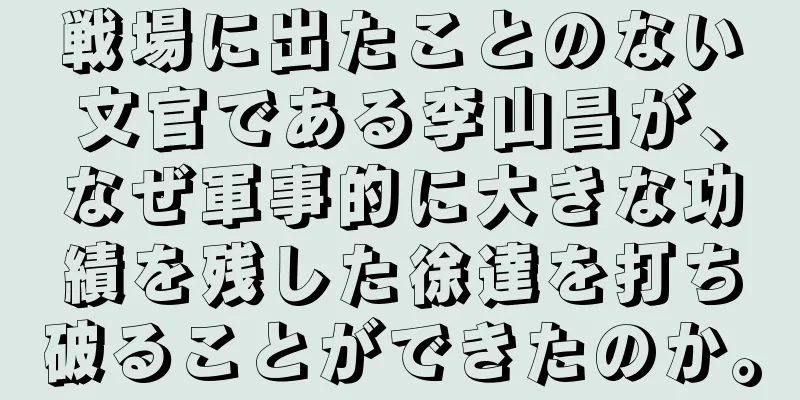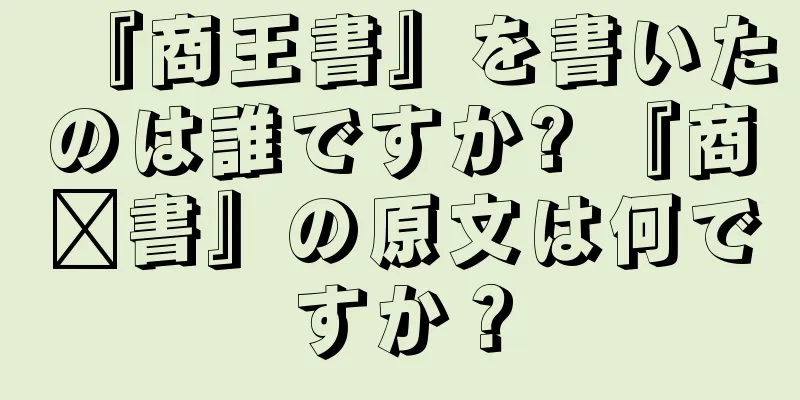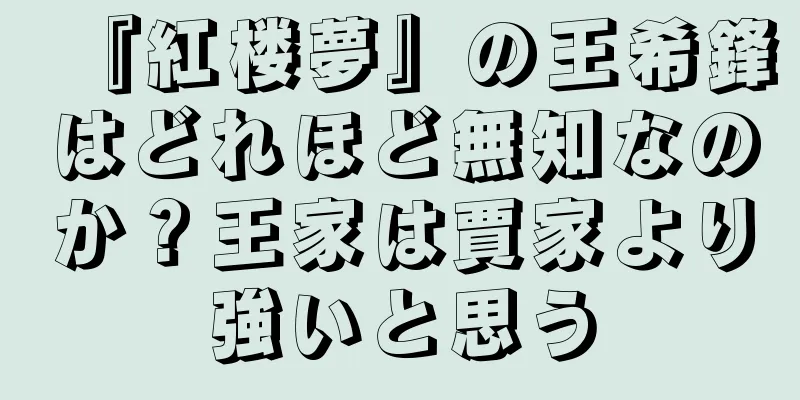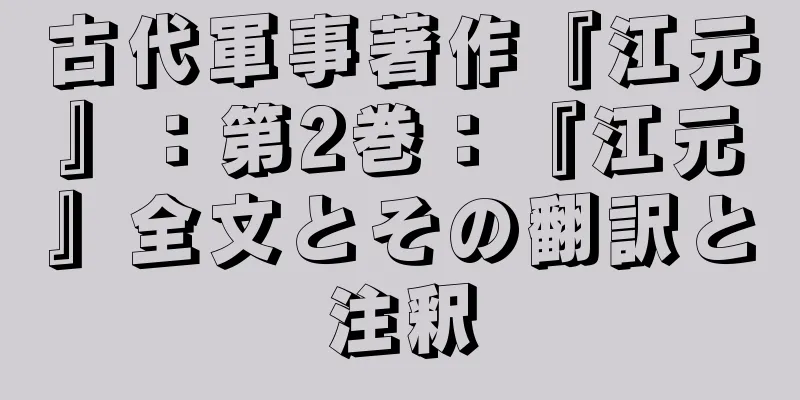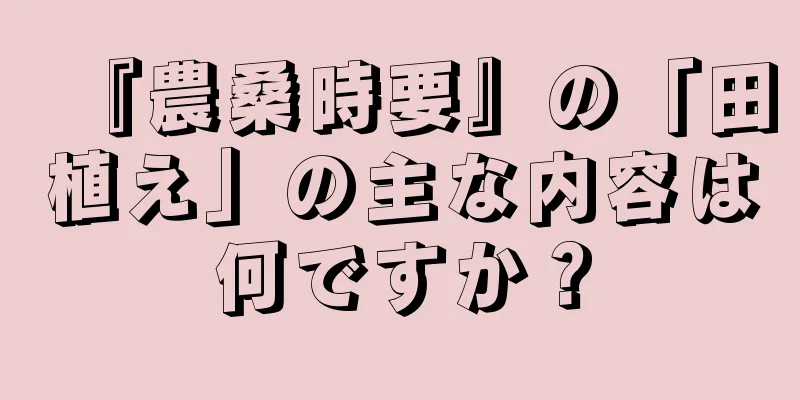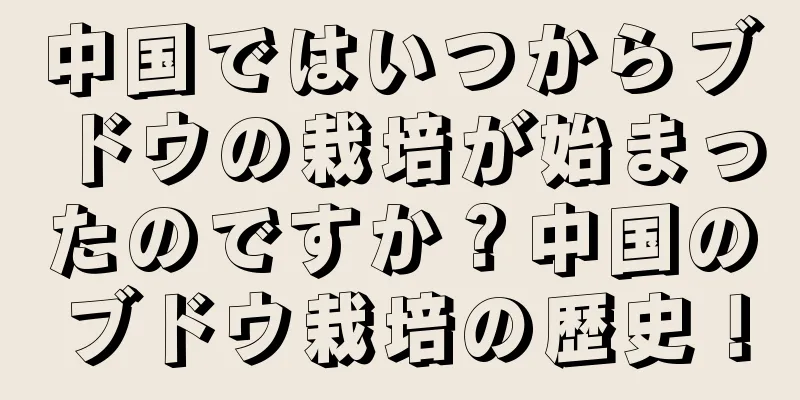古代の礼儀作法と法律:「三つの服従と四つの美徳」
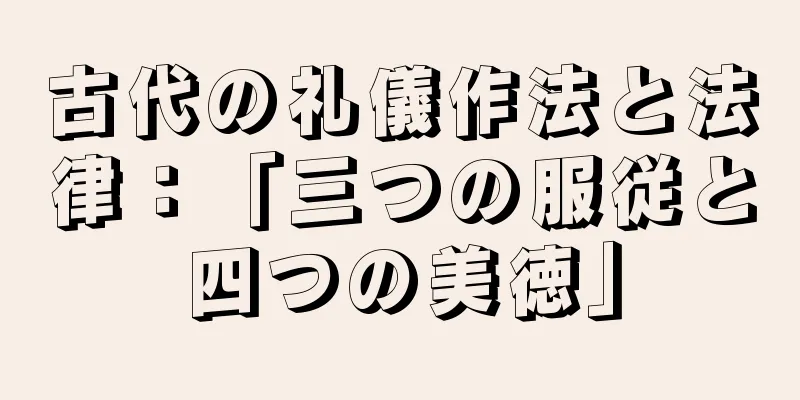
|
「三服四徳」は漢民族の古代の習慣の一つであり、現代人もそれについて語るのが好きです。 「三服四徳」は、家父長制家族の安定に適応し、家父長制と家父長制の家族(氏族)の利益を守るために考案されたものであり、「内外の区別」と「男尊女卑」の原則に基づいており、儒教倫理が女性に生涯にわたる道徳、行動、修養の面で課す規範と要件です。 「三服」という言葉は、周漢の儒教の古典『伊礼喪服子夏伝』に初めて登場した。既婚女性が夫と父のために喪に服す期間(夫は3年、父は1年)について論じた際、「女性には『三服』の意味があるが、『排他的』な方法はない。結婚前は父に従い、結婚後は夫に従い、夫の死後は息子に従う」と述べられている。これは、女性は娘、妻、母親として男性に従うべきであるという意味にまで拡張されています。しかし、女性には従順という長い歴史がある。商王朝の甲骨文字の「女」という文字は、ひざまずく人物を表している(フォントを表示)。『易経』には、女性は従順で忠実であり、永遠に夫に仕えるべきだと説く卦がある。後に、女性は夫に忠実であり続けることが求められ、未亡人の再婚は制限された。 「四つの徳」という言葉は『周礼天官内在』に登場します。内在とは、後宮の女性を指導する役職で、後宮の女性に「陰の礼」と「女性の務め」を段階的に教える責任があります。その中で、上位の「九妾」は女性学の方法を担当し、九妾に女性の美徳、女性の言葉、女性の容姿、女性の仕事を教えます。 「これはもともと宮廷の女性のための教育の範疇でした。後に「三服四徳」と組み合わされて、女性の道徳、行動、能力、教養の基準、すなわち「三服四徳」となりました。三服四徳とは、結婚前は父親に従い、結婚後は夫に従い、夫が亡くなった後は息子に従うというものです。「結婚前は父親に従い」 「Cong」には、聞く、従う、服従する、従うなど、複数の意味があります。三服を守らなければならない女性は、自己中心的であったり、自立的であったりすることはできず、父親の命令、夫の願い、子供の願いに従い、孝行な娘、徳のある妻、良い母親でなければなりません。 「結婚する前に父に従う」とは、未婚の娘が父と両親の言うことを聞くことを要求し、「父の命令に背かない」とは「親孝行をする」ことを意味する(孔子の説明によると「親」は両親を指すが、「父に仕えることで母に孝行する」とも言った)。孝行な娘は、日常生活で父親の面倒をよく見るだけでなく、危険にさらされた父親のために立ち上がらなければならない。例えば、前漢の文帝を説得して体罰を廃止させ、父親を犯罪から救った淳于鉄英や、水に落ちた父親を救おうとして溺死した東漢の曹鄂(歴史書には曹鄂の孝行を称える「曹鄂碑」がある)。生涯にわたる結婚という大切な事柄において「親の言いつけ」に従うことは、「従順」であり、親孝行の表れでもあるのです。 「結婚したら、夫に従うべきです」 「結婚したら、夫に従うべきです」とは、既婚女性は夫に従い、服従し、従わなければならないという意味です。 「夫に従う」ことは、女性が結婚することから始まります。結婚式は「男性が女性を導き、女性が男性に従う。そこから夫婦の義が始まる」ものであり、母親は娘に「夫に逆らってはならない」と教えます。夫の実家に行くと、夫の世代や身分に応じて相対的な呼称(嫁、義妹、叔母、義姉など)が与えられます。妻は夫を「天」とみなし、「天の意思は逃れられないし、夫の命令には背くことはできない」と信じています。妻は夫に従い、夫を尊敬し、夫の命令に従わなければなりません。例えば、漢代の孟光は夫の梁洪に対して「ボウルを眉の高さに持つ」という接し方をし、「お互いを客人のように尊重している」と賞賛された。妻はまた、日常生活において夫に代わって親孝行をし、義理の父母に仕え、夫のために子供を産むことが求められます。「夫を支え、子供を育てる」ことは宋代以来、女性にとって最も重要な責任となっています。 「夫に従う」とは、夫に忠実で貞潔を守り、夫の死後も他の夫と結婚せず、さらには自殺して夫に従うことも意味します。春秋時代、西王の妻である西夫人は、夫が楚の国に捕らえられたとき、死ぬと脅して拒否しました。楚王は彼女を妻にすることを強制し、彼女は歴史書に貞潔の模範となりました。貞操と忠誠を賞賛する公式の制度は、王朝を通じて制度化され、一部の女性が自殺することになった。夫が病気や戦いで死ぬ前に、妻や側室は夫への忠誠を示すために事前に自殺した。 「夫が亡くなったら息子に従う」 「三つの服従」のうち、「夫が亡くなったら息子に従う」だけが不可解です。なぜなら、儒教の倫理には「母を敬い、孝行する」という伝統があり、母親は息子に対してかなりの権力を持っているからです。 しかし、礼儀作法には「女性は他人に従順でなければならない。若いときは父親や兄弟に従い、結婚したら夫に従い、夫が亡くなった後は息子に従う」とも規定されている(『礼記:郊外の供儀』)。ここでの「従う」とは「教えや命令に従う」という意味で、すべての事柄は父親、夫、息子によって決定されることを意味する。夫を亡くした未亡人にとって、「息子に従う」ことは「夫に従う」ことの延長線上にある。貞潔を守り再婚しないだけでなく、大変な苦労をして息子を育て、家長として息子に従い、重要な事柄は息子に決めさせなければならない。春秋時代、魯国に9人の息子を持つ未亡人がいました。年末の祭祀が終わった後、彼女は実家に帰省したいと考えていました。「夫が亡くなったら息子に従う」という作法に従って、息子たちの同意が必要でした。息子たちを呼び出して約束を取り付けた後、彼女は9人の嫁に玄関の番を頼み、夕方には帰ると言いました。結局、彼女は暗くなる前に家に戻り、暗くなるまで玄関の外で待っていました。彼女は魯国から来た医者に診察してもらい、礼儀正しいと褒められました。孔子の叔母である景江も模範的な未亡人でした。彼女は何事にも礼儀正しく行動しました。夫と息子が相次いで亡くなったとき、彼女は朝には夫のために、夕方には息子のために泣きました。孔子は彼女を「礼儀を知っている」と称賛しました。 四つの徳目:徳、言葉、容姿、技巧。いわゆる「四つの徳目」とは、徳、容姿、言葉、技巧のことです。つまり、女性にとって、まず大切なのは道徳心、つまり自分自身の正しい基盤を確立できることです。次に、容姿(外出時には威厳があり、落ち着いていて礼儀正しく、軽薄で気楽な態度を取らないこと)、言葉(人と話すときに意味を持たせることができ、相手の言うことを理解し、何を言うべきか、何を言うべきでないかを知ることができること)、そして家計管理の方法(家計管理の方法には、夫を支え、子供を教育すること、年長者を敬い、若者を愛すること、倹約すること、その他の生活の細部が含まれます)が重要です。 (周立、天観、九品) 女性の徳とは、貞操を守ること、一人の男性に忠実であること、二人の夫と結婚してはならないことなどです。封建時代に建てられた女性のための記念碑は、すべて女性の貞操を讃えるものだったと言えます。処女を失った女性は、世間に謝罪するために死ななければならない。死後も「ヒロイン」として人々に讃えられる。しかし、処女を失った後も生きていれば、人間に蔑まれる怪物となる。 女性の話し方: 女性は美しい言葉遣いをし、慎重かつ適切な話し方をし、下品な言葉を使わないことが求められます。 女性の容姿とは、女性の肉体的な外見の美しさを指します。「女性は自分を喜ばせるために着飾る」。女性は、威厳のある上品な容姿で夫を喜ばせるべきです。 女性の仕事とは、紡績、織物、裁縫、刺繍などの労働を指します。女性はこの範囲内でのみ知性と才能を発揮することができます。 |
>>: 昔の美人たちはどのように肌の手入れをしていたのでしょうか?
推薦する
「女仙の非公式歴史」第6章:古い借金を返済するためにリン・ランと半年結婚し、売春婦を訪ねて3回性欲を失った
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
馮子英が鉄王山を包囲したとき何が起こったか?真実の分析
その激動の時代に、馮子英という名の平凡な男が、その勇気と知恵によって伝説を創り出しました。彼の物語は...
「黄金の家に住む美しい少女」という慣用句はどこから来たのでしょうか?漢の武帝は彼女をどのように扱いましたか?
衛王后(?~紀元前91年)は衛王であった。河東平陽(山西省臨汾市、金山市の南西)。漢の武帝の皇后。彼...
秦の十六国時代の苻登は何人の妻を持っていましたか?苻登の妻は誰でしたか?
苻登(343年 - 394年)、号は文高、秦の玄昭帝苻堅の孫であり、将軍苻昌の息子であり、十六国時代...
『董香閣 氷皮玉骨』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】私が7歳のとき、梅州出身の老尼僧に会いました。彼女の姓は朱でしたが、名前は忘れてしまい...
宋の仁宗皇帝はなぜ皇太子を任命するまでに40年も待ったのでしょうか?理由は何ですか?
古代王朝にとって、皇太子を立てることは非常に重要な事柄でした。なぜなら、皇太子がいれば、自然死であろ...
『北宋史』第23章:木こりが孟良流を捕らえる計画を立て、騎手一人を派遣して焦瓜を捕らえる
『北宋実録』は『楊将軍伝』とも呼ばれ、明代嘉靖年間に熊大牧によって著された。楊将軍が遼に抵抗した際の...
宋慈の『三段清明節』を鑑賞するとき、作者はどのような表現形式を使ったのでしょうか?
三台・清明応志、宋代の万奇雍、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします、見てみましょ...
水滸伝の張青の強さは武松や林冲と比べてどうですか?
張青は『水滸伝』の登場人物で、通称は「梅玉堅」、張徳県の出身で、もともとは東昌県の守備隊長であった。...
水滸伝 第30話:張都堅の血が元陽楼に飛び散り、呉星哲が夜の百足峠を歩く
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
『湘寺録』の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
象寺の記録王守仁(明代)霊山と博山には象寺があります。下に住むミャオ族とイ族は皆、彼を神として崇拝し...
陳仁傑の『秦元春・定有年の情』:作者は全盛期で、活力と生命力に満ちていた
陳仁傑(1218-1243)は、陳経国とも呼ばれ、雅号は崗富、号は桂峰で、長楽(現在の福建省福州)の...
「小松」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
小松杜荀和(唐代)幼い頃から草が生い茂る中で暮らしてきましたが、少しずつ雑草が生えてきたように感じま...
諸葛亮は、言ってはいけないことを言っていたにもかかわらず、なぜ魏延を殺す勇気がなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
なぜ曹操は郭嘉や荀攸などの顧問に呂布を殺すべきかどうか尋ねなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...