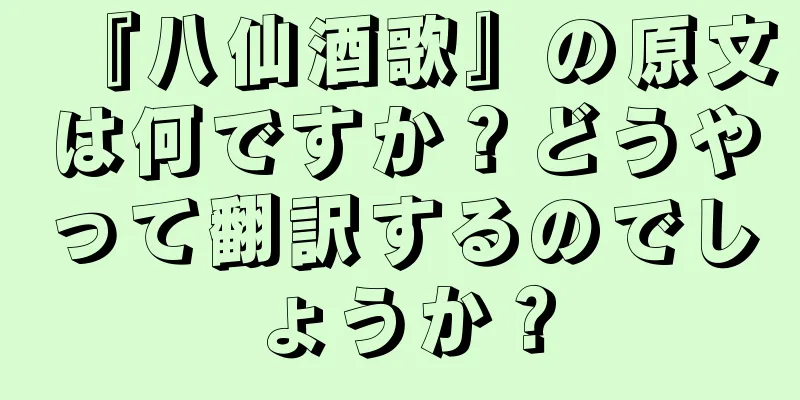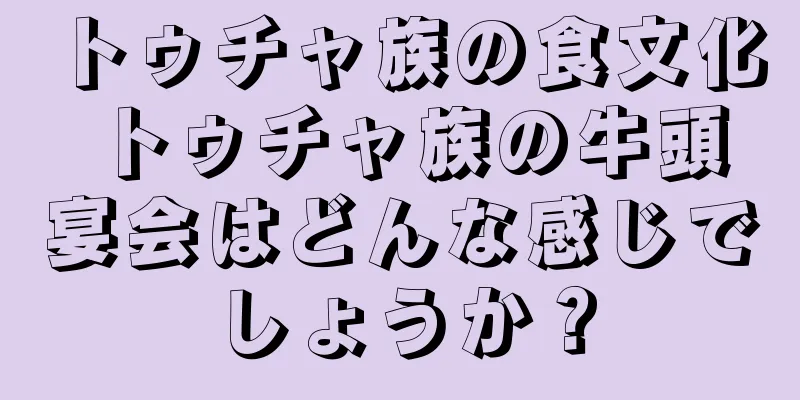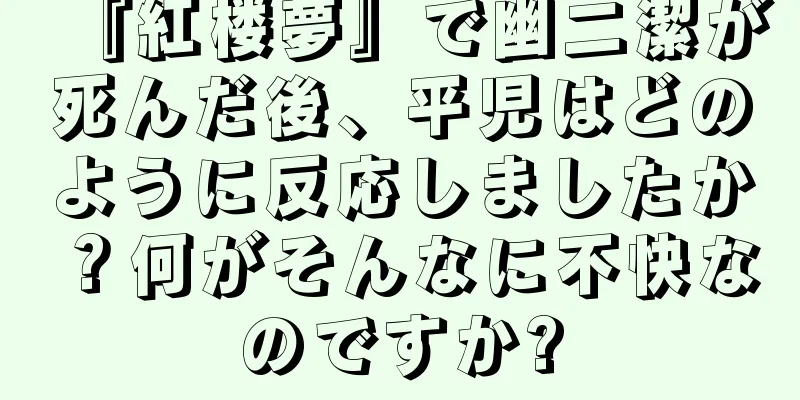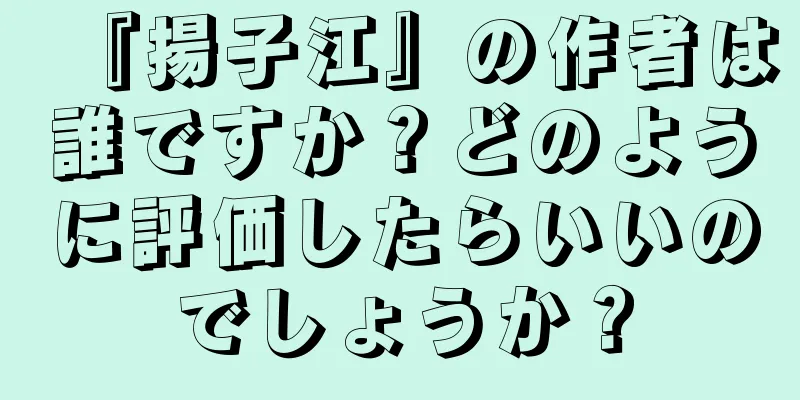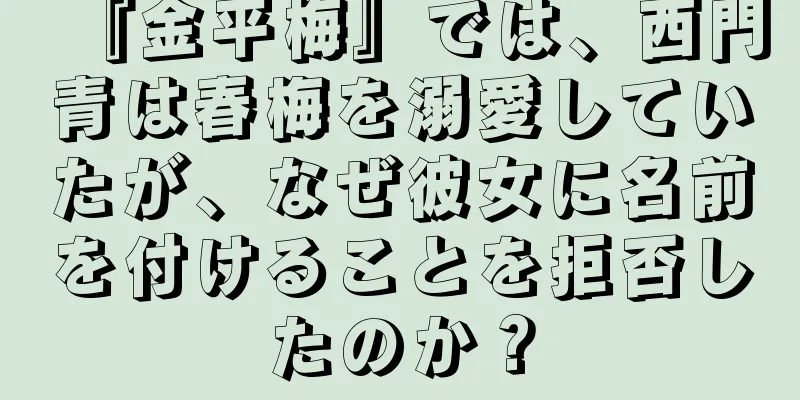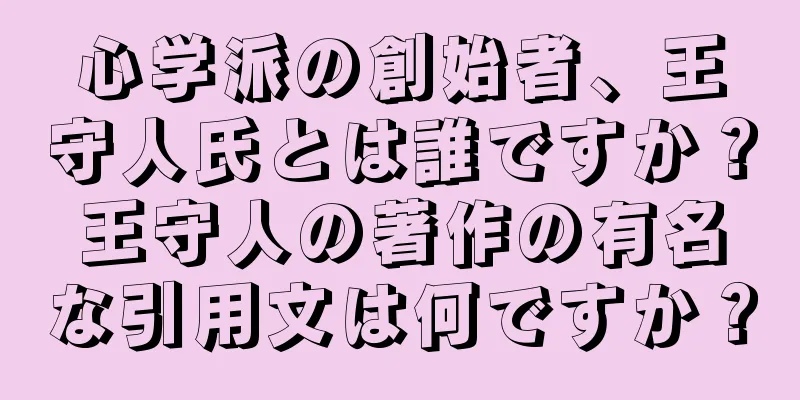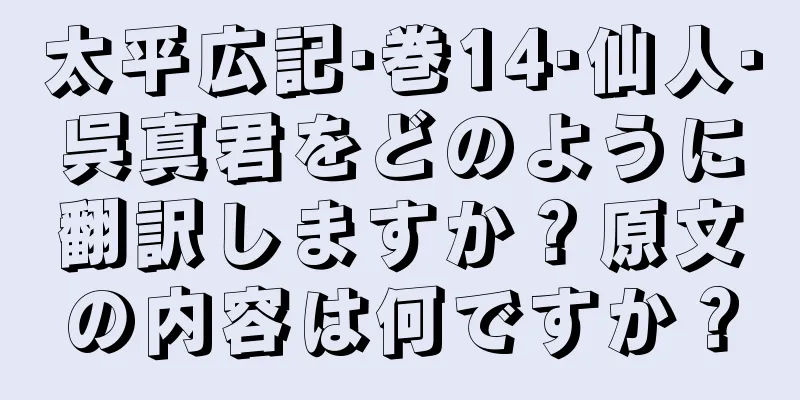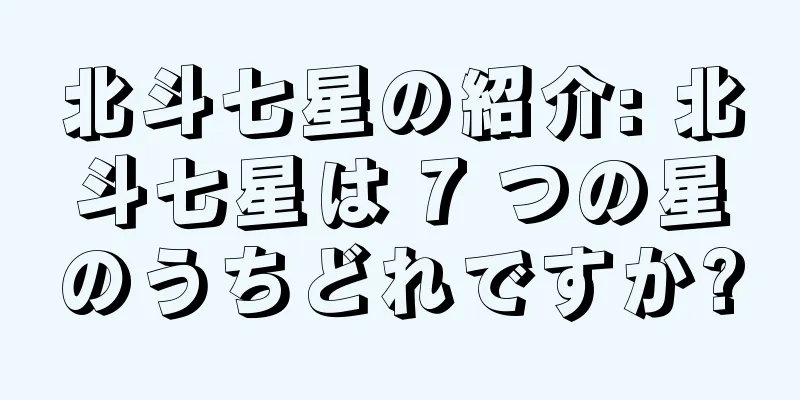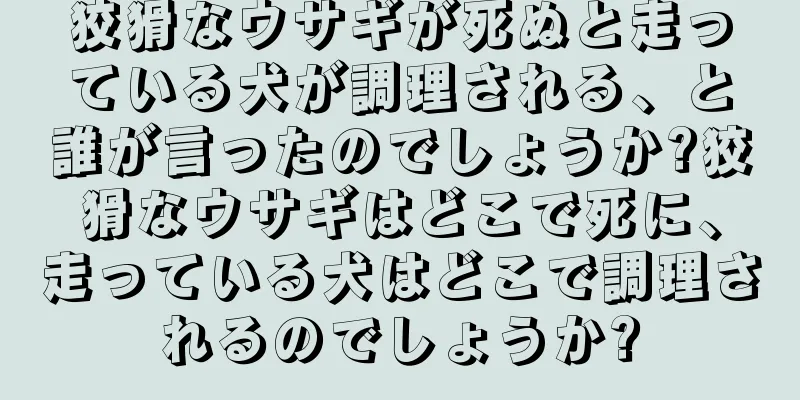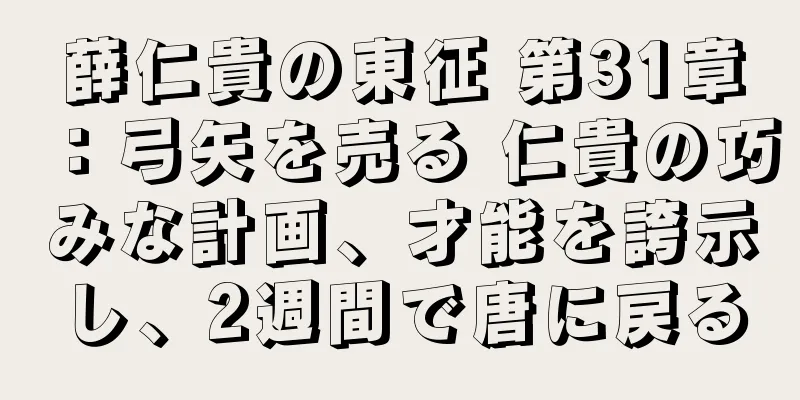映画やテレビシリーズに登場した古代の毒薬トップ3
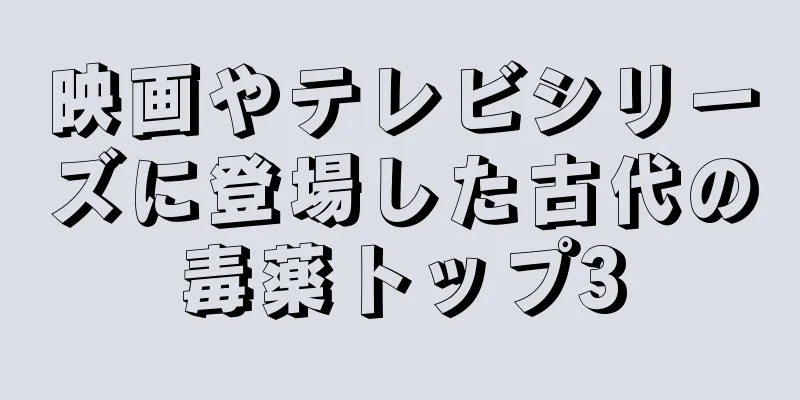
|
人類が毒を発見したのは偶然だったのかもしれません。おそらく、調理中に特定の植物が非常に有毒であることを発見したのでしょう。しかし、毒に関する知識を持つ者は、当時、部族の魔術師として尊敬されていました。 記録に残る最初の毒殺事件はキリスト教時代のローマ帝国で起こったものですが、それ以前にもインド人、中国人、ギリシャ人、エジプト人が毒を使用していたと言われています。以下は古代の9つの主要な毒です。 1. 喉から血が出る 血の渇き 「毒矢木」や「ハサミ木」とも呼ばれ、国家保護下にある絶滅危惧植物であり、世界で最も有毒な植物種の一つです。 樹液は乳白色で非常に有毒です。傷口から液体が血液に入ると、生命を脅かす可能性があります。古代人は野生動物や敵を殺すために矢にこれをよく塗りました。フラッシュセール。東南アジア原産。私の国、海南省の西双版納植物園で見ることができます。 2. ゲルセミウム・エレガンス ゲルセミウム・エレガンス 『射雁英雄の帰還』を見た人なら、楊過が恋花の毒に侵された後、失恋草を使って毒をもって毒に対抗する解毒法を必ず覚えているだろう。 ゲルセミウム・エレガンスには、毒素を攻撃して除去する効果、瘀血を解消して痛みを和らげる効果、虫を殺して痒みを和らげる効果があります。皮膚湿疹、体部白癬、足白癬、打撲、骨折、痔、せつ、癤などの外用に適しています。四大害虫の駆除やウジ虫の駆除にも最適です。 それはウリ科のつる植物であることが判明しました。本に書かれているような草ではなく、一年草のつる植物でした。主な毒性物質はククルビタシンです。 原書によれば、これを食べた後、腸が黒くなって癒着し、腹痛が続いて死亡するそうです。一般的な解毒方法は、胃洗浄、炭灰摂取、アルカリ水と吐剤の使用です。胃洗浄後、緑豆、スイカズラ、速煎じ薬を使用して解毒することができます。 3. 赤い鶴 レッドクレーン 鶴の肉、鶴の骨、鶴の脳は薬として使用できますが、すべて無毒であり、すべて滋養強壮の薬です。赤い紋のある石は、実は赤い鶏冠石です。鶏冠石は三酸化ヒ素の天然鉱物で、加工すると有名なヒ素になります。 「鶴の嘴の赤」は古代におけるヒ素の曖昧な呼び名です。 ヒ素が人体に入ると、タンパク質の硫黄基と結合し、タンパク質を変性させて活性を失わせます。細胞内の酸化エネルギー供給経路を遮断し、ATPエネルギー供給不足で人を急速に死に至らしめます。これはシアン化水素の作用機序に似ています。 天然ヒ素の化学組成は As2 O3 で、等軸六八面体結晶です。単結晶の形状は八面体で、菱形十二面体もあります。集合体は星形、地殻形、髪の毛形、土形、鍾乳石形などがある。白色には、空色、黄色、または赤色の色合いが含まれる場合があり、また、無色で白または淡黄色の縞模様がある場合もあります。 光沢はガラスやダイヤモンドに劣らず、脂っぽく絹のような光沢も持ち合わせています。モース硬度は1.5、比重は3.73~3.90、へき開は完全で、破片は貝殻状で脆く、水に溶けやすく、毒性が強い。 |
<<: 日本の軍帽についている2枚の「布」は何の役に立つのでしょうか。奇妙な
推薦する
明らかに:「紅楼夢」で言及された6つの珍しい宝物
『紅楼夢』はわが国の四大古典名作の一つであり、中国古代文学史上重要な位置を占めています。この小説は、...
蜀滅亡に多大な貢献をした鄧艾だが、良い最後を迎えられなかった。一体何が起こったのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
孟子の物語:人間の本性は生まれながらに善良であるという物語
孟子は幼少期に「優れた」教育を受けた。孟子の母親は、生まれる前にどのように教えるべきかを知っていまし...
朱元璋はどのようにして3回の行動で劉伯文を死に至らしめたのか?
明朝が成立する前、劉伯温は至宝であったが、朱元璋が権力を握った後、瞬く間に野原のいばらの草となってし...
生涯無名のまま生きた5人の詩人、彼らの有名な詩の数々
唐の時代は経済的に繁栄しただけでなく、文化面でも非常に繁栄していました。唐代の詩は封建時代に頂点に達...
岑申の詩「張大尉を東に送る」の本来の意味を理解する
古代詩「張将軍の東への帰還の別れ」時代: 唐代著者: セン・シェン白い羽と緑の弓弦、毎年常に先端にあ...
『紅楼夢』の中秋節の宴会はなぜ「瓜兵酒」と呼ばれるのでしょうか?理由を説明する
『紅楼夢』には中秋節が2回登場しますが、中秋の名月の晩餐会はなぜ「瓜瓶酒」と呼ばれるのでしょうか?こ...
『旧唐書』巻72にはどんな物語が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
蒋子牙の『太公六道』:「六道・龍道・奇兵」の作例と鑑賞
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われてい...
古代において「皇后女官」という称号はいつ頃から現れ始めたのでしょうか? 「勅令」とはどういう意味ですか?
古代に「皇后妃」という称号はいつから現れたのでしょうか?「皇后妃」とはどういう意味でしょうか?興味深...
小説『紅楼夢』に出てくる秦克清の部屋のレイアウトはどのようなものですか?
秦克清は『紅楼夢』の主人公です。金陵十二美女の一人。 ご存知ですか、次の興味深い歴史編集者が説明しま...
『後漢演義』第41章はどんな物語を語っていますか?
鄧宗とその息子を廃位し、二人とも餓死して甘陵母娘に供物を捧げ、自らの権力を誇示した。しかし、安帝永寧...
襄公5年に古梁邇が書いた『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
古梁邁が書いた『春秋実録古梁伝』には、襄公五年に何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が気に...
『韓湘子全伝』第14章:湘子は天について語り、元陽を養うが、退子は理解しない
『韓湘子全伝』は、韓湘子が仙人となり、韓愈を導いて天に昇るまでの物語です。本書は、明代天啓三年(16...
『紅楼夢』でシキはなぜパン・ユアンと結婚しなかったのですか?
思奇(しき)は、本名を秦思奇といい、『紅楼夢』の登場人物である。四人の猛者メイドの一人。下記の興味深...