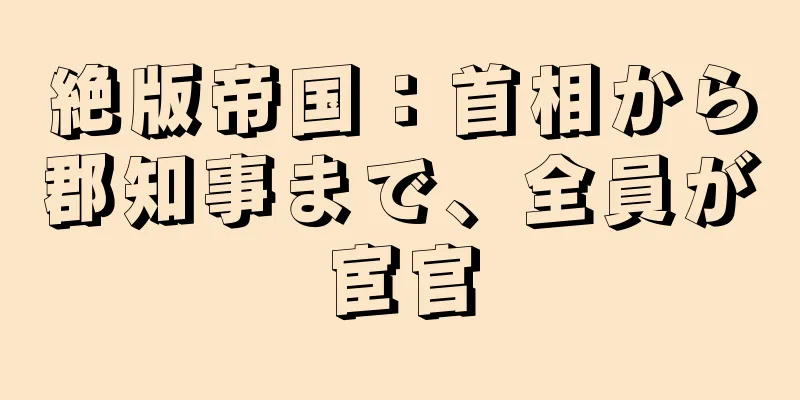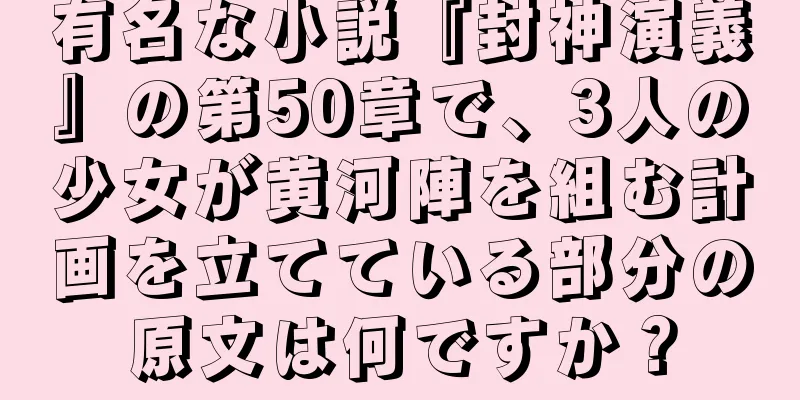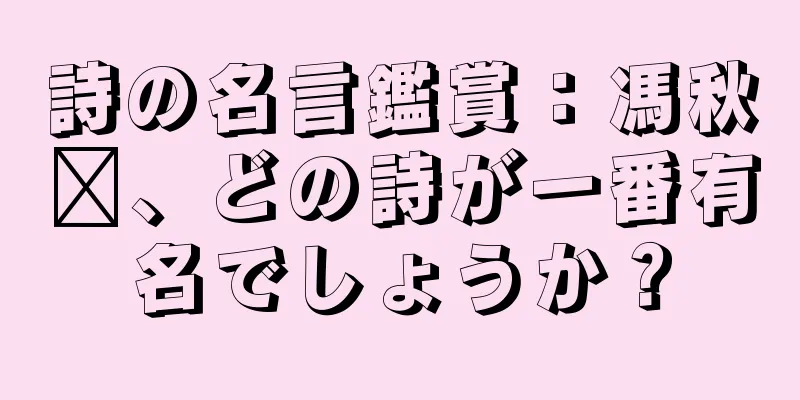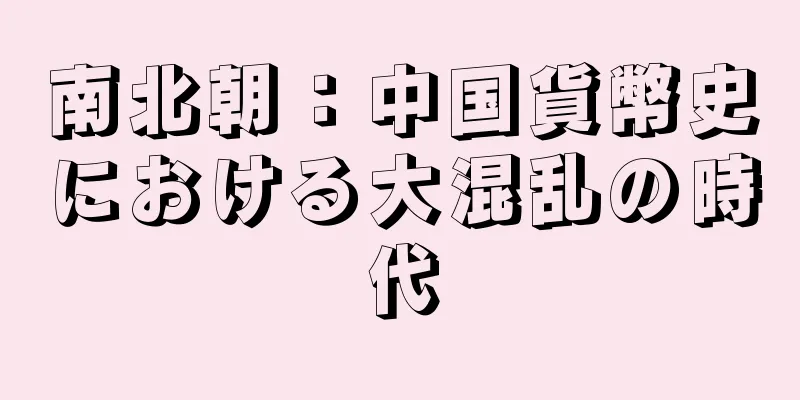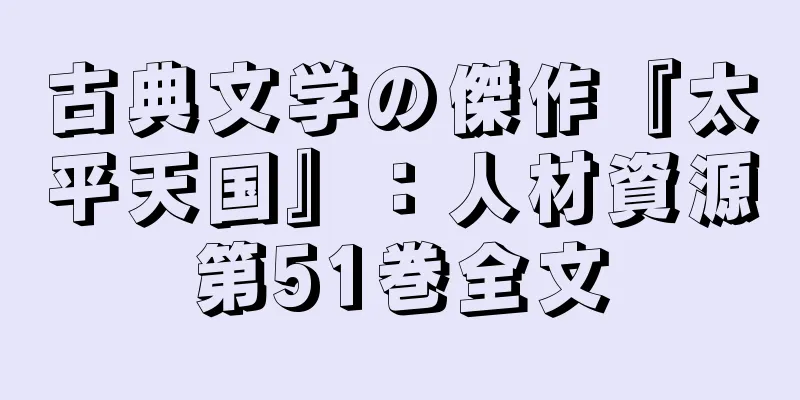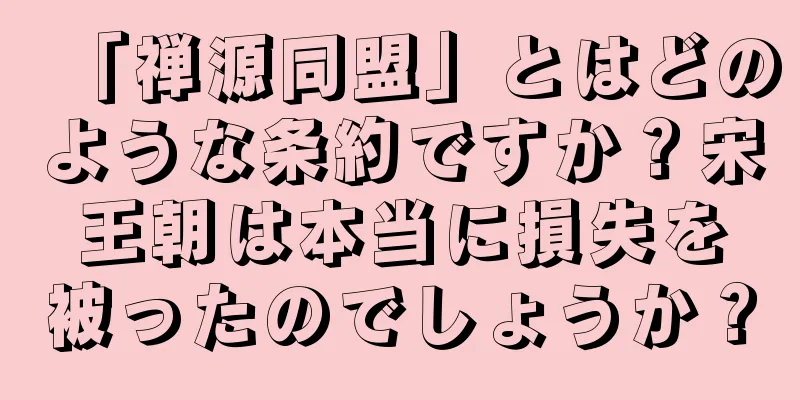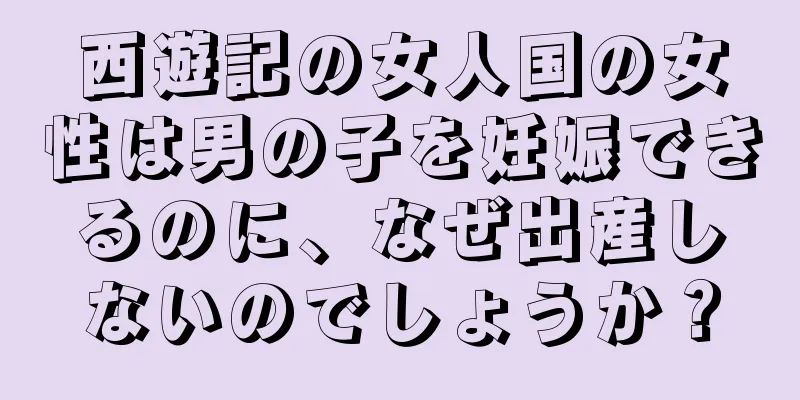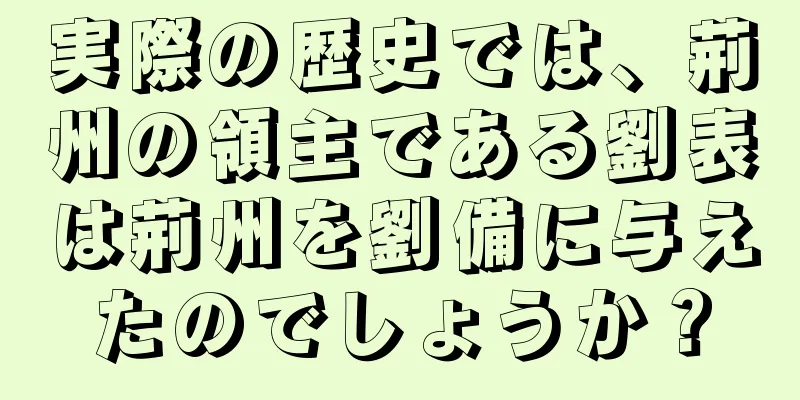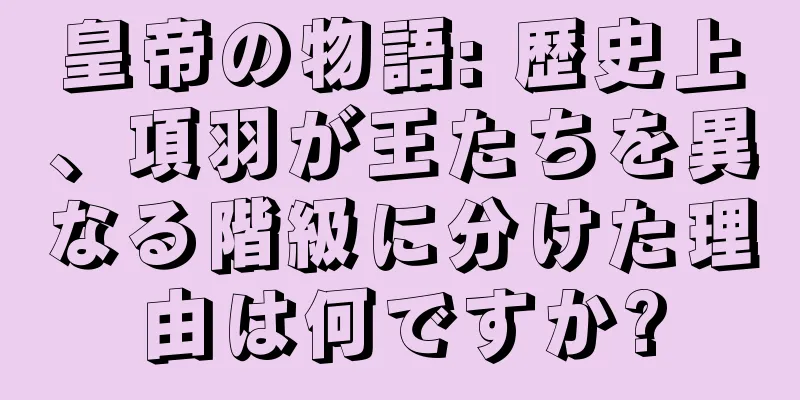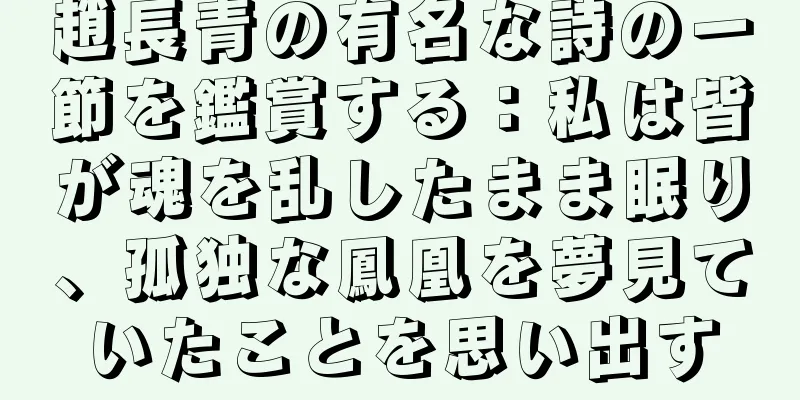蒋子牙の『太公六道』:「六道・龍道・奇兵」の作例と鑑賞
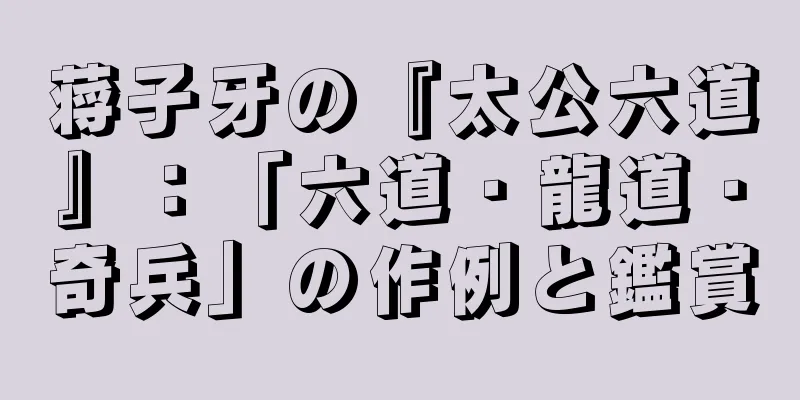
|
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われています。中国の古典的な軍事文化遺産の重要な部分として、その内容は奥深く、思想は豊かで洗練されており、論理は厳密で、古代中国の軍事思想の真髄が凝縮して体現されている。この本は周代初期に太公王(呂尚、姜子牙)によって書かれたと言われており、全編が太公と文王、武王との対話の形でまとめられています。それでは、次の興味深い歴史編集者が、姜子牙の「六策・龍策・奇兵」をお届けしますので、見てみましょう! 【オリジナル】 武王は太公に「兵法の要点は何ですか」と尋ねました。太公は答えました。「昔、戦いに長けた者は、空でも地上でも戦うことができませんでした。彼らの成功または失敗はすべて神の力に依存していました。それを得た者は繁栄し、それを失った者は滅びました。」 「二つの陣営の間では、兵士を無秩序に行進させて状況を変え、草を密生させて逃げられるようにし、谷を危険で障害物にして戦車を止め騎兵を拘束し、狭い山と森を封鎖して少数の兵で多数を攻撃し、谷を暗く不明瞭にしてその姿を隠す。明るく澄んだ場所を明瞭にして勇気と力で戦う。矢を柵のように速くして巧妙な策を破り、狡猾で隠されたものを準備して遠くから敵を欺きおびき寄せ、軍を破り将軍を捕らえ、場所を四つに分け、包囲攻撃して方陣を破る。 怯えている者につけ込めば、一軍で十軍を倒すことができる。疲れている者につけ込めば、十軍で百軍を倒すことができる。並外れた技術につけ込めば、深い水や川を渡ることができる。強力な弩と長い武器につけ込めば、水を越えて戦うことができる。長い峠と遠距離の陣地につけ込めば、都市や町を倒すことができる。太鼓と騒音につけ込めば、並外れた計画を遂行することができる。強風と大雨につけ込めば、前線を攻撃して後方を占領することができる。敵の使者を装い、殴打して食糧供給を断つことができる。敵に降伏するよう偽の命令を出し、北へ逃げさせることができる。戦いは正義をもって行わなければならない。敵を倒すよう民を激励することができる。 高い称号と重い褒賞は従順を奨励するために用いられ、厳しい刑罰は怠惰を戒めるために用いられ、喜びと怒り、与えることと受け取ること、民と軍、緩急の交替は部下を調和させ統制するために用いられる。高くて開けた場所は国を守るために用いられ、安全で遠い場所は国を要塞化するために用いられる。山と森、緑豊かで荒々しい場所は人の出入りを静めるために用いられる。深い塹壕、高い要塞、豊富な食料の場所は、長続きするために用いられる。 「だからこう言われている。戦争と攻撃の戦略を知らなければ、敵に助言することはできない。分散して移動できなければ、敵に奇襲を勧めることはできない。混乱を制御できなければ、敵に変更を加えるよう勧めることはできない。」 「こう言われている。将軍が優しくなければ、三軍は仲よくならない。将軍が勇敢でなければ、三軍は鋭くならない。将軍が賢くなければ、三軍は疑い深くなる。将軍が明晰でなければ、三軍は大いに危険に陥る。将軍が細心でなければ、三軍は機会を失う。将軍が常に用心深くなければ、三軍は備えを失う。将軍が強くなければ、三軍は任務を失う。したがって、将軍は人生の主人である。三軍は将軍によって統治され、将軍とともに混乱する。賢い将軍を得れば、軍隊は強くなり、国は繁栄する。賢い将軍を得なければ、軍隊は弱くなり、国は滅びる。」武王は言った。「よかった!」 【翻訳】 武王は太公に尋ねた。「兵法の要点は何ですか?」 太公は答えた。「昔、兵法に長けた者は、空や地上で戦うことはできなかった。成功か失敗かは、不可解で予測不可能な状況を作り出すことができるかどうかにかかっていた。そのような状況を作り出すことができた者が勝ち、作り出せなかった者が失敗する。二つの軍が対峙したとき、彼らは鎧を脱ぎ、武器を置き、兵士を解放し、隊列を混乱させた。その目的は、敵を欺きおびき寄せるためであった。隠れて退却できるように、草木の生い茂った場所を占領した。少数の兵で多数を倒すために、谷間の危険な地形を占領した。敵の戦車や騎兵の動きを阻止するために、谷や沼地などの低く湿った暗い場所を占領した。 危険な峠、山岳地帯、森林を占領する目的は、軍隊の動きを隠すためであり、平地や開けた場所を占領する目的は、敵と勇猛果敢に戦うためであり、矢のように速く、機関銃のように激しく動く目的は、敵の綿密に練られた戦略を電光石火の速さで打ち破るためであり、巧みに待ち伏せを仕掛け、奇襲部隊を展開するためである。敵を欺き、騙すことは、敵を倒し、敵将を捕らえることを目的としており、四方八方から攻撃することは、敵の円形や方陣を崩すことを目的としており、敵が慌てているときに攻撃することは、1対10の優位を達成することを目的としており、敵が疲れて夜営しているときに奇襲を仕掛けることは、10対1の優位を達成することを目的としている。 巧みな技術で橋や船を造り、深い水や大河を渡ることを目的とする。強くて長い武器を使用し、渡河作戦を容易にすることを目的とする。辺境に関所を設け、斥候を派遣し、素早く移動して通常の規則に従わず、敵の都市を征服し、敵の土地を占領することを目的とする。わざと大きな音を立てて前進を叫ぶことは、敵の目と耳を混乱させ、奇妙な戦略を実行することを目的とする。強風や暴風雨の中で行動し、前後から攻撃することを目的とする。敵の使節を装って敵の背後に忍び込み、敵の食糧供給を断つことを目的とする。 敵の命令を利用し、敵の軍服を着用するのは、退却の準備を容易にするためであった。将兵に戦争の正当性を説明するのは、士気を高めて敵を倒すためであった。階級を高め、褒賞を増やすのは、将兵に勇敢に戦うよう促すためであった。厳しい罰を科すのは、疲れ果てた将兵に戦い続けるよう促すためであった。喜怒哀楽、褒賞と罰、礼儀正しさと力強さ、緩急は、全軍の意志を調整し、部下の行動を統一するためであった。 高く広い地形を占領するのは警戒と駐屯を容易にするためであり、危険で狭い場所を守るのは自軍の防衛を強化するためであり、深い山と密林のある地形を占領するのは軍の動きを隠すためであり、深い塹壕を掘り、高い障壁を築き、より多くの食糧と飼料を貯蔵するのは持久戦を遂行するためである。 したがって、攻撃と戦争の戦略を理解しなければ、敵と戦うことはできません。部隊を柔軟に使用する方法を知らないと、奇襲勝利を達成することはできません。軍隊内の秩序と混乱の関係を理解していないと、変化に適応することができません。したがって、将軍が親切でなければ、軍は彼を支持しない。将軍が勇敢でなければ、軍は戦闘力を持たない。将軍が賢くなければ、軍は疑念を抱く。将軍が抜け目がなければ、軍は悲惨な敗北を喫する。 将軍が問題を慎重に考慮しなければ、軍隊は戦う機会を失う。将軍が警戒を怠れば、軍隊は準備不足になる。将軍が力強く指揮しなければ、軍隊は任務を怠る。したがって、将軍は軍隊の主人です。将軍が規律正しいなら、軍隊も将軍とともに規律正しくなります。将軍が無能であれば、軍隊は将軍とともに混乱します。賢明で有能な将軍がいれば、国は繁栄し、軍隊は強くなります。賢明で有能な将軍がいないと、国は弱くなり、軍隊は滅びます。 ” 武王は言った。「よく言ったな!」 【図】 柔軟性、順応性、奇襲による勝利能力は、作戦を指揮する際に従うべき基本原則です。つまり、「攻撃や戦闘の仕方を知らなければ、敵と話すことはできない。分散して移動できなければ、奇襲について話すことはできない。混乱を制御する方法を知らなければ、変化について話すことはできない。」宋の襄公が洪水の戦いで惨敗したのは、この原則に違反した結果であった。 斉の桓公が亡くなると、斉は内乱に見舞われ衰退し、南方の強国である楚はこれを機に中原に侵入し覇権を握った。中原諸国から「蛮国」とみなされてきた楚の北進は、中原の小国に不安を抱かせた。それから 常に仁と義を誇っていた宋の襄公は、宋の君主としての地位と最も名誉ある称号を利用して、諸侯を率いて楚と戦い、斉の桓公の支配的な地位を継承しようとした。宋の襄公は野心的であったが、国の力には限界があったため、斉の桓公の例に倣わざるを得なかった。彼は「仁義」をスローガンとして、諸侯を召集し、毓地(現在の河南省隋県の北西)で会議を開き、自身の名声と地位を高めた。 宋の襄公は、不測の事態を防ぐためにもっと多くの戦車を持ってこいという大臣たちの助言を拒否し、代わりに数台の戦車だけを連れて行きました。その結果、同盟会議において多くの小国から冷遇されただけでなく、楚軍に生け捕りにされてしまった。楚軍は彼に宋の首都商丘を攻撃するよう強制したが、宋軍と民衆の抵抗により、楚軍は長い包囲戦の末にその都市を占領することができなかった。その後、魯国の仲介により、楚の成王は宋の襄公を釈放し、帰国を許可した。 宋の襄公は大きな屈辱を受けたため、復讐を誓った。しかし、自分の力が楚に及ばないことを知っていたため、楚に降伏した鄭に目を向けた。そのため、大臣たちの反対にもかかわらず、彼は鄭を攻撃することを主張した。鄭は宋軍が攻めてくると聞いて楚に助けを求めた。楚はすぐに軍を起こして宋を攻撃し、鄭を救出した。宋の襄公はこの知らせを聞くと、急いで軍を鄭から撤退させた。周の襄王14年(紀元前638年)10月末、宋軍は宋の領土に戻り、楚軍は宋に向かって進軍を続けた。 宋の襄公は、楚軍の前進を阻止するため、紅水(現在の河南省の商丘と浙城の間を南東に流れる臥河の支流)の北に軍を配置した。 11月1日、楚軍は紅水河の南岸に進軍し、河を渡り始めた。この時、宋軍はすでに戦列を敷いていた。両軍の兵力の差を考慮して、宋の大臣公孫固は宋の襄公に、楚軍が川の半ばを越えた時に攻撃する好機を捉えるよう進言した。彼の進言は却下され、楚軍は紅水河を渡河することに成功した。 楚軍が渡河した後、大臣たちは楚軍がまだ陣形を整えておらず隊列も整っていない時に宋の襄公に攻撃を勧めたが、彼の勧めは再び却下された。楚軍が軍隊を展開して準備を整えた後、宋の襄公は太鼓を打ち鳴らして攻撃した。その結果、宋軍は弱体化し、精鋭部隊はすべて壊滅し、宋の襄公自身も重傷を負った。襄公は、残った数人の兵士の必死の保護のもとでようやく包囲を突破し、慌てて宋に逃げ帰った。 戦争後、多くの大臣が宋の襄公の誤った行為を批判した。しかし、宋の襄公は「君子は重傷を負わせず」(傷ついた敵にこれ以上傷つけない)、「白髪の老兵を捕らえず」(白髪の老兵を捕らえない)、「関を塞ぐことに頼らず」(勝つために関を塞ぐことに頼らない)、「太鼓を鳴らさずに戦列を組まない」(まだ戦列を組んでいない敵に積極的に攻撃しない)と説得力のある主張をした。不利な状況に陥ったとき、驚きの勝利を達成するには柔軟性と適応力に頼るしかありません。宋の襄公は「愚かな仁義」を追求し、考え方が保守的で、慣習に固執し、時代遅れの軍事教義に固執したため、軍の敗北と自身の死という悲劇的な結末を迎えた。 |
<<: 『紅楼夢』では、薛宝才は林黛玉よりどのような点で劣っているのでしょうか?
>>: 蒋子牙の『太公六涛』:「六涛・龍涛・李君」の作例と鑑賞
推薦する
王希峰はなぜ賈容を叱ったのか?事件の原因は何ですか?
王希鋒はなぜ賈容を叱責したのか?以下、Interesting History編集部が関連内容を詳しく...
王季の絵画「秋の夜に王さんと幸せな出会い」は、月明かりの下でホタルが飛び交う秋の夜の山村の風景を描いています。
王冀は、号を武公といい、東高に隠棲していたことから東高子と号した。唐代初期の詩人で、後世に五音節制詩...
神龍の政変後、5人の英雄の死が武三思と関係があると言われた理由は?
神龍の政変の際、武則天に退位を迫った5人の大臣は、なぜ誰も幸せな結末を迎えられなかったのでしょうか。...
「縮刷版ムーラン花 春を守れない」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
短縮語のマグノリア:春は維持できない顔継道(宋代)スプリングは保持できません。まさに退屈な時間のよう...
清朝の地図 - 清朝時代の古代中国の地図
清朝の地図清王朝(1616年 - 1911年)は、女真族によって建国された封建王朝でした。 1616...
淮南王劉安の反乱がなぜ二代にわたる恨みだと言われるのか?
漢の武帝の治世中に、淮南王劉安の反乱という衝撃的な事件がありました。この事件の奇妙さと残酷さに比べれ...
古代の詩に隠された春の意味を探ります。詩人たちはどのような情景を描写したのでしょうか。
文人や詩人は春の隠された意味を詩に書き記しました。Interesting History の次の編集...
「卜算子·咏梅」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
不算子:梅の花の頌歌陸游(宋代)宿場町の壊れた橋の脇には、主のない寂しい花が咲いている。もう夕暮れで...
解読:北欧神話の神々の王オーディンはなぜ片目を失ったのか?
オーディンは元々片目ではなかった。彼が片目を失った経緯は次の通りです。世界樹ユグドラシルの3つの主要...
済公伝第83章:夜空を飛んで風を殺す小神 済公が冗談を言って空飛ぶ泥棒を捕まえる
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
何千年もの間、中国人によって誤って伝えられてきた8つのことわざ!姿勢を改善する
世の中の素晴らしさは、実際に見なければわかりません。私たちが普段口にする8つの慣用句は、実は今のよう...
春節の間、なぜ徹夜するのでしょうか?中国の旧正月の習慣
はじめに:大晦日に徹夜するのは漢民族の民俗習慣であり、趙徐花、敖年、敖夜とも呼ばれています。大晦日に...
張盾は宋代に多大な貢献をした人物です。なぜそのような人物が裏切り者になったのでしょうか?
叛逆臣と言えば、歴史上、国家と人民に災難をもたらした極めて邪悪な人物をすぐに思い浮かべる人が多いでし...
シベ文化 シベの弓矢文化はどのようにして生まれたのでしょうか?
シベ族の伝統的な弓矢文化シベ族は古来より乗馬と射撃が得意な民族です。弓術はシベ族の文化において長い歴...
皇帝の物語:唐の中宗皇帝、李献はなぜ衛皇后と安楽公主をそれほど溺愛したのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...